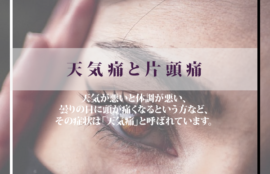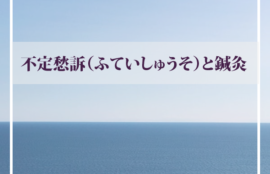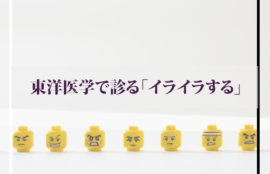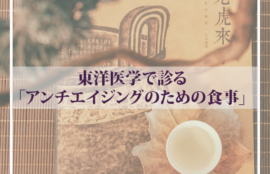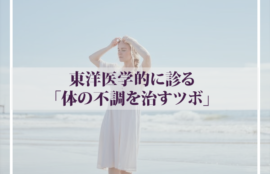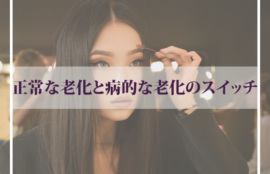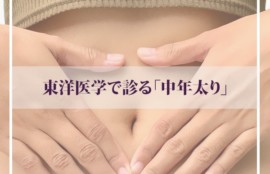東洋医学では「気・血・水」のバランスが崩れると体に不調をきたすと考えます。この「気・血・水」の3つは、人の体の構成要素と考えられています。
「気」は、人体の生命活動のエネルギー源です。「血」は、西洋医学における血液の血とは、少しイメージが異なり、全身に栄養を供給し潤すことと、精神活動の基礎物質という二つの働きがあります。「水」は、津液とも呼ばれ、体の中の血液以外の水分です。「水滞」は全身を流れる津液がスムーズに循環することが出来ない状態です。
「水滞」は全身を流れる津液がスムーズに循環することが出来ない状態で、水の巡りが悪いことで不要物が排出されにくくなります。「水滞」で現れる代表的な症状が、手足のむくみです。むくみは、体内に不必要な量の水分がとどまっている状態です。特に梅雨の時期は、湿度の高さなどが原因で余分な水分が排出されにくいため、「水滞」になりやすいです。
また、手足に冷えが生じることもあるため、東洋医学でいう「冷えは万病の元」につながります。「水滞」に限らず「血虚」「気虚」も同様に冷えが見られます。
以下のような症状がある場合は、水の巡りが悪い「水滞」の可能性が高くなります。
- 身体がむくみやすい
- お腹に水が溜まる
- 朝に身体がこわばる
- めまいや吐き気がする
- 体が重く、倦怠感がある
- 下痢をしやすい
- 吹き出物が出やすい
- 腸がぐるぐる鳴る
東洋医学で診る、水の飲みすぎ
血液をサラサラにするために、毎日お水を1日2リットル飲みましょうというのは、東洋医学でいう「水毒」になる可能性が高くなります。水を摂りすぎると、むくみ、不整脈、肩こり、目眩などの身体的な症状の他にも、不安、不眠などの精神的な不調をもたらすことが分かっています。こうした症状を東洋医学では「水毒」として、水分過剰による症状であるとしています。
身体の健康は排出することが前提になっており、例えば酸素でさえ取り込みすぎれば痙攣や失神になる過呼吸症候群を発症します。同じく水分も発汗や利尿が促された後であれば問題ありませんが、水分を過剰に摂ることが様々な弊害を起こす原因になります。
若々しくて美しくなるため、みずみずしいを維持するため、水分を沢山摂ることで若返りになると考える人が多数いらっしゃいます。
水毒の確認方法
“水毒”という言葉は、あまり馴染みがないと思います。古来日本には“難病・奇病は「水毒」”という諺もあります。
水毒とは、身体の中の水が全身をめぐらずにどこかに溜まっている状態のことです。人の体重は2/3は水分(細胞内液)で、残りの1/3は血液(血中ナトリウム)などで、水分の代謝が狂い、血中の中に水分量が多くなり、相対的にナトリウムが減ってしまうことで様々な症状が発生すると考えられています。特に、日本人の疾患は水の過剰に起因するものが非常に多いと言われています。
口から摂り入れられた水分は、大血管、小血管、毛細血管の順に送られます。そして血管から細胞へ吸収されます。体内水分量は子供で70%、成人で60%、高齢者になると50%と減少します。つまり細胞が吸収できる水分量は加齢とともに減っていきます。
一方で、細胞に水分を送りこむためには血流をよくする必要があります。血流が悪いのに、水分を過剰摂取すると様々な問題が起こります。つまり運動や入浴などによって体を温め、血液を循環させなければ、細胞内域には水分が十分に吸収されず細胞外域に残ることになります。
東洋医学でいう水毒は、細胞には水分が不足しているのに、細胞の外側には水分が過剰に存在する状態のことを言います。この水毒が引き起こす症状は、肥満、リウマチ、偏頭痛、アレルギー疾患など様々な病気や不調です。
体のあらゆる臓器は36.5度以上の体熱で快適に機能するようになっています。そのため体内に体を冷やす余分な水分が存在すると、体外に排出しようとして体を温めようとします。
そのため、水毒の疑いある人は、
- くちゃみ鼻水がよく出る、唾液が多い
- 下痢、水様便がよくある
- 頻尿、乏尿(排出ができない)、寝汗をかく
- 運動、入浴以外でもすぐ汗をかく
などの水を外に出そうとする症状を呈します。またむくみや下腹部のぽっこりなどが代表的な身体症状です。
水毒が引き起こす症状
水が原因で体が冷えると、細胞からは血管を拡張して血行をよくするプロスタフランディンとブラジキニンなどの炎症物質が産生されます。例えば冬場のしもやけも冷えからくる炎症と言えます。炎症は病気ではなく、体に異常が生じた時におこる防御反応です。熱を出すことで免疫を高めたり、体を正常に戻そうとする働きです。この炎症が長引いたり、過剰になるとそれ自身が悪影響を及ぼします。
炎症には腫れる、赤くなるなど様々な反応が含まれ、炎症が過剰になれば免疫も過剰になります。花粉症や食物アレルギーも免疫の過剰反応です。このような炎症を引き起こすきっかけが冷えて血行が悪いという状態が長引くことで起きてしまいます。肥満、神経痛、アレルギー疾患、耳鳴り、目眩、頭痛、高血圧などの疾患の原因になりうるのが水分の摂りすぎです。
西洋医学では血液をサラサラにするために水分をできるだけ多く摂るように勧められてきましたが、水毒が原因となる心不全では水分摂取を制限した治療が行われます。
足のむくみ
その主な原因は、過剰な水分の摂取や、冷えなどです。また尿量・回数ともに増えたように感じたときは、水分を摂りすぎていないか見直す必要があります。水毒の例で1番分かりやすいのは「むくみ」というサインです。水は重たいので下に溜まりやすく足のむくみが最も多いです。
足は心臓から最も離れている為、静脈やリンパ管の流れが滞ると、血液や体液、老廃物が流れず、足の皮下組織に余分な水分として溜まります。東洋医学では、足のむくみは内臓と関わりがあり、「腎」と「脾」の働きが低下していると起こります。腎臓の水分代謝力が低下すると、余分な水分を溜め込みます。
体内に溜め込んでいる余分な水が多ければ多いほど、身体は冷えます。冷えた身体で外から温めても、なかなか身体の中までは温まりません。1度冷えてしまうと、しつこく冷えが残るのが水毒タイプの冷えです。まず冷えを取り除きましょう。
また、体内の水分量が増えると胃腸機能が低下し、更に悪化すると吐き気、嘔吐、心不全、呼吸困難などの重い症状が見られることがあります。これらの場合には、体内のナトリウムが不足している状態なので、経口補水液を摂取しましょう。根本的には水毒体質を改善していきましょう。
血流の悪さは乾燥肌を速める
乾燥肌は毛穴の開き、たるみ、シワなどにつながるため、お水を沢山飲まれる方がいます。しかし沢山飲んでも改善されない方は、根本的な対策が必要かもしれません。本来であれば飲んだお水は、血流によって水分を必要としている細胞の中に運ばれ、利用されます。つまり水分がお肌の細胞にしっかり届けば、潤いやハリが保たれるはずです。
しかし、血流が悪いとどれだけ水分を摂っても細胞に水分が行き渡らず、お肌の細胞へ正常な水分が運ばれない場合には、別の場所で水分がだぶつき、余計に肌の状態が悪化する可能性があります。さらにその余分な水分により、むくみ、冷え、免疫力の低下まで起きてしまいます。このように水分を摂ることも大事ですが、表面的な症状だけに気を取られて対策を取ることが大切です。
日本人は水滞になりやすい体質!
日本人は胃腸が弱い体質の人が多いうえ、湿度が高い環境のため水分代謝がしにくく、内臓に負担がかかりやすいといわれています。通常、体内に不要な水分は汗や尿によって体外に排出されます。しかし、内臓の働きが悪くなると排出機能がダウンし、体に余分な水分が溜まってしまうのです。
例えば、腎臓機能が低下すると、尿をつくる働きが弱くなるため、体の外への水分排出が少なくなります。また小腸機能が低下すると、効率的に水分を吸収することができなくなるので、水滞を招くリスクが高くなります。さらに自律神経の乱れも、水滞のリスクを高めます。
冷たい食べ物や飲み物は、内臓を冷やしてしまい、水滞のリスクを高めます。またトイレを我慢しないこと、アルコールを控える、基礎体温を高めることも、水滞の予防につながります。食習慣の見直しは「水滞」を改善するのに効果的です。胃腸を整える食べ物を食べましょう。
- はとむぎ:余分な水分を排出し、消化器官を助ける。むくや水イボ、肌荒れにもよい。
- とうがん:余分な熱や水分を排出し、解毒する。暑気あたりやむ、二日酔いにも効果的
- こんぶ:余分な熱や水分を排出する。肥満や高血圧を抑える効果もある。
梅雨の湿度、揚げ物や甘いもの、アルコールの過剰摂取などは水滞を加速させます。消化機能を低下させる冷たい飲み物は避けて。温かいものや常温のものを選んでください。ただし水分の摂りなさ過ぎもNGです。
私たちの細胞1つ1つが元気に活動してくれることが健康に繋がります。しかし細胞はとても繊細で塩分濃度や酸素など、様々な栄養素が絶妙なバランスに調節されていないと生きていけません。その細胞内の塩分バランスの維持や老廃物の処理を担うのが腎臓で、1分間におよそ1リットルの血液を浄化しています。この腎臓が血液の濾過装置として働くことで細胞のバランスが保たれています。この腎臓の働きを保つのが「水」です。
2020年に日本人を対象に行われた研究では、普段から水を意識的に摂取した人はそうでない人に比べ血圧が有意に低下し、腎臓の血流量が維持でき、血液中の老廃物の濃度が下がったことが分かっています。
ルイボスティーの健康効果
ルイボスティーは、健康効果が高いことで知られており、特に腸内環境の改善におすすめと言われています。腸内環境を整えておくことは健康だけでなく、美容にとっても欠かせません。ルイボスティーを飲み続けると他にも様々な健康効果が期待できます。
ルイボスティーは、ノンカフェイン&ノンカロリーのハーブティーで、その最大の特徴は様々なミネラル、ポリフェノールが豊富に含まれていることが挙げられます。ルイボスティは、南アフリカのセダルバーグ山脈の一帯でしか生育しないルイボスというマメ科の植物を発酵、乾燥させ製茶したものです。
血液サラサラ効果
ルイボスティーを毎日飲み続けることで期待できる健康効果の1つ目は、血液がサラサラになることです。ルイボスティーで血液がサラサラになるのは、ルイボスティーにはポリフェノールがたっぷり含まれており、体内に大量に発生した活性酸素を取り除く効果が期待できるからです。
ちなみに血液ドロドロな状態は、水分が少なく、血小板の活性が高まって固まりやすくなっている状態のことです。血液が固まってしまうと血の塊である血栓ができて血管を塞ぐことになり、脳卒中や心筋梗塞に繋がる可能性もあります。また活性酸素によって血管が傷ついたり、加齢によって血管が硬くなっていたりすると血管に老廃物が溜まりやすくなり、しなやかに血管が動けないことで血流が悪くなってしまいます。
ルイボスティーを飲むことを心がけることで、活性酸素によって血管が傷ついてしまうのを 防ぐ効果が期待できます。さらにルイボスティーには、ミネラルがたっぷり含まれている以外にも、鉄分も豊富に含まれています。血液サラサラにするためには血液の量が十分にあることも必要なため、血液の材料になる鉄分も補給できます。
貧血の予防効果
ルイボスティーには、鉄分を始めとするミネラルやビタミンが豊富に含まれています。実はコーヒーや緑茶は健康に良い飲み物と言われていますが、貧血予防と言う観点ではあまり良くありません。なぜならコーヒーや緑茶には、カフェインやタンニンが含まれており、これらはミネラルの吸収を阻害してしまいます。そのため緑茶やコーヒーは食事と一緒には飲まずに、食後少し時間を開けてから飲むのが良いと言われています。
しかしルイボスティーは、ノンカフェインでカフェインもタンニンも含まれておらず、しかも鉄分が含まれているため、食事と一緒に飲んでも良く、ルイボスティーだけ飲んでも貧血の予防効果が期待できます。
腸内環境が整う
腸内環境が整って腸活の効果が期待できるお茶と言われるものの中には、腸の蠕動運動を促進して排便を促すようなものがあります。しかしルイボスティーには、ミネラルの1つであるマグネシウムも豊富に含まれており、マグネシウムは腸の中で水分を集めて硬くなってしまった便を柔らかくする効果が期待できます。
さらにマグネシウムには神経の興奮を抑えてメンタルを安定させる効果もあります。つまり強いストレスで便秘や下痢などのお腹の調子を悪くしてしまったりする場合、マグネシウムが含まれているルイボスティは、張り詰めた神経をほぐしながらソフトに便秘を予防してくれる効果が期待できます。ただし飲み過ぎてしまうとマグネシウムの効果が強くなってお腹が緩くなることもあるため、目安として1日2杯から3杯程度が適量だと言われています。
アンチエイジング効果
ルイボスティーには、ポリフェノールがたっぷり含まれており、その中でも特に注目されている成分がスーパーオキシドディスムターゼ(SOD)です。SODは、強い抗酸化作用のある酵素成分であり、体内の活性酸素を取り除いて細胞の老化を抑制する効果が期待できます。活性酸素は、ストレスや不規則な生活などによって体内に蓄積されてしまい、増え過ぎると肌の老化や免疫力の低下などに繋がります。健康に良いことで有名な緑茶やウーロン茶にもSODは含まれていますが、ルイボスティーは緑茶の82倍、ウーロン茶のおよそ30倍ものSODが含まれています。
また、SODには冷え症を改善する効果があることも分かっています。血液サラサラになることで血流が良くなって代謝が良くなり、体が内側からポカポカ温まる効果も期待できます。
むくみ改善効果
ルイボスティーには、カリウムがたっぷり含まれており、体内の余分な塩分や水分を排出する効果が期待できます。さらに毛細血管の働きを促進するルチンと呼ばれる成分も含まれており、このルチンは血行を促進することでむくみ改善に役立つと言われています。
デトックス効果
強力な抗酸化作用が期待できるSODの他に、10種類以上のミネラルが含まれています。そのためルイボスティーは血流を改善し、免疫力を上げて細胞の若返りを促進してくれますが、さらにルイボスティーにはヒデキシンやイソボデキシンも含まれています。
ヒデキシンやイソボデキシンは海外ではストレス緩和のサプリメントとしても売られており、フラボノイドの中でも特に抗酸化作用が強いと言われているのがヒデキシンやイソボデキシンです。さらにヒデキシンやイソボデキシンには、安眠効果があるとされています。
また、ルイボスティーの抗酸化物質は、血管が傷つくのを防いでくれることで糖尿病や新血管疾患のリスクを下げることも分かっています。研究では、ルイボスティーを飲むと血糖値の急激な上昇を防ぐ効果が期待できることも分かっており、これはルイボスティーに含まれるアスパラチンと呼ばれる抗酸化物質の効果だと言われています。実際、糖尿病と同じ状態になっているマウスの研究でも、ルイボスティーを摂取することで血糖値が低下することが分かっています。
脂肪燃焼効果
抗酸化成分であるケルセチンが、ルイボスティーには豊富に含まれており、この成分には脂肪分解酵素の活性化を促す働きがあると言われています。つまり血糖値の急上昇を抑えることで体に余分な脂肪が溜まってしまうのも抑えることができ、太りにくく痩せやすい体作りには欠かせない成分です。
アレルギーの予防効果
ルイボスティーには、アレルギーの予防効果が期待できます。これらは、ルイボスティーに含まれるSODの効果だと言われています。また強い抗酸化作用の他に、抗ヒスタミン作用もあるため、辛いアレルギーの症状を緩和する効果が期待できると言われています。
ちなみに胃が弱っていたり、腎臓の病気を抱えていたりする人は、ルイボスティーは控えた方が良いでしょう。なぜなら胃が弱っている時はミネラルが多すぎると負担になってしまう可能性があり、さらに豊富なカリウムも腎臓が弱い人にとっては負担になってしまうこともあります。
水出しor煮出し
健康効果をしっかり得たい人は、煮出したルイボスティーを飲みましょう。なぜなら水出しでは、水に溶けにくいミネラル類や抗酸化物質が十分に抽出されないからです。またルイボスティーに含まれるミネラル類は加熱しても変化しづらいと言われています。
水滞を改善する
身体の水分量を調節することで「水滞」を改善することができます。身体の水分量を調節するのは、排尿や排便、発汗などで、身体から余分な水分が排出されるというのは、イメージできると思います。食事などによる水分吸収が多くなるのか、もしくは排出が少なすぎれば「水滞」になります。
水分量で難しいのは、身体が必要とする水分は、その人の活動環境や、運動量、筋肉や代謝の量にもよって違います。そのため、心がけてほしいのは、一度に多くを飲むのではなく、少量を小まめに飲むことです。そうすることで身体が吸収・排出する水分量を調整してくれます。
また、適度な運動を習慣づけて代謝を良くすることも身体には大事なことです。適度の運動が代謝を改善しますし、排泄を適切に行なうためには、胃・腸・腎臓・膀胱などの内蔵を正しく働かせることが必要です。
水の巡りをよくするツボ
身体の水の循環を良くする働きがあり、余分な水分の排出に効果的なツボです(経絡:足の太陰脾経)。
豊隆(ほうりゅう):脛の少し外側で(指2~3本分)、膝と外くるぶしを結んだ線の真ん中の高さ
効果:胃痛や胃もたれなど消化器症状に効果、痰(病的で粘り気のある水分)を排出するように促すという効果
陰陵泉(いんりょうせん):脚の内側、すねの太い骨の内側沿いを下から指でたどり、ひざ下の太い骨にぶつかったキワ
効果:顔のむくみ、冷え性、疲労解消に効果

ほどよい刺激を感じる程度の強さで、ゆっくり押してゆっくり離しましょう。ぜひ知識を持って自分の大切な身体を癒やしてください。
水毒に効くツボ
湧泉(ゆうせん):土踏まずの前の方の中央にあって、足の指を曲げたときに最もへこむところ
「足の冷え」「脚の疲れ・むくみ」だけでなく、女性特有の症状「更年期障害」「生理痛」にも効果。

委中(いちゅう):膝裏の中央。膝の後ろの横皺の真ん中
ここを押して痛みがある場合は、むくみが強い可能性が高い。

美容鍼灸で水毒解消
運動、入浴、サウナなどでスッキリするのは、排出分泌現象が伴うからです。この現象はリラックスの神経と言われる副交感神経が働くことによって促進されます。
同じように鍼灸刺激によって、自律神経の副交感神経活動を亢進させることができ、実際にも胃や腸の動きが活発になるとか、よく眠れるという現象が臨床鍼灸の現場でも確認されています。
また、高周波によって深部加温することで、サウナや筋肉運動と同じ効果が期待できます。身体の奥深くから温度を上昇させることで代謝が活性化し、身体全体の温度を上昇させます。血行が良くなり、発汗を促し、体温が約1度上昇すれば、代謝は12%アップします。血行が良くなると腎臓への血流も良くなり、腎臓の働きが活性化して尿の生成排泄も多くなります。
日頃から冷えに悩んでいる方、汗をかきにくい方、疲れを取りたい方などには特におすすめの施術です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。