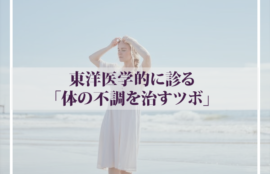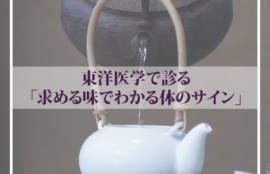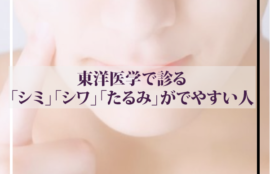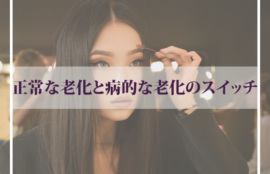食事を減らしてもヤセない…
水を飲んでも太る…
運動しても効果がない…
ダイエットを頑張っていても、全く効果が出ないのは、食事や運動だけの問題ではありません。それは腸内にいる「汚デブ菌」が原因です。
デブ菌と痩せ菌
肥満と腸内環境は大いに関係があり、食べても太らない人は腸内フローラのバランスが良い人と言われています。大腸に存在する細菌を腸内細菌と言い、菌種ごとに塊となって腸の壁に隙間なく張り付いています。その状態が花畑に似ていることから腸内フローラと呼ばれ、腸内フローラにはデブ菌とやせ菌が存在していて、肥満の人はデブ菌が多い傾向にあります。つまり痩せやすい体質になるには腸内フローラの改善が必要です。
腸内細菌には善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類あり、この割合が2:1:7が最も理想的な腸内のバランスと言われています。善玉菌が減って悪玉菌が増えると日和見菌が悪玉菌の味方になり太りやすくなるだけではなく、病気のリスクも高くなります。
一方で、デブ菌はファーミキューテス門と言って脂肪を溜め込む働きがあります。ファーミキューテス門と呼ばれる日和見菌がデブ菌と言われているかと言うと、食べ物から必要以上にエネルギーを摂り込み、体に脂肪として蓄えてしまう働きがあるからです。ファーミキューテス門は、 食べ物のカスとして配備されるものからも過剰に栄養を吸収するため、肥満の人はファーミキューテス門が多いと言われています。
このファーミキューテス門が大腸の中で排出されるカスに残った僅かな栄養も吸収するのには理由があり、人類が飢餓と戦ってきた歴史と関係し、少ない栄養でも人類が生存するための機能こそがファーミキューテス門になっているからと言われています。ファーミキューテス門は日和見菌の一種であり、善玉菌が優位な環境では本来の働きを発揮できないという特性があります。つまり善玉菌が優位になる状態をキープする食事や生活習慣を実行するのが大切になります。
一方、やせ菌はバクテロイデス門と言って脂肪を燃焼させる働きをしてくれます。バクテロイデス門は、食べ物からあまりエネルギーを吸収することはなく、バクテロイデス門とビフィズス菌が手を組んで短鎖脂肪酸という物質を作り出します。この短鎖脂肪酸が脂肪の吸収を抑えて体内の脂肪の燃焼を助けてくれます。
やせ菌の元は発酵食品や野菜類、ビフィズス菌を含むヨーグルト、味噌などの発酵食品や海草類、大豆類、キノコ類などと言われている。年齢を重ねるとビフィズス菌が減少してしまうため理想的な腸内バランスを保つのは難しくなります。意識して日々の食事でやせ菌を増やす食べ物を摂ることで、40歳以上でも無理なく痩せていくことが出来ます。
東洋医学で診る「中年太り」
東洋医学では、中年太りの原因を体のバランスやエネルギーの流れの乱れと捉えます。具体的には中年太りを陰陽のバランスの乱れ、つまり体のバランスを陰と陽の相互作用として捉えます。陰は体の内側に位置し、陽は外側に位置します。例えば陽性のエネルギーが過剰になると内臓脂肪が増加しやすくなり、気の滞りや血の滞ることによって引き起こされると考えます。この気の滞りや血の滞りは、ストレスや不規則な食生活、運動不足などが原因です。これによって体の新陳代謝が低下し、脂肪が蓄積されやすくなります。
また、東洋医学では脾の働きが消化吸収や体内の水液循環に重要な役割を果たすと考えます。脾の機能が低下すると食べ物の消化吸収が不良になり、水分代謝が乱れて体重増加につがるとされています。
一方で、体の冷えも中年太りの原因の1つとして考えられます。体が冷えると代謝が低下し、脂肪の蓄積が促進されます。また冷え症の人は食欲が増進しやすく運動不足になりやすい傾向があります。
このような中年太りは様々な研究が行われており、実は中年太りは加齢に伴って太りやすくなる現象ですが、そのメカニズムは不明でした。この研究では、脳の視床下部にある神経細胞の構造が変化することで中年太りが引き起こされているのではないかと探られました。研究グループはラットを用いて代謝や摂食を調節する脳の視床下部の神経細胞ニューロンに着目し、特に抗肥満機能を持つ「メラノコルチン4型需要体(MC4R)」の細胞内局在が加齢によってどのように変化するのかを調査しました。このMC4Rは脂肪が蓄積するにつれて太ってきているという情報を受け取り、代謝を促したり食べる量を減らしたりする指令を出すタンパク質です。研究グループは、MC4Rを可視化できる信頼性の高い抗体を用いて調査した結果、MC4Rが視床下部ニューロンのアンテナ構造に局在し、その一次繊毛が加齢に伴って退縮することを明らかにしました。
局在一次繊毛の退縮は、過栄養状態で促進され、ラットが摂取する餌の量を制限すると抑制されました。この研究成果は、肥満の根本的な原因に迫るものであり、肥満に起因する糖尿病などの様々な生活習慣病の未病段階での予防法や画期的な治療法の開発につがることが期待されています。
東洋医学で診る「汚デブ菌」
東洋医学では、「気」「血」「津液(水)」の3つが健康を支えていると考えます。この3つが身体をスムーズに巡れば、人は健康状態を保てますが、不足したり、滞ったりすれば、人は健康を損なうことになります。
3つの内、「津液(水)」が関係する体質としては、「陰虚」と「痰湿」があります。「痰湿」体質の方は、水分代謝がうまくいかず、余分な水分や脂肪が溜まっている状態です。つまり、この体質は食べ物や老廃物がヘドロのように胃腸に溜まってしまう体質です。
その結果、体が余分なものを外に排泄しようと、体に溜まった老廃物、つまり「痰湿」が、ニキビ、吹き出物、痰、おりもの、ときには軟便や下痢となって体の外へ出ようとします。そして痩せにくく、水を飲んでも、空気を吸っても太る…そんな状態になってしまいます。
この「痰湿」体質の人は暴飲暴食、脂っぽいものや甘い物の摂過ぎ、運動不足の傾向があり、肥満、体脂肪率や皮下脂肪が高い、また血中コレステロールや中性脂肪が高く、高脂血症になりやすい傾向があります。その他、頭が重い、体がだるい、吐き気やめまいが出やすい、痰が多い、むくみなども表れます。
「痰湿」体質にはさらに、体が冷えて舌には白いベトベトした厚い苔が見られる「寒のタイプ」と、体に熱のこもり、舌には黄色いベトベトした厚い苔が見られる「熱のタイプ」に分かれます。
「痰湿」改善のポイント
「痰湿」改善のポイントは、まず食べ過ぎないことです。食事をよく噛んで食べると、過度の食欲と食べ過ぎを抑えてくれる効果があります。よく噛む習慣を身に付けるように心掛けましょう。その上で、チョコレートや生クリームなどの糖質の多いものは控えめに、油っこいもの、お酒の飲みすぎも避ける…。
そして、水の代謝をよくするオススメ食材の、昆布・ワカメ・のりなどの海藻類、イワシ・サンマ、たけのこ、ごぼう、レタス、白菜、大根、玄米、とうもろこし、大豆、小豆、枝豆、黒豆を摂りましょう。
その他には、「痰湿」体質を改善する大事なことは毎日運動をすることです。運動を行い、汗をかいて体に溜まった余分な水分や老廃物を積極的に排出することで、少しづつ体質改善に繋がります。
ダイエットに失敗するデブ味覚
食欲を抑えるのが難しい理由に、味覚が鈍感になっていることが挙げられます。肥満の人の多くは、甘味、酸味、塩味、苦味の4つの味覚が鈍感になり、標準的な体型の人とは異なった味覚(デブ味覚)になっていることが指摘されています。
肥満度の表す指標にBMIがますが、22 前後が標準体型、25以上になると一般的に肥満と言われますが、オーストラリアで行われた味覚と肥満に関する研究によれば、BMIが25以上の肥満の人と標準体重以下の人を比べところ、BMIが25以上のグループの方は味覚が鈍感だったという結果が出ています。つまり味覚が鈍感になるとたくさん食べても満足することができず、必要以上に食べ過ぎてしまことで太ってしまいます。
私たちの舌には、味蕾(ミライ)と呼ばれる突起物があり、この部分で食べ物の味を感じ取ります。基本の4つの味覚にはそれぞれ敏感さに差があり、最も感じやすいのが苦味です。苦味を感じやすのは、私たちの体は苦味=有害物と判断する機能が備わっており、苦味の感覚が鋭くなっています。この苦味には、本能的に食欲を抑制する働きがあります。
次に敏感な味覚は酸味で、酸味は腐敗を感知します。酸味が鋭いのも苦味と同じように有害な物質を避けるためです。味覚が敏感な苦みと酸味が含まれている食べ物は日常の食生活で摂り過ぎることはそんなにありません。一方で甘味と塩味は、味を感じにくい味覚です。甘味を感じる糖は体のエネルギー源となるため生命活動を維持するために積極的に摂取する必要があります。塩分も体のミネラルバランスを調整する ために必要な栄養素となり、一定以上の塩分を摂取しなければなりません。このように甘味と塩味は必要不可欠な栄養素なので味の感度を避けて摂取量を増やし食欲を増進する働きがあります。
このように味覚と食欲には深い関係があり、ダイエットを成功させるためには味覚をコントロールして食欲を抑えることが大事です。また最新の研究では、脂肪味という新たな味覚が発見されています。脂肪味が鈍感な人ほど肥満傾向にあることがわかっています。肥満の人ほど油っぽい食事を好むのは、脂肪味の感度が普通の人と比べてかなり落ちているからと言われています。
食欲を抑えられるようになるためには、この中で苦味を感じる機能をまずは取り戻すことが必要です。苦味をしっかりと感じることができれば、苦味が食欲のストッパーになってくれます。その理由は、舌が苦味を感じると苦み成分が信号化されて、脳の視床下部へと情報伝達されます。視床下部には食欲を高める神経の「アグーチ関連ペプチド産生神経」と、食欲を抑える神経の「プロオピオメラノコルチン酸性神経」があります。苦味の信号は食欲を抑える「プロオピオメラノコルチン酸性神経」に伝達され、食欲が落ち、少しの食事量でも満足できるようになります。
また、苦味の信号が脳に送られることで、味覚が根本から変化するため食の好みも変わっていきます。そのため油っぽいもの、甘いもの 、濃い味を受け付けなくなり、あっさりとした味のものを美味しく感じるようになるはずです。
また、苦味は胆汁の分泌を促進するという働きもあり、なかなか痩せないという人は胆汁の分泌不足が原因の一つと言われています。胆汁は摂取した脂肪を分解して、栄養を吸収しやすいようにする役割を担っています。胆汁が正常に働いていれば脂肪が分解されていきますが、肥満の人は胆汁の分泌量が少ないため脂肪が分解されずにお腹やお尻などに脂肪がついてしまいます。
私たちは苦味を感じると、肝臓から胆汁がよく分泌されるようになります。しかも研究によると、苦い食べ物を食べなくても、舌で苦味を感じるだけで胆汁の分泌促進効果があると分かっています。
一方で、苦味に対する感受性は人種によって大きく違い、世界には苦味を感じない人が多くいます。例えば中国では6から23% インドでは40%、ヨーロッパでは30%の人が苦味を感じないと言われています。日本人は9割の人が苦みを感じやすい遺伝子を 持っていると言われています。
東洋医学で診る「太りにくい体づくり」
人の身体を構成し、全身を巡る3つの要素が「気•血•水」です。
「気」は、元気や気力などの生命エネルギーのことで、神経機能を担います。
「血」は、全身を巡って栄養を運ぶ血液のことを主に指します。
「水」は、水分の代謝や免疫系など血液以外の体液のことです。
東洋医学では、太りにくい体づくりは「気•血•水」のバランスを整え、代謝を活発にすることで、脂肪がつきにくくなり太りにくい体になっていくと考えます。
「気•血•水」は中医学的には五臓(肝・心・脾・肺・腎)と合わせて考える必要があり、複雑な仕組みの上に成り立っています。例えば「食べること(脾胃の機能)」や「呼吸すること(肺の機能)」で「気」がつくられます。食べ物が消化されたものから「水」がつくられ、消化されたものと「気」から「血」がつくられます。つくられた「血」は「肝」に蓄えられ「心」の働きで全身に巡り、「水」は「肺」の働きで同じく全身に巡ります。最終的に水は「腎」から排泄され「血」は肝に入り、睡眠中に浄化されます。
このサイクルの中で、胃腸の働きが悪いと、体の脂肪を燃焼させる働きも低下してしまいます。つまり胃腸が弱いと基礎代謝が低下して、返って太ってしまうことさえあるのです。また肝臓には、食物から吸収された栄養素をからだが利用しやすい形に分解・合成する「代謝」の機能があり、肝臓の疲れも太ってしまう原因となります。
東洋医学で胃腸は「脾」、肝臓は「肝」です。「脾」や「肝」の働きを高めることは脂肪を燃焼しやすい体づくりに効果があります。
太りにくい体づくりのための代謝
太りにくい体づくりには、代謝を意識する必要があります。代謝は生きて行くのに必要なエネルギーを作り出すことですが、消費されるエネルギーを上げることで太りにくい体質になります。代謝には生活活動代謝、食事誘発性熱産生、基礎代謝の3種類があります。
生活活動代謝は、日常生活の中で体を動かすときに消費されるエネルギー代謝のことです。1日に消費されるエネルギーのうち、約30%が生活活動代謝です。日常生活の活動量を上げるため、なるべく歩くこと、テレビを見ながら腹筋するなどの「○○しながら運動する」ことを意識してみましょう。
食事誘発性熱産生は、簡単に言うと食事によって栄養素が分解される時に、そのエネルギーが消費される過程で体が温かくなることで発生します。1日に消費されるエネルギー量のうち食事誘発性熱産生は約10%です。最も効果的なのは、よく噛んで食べることです。よく噛むことで満腹感を得られるだけでなく、代謝を上げてくれる効果もあります。
そして、最も重要なのが基礎代謝です。1日に消費されるエネルギー量のうち、約60%と大きな割合を占めています。基礎代謝の約30%は肝臓や腎臓といった内臓が占め、次に筋肉が占める割合が20%前後です。つまり、肝臓や腎臓といった内臓を労わり、運動などで筋肉をつけていくことが大切です。特に肝臓が占める基礎代謝量は全体の21%と高く、基礎代謝を上げるために肝臓をケアしましょう。
就寝3時間前には食事を終えるようにして、寝ている間に肝臓を含めた内臓をしっかり休ませてあげることを心がけましょう。 と、内臓の中でも大きな割合を占めています。肝臓は代謝、解毒、エネルギーの貯蔵、胆汁の生成・分泌と様々な働きを担っているため、知らず知らずのうちに肝臓を疲れさせていることも。基礎代謝を上げるためには、肝臓を疲れさせないことも大切です。
代謝が上がる抹茶
抹茶と緑茶は原材料の茶葉の種類はほとんど同じですが、抹茶の方が手間暇かけてつくられているため、抹茶1杯に含まれる抗酸化物質は緑茶約3カップ分相当となり、健康効果がさらに高いことが知られてきました。この抗酸化物質は体の酸化を予防し、細胞の損傷を減らし、慢性疾患を予防してくれる効果があります。
一方で減量のためのサプリメントを見てみると緑茶抽出物と書かれているものが多いように、抹茶や緑茶の痩せる効果が知られています。実際、研究でも代謝を促進して、エネルギー消費を増やし、脂肪燃焼を促進するのに役立つことが示唆されています。適度な運動中に緑茶抽出物を摂取すると脂肪燃焼が17%増加することも確認されており、サプリでもプラセボと比較して24時間のエネルギー消費が大幅に増加したことも分かっています。さらに緑茶が体重を減らし体重減少を維持するのを助けてくれるという研究も数多くあります。
さらに抹茶に含まれる「リパーゼ」という脂肪の分解を促進する酵素の働きを活性化させる働きがあり、その働きによって体内の脂肪が分解され、エネルギーとして消費されるようになります。また食物繊維も多く含まれているため、腸内環境を整えてくれるとともに、血糖値の上昇をゆるやかにしてくれて太りにくい体質づくりができます。このようにダイエットに強い味方になるのが抹茶です。
ただし、1日2杯(474ml)までにしておきましょう。なぜなら農薬や土壌汚染リスクがあるためです。どんなに体に良い食べ物や飲み物でも適量を摂取することを心がけましょう。
太りにくい体づくりのツボ
太りやすい理由には「脾」の消化作用が関係しています。そのため、まずは体調を整えるツボで「脾」の働きを高めて、食べたものがきちんと消化されることで、健康的で美しい体を保ちましょう。
血の巡りをよくする
三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分、上にいったところの骨ぎわ。

胃腸の働きを回復
足三里(あしさんり):膝の下の外側のくぼみから、指4本分下がったところ。

消化機能を整える
曲池(きょくち):ひじを曲げたときにできるシワの、親指側のきわ。
肝臓の疲れを取る
肝兪(かんゆ):背中の真ん中から、指2本分ぐらい外側の位置。

もちろん本格的に痩せたい方は運動を取り入れることがベストです。ぜひダイエットのサポートとしてご活用ください。
「痰湿」体質おすすめのツボ
水分代謝を促すツボ
水分(すいぶん):おへそから真上に親指の幅1本分上がったところ。

胃腸トラブル、便秘、下痢を緩和するツボ
大腸兪(だいちょうゆ):背骨と左右の骨盤を結んだ線の交わるところ。

日々の食事やマッサージで、体内の老廃物を排泄しやすいように養生を心がけ、ダイエットをする前には痰湿体質を改善してムダなく効率的に結果をだしましょう!自分の体質を知ることで改善方法はかわります。体質改善を考えている方はどうぞご相談くださいませ。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。