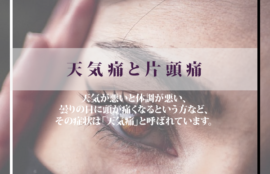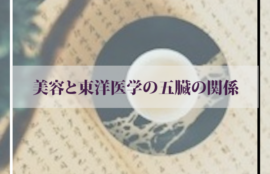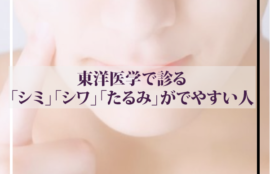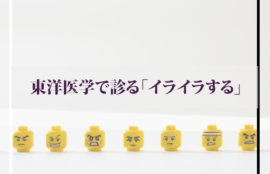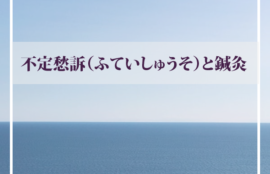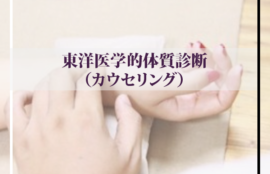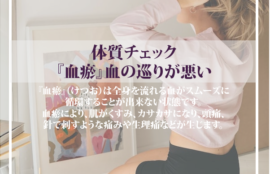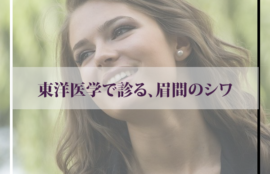以前は、筋肉に乳酸が溜まると疲労につがるって言われていましたが、最近の研究では、乳酸は疲労の結果として溜まるものであり、疲労の原因は酸化ストレスではないかと考えられるようになりました。山口大学大学院医学系研究科の研究論文「疲労病態における酸化ストレス、抗酸化力の評価」でも酸化ストレスと疲労の関係について詳しく検証されています。
酸化ストレスは、体内で活性酸素が増えすぎて、それを除去する体の抗酸化機能が追いつかなくなる状態のことです。活性酸素は、生活習慣や病気、ストレスや老化などをきっかけに体内で通常の酸素が活性酸素に変化します。適度な量の活性酸素は、細胞伝達物質になったり免疫の役目を果たしますが、過剰になると細胞を傷つけたり、癌や血管の病気とか生活習慣病の原因になります。
その活性酸素が疲労の原因である酸化ストレスを体に引き起こしています。つまり疲労を回復させるためには活性酸素を減らすことが大事になり、具体的には適度な休息と睡眠、ストレスの解消、抗酸化成分を多く含んだ食事など、普段から心がけていれば活性酸素の過剰 な増加を抑えることにも繋がります。活性酸素が増えないように生活することは、疲労の一員である酸化ストレスを引き起こさないことにもなり、生活習慣病の予防になるため、是非実践して欲しいことです。
疲労とは何か
疲労には大きく分けて「末梢性疲労」と「中枢性疲労」の2種類あります。1つ目の末梢性疲労は、一般的に体の疲れのことです。運動をすると筋肉に蓄積されていたエネルギーが消費され、足りなくなると筋肉の神経伝達が遅れてしまい、これが疲労として感じられます。また激しい運動をすると筋肉で炎症が起こり、その回復のために必要な休息をしろという信号が脳から出て疲労という形で表れます。
2つ目の中枢性疲労は、体の 疲労ではなくて頭脳や精神的な疲労のことです。勉強するとか、作業するとか長い時間に集中した時や過剰なストレスを受け続けた時に脳細胞が疲労を感じる疲労です。その2つの疲労ともに活性酸素が関係しています。
活性酸素が発生するのは体や精神、つまり脳に負荷がかかった時です。つまり徹夜や激しい運動やストレスで活性酸素が発生すると、その活性酸素が細胞を傷つけて老廃物が発生します。そして次に問題になるのは、疲労因子(Fatigue Factor)というタンパク質です。近年の研究で明らかになり、活性酸素が傷つけた細胞から老廃物が出ると、この老廃物が疲労因子(FF)の発生を促していることが分かってきました。そしてFFが血液中で増えて人の脳に疲労シグナルを送り、脳が疲れを感じることになります。
一方、疲労回復因子(Fatigue Recovery Factor)いうタンパク質も見つかっています。疲労回復因子FRは、活性酸素で傷つけられた細胞を修復してくれ、疲労因子FFが増えると付き合うように疲労回復因FRも増えます。疲労の初期ではFFが増えて疲労状態になりますが、FFの増加をきっかけにFRも増え始めて、FFよりもFRの方が多くなり、疲労が回復していきます。このFRは適度な運動をしたり、十分な急速を取ればより効率的に増えることが分かっています。
疲れが残ってしまう原因
運動不足
疲れている時は体を休める自体は大事なことですが、ずっと動かないでいたりすると返ってストレスの原因になってしまいます。2017年に運動とメンタルの関係性を追跡調査した研究があり、この結果で週に1時間程度の軽くでもいいから運動している人は、メンタルが悪化するリスクが12%も下がった報告があります。研究では、まとめて1時間の運動をしなくても、1日10分程度の運動を毎日続けるだけで、1時間まとめた運動をした時と同じくらいのストレス解消効果が発揮されることが分かっています。
適度な運動をすると脳内ではセロトニンと呼ばれるホルモンが分泌され、セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれ、メンタルが改善する効果が期待できます。運動を続けている人は、運動後にすっきりして気持ちいいっていう人が多いですが、これはセロトニンの効果で心が落ち着いたり、前向きな気持ちになれるからです。
また、あまりに筋肉を動かさないと血流も悪くなり、体中に酸素がしっかり生き渡らないため、疲れも取れなくなってしまいます。急に激しい運動をするのではなく、まずはウォーキングとか軽い運動から始めてみるのがおすすめです。
悩み事を溜め込んでいる
悩み事を吐き出さずに自分の中に溜め込んでしまう、と体が休まっていてもメンタルが休まらず、どんどん疲れが溜まります。そのため溜め込んでしまっている思いや悩み事は、ぜひ紙に書き出してみましょう。紙に書き出すと気分がすっきりしてポジティブな気持ちを取り戻すことができます。
これはカリフォルニア大学が行った複数の研究で証明されており、自分が感じている気持ちを言葉にして紙に書き出すだけで幸福感は上がって、ネガティブな感情は下がることが確認されています。また気持ちを書き出すことを続けて いると数週間から数ヶ月で、うつや不安の症状が改善することも分かっています。
紙に書くだけで効果が発揮されるのは、悩み事をいつも抱え込んでいる人は、悩み事のために脳の機能を使ってしまっているからです。つまりあれこれ悩んだり、考え事したりしてるだけで疲れてしまう原因になります。紙に書き出すことで自分が悩んでいることが整理され、脳が無駄なエネルギーを使わなくて済むようになります。
これを心理学では、エクスプレッシブライティングと呼びます。書き方のポイントとしては、事実とその時の気持ちをセットで書くことが挙げられます。例えば今日仕事で得意先からすごく叱られて腹が立ったなど、胸の中に貯めていた思いを全部書き出したらゴミに捨てると良いでしょう(ネガティブダスト)。
疲労が溜まる原因や行動
疲労が溜まる原因は、活性酸素がたくさん発生することであり、つまり活性酸素を多く発生させる行動をすれば疲労が溜まってしまうことになります。例えば、睡眠不足は活性酸素を多量に発生させるし、長時間の集中力を伴う緊張も活性酸素の発生につながります。その活性酸素が細胞を傷つけて老廃物を出し、その老廃物が疲労因子FFを増やしてしまいます。
またデスクワークで同じ姿勢を続けたり、無理な動作を繰り返すことで起こる筋肉の凝りも同じで、逆に運動不足でも活性酸素の発生につながります。運動不足になると新陳代謝などが低くなり、体内では血液や水分の循環が悪くなります。それは筋肉の凝りに近い状態です。つまり激しい運動は疲労に繋がりますが、動かなすぎても活性酸素が発生するため、適度で軽い運動は疲労の予防になります。
身体と疲労の繋がり
体の歪み
疲労の原因は体の歪みから来ていると考えられています。猫背の人や左右の型の高さが違う人だけが原因ではなく、足を組んで座る、バッグをいつも片方の型にかけるといった体のバランスを崩すような生活習慣の積み重ねが体の歪みの大きな原因になっています。疲れにくい体になるためにも体を歪ませる生活習慣は見直しましょう。
体が歪むと体の動きをコントロールする中枢神経からの指令が手や足などにうまく伝達されなくなります。それによって体を思うように動かせない状態になり、体がだるい、重いといった疲れを感じる原因になります。脳と脊髄からなる中枢神経は体の中心を通っているため、体が歪むことで中枢神経も一緒に歪み、中枢神経の働きが悪くなることになります。しかも体の歪みは疲れだけではなく、自律神経失調症にも繋がります。
自立神経失調症は交感神経と副交換神経からなる自律神経のバランスが崩れることで起こります。つまり中枢神経と同じように体の中心を通る脳と脊髄がスタート地点になっている自律神経も体の歪みによって一緒に歪んでしまい、伝達がスムーズに行われなくなり、自律神経が乱れ余計に疲労を感じやすくなってしまいます。
また、大阪市や大阪市立大学、食品、医薬品メーカーなどが進めている疲労に関する共同研究の疲労プロジェクトによると、疲労の原因は交換神経が活発に働くことで神経細胞内に活性酸素が大量に発生し、細胞にダメージを与えることが原因と考えられています。体が歪むことで筋肉が緊張し、それがストレスとなって交感神経が働くことも分かっています。これを考えると体が歪めば歪むほど神経細胞内で活性酸素が溜まっていき、それが引き金となって神経伝達もスムーズにいかなくなり、体がどんどん疲れやすい状態になってしまいます。
活性酸素
疲れを感じる主な原因の1つは活性酸素と言われています。活性酸素は、体内に入った酸素が通常よりも活性化された状態のことを示します。厚生労働省の提供しているEヘルスネットでは、活性酸素は細胞伝達物質や免疫機能として働く一方で、過剰な酸性は細胞を障害し、心血管疾患並びに生活習慣病など様様な疾患をもたらす要因とされています。しかしながら強い酸化力を生かして細菌やウイルスを撃退したり、細胞間の伝達を担っています。
まず欠かさず取って欲しいものはビタミンです。活性酸素の働きを抑えるビタミンを抗酸化ビタミンと呼ばれており、特に有名なのがビタミンCです。ビタミンCを含む食材にレモンが有名ですが、ピーマンやブロッコリー、パセリといった緑色の野菜にもビタミンCは多く含まれています。また野菜にはビタミンAやビタミンE、それ以外にもポリフェノールといった色素成分など抗酸化力のある栄養が他にも含まれています。
不規則な睡眠
不規則な睡眠だと疲れが取れないのは、不規則な睡眠によって体内時計が乱れることで疲れが取れにくくなってしまうからです。体は一定のリズムに合わせて機能されており、体内時計は体の中にある昼と夜を認識している時計のようなものです。その時計によって体の中では様々な生理的なプロセスを調整しており、例えば体温やホルモンの分泌睡眠と覚醒のサイクルを調整しています。体内時計が正常に機能していれば、これらのリズムが安定し、健康な状態を保つことに役立ちます。
体内時計と睡眠は深く関係しており、体内時計が昼夜を正確に認識できると夜 に睡眠を取るように調整されます。不規則な生活習慣や夜更かしは体内時計の乱れを引き起こし、それが疲れやストレスの原因になります同じ時間に寝て、同じ時間に起きれるように努力することが大切です。
過度なストレス
ストレスによって疲れが取れにくくなるのは、そもそもストレスというのは体に様々な影響を与え、例えばストレスホルモンの分泌が増えることで心拍数と血圧が上昇し、体が緊張状態になるため疲れが取れにくくなります。ストレスホルモンは、コルチゾールやアドレナリンが該当しますが、体が環境に適応するために分泌されるものであって、これが長期的に分泌されると体内で悪影響を及ぼします。またストレスが原因で夜に眠れず、体が回復できずに疲労を蓄積してしまうケースもあります。
ストレス解消には、趣味を楽しむこと、スポーツや旅行など息抜きすることが大切です。そして様々なリラックス法を試してみて自分が合うと思ったリラックス法を続けてみましょう。他にもビタミンCやマグネシウムもストレス軽減に役立つため、積極的に摂取しましょう。
水分不足
水分は体を作る上でとても大事、水分不足は疲労に繋がります。まず成人で体の中の水分量は約60%と言われており、当たり前ですが体の中を流れる血液もリンパなどにも水が必要です。水分が不足すると血液はドロドロになってしまい、また汗もかけないため体温調節も上手くできません。そうなると疲労感だけでなく頭痛、めまい、集中力の低下便秘など様々なところで不調が発生します。体の調節機能がうまく働かなくなるため、至るところで不調が起きてしまいます。
慢性疲労の原因「副腎」
いくら寝ても疲れが取れない、こんな慢性疲労に悩まされていて毎日が辛いですという方、そして病院に行ったとしても病名がつかない、原因が分からないと悩んでいる方は多いでしょう。原因がよくわからず、病気ではないため頑張らなきゃと毎日疲れた体に鞭を打っている人も多いかもしれません。
ですが寝ても取れない、しつこい疲れの原因は年のせいでもなく、ましてや気のせいでもありません。その原因は副腎にあります。疲れの原因の9割は、副腎であることが最新の知見によって分かってきています。
この副腎疲労は多くの人に見られる症状で、慢性的に疲れている人によく見られる状態です。副腎疲労とは副腎という臓器が酷使されて疲れきってしまう症状のことです。副腎疲労は、子供から高齢者まで幅広く見られる症状ですが、最も多いのが30代から40代の働き盛りの世代であると言われています。
副腎は腎臓の上に位置する約2から3cmの小さな三角形の形をした臓器で、左右に1つずつあります。1つは約4から5g程度の非常に小さな臓器ですが、人が生きるために必要なホルモンを分泌するとても大切な臓器です。副腎は元気の元になるホルモンであるコルチゾールを分泌し、パワーを出す役割があります。そしてこのコルチゾールは早朝をピークに最も多く分泌されます。やがてコルチゾールの分泌量は昼にかけてなだらかに減少し、そして夕方から夜になればコルチゾールはほとんど分泌されなくなり、その分泌量が下がれば夜にぐっすり眠ることができます。
このコルチゾールが分泌されなくなるとやる気がなくなり、疲れが慢性化して常にバテた状態になります。つまり副腎が疲弊すると元気の元であるコルチゾールが激減し、気力がなくなり、ずっと疲れを感じるようになります。そしてコルチゾールには元気を出すという役割以外にも体内の炎症を抑えるという大切な役割があります。
認知症を始めとする老化症状は、体内の炎症が大きな原因の1つのため体内の炎症を的確に抑えることができれば、認知症だけでなく生活習慣病なども改善 することができます。逆に言うと炎症を放置すると老化し、認知症を始めとした加齢性の病気にかかりやすくなることになります。
現代では私たちは様々なストレスに晒されており、このストレスが様々な形で体に炎症を引き起こしています。しかし私たちの体には起ってしまった炎症を 抑えてくれる機能が元来備わっており、そのホルモンがコルチゾールです。
この副腎の疲れという概念は、アメリカやヨーロッパの抗加齢医学会でも副腎疲労が注目されており、実際に臨床の現場にも副腎のケアが取り入れられています。
疲れが取れる食品
実は炎症を修復するためには亜鉛という栄養素が欠かせません。亜鉛を摂取することで炎症を正しく修復すれば、副腎の負担が減り、副腎が徐々に回復して いきます。また亜鉛は男性ホルモンであるテストステロンにも大いに関係しています。
テストステロンは若々しさを保つホルモンであり、モチベーションややる気、意欲などにも大きく関係しています。加齢とともにテストステロンは自然に減少していきますが、テストステロンの減少が早いと老化スピードが加速してしまうことが分かっています。またテストステロンが減少していくとメンタルの健康が崩れてしまったり、疲労感、イライラといった症状が現れるようになります。
またテストステロンは男性ホルモンという名前がついていますが、女性の体内でも分泌されており、女性にとっても非常に重要なホルモンです。そのテストステロンの不足を解消する方法の1つが亜鉛を摂取することです。亜鉛はそもそも人間の体にとって必要不可欠な必須ミネラルの1つであり、そして体の中で実に様々な大切な役割を持っています。
亜鉛が豊富に含まれている食べ物の代表が貝類です。そして貝類の中でも特に牡です牡蠣には亜鉛がダントツで多く含まれており、効率的に亜鉛を補うことができます。その他の食材では、魚介類やレバーなどに亜鉛は多く含まれています。
現代人の疲労
現代人の疲労は体の疲労というのは少なくなっており、大半は脳の疲労です。つまり筋肉疲労の抹消性疲労ではなく、中枢性疲労が圧倒的に多くなっています。体が疲れているのではなく、脳が疲労して体も疲労していると思い込んでいる方が多くいます。激しい運動をしたわけでもないのに全身疲れていると感じた場合は、脳が疲れているだけの可能性があります。そのため脳の疲労をリセットできれば全身の疲労も軽くなります。
その脳の疲労を取る方法は、目を閉じて疲れ目を緩和することです。実は脳の疲れの原因の多くは眼精疲労の場合が多いです。人は情報の80%を視覚から集めており、しばらく目を閉じるだけでも脳を休ませることになります。また眼精疲労解消のツボ押しも脳の疲れの解消に良いです。
眼精疲労のツボ
デスクワークが多く、スマホを手放せない人も多いため、以前にもまして目を酷使している人ばかりです。パソコンやスマホを見続けた後、目が疲れたと思った時休息や睡眠を取って治る場合は疲れ目が原因です。しかし十分に休んでも目に疲れが残ったり、痛み続けたり、肩こりや首こり、頭痛吐き気やめまいも起こったりすれば、それは眼精疲労です。眼精疲労の時には、とにかく目を休めるのが1番で、そしてツボ押しもお勧めです。
- 太陽(たいよう):眉毛の1番外側と目尻のちょうど間の高さで、目の外側こめかみのくぼみ
- 魚腰(ぎょよう):眉毛のちょうど真ん中にあるくぼみ
- 瞳子髎(どうしりょう):目尻から指1本分外側を触ってくぼみがあるところ
- 四白(しはく):目のちょうど真ん中から下の方、胸骨にあるくぼみ
- 晴明 (せいめい):目の一番内側と 鼻の付け根の間にくぼみ
パワーナップ(昼寝)
昼寝は、パワーナップと言って短時間の昼寝のことで、具体的には12時から15時の昼間に寝る15 分から30分ほどの昼寝のことです。30分以上寝てしまうとより深く寝てしまうから目覚めが辛くなります。ちなみにレム睡眠は、浅い眠りでノンレム睡眠が深い眠りで、夜の睡眠では、この2つを何回か交互にくり返します。そしてパワーナップはノンレム睡眠のみで目を覚ます昼寝になります。
ノンレム睡眠は4つのステージに分けられ、睡眠状態になって20分ほどの段階でノンレム睡眠のステージ2になります。カリフォルニア大学バークレー校の神経科学者マシュー・ウォーカー先生の研究で明らかになったのは、このステージで脳内がクリアに掃除されることです。
実は脳はコンピュータに近く、コンピュータのキャッシュメモリは大量の情報が処理される中で情報データを一時的に保持して、情報処理装置CPUの命令で情報の出し入れする記録媒体です。脳では主に海馬がこのキャッシュメモリの役割を果たしており、ここで短期記憶 出し入れを行っています。この機能をワーキングメモリとも言い、ワーキングメモリは疲労すると短期記憶のゴミが溜まってしまうことが分かっています。さらに逆に溜まることで疲労と感じてもしまいます。コンピュータでは、同時に多くのアプリを動かし過ぎるとコンピュータの動きが遅くなり、これはメモリに多くのデータが呼び出されていて、作業に使える領域が少なくなってしまうからです。脳もこれに近く、ワーキングメモリに短期記憶のゴミが溜まると脳全体の活動が悪くなります。
疲れを残さない方法
腹8分目の食事
食事では、いろんな栄養素を摂ることを意識して沢山食べてしまうと消化に時間がかかって疲れてしまいます。例えば午前中は元気だったのにランチ食べた 後は眠くなってぐったりするなど、食べ過ぎていることが多いと思います。満腹ではなく、腹8分目にすることで消化に時間をかけず、消化によるエネルギーロスを防ぐためにも、糖尿病などの生活習慣病の予防というためにも必要なので、まずは腹8分目に食事をすることを心がけましょう。
甘いものを単食食いしない
疲れたから甘いもの食べて補給すると、疲れが改善するようなイメージあると思いますが、瞬間的には元気になった後に疲れを感じる方が多いと思います。スイーツを食べて急激に血糖値が上がると、それを抑えようとインスリンが分泌されて血糖値を下げる働きがあります。その血糖値の乱高下が体にすごく負担になり、それによって疲れやすい体になってしまいます。もちろん脳のエネルギー源は糖質であるため、糖質を食べることが全部NGではありませんが、単食食いを避けるために、例えばグラノーラや干し芋のような糖分も入っていつつ、食物繊維も多いものを選んで食べましょう。
タンパク質とビタミンを意識して摂る
外食が多くなるとどうしても炭水化物よりの食事が多くなります。これは血糖値の乱高下につながり、疲れやすい体になってしまいます。体にはタンパク質とビタミが大事で、特にタンパク質は筋肉の元となり、代謝を上げて、疲れにくい体に必要です。つまり体を作る材料が少なくなると筋肉疲労の改善が遅くなったりします。
お肉やお魚も大切ですが、植物性のタンパク質の大豆など、いろんなタンパク質を摂ることが大事になります。もちろんプロテインを意識して摂ることも良いですが、なるべく食事でタンパク質を摂り、補助としてプロテインを活用しましょう。同じ観点からビタミンも代謝を回していく時に大事になってくるので、できれば食事で摂ることを心がけましょう。
下半身の筋肉をマッサージする
特に下半身は冷えやすく、むくみやすい場所です。大きな筋肉は下半身に集中しており、例えば太ももの筋肉、お尻の筋肉、ふくろはぎの筋肉がしなやかになると体全体の代謝は上がっていきます。
実は、疲れにくくするためには激しい運動や筋トレよりも下半身をしっかり使うような軽いウォーキングが適切です。なかなか時間が取れない方は、下半身の筋肉をしっかりと揉みほぐすマッサージやストレッチもおすすめです。
体を冷やさない
特に冬は外気が寒くなると体が縮こまって筋肉が硬くなってしまいます。そうなると血流が悪くなり、それによってだるさ、頭痛、体調不良に繋がりやすくなります。
体をなるべく温かい状態にすることで疲れにくくなっていきます。体温をしっかり上げていくことが大事なので、必ずシャワーだけではなく半身浴など体を温め、体を常に温かい状態にして血流を良くすることこそが疲労回復につがってくると思います。
疲労を回復する方法
体を動かす動的回復法
大量に汗をかくほどのきつい運動は、さらに疲労を貯めることになるため20から30分程度の動的回復法をするのがベストです。しかも軽めの運動は、疲れを解消するだけではなく、体の変な癖や歪みも直してくれます。
スウェーデンのカロリンス研究所で研究者として活躍したアンダースハンセン氏は人間の脳を始めとする中枢神経は原始時代から体を動かすための構造になっており、動き続けることが人間本来の姿だと言っています。
どうして軽めの有酸素運動をすると疲労の解消につがる理由は5つあります。①睡眠が深まる、②成長ホルモンが分泌される、③疲労物質が押し流される、④セロトニンが分泌され精神的疲労が回復する、⑤コルチゾールが低下し、ストレスが軽減される、です。
成長ホルモンは代謝を促す効果があるため疲労回復には、すごく大切なホルモンです。また寝ている間に分泌されることもあって睡眠も疲労の解消には欠かせない要素になっています。そして運動をすると血流が促進され、脳と筋肉にたくさんの酸素を送ることができるため、疲労物質が体の中に溜まるのを防ぐ ことができます。一方、幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンの分泌が促され、ストレスホルモンとも呼ばれるコルチゾールの分泌が抑制されることによって心のバランスを整えてくれることになります。
動的回復法は、疲労の解消が目的であるため、少し汗をかくぐらいの強度がベストで、ストレッチやウォーキング、入浴がおすすめです。動的回復法の入浴は、冷水シャワーとお湯に浸るのを交互に繰り返す交互浴と呼ばれるものです。具体的な方法は、1分間の冷水シャワー後にバスタブに30秒、冷水シャワー30秒の1 分間1セットの交互浴を約10回繰り返して、最後にまた冷水シャワーを1分間ほど浴びるというものです。これによって交感神経と副交感神経が交互に刺激され、自律神経が整います。
この入浴をする時には3つ注意して欲しいことがあり、まず1つ目は交互浴の前後にコップ1杯程度の水を飲むことで脱水症状を防ぐことです。2つ目は、長時間やりすぎないようにすること、3つ目はお湯を熱くしすぎないようにすることです。これは暑いお風呂に長時間入ると交感神経が優位になって、夜に寝られなくなるからです。大体40度くらいを目安にすると良いでしょう。
やっぱり睡眠も大事
スタンフォード大学では運動部の全選手にアイトラッキングテストっていう小さな黒点を目で追わせることで脳の動きを計測するテストをさせています。寝不足状態の脳は思っている以上に活動レベルが低下することが分かっており、疲れの原因になります。
まずは時間の確保が大事で、最低7時間は寝るようにした方が良いでしょう。またこれ以外にも次の4つのポイントを抑えておきましょう。①就寝時間、起床時間、睡眠時間は極力変えずに体のリズムをできるだけ一定にする、②休日に寝だめして体内時計を狂わせない、③就寝直前の交互浴は避け、寝る90分前までには入浴を済ませる、④IAP呼吸法を行う、です。
大学病院に勤務する交代勤務を行う看護師390人を対象に行ったアンケート調査を分析したところ、連休中に外出したり、散歩やドライブに行ったりする外出思考タイプに分類された交代勤務看護師では、2度寝をしたり朝ゆっくり起きたりする睡眠思考タイプや家でボーっとしたり、テレビ鑑賞をしたりする在宅思考タイプの人たちよりも有意に早い疲労回復、低い疲労度が示されています。
それに対して睡眠思考の交代勤務看護では優位に遅い回復を示しています。また2交代に比べ、3交代に従事する睡眠思考タイプの人で高疲労度を示していました。中でも外出思考タイプの人たちの疲労回復が早いことは、じっとしているより体を動かした方が疲労回復の効果があることを示しています。それに睡眠思考の交代勤務看護士で有意に遅い回復を示していたことから、休日の寝すぎが疲労の回復につながらないことの証明にもなっています。
この研究の疲労の回復についての判断は、疲労の回復状況については蓄積疲労度チェックリストを使って、簡単な質問で判断されています。つまり何か検査をした数値の結果ではなく、看護師の主観で疲労の度合が決められています。
IAP呼吸法
体の歪みを直して疲労を回復する方法は、最低でも 1日1回IAP呼吸法をすることです。IAPとは、イントラアブドミナルプレッシャーの略で、復活という意味があります。つまりIAP呼吸法とは、復活呼吸法のことで復活を高く保ったままで呼吸をする方法です。
複式呼吸は、息を吐く時にお腹もへこませて呼吸をしますが、この時膜が上がり腹圧も一緒に落ちてしまいます。腹圧呼吸では息を吐く時にお腹をへこまさず、そのまま腹圧を保って呼吸します。こうすることで腹部を取り囲んでいる横隔膜、内臓を支えている骨盤底筋群を支えているインナーマッスルが強化され、これらの筋肉がコルセットのように機能して内臓のずれや骨の歪みを改善してくれます。そして体の中心が定まれば無駄な動きがなくなり、同時に中枢神経の伝達、自律神経の乱れが改善し、疲労の予防や回復に繋がっていきます。
IAP呼吸法のやり方は、まず耳と肩のラインが真っすぐになるようにリラックスした状態で椅子に座ります。次に肩を上げずに5秒かけて鼻から目いっぱい息を吸いながらお腹を膨らませます。そして次が大事で、お腹に力を入れてお腹を膨らませたまま5から7秒かけて口から息を吐き切ります。この一連の流れを繰り返すのがIAP呼吸法です。特に寝る前に2分程度IAP呼吸法をすることで自律神経とホルモンのバランスが整い、睡眠時の疲労の回復率が上がるとされています。
鍼灸治療の疲労回復効果
鍼灸治療は、幅広い症状に対して効果が確認されており、WHO(世界保健機関)もその効果を認めています。特に疲労を引き起こす様々な原因に対して、根本的な改善が期待できるため、疲れが中々取れないなどに悩まされている方にもおすすめの治療法です。疲労回復効果を期待できる理由は、以下の3つが挙げられます。
免疫力アップ
疲労が溜まっている場合は、免疫力が下がっており、そのため外部からの刺激(細菌、塵埃、大気汚染等)に適応できず、体調不良を引き起こす原因となります。通常であれば体内に細菌などの異物が侵入すると、免疫機能が働き、その異物を排除しようとします。鍼灸治療では、このメカニズムを利用して、ツボを刺激することで免疫機能の働きを促進させることができます。
血行促進
身体に疲労が溜まると、筋肉がコリ、筋肉の役割である血液を送り出すポンプ機能が有効に働きません。そのため筋肉がコリ固まると血行が悪化し、その結果、全身の細胞に十分な栄養素が届けられなくなるだけでなく、老廃物を回収及び排出することもできなくなって、されに疲れが溜まっていきます。鍼灸でコリを解消し、血流をよくさせることで、血行不良によって引き起こされる様々な体調不良の原因を解消することができます。
自律神経を整える
過度なストレス、睡眠不足が続くと交感神経が過剰に働き、副交感神経が上手く機能しません。副交感神経が働かなければ、身体が休養できない状態になります。その結果、疲れているのに眠れない、イライラしてしまう、頭痛や耳鳴りなどの体調不良の原因になります。鍼灸には過剰に働いた交感神経を抑制し、副交感神経を活発にする効果があり、自律神経のバランスを整えることができます。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。