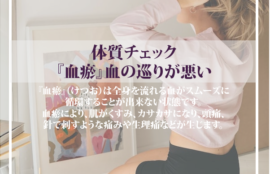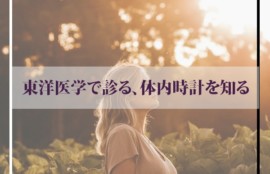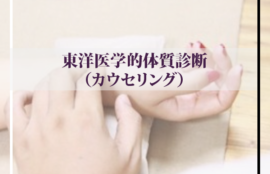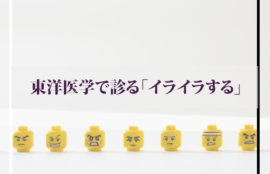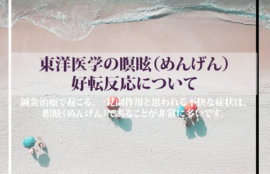私たちの身体が影響を受けるストレス、つまり感情が病気の原因に大きく関わることは西洋医学、東洋医学共に認められています。
不調や病気と戦わない
不調や病気が治りやすい人、治りづらい人の違いは、不調や病気と闘っている人ほど病気が治りづらいという研究があります。毎日とにかく病気を治そうと頑張り、心休まる暇などない人ほど大きなストレスが掛かっているからです。またこのような人は自分のネガティブな感情(不安など)をコントロールできていない特徴があります。
不調や病気と闘ってしまうと、短期的には副腎髄質からアドレナリンが、長期的には副腎皮質からコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されます。アドレナリンは、不安、恐怖、怒り、興奮などによって分泌されます。アドレナリンは、短時間ではストレスからの防衛ホルモンとして効果的に働きます。
アドレナリンの役割は、私たちの身体能力を高めて戦闘状態にすることです。しかしそれが長時間続いたり、1日何度も起こると体の機能を酷使し、体に無理がかかります。例えば心拍と血管が上がるために血管が収縮し、血流が悪化して全身の細胞に栄養が行き渡らなくなります。またアドレナリンは血小板の働きを活発化するため血液が固まりやすくなります。つまり血管の老化を加速させて、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクが高まってしまいます。また常に戦い続けていると自律神経が乱れて交感神経優位の状態が続き、夜に交感神経が鎮まらずに脳が覚醒したままになり、不眠などに繋がってしまいます。
私たちの体は短期的なストレスならば耐えることができますが、たとえ小さなストレスであっても長く続いてしまうと、心と体を確実に蝕んでいきます。ストレスが長期化するとコルチゾールというホルモンが過剰に分泌され血糖や血圧が上がり、体が休まりません。さらに免疫を抑える効果もあり免疫力が低下してしまいます。またコルチゾールレベルが高い人は高血圧、糖尿病、感染症などの原因にもなります。このように不調や病気と闘うことが不調や病気を悪化させる最大の原因になることがあります。
副腎疲労症候群とは
最近、寝ても疲れが取れない方は、心の疲労や肉体の疲労だけではなく、内臓特に副腎に疲労が溜まっているかもしれません。副腎に疲労が溜まることを「副腎疲労症候群」と言います。
副腎は、腎臓の上にある小さな臓器で、様々なホルモンを分泌しています。この副腎から分泌されるホルモンは、血圧や水分量、血糖などの体内環境を一定に保つために分泌されるホルモン群であり、生きていく上で重要なものになります。
そして副腎は体内環境を一定にするだけではなく、ストレスに対抗するためのコルチゾールというホルモンを分泌しています。コルチゾールは、もともと人類は飢餓というストレスの中で空腹でも狩りをしなければならないような時に 瞬間的に作用するホルモンでした。現代人は慢性的なストレスに晒されて、副腎がコルチゾールを出し続けて疲労が続いてしまい、これが副腎疲労になります。
副腎が疲労して機能が低下することによって引き起こされる症状としては、食欲 低下、それに伴う体重の減少、低血糖による集中力の低下、吐き気や下痢、月経不順、花粉症やアトピー、強いストレスの後にくる強いだるさ、疲労感などがあります。
慢性疲労症候群の原因
慢性疲労症候群の原因に考えられているのがストレスです。副腎は、ストレスを受けることでホルモンを過剰に分泌したり、分泌しなくなったりします。つまりストレスによってホルモンの分泌量が不安定になり、さらに副腎が疲れてしまうことになります。
そしてストレスには3種類あり、精神的なストレス、肉体的なストレス、環境的なストレスです。環境的なストレスは、排気ガスやカビ、知らずに吸っている有害なものも体内に小さな炎症を引き起こし、それがストレスになります。このように、副腎に影響を及ぼすストレスは様々なストレスが絡み合うことによって影響を引き起こすと考えられています。他にも生活リズムが乱れて睡眠不足や栄養不足になってしまうと副腎に疲労を溜め込んでしまうといった原因の一つと考えられています。また夜間はホルモンの分泌が最も活発になる時間帯ですが、この時間帯に休息を取らないとホルモンの分泌量が減って、副腎にまた疲労が加わってしまうことになります。
扁桃体が不快に思うことは止める
私たちの健康に大きな影響を与える自律神経や免疫力は、脳の扁桃体が不安という不快な刺激を受けることが要因として働くことが分かっています。つまり不安を感じているかどうかが健康に大きな影響を与えているのです。昔から病は気からと言われていたように、医学的に見ても正しいことが分かりつつあります。
扁桃体は日常の中で受ける刺激を快いものか不快なのかを判断する役割を持っています。美しい音楽から刺激を受ければ、扁桃体が心地よいと判断して体がリラックスします。一方で騒音の刺激を受ければ、不快のものと判断し、自律神経に働きかけて緊張させ、その状態が続くことで自律神経は乱れ、免疫力はどんどん低下していきます。
生活習慣を整えて、扁桃体が快い状態を作り出すことで自律神経が整い、免疫力がアップして健康な状態になります。さらに扁桃体を強化してあげることで、不快な刺激への抵抗性をつけることができます。扁桃体を整えるためには、不安イメージに上手に付き合っていく必要があります。
また私たちの体には扁桃体を刺激する皮膚センサー、目・耳・鼻・口などの感覚器官センサー、腸センサーの3つのセンサーがあり、これらのセンサーが外から刺激を受けます。この3つのセンサーが受ける刺激を不快しないようにすることで健康になっていきます。
面倒くさいを克服する方法
私たちの意欲や活力、欲求といった知的活動は全て脳内ホルモンによってコントロールされています。脳内ホルモンには、幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンや緊張をした時などに放出されるノルアドレナリンなどの様々なものがあります。その中でも特に面倒くさいの克服に役立つのがエンドルフィンとエンケファリンです。
私たちが物事を面倒くさいと思ってしまうのは、そもそもやらなければいけないタスクが好きではないからです。つまり脳にとって嫌いという感情は非常に大きなストレスになります。このことを逆手に取った科学的な方法があります。
それは意外ですが、嫌いなことを前にしたら「嫌だ嫌だ」と赤ん坊のように連呼する方法です。とにかく駄々をこねるんです。
世の中には我慢強い人もいれば少しのことにも我慢できない人もいます。実はこの両者の差こそ脳内ホルモンのエンドルフィンとエンケファリンの差であると言われています。これらエンドルフィンとエンケファリンには強い鎮静作用があります。脳内でエンドルフィンやエンケファリンが分泌されると、私たちの苦しみや痛みは消えます。このことを利用して何かストレスのかかることをやらなければいけない時、むしろ初めに多少のストレスをかけることでエンドルフィンやエンケファリンを意図的に分泌させることができます。そのためには、まず脳に苦痛を認知させることが重要です。
それが赤子のように「嫌だ嫌だ」と泣き叫んで、脳にこれからやろうとするタスクが苦痛であることを無理やり分からせることです。面倒くさいという程度のちょっとした苦痛だと脳がちゃんと苦痛を認知できていない可能性があります。そのため、まず苦痛を大袈裟に表現し、脳に認識させる必要があります。
ストレスが不調の原因
病気や体調不良は偶然でなく必然で起こります。なぜなら私たちの体は免疫を始めとする体内の防衛機能によって守られているはずなのに、生活習慣の中にそれが崩れる原因があるからです。
ストレスなどで心身に大きな負担がかかり続けると、免疫力を発動させる仕組みや生きるために必要なエネルギーをつくる仕組みがうまく働かなくなります。特にストレスによって自律神経の1つである交感神経が緊張し、血流障害や組織破壊などで不調や病気の原因になります。また最も免疫力を発揮するリンパ球が減少するため、病気や不調が治りにくくなります。
特に生きるために必要なエネルギーを生み出すミトコンドリアと解糖系が、血流障害によって低体温と低酸素状態になるとそれらの働きが抑制されます。このように病気や不調は、免疫力や生きるために必要なエネルギーが低下することにより起こります。
「泣く」ことが体によい理由
「笑う」ことで免疫力を上げることをご存知かもしれませんが、実は「泣く」ことも体に非常に良いです。無理をしたり、ストレスを抱えたりすると交感神経が緊張し、血流障害や組織破壊によって不調の原因になります。
その交感神経の緊張をその場で取る効果に優れているのが泣くことです。つまり泣くことで、交感神経の緊張が取れ、自立神経の偏りが整い、副交感神経の反応で体温が上がって血流が良くなります。この「泣く」ことが副交感神経の反応であるという証拠は、涙が副交感神経の分泌現象だからです。同じように泣く時に出る鼻水も副交感神経の分泌現象です。
心に響く歌を聴いたり、感動する映画を観て泣いたりすると清々しい気分になるのも同様の反応です。「泣く」とその場で交感神経の緊張が解放され、血流が改善して、体温も免疫力も上がります。「泣く」のは弱さの表れであると考えて、泣くことを我慢する必要はありません。「泣く」という行為は私たちが心身ともに健康でいるために必要です。
不快な刺激を減らす生活習慣
まず大事なのが、朝の習慣です。朝は体を休ませる副交換神経から体を起こして活動的にする交感神経へ切り替わります。この朝に快適な刺激を受けて扁桃体を整えることが、1日の体の状態を決定します。そのため皮膚センサーを朝に刺激することがベストタイミングになり、特に手足のツボを刺激してあげたり、擦ったりして刺激してあげることが大切です。
また体内時計が狂うと1日の始まりから扁桃体が不調のままになることが分かっています。そのため朝の太陽の光によって視覚センサーを刺激して、扁桃体を内側から安定させることが大切です。特に10分程度の太陽の光を浴びて目覚めることが扁桃体への快い刺激になります。太陽の光をゆっくり浴びると幸福ホルモンであるセロトニンが分泌され、扁桃体が不安定になるのを抑えてくれます。
いずれにせよ西洋医学、東洋医学でも心と身体を分けて考えるのではなく、むしろ身体の一部が心である、あるいは身体の一つの部分が心であると考えることができます。心と身体は分けることができない、身体が疲れれば、心も疲れますし、身体が休まれば、心も休まります。
身体を大事にすることで心が健康になる。身体に無理をさせることは心に無理をさせることになります。心を健やかに保つことが万病さえ起こさせない可能性があることが分かってきています。
「運動」でメンタルケア
現代病をはじめとした、様々な不調の原因の1つが「運動不足」です。なぜ運動が身体に良いのか、運動が私たちの人生にどのような効果があるのかを理解して実際に運動することが重要です。特に運動がもたらす効果が、心の状態と幸福感への影響です。運動をすることによってメンタルの健康を保つことができ、メンタルの疾患を予防することができます。運動は副作用のない最強の薬とも言われており、気持ちが晴れ、悲観的な考えが消え、自尊心が高まります。
実際にも研究によって、定期的な運動は抗うつ剤よりも強力であるとし、科学的に裏付けによる観点から、運動を重要な治療法と考えている医師も多くいます。また毎日20から30分ほどウォーキングすることで、うつを抑制する効果も研究で明らかになっています。
それではなぜ運動がメンタルの健康にとって効果的なのか、それは脳内神経伝達物質である「セロトニン」「ノルアドレナリン」「ドーパミン」にあります。これらは私たちの感情を決定しており、例えば「ノルアドレナリン」が分泌されれば、やる気や集中力につながり、「セロトニン」が分泌されれば幸せな気分になり、逆に不足すれば不安になったりします。つまり人の感情は所詮脳内の神経伝達物質によって決まっているのです。
運動にはこれらを副作用なく増やすことができ、効果は運動を終えた時に感じられ、その状態は1時間から数時間続きます。さらに定期的に運動することによって分泌される量も定期的に増えていくことが分かっています。そしてその効果も丸一日続くようになります。
近年注目されている運動効果として、「BDNF」があります。「BDNF」は脳由来神経栄養因子と言われるもので、脳の天然肥料や奇跡の物質とも表現されています。例えば「BDNF」は、脳細胞の損傷しないように保護し、新たに生まれた細胞を助け、初期段階の細胞の生存や成長を促す役割があります。また脳細胞リンクを強固にして、学習や記憶力を高め、脳の可塑性を促して老化を遅らせる働きがあります。
「BDNF」を効果的に増やす唯一の方法が「運動」です。定期的に運動すれば「BDNF」が増え、一旦増えた「BDNF」はすぐに下がるのではなく、2週間ほどで下がり始めることが分かっています。つまり毎日運動する必要はないのです。ちなみに「BDNF」を増やしたいのであればランニングなどの有酸素運動が効果的です。
周りの環境こそ大事
いつもネガティブ思考はメンタルに負担が大きく、その結果、交感神経が緊張してストレス系のホルモンであるコルチゾールなどの分泌量が増加し、幸福系ホルモンのセロトニンやオキシトシン、快楽系のホルモンなどが抑制されてしまうため、体全体がマイナス方向へ傾いていきます。
ネガティブ思考からポジティブ思考になるための方法は、ポジティブな人と付き合うことです。私たちは驚くほど他人からの影響を受けており、性格、趣味、思考パターン、習慣などは普段付き合っている人に大きな影響を受けています。つまり周りにポジティブな人がいればポジティブな人に、ネガティブな人が沢山いればネガティブな人になってしまうのです。
そんなに人は単純ではないと思われるかも知れませんが、しかしハーバード大学などの研究によって、肥満、飲酒、喫煙、睡眠不足、うつなど家族や友人の間で感染するということが明らかになっています。例えば妹が肥満になった女性は、将来肥満になる可能性が67%増加、兄弟が肥満になった男性は45%増加したことが分かっています。
そもそも私たちが周りにいる人に影響されるのは、私たちの脳には「ミラーニューロン」という神経細胞があるからです。例えば赤ちゃんが周りで喋っている言葉を、このミラーニューロンによって学習しているとも言われています。つまり、この細胞によって無意識に相手の発言や行動、習慣を真似してしまう性質があります。そのため他人の発言や行動、感情や習慣などが感染すると考えられています。
このミラーニューロンがある理由は、人に共感するためです。人は社会的な動物であり、皆が協力して暮らさなければならない生き物です。人が協力して生きるためには、他人の気持ちを推し量り、他人の痛みを理解し、共感することが大切です。だから相手の気持ちや行動を映し出す「ミラーニューロン」があり、それによって相手の発言や行動や習慣を真似してしまい、だからこそ付き合う人の影響を強く受けて、その行動や習慣が感染してしまうのです。
落ち込んだ時には掃除
何か気持ちが塞ぐことや落ち込むことがあるとなかなか立ち直れない人がいます。仕事でミスをした、人間関係でこじれてしまった、他人に裏切られてしまったと言った時、そのことがずっと心にわだかまってしまい気持ちの切り替えがうまくいかず悶々とした気持ちで毎日を過ごしてしまいます。
もちろん、どんなに健康な人でもメンタルにはブレがあり、落ち込むときがありますが、気持ちの切り替えが上手い人は落ち込んでいたって何も始まらないことを分かっています。周りの人から立ち直りが早いとか、メンタルが強いと見られている人は落ち込んだ時に速やかに対処ができる人です。
その人が落ち込んだ時にするのが体を動かすことです。とは言えメンタルがボロボロの状態で運動するのもハードルが高いと思う人におすすめしたいのが掃除です。何か嫌なことがあった落ち込んだことがあったら一生懸命に体を動かして無心で掃除をする。そうすれば余計なことを考えずに済み、掃除をすることによってその空間が綺麗になり、掃除をした後の清々しさを感じることができます。
綺麗な空間にいると清々しい気持ちになれて、晴れやかな気持ちになることができます。塞いだ気持ちも落ち込んだ気持ちも文字通り一掃されます。掃除というのは単にチリやホコリを払ったり、その場を磨いたりするだけのものでは なくて、自分の心についたチリやホコリを払って心を磨くという行為です。
自分にも他人にも求めすぎない
私たちはとにかく何でもかんでも求めすぎ、期待しすぎです。特に男女関係において完璧を求めてしまう傾向にあります。例えば夫婦の間であっても夫は妻に優しさ、思いやり、細やかな気遣いなどを求め、妻は夫に逞しさ、包容力、経済力などを求めたりします。
求めるのは自由ですが、自分が求めているものを何から何まで備えている完璧な人などこの世のどこを探したって見つかるわけがありません。その結果自分が求めている人が見つからないとか、自分が求めている風にパートナーが動いてくれない、求めていたパートナーとは違ったなどといった不満やイライラが生じてしまい、人間関係がこじれてしまいます。
また、男女関係のみならず、人間関係全般において求めすぎていないでしょうか。人間関係をうまく運ぶ極意は求めすぎないということ、他人とうまく関係 を結び、寛容であることの根っこに存在しているのは求めすぎない心です。
メンタル安定≒感謝すること
体の健康においても、メンタルにおいても良い習慣というのは非常に重要なことです。日頃の良い習慣が私たちの健康を育み、メンタルを安定させてくれます。一方で、自分を良くするための様々な良い努力をしつつも、それを無効化するマイナスの習慣を、無意識にほったらかしにしています。
例えば、コップに半分の水が入っているとします。ネガティブに考えがちな人は、グラスに水が半分しかないと思うでしょう。ですが、そのグラスに水が後半分も残っていると言い換えて欲しいのです。このようにポジティブな言葉に言い換える癖をつけることで、私たちは意識的に自分自身の心安定を取り戻すことができます。
そして、小さな幸せを探しそれに対して感謝してみてください。自分自身の苦しみに目を向ける場合と感謝に目を向けた場合とでメンタルに大きな違いが出ることが長年の研究によって分かってきました。
最新の心理学の研究では、毎日感謝できることを見つけるだけで、メンタルに強力な良い変化がもたらされることが分かっています。さらにアメリカ心理学会発行の専門誌に掲載された2003年の研究によると、感謝の心はメンタルの健康だけでなく、私たちの体の健康にも良い影響を及ぼすことが分かっています。感謝する人は、そうでない人よりも免疫力が高く、血圧も低くて、病気になりにくい傾向があります。また睡眠時間や睡眠の質も高く、目覚めた時の爽快感も良いことが分かりました。また感謝することで前向きな感情を呼び起こしポジティブマインドの連鎖に入ることができます。そのため日常的に感謝する人の方が幸せや満足感を経験しやすいと言われています。
何が何でもありがとう
私たちが傷ついたり悩んだりする原因の大半は人間関係にあります。人間関係の問題は様々な形で現れます。友人、家族、恋人、同僚など私たちが関わる人々との間の誤解、対立、期待と現実のギャップコミュニケーションの不足、価値観の違いなどが挙げられます。特に人々はそれぞれ異なる背景、信念、経験を持っています。これらは価値観の違いを生み出し、これが対立や摩擦の原因となることが大半です。また期待と現実のギャップに悩まされている人も多いでしょう。人々は他人に対してある程度の期待を持ちますが、これが現実と一致しない場合、失望や不満、イライラや怒りが生じることがあります。
例えば、相手の何気ない言動に、本人には悪意など微塵もないのにあんな対応されたなどとマイナス方向に深読みをしたり、少しぶっきらぼうな対応をされただけで嫌われていると思い込んでしまう人もいるでしょう。
しかし、図太い人というのは相手の言動に対し良い意味で鈍感でおおらかです。チクリと胸に刺さるような言葉も気にかけない、いちいち相手の行動や発言に悪意や悪い感情を剥ぎ取りません。もちろん相手の行動にカチンとくることはあります。そんな時は深い呼吸を数回して「ありがとう」を三度心の中で唱えましょう。すると怒りの感情はふっと静まります。これを心の中で唱えることによって怒りを鎮めることができ、過剰反応を防ぐことできます。
言霊の力
良い波動を宿す言葉で自分の心に呼びかけることが大切です。日本では古くから言霊の不思議な力が信じられていて、口にしたことは現実になると言われてきました。また子供の頃に親に「痛いの痛いの飛んでいけー」と言われて痛みが引いた経験がある方結構いらっしゃるのではないでしょうか。
私たちが使う言葉というのも現実に非常に大きな影響をもたらします。言霊には心が喜ぶ良い言霊と、心が悲しむ悪い言霊があります。実際に口にしてみて良い音だなぁと感じたり、その言葉を口にしてみて気持ちが明るくなったら良い言霊だと判断できます。逆に違和感や、後味の悪さを感じる言葉は悪い言霊です。
また、相手も自分も互いに気持ちが明るくなる「ありがとう」「お疲れ様」なども良い言霊です。機械的に言うのでなく、ぜひ今度から心を込めて言ってみてください。そして言霊を言うタイミングは、常に気が付いた時にです。ポイントは良い事が起こってから言うのではなくて、起こる前から常にたくさん唱えることです。言霊を先に言うことで言葉通りの現実が引き寄せられるからです。
これは脳科学的にも説明できます。脳は意識したものを見つけ、その通りの状況にしようと働くことが分かっています。つまり例え良いことが起こっていない状況でも良い言霊を口にしていると脳がその通りの物を見つけようと働いてくれます。
また、間違いなく誰もが日々唱えると良い言葉は「ありがとう」です。「ありがとう」を漢字で書くと「有難う」となります。「ありがとう」とはそのままでは現実に有り得なかったこと、起こり得なかったことがあり得るようになったことの感謝を相手に伝える言です。そして言った本人だけではなく相手も幸せにする、まさに最強の言葉です。
東洋医学で診る「感情」
西洋医学にない東洋医学の特徴として、ストレスや感情を内因あるいは七情の乱れとして分類し、それらの感情が身体のどの部位にどう作用するかを定義していることが挙げられます。
まず、感情を「怒・喜・思・悲(憂)・恐(驚)」という七情に分類し、それらを身体の五臓(西洋医学の臓器とは違いがある)と関連付けています。肝(怒り)、心(喜び)、脾(思い)、肺(悲しみ・憂い)、腎(恐れ・驚き)を司ると言われています。
感情の過度の起伏は、内臓に悪影響を与えて病を発症させ、逆に内蔵の異常は感情の不安定を引き起こします。
肝と怒の関係
人が生きる上で大切なのが「怒」です。正当な「怒」はたくましい行動力と決断力をもたらします。「肝」が座っているという言葉があるように、この「肝(経絡)」が安定している人は、有言実行でリーダーシップを発揮すると言われています。反対に強くなりすぎる人は怒りっぽく、短気、弱くなりやすい人は優柔不断という事になります。
いずれにせよ、怒り過ぎたり、我慢したりすると「肝」に関係する身体機能に異常が表れます。
心と喜の関係
心(心臓)は、喜びと深く関係し、強すぎる悲しみは身体や心に異常をきたします。また喜びが不足したでも、悲しみが心に大きく拡がり、うつ病や精神疾患を引き起こします。
一方、喜び過ぎるとやはり心臓には負担になります。例えばお酒を飲んでハイになり、調子に乗ってしまうことで、魔がさしたとしか思えないような事故に巻き込まれたりもします。
脾と思いの関係
「脾」は、西洋医学でいう消化器系全般のことです。口から喉、食道、胃から大腸までの消化器と膵臓や肝臓の働きの一部が含まれます。
「脾」は「思う」「考える」「悩む」という意識活動を司り、脾の働きが悪くなると、頭がうまく働かなくなり、考えがまとまらなくなります。そうなれば他の経絡(肝)にまで影響してイライラや怒りを生じさせることもあります。
思い悩み、考え込みは、人生の中で避けることはできませんが、過ぎると食べることさえ忘れてしまう、または食欲が異常に昂進し急激に太ってしまったりすることさえあります。
肺と悲しみの関係
「肺」は、西洋医学でいう肺と同じくに呼吸に関係していますが、と東洋医学では、「悲しみ」「憂い」を司るのが「肺」とされています。「憂い」「悲しみ」が過ぎると、息苦しさや嗚咽にも繋がります。憂鬱な時にため息が出るのも、「肺」との関係を表しています。
呼吸器の問題、鼻から喉、気管支から肺に関するすべての症状は「肺」の経絡の変動により引き起こされます。風邪を引くと、鼻水、鼻詰まり、咳やくしゃみ、こういう症状は「肺の経絡」を治療することで改善されます。
東洋医学的な病証では、「肺」は肛門と密接な関係があり、排尿障害(夜尿、排尿困難、尿漏れ、失禁なども肺経の治療でよくなっていきます.
腎と恐れ・驚きの関係
「腎」は、西洋医学でいう腎臓と似ていますが、その機能である泌尿器系だけでなく、生殖器、脳、免疫系にも関わっています。「腎」は「心」とバランスを取り合っていますが、これが崩れると、更年期のようなのぼせや頭痛、肩凝りを起こします。
「腎」は恐れ・驚きを司り、例えばストレスによって、一晩で髪毛が真っ白になったとか、胃潰瘍になることは、恐怖や不安に「腎」が犯された結果起こったものと考えます。他にも、認知症などで妄言や徘徊を起こすのも、腎と心のバランスが崩れて脳に栄養が行き渡らなくなった状態と考えられます。
これらのように、感情(七情)の乱れが身体のどの部位にどう作用するかを診るのが東洋医学の特徴です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。