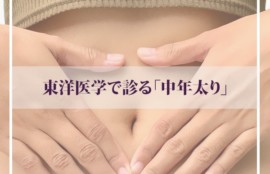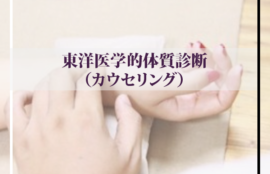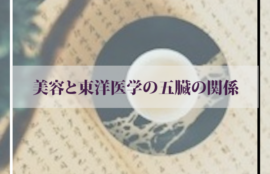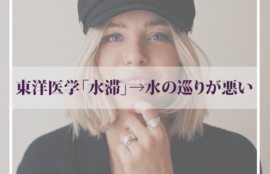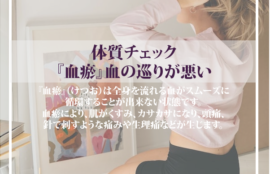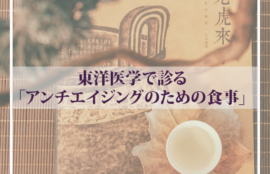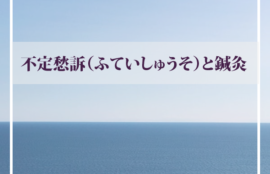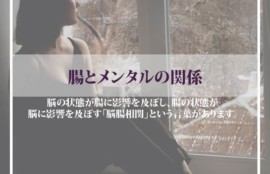年齢を重ねることにより、健康状態に大きな問題がない場合でも、日常生活で肉体的な不調を経験するようになります。その大きな原因は老化です。私たちがどれだけ健康に気をつけて生活しても老化という現象は止めることはできません。特に暴飲暴食を繰り返したり 油っぽいものばかり食べたり、甘いお菓子を毎日食べたりしていれば、老化のスピードは確実に速まります。逆に言えば食生活を見直すだけでも老化の進行を遅くすることは十分に可能です。
漢方と薬膳
中国の伝統医学といえば代表的なものに漢方が挙げられます。漢方は中国の伝統医学の一部で、特定の病状を治療するための薬草や自然の成分を利用したものです。ただ私たちがよく知っている日本の漢方は、中医学から離れて日本独自の進歩を遂げており、一般的には和漢と言います。
漢方の歴史は古く紀元前2000年より前からあったと言われ、そのベースには1000万種類以上の様々な生薬や薬草を組み合わせることにあります。これが漢方薬であり、例えば単独の薬草は生薬で、1万種類以上の生薬を混ぜて組み合わせて作ったものを漢方と言います。およそ10万パターン以上のレシピがあると言われています。
実は漢方とは、ただ薬を飲むことではなく、日々の食事をしっかりと見直し、漢方の原料となる栄養たっぷりの食材をバランスよく食べることが重要視されています。つまり漢方は、漢方薬による単なる薬物療法だけでなく、食事や生活習慣の改善を通じた全体的な管理の一部です。特に体に良い薬膳を日々の食事に取り入れることで健康的に長生きできる体を作ることができると考えられています。
しかし漢方薬に対して、2007年に科学雑誌ネイチャーには伝統的な東洋医学や中国医療に質的研究(治療データから効果分析)が行われておらず、多くの治療メカニズムが検証されていないため、何の効果もないのではないかと言う論評を発表しています。
漢方薬の多くは中国で研究
漢方薬が効くというデータは、実は中国で行われた研究が多くなっています。2007年に行われた比較研究では、136の漢方薬に関する実験データを分析しています。その研究では、特に中国で行われた研究において漢方薬が効くと言う成果が多いことが挙げられています。つまり中国の立場から研究した成果が多く、そのため信頼度が低いと考えられています。
質の悪い研究が多い
研究には、質が悪い研究と高い研究があり、当然質が高い研究は、長い時間や何千人を対象にして行われます。例えば認可される薬は、何千人も対象にして、何回も臨床試験を行って、やっと薬になりますが、漢方にはそれがなく、しかもこれらに適するような質が高い研究が、漢方研究全体の2%しか行われていないと言われています。
つまり漢方の効果が認められると言っても、小さい集団で行われた実験が多く、その効果があるのかどうか何とも言えない研究が多いことが挙げられます。つまり歴史が古いが、まともなデータが少ないことになります。
一部の漢方薬むしろ危険
漢方薬はむしろ危険と警告する研究もあります。漢方薬は生薬を色々混ぜるのですが、実は混ぜてはいけない成分が混ざっているケースが結構あると言われています。そういうものが入っている漢方を使うと、毒素が体に溜まり健康被害を起こす可能性があると言われています。もちろん薬にも副作用がありますが、漢方の効果が曖昧であるのと同じように、その副作用も曖昧なものになっています。
試すなら和漢か生薬
漢方薬には、科学的なデータが少なく、しっかりと分析もされてない部分もありますが、実は日本の漢方は、中国の漢方とは違い、その成分の分析がしっかりされているものが多くあります。実は日本の漢方は信用できると言われています。なぜなら日本では、高品質の材料を用いて、高度に管理された環境下、厳密な規格のもとで作っているため安全性も高いと受け止められています。
もちろん漢方は、個人差が大きく、人によってはすごく効くっていう人もいれば、そうでない人もいます。あくまで和漢でも絶対に効くというものではありませんが、試すのであれば和漢の方が良いと思います。
また、漢方薬は 1万種類以上の生薬を組み合わせて10万パターン以上のレシピを作っていますが、それらを混ぜた時の効果が変わると言うデータは少ないのが現状です。
それぞれの生薬単体で見ると信頼できる研究も数多くありますが、生薬を組み合わせて漢方薬にするとまともなデータがほとんどありません。そもそも組み合わせる意味があるのかが判断が難しく、組み合わせることによって本当に効果が上がるのか、逆に体に毒になるようなものが混入している可能性もあるので生薬単独で使うのが良いのではないでしょうか。
中国の伝統医学の基本
中医学の教科書である皇帝内径(こうていないけい)という書物の初めには、「養生して暮らせば100歳を超えて天寿を全うできる」と書かれています。早く老いてしまう人とずっと元気な人は一体何が違うのか、そんな疑問を追求した学問が中医学であり、中医学は心身ともに健康に生きて天寿を全うするための理論の集大成とも言えます。
病気は治療が必要ですが老化は自然な現象です。自然な現象である老化を止めることは不可能ですが、食べるものに気をつけることで老化の速度はゆったりとした変化になるというのが中医学の基本的な考え方です。また中医学では体中を絶えず巡り、臓器や器官が生命活動を維持するために必要を不可欠な気血水の三要素を重視しています。
生命の活動を支えるために気血水という3つの基本的要素が体の中で常に流れていると考えられており、これらは生命機能の維持に欠かせない要素とされています。気血水のうち一つでも不調になれば、残りの2つの要素に影響してしまうという三位一体として考えられています。気血水は互いに関連し、一つが不均衡または不足すれば他の2つにも悪影響を与え、体の健康全体が乱れてしまいます。
気血水について
気は広い意味で生命エネルギーを表しています。これは生物の生命活動を支えるエネルギー源として理解されます。日本語でも気力や元気という言葉があり、気力や元気のように気を含む言葉が、それぞれ生命力や活力を表しています。このように気というのは人間の体を動かす原動力を意味しています。また病は気からという言葉があり、この言葉において気は心を表しており、心も気に含まれます。つまり病は気からという言葉は、気が心や精神状態を表し、さらにこれらの心理的な側面が全体の気、つまり生命力に影響を与えるという考え方を表しています。
この気という抽象的な概念は西洋医学には存在しません。これが東西の医学理論の違いを反映しており、目に見えない気、心、精神の状態が健康に大きく関わるとして、この気を重要視しています。物理的には見えない気や心、精神状態が身体の健康に深く影響を与えると認識されており、そのため気は重要な要素とされています。
血は文字通り血液を表しています。血液は全身を巡り内臓器官が働くための栄養を運ぶ重要な役割を果たしています。栄養素や酸素を全ての器官や細胞に運び、これらが適切に機能するための基盤を提供しています。血が不足すると肌や爪が乾燥したり、ストレスやイライラなどの精神状態にも関わってきます。これは血液の栄養輸送機能が低下することで、身体全体のバランスが乱れるためです。
水は、リンパ液、汗、尿、唾液、鼻水など体内にある血液以外の体液全般を表しています。体中のあらゆる場所を巡り、皮膚、目、鼻、内臓など様々な粘膜組織を潤して、体の潤滑剤としての役割を果たしてくれています。水が不足してしまうと体の各部分が乾燥してしまい、正常に機能することができなくなってしまいます。逆に水が多すぎてもむくみやしびれなどの原因となってしまいます。
このように気血水が三位一体で、十分に満ち足りているとき人間は健康的な状態でいるというのが中医学の考え方となります。これら気血水が不足すると私たちは不調に陥ります。不足は中医学で「虚」という言葉で表現され、虚を補うことで不調の解消を目指します。この虚を補うのが日々の食事です。
中医学の専門的な言葉を引用すると、気を補うことを理気、血を補うことを活血、水を補うことを生津、水を排出することを利水、利尿、利湿などと言います。元気がなく、やる気が出ないのであれば気を補うための理気を、月食が悪くて貧血状態であれば活血を、乾燥の症状が現れているのなら水を補給する生津を、といった感じで体の不調に合わせて気血水を食事で補っていくわけです。
五臓六腑について
東洋医学において人間の体を構成する要素は「心、肝、脾、肺、腎」の五臓を中心に成り立っていると考えます。五臓六腑という言葉は、中医学が由来で五臓は、まさに心、肝、脾、肺、腎の5つの重要な器官を表しています。ただし中医学の五臓と西洋医学の臓器は異なる意味を持っています。私たちが慣れ親しんでいる西洋医学で言うと、心、肝、脾、肺、腎は心臓、肺、脾臓、肝臓、腎臓という臓器の名前を指します。
ですが中医学ではもっと広い意味を持っています。東洋医学において心は血を巡らせ、精神活動の主体となる機能全体を指します。肺は呼吸を司り、気血水を全身に届ける体内の循環をコントロールする役割です。脾は消化機能全体を指していて、気を補給する役割を指しています。肝は体内に取り込んだ気を全身に巡らせ、血を体内に保存し、全身の代謝を司る役割を果たします。そして腎は成長、発育、生殖に関わり、水の代謝も司っています。
これらの五臓は自然界を5つに分類して理解する五行思想にもつながっていきます。五行思想とは古代中国で生まれた哲学的な思想で、火、土、金、水、木の五行がお互いに影響を与え合い、天地万物が循環するという哲学的な考え方です。五行思想では方角や色、感情などあらゆるものが五行に当てはめられています。
例えば、肝は気に当てはめられ、感情は怒り、影響が現れる期間は目、影響を受ける水は涙、影響を受けやすい季節は春といった感じで定められています。春の不調は花粉症で涙が出たり、目が充血したりと季節や感情によって体に現れる変化が異なります。このように中国では古来より人間は自然界の一部であり、暑さや寒さなどの自然環境の影響を受けると考えられてきました。
五臓の中で一つでも不調の臓があれば、影響は他のゾーンにも及んでしまい、ひどくなると病気になってしまいます。健康でいるためには五臓を全てが健全に働かなければなりません。中でも特に重要な位置づけとなっているのが腎です。
中医学において、父親の精と母親の精の2つが交わることで新しい命、つまり新しい精が誕生し、腎に宿ると考えられてきました。新しい精が腎に宿るは先天の精と呼ばれています。ただ私たちはこの世に生まれたところで生きていくためには食事をしなければなりません。その生命活動を維持するためには食べたり飲んだりして栄養を補給する必要がありますが、補給した栄養物質は後天の精と呼ばれ、やはり腎に貯蔵されます。つまり中医学において、親から受け継いだ精、食べ物から受け継いだ精の2つの精の力によって、それぞれの臓器が働き、気血水が全身を巡り健康的に生きられると考えられています。
2つの精が腎に貯蔵された段階で、先天の生と後天の精はまとめて腎精と呼ばれるのですが、人生のピークは30歳代半ば頃で、40代以降は減り続けると言われています。加齢が進むと人生が少なくなるので栄養補給をしっかりして精を担わないと老化が加速して、様々な不調が現れてしまいます。
【最新研究】漢方薬と腸内細菌の関係
実は漢方薬がなぜ効くのかはまだ未解明な部分が多くありますが、その漢方薬の効果に腸内細菌が深く関わっていることが明らかになってきました。その一端を解き明かしたのが名古屋大学医学部付属病院の外科医横山博士です。横山先生が漢方薬を手術の際に使うケースに胆管がんが挙げられます。胆管がんは肝臓で作られる胆汁の通り道である胆管にできるがんです。そのため胆管が詰まり、肝臓に胆汁が蓄積して黄疸になり、肝臓の機能が損なわれます。その結果、黄疸の数値が下がらなければ最終的な胆管がんの手術ができなくなるため、黄疸の改善に使われるのが茵蔯蒿湯(いんちんこうとう)と言う漢方です。
茵蔯蒿湯を投与して胆汁の流れは2から3日で良くなる患者さんも多くいますが、胆汁の流れがよくならない患者さんもいます。なぜ同じ症状でも漢方薬の効果に違いがでるのか、そこに腸内細菌が深く関わっていると考えられています。茵蔯蒿湯には、インチンコウ、ダイオウ、サンシシが含まれており、この中で肝臓に最も作用するのがサンシシに含まれるジェニポシドと呼ばれる物質です。
ジェニポシドを含んだ漢方薬が、腸の中に入ると腸内細菌が集まり始めます。すると漢方薬を分解する酵素を出し、その酵素にジェニポシドが付くと糖の成分が外れ、ジェニピンという物質に変化します。これが黄疸を改善する薬効成分になります。つまり腸内細菌が漢方薬の効果を引き出していることになります。
一方で腸内細菌の違いがどのように影響しているのか、黄疸の患者52人から腸内細菌を採取して茵蔯蒿湯を加え、ジェニピンの作られる量を比較しています。その結果、善玉菌の割合が少ない人はジェニピンの産生能力は低いことが分かっています。そのため茵蔯蒿湯に対する反応にばらつきがあるのは、腸内細菌が影響を及ぼしていると考えられています。
これらのように、腸内細菌を介した生薬の効果が次々に明らかになってきました。例えば甘草(カンゾウ)の免疫調整作用、人参(ニンジン)の疲労回復作用、紫胡(サイコ)の抗炎症作用など、漢方薬の効果に腸内細菌が重要な働きをしています。つまり腸内細菌を改善することで漢方の効果をより引き出せる可能性が示唆されています。
一方で、漢方薬と腸内細菌の研究によって、新たな免疫システムの存在も分かってきています。日本で最も販売されている漢方薬の大建中湯(だいけんちゅうとう)は、便秘を始めお腹の不調の改善に広く使われています。しかし薬理効果については知られていましたが、免疫への作用については全く分かっていませんでした。
そこで理化学研究所佐藤博士は、腸炎を患うマウスに大建中湯を与えたところ、僅か5日程で腸炎が改善すること確認されています。そこに世界で初めて確認された免疫細胞の3型自然リンパ球の働きがあったことが分かっています。この3型自然リンパ球は、病原体から体を守る腸の粘膜バリアの維持に深く関わっていることが分かってきました。まず漢方薬の成分が腸に入ると腸内細菌が集まり、腸内細菌が漢方薬を餌にしてプロピオン酸と呼ばれる代謝物を放出します。プロピオン酸は腸の表面にある細胞を通り抜け、3型自然リンパ球に到達します。するとバリア機能を高めるメッセージを送り、それを受け取った腸細胞が腸を守る粘膜の生産を促しバリア機能を強化し、腸を炎症から守り、健康な状態へと回復させます。このように腸内細菌の役割が明らかになってきたと同時にその漢方薬の効果の謎が明らかになってきています。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。