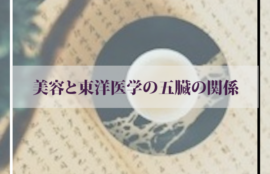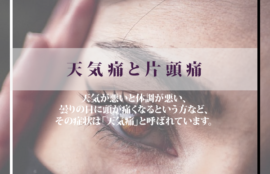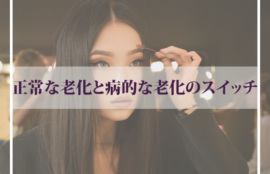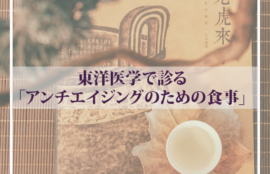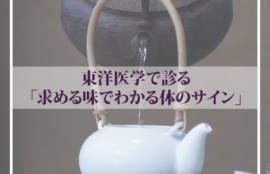こんな症状ありませんか?
- 集中力が続かない
- 忘れっぽい
- 落ち込みやすい
- 肌や髪の乾燥
- ドライアイ
- ドライマウス
- 月経不順(間隔が長くなる)
- ホットフラッシュ
- 顎の吹き出物
- 便秘
このような症状は「血不足」になっているサインです。この場合は東洋医学で言う「血」(けつ)を補うことで症状も緩和されます。
東洋医学では「気・血・水」のバランスが崩れると体に不調をきたすと考えます。この「気・血・水」の3つは、人の体の構成要素と考えられています。「気」は、人体の生命活動のエネルギー源です。「血」は、西洋医学における血液の血とは、少しイメージが異なり、全身に栄養を供給し潤すことと、精神活動の基礎物質という二つの働きがあります。「水」は、津液とも呼ばれ、体内の水分です。
「血虚(けっきょ)」は全身の「血」の働きが低下、または不足している状態です。女性の悩みの多くは「血虚」と呼ばれる体質が関係しているといわれています。例えば女性特有の症状である月経の状態は、「血」の働きが大きく関係しています。ただし「血虚」=「貧血」ではありません。東洋医学では、自覚症状や舌の色などによってあてはまる体質や症状があれば「血虚」と考えます。「血」の役割は、体全体を巡り潤し養う“需要作用”や、精神活動(思考力、判断力など)のエネルギー源になることです。
「血虚」の症状
『血虚(けっきょ)』は、身体を滋養する血が足りなくなっている状態です。心身に栄養が行き渡らず、新陳代謝や精神の安定を図ることができない状況といえます。顔色は青白く、潤いのないカサカサ・パサパサした肌や髪が特徴的です。
「血」は、「気」と「水」が結合してつくられるか、腎精と呼ばれる生命の源となるエネルギーからつくられます。これらは、飲食と呼吸によってつくられるので、ダイエットなどで栄養が不足したり、五臓の関係からすると「脾」「肺」「腎」の働きが低下すれば、「血」の材料を吸収・生成できなくなるため「血」がつくられなくなります。
女性は、生理があるので「血」が不足しやすく、現代女性に血虚の症状が多いです。食生活の乱れや睡眠不足なども血虚の原因となります。男性の場合だと、抜け毛や白髪、円形脱毛症などになったりします。また疲れやすく、めまい・立ちくらみなどの症状も出てきます。
「血虚」の症状としては、顔が青くなるほか、目や髪・皮膚を潤す栄養素が足りなくなり
・目の疲れ
・白髪、抜け毛
・肌荒れ
などか目立つようになります。
また「血」と関わりのある「心」の機能も低下するため、
・眠りが浅くなる
・不安感に襲われる
・物忘れが多くなる
などの症状が現れるようになります。
血不足による心への影響から不安、不眠の傾向が強く、眠りが浅いため夢を見ることが多いといえます。血は深夜1時〜3時に作られます。その間にしっかりと熟睡していることが大切です。東洋医学では、睡眠中にたくさんの夢を見る事を「多夢」と言います。本来、質の良い睡眠は起きたときにスッキリ感があり夢を見ない睡眠です。夢をよく見るのは、東洋医学でいうと「血」が足りない「血虚」という状態です。特に嫌な夢・現実的な夢は体の不調と関わりがあると考えられ、体質を知る手がかりにもなります。
熟睡出来ない方は自律神経の乱れも大きく関わりますので、整えると睡眠の質も変わり同じ睡眠時間でも身体が変わってきます。
血を補うおすすめ食材
●黒豆
血を補い、巡らせる。むくみの解消や老化抑制。疲労回復効果。
●レバー
造血作用があり、不足した血を補う。眼精疲労や視力低下にもよい。
●牡蠣
身体を潤す。精神不安や不眠にも効果。
目を使うと血の消耗が激しくなるので、目を休ませましょう。また、血は午前1時〜3時に古い血が淘汰され、新しい血が生成されます。この時間はしっかり睡眠をとるようにしてください。
赤味噌+白味噌で貧血予防
白味噌と赤味噌のどっちが健康に良いかの結論は、赤味噌ベースの味噌汁にトッピングとして少量の白味噌を加えてあげることです。基本的には、赤味噌の方が健康効果が高いものの、白味噌には赤味噌にはない効能があります。
そもそも白味噌と赤味噌の大きな違いは熟成期間の違いです。白味噌が大豆を煮て短期間の発酵によって作られるのに対し、赤味噌は大豆を長時間水につけて蒸すことで作られます。発酵食品は熟成期間が長ければ長いほど良質なアミノ酸やプロバイオティクスが蓄積されます。実際100gあたりの栄養化を比べても赤味噌の方が白味噌よりも多くの点で優れていることが分かっています。
例えばタンパク質は、一般的な白味噌100g あたりのタンパク質が9.77gであるのに対し、赤味噌は13.1gと約1.5倍の量になります。また血液の材料となり、貧血を予防する鉄や葉酸といった栄養素も赤味噌の方が多くなっています。
ちなみに赤味噌は白味噌よりも塩分量が多いため体に悪いと言われることがありますが、研究によって赤味噌は1日2杯程度であればむしろ血圧を下げてくれる効果が実証されています。これは赤味噌が豊富に持っているカリウムが余分な塩分を尿として排泄してくれるためです。
ただし、赤味噌には白味噌にはない唯一のデメリットがあります。それは赤味噌には、エイジスという老化物質が少なからず含まれてしまう点です。実は赤味噌の独特の茶色の正体こそがエイジスです。エイジスは簡単に言うと食べ物の焦げのことであり、糖質とタンパク質が同時に加熱されることで起きる反応(メラード反応)によってできます。
このエイジスは、お肌のシミや認知症、白内障など数多くの加齢性の病気に関係していと言われており、特にエイジスが大量に含まれている揚げ物などは若々しさの大敵であると考えられています。赤味噌は、大豆を高温で長時間蒸して作るため、大豆タンパクと糖が反応してエイジスができ、それがその独特な茶色を形成しています。老化物質であるエイジスが含まれているのであればむしろ赤味噌は体に悪いと不安に思ってしまった人いるかもしれませが、赤味噌は白味噌に比べてエイジスが多い一方で、同時にエイジスを無力化してくれる抗酸化力も高いことが分かっています。
種類別の味噌の抗酸化力を調べた研究では、味噌の色の濃さが抗酸化力に比例することが分かっています。つまり味噌は色が濃ければ濃いほどエイジスを無毒化する力が強いことになります。特に色の濃い赤味噌や八丁味噌の抗酸化力は白味噌に比べ4から5倍で非常に高い抗酸化力を誇ります。
一方で赤味噌にはない白味噌独自の栄養素もあります。それがビタミンB12です。ビタミンB12は血液を作るために不可欠なビタミンで、鉄と葉酸の3つが揃って初めて血が作られて貧血が改善します。赤味噌にはビタミンB12がほとんど含まれていないため、貧血予防という観点では赤味噌をベースとした味噌汁に少量の白味噌を加えてあげましょう。
また、赤味噌にはない白味噌の特徴としてGABAがあります。GABAは、脳の興奮を抑える神経物質で、脳をリラックスさせ、夜の眠りの質を高めてくれる効果があります。実はGABAは血液と脳の間にある血液脳間門という関所を通り抜けることができません。つまり口から摂取したところで脳には届いてくれません。しかし白味噌を摂取することで得られるGABAの効果は、脳ではなく腸に関係しています。
このGABAの需要体は、脳だけではなく腸にもたくさん存在しており、GABAを摂取することで腸内環境が改善すると考えられています。実際研究では、GABAを作り出す乳酸菌の摂取によって腸内環境の乱れが改善したことが確かめられています。また白味噌は赤味噌に比べて食物繊維の量も豊富で、より腸に良い影響をもたらしてくれると考えられています。
血をつくるツボ
血海(けっかい):膝のお皿から指3本分上、やや内側にあるツボ
血を生み出す働きがあり、「血の海」と書くほどの、「血虚」を改善する重要なツボです。

三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分あがった、すねの骨の内側にあるツボ
月経の血量や痛みも抑えてくれる婦人科の特効穴と言われるほどのツボです。

血虚が引き起こす症状
肝火上炎(かんかじょうえん)
寝つきが悪い、ひどいと明け方まで眠れない方もいます。普段からイライラが強く、怒りやすい傾向があります。身体の中の「気」が滞り、熱を持った状態のため、身体の中の熱が昇って、頭部や顔面部に症状が出やすくなります。
特に、疲労やストレスの蓄積から気の流れが悪くなり生じた熱が、顔を赤くしたり、目を充血したり、のどが渇いたりします。このタイプの方の場合、気の流れを整えるツボを刺激して身体の熱をとりましょう。
曲池(きょくち):肘を曲げたときにできるシワの端と肘の外側にある骨の中点

痰熱内擾(たんねつないじょう)
寝つきが悪い、眠りが浅い、夢見が悪いといった症状が多いタイプです。食生活の乱れ、臓脾の機能低下などにより体内に水分が滞るため、熱が生じやすくなります。
このタイプは、日々のストレスで自律神経の緊張も強くなっており、イライラ、動悸、痰(たん)が多いといった症状を伴うこともあります。お酒や脂っこい食べ物、香辛料を控えて、食生活を改善しましょう。
心脾両虚(しんぴりょうきょ)
眠りが浅く熟睡感を得られないことが多く、貧血傾向になっていることもあります。また胃腸が弱い方になりやすい傾向があります。心と脾はお互いに協力しあって身体を調整していますが、病気・月経過多・悩み事が多いと、脾の力が弱り、心に栄養が届かず、睡眠に影響が出ます。精神的にストレスになることを極力避けて下さい。
心腎不交(しんじんふこう)
寝ついても途中で起きてしまうことが多く、潤い不足で口が渇き、ほてりや動悸を感じたりすることもあります。このタイプの場合は、水分を補ってあげることが必要となりますので、水の巡りを整えるツボを刺激しましょう。
三陰交(さんいんこう):内くるぶしの出っ張りから指4本分上の骨の際。押すと少し痛みを感じるところ

鍼は自律神経調整や体質改善を得意としますので、上記に心当たりがある方は一度、カウンセリングを受診してみて下さい。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。