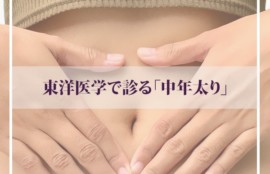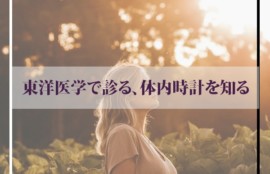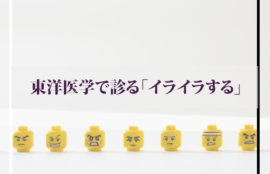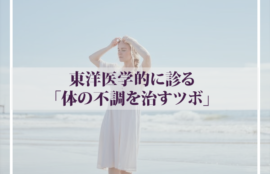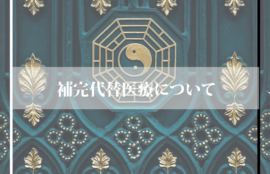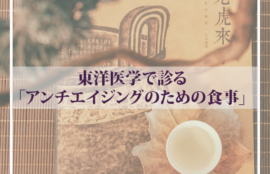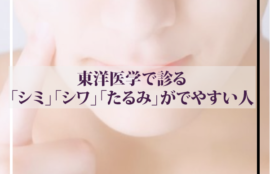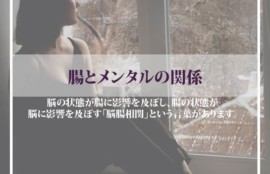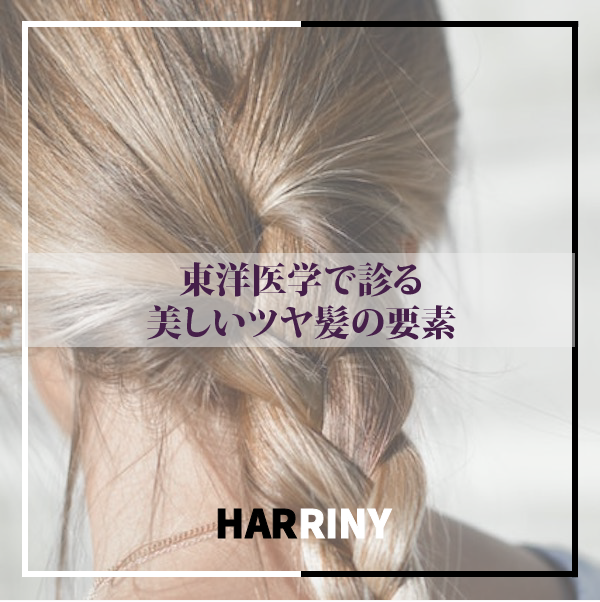
加齢に伴い、髪のツヤが無くなり、パサついてくる髪のトラブルがあります。美しくツヤのある髪は次の2つの要素が揃うことで得られます。
1つ目の要素は、「血液」が十分に供給されていることです。髪は東洋医学で血余といい、血液の一部であると考えます。貧血などで血液が不足すれば、体の末端にある髪の毛まで血液(酸素や栄養)を回す余裕がなくなり、髪は貧弱になります。
2つ目の要素は、「女性ホルモン」です。女性ホルモンや男性ホルモンは、東洋医学では「腎」が司ると考えます。「腎」が衰えると、ホルモン分泌も低下し、白髪や薄毛、脱毛といった症状が出てきます。
以上から東洋医学のツボを押すことで血流改善と腎のエネルギーを回復させようということになります。しかし毎日ツボを押したからと言って劇的な変化があるわけではありません。なぜなら生活習慣、食習慣が体に与える影響の方が大きいからです。
当たり前ですが、人の体は食べ物からできています。栄養バランスを考えて食事して、睡眠不足にならないようにすること、そうでなければツヤ髪になることはありません。
東洋医学で診る、美しいツヤ髪の要素
東洋医学では、髪は体全体の健康状態や気血の流れを反映する重要な要素として捉えられています。具体的には、髪の状態は五臓六腑のバランスや気血の流れと関連しています。髪の健康状態が悪い場合、それは体内の臓器や経絡の異常を示すサインとして捉えられます。
髪の栄養は、気血の流れによって頭皮に運ばれます。この気血の流れが滞ることで髪の栄養供給が不十分になり、髪の健康が損なわれると考えられています。また髪の健康は頭皮の状態と密接に関連しており、頭皮の乾燥や油分の過剰分泌、血行不良などが健康に影響を与える要因として考えられています。
特に東洋医学では体内の気のバランスが髪の状態に影響を与えると考えられており、気の不足や気の滞りが髪の健康を損なうとされ、髪の艶や質感の低下、抜け毛や薄毛などが気の不調のサインとして解釈されます。
ツヤ髪を改善する方法
ツヤ髪を改善する方法は、①腸での活性酸素の異常発生を抑える、②髪の毛が生える食べ物を食べることです。
腸での活性酸素の異常発生を抑える
活性酸素を過剰に発生させる要因には、紫外線、有害物質、食品添加物、バランスの悪い食事、喫煙、飲酒、睡眠不足、ストレスなどがあります。これらの要因を取り除くことが大事ですが、実は活性酸素の90%は腸内で起こっています。つまり腸内での活性酸素の異常発生を抑えること絶対に必要なのです。
しかし、現代人の腸は非常に汚れていると言われ、その原因として食生活の欧米化し、食物繊維の摂取量が減少していることに起因しています。また食べ過ぎによって、腸で消化されないものが大腸内に止まり、悪玉菌や活性酸素を発生させ、腸の汚れの原因となります。つまり加工食品を止め、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な食事に変えて、善玉菌優位の腸内環境をつくる努力が必要になります。
アルコールを避ける
アルコールは髪の毛のみならず、私たちの体に様々な悪影響を与えています。アルコールを飲むと、その毒を解毒するために体中に存在するアミノ酸やビタミンなど、様々な栄養素が消費されます。体中の栄養素が消費されてしまうと当然のことながら頭皮へ配分される栄養素も少なくなってしまいます。その結果、頭皮の栄養が欠乏し、髪の毛の原材料がなくなって髪が薄くなってしまうと考えられます。
塩分摂り過ぎに注意
加齢によって血液がドロドロになることで頭皮まで血が届かなくなり、頭皮に必要な栄養素が運ばれなくなります。そして塩分の摂り過ぎは、血液をドロドロにしてしまう最たる 元凶です。塩分を摂取すると当然のことながら血圧が上がり、血管の内壁が傷ついていくことになります。血管の内壁が傷つくと、それを修復するために大量の悪玉コレステロールが 肝臓から動員されて血がドロドロになります。ドロドロの血液は頭皮の薄い毛細血管を通り抜けることができず、そうなれば髪の毛に栄養が行き届かずに抜け毛になってしまいます。
バター(油物)は避ける
実験によってバターを食べさせたマウスと食べさせていないマウスを比較したところ、バターを食べさせたマウスでは、毛が生えるのが遅いということが分かっています。AGA治療において、油物は絶対避けるというのは常識になっています。脂っこい食べ物を食べてしまうと皮脂の量が増えて、頭皮にある毛穴が詰まってしまいます。毛穴に皮脂が詰まれば、そこから出てくる髪の毛は当然成長しづらくなります。
また、油物を食べすぎると食事から取った方は脂肪酸の影響で体に悪影響があります。例えば皮脂で毛穴が詰まる、頭皮の毛細血管もドロドロになって血流悪くなるなど、油物には何1つ良いことがありません。
塩素除去シャワーヘッドを使う
日本の水道水には塩素が入っており、この目的は水に雑菌が湧かないようにするためです。この塩素は、タンパク質を破壊する作用を持っており、これが毛根の細胞を壊してして頭皮の環境を乱し、長年の使用で薄毛の原因となってしまいます。
水道水に使われている次亜塩素酸ナトリウムの効果を見ると、次亜塩素酸水の効果の基本はタンパク変性作用です。ウイルス表面のスパイクタンパクや菌の表面タンパクを酸化分解して不活化するメカニズムを持ち、ウイルスや菌の種類を選ばず、ほとんどの微生物に有効です。低濃度でも十分な効果を発揮し、耐性菌や変性ウィルスが現れても、表面がタンパク質である限り効果を発揮します。老化で薄毛の原因になるのが毛包細胞と17型コラーゲンで、これらはタンパク質であり、薄毛になりやすい人は塩素の入ったシャワーを浴びることで頭皮の老化を促進してしまいます。
特に肌が弱い場合は要注意です。これは実際にアトピー性皮膚炎の方の実験で立証済みです。九州大学大学院皮膚科学分野では、アトピー性皮膚炎の患者に対して塩素除去のシャワーヘッドとプラセボのダミーシャワーヘッドを3週間使用した場合、どんな変化が起きるかを実験しました。
その結果、浄水シャワーヘッド使用例では、使用前後において、かゆみ及び重症度を示すTARC値に関して統計的に優位な減少が観察されました。一方ダミーシャワーヘッド使用対象群では、そうした現象は見られませんでした。これらにより浄水シャワーヘッド使用はアトピー皮膚炎の症状の一部を改善させることが示されています。ちなみにこれは日本皮膚アレルギー学会でも発表された内容です。また別の研究でも残留塩素を含む何種類かの水を用意し、肌への影響を調べたところ、肌の保水力や保湿機能が下がることも分かっています。
髪の毛が生える食べ物を食べる
大豆と唐辛子
髪の毛が生える食品の代表が大豆と唐辛子です。大豆に含まれるイソフラボンと唐辛子に含まれるカプサイシンを同時に摂ることで、効率よく発毛促進物質を増やせることが分かっています。またわかめ、昆布に含まれるフコイダンという成分も発毛促進物質を増やすことが分かっています。一時はこのような効果が否定された時期もありましたが、フコイダンを大量に含む、昆布の仮根部分に毛髪に効果があるという研究も行われてモニター調査でもその効果が実証されています。
牡蠣
牡蠣は非常に亜鉛が豊富な食べ物で、細胞の生産と修復そして頭皮と髪の健康を維持する効果があります。亜鉛不足は髪の成長を遅らせるだけでなく 髪の質感や強度にも影響を与えます。髪の主成分はケラチンというタンパク質ですが、髪のサラサラ感をアップさせる効果も期待できます。ケラチンは髪の強度と柔軟性を保つ役割があり、髪の質感を改善してくれます。
牡蠣に含まれる栄養成分は生で食べた場合と加熱調理した場合とでそれぞれ異なる影響があります。亜鉛やタンパク質など髪の健康に必要な成分は生でも加熱調理でも摂取することができます。ただしビタミンB群は加熱調理で一部が失われる可能性があるので注意しましょう。
赤身肉
ホルモン剤なしの牧草だけで育てられたグラスベッドビーフがお勧めですが、それ以外にも赤肉を食べることが重要です。加齢によってタンパク質不足に陥りがちになり、加齢と共に筋肉の量が減ります。そのため口から食べたタンパク質はアミノ酸に分解されて、頭皮ではなくまず内臓や骨格に供給され、頭皮に供給されるタンパク質が減って髪の毛を作る原料が不足してしまいます。
そこで是非とも食べていただきたいのが赤肉です。赤肉には豊富なタンパク質が含まれているのみならず、髪の毛の発育を助ける亜鉛も大量に含まれています。育毛促進において亜鉛が大切というのは有名な話ですが、亜鉛は髪の毛の主成分であるケラチンを合成するのに必要な栄養素です。赤肉を食べることでタンパク質と亜鉛という2つの成分が頭皮に供給され、髪の毛が増えてフサフサになっていってくれます。
黒ゴマとホタルイカ
食べれば食べるほど黒髪が増える食べ物が黒ゴマです。黒髪は頭皮に存在するメラノサイトが合成したメラニンによって髪が染められることで完成しますが、黒ゴマは、このメラニン合成を促進してくれる効果があります。なぜなら黒ゴマに含まれている栄養素のアントシアニンは、ポリフェノールの一種でメラニン合成を活性化してくれる働きがあると言われているからです。他にも黒ゴマに含まれているセサミンには抗酸化力があり、頭皮で発生してしまった有害な活性酸素を除去して毛母細胞の錆を取ってくれることが期待できます。
さらにお勧めの食材が、ホタルイカです。2005年のチリ大学の研究によれば、銅はチロシナーゼという酵素の合成に密接に関わっていて、この酵素が白髪の予防に効果があることが分かっています。黒ゴマには、フェニルアラニンと言う必須アミノ酸も含まれており、これは体内でチロシンに変化した後、チロシナーゼの働きでメラニン色素に変化します。つまり白髪予防のためには黒子までフェニルアラニンを摂取するだけでは不十分で、そこからさらにチロシナーゼを加えてあげる必要があります。しかしチロシナーゼは加齢と共に減少してしまうことが知られていて、そのまま摂取しても消化吸収の過程で分解されてしまうためサプリメントなんかで補うことができません。その加齢によって衰えてしまったチロシナーゼの活性を補強してくれる働きがあると知られているのがホタルイカです。
ちなみにホタルイカには銅が100gあたり12mgほど含まれており、一般に銅の含油量が多いとされる牛レバーの2倍以上になります。またホタルイカには頭皮の血流をよくしてくれるビタミンや髪の毛の材料になるタンパク質も豊富に含まれています。
ホタテと小松菜の組み合わせ
ホタテと小松菜の組み合わせはアンチエイジングケアに効果的な食べ物だと言われています。ホタテは良質なタンパク質を豊富に含んでいるだけでなく、アミノ酸の一種タウリンも含まれています。タウリンには頭皮の血行を良くし、髪の成長を促す効果があります。
小松菜はビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、そして鉄分を豊富に含んでいます。これらの栄養素は頭皮の健康を維持し、髪の毛の生成を助けてくれます。特にビタミンAは、細胞の成長と分化を助け 髪の毛の成長に役立つ鉄分は酸素の運搬を助け、髪の毛の成長に必要な栄養素を頭皮に運んでくれる役割があります。
モロヘイヤ
モロヘイヤは美容食材と言われるほどβカロテンが非常に豊富な食べ物です。βカロテンは体内でビタミンAに変換される強力な抗酸化物質で髪にも良い影響を与えます。髪の毛は体内で最も早く成長する組織の一つですが、その成長にはビタミンAが必ず必要になります。ビタミンA不足は頭皮が乾燥し、痒みやフケの原因となる可能性があります。またモロヘイヤは、カルシウムや鉄分、マグネシウムなど髪の健康を支えるミネラルも豊富に含んでいます。これらのミネラルは髪の毛の成長と強度を助けてくれます。
鶏肉とカシューナッツの炒め物
40歳を過ぎてくると新陳代謝が衰え始め、髪のメラニン色素生成能力も低下してきます。肌には悪いメラニン色素ですが、髪にとっては大事なもので、メラニン色素が少ないと白髪が増えます。
鶏肉のカシューナッツ炒めは、鶏肉とカシューナッツを炒めただけの簡単な料理ですが、鶏肉はタンパク質が豊富で、特に髪の主成分となるケラチンの原料になります。また鶏肉はビタミンB群も豊富で、特にビタミンB12は体内でDNを正常に複製するのに重要な働きをします。
カシューナッツは亜鉛や銅、セレンなどのミネラルを豊富に含んでおり、これらミネラルは頭皮や髪の毛の健康に必要で、特に銅はメラニン色素の生成に必要な栄養素です。
納豆のオクラ和え
納豆は非常に栄養価の高い食品で、特にビタミンK2が豊富です。ビタミンK2は、カルシウムの吸収を助ける役割を果たし、それが髪の健康に良い影響を与えます。さらに納豆に含まれるビタミンB群は、健康的な頭皮と髪の毛の生成を助けます。またオクラにはビタミンCやビタミンEが含まれていて、これらのビタミンには抗酸化作用があります。さらにオクラに含まれる水溶性の食物繊維は、胃腸の働きを活発にし、栄養吸収を向上させる役割も果たします。このように納豆のビタミンB群とオクラのビタミンC 、ビタミンEが髪に潤いを与え、カサつき改善する効果が期待できます。
ツヤ髪になる東洋医学的食事
東洋医学的には、五行説という考え方があります。「腎」と関係と深い食べ物が「黒」の食べ物です。例えば昆布やワカメなどの海藻類が髪に良いということを聞いたことがあると思いますが、これらは「黒」の食べ物の部類に入ります。
「腎」をケアする黒い食べ物を摂ることも大切ですが、むしろ健康に悪い食べ物を避けることの方が簡単であると思います。むしろ食べ過ぎを避け、腹8分目や16時間断食をする方が、結果として代謝があがり、血流が改善して髪の毛に栄養が増えることでツヤ髪になります。
正しいブラッシングで頭皮の血行を促す
加齢とともに、抜け毛、白髪、パサつきや広がりなど髪の状態が大きく変化します。しかし髪は日々のケアでツヤやボリュームが最も変わってくる部分です。ケアを怠ると老けた印象に即繋がるのが髪の毛の状態です。毛根細胞は加齢だけでなく、ストレス、栄養不足、頭皮の血行不足、ホルモンバランスの乱れによって生え方にばらつきがでたり、細く弱々しくなったり、ヘアサイクルが乱れ十分に成長しないまま抜けるなどが生じます。髪の毛は、毛母細胞が分裂する時にできるタンパク質が積み重なって成長していきます。髪が抜けてしまっても毛母細胞が活動する限り、髪の毛はまた再生します。しかし毛母細胞に十分な栄養がなければ、髪ツヤが無くなる、白髪が増える、ボリュームがなくなるなど様々な髪のトラブルが生じます。
ヘアケアの基本はブラッシングです。ブラッシングの習慣のある人は、髪の毛にツヤがある方が多いです。その理由は、髪のトラブルは頭皮の血行不良によって引き起こされているからです。頭皮の血行が滞れば、毛母細胞に栄養が届かず、健康な髪が育ちにくくなります。ブラッシングは頭皮に刺激を与えて血行を促すため、髪のトラブルの改善に大きく役立ちます。またブラッシングによって頭皮の脂分が髪の毛をコーティングすることで、髪の毛にツヤがでます。ブラッシングすると髪の毛が抜けると不安になる方がいますが、ブラッシングで抜ける髪の毛はほっておいてもいずれ抜けてしまう髪の毛です。ブラッシングで血行を促し、頭皮環境を整え、ヘアサイクルを正常に働かせることが大事です。頭皮を過度に傷つけないようにするため、ブラシはピンの先が丸く台座がクッションになっているものを選びましょう。
シャンプーはアミノ酸系で、頻度を減らす
頭皮環境を整えるために、毎朝晩シャンプーしていると、頭皮の乾燥を招き、かゆみが発生し、角質の脱落量が増えてフケが目立つため、2日1回程度が理想と言われています。またシャンプーは、ある程度洗浄力があり、髪と頭皮にやさしいアミノ酸系が理想です。シャンプーボトルの成分表示に、ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNaの表記があればアミノ酸系シャンプーです。
また、自然乾燥はパサつきやうねりの原因、頭皮が乾燥してフケや抜け毛、かゆみの原因になるためドライヤーで根元から乾かしましょう。
髪の光老化を防ぐ
肌が紫外線によってダメージを受けることは多くの人が知っているはずです。同じように頭皮や髪も紫外線によってダメージを受けます。そのため紫外線ケアは、帽子、日傘、UVカットスプレーなどでケアしましょう。ただし太陽の光を浴びることは様々な健康上のメリットもあり、例えば免疫力の維持、体内時計の調節、ビタミンDの生成など、よって1日20分ほどは日に当たった方が良いとも言われています。
美しいツヤ髪のツボ
ツヤ髪、血流改善、ホルモンを整えるツボをご紹介します。
腎穴(じんけつ):小指の第1関節の真ん中

血海(けっかい):ひざのお皿の内側から、指3本分上

三陰交(さんいんこう):足の内くるぶしの骨から指4本分上で、すねの骨のきわ

お風呂上がりや腎機能が働く夕方にツボ押しをするとさらに有効です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。