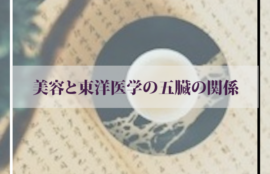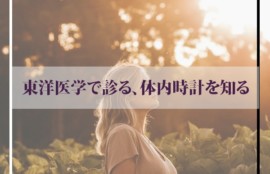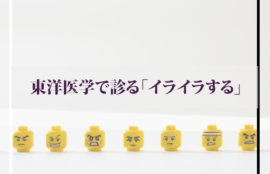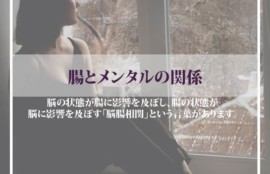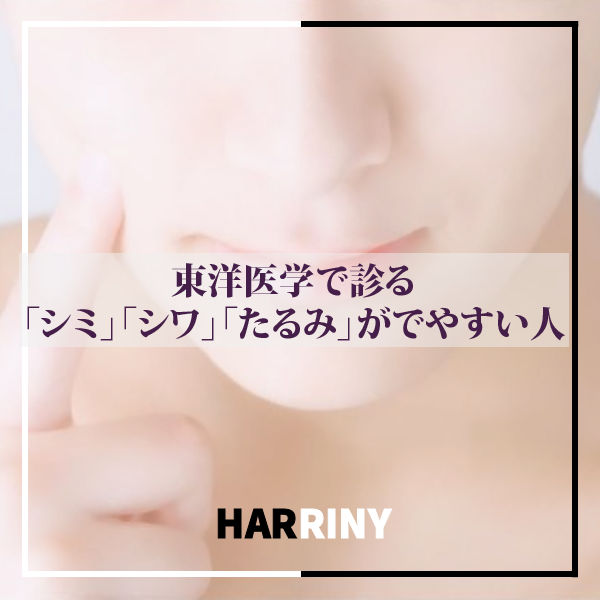
シミ、シワ、たるみは、老け見えの大きな原因です。これらには、いくつかの原因がありますが、最大の原因は紫外線による真皮層に受けたダメージです。真皮層で生成されるコラーゲンとエラスチンによって、皮膚は支えられるだけでなく弾力を維持し、頬などの形を保ちます。この真皮層にダメージが加わり、炎症が起こると、コラーゲンやエラスチンにもダメージが伝わります。他にも脂肪が蓄積されたことによってコラーゲンやエラスチンが肌を支えきれなくなってたるみにつながります。
シワができる3つの原因
1つ目のシワの原因は加齢とともに体内の「コラーゲンとエラスチン」が減少してしまうことが挙げられます。コラーゲンは繊維状のタンパク質であり、組織や細胞を繋ぎ合わせる接着剤のような役割をし、体の形成や機能の正常化に不可欠な成分です。
私たちの肌は、表皮と真皮で構成され、前者は水分の保持や体温の維持など外側から体を守る役割があり、後者は表皮の内側で肌のハリや弾力を保ち維持する役割があります。この真皮の約70%を構成する成分がコラーゲンです。
エラスチンは、体内に存在する弾力性をもった繊維状のタンパク質のことで、真皮に存在し、肌の弾力において重要な役割を果たしています。若いと体内のエラスチンのレベルが高いため肌にしっかりと弾力があります。
2つ目の原因は、加齢とともに、紫外線の影響、不摂生な生活、タバコやアルコールなど肌を傷つける「フリーラジカル」が発生し、肌が徐々にダメージを受け、状態が悪化して皮膚の弾力性が失われていきます。
最後の原因が、加齢とともに「肌が乾燥しやすくなる」ことです。当たり前ですがお肌の水分が若い頃よりも失われ、シワができやすくなります。また時間とともに肌がどのように老化するかは、環境的な要因以外にも遺伝的な影響もあります。
お顔にシミができる原因
紫外線ダメージ
肌が紫外線ダメージを受けると細胞が損傷し、その損傷を修復するためにメラニン色素が生成されます。メラニンにはユーメラニンとフェオメラニンの2つのタイプがあります。 ユーメラニンは黒や茶色の色、フェオメラニンは黄色や赤色の色を出します。メラニンはただ紫外線からの保護だけでなく細胞を守る抗酸化作用も持っています。しかし、その生産が過剰になると色素沈着として現れ、シミやそばかす、肝斑などが形成されます。紫外線ダメージが強いもしくは長期化すると肌を保護するためにメラニン色素が大量に生産され、シミが増え、老けた印象の顔になります。
また、紫外線にはUVAというUVBがあり、UVAは皮膚の真皮層まで到達し、肌にダメージを与えます。UVBは主に表皮だけに影響を与え、肌の表面を日焼けさせます。紫外線からの皮膚ダメージは一度できてしまうと改善が難しいケースも多く、常日頃から紫外線対策をしておくことがおすすめです。
加齢
加齢よる皮膚の変化は複数の要素に影響されますが最も大きな要因は新陳代謝の減少です。新陳代謝が遅くなると肌の細胞が古くなって剥がれ落ちるスピードも遅くなり、その結果メラニン色素が肌に長く残り、シミや老人性色素斑ができやすくなります。また加齢に伴い 皮膚のコラーゲンとエラスチンと呼ばれる繊維も減少し、これらの繊維は皮膚の弾力と構造を支えているため、減少してしまうとシワやたるみを引き起こすことになります。
さらに加齢によっての保湿能力も低下し、乾燥した皮膚は紫外線のダメージを受けやすくなり、メラニン色素の不均等な分布を引き起こす原因となります。加齢と紫外線の影響は相乗効果をもたらすことも多く、紫外線によるダメージが積み重なると加齢による皮膚の変化がさらに加速する可能性があります。早いうちから紫外線対策と 保湿ケアを行えば加齢による皮膚の問題もある程度は予防できます。
ホルモンバランスの変動
女性は月経、妊娠、更年期などといったライフステージでホルモンバランスが変動します。ホルモンバランスが変わるとそれが皮膚にも多様な影響を与え、特にメラズマと呼ばれるタイプのシミはホルモンバランスの変動が大きく関わっています。メラズマは、女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンの影響を受けやすく、メラニンを生成する細胞の活性 を高め、メラニン生成が促進します。
特に妊娠中や避妊薬を使用している期間や更年期には女性ホルモンのレベルが大きく変動し、メラニンの生成が不均等に行われ、肌にシミが形成されやすくなります。メラズマは額、頬、口の周りなどに現れることが多く、人によっては顔全体に広がることもあります。このタイプのシミは一般的なシミよりも治療が難しく、頑固な場合が多いです。ホルモンバランス変動による肌の問題は内科的な治療と皮膚科的な 治療両方が必要になります。
食生活の乱れや栄養不足
不均衡な食生活が続くと皮膚細胞の新陳代謝が乱れ、メラニン色素が不均等に分布する可能性が高まります。特にビタミンCとビタミンEが不足するとさらにシミが形成されやすくなります。ビタミンCとビタミンEには、抗酸化作用があり、体内の酸化ストレスを中和し、細胞を保護する役割がありますが、フリーラジカルが皮膚細胞にダメージを与えると メラニンの生成が促進される可能性あります。ビタミンCやビタミンEを摂ることで、フリーラジカルのダメージを軽減し、シミの予防効果が期待できます。
因みに食生活が乱れ、ジャンクフードや糖質を多く摂っていると顔にシワが形成されやすくなります。なぜなら不飽和脂肪酸が豊富なジャンクフードは、体内で炎症を引き起こし、その炎症はコラーゲンとエラスチンという皮膚の構造タンパク質にもダメージを与え、皮膚の弾力と強度を低下させ、その結果シワが形成されやすくなるからです。
遺伝
親が皮膚の老化が早い傾向にある場合、その傾向は遺伝的に引き継がれる可能性が高くなります。遺伝は皮膚の弾力性、厚み、油分の生成量、そして自然な修復メカニズムに影響を与え、これらの遺伝的要素がシワの形成につながることもあります。例えばコラーゲンとエラスチンが効率よく生成され、長く維持される遺伝子を引き継いだ場合、一般的な人よりシミが形成されにくい肌質になります。逆にコラーゲンとエラスチンの生成が少ない、もしくは分解が早い遺伝子を持っていた場合は、肌が早く老化して、シミが形成されやすくなります。ただしシミの原因はたくさんあるので、遺伝だけで安心したり、不安になる必要はあまりありません。
シミは暑さ、温度差でも増える
私たちの体には明るくなれば活動し、暗くなれば眠るという時計遺伝子があります。時計遺伝子は明るさに対して、紫外線が増えることを感知して、あらかじめメラニンをつくる指令を出します。この日差しが強くなる(明るくなる)ことを感知する時計遺伝子がDEC1です。
一方で明るくなり気温が上がることでもDEC1に異常が発生してメラニンの産生を増加させることも分かっています。つまり明るさ(日差しの強さ)と温度の高さ(暑くなる)が、DEC1の発現に関与しています。このように同じ紫外線量でも明るく気温が高くなるとメラニン産生の刺激が多くなり、細胞にダメージを与えないようにメラニンを産生を促すことで肌を守ろうとするのです(2019年POLA発表)。
さらに、シミは温度差でも増えるということが分かっています。温度差が肌に炎症を起こさないように、SCF遺伝子が活性化して、あらかじめメラニン産生を促します。一方でメラニンの合成を抑制するMITFという成分の産生が下がることも分かっており、そのため必要以上のメラニンをつくってしまいます。また温度差によって、肌の炎症物質であるIL-6やプロスタグランジンが増えることで皮膚のバリア機能を低下させることも分かっています。これらの物質もメラニン生成を促す刺激になるため、その肌荒れがシミの原因になります。
以外なシミの原因
紫外線によるお肌のシミが気になる方は多く、日焼け止めを欠かさないことはシミ対策に大切なことです。しかし肌のシミは日光が皮膚に当たることが原因だと思われがちですが、肌のシミは、実は目に日光が入ることも原因のひとつです。
なぜなら紫外線が目に入ると、脳に指令が伝わり、皮膚組織を紫外線から守るために色素沈着が生じます。これが肌のシミの原因になるため、肌を保護するだけでなく、サングラスをして目を守ることがシミ対策には大事なことなのです。
肝斑とシミの見分け方
肝斑(かんぱん)とシミは、見た目や診断だけではわかりにくいため、見た目だけでなく問診などによって総合的に判断していく必要があります。
肝斑の特徴としては、左右対称にもやっと形がはっきりせずに両頬に広がるシミが一般的です。肝斑の中にも、一筆状の細い肝斑や両頬に蝶形に広がるタイプもあります。基本的には左右対称ですが、非対称のものもありますし、下瞼の近くにはほとんどできないのも特徴のひとつです。肝斑はホルモンバランスが乱れやすくなる40〜50代の女性に多く見られます。
一方でシミは、日光黒子や老人性色素斑などと言われ、肝斑に比べて色が濃く、形がわかりやすく、境界がはっきりしています。シミは日光黒子や老人性色素斑以外にもいくつもの種類があり、しっかり見分けることが大切になります。
シミが増えやすい人の特徴
白い肌とシミ
シミが増えやすい人の特徴の一つが、肌が白い人です。肌が白い人は皮膚に含まれているメラニンが少なく、メラニン色素の沈着も少ないためシミもできにくいと考えるかも知れません。ただメラニンの量が少ない場合、皮膚の防御反応が過剰に働いてしまいます。つまり肌の白い人はメラニンの量が少ない分、肌を守ろうと必要以上の働きをすることで逆にメラニンが過剰に作られてしまいます。その結果シミができやすくなります。しかもメラニン色素は加齢とともに減少していくため、元々肌の白い人は他の人よりも余計にメラニン色素が減ってしまい、より一層シミができやすい肌になってしまいます。
シミと乾燥肌
乾燥肌がシミに関係ある理由の一つに、肌の乾燥はターンオーバーの乱れにつながってしまうからです。肌が乾燥すると肌内部を守ろうとして、ターンオーバーのスピードが速まってしまいます。そもそも加齢とともにターンオーバー が遅くなるのは、新しい細胞を作るのに時間がかかってしまうためです。しかし肌の乾燥が原因で新しい細胞を急いで作ろうとすると、新しく作られた細胞は当然未熟で弱い肌を作ってしまいます。弱い肌は外部刺激から肌を守る役割を果たすバリア機能が弱くなります。皮膚の一番外側にある角質層には、水分を保持して外的刺激から肌を守るバリア機能がありますが、バリア機能は水分と油分のバランスが取れている状態で正常に働くため、水分が減った乾燥状態ではバリア機能が低下してしまいます。
バリア機能が低下すると、紫外線などの外部刺激を受けやすくなり、シミができやすくなります。また若い頃にオイリーな肌であっても皮脂の分泌量は年齢とともに減少していき、特に50歳あたりになると誰もが肌の乾燥を感じやすくなります。皮脂の分泌量は20代が最も多いと言われ、その後50代にもなると脂性肌や混合肌だった人も乾燥肌になることが多くなります。
シミと肌を触る習慣
シミは紫外線だけでなく、摩擦による刺激でもできてしまいます。摩擦によって肌内部で起こる炎症が原因で、メラニンが過剰に生成されます。加齢とともにターンオーバーが乱れるため、過剰に生成されたメラニンの排出が追いつかなくなり、その結果シミができてしまいます。
因みに肌を触る以外でも、肌に強い刺激を与える習慣がある人も要注意です。強い刺激を与える習慣、例えば強い力でクレンジングしたり、洗顔後にタオルでゴシゴシ拭いたり、化粧水をつける際にコットンで擦ったりすることが挙げられます。
肌に合わない化粧品
以前、美白成分のロドデノールを使った化粧品(医薬部外品)が販売中止になりました。ロドネノールは、メラノサイトの色素(チロシナーゼ)を分泌するのを抑制して、色素をつくらないようにする働きがあります。しかしその代謝産物がメラノサイト色素をつくる細胞そのものを攻撃して細胞死に至り、色素細胞が無くなったため白斑という色が抜ける肌状態になることが販売してから分かりました。被害に遭われた多くの方は、肌に異変を感じていましたが、その異変が肌を白くすると我慢して使い続けていました。
化粧品は、肌に違和感を感じたら、肌が危険信号を出していることが多いため、使用を中止することが大事です。輸入化粧品や新しい化粧品など、様々なシミ対策化粧品が開発され販売されています。美白化粧品によってコントロールできるシミは、ターンオーバーレベルのものが多い(ほっといても消えるシミが大部分)と考えるべきでしょう。
5種類の顔のたるみ
真皮老化たるみ
真皮老化たるみは、肌にハリと弾力を与えてくれる真皮が老化することによって現れるたるみのことです。私たちの皮膚は表皮、真皮、皮下組織の3層で出来ており、表皮の下にある真皮は皮膚の本体とも言える部分で、見た目の老化に一番関係が深いと言われています。
真皮はコラーゲンとエラスチン、ヒアルロン酸の3つの美肌成分でできています。コラーゲンは肌のハリに欠かせない成分、エラスチンは肌の弾力を保つために重要な成分です。コラーゲンとエラスチンは網状に形成されていて、その間をスポンジのようにヒアルロン酸が存在します。
年齢とともにコラーゲンとエラスチンは体内で作られる量が急激に減少し、コラーゲンとエラスチンが減ってしまった真皮は、古くなったゴムみたいに弾力やハリを失います。
また、老化が原因のたるみは他にもあり、皮膚や筋肉と骨をつなぐ靭帯も劣化するため、皮膚を支えられなくなり、肌がハリと弾力を失って重力に負けて顔のたるみが発生してしまいます。さらに骨密度も年齢とともに低下するため、骨が痩せると皮膚がたるんでハリがなくなります。一方で基礎代謝も減るため顔についた脂肪がそのままたるみにつながることもあります。
乾燥たるみ
真皮にあるヒアルロン酸は、肌内部の保湿を保つ働きがあります。このヒアルロン酸も年齢とともに減少して、肌の水分が減ってしまうだけでなく、たるみにもつながります。乾燥は内側からだけでなく空気が乾燥するなど、外側から水分が奪われることもあります。特に目元は保湿力が低く、乾燥がたるみとして現れやすい部位であるため注意が必要です。
痩せたるみ
短期間で太ってしまうことで頬や顎の下に脂肪がついて二重顎になり、顔がたるみます。一方、短時間で脂肪だけを落としても皮膚はその変化に追いつけず 伸びた皮膚がたるみとして残ってしまうこともあります。無謀なダイエットとリバウンドを繰り返すと皮膚が伸縮してたるみにつながるため注意が必要です。
無表情たるみ
人間の顔には表情筋と呼ばれる筋肉があり、顔の脂肪や皮膚を支えています。普段から喜怒哀楽を表情に出さないと表情筋衰えてたるみにつながってしまいます。
うつむきたるみ
猫背など姿勢の悪い状態でうつむいた状態を長く続けると顔の筋肉がうまく働かずにたるんでしまいます。またたるみだけではなく、首に深いシワができてしまうこともあります。
その他のたるみの原因
他にも顔がたるむ原因に女性はエストロゲンの減少も関係しています。女性ホルモンはエストロゲンとプロゲステロンの2種類があり、卵巣から分泌されるエストロゲンの分泌量は40代から急激に低下します。このエストロゲンはコラーゲンやエラスチンの生成を促す働きがあるホルモンです。ホルモンが低下すると皮脂腺や汗腺が萎縮して全身の肌の乾燥にもつながってしまいます。
一方で、紫外線もたるみの原因になります。紫外線といえばシミのイメージですが、たるみにもつながってしまいます。紫外線にはUVA、UVB 、UVCの3種類があります。日焼けやシミはUVBの影響で、UVBを浴びた肌はメラニンを生成して、肌の色を濃くしてUVによるダメージを防ごうとします。過剰にメラニンが生成されてしまうとシミや色素沈着を引き起こしてしまいます。
厄介なのは真皮までダメージを与えるUVA です。UVAは最も波長の長い紫外線で真皮まで到達して、コラーゲンやエラスチンを壊します。コラーゲンやエラスチンを作るための繊維芽細胞もUVAによって損傷を受けてたるみにつながります。UVAはUVBの20倍以上も降り注いでいて、波長の長さから雲やガラスも通過します。つまり曇りの日や家の中にいる時も油断は禁物です。
また、肌の糖化もたるみにつながってしまいます。食事などから摂取した糖分のうちエネルギーとして使われなかった部分はタンパク質と結合します。糖とタンパク質が結合することで細胞にダメージを与えてしまうことを糖化と言います。コラーゲンとエラスチンもタンパク質の一種のため糖化によって伸縮性が失われ、肌のハリや弾力、瑞々しさがなくなってたるみやシワができてしまいます。
お顔の「シミ」「シワ」「たるみ」対策
保湿
保湿が大事なのは分かっていても正しい保湿ケアができていない人が多くいます。肌の表面には角質層と呼ばれる部分があり、この角質層が乾燥すると肌のバリア機能が低下します。バリア機能が弱まると外部からのダメージに対して肌が脆弱になり、シミができやすくなります。逆に角質層がしっかりと保湿されている状態であれば、肌は自らを守る機能をしっかりと発揮します。
そのため保湿剤を選ぶ際には、自分の肌質に適したものを選ぶことが重要です。乾燥肌、脂性肌、混合肌、敏感肌といった肌質によって最適な保湿剤は変わってきます。乾燥肌には水分と油分をしっかり補給できるクリームやオイルベースの製品が良く、成分で言えばヒアルロン酸、セラミド、グリセリンといった高保湿成分が含まれている製品が効果的です。
乾燥肌の場合、軽いテクスチャーでは物足りなく感じるため、重い感触の製品がおすすめになります。脂性肌の場合、油分が過多になりやすいため、水分を多く含むが油分は控えめな製品が良く、ジェルタイプやローションタイプの保湿剤がおすすめです。成分としてはサリチル酸やニキビ予防成分を含む製品を選ぶと良いでしょう。混合肌の場合、顔の部分によって状態が変わるため一概には言えませんが、バランスを考慮した製品が良いでしょう。例えばジェルとクリームを使い分けると言った方法が適しています。油っぽい部分はジェル、乾燥部分はクリームで保湿をするなどの使い分けがおすすめです。
そして敏感肌の人は成分に特に注意を払う必要があり、無香料、無着色、アルコールフリーの製品を選ぶようにしましょう。さらに炎症を抑える成分、アロエベラ、カモミールが含まれているとより安心して使用できると思います。
抗酸化作用の高い食品
抗酸化作用とは体内で発生する活性酸素を抑制する能力のことで、活性酸素は日々体内の様々な反応で生成されています。活性酸素が過剰になると細胞にダメージを与え、肌の老化を促進させてしまいます。そのため食事から抗酸化作用の高い食品を摂取することが大事になります。
抗酸化成分にはビタミンC、ビタミンE、フラボノイド、ポリフェノール、カロテノイドなどがあります。ビタミンCはメラニン生成を抑制し、既存のシミやくすみを薄くする効果が期待できます。ビタミンCは柑橘類やベリー類、ブロッコリーやパプリカに多く含まれています。
ビタミンEは細胞膜を保護し、皮膚の老化を遅らせる効果があります。抗酸化ビタミンを豊富に含む食品としては、トマト、ほうれん草、種類などが挙げられます。食品だけでは十分な量の抗酸化物質を摂取できない場合は、サプリメントの活用をおすすめしますが、その場合は第三者機関の認証を受けているか確認しましょう。代表的な認証機関としては、食品や医薬品の品質をチェックするNSFやUSPがあります。
運動習慣
運動をすることで筋肉から分泌されるマイオネクチンは、体内での炎症反応を抑制する働きがあることが確認されています。マイオネクチンは主に筋肉から分泌されるタンパク質の一種、このタンパク質は運動によって筋肉から放出され、体内を循環します。
マイオネクチンは脂質代謝を正常化する働きもあり、炎症を引き起こす可能性のある代謝異常を緩和します。炎症は様々な皮膚トラブル特にシミや肌の老化を起こす可能性があり、炎症が起きると体はそれを鎮めようと炎症性サイトカインと呼ばれる物質を分泌します。これが過度になると皮膚にダメージを与え、メラニン色素の過剰生成を引き起こします。このメラニン色素が肌の特定の部分に集まるとシミになります。
日焼け対策
日焼け対策はシミの予防や改善をする上で欠かせない要素です。日焼け止めには主に化学性と物理性の2つのタイプがあります。化学性の日焼け止めは、紫外線を肌で吸収し、それを無害な熱エネルギーに変換するタイプの日焼け止めで、塗り心地がよく白浮きすることが少ないというメリットがあります。しかし紫外線吸収剤が含まれていて、それが皮膚から体内に浸透すると言うデメリットがあります。また肌に対する刺激も強く、肌細胞を劣化させる可能性もあります。
一方の物理性の日焼け止めは、肌の表面で紫外線を反射させて、肌を保護タイプの日焼け止めで、塗り心地が悪かったり、白浮きしやすいというデメリットがあります。しかし体内に入り込んでくる化学薬品は含まれておらず、健康を害する心配はそこまでないと言えます。また、日焼け止めのPAとSPF値の違いがあり、PAは皮膚の深部まで到達するUVAからの保護レベルを示し、pHはプラスの数で表され、PA4+が最も高い保護レベルとなっています。日常生活で少量の日光にさらされる場合は、PA3+程度で大丈夫です。長時間屋外で過ごす場合や紫外線の強い夏場はPA4+が理想的です。
SPFは、表皮だけに影響 を与えるUVBから肌を保護する力を示しています。SPF値が高いほどその保護力は強く、一般的にはSPF30からSPF50が広く使用されています。それ以上のSPF値はあまり意味がなく、塗り心地が厚く感じられることが多くなります。日常使用であればSPF15から30程度で十分で、長時間屋外で過ごす場合や紫外線の強い夏場はSPF30以上の製品を選ぶことにしましょう。
屋外活動が長い場合、汗をかいた後は2から3時間ごとに日焼け止めを塗り直すようにしましょう。特に激しい運動後は汗で日焼け止めが流れてしまう可能性が高く、日焼け止めは 一度塗ったら終わりではなく、何度も塗り直すことが大事です。
美白成分が含まれたスキンケア製品
美白成分は、メラニン生成を抑制したり、既存のメラニンを分解排除したりする作用があります。美白成分のハイドロキノンはメラニン生成の過程に直接働きかけ、高い美白効果を発揮しますが、一般的には医師の処方箋が必要な成分です。低濃度のものは市販でも入手可能ですが、高濃度のハイドロキノンは刺激が強く、皮膚が薄くなるリスクがあります。シミを改善したいという目的であれば低濃度のハイドロキノンで十分でしょう。ただし肌質やシミの大きさにもよるため、シミが必ず消えるとは断言できないでしょう。
ナイアシンアミドの美白成分もシミの改善効果が期待できます。ナイアシンアミドは色素沈着を減らすだけでなく、肌のバリア機能を向上させる作用があります。化粧品では、ナイアシンアミドの配合率が2から5%の製品が多く、この濃度範囲でも使い続ければ効果を 期待できます。一部の製品では10%前後のナイアシンアミドが配合されているものがありますが、美白成分が高濃度になるとどうしても肌への刺激が強くなるため、高濃度の美白成分を使用したい場合は、必ず使用前にパッチテストを行いましょう。
また、リコリスエキスという美白成分もシミの改善効果が期待できます。リコリスエキスは天草と呼ばれる植物の根から抽出される成分です。その主成分であるグラブリジンには強い抗炎症作用と肌の色調を整える効果やメラニンの生成を抑制する働きもあり、シミやくすみの予防、改善が期待できます。
「シミ」「シワ」「たるみ」に効果がある栄養素
お肌にハリが出るリグナン
お肌のハリを出すという点で注目したい栄養素がリグナンという珍しい物質です。リグナンは、かぼちゃのうちでも特に種の部分に豊富に含まれていることが知られています。リグナンは植物ポリフェノールの一種で、高い抗酸化作用を発揮する他、体内で女性ホルモンの エストロゲンに似た作用を示すという珍しい効果もあります。エストロゲン用の作用を示す天然物質としては大豆に含まれているイソフラボンが有名です。かぼちゃの種に含まれるリグナンには、イソフラボンと同様の女性ホルモン用作用によってお肌の若返りをもたらしてくれる効果が期待できます。リグナンを適切に摂取することでお肌に潤いが与えられることが知られおり、皮膚の水分はお肌のハリに不可欠な要素のため、リグナンたっぷりのかぼちゃの種を食べることでたるんだお肌がみるみる蘇っていくことでしょう。
また同じく植物の種としてはかぼちゃの種に加え、ひまわりの種もおすすめです。ひまわりの種には豊富なカリウムが含まれており、カリウムは体内の過剰な塩分を尿として排出する機能があり、それによって細胞の間質液中のナトリウム濃度が下がって、むくみが取れることが期待できます。
大豆製品に含まれる大豆イソフラボン
大豆製品は大豆を加工したもので、大豆の高いタンパク質を引き継いでいます。タンパク質には動物性と植物性があり、大豆製品は植物性タンパク質となります。植物性タンパク質は、不飽和脂肪酸が豊富で、コレステロールを含まないという特徴があります。また植物性タンパク質は食物繊維を豊富に含み、消化システムの健康にも役立ち、便秘の予防や腸の健康維持にも効果的です。さらに大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと同じ働きがあり、更年期障害の緩和や骨密度の低下を防ぐ効果があります。大豆製品には、豆腐、納豆、味噌、油揚げ、きな粉など様々な種類のものがあります。
お肌のバリア機能が強化するフコイダン
昆布が持っている栄養素の中でも私たちのお肌のハリに関係しているものがフコイダンです。フコイダンは水溶性食物繊維の一種で、水溶性食物繊維には腸内にたまった便にぬめりを持たせるもとで便通をスムーズにしてくれる作用があります。便通がスムーズになれば、それだけ腸内の毒素が排泄されるため、腸内環境が良くなってお肌が綺麗になる効果が期待できます。
さらにフコイダンには私たちのお肌のバリア機能を保管してくれる働きがあるとも言われています。年を取ると皮膚のバリア機能が低下することで乾燥や紫外線など様々なダメージに晒されやすくなります。このようなダメージによって皮膚の細胞内で活性酸素が発生し、お肌が錆びついてシミなどの原因になることが分かっています。
フコイダンには高い保水効果があり、このようなお肌のダメージを未然に防いでくれる効果が期待されています。そのためフコイダンは食べるだけでなく美容液などにも配合され、お肌に直接塗るのも良いとされています。さらに最近の研究ではフコイダンに細胞を再生する効果があるということも分かってきました。
健康な肝臓は7割切り取っても時間が経つとトカゲのしっぽのように再生することが知られています。このような 肝臓の再生には肝細胞増殖因子( HGF)という物質が関わっており、フコイダンはお肌において、このHGFを増やす効果があることが分かってきました。HGFは、お肌の再生医療として今美容業界で研究が進んでいる物質です。
さらに昆布には甲状腺ホルモンの材料となるヨウ素が豊富に含まれています。甲状腺ホルモンは私たちの代謝をアップし、体の内側から活力をみなぎらせてくれるホルモンです。
お肌のターンオーバーを促す亜鉛
牡蠣にはたっぷりの亜鉛が含まれており、亜鉛は私たちの皮膚のターンオーバーを促す非常に重要な栄養素です。年を取ると皮膚のターンオーバーが乱れ、古い細胞が蓄積し、新しい細胞が生まれてこなくなります。牡蠣はそのようなお肌の新陳代謝の乱れを正し、どんどんお肌を若々しくしてくれます。また亜鉛はタンパク質の合成に不可欠であり、お肌に存在するタンパク質といえばコラーゲンが挙げられます。
徳島文理大学と昭和大学の共同研究によれば、亜鉛が皮膚のコラーゲンの形成に重要な役割を果たしていることが分かりました。コラーゲンを生み出す細胞を繊維芽が細胞と言い、この繊維芽細胞内の亜鉛代謝に関わる遺伝子を抑制したマウスでは、皮膚が薄くなってコラーゲンが顕著に減少することが分かっています。さらに牡蠣には、セレンという普段の食事からは摂りづらい珍しい栄養素も豊富に含まれています。セレンは抗酸化ミネラルと呼ばれていて、その高い抗酸化作用から細胞の老化を防いでくれるのみならず、甲状腺ホルモンを活性化して活力をアップさせてくれる作用もあります。
お肌の潤いを保つタンパク質
お肌の健康のみならず、筋力を保ち常に若々しくいるためにタンパク質をしっかり摂取するということは絶対に必要です。一般に成人では1日に体重1kgあたり1gのタンパク質を 摂取するべきだと言われています。
鶏胸肉は動物性食材の中でも特にタンパク質が豊富で、100gあたり約31gのタンパク質を含み、低カロリーでかつ低脂肪です。また鳥胸肉は人体が必要とする9種類の必須アミノ酸を全て含んでおり、アミノ酸は細胞の修復、免疫機能のサポート、ホルモンの生成など体の様々な機能に関与します。さらにお肌の潤いを保つために重要なビタミンA、ビタミンB群やミネラルも含まれており、これらの栄養素はエネルギーの代謝や細胞の機能をサポートしてくれます。
また毎日の食に摂り入れやすく、高タンパクな食材がたまごです。たまごは高タンパク質食材で、健康な皮膚、髪、筋肉、骨を維持するために役立ちます。たまごには、ビタミンA、ビタミンD、B12、B6 、E、葉酸、亜鉛などが豊富に含まれています。これらの栄養素は、皮膚の健康や免疫機能の維持、老化を抑えるための要素として重要です。
また卵黄にはコリンという栄養素も含まれており、コリンは神経伝達物質の生成に関与し、記憶力の維持や認知機能のサポートをしてくれます。さらにたまごに含まれるルテインとゼアキサンチンは、目の健康を維持するのに役立つ栄養素です。
健康と美容の両方で役立つリジン
オートミールは、オーツ麦の小粒を粉砕や圧延して加工したもので、一般的なシリアルよりもタンパク質含有量が多いです。例えば約50gの乾燥オートミールには、約5から7gのタンパク質が含まれています。タンパク質の質は、含まれるアミノ酸の種類やバランスによっ て決まり、オートミールには人体で合成されない9種類の必須アミノ酸が含まれています。特にリジンというアミノ酸が比較的豊富で健康と美容の両方で役に立ってくれます。
フリーラジカルを抑えるビタミンC
カッテージチーズは低脂肪でありながら高タンパク質を誇る乳製品です。近年、健康や美容を意識する多くの人々の間で理想的な食材として認知されるようになりました。カッテージチーズには骨や歯の健康をサポートするカルシウムが豊富に含まれており、さらにビタミンDを加え、カルシウムの吸収率をアップさせている製品もあります。
また、カッテージチーズには、皮膚の弾力性やハリを保つために必要なビタミンCも含まれており、ビタミンCは強力な抗酸化作用も持っているため、フリーラジカルと呼ばれる不安定な分子を中和する働きがあります。フリーラジカルは紫外線、空気汚染、タバコの煙などの外部要因によって生成されることが多く、フリーラジカルが体内で増えすぎると細胞にダメージを与え、老化を促進してしまいます。ビタミンCの抗酸化作用でフリーラジカルを抑えることができれば老化を遅延させることができます。カッテージチーズの1日の推奨摂取量は100gから200gとなっています。
東洋医学で診る「シミ」「シワ」「たるみ」
「腎」の調子が悪くなると
東洋医学では、五臓のうち「腎」の働きが低下すると、肌の若さが失われるとされます。「腎」は、体の水分調整や排泄をコントロールしており、水分・血液のろ過を担い、不要物を出す働きが停滞すると、皮膚の色が黒ずむと考えられています。また血とも関連があり、血流のよい肌は「血色がいい」と言われるように、「腎」の働きが弱まると、シミ・シワが目立つようになると言われています。そして体のエネルギーである「気」は、肌を持ち上げてハリを保つ働きがあるため、不足すると皮膚がたるんでしまいます。
またアンチエイジングを考える上で、東洋医学の「腎精不足証」も重要な要素です。腎精不足証は、腎の精気が不足し、成長発育の遅れ、生殖機能の低下などを引き起こすとされています。これは先天的な問題や栄養不良、過度の労働、長期の病気などによって引き起こされることがあります。
腎精不足証の改善には、バランスの取れた食事、十分な休息、ストレス管理が必要です。また特定の漢方や鍼治療が有効です。腎精不足証にお勧めのツボは、百会、腎兪、関元です。
「肝」の調子が悪くなると
東洋医学では「肝」が弱ってくると血が滞り、シミが出やすくなると考えます。よく言われているのが、「顔はその人の内臓状態を映す鏡」です。東洋医学で言う「肝」と西洋医学で言う「肝臓」は、似ているけれど非なるものです。
この「肝」は、主に2つの大きな働きがあります。それが、疏泄(そせつ)機能と蔵血(ぞうけつ)機能です。前者は「気」を身体のすみずみまで行き渡らせる機能で、後者は「血を」コントロールし、身体が必要としている場所に血を分配する機能です。
「肝」の調子が悪くなると「気」の流れが悪くなり、主に3つの症状が表れます。1つ目が、気の不足が起こす症状で、疲れやすくなり、免疫力が低下する、だるさが溜まるなどです(気虚)。2つ目が、気がスムーズでなく滞る状態で、ストレスやお腹や胸が張り、痛む感じになりやすいなどです(気滞)。3つ目が、気が体の中で上昇して、イライラや怒りやすくなったり、めまいや不眠などの症状を引き起こすことがあります(気逆)。
一方で、「肝」は全身から老廃物を集めてきた血をキレイにし、心身の活動が低下する夜間には、血を整えて、栄養を与えます。しかし血の巡りが悪くなると、肌のターンオーバーに必要な栄養か不足し、肌がカサカサしてシワになったり、シミが沈着します。
要注意な生活習慣
次の様な生活習慣に当てはまる方は「腎」「肝」の働きが弱くなりやすいので、要注意です!
- 夜にきちんと睡眠を取らない
- イライラ、怒りっぽい
- 気分が落ち込みやすくクヨクヨしがち
- PCやスマホをよく使い、目を酷使
- 緊張感の多い生活を送っている
もし、当てはまる項目があれば、「腎」「肝」を整える養生が必要です。まずは深呼吸をして、たくさん笑い、ストレスを溜めないといったことも非常に効果的です。
シワと良質な睡眠の関係
心臓やリンパのポンプ機能は歳を重ねるごとに落ちます。若い頃は睡眠不足でもなんとかなっていましたが、30代40代と歳を重ねるごとに心臓やリンパの機能が弱くなって、水分が体に巡りにくくなります。夕方になると足がむくみ、どんどん顔が乾燥してきたり、テカリが出てきたりするこれは重力で水分が下に行ってしまっている状態です。若い頃は優秀なポンプ機能のおかげで水分を体中に巡らせることができていましたが、大人になればむくみとして現れてきます。これをクリアに戻してくれるのが睡眠です。
睡眠中は横になり、重力が体の全体に均等にかかり体中に水分が巡りやすくなります。夕方には目が落ちてくぼみやすい人も、朝は大丈夫な場合が多いのはこの理由だからです。しかし睡眠時間が短くなるときちんと水分が体中に巡る時間が足りなくなってしまいます。
因みに22時から2時がお肌のゴールデンタイムと呼ばれていましたが、実はこれは正確ではありません。この時間よりも深い眠りについているかどうかが問題になります。深いノンレム睡眠は寝付いてから90分から120分に多く現れ、そのタイミングで成長ホルモンが最も多く分泌されます。ただし、睡眠にはノンレム睡眠とレム睡眠の2種類あり、朝方になるとレム睡眠の時間が長くなります。そのためできれば0時までには寝ると良質な睡眠が取れる可能性が高くなります。
十分な睡眠時間を確保することも大事ですが、シワの観点から見ると8時間くらい寝るのが良いと言われています。これは研究でも明らかになっていて、睡眠時間を5時間の時と8時間の時で比べて見ると、5時間睡眠の時の方がシワが増えた人が45%、その上シミが増えた人13%、赤みが増えた人が8%でした。このように美肌と良質な睡眠は密接な関係があることが分かっています。
肌フローラを整える
肌を綺麗に保つためには、肌老化の7割と言われるため①UVケアをする、洗顔等でゴシゴシ擦って炎症を起こさないためにも②摩擦を避ける、肌のバリア機能を低下させないための③肌を乾燥させない、この3つが基本的なことです。
これらのベースを守りつつ、ぜひ取り入れて欲しいのが「乳酸菌」です。乳酸菌というと腸内環境と思われるかもしれませんが、腸と肌には相関関係があります。
腸には善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3つがあり、これらのバランスが保たれている状態を腸内フローラと呼ばれています。悪玉菌が増えると腸内で有害物質(p-クレゾールなど)が増え、それによって便秘になったり、ガスが臭くなったりすることがありますが、この有害物質が血液に乗って肌へも悪影響を与えてしまいます。例えば肌の水分量が低下して乾燥が起こります。
一方で、善玉菌が増えると、生成された酢酸、乳酸によって悪玉菌が増殖するのを抑えてくれます。つまり悪玉菌がつくる有害物質を抑えてくれる作用があります。このように乳酸菌を摂取することで腸内のバランスが保たれ、悪玉菌が増えるのを抑えてくれるので肌の調子も良くなるということになります。腸の善玉菌を増やすためには、発酵食品や乳酸菌飲料などが摂取する方法があります。
同じように肌にも善玉菌が存在しており、常在菌のバランスが崩れると腸と同じように肌荒れを起こすことが分かってきています。つまり肌の状態を保つためには、肌の常在菌のバランスを保つ必要があるのです。
肌の善玉菌は「美肌菌」とも呼ばれ、表皮ブドウ球菌が代表的な菌です。例えば肌の皮脂を分解し、脂肪酸(弱酸性)に変え、悪玉菌が増殖することを抑えてくれる役割があります。また皮脂を分解する時に、グリセリンという保湿成分をつくってくるため肌荒れを抑えてくれる役割もあります。また皮脂が酸化してしまうと、シミやシワの原因になる過酸化脂質になるため、酸化を抑えてくれる役割もあります。
これらの美肌菌は、年齢、紫外線、ストレスなどの生活環境によって大きく変化してしまいます。
ツボで流れを整える
美肌菌のためにも「腎」「肝」の働きに関係するツボを、親指で軽く押すことで、心と身体の緊張をほぐしてあげましょう!
太衝(たいしょう):脚の親指と、人差し指の骨の間のくぼみにあるツボ

太渓(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間

三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上に位置するツボ

働きが低下している部分をケアすることで、予防・改善の効果が現れます。
大人のSTK鍼灸コース(シワ・たるみ・くすみ)
多くの人にとって、お肌の「透明感」は、昔も今も変わらない憧れです。その透明感の正体は、白い肌と思われがちですが、まずはお肌全体が滑らかで均一であることでしょう。つまり透明感は、肌の色そのものではなく、きめが細かくて血色がよく明るい「健康的な肌」ということです。当たり前ですが、角質が残っていたり、毛穴が目立っている、血色が悪い、乾燥でカサカサしているなどは、透明感のある健康的な肌になり得ません。
しかし、年齢を重ねるにつれて、どうしてもお肌の色むらが気になります。特に清潔感を保ちながら年齢を重ねる難しさがあり、意識したアンチエイジングケアが必要になります。私たちのお肌は年齢と共に衰え、シワ・たるみ・くすみなどが目立ち始めます。
【シワ】
シワは、加齢による「表情筋の衰え」と「肌の水分量の低下(乾燥)」が主な原因です。シワは、紫外線による肌の乾燥を防ぎ、保湿などで水分を補い、表情筋を鍛えて、お肌に柔軟性を持たせることでシワ予防や目立たなくすることが可能です。特に、シワが起こりやすい前頭筋、口輪筋、眼輪筋などを美容鍼で刺激することで筋肉をほぐし、肌の血流が良くなって肌にハリが戻ります。
【たるみ】
たるみは、「表情筋の低下」「肌の弾力の低下」「新陳代謝の低下」などが主な原因です。たるみを改善するためには、シワと同じく表情筋を鍛え、しっかり保湿ことも大切ですが、お肌の真皮に存在しているコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸の生成を促すことも重要です。これらの成分は線維芽細胞で生成され、肌に弾力と潤いを与えます。
【くすみ】
くすみは、首や顔の筋肉のコリによって血行が悪くなり、お肌のターンオーバーが遅れることで起こります。ターンオーバーが遅れると、肌の表面に不要な角質が蓄積されてしまい、肌の透明感が失われた結果「くすみ」が生じます。くすみの改善には、まず身体の血流を促進して、ターンオーバーを正常に戻し、新陳代謝を促すことが大切となります。
美容鍼で顔のツボを刺激して筋肉のコリをほぐし、血行を促進することで、肌に透明感やハリが出てフェイスラインもシャープになります。このように、お肌の「透明感」を保つためには
- ターンオーバーを正常に保つ
- 表情筋を鍛える
- 血流を促進する
- コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸の生成促進
が重要となります。そして大人のSTKコースの魅力は「肌質の変化」です。コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸の生成などの美容成分の分泌を促進することで、翌日以降のハリや弾力、キメや透明感、お化粧のりの良さをぜひご体感ください。
当院では「透明感」のお悩みを、化粧品などで隠すのではなく「美容鍼」で身体の中から改善することを重要視しています。お身体の不調は、肌や表情にあらわれて表れてしまします。お化粧では隠しきれないその疲れを、全身治療+美容鍼でお身体の中から改善していきます。「透明感のある肌」を目指すためには、血行促進、保湿、角質の除去などを心がけて、肌理の細かい健康的な肌にすることが重要です。毎日のケアで「透明感」のある健やかな肌を目指すお手伝いを致します。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。