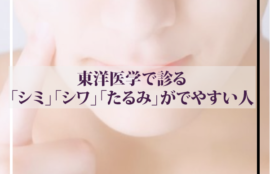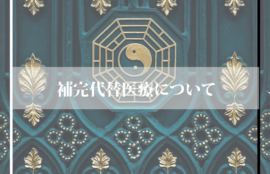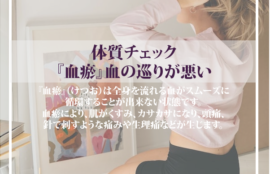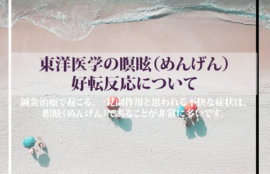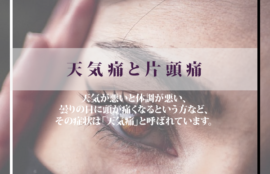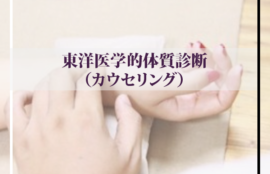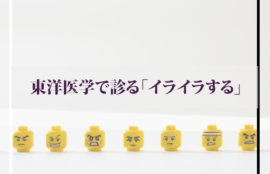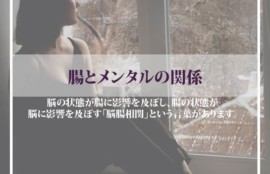〝甘いものが大好き!〟
〝疲れた時や仕事が立て込んでいる時などに
甘いものが食べたい!〟
というは、脳がいち早くエネルギーになるぶどう糖=甘いものを取り入れたいと思うからです。ただし、甘いもの(精製された糖)は血糖値が短い時間に激しく上下します。そのため血糖値が下がった時にまた甘いものを食べたくなるという、血糖値の急上昇と急降下を繰り返して、余計に体が疲弊します。また血糖値の急降下は、眠気やだるさの原因となります。
そのため、疲れた時には血糖値を緩やかに上げるGI値の低い食品を選んで食べることが大切になります。
メンタルと甘いものの関係
食べ物とメンタルの関係には大きな影響があります。砂糖が入った飲み物が抑うつ症状やうつ病のリスクを高めることが様々な研究で指摘されています。これは砂糖によって糖質中毒になる可能性があるからとされています。
甘いものを食べると体内の血糖値が急上昇します。特に甘い飲み物は、胃で消化する必要がないため、小腸まで直接届いて糖分が吸収されて血糖値が急激に上昇します。この状態になると脳内から幸福物質(脳内物質)であるセロトニンやドーパミンが分泌されて幸せな気分になります。しかしそれは一瞬です。
血糖値が急上昇すると、体は血糖値を下げるため膵臓からインスリンを急激に放出します。すると今度は急激に血糖値が下がり、低血糖状態に陥り、幸せな気分から一転してイライラしたり、気持ちが不安定になり、眠気や吐き気に襲われます。そしてまたあの気持ち位状態に戻りたいと思い糖質を求める負のループに陥ります。このような状態を糖質中毒と言い、血糖値が何度も乱高下するため、血管がボロボロになり、インスリンの分泌能力が衰え、効き目も悪くなり、糖尿病をはじめとした様々な深刻な病気につながります。
特に注意してほしいのが、甘い飲み物です。2019年の研究によると、砂糖が添加された甘い飲み物の摂取量が1日あたり約350ml増えるごとに、すべての原因による死亡リスクが11%高くなることが分かっています。またフルーツジュースの場合は悪影響が大きく、死亡リスクが24%高くなることが分かっています。このような研究結果があるため、甘い食べ物を気おつけると同時に、甘い飲み物については徹底的に避けるようにしましょう。
体調が悪くなると食べたくなる
体調が悪くなると無性にポテトチップスなどの高脂肪スナックが食べたくなる人がいたら、それは特定の栄養素が欠乏しているサインである可能性が指摘されています。例えば高脂肪スナックが食べたくなるのは、一般に体の中でカリウムが不足しているサインであると考えられています。
体調が悪くなると下痢や嘔吐してしまう方も多いかもしれませんが、下痢や嘔吐は水分だけではなく、大量のカリウムが失われます。カリウムは血圧を調整してくれる他、筋肉を動かすためのシグナルになるなど健康のために重要な働きを担っています。カリウムが不足するサインとして、無性にスナックが食べたくなるような異常食欲を起こすことが分かっています。
しかし、カリウムを摂取するために高脂肪スナックを食べたところであまり効果はありません。カリウムを効果的に摂取するには、ミネラルの多い天然塩や果物を食べたりするのが一番です。また同じような体からのSOSサインとして甘いものが食べたくなる時があります。普段は甘いものを食べないのに、ケーキのようなお砂糖をたっぷりのスイーツが食べたくなる日があります。それはだいたい疲労が原因であると言われています。
もう一つ有名な異常食欲の例として、無性に氷が食べたくなるのがあります。氷を食べたくなるというのは異食症として有名で、鉄が足りなくなった時にしばしば起こる症状です。鉄が欠乏すると鉄を原料として合成されるヘモグロビンが減って貧血になります。そのため無性に氷が食べたくなるというのは生理の関係で貧血になりやすい女性に多い症状です。女性の方で無性に氷が食べたくなった時は、高確率で鉄不足に陥っているため、レバーやほうれん草など鉄がたっぷりの健康的な食事を摂りましょう。
このように体内である栄養素が欠乏した時に、なぜかそれとは全く関係のないものを無性に食べたくなるメカニズムについては、まだ解明されてはいません。
東洋医学で診る、甘いものを食べたくなる
一方で東洋医学的には、甘いものを摂りたいというのは、『脾』が弱っているサインです。『脾』は、西洋医学の「脾臓」とは少しイメージが違います。『脾』とは、現代で言うならば胃に近い働きをしていて、消化・吸収・栄養を担い、内臓や外見の位置を保つことに関わっています。また感情面では「思い悩み」と関係があり、思慮、思考、判断、執着的、知的などの精神的な関係があります。
例えば「ストレスが胃にくる」とも言い、東洋医学でいう脾や胃の感情は「思い悩み」が影響するため、常にストレスと隣り合わせの部位でもあります。
特にストレス社会である現代では、胃腸の不調など消化器系の問題を抱えている人が非常に多くいらっしゃいます。つまり脾や胃にかなりの負担がかかっている状態です。そのため脾臓のバランスをとることによって、甘いものへの欲求を抑えることが大切になります。
脾が不調になると出てくる体のサイン
- フェイスラインのたるみ
- ほうれい線
- 目尻や口角が下がる
- 肌が黄っぽくなる
- 胸、お尻、お腹がたれる
- 胃がもたれる
精製された糖(白砂糖、小麦粉、白米)
精製された糖の代表が白砂糖、小麦粉、白米です。これらが原因(白い悪魔)となって起こる病気として、糖尿病、アルツハイマー型認知症、慢性関節炎、各種アレルギー疾患などがあり、これらは食事で原因で起こる「生活習慣病」とも言われています。生活習慣病は食事を見直すことでしか改善できない病気とも言えます。
なぜ精製された糖(炭水化物)が体に良くないのかというと、あまりにも消化・分解が簡単なためです。分解されたぶどう糖はすぐに血液中に入り、急激に血糖値を上げてしまいます。そうなると脳が瞬時に体に緊急事態が起こっていることを膵臓に伝えて、大量にインスリンが放出されます。しかしやがて疲れ果て、徐々にインスリンを作り出す能力も衰えて同時に血糖値が下がりにくくなります。この状態が「糖尿病予備軍」と言われる状態で、さらにこの状態が続けば血糖値が下がらなくなり、本格的な糖尿病になってしまいます。
また、膵臓に負担をかけることは、副腎にも負担をかけることになります。血糖値の乱高下は体に強いストレスを与えるため、副腎からコルチゾールやアドレナリンなどのストレスに対抗するためのホルモンが分泌されます。そしてこの状態が長く続けば当然副腎も疲弊していき、副腎疲労を招き、様々な不調が体に現れるようになります。
甘いもの(精製された糖)≠糖質
糖質は太るから摂らないという方もいらっしゃいますが、当たり前ですが体にとっては必須なものです。炭水化物を抜くと痩せるというのは、白米やパンなど分かりやすく制限しやすいからです。研究では、糖質を制限してもしなくても、同じカロリー量であればダイエット効果が変わらないことが分かっています。さらに糖質は長い間制限してしまうとかえって太るということも分かっています。いずれにしても糖質制限は分かりやすく、最初は痩せますが、それ以上に長期的に見れば痩せづらい体になってしまいます。
医学誌で有名なランセットで発表された論文では、死亡率と糖質量に相関関係があり、総摂取カロリーの50%前後が一番死亡率が低いことが分かっています。つまり1日に食べるカロリーのうち半分程度は糖質から摂ることが良いのではないかということです。ちなみに低糖質(30%以下)より高糖質(70%以上)の方が寿命が長くなることも分かっています。
摂るべき糖質は、ざっくり言えば、自然のままの加工していない糖質です。また抗栄養素が少ない食材、炎症を促進するようなグルテンが含まれる小麦や豆類は少なめにした方が良いでしょう。
フルーツも糖質!?
フルーツは糖質が多いという人もいますが、むしろフルーツを沢山食べる人ほど肥満や糖尿病のリスクが低くなるという研究結果があります。
例えば2021年のオーストラリアの研究ではフルーツの摂取量が多いほど血糖値を正常に保つ機能が上がったという結果が出ています。フルーツの摂取量が少ないグループと比較すると1日200g 以上フルーツを食べているグループは、糖尿病のリスクが36%最も下がりました。
また日本でも2019年に御茶ノ水女子大学が実施した研究によるとフルーツを多く食べる人ほど脂肪肝になりにくいという結果が出ています。フルーツには食物繊維やビタミン、ミネラル、フィトケミカルのポリフェノールやカロテノイドなどが豊富に含まれています。
質の高い糖質が含まれる食材
| ベリー類(毎日100g) | 大量のアントシアニンである抗酸化物質は体内の炎症レベルを下げてくれます。冷凍ベリーは安価でアントシアニンの吸収効率が高いためおすすめです。 |
| オレンジ | ミネラルの中で特に重要なマグネシウムが多く含まれ、睡眠の質に大きく影響します。シトラスフラボノイドという抗酸化物質も多く含まれます。 |
| ぶどう | ルテイン、ケアスティンなどフィトケミカルが多く含まれており、抗酸化作用、抗炎症作用の両面で非常に効果が高いです。 |
| パイナップル | ミレラルやフィトケミカルのバランスが良く、中でもプロメラインという抗炎症作用に優れた栄養素です。またパパイヤもミネラルやビタミンが多く含まれ、パパインという独自の成分が抗炎症作用が高い物質であると知られています。 |
| ざくろ | 心疾患、関節痛の予防、腸内環境の改善、抗酸化や抗菌作用など様々なメリットがあります。また甲状腺ホルモン生成を促して代謝アップになるため、肌にも良い効果があります。 |
| さつまいも | 糖質の質を上げるためには、お米や小麦を摂るのを止めて、さつまいもを主食にすると良いと言われています。またジャガイモも栄養バランスが良く、食品満足度も高いことが特徴です。ただし蒸したり、冷やしたりする必要がありあります。特に冷やすとレジスタントスターチという食物繊維が腸内環境を良くしてくれます。 |
食欲が抑えきれない理由
30代や40代の女性で食欲が抑えきないという悩みを持っていませんか。特に30代や40代の女性は、生活の変化、仕事や家庭のストレス、そしてホルモンの変動が大きく影響する時期です。この年齢層の女性は若い頃に比べて代謝が落ちる一方で、食欲のコントロールを難しくする多くの要因に直面しています。
加齢に伴い代謝率は徐々に低下し、30代40代になると筋肉量の減少が始まり、これが代謝の低下を加速させるため以前と同じものを食べても体重が増えやすくなります。さらにこの年齢の女性は妊娠や出産を経験することも多く、これらの経験は体型や体重に長期的な影響を及ぼす可能性があります。
また30代や40代の女性は、更年期に向けてホルモンバランスが変化し始め、エストロゲンとプロゲステロンの変動は気分の波や不安定さを引き起こすことがあり、これが食欲増加につながることもあります。特にストレスや感情的な不安定さを食べ物で慰めようとするエモーショナルイーティングが見られることがあります。
この行動パターンでは、人々がストレス、悲しみ、寂しさ、不安、退屈さ、さらには喜びや祝賀の感情など特定の感情的な状態に反応して食べ物を摂取します。重要なのはエモーショナルイーティングが物理的な飢がからではなく、感情的な需要に答える形で行われる点です。食事を通じて一時的な安心感や慰めを求め、感情的な不快感を和らげようとするものがあります。このようにエモーショナルイーティングは短期的には感情的な不快感を和らげる効果があるかもしれませんが、長期的には様々な問題を引き起こす可能性があります。
例えば体重の増加、食べ物への依存、健康問題、自己評価の低下などが含まれ、また感情的な問題の根本原因に対処せず食べ物でごまかすことで問題がさらに悪化することもあります。エモーショナルイーティングを克服するためには食べる行動の背後にある感情的な原因に焦点を当て、それらを的確な方法で処理することが重要です。これにはストレス管理技術の習得、感情を表現する安全な方法の探求、適切な食事習慣の確立、必要に応じて専門家の助けを求めることが含まれます。感情と食べる行動の間の関係を認識しそれに対処することで健康的な食生活と感情的な幸福を促進することができます。
疲れやすいのは糖質過多
多くの人の疲れやすさの原因は、血糖値の乱高下です。例えば仕事で疲れていたり、ストレスがたまっていたりすると、ついチャーハンやラーメン、甘いお菓子を食べたくなります。白米や麺類、砂糖などの精製糖質を食べると血糖値急激に上がり、その血糖値を下げようとインスリンが大量に分泌されます。その結果、低血糖状態になって眠気や疲労感に襲われます。
糖質の過剰摂取による疲れやすさを改善するためには、精製糖質を控えることが必要です。例えば白米ではなく玄米を食べるだけで血糖値の上昇が緩やかになり、低血糖状態になるのを抑えることができます。また甘いジュースに含まれている果糖ブドウ糖液糖は血糖値の上がり方が非常に大きいため要注意です。
そして疲労のもう一つの原因として考えられるのは摂取した栄養素が、きちんとエネルギーに変換されていないことです。ブドウ糖からエネルギーを生成するのは細胞の中にあるミトコンドリアの働きです。このミトコンドリアがエネルギーを生成するためには三大栄養素の他にもビタミンB群、マグネシウム、鉄が欠かせません。野菜や果物を豆類、海藻類などが不足するとビタミンB群やミネラルが不足するため、いくらエネルギー源となる炭水化物を摂取しても、ブドウ糖からエネルギーにうまく変換できずエネルギー不足に陥ってしまいます。疲れを感じたらまずはビタミンB1の摂取を心がけてください。
2011年のオーストラリアの研究によれば、乳酸が溜まった患者にビタミンB1を摂取することで疲労が改善されたことが認められています。またビタミンB1には糖質やアルコールの代謝を促す役目もあり、精製糖質やお酒を控えるだけでも疲れが取れる可能性があります。ビタミンB1は、玄米や豚肉、うなぎ、鯛、カシューナッツ、大豆、ゴマなどに含まれています。
一方で血糖値の乱高下が激しい人ほど、マグネシウムが不足しているという研究報告があります。マグネシウムは糖質をエネルギーに変換するのに欠かせないミネラルなので、マグネシウムの補給するたにも海藻、わかめ、味噌、納豆、玄米、そば、いわし、あさり、アーモンドなどを食べましょう。またココナッツやMCTオイルに含まれている中鎖脂肪酸は、脳の元気回復に効果的な栄養素です。
寝る前に甘いものを食べたくなったらハチミツ
寝る前に甘いものを食べたくなったらハチミツを舐めましょう。なぜならハチミツには様々な健康効果が確認されています。また寝る前にハチミツを舐めると虫歯になると思われるかもしれませんが、舐めてから寝ることで虫歯や歯周病の予防になることが分かっています。
腸のお掃除効果
単に体を休めるということが睡眠と考えている方も多いと思いますが、むしろ起きている時よりも眠っている時の方が活動が活発な内臓も存在します。その 代表例が腸です。
自律神経には、交感神経と副交感神経の2つがありますが、交感神経は主に体が活発に動く時に、副交感神経は体がリラックスする時に働く神経です。寝ている間、当然体はリラックスしているため、副交感神経が優位に働きますが、胃腸のような消化管の働きを促すという作用もあります。そのため眠っている時は副交換神経が優位になることで腸の活動が活発化します。
そして寝る直前に蜂蜜を食べると、腸が活発化している時間帯に蜂蜜が腸に届いて素晴らしい効果を発揮してくれます。
蜂蜜が持っている具体的な腸の健康効果に、腸のお掃除効果があります。蜂蜜にはオリゴ糖やグルコン酸など腸を綺麗綺麗にしてくれる栄養素が詰め込まれています。これらは腸内の善玉菌の大好物であり、善玉筋は腸のお掃除屋さんの役割を担っています。掃除された腸の汚れは、翌朝に便として体の外に出てくれるでしょう。
美肌になる効果
成長ホルモンは、全身の細胞を生まれ変わり促し、当然その中にはお肌の細胞も含まれています。寝る前一般の蜂蜜によって成長ホルモンが分泌されれば、肌の奥で新しい細胞が作られ、皮膚のターンオーバーが正常化し、それによって寝ている間に美肌になっていくことが可能です。さらにお肌は日々紫外線や乾燥に晒されることで錆びますが、蜂蜜はこの錆を取ってくれるポリフェノールによる抗酸化作用があります。また蜂蜜には、ビタミンB群やミネラルなどお肌の再生に必要な栄養素が詰め込まれています。そして、寝る前一杯の蜂蜜には、寝ている間の血流を促進する効果もあり、蜂蜜を摂ることでビタミンやミネラルが血流に乗ってお肌に運ばれ、どんどん肌 が元気になっていきます。
特に蜂蜜が持っている効果に美白効果があります。年を取ると細胞に色素が沈着し、全身が黒ずんでしまいますが、研究によって蜂蜜が持っているプロリンというアミノ酸がメラニンの生成を抑えてくれることが分かっています。
口の中の虫歯菌を退治する
寝る直前に蜂蜜舐めても虫歯になりませんか、と疑問を持っていると思いますが、むしろ寝る直前に蜂蜜を舐めてから寝ることで虫歯や歯周病の予防になることが分かっています。
虫歯の原因となる糖は、ショ糖と言い、お菓子などに含まれている砂糖の主成分です。一方で蜂蜜に含まれるのは、そのほとんどが果糖とブドウ糖です。これはミツバチが採取した花の蜜であるショ糖が巣の中で全て分解されてしまうからです。そのため蜂蜜には殺菌作用があり、歯磨きの後に蜂蜜を舐めるのはむしろ虫歯予防になると言われています。
ちなみに消毒液のオキシドールですが、これは天然にも存在し、微量ですが蜂蜜にも含まれていることが分かっています。オキシドールは殺菌効果があるため、夜寝る前に蜂蜜を舐めることでそこに含まれるオキシドールが口の中の雑菌を除菌してくれます。
さらに蜂蜜には口の中の善玉菌を増やしてくれるという効果もあります。虫歯は口の中の代表的な悪玉菌であり、逆に蜂蜜によって口の中の善玉菌を増やすことで、虫歯や歯周病になりにくくなります。
甘いものを食べたい時はビタミンC
働いてクタクタになって家に帰ってきた時や体を動かして疲れ時など甘いものが食べたくなります。仕事の合間や帰宅後にチョコレートやクッキーなどの甘いものを食べる習慣がある人も多いでしょう。ですが甘いものを食べてもなんだか物足りなくて、チョコレートを一袋食べてしまったなどがよくありませんでしょうか。実は甘いものを食べても、甘いものへの欲求が止まらないどころか、さらに甘いものを食べたくなるのは、体が本当に欲しているのは糖分ではないことが原因と考えられます。
1900年代まで砂糖は非常に貴重なものであり、庶民が甘いものを食べたい欲求を満たしていたのは、主に果物です。もっと時代を遡って、原始時代の生活を考えてみても疲れた人の欲求を満たしてくれたのは果物でした。つまり人は何千年も何万年も、疲れて甘いものを食べたくなった時に食べていたのは果物です。
ここで重要なポイントとなるのが、果物にはビタミンCがたっぷりと含まれていることです。果物を食べれば、果糖と一緒にビタミンCを摂取することができます。つまり人間の脳は甘いものが欲しいという信号を送れば、ビタミンCを摂取することができるということを本能レベルで理解しているのです。
そのためビタミンCが欠乏している時、人は甘いものが食べたくなります。ビタミンC は、体内で疲れを引き起こす活性酸素を抑える役割を持っています。またビタミンCは免疫機能にも作用するため、疲労を感じている時や体調不良の時にも摂取したいビタミンです。
このように甘いものを食べたくなる時の本質的な欲求は、エネルギー源となる 糖分ではなく、疲れを回復してくれるビタミンCです。しかし現代は、甘いものといえば果物ではなくチョコレートやケーキなどのお菓子を想像してしまいます。甘いものを食べれば快楽を感じさせるドーパミンが分泌され、脳は一時的に満足して満たされた気持ちになります。しかしビタミンCが補給されないため、体は引き続き甘いものを要求します。その結果、甘いものを食べても、もっと甘いものが食べたいと言う甘いものへの欲求が止まらなくなってしまうのです。
そもそも糖分を摂取すると血糖値が急激に上がるため、血糖値を下げるためにインスリンが分泌されます。そうすると急激に血糖値が下がって結果として、低血糖状態に陥ります。低血糖状態になるとイライラや不安、疲れ、だるさなど心身のあらゆる不調を感じるようになります。そして低血糖状態の体は、エネルギーを求めてまた甘いものを欲しくなるという負のスパイラルに陥ります。
最低限の糖質で痩せやすい体へ
ただし、糖質制限といってもお米を減らして野菜を多く摂る場合と、肉を主食にする場合は全く糖質制限の質が違います。このような質が考慮されていない研究という側面がありますが、いずれにせよ質の高い糖質を摂ることが大事なことになります。つまり糖質制限ではなく、糖質厳選することが重要であり、糖質制限では必要な栄養素が不足することが問題なのです。
ダイエットで体が飢餓状態になると、脂肪がエネルギーとして燃やされます。さらに追い込まれると老化した細胞や体に残った必要のないものが燃やされてエネルギーにしようと働きます。ここにアンチエイジング効果があり、この時点で食べ物を補給すれば、新しく細胞を生成するターンオーバーが活性化して美しいお肌が保てることになります。
このようなオートファジーによる細胞活性化するためダイエット(断食)するわけですが、ここで酵素ジュースや野菜ジュースを飲んでも意味がないことが分かるでしょう。
最高の食材はジャガイモ
ジャガイモには、睡眠の質や腸内環境を改善、免疫力アップによるアレルギーの改善などに効果があると言われています。ジャガイモに含まれる糖質と食物繊維(レジスタントスターチ)が腸内環境を改善し、免疫系が改善するため睡眠の質を上がり、体内の脂肪が燃えやすい状態をつくってくれます。実は睡眠の質には免疫系の問題が多く関わっているという指摘が多くあります。
腸内環境を改善するレジスタントスターチは腸内細菌のエサになり、酪酸と言われる短鎖脂肪酸を生成します。この酪酸が免疫を改善し、体内の炎症を抑えてくれる役割を果たします。つまり睡眠の質だけでなく老化対策になるのではないかと考えられています。
この酪酸は腸のバリア機能、リーキーガットを抑えてくれて、食後の血糖値、インスリンの上昇を抑え、血糖値を安定させる効果があると考えられています。
また、ジャガイモはリーキーガットの原因になるレクチンという物質が含まれていることやGI値が高い食べ物として知られていますが、ジャガイモの食べ方でこれらのデメリットはなくすことができます。
茹でたジャガイモは、血糖値の上昇が抑えられ、さらに冷やすとレジスタントスターチ量が増えます。ただしオーブンで焼くとGI値が100まで上がることが分かっており、揚げるのもNGです。また必ず良質な油(オリーブオイルなど)と一緒に摂ることで、GI値が下がり、緑葉色、葉物野菜と摂ると糖質の吸収を緩やかにしてくれます。
タンパク質で食欲を止める
甘いものが食べたい!でも食べて後悔したくない。意志力で食欲をコントロールすることは難しいですが、そこでタンパク質をしっかり摂取することで食欲が止めることが最も効果的であると多くの研究者が語っています。
特に加工食品をいつも食べている人は、ついつい味が濃いものばかりを好み、味が薄い食品を遠ざけてしまっているのではないでしょうか。この味覚刺激から逃れるための方法は、タンパク質の摂取量を増やすことです。
人間というのは本来タンパク質が足りなくなった時に食欲が掻き立てられ、その風味や味への渇望を感じるようにできています。ですが私たちはタンパク質への欲望を塩辛いポテトチップスなどで満たしてしまっているわけです。
本来しょっぱいものが食べたくなったり、甘いお菓子が食べたくなったりした時に、体が欲しているものはタンパク質です。つまりタンパク質を意図的に十分量を摂取することによって、こういった欲を自然と収めることができます。
タンパク質は空腹ホルモンのグレリンを低下させ、満腹ホルモンであるペプチドYYのレベルを高めて食欲を満たしてくれます。ついつい沢山食べてしまうお菓子や白米は、タンパク質がほとんどなく、いつまでも食欲が満たされないからです。私たちの食欲をコントロールしているのは、タンパク質をどれだけ食べたかによります。例えば肉や魚、卵や豆類はタンパク質が豊富なため、ある程度食べると食欲がなくなります。タンパク質を摂らない限り、食欲はなくならないことを憶えておきましょう。
同様に甘味に関しては、甘味を欲している時はビタミンCが不足している場合が多いと言われています。これはもともと甘い食べ物が食べたいという時には、 果物を食べることによってビタミンCを補給してきたからです。
運動で食欲を止める
運動は糖質中毒から抜け出すために非常に有効な手段です。運動することで糖質への欲望を抑えてくれるエンドルフィンと言われる脳内物質が放出されます。運動をした後に、甘いジューズやアイスクリームなど食べようという気にならないことを確かに経験したことがあるかと思います。甘いジューズやスイーツを食べたいと思ったら、すぐに運動すればその欲望は薄まり、または完全に消えていることでしょう。
お酢で食欲を止める
甘いものを食べたくなったら、コップ一杯の水に大さじ1の酢を入れて、甘いものを食べる前、もしくは食べた後直ぐに飲んでみましょう。酢は甘いものを食べた後に血糖値スパイクとインスリンスパイクを小さくする効果があります。さらに酢は甘いものへの渇望を抑えて、空腹感を和らげ、脂肪を燃焼しやすくなるという働きも期待できます。
酢の健康へのメカニズムも最近の研究で明らかになってきており、1つがデンプンをグルコースに分解するα—アミラーゼという酵素の活動を抑制することです。そのため摂取した糖やデンプンがゆっくりとグルコースに変わるため、急激に血中にグルコースが流れることを防いでくれます。これは食物繊維の持つ役割と同様です。
2つ目が酢酸は血流に入ると筋肉に入り込み、通常よりも早くグリコーゲンをつくるように筋肉に促します。つまり血中のグルコースが効果的に筋肉に取り込まれるので血糖値の急上昇を防いでくれます。最後が酢酸は、ミトコンドリアが脂肪を燃やすようにDNAに命じてプログラムを少し変更させます。これら3つの働きによって甘いものを食べる前に飲むと、血糖値スパイクを抑える他、ダイエット効果も期待できます。
甘いものを抑えるツボ
脾が弱ると身体は自然と甘いものを欲して食べたくなりますが、チョコレートなどの嗜好品を選んでしまうと身体の中に『湿』が溜まり、身体が重だるく、そしてむくみやすくなってしまいます。 そんな時には、慢性的な胃もたれ・膨満感、甘い物の過食などの症状がある方におすすめするツボです。
太白(たいはく):足の親指の付け根にある太い骨(中足指節関節)の内側で、膨らみの後ろの陥凹部
親指の腹でツボを気持ち良いと感じる強さで押してください。

消化器の働きを高めるほか、余分な湿を取り除く、内出血が出やすい・鼻血・血尿・不正出血など血液が漏れ出さないよう保持する力を高めることができます。
ぜひ知識を持って自分の大切な身体を癒やしてあげてください。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。