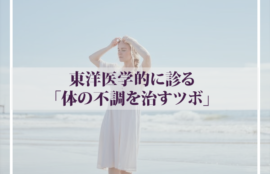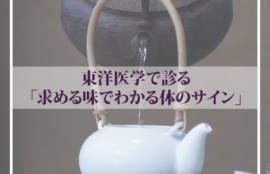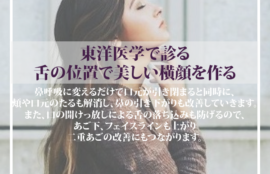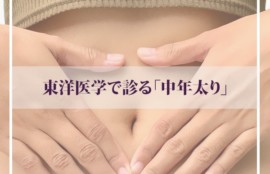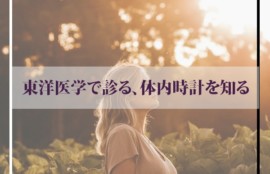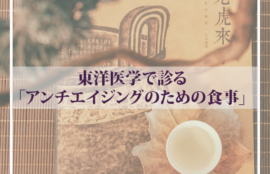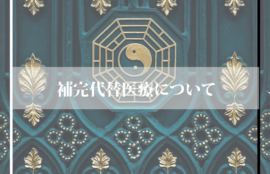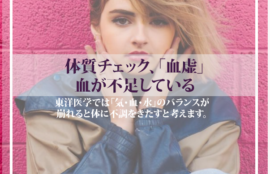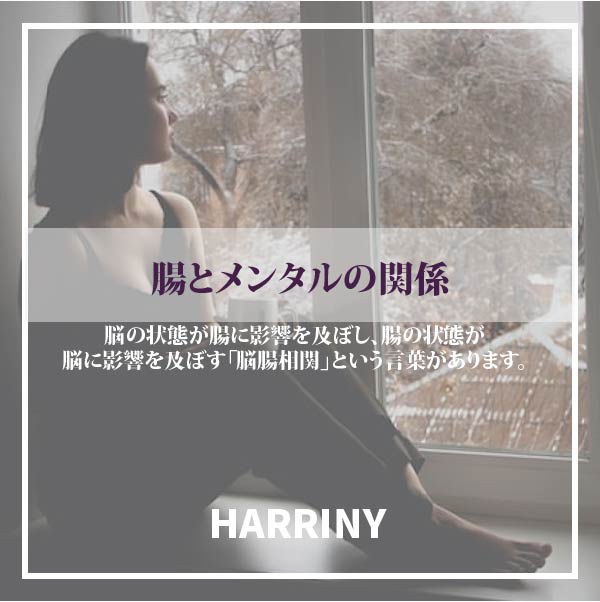
健康とは、肉体的な健康と精神的な健康が保たれている状態です。自分らしく生きるためには、身体と心の健康を保つことが重要です。そして心の健康が肉体的な健康に及ぼす影響が大きく、その健康を保つ重要性が高まっています。
メンタルの健康の重要性
肉体的な健康に対して、メンタルの健康への意識は疎かになりがちです。メンタル的な健康は、肉体的な健康に対して、目に見えないし、症状も分かりにくく、気づきにくい特徴があります。また強いストレスやメンタルの状態が悪くなると食生活が乱れる傾向にあり、加工食品などで手っ取り早く食べることで食事を済ませることになります。
こういった食事は、中毒性が高く、脳内のドーパミンをお手軽に増やすことができます。特に甘いお菓子などは、脳内のセロトニンを一時的に増やすことができ幸せな気分になるという状態になりますが、その後さらに気分が凹むことになり、長期的に見れば肉体的な健康に悪影響を与えてしまいます。
アメリカ栄養士協会によると、人々は落ち込んだり、ストレスを感じたりすると食べ過ぎてしまう傾向があると分かっています。ストレスで暴飲暴食してしまうことは経験上理解できると思います。このようにメンタルが悪化すると食生活が乱れ、ますますメンタルが悪化するという悪循環を生じてしまいます。さらには眠れない、寝付けない、夜中途中で目が覚めるなどのように睡眠にトラブルを抱えている状態になりメンタルに悪影響を及ぼす負のサイクルが始まってしまいます。
不安になりやすいのは脳の構造にある
そもそも女性は不安になりやすい傾向があり、その理由は脳の構造の違いにあります。私たちは不安を感じると脳からCRHというホルモンが分泌されますが、男性よりも女性の方がこのホルモンへの感受性が強くストレスを感じやすいと言われています。これは赤ちゃんを産む女性は外敵に襲われるリスクを避けるため、長い年月をかけて進化した結果でもあります。
また、女性は生理によって大量の血を失い貧血になります。血の主な材料は鉄分ですが、鉄分は幸せホルモンのセロトニンを作り出すための不可欠な物質でもあるため、生理及び貧血によって鉄分が不足するため、この幸せホルモンが少なくなって不安感が強くなってしまうのです。逆に血流を改善することで貧血を改善して幸せホルモンを産生して不安を和らげることができます。
また、自分自身を後回しにして他人の都合を優先してストレス溜め込んでしまう傾向が多くあります。ストレスが溜まると、自然と体が緊張して、常に肩や首に力が入り血流が悪くなり体のこわばりやこりに悩まされます。
腸内環境と便秘とうつ
腸内細菌は脳に影響を与えて、精神においても影響を与えていると言われています。脳と腸は自律神経やホルモンを介して互いにつながっています。そのため腸に何らかの異常があると結果として、脳に対しても悪影響が生じてしまいます。
実際、便秘とうつ病が併発しやすいことが分かっています。便秘が続いていることは腸内環境が悪化しているということになり、腸内環境の悪化がうつ病を引き起こしていると考えられています。また逆に、うつ病になると自律神経の活動力が落ち、その結果腸の働きが低下し、便秘になってしまうという場合もあります。
このように脳と腸は相互に関係し、影響し合っています。さらに腸内細菌の状態が脳にまで影響を起こし、感情や性格を左右することを示した研究もあります。実際セロトニンやドーパミンといった脳の神経伝達物質は、腸内細菌によって作られていることが分かっています。つまり腸内細菌のバランスが乱れは、これらの神経伝達物質の生産が乱れてしまい、感情や性格にまで影響を及ぼすわけです。さらに便秘がちで腸内環境が悪化している人は、物忘れが増加したり、記憶力が低下していることも明らかになっています。
一方で加工食品の摂取が増えたり、ストレスが多い生活を送っていると腸内環境が悪化していきます。そしてリーキーガットと称される状態に陥ってしまいます。リーキーガットとは腸の壁が破損し、普段通過させない物質が体内に入ってしまう状態のことです。リーキーガットは腸の細胞に微細な開口部が生じる現象で、腸内で食物を消化し、吸収する際に必要な栄養素だけを通すバリア機能がうまく機能しなくなる現象です。
通常、腸の粘膜は細菌や食物の不純物を防ぐバリアとして働いていますが、バリアが弱まると体内に有害な物質が入ってきてしまいます。リーキーガットが発生すると、これらの微細な開口部から消化されていない食物やエンドトキシン(内毒素)などが血流に浸透します。
エンドトキシンは特に悪玉菌が産生する有害な物質で、これが血流に入ることは体にとって非常に良くない状態です。これに対して人体は免疫システムを活性化させ、体内の多くの領域で持続的な炎症を引き起こします。体は有害物質を攻撃しようとして免疫反応を起こしますが、これが過剰になると炎症を起こし、それが慢性化すると健康に悪影響を及ぼします。
この状態に陥ると健康的な生活を心がけていても、体内の炎症が持続しているため、通常の健康維持の努力だけでは抑えることが難しいとされています。例えば野菜を摂取したり、毎日8時間の睡眠をとっても腸内環境が悪いままだと、 腸の防壁を突破した有害物質が体内で暴れ続け炎症は治まりません。リーキーガットの場合、根本的な腸の問題が解決されない限り、体中で巻き起こっている炎症を止めることはできません。
リーキーガットはアレルギーや認知機能の衰えなど、多くの症状を引き起こしますが、特に注目すべきは疲労感との相関です。リーキーガットにより体内の炎症が起こると体が常に戦っている状態になり、これが人を疲れやすくします。 現代社会では解明されていない疲労に悩む人々の数が急増しており、その正確な数字は不明ですが、厚生労働省の調査では回答者の38.7%が慢性的な疲労感を報告しています。
実際こういった現代人が経験する未解明の疲労は、複数の研究において腸内細菌と深く関連していることが明らかになっています。腸内細菌のバランスが崩れたり、リーキーガットが起こると、精神的健康、特に疲労感に関連していることが示され続けています。これはリーキーガットの影響で体内に侵入した毒素が脳に到達し、そこで激しい炎症が生じることが不安、抑うつ症状および疲労感の増加につながっているのではないかと考えられています。
食事とメンタルの関係
肉体的な健康だけでなく、メンタルの健康のためにも食べ物は大変重要です。メンタルの調子が悪い場合、栄養をしっかり摂ることが大切です。例えば鉄を補うことで、メンタルの調子が改善することも多くあり、その場合は単に栄養素が不足していたことになります。
栄養は、ただ沢山食べれば満たされるものではありません。ただ食べれば栄養が得られるわけではなく、沢山食べても必要な栄養素が不足してしまうと体は 栄養失調の状態になります。精神的に不安定な人々の中には、この状態に陥っている人が少なくないと言われています。
このように体を分子レベルでチェックして、細胞が正しく働くように整えて、病気を防ぎ、老化を遅らせるようにするのが「オーソモレキュラー栄養医学」です。栄養素がきちんと取れているかを血液でチェックして足りないものを補っていくものです。
このように食事や栄養素がメンタルに大きく関係しており、幸せホルモンのセロトニン、やる気のドーパミン、安らぎのオキシトシンは全て肉や魚や豆に含まれるタンパク質からつくられます。つまりイライラ、不安、無気力は単にタンパク質が不足しているのです。
小麦の糖質とグルテン
糖質の中でも特に小麦は脳や体に対して悪影響の多い食材です。その理由は、血糖値に悪影響を与えるからです。精製された小麦から作られた食品は、お米よりも急激に血糖値を高くすることが分かっています。
血糖値の急激な乱高下は、血管を傷つけたり、動脈硬化の原因となったりするリスクの高い現象です。もちろんこの乱高下はお米でも起きますが、それ以上に小麦では起きやすいです。
さらに小麦には、タンパク質からできたグルテンと呼ばれる成分が含まれています。グルテンは良い食感を食品に与えてくれますが、その粘り気ゆえに消化しにくく腸粘膜を炎症させやすいことが分かっています。
この腸粘膜の炎症が、いわゆるリーキーガット症候群で、腸の粘膜に損傷ができて、腸内にあるべき物質が腸から漏れ出してしまいます。このリーキーガット症候群は様々な疾患の原因ではないかと考えられています。
実際、小麦を食べるとその直後にお腹が張ったり、頭が鈍くなったりすることを実感する方が多くいらっしゃいます。お腹が張るというのは、腸内環境が悪化している現れです。そして腸内環境が悪化することで、セロトニンなどの脳に必要なホルモンの産生も減ってしまうと考えられています。
メンタルに良い食べ物
メンタルは食べるものによって非常に大きな影響を受けます。特に腸内環境を整える上で、おすすめが以下の食べ物です。
- プレバイオティクスとプロバイオティクス
- クルミ
- 全粒穀物
プレバイオティクスとプロバイオティクス
プレバイオティクスは、ビフィズス菌などの有用菌の餌になり腸内環境を整えてくれる食品のことです。代表例はオリゴ糖(玉ねぎ、アスパラガス、バナナ、大豆)や水溶性の食物繊維(果物と野菜、きのこ、豆類など)です。
プロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善することにより、人に有益な作用をもたらす生きた微生物を含む食品やサプリのことです。例えばヨーグルト、キムチ、みそ、納豆などの発酵食品で、乳酸菌、ビフィズス菌、酵母菌、麹菌など有用菌が含まれる食べ物です。定期的に食べるのが難しい場合は、ビオフェルミン、ラクトーンA、ラクトビフィプロバイオティクスといったサプリを活用しましょう。
まずプレバイオティクスで腸内菌に餌を与えて、腸に良い菌を増やしつつ、プロバイオティクスで生きた腸に良い菌を届けてあげることで腸内環境を整えましょう。
クルミ
ナッツの中でも特に健康効果が高いのがクルミです。ナッツとクルミは不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、この不飽和脂肪酸によって不安を感じる可能性が低いことが分かっています。
全粒穀物
全粒穀物の摂取量を比べた研究があり、適量な量を食べている女性は、少ない女性に比べて不安を感じる可能性が低いことが明らかになっています。一方で白米、パン、白麺、焼き菓子といった精製された穀物を摂取した女性は不安を抱える可能性が高くなることが分かっています。
全粒穀物は精白などの処理で、糖となる果皮、種皮、胚、胚乳表層部といった部位を除去していない穀物やその製品のことです。代表例は玄米、全粒粉パン、十割そば、全粒小麦、オーツ麦、オートミール、全粒ライ麦、キヌアなどです。
また全粒穀物はメンタルへの良い影響だけでなく、健康寿命を延ばす効果が分かっています。イギリス医師会雑誌に発表された論文によると、全粒穀物の生活習慣病に対する影響を調査した結果、心臓病やがんなどの発症率または感染症などの病気による死亡のリスクを減らすことが証明されています。この研究によると、1日90g以上の全粒穀物を食べることで、心臓血管系の病気は役20%減少し、全てのタイプのガンは約15%減少していることが分かりました。
これは全粒穀物に含まれる食物繊維、ビタミン、ミネラルによるものと考えられています。日本の玄米はおにぎり一個で約90gなので気軽に摂取できます。
全粒穀物のデメリット
パスタや白米などの精製穀物は高GI食で体に悪いというのが一般的ですが、現在では少しずつですが精製穀物の価値が上がってきている現状があります。
全粒穀物は外側の糠や胚芽が取り除かれていないので一見、体に良さそうに見えます。しかし市販されている全粒粉を使ったクラッカーやマフィンなどは、粉にするために細かく挽かれており、全粒穀物の持つ健康効果がほとんど失われています。また低GIというメリットも、血糖値の上昇速度も細かく砕かれたものでは精製穀物とほぼ変わらないことが分かっています。さらに細かく挽くことで、穀物に含まれる天然の油の酸化スピードが速まり、健康に害を及ぼすこと示されています。
日本人にとって未精製穀物の代表は玄米ですが、玄米にもデメリットがあります。食物は元来、動物から食べられないように毒素を持ちます。その毒素は適量であれば健康効果が高いものもあり、一方でマイナスの影響しか与えないものもあります。こうした毒素は外側な糠やふすまに含まれており、精製の過程で取り去ることができます。また玄米の糠には土壌汚染の影響で大量のヒ素が含まれていることがあります。ヒ素は肝臓と腎臓に悪影響を与え、デトックス機能を破壊することになります。玄米は栄養素の面では白米より優れているものの、良い栄養に加えて植物毒や重金属といった悪い栄養の含有量が多いことが欠点になります。
他にも全粒穀物のデメリットとして、ビタミンDの体内値を低下させることや、オメガ6脂肪酸による酸化、炎症レベルを高めることも挙げられます。もちろん栄養素が多く含まれるメリットがありますが、それを上回るデメリットがあることを理解するべきです。事実世界を見ると、日本を含めた長寿国のほとんどが主食として精製された炭水化物(白米、パスタなど)を食べており、全粒穀物を滅多に食べていません。
メンタルと睡眠
睡眠の質が低下するとメンタルにも大きな影響を与えます。睡眠不足だと不安になったり、イライラが止まらなかったり、感情の起伏が激しくなるのは、脳の扁桃体が睡眠不足で制御できなくなるからです。睡眠の質を向上させるためにメラトニンは導入を考えてみる価値はあるサプリです。
栄養素は食事から摂取することが基本ですが、メラトニンサプリは睡眠の質の向上に大変役に立たちます。睡眠の質が悪い人は、ホルモンバランスが乱れ、食欲ホルモンが過剰に分泌されており、暴飲暴食で身体を健康に保つことができていない方が多くいます。
メラトニンは、脳の松果体において生合成されるホルモンの1つであり、健やかな眠りにとても重要であると言われています。メラトニンがしっかり分泌されていれば、睡眠の質が向上し、寝つきが良く、中途覚醒が少なくなります。さらにメラトニンは、多くの慢性疾患において抗炎症作用を発揮してくれるということを示す研究も数多くあります。
怪我をすれば傷を治すために急性炎症が起こり、一方で炎症状態が持続する慢性炎症は、生体組織の機能や構造に異常が起こり、様々な疾患の原因になる炎症です。また老化もこの慢性的な炎症によって進行するのではないかと考えられています。また学習能力や記憶力、注意力を損なうことも分かっています。2017年にカロリンスカ研究所のチームが行なった約5万人を対象とした調査では、謎の体調不良を抱えている人は、体内の炎症レベルが高いということが分かっています。
この慢性炎症が引き起こる原因に睡眠不足があります。研究では毎晩6時間以下の睡眠で1週間を過ごした場合、炎症や免疫系、ストレス反応に関連する711個の遺伝子の発現に影響が出たとの報告があります。一方で内臓脂肪も慢性炎症の原因と言われています。内臓脂肪は内臓の毛細血管近くにあり、脂肪が分泌した炎症物質は血液を通して全身に巡ってしまいます。
睡眠が不足しがちな方は、メラトニンを摂り入れることで、睡眠の質の向上や体内の炎症を抑えるという効果が期待できます。もちろん睡眠時間を確保して、サプリを頼る前に生活改善をすることが大切で、あくまで補助としてのサプリを使いましょう。
残念なことにサプリを利用する場合は、日本のドラックストアなどで販売されていないため海外サイトから購入するしかありません。メラトニンは5mg以下であれば耐性もつきにくく副作用が出る可能性も低いと言われていますが、0.3mg程度からスタートして効果がなければ少しずつ増やすことにしましょう。また既に不眠症などで通院されている方は必ず担当医師に相談してから検討して下さい。
自律神経と更年期の関係
自律神経の乱れも更年期も女性ホルモンのバランスが崩れることによって心身に様々な不調を引き起こします。特に心身に悪影響があらわれる状態が「更年期障害」と言われるものです。一方で「自律神経失調症」と「更年期障害」の症状はよく似ており、いずれも女性ホルモンのバランスの崩れから、自律神経のバランスも崩しやすくなります。このように自律神経と女性ホルモンは、お互いに影響を受けやすい関係にあると言えます。
この女性ホルモンの中でも、エストロゲンというホルモンは40代半ばから急激に減少するため、更年期に大きく影響します。さらに大きく「ゆらぎ」ながら減少するため、脳が混乱して自律神経が乱れ、ホットフラッシュ、イライラ、憂鬱などの典型的な自律神経失調症状を引き起こします。
この「ゆらぎ」は、脳から卵巣にエストロゲンを分泌する指令されますが、たくさん分泌できる日とできない日があり、そのギャップにより生じます。「ゆらぎ」は30代後半から始まり、まず月経の乱れがあらわれます。そして更年期になれば、誰にでも女性ホルモンの急激な減少がみられ、症状が軽い方もいれば、日常生活に支障をきたすほど強くあらわれる方もいます。
ホットフラッシュを改善する食生活
更年期を迎える女性に現れる症状として、ホットフラッシュがあります。例えば周りは暑く感じていなくても、自分だけ暑く感じたり、汗を感じてしまう症状です。このホットフラッシュは食生活を気をつけることで改善することが知られています。
少なくとも1日2回程度の中等度から重度のホットフラッシュの自覚がある84人の閉経後の女性を対象とした研究があります。この中で食生活に介入を行うグループと、通常の食事のままのグループに分けられ、前者の方には低脂肪のビーガン食とし、動物由来の食品は避けて油やナッツ、アボガドなどの脂肪分の多い食品は最低限に抑え、食事毎に半カップ約86gの大豆を食べるように指示されました。
結果として、ビーガン食としたグループのホットフラッシュの頻度が12週間で78%減少しました。この結果からホットフラッシュには、動物性脂肪が関連していることが考えられ、特に更年期症状が強く出る場合には、動物性脂肪を減らすことが効果が高いと考えられています。
メンタルに良い栄養素
メンタルにおすすめ栄養素は以下の3つです。
- タンパク質
- コレステロール
- ビタミンB6
メンタルとタンパク質
こころの不調の原因がタンパク質不足にあるとも言われています。髪や皮膚、筋肉や骨、ホルモンや酵素免疫に関わる抗体でさえその材料はタンパク質であり、また脳内神経物質を作る大元の栄養素もタンパク質でできています。タンパク質が不足するとメンタルに影響が出るのは、セロトニンが不足してしまうからです。うつなどのメンタル疾患の多くはセロトニンの不足であると考えられています。また間違ったダイエットでタンパク質を摂らない生活を長く続けた結果、ダイエットに成功したにも関わらず気分が落ち込んでしまうこともあります。
セロトニンはトリプトファンというアミノ酸で脳内でつくられており、セロトニンが不足すると不安や抑うつ症状が出ます。つまりトリプトファンが足りなくなると十分なセロトニンが作られません。トリプトファンをつくるためにはアミノ酸の一種であるタンパク質を摂る必要があります。トリプトファンを多く含む食材は、大豆製品、卵、肉類、カツオ、マグロ、サンマなどの赤身肉の魚、ナッツ類です。またこのトリプトファンは睡眠ホルモンのメラトニンの材料にもなります。
メンタルとコレステロール
2015年に厚生労働省はコレステロールの食事での摂取制限を撤廃しています。実はコレステロール値が私たちの精神状態に大きな影響を及ぼしています。コレステロールは、細胞を守る細胞膜やホルモンをつくる材料であり、神経細胞や脳細胞もコレステロールを多く含んでいて必要なものです。
私たちの体にあるコレステロールの3分の1は脳にあると言われ、このコレステロールの割合が低くなると、脳の活動も低下してうつや認知症が引き起こされることが分かってきています。このコレステロールはセロトニンを脳まで運搬することを担っており、コレステロールが低下するとセロトニン不足になりうつなどになってしまうことになります。
コレステロールを多く含む食材は、肉類です。栄養の面から見れば野菜中心になるとタンパク質不足に陥っていることが多く、肉類も食べてバランスの良い食事を心掛けましょう。
一方で鉄不足もメンタルの不調を引き起こすことがあります。鉄分は、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン、メラトニンなどの脳内神経伝達物質の合成に欠かせない栄養度であり、鉄不足によってこれらの物質の機能を低下させてメンタルの不調につながります。特に女性は生理があるため、鉄分を意識して食べ物から摂取しましょう。
メンタルとビタミンB6
鉄分と並んで現代人に不足しているのがビタミンB群です。特にビタミンB6がメンタルの健康にとって非常に重要なビタミンです。ビタミンB6は脳内神経伝達物質を合成するために重要な栄養素であり、セロトニン、ドーパミン、GABAを合成するにもこのビタミンB6が必要です。GABAはγ-アミノ酸と言い、これが不足すると不安やホットできないことが多くなると言われています。にんにく、唐辛子、ゴマなどには、このビタミンB6が多く含まれているため、メンタルの安定に欠かせない食べ物です。
不定愁訴と自律神経
不定愁訴と自律神経には密接な関係があります。自律神経の乱れが様々な体の乱れにつながり、代表的な症状として、以下の症状が挙げられます。
- 慢性的な睡眠不足(不眠)
- 急な動悸・胸のしめつけ
- 慢性的な首肩コリ
- 集中力の低下
- 不安な気持ちに襲われる
- 些細なことでイライラする
- 感情の起伏が激しい・抑えられない
- ちょっとしたことでひどく落ち込む
- 季節に関係なく手足が冷える
- 体が重だるく疲れがとれない
- 耳鳴りや頭の重さを感じる
- しびれを感じる場所がある
自律神経を整える鍼灸治療
自律神経の乱れが、頭痛、不眠、首肩こり、婦人科系の疾患などの様々な不調の原因になります。自律神経は意識してコントロールできない呼吸、代謝、消化を調整する役割がありますが、加齢、ストレス、生活習慣などからホルモンバランスが乱れ、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
特に女性は生理に伴い、女性ホルモンのエストロゲン分泌量が大きく増減するため、自律神経のバランスも崩れやすくなります。また自律神経のバランスが乱れると、女性ホルモンのバランスにも影響して、生理前後の不快な症状を悪化させることもあります。
女性ホルモンの減少で起こる様々な症状を、総称として不定愁訴(ふていしゅうそ)と呼びます。その代表例が自律神経失調症状であり、上半身が急に熱くなる(ホットフラッシュ)や発汗などが挙げられます。
そのほかにも肩こり、腰痛、皮膚の乾燥、手のこわばりなどもよくみられます。さらに社会的・心理的なストレスも重なり、情緒が不安定、気分の落ち込みなどが誘発するケースもあります。不定愁訴と自律神経には密接な関係があり、自律神経の乱れが様々な体の乱れにつながります。代表的な症状として、以下の症状が挙げられます。
| 肩こり | 肩こりを改善することで、不定愁訴の症状が改善することあります。肩こりがあると自律神経のバランスが働きにくくなります(頚髄と呼ばれる脳から続く脊髄)。 肩こりは、スマホやパソコンなどで前傾姿勢になり、筋肉の負担が増え、血流の流れやリンパ液の流れも悪くなることから生じますが、その症状はゆっくりのため、肩こりが原因で起きている症状ではないと、見過ごされている事が多くあります。 鍼灸治療で血液循環を促進して、深部のこりを緩めていくことが症状緩和になります。 |
| 頭痛 | 特に40代以降に起こる頭痛は、脳血管の血管壁の痙攣や収縮によって起こっているのではないかと考えられています。またエストロゲン分泌量の減少が関係しているとも言われています。 頭痛の症状は様々ですが、目の疲れが伴う場合には、頭の鍼が症状の緩和に効果的です。 |
| のぼせ・ほてり・発汗 | ホットフラッシュは、不定愁訴の代表的な症状のひとつです。自律神経のバランスが崩れ、血管の収縮・拡張のコントロールが上手くできなくなることが原因です。 一方で頭部は熱を持つものの、足元は冷えている方も多く、その場合はのぼせと冷えを同時に治療することができる鍼灸治療が効果的です。 |
| 不眠 | 女性ホルモンのエストロゲン分泌量が大きく増減するため、自律神経のバランスも崩れやすくなります。その結果、寝つきが悪くなる、眠りが浅い、夜中に何回も目覚めるといった症状があらわれます。 鍼灸治療によって自律神経の乱れを鎮めて、全身調節を行うことによって、身体のリズムを正常な状態に取り戻すようにします。そのため鍼灸治療をした夜はぐっすり眠ることができたという方が多くいらっしゃいます。 |
| イライラ・うつ状態・不安感 | イライラしたり、不安になったり、怒りやすくなるなどの感情の起伏が大きくなるのも不定愁訴の症状のひとつです。これはホルモンの変化やゆらぎが大きく感情の起伏に影響しているからと言われています。 鍼灸治療では、自律神経の乱れを整えて、副交感神経を少し優位にすることで感情のコントロールができるように導いていきます。 |
| 動悸・息切れ | 動機・息切れは、エストロゲンが大きく「ゆらぎ」ながら減少するため、脳が混乱して自律神経が乱れることで起こります。 鍼灸治療によって、呼吸に関係する筋肉(胸鎖乳突筋や肩甲骨内側の筋肉)を調節することで、自律神経を整えます。 |
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。