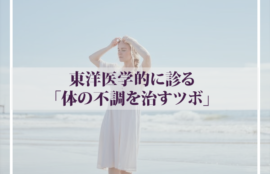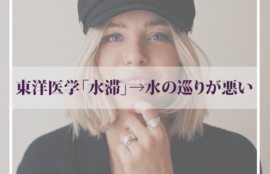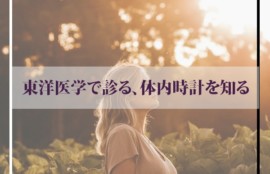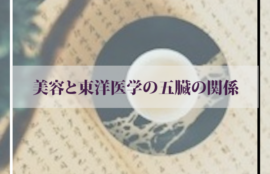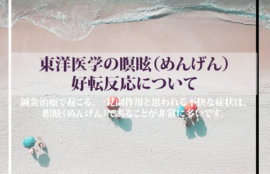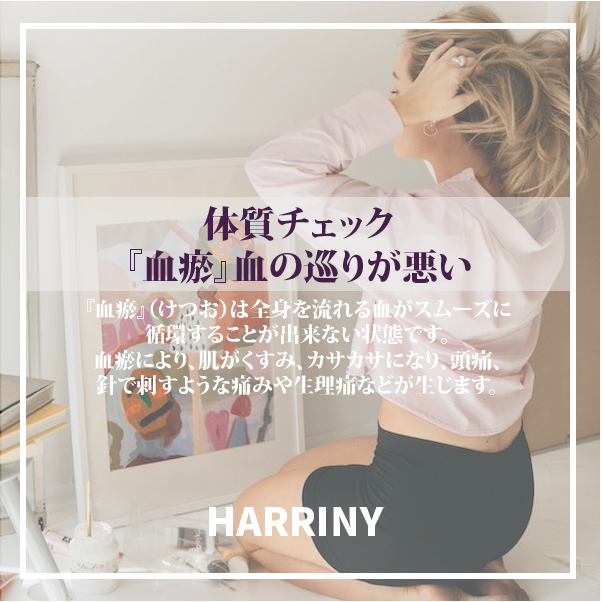
こんな症状ありませんか?
- シミ・そばかすが多い
- 顔色がくすみやすい
- アザができやすく治りにくい
- 肩こりになりやすい
- 肌が乾燥しやすい
- 足の表面に血管が浮く
- 頭痛を起こしやすい
- 生理痛がある
このような症状がある方は全身を流れる〝血〟がスムーズに循環することができない状態です。東洋医学では血瘀(けつお)といいます。血行不良により、顔は肌の色がくすみ、カサカサになり、頭痛、針で刺すような痛みが生じます。女性の場合は生理痛が起こることもあります。また血瘀によって臓腑などにも停滞し、排出されないでいる不要な血のことを瘀血(おけつ)と言います。これがら溜まった部分には痛みや凝りが現れます。血瘀の改善には、血と気のトラブルを解決することが大切です。
東洋医学では「気・血・水」のバランスが崩れると体に不調をきたすと考えます。この「気・血・水」の3つは、人の体の構成要素と考えられています。「気」は、人体の生命活動のエネルギー源です。「血」は、西洋医学における血液の血とは、少しイメージが異なり、全身に栄養を供給し潤すことと、精神活動の基礎物質という二つの働きがあります。「水」は、津液とも呼ばれ、体内の水分です。
この中で「血」は、体や脳にも栄養や潤いを届け、それぞれの組織の働きを助けます。例えば安眠を助け、記憶力を高めるほか、精神を安定させる作用もあります。
『血瘀』のチェック
『血瘀』(けつお)は、全身を流れる「血」がスムーズに循環することが出来ない状態です。よって全身または部分的に血が余剰して停滞している状態です。「血」が停滞すれば、動脈や静脈、毛細血管に汚れが沈着し、血管は硬く狭くなり、心臓への負担が大きくなります。
また、肌がくすみ、カサカサになり、頭痛、針で刺すような痛みや生理痛などが生じます。特に更年期の女性にも多い冷えのぼせなどの症状や頭痛やイライラは、気がスムーズに流れなくなり(気滞)、血の滞りが生じている状態です。『血瘀』の改善には血と気のトラブルを解決することが大切です。
血の巡りが悪い原因
・身体の中で血が少ない
・体内に熱がこもって血を滞留させている
・血管内の血は「気」の力によって移動する為、「気」の巡りが悪くなると停滞する
・身体の冷え
また同じ姿勢を長時間続けることが、血行を阻害して『血瘀』を助長します。
血流エクササイズ
東洋医学における血流とは、血液だけでなく栄養やホルモンエネルギーのすべてを含んだ概念です。人間の体には約37兆個の細胞があると言われており、これら細胞の一つ一つに酸素を届けるものこそ血液に他なりません。
また、血流は脳やホルモンの働きを支えることで心の活動にも影響を及ぼしています。つまり血流が悪くなると細胞に酸素を届けることができなくなるばかりでなく、心 の栄養も奪われます。さらに血流の悪化によって代謝が落ちて肥満につながることもよく知られています。
血流低下を解決できるのが「血流エクササイズ」です。血流エクササイズは一言で言うと首の後ろを伸ばすエクササイズです。まずは落ち着ける場所にゆったり座りましょう。
鼻から3秒かけて息を吸いながら顎を上げます。そしてご自分の耳を歯車の中心であると想像して、それを回転させるイメージで口から7秒をかけて息を吐きながら頭を前方に傾けていってください。この時ただ顎を引くのではなく頭を回転させるイメージで首の後ろ側を伸ばすようにします。
首筋を伸ばすだけでお腹に勝手に力が入って肛門が締まり、背中がすっと立った感じがしませんか。
この血流スイッチでは、お腹、骨盤底筋群、背中の3カ所を鍛えることができます。首の後ろ側は、背骨や筋肉、腱などを通じて骨盤底筋群とつながっており、ここを伸ばすことで骨盤底筋群も引き上げられます。
さらに骨盤底筋群に力を入れると共同収縮という筋肉の原理によってお腹が引き締まります。お腹に力を入れることは内臓のストッパーである腹筋を収縮させることに他なりません。これがいわゆる体幹と言われる部分です。体幹を鍛えることで内臓を上げ、元の位置に戻し、姿勢が良くなってぽっこりお腹が改善できます。
一方で、骨盤底筋群を鍛えることで女性の場合は、胃腸のみならず子宮の位置を戻すこともできます。子宮が下の方に下がってしまうとその重みで骨盤が歪んでしまいます。これを改善することでお尻のシェイプアップも期待できます。
そして、首の後ろを伸ばして背中が引き上げられることで猫背が改善します。背中が丸まると最大の呼吸筋である横隔膜が圧迫され呼吸が浅くなってしまいます。呼吸は血液を肺に戻す働きがあるため、呼吸が浅くなることで血流が滞ってしまいます。これが肩こりや腰痛の原因となっています。
また猫背で腰が後方に抜けるとバランスを取ろうとして膝が曲がってしまいます。これによって第二の心臓と呼ばれるふくらはぎがうまく使えず、足の血流が滞ってしまいます。しかし血流エクササイズによって猫背が改善することで呼吸が深くなり、ふくらはぎの筋肉が収縮して血流が改善していきます。
ちなみに血流エクササイズは朝行うのがおすすめです。東洋医学においては朝は内臓の時間とされており、胃腸の位置の改善という観点からはエクササイズは午前中に行うのが良いでしょう。エクササイズ前にお腹を温める薬膳茶などを飲むとさらに効果的です。
血流の悪化が及ぼすメンタルへの影響
血流の悪化が及ぼす悪影響は体に対してだけではありません。私たちのメンタルもまた血流の影響を大きく受けます。血流の悪化がメンタルに及ぼす悪影響としては、些細なことでも不安でたまらなくなる、ストレスの悪循環から抜け出せなくなるなどがあります。
そもそも女性の方は不安になりやすい生き物です。女性が不安になりやすい理由は2つあり、一つは脳の構造の違いです。私たち人間は不安を感じると脳からCRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)が出ます。男性よりも女性の方がこのホルモンへの感受性が強く、ストレスを感じやすいと言われています。これは多くの哺乳動物では、メスが赤ちゃんを産み育てるため、外的に襲われるリスクを避けるために長い年月をかけて女性が進化した結果であると考え られています。
もう一方で女性が男性に比べて不安になりやすい大きな原因が貧血です。女性は、月に一度生理があってその時に大量の血を失います。生理によって貧血になると鉄分が足りなくなります。鉄分は血の主な材料になるだけでなく、幸せホルモンとも言われるセロトニンを作り出すための必要を不可欠な物質です。つまり女性の場合生理によって貧血となってしまうと鉄分が不足することで 幸せホルモンが少なくなってしまいます。幸せホルモンが少なければ不安感が強くなるのは当然のことと言えます。逆に言えば、血流を良くして貧血を改善することで幸せホルモンが産生され、不安を和らげることができます。つまり女性の不安解消の策は血流にありということです。
さらに、血流の悪化がメンタルに及ぼす悪影響がストレスをため込んでしまいがちになるということです。ストレスには2種類あり、一つは自分が達成したいことのために降りかかる試練を克服しようとする時に感じるストレスです。これは必要なストレスで、例えば何か夢や目標を達成しようとする時、それに向けて努力するためには自分自身を奮い立たせるためのストレスが不可欠です。もう一つのストレスはいらないストレスです。例えばあまり好きではない人と付き合わなきゃいけない、行きたくない会食に行くなど、自分がやりたくないことによるストレスのことです。このような要らないストレスが積み重なることでストレスが雪だるまのように巨大化します。特に女性の場合、献身的な人が多く、自分自身を後回しにして他人の都合を優先ストレスを溜め込んでしまう傾向にあります。ストレスが溜まると自然と体が緊張するようになり、常に肩や首に力が入って血流が悪くなってしまいます。血流が悪くなれば、肩が凝りさらにストレスがたまるという悪循環に陥ってしまいます。
そしてこのような血流の悪化とストレスが溜まりに溜まって、いつしか心が壊れてしまうことがあります。例えば理由もなく突然涙が溢れ出してしまう経験 をされたことがある方はいらっしゃらないでしょうか。このような兆候は確実にうつ病のサインです。一度うつ病になってしまうと、そこから回復するのは 容易ではありません。全て自分が悪いんだと思い込んで逃げてはいけないと自分を責めてどんどん症状が悪くなっていってしまいます。
このような状況ではとても前向きにリラックスして血流改善エクササイズをやろうなんて気にはなれないでしょう。そのため、こうなる前に事前に対処する必要があります。
不安やストレスをうまく解消する行動
ただ一つのやるべき行動は嫌なことから逃げることです。人生は逃げるが勝ち です。自分の嫌なことからは逃げて良いです。無理に我慢したり戦ったりしようとせず、嫌なことや苦手なことからは逃げる癖をつけていきましょう。そうすることで毎日楽しく幸せに生きることができるようになります。それは決して卑怯なことではありません。嫌なことから逃げるのは、むしろ自分自身を守るための勇敢な行動だと言えるでしょう。嫌なことから逃げてあなたのメンタルをマイナスからゼロまで引き上げることができたら、次はそのゼロからスタートです人生をプラスにする段階に行くことができます。
この時に大事なことは苦手なことを克服するよりも、まずは得意なことを伸ばすことです。人間は皆一人で生きているわけではありません。自分が苦手なことは他の誰かの得意なことだったりします。であれば、苦手なことは誰かにお願いして、空いた時間を使って自分の得意なことをした方が良いのではないでしょうか。
私たち日本人は子供の頃から苦手なことから逃げてはいけないと教えられています。このような教育が自分を追い込みストレスを溜め込んでしまう原因になっています。ですが人には好き嫌いがあって得意と苦手があるのが自然なことです。苦手なことに時間を費やし苦労をするよりも得意なことを伸ばした方がはるかに効率が良いでしょう。そして何より自分の好きなことに没頭でき、人生に夢中になることができます。
血が滞るアルコール
アルコールは体中から大量の水分を奪います。ご存知の通りお酒を飲むとおしっこに行きたくなるのは、アルコールに強い利尿効果があるためです。もう一つの理由として毒を体外に排出するためという理由が挙げられます。
アルコールは肝臓で代謝されるとアセトアルデヒドという毒性のある物質に変換されます。私たちの体は血中の毒素を排出するために汗をかき、おしっこが大量に出ることになります。またお酒を飲むと口臭が気になるは、おしっこでは排出しきれないアセトアルデヒドを呼気からも一生懸命排出しようとしている証拠なのです。またお酒を飲んだ翌日に、汗が酒臭くなるのもアセトアルデヒドを皮膚から排出しようとするメカニズムです。
このようにアセトアルデヒドという毒素を排出しようとする過程で大量の水を失います。このような機序により細胞からのみならず、血液中からも大量の水分が失われて血がドロドロになります。さらにアルコールには中性脂肪を上昇させて間接的に血をドロドロにさせるという副作用もあります。
私たちの肝臓はアルコールを汗とアルデヒドに分解する過程でトリグリセリドを作り、このトリグリセリドが血液中に漏れ出すことで血が油でベトベトになります。
ちなみにアルコールを摂取することでHdlコレステロール、つまり善玉コレステロールが上がるという研究が存在します。確かにアルコールにはHdlコレステロールの合成を増やし、分解を低下させる働きがあり、これは科学的な事実です。お酒好きの方がこの見解を持ち出して、お酒は血をサラサラにすると考えていますが、健康というのはバランスであり、飲酒によってHdlコレステロールが増えたとしても、アルコールにはそのHdlコレステロールの上昇を簡単に覆してしまうようなデメリットがあまりにも多すぎるのです。
血を巡らす食材
・玉ねぎ→気と血の巡りを良くし、胃の不快感を解消
・いわし→気と血の不足を補い、体に血を巡らす。精神不安や物忘れ緩和。
・サフラン→血を巡らせ、解毒する。肌のシミやくすみを抑える。
食事は血をドロドロにする原因となる甘い菓子類や動物性脂肪のものは控えるようにしましょう。
血行がよくなるツボ
太衝(たいしょう):足の甲の親指と人指し指の間をなぞっていき、指が止まるところ
肝臓は体に流れている血液やリンパなどの流れと関係し、解毒作用を持つとされおり、肝臓と関係のある太衝を刺激することで、血液の代謝を促し、ドロドロ状態を改善。

三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分あがった、すねの骨の内側にあるツボ
血液の生成を元気にする、血液の流れを調節するツボです。

【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。