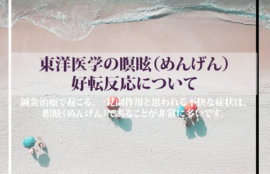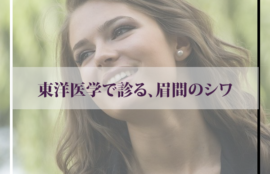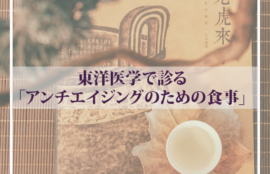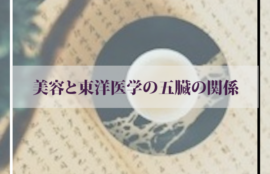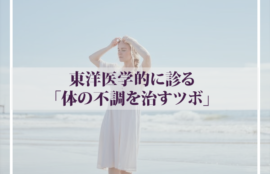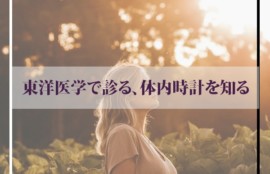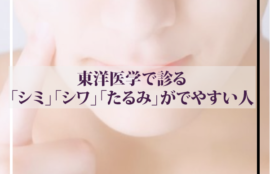現代人が日常的に食べているような食事を続けてしまうとどうしても体に毒が溜まっていってしまいます。その毒をきちんと排泄するような習慣がないと体の中に毒が蓄積し、いずれ心と体の両方がボロボロになってしまいます。
なんだか気分が乗らない、頭が働かない、昔よりも体力が落ちた気がする、最近記憶力が悪くなってきた、これらは全て体の中に毒が溜まったことが原因かもしれません。心と体から毒を出すために最も大切なことは、食事を変えることです。もっと言うと体に負担をかけないような食事を心がけることで体に毒が溜まるのを防ぐことができます。逆に体に負担をかければかけるほどにどんどん体に毒が溜まっていき、その代表例が過食、暴飲暴食です。
体に負担をかけないためには、まず小食を実践する必要があります。さらに食べる時間帯についてもしっかりと意識することが大切です。
デトックスする意味
老廃物を一言で説明すると体に必要なくなったものの総称で、必要な栄養素が体内で吸収利用された後最後に残る不要物のことを指します。例えば古い角質、腸内細菌の死骸、他には尿酸や尿素、尿酸、クレアチニンなどです。尿酸がたまると腎臓の機能が低下して慢性腎不全に陥ることがあったり、クレアチニンの血中濃度が上昇すると腎臓の機能低下を意味するため、老廃物の排出に腎臓は大きな働きがあることになります。
体内老廃物は主に便や尿、汗、毛髪から排出されます。その割合は便が75%、尿が20%、汗が3%、毛髪と爪がそれぞれ1%と言われています。老廃物を体に溜め込んだままにしておくと、まず老廃物に含まれている毒素や疲労物質により体への痛みや疲労感が表れます。例えば肩こりやだるさ、蕁麻疹などの原因の一つが老廃物に含まれる毒素や疲労物質をうまく排出できないことにあります。
また老廃物と一緒に排出される水分も排出できないことがあり、水分が排出できないとむくみの原因になったり、むくみに伴う冷え性を引き起こす可能性も考えられます。そして余計なものを体内に溜め込んでいると必要な栄養をうまく吸収できなくなってしまいます。その結果、体は自分の身を守るために脂肪などのエネルギー源を必要以上に確保しようとし、太りやすい体質になってしまいます。
さらに必要な栄養素が吸収されなくなり、老化や免疫低下の原因にもなります。老廃物そのものと脂肪細胞や水分がくっ付き、セルライトの原因にもなります。このセルライトは放置しておくと腰痛や肩こりを引き起こすこともあると言われています。さらに老廃物の蓄積は腸内環境の乱れや代謝の低下などの原因にもなります。これらは食欲不振や消化吸収能力の低下、便秘や肌荒れ、そしてアトピー性皮膚炎などの不調を引き起こしかねません。溜まった老廃物は血管やリンパを圧迫し、流れを妨げて老廃物がさらに排出しにくくなるという悪循環に陥ってしまいます。
老廃物がなぜ溜まるのか
老廃物は基本的には、便や尿、汗と一緒に体の外へ排出されます。しかし筋力が低下していたり、血液やリンパの流れが悪かったりするとスムーズに排出できずに体内に留まってしまいます。老廃物の約9割は、リンパ管によって運ばれて外部に排出されますが、このリンパ管の中を流れるスピードは1分間に30cmです。
リンパ液を運ぶリンパ管は心臓のようなポンプ機能を持たないため、リンパ液はリンパ管の動きだけではなく、筋肉の収縮によって少しずつ老廃物を移動させることで排出しています。つまり筋力の低下で筋肉の動きが 少なくなると、リンパ液の循環が滞りやすくなって老廃物を排出しきれなくなり、体の中に蓄積されてしまいます。
他にも、加齢や生活習慣、ストレスが原因で便秘になったり、汗をかきにくくなったりしてもデトックスがうまくいかなくなります。便秘は老廃物の蓄積の結果でもあり、原因でもありますが、例えば新陳代謝が低下していると老廃物が排出できず体に残ってしまうことになります。さらに食生活などの乱れによって腸内環境が悪化すると便として排出されるはずだった老廃物が排出できなくなります。このように老廃物を溜め込まないためには悪循環を断ち切ることが大切です。
髪も肌もツヤツヤになる腸デトックス
腸は、私たち全身の健康に大きく関わっている臓器であり、腸を整えることによって見た目が美しくなるだけでなく、当然のことながら全身が健康になれます。腸の状態が悪い人というのは全からく肌の状態や健康状態も悪く、逆に腸の状態が整っていれば肌の状態や健康状態も非常に良いという人がほとんどです。腸が汚れているのに見た目が美しいということもありえませんし、腸が汚れているとお肌や髪を始めとして様々な外見上のトラブルが起きてしまいます。
腸の重要性
見た目や美しさや若々しさを気にするなら、まずは腸を整えるべきです。腸は摂取した食べ物や飲み物を処理し、健康を維持するために必要なビタミンやミネラルといった栄養素を細胞に供給するという役割を担っています。そして細胞にしっかりと栄養が行き届き、細胞が元気になれば当然のことながら健康になれるのはもちろんのこと、髪や肌も自然に綺麗になります。当たり前ですが髪も肌も全部細胞でできています。当然美しい髪と美しい肌を手に入れるには腸内環境を整えることが必要です。
また近年、腸の健康と肌の健康には強い相関関係があることを示唆する証拠が積み上がっています。例えば活性酸素は細胞を老化させたり、細胞にダメージを与えますが、活性酸素が過剰に発生してしまうと様々な病気が引き起こされたり、老化が加速します。そしてこの活性酸素は主に腸内で発生しており、活性酸素の異常発生の90%が腸の中で起きていると言われています。つまり腸の状態が悪いと活性酸素が過剰に発生してしまい、肌や髪などの全身の老化につがってしまう恐れがあります。
腸と免疫力
一方で腸の状態が影響を与えるのは見た目だけではなく、例えば免疫力に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。腸が人体最大の免疫器官であり、体全体の免疫細胞の約60%から70%が腸に集中しているということが分かっています。細菌やウイルスなどは腸の粘膜から侵入してくる傾向にあり、だからこそ腸にはたくさんの免疫細胞が集まっています。
そして免疫力をしっかりと高くキープすることは健康な体と健康なメンタルの基盤とも言えるほど重要なものです。免疫とは細菌やウイルスなどの病原体や異物を撃退する、私たちの体に備わっている能力のことであり、免疫系は臓器 、細胞、化学物質などの複雑なネットワークで構成されていて、それらが連携して感染や病気から私たちの体を守ってくれています。免疫系が適切に機能していればウイルスや細菌などの病原体から、私たちは体を守ることができますが、免疫力が低下してしまうと細菌やウイルスを排除することができずに感染症を始めとした様々な病気になりやすくなってしまいます。
腸とホルモン
そして腸の役割はこれだけではなく、腸の重要な働きにホルモンを分泌するということが挙げられます。ホルモンは体内で作られる物質であり、特定の臓器の働きをコントロールしています。ホルモンはメッセンジャーとして働き体の ある部分から別の部分に信号を送ることによって、その部分に影響を与えることができる物質です。特に腸では消化や栄養吸収のコントロール、糖分バランスの調節、食欲の制御など様々な機能において、ホルモンが重要な役割を果たしています。具体的には腸では腸クロム親和細胞と呼ばれる細胞からホルモンが分泌されています。この細胞は腸全体に存在し、セクレチン、ガストリン、コレシストキニンなど様々なホルモンを分泌することができます。このような腸で分泌されるホルモンは消化を助けたり、インスリンや糖のバランスを保つなど様々な有益な働きをしており、これらのホルモンはいずれも正常な消化や栄養吸収に絶対に必要なものです。
また腸が分泌するホルモンの中で大切なのがセロトニンというホルモンです。セロトニンは別名幸福ホルモンとも言われており、その名前の通りセロトニンが分泌されている時に人は幸福を感じると言われています。つまり私たちは幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンを十分に分泌させることによって幸福を感じることができ、精神が安定し安心して仕事などに取り組むことができるようになります。逆にセロトニンが不足してしまうと、うつ病を発症してしまったり、気分が不安定になってモチベーションが低下してしまったりします。
このセロトニンをしっかりと分泌させるために腸内環境を整えることが大切です。実はこのセロトニンのほとんどが腸で作られているとされています。実際にセロトニンは脳内ホルモンと言われており、その受容体の90% 以上は腸に存在しています。このことから多くの研究者は、腸内環境の悪化がセロトニン不足の原因なのではないかと考えています。
腸デトックス
腸を汚す食べ物を徹底的に排除する
腸を掃除したい、腸を整えたいと思った時に腸を汚してしまう食べ物を遠ざけるということがまず必要になります。いくら掃除をしたところでゴミが次々に 入ってきたら一向に綺麗になりません。腸を汚す原因となるのは、例えば過剰な糖質や酸化した油などが代表的なものです。特に糖質に関しては悪玉菌の餌になってしまうので是非とも避けましょう。砂糖がたっぷりと入った食べ物を食べることは、悪玉菌に餌をあげて悪玉金を腸の中で育てているのと同じこと です。
そして過剰な糖質や酸化した油などを多く含む食べ物を排除することも重要です。その代表的なものが加工食品です。大抵の加工食品には糖質がたっぷりと添加されていたり、酸化した質の悪い油が使われています。また腸に悪い影響をもたらすと言われている食品添加物なども含まれています。
プロバイオティクスを摂り入れる
プロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善することによって人に有益な作用をもたらす、生きた微生物を含む食品やサプリのことです。例えば食品ならばヨーグルトや甘酒、乳酸菌飲料、ぬか漬け、味噌、キムチ、納豆などのいわゆる発酵食品と呼ばれるものにプロバイオティクスが含まれています。これらには乳酸菌やビフィズス菌、酵母菌、麹菌なの有用菌が含まれています。
そしてプロバイオティクスのサプリメントは様々な有効性が証明されており、有名どころだとビオフェルミン、ラクトンA、カリフォルニアゴールドニュートリションのラクトビフィプロバイオティクスなどがあります。こういったものも上手に活用しましょう。
ストレスをできる限り減らす生活を意識する
私たちは誰もが多少なりともストレスを抱えて、ストレスとうまく付き合いながら生きていく他ありません。しかし過剰なストレスや慢性的なストレスだけは是非とも回避することが大事です。過剰なストレスや長く慢性的に続くストレスは、あなたの心身を確実に蝕んでいきます。ストレスが引き起こす悪影響として最も分かりやすいのがメンタルへの悪影響です。またストレスが引き起こすのはメンタル上の問題だけではありません。
実はストレスと腸が関係していると言われてもなかなかピンと来ない人も多いかもしれませんが、脳腸相関という言葉があるように、文字通り腸と脳は密接に関係しています。
脳と腸は神経系内分泌系免疫系の3つの経路を返して互いに影響を及ぼし合っています。普通私たちの脳が体のあらゆる臓器に命令を出すという情報の一方通行的な流れを意識する人も多いと思いますが、実際は脳と腸の情報交換は脳からの一方通行ではなくて腸からも脳にメッセージを送っています。つまり腸内の状態によって、その情報が脳へと伝えられそこから体のあらゆる場所に影響を及ぼしています。
例えば、脳と腸の繋がりを示す最も分かりやすい具体例がストレスを感じると下痢気味になったり、緊張するとトイレに行きたくなるということでしょう。これは脳と腸が迷走神経というものを返して繋がっており、脳がストレスを感知するとその影響が腸内環境に現れるからです。また腸内環境が整っていると脳に良いフィードバックが送られて脳が不安を感じることやメンタル的に不安定になってしまうということが抑えられます。逆に腸内環境が悪化してしまっている人は、メンタルに問題を抱えやすいということも分かっています。
誰にでも効果が期待できるストレス解消法は、やはり体を動かすことでしょう。体を動かすことによってストレスが激減するというのは、あらゆる研究で既に証明されています。また運動はエンドルフィンの分泌を促し、気分も爽快になります。最近ストレスを溜め込みすぎているのならば、それは運動していないことが原因かもしれないので、1日10分でも毎日の生活に運動を取り入れましょう。
姿勢を改善する
パソコンを長時間使ったり、スマホを長時間使ったりする人は、どうしても姿勢が悪くなります。おそらく大半の人が猫背になっていたり、前かがみ姿勢になっていると思います。この姿勢が非常によろしくなく、首や肩などに負担をかけてしまって首こり、肩こり、頭痛などにつながるのはもちろんのこと、腸にも悪影響がもたらされてしまいます。
具体的には、猫背や前かがみの姿勢を続けていると腹部が圧迫されて血流が悪くなり、腸の動きが停滞しやすくなります。逆に良い姿勢を保つことによって腹部や大隔膜が自由に動かせるようになり、食べ物がより効率的に消化器官を通過することができ、速やかな消化につながります。そのため自分が今前屈みになっていたなと気づく度に、しっかりと背筋を伸ばした正しい姿勢を取ることを心がけましょう。
一方で椅子に座っている時に足を組んでしまう癖があるという人も良くありません。足を組んでしまうと腹部を圧迫して腸に負担をかけてしまいます。一時的なら構いませんが足を組むという習慣はできるだけ直すようにしましょう。
運動と睡眠を整える
運動というのはストレスを解消する素晴らしい方法ですが、それ以外にも運動には様々なメリットが存在しています。研究によると体を動かすと腸内細菌の多様性が高まり、健康全体に良い影響を与えることが分かっています。例えば運動は、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉金の増加にもつがることが研究によって明らかになっています。これらの良い細菌は消化の改善、免疫システムの機能向上、さらには慢性疾患のリスク軽減につがるということが分かっています。また運動することによって体内の炎症が抑えられることも分かっています。さらに運動によって脳機能が高まったり、脳の状態が整います。その結果、脳と大きく関係している腸の状態も改善すると言われています。
一方で睡眠が重要だというのはもはや言うまでもないでしょう。そしてもちろんのこと睡眠は腸にも大きな影響を与えています。睡眠中は、脳のお掃除がしっかりと行われるための時間であり、睡眠時間が不足してしまうとお掃除がしっかりと行われず、脳にどんどんゴミが溜まってしまいます。また脳の疲れも取れません。睡眠時間を確保すれば脳のゴミがしっかりと取り除かれ、脳も疲労から回復します。
そして繰り返しますが脳と腸は大きな関係があり、脳の状態が良くなれば当然腸の状態も良くなります。また腸の運動は自律神経がコントロールしているということも分かっています。そして自律神経を整えるには質の良い眠りと十分な眠りが必要であるということが分かっています。つまりしっかりと眠ることによって自立神経が整い、その結果腸の環境が整うということです。
デトックスする食べ物
謎の体調不良がある、なんだかいつも疲れている人は、もしかしたら体の中には毒が溜まってしまっているのかもしれません。世の中には体に溜まった毒をしっかりと排出してくれる食べ物が存在しています。こういった食べ物を積極的に食べることによって体内の毒を排泄しましょう。
食物繊維でデトックス
そもそも私たちの体には、体の中の毒を出す仕組みが備わっています。その最も 大きな仕組みが排便です。体の中のいらないものや老廃物、毒などを便としてスムーズに排出することは毒出しの基本中の基本です。今、便秘気味ですという人は、体内の毒をスムーズに排出できず、体内に毒を溜め込んでしまっているような状態です。まずは便通を良くしてあげることこそがデトックスの基本であると言えるでしょう。
便秘の状態というのは分かりやすく言ってしまえば、腐ったものを腸内に溜め込んでいる状態です。便秘がひどくなると体内には毒素や老廃物などのいらないものが溜まってしまいます。それによって腸の中で病気や老化を促進する活性酸素や悪玉菌が増加し、腸内環境が乱れてしまいます。悪玉菌は有害物質を発生させたり、私たちの健康に悪い影響を与えてしまいます。例えば悪玉菌が作り出す有害物質によって腸の消化吸収能力が低下してしまい、栄養素が十分に吸収できなくなり、体中の細胞に十分な栄養素が供給できなくなったりします。また悪玉菌が優勢になって腸内細菌のバランスが乱れてしまうと、老化が 促進されたり、アレルギーが起こったり、高血圧、糖尿病などのリスクが高まってしまうことも分かっています。さらに便秘だと便が腐敗することによって老廃物も増えてしまいます。
こうして増えた老廃物や毒は、腸の粘膜から再吸収され全身を巡り、体の各細胞や臓器などに悪影響をもたらしてしまいます。そのため便秘の人は一刻も早く、便通を良くする食べ物 を食べることで、その便秘を解消しましょう。
便通を良くする最も有名な食べ物は、食物繊維です。食物繊維は体内の毒素を排出してくれる働きがあることに加え、便を柔らかくして便の傘を増やし、腸の動きを活発にし、排便を促進してくれる栄養素です。
またよく知られているように食物繊維は、腸の善玉菌の餌となり、腸の善玉菌を育ててくれます。そして善玉金が育つことによって腸内環境が整えば、悪玉菌が有害物質を作るのを防いでくれます。
EPAとDHAについて
私たちの体の中で活動している1つ1つの細胞が活動を続けるためには、酸素や栄養素をきちんと受け取り、そして細胞の中で生まれた老廃物を排除できるということが重要です。そして老廃物を排泄するために必要なのが、ずり血液です。細胞は血液によって運ばれてきた酸素や栄養素を受け取って、逆に老廃物を血液の中に流すことによって老廃物をスムーズに排泄しています。血流が悪くなってしまったり、血管が弱くなったりしてしまい老廃物がスムーズに排出できなくなると当然のことながら様々な不都合が生じてきます。そのため毒素を排泄するためにも血管を綺麗すること、そして血流を良くすることが重要です。
そこでお勧めなのがEPAやDHAです。主に魚に含まれるEPAやDHAは、血管をツルピカにしてくれ、特にEPAの血液サラサラ効果というのは科学的にも証明されています。日本では 2009年に有名な大規模臨床試験の結果が発表されています。対象となったのは、既に高コレステロール血症と診断されて投薬を受けている患者さんで、その数は1万8000人、平均追跡期間は46年という大規模で長規模な研究です。
対象者は基本の服薬に加えてEPAを1日あたり1800mg 投与されるグループと基本の服用のみを継続するグループとにランダムに割り当てました。高コレステロール血症は、冠動脈疾患を発症する大きなリスクファクターの1つです結果としてEPAを追加で投与された人は、そうでない人と比較して約19冠動脈疾患になるリスクが減少しことが判明しました。また一度心筋梗塞を起こしたことがある人について、冠動脈疾患発症率を比較するとEPAを追加で投与された人は、そうでない人と比較して約41もの減少が認められました。
さらに近年 EPAは抗炎症作用を持ち、さらには抗がん作用もあるのではないかと注目を集めています。まだ細胞レベルの研究ですが、EPAが膵臓癌細胞の増殖を抑えたことを報告している論文もあり様々な種類の癌でその効果が検証されつつあります。
そのような中、EPAがたっぷりと含まれている食べ物が青魚です。青魚とは、サバ、マグロ、アジ、イワシ、サンマなどの背の青い魚のことです。当然のことながら一言で青魚と言ってもたくさん種類があり、青魚の中でも特にEPAが豊富に含まれている魚を食べて欲しいです。文部科学省が発表する日本食品表示成分表によると、 EPAの含有量の多い青魚なランキング1位はサバ、2位はキンキ、サンマ、3位はマグロとなっています。
またEPAには、その他にも様々な働きがあります。例えばEPAには炎症を改善してくれるという効果も認められています。 EPAを摂取することによって脂肪に溶け込んだ毒を排除し、細胞膜に柔軟性を取り戻すことによって毒素の排泄を促し、炎症も改善してくれます。その他にもEPAには、アレルギーを予防してくれたり、高血圧を改善してくれたり、動脈効果を防いでくれたり、脂質異常症を防いでくれたりとたくさんの働きがあります。
一方で、青魚にはもう1つの栄養素DHAも含まれています。このDHAも様々な効果が認めらており、例えばDHAは炎症を抑えてくれる効果が科学的に認められています。さらにこのDHAは、脳に非常に良い影響を与えてくれることが分かっています。私たちは年を取るにつれて、どうしても認知機能が衰えてしまったり、頭の働きが鈍くなる傾向にあります。このDHAは、脳に良い影響をもたらしてくれ、アルツハイマー病を防いでくれたり、認知機能の低下を防いでくれるということが期待されています。
排泄・摂取・吸収のサイクル
ハリニーでは東洋医学の理論に基づいて1日を3つのサイクルに分け、体に毒が溜まらないための食事を行うことを推奨しています。
| 午前4時から正午まで | 排泄の時間 | 体が毒を外に排雪する時間 |
| 正午から午後8時まで | 摂取の時間 | 体が主に 必要とする食べ物と栄養を取り入れる時間 |
| 午後8時から午前4まで | 吸収の時間 | 体が日中に摂取した食べ物から栄養を吸収し、それを活用する時間帯 |
私たちは、何を食べると良いかばかりを考えていますが、体は栄養吸収以上に排泄を求めています。便や尿は元より、体にとって不要になった老廃物を排出することが健康にとって重要なことです。排泄がうまくいかなくなると老廃物が体に蓄積していきます。これこそが体の毒であり、具体的に言えば食事から摂取したものがうまく排出されなかった結果、体に溜まったもののことを指しています。つまり食品は食べれば食べるほど体に毒を溜める危険性を秘めています。
もちろん、食品の中には抗酸化物質や抗炎症物質など体にとって必要なものも沢山含まれています。しかし過剰に摂取した栄養素は体に溜まって毒になってしまいます。どんなに体に良い食品であっても食べ過ぎてしまったら逆に毒になってしまうので、適度な摂取で止めておこうという意識を持つことがとても大切です。
また、この毒はどこに溜まりやすいのかと言えば体の管に溜まりやすいとインドの伝承医学アーユルベーダは教えています。管というのは胃や腸といった消化管、血管、リンパ管などです。例えば動物性脂肪を摂り過ぎればコレステロールとして血管に溜まり、過酸化脂質に変わります。この過酸化脂質は非常に体に悪い毒の典型例で、悪玉の脂肪です。この悪玉脂肪が血管に溜まっていってしまうことで血管が老化したり、血管がボロボロになってしまうことになります。
また便が腸に溜まれば、それはやがて宿便と呼ばれるものになってメタンガスなど毒素を発するようになります。また溜まった毒素が粘膜質の腸管を荒らして腸壁がただれ、栄養吸収がうまくいかなくなることもあります。そこがポリープや腫瘍の温床となることもあります。結果として腸内環境はボロボロに乱れて、その影響が全身にも現れてきてしまいます。
最近の研究では腸が荒れると脳の神経系にも悪影響が出て、自律神経が乱れ、ホルモンバランスを崩し心まで乱れることが分かっています。
朝の排出の時間が大事
毒素を貯めることなく適切に排出するためには、排泄の時間である午前4時から正午までが重要です。朝に排泄を済ませるという方も多いと思いますが、前日食べたものを朝すっきりと排泄することが1日をリズムよく過ごす鍵です。そのため朝に排泄を邪魔するような食品を食べるのは絶対に避けるようにしましょう。
朝は基本的に何も取らないということをおすすめしますが、果物だけは食べて良いでしょう。なぜなら人間の生理サイクルを考えた時に午前中にしっかりと 便を出すことはとても重要です。体は朝目覚めるとまず便や尿体の老廃物といった毒を大外へ排出しようとします。それが体の自然な生理リズムであり、さらには排泄によって自律神経の切り替えを行う作用も期待できます。
果物には、酵素が豊富に含まれており、消化に負担をかけずに摂取できる食品です。その結果、腸の排便リズム、排泄機能が邪魔されません。さらに言えば果物は、果物だけで摂る方が胃腸を助けます。果物と他の食べ物、例えばご飯やパン、肉などを一緒に食べてしまうと胃の中で腐ってしまうことが分かっているからです。タンパク質の消化に時間を要し、その間果物は消化を待たなくてはなりません。果物には様々な栄養素が含まれていますが胃の中で発酵してしまうと栄養分が損なわれてしまいます。そのため果物は必ず果物単体で摂取 するべきであり、朝昼夜を考えた時に朝だけ果物を単体で摂取するというのが最も良い食習慣と言えるでしょう。
また水は、果物の摂取と関係なく午前中にしっかりと飲むようにしましょう。排泄を促すためにも寝ている間に失われた水分を補給しましょう。なぜなら私たちの体の70%近くは水でできており、体内の水が不足すると、血液も水分不足になり、粘り気の強い状態となって血液循環が悪くなってしまいます。血液の循環が悪くなると全身の細胞に酸素や栄養素が十分に生き渡らないということになります。
さらに血液の働きは、全身の細胞から老廃物を回収する役割も担っています。その血液がうまく回っていないということは全身にゴミが溜まったままの状態になってしまうことになります。これこそが全身に毒が溜まっている状態で、毒が溜まり続けると細胞の炎症の原因にもなります。なんとなく体がだるいな、調子が出ない、肌がカサカサするなどは全て体内の水分不足から来る症状です。
お水を小まめに飲む
現代人は水不足の人が多いことが分かっています。例えば2021年3月に行ったミズラボ編集部の独自調査によると、20代以上の女性 107人のうち、意識していないと回答した人の割合は57.9%、意識していると回答した人の割合は42.1%でした。
水を飲むと代謝がスムーズになり、排便も促されます。血液は赤血球や白血球などの細胞と結晶で構成されていますが、結晶の90%は水です。そのため体内の水分が不足すると血液が濃縮されて血の巡りが悪くなり、老廃物の運搬が滞ってしまいます。適度な水分補給を心がければ体液の状態が一定に保たれ代謝がスムーズになります。
そして便秘を引き起こす要因の一つが水分の摂取不足です。水分には便を柔らかくするだけじゃなく腸管の蠕動運動を促す働きもあり、特に起床や空腹時の水分補給は腸管が刺激されて便意が起きやすくなります。水を1回に飲む量を、コップ1から2杯にして1日に1.2 リットル飲む、これがデトックスのための適切な水分補給になります。
その他にも、筋トレをして筋肉がつくと血流が増えて代謝が良くなり、老廃物が排出されやすくなります。おすすめは腸腰筋を鍛えることです。これはヘソから鼠径部にかけての筋肉でリンパが集中する場所です。リンパの流れが良くなれば老廃物の排出もスムーズになります。筋トレの他にはリンパマッサージがおすすめです。
運動やお風呂で汗をかく
日々の生活の中でできるデトックスは運動やお風呂で汗をかくことです。汗には2種類あり、エクリン汗腺とアポクリン汗腺があります。エクリン汗腺は全体に分布し、99%が水分のためベタベタしていなくて臭くもないさわやかな汗です。エクリン汗腺は基本的に体温調節をするのが役目になっています。アポクリン汗腺は水分にタンパク質や脂質などの有機成分も含まれ、アポクリン汗腺から出る汗が皮膚の表面の雑菌に分解されると脂肪酸ができ、その脂肪酸が臭い汗になります。アポクリン汗腺は体毛がある限られた部分にしかありません。
デトックスには、アポクリン汗腺から汗を出す必要があり、そのため有酸素運動や入浴が大事になります。体からじんわり汗が出る感覚がポイントで、入浴の場合は低温でゆっくり浸かる40度くらいのぬるま湯にじっくり肩まで使って温まることです。じわじわ汗が出てくる時間は10分から15分程度で十分です。週1でサウナに行くよりも毎日しっかり入浴をする方がずっと効果は高くなります。
そして汗をかくために入浴と組み合わせて欲しいのが有酸素運動です。ウォーキングやランニング、トレッチやヨガ、通勤時間に早めに歩いたり、階段を普段から使うそんな小さなからでも大きく変わることができます。
赤外線サウナ
赤外線サウナは、近年健康促進効果や美容への影響で注目を集めているアイテムです。赤外線サウナには様々な形状とサイズがありますが、一人用の小さな個室のような形状をしていることが多く、中に座って使用するスタイルが一般的です。
赤外線サウナは短時間で体温を上げ、大量に汗を書くことができるデトックス効果があり、不要な物質や毒素を排出することができ、肌質の改善効果が期待できます。さらに赤外線 サウナには、むくみ解消効果もあります。 汗をかくことで体内の余分な塩分や水分が排出され、体の水分バランスが整います。赤外線サウナでの発汗は皮膚からだけでなく、体内の深部からも毒素が排出されるため、より効果的なむくみ解消が期待できます。
さらにサウナによる体温の一時的な上昇は、免疫システムを活性化させると言われており、体温が上昇すると白血球やキラーT 細胞などの免疫細胞が活性化します。その結果、感染症や疾患に対する身体の防御力が高まります。免疫力の強化は、感染症や風邪などの予防にはもちろん長期的には慢性疾患リスクを減らす役割も果たします。さらに強い免疫システムは、日常生活でのストレスや疲れに対する回復力も高め、その結果として老化プロセスを遅らせる可能性があります。
研究によるとサウナを頻繁に利用することで心血管や呼吸器の疾患リスクが低下すると言われています。またサウナは血管を拡張させ心拍数を増加させる効果があり、心臓がより効率的に血液を全身に送り出す能力が向上することで循環器系全体が強化されます。
玄米菜食という食習慣
玄米菜食は、果物と野菜、玄米を中心に食べることによって体の毒を出そうという食習慣になります。米は胚芽や糠の部分に栄養素が豊富に含まれていますが、それらの栄養素全て取り除いてしまったものが白米です。一方でその大切な栄養素を残しているのが玄米です。そのため玄米を主食にすると玄米自体は健康維持に必要な栄養素のほとんど全てが含まれているため、他の栄養素あまり気にする必要がなくなります。
しかも、玄米は噛むほどに美味しさを実感できます。この噛むという行為が非常に重要で、よく噛んで食べると満腹中枢が刺激されて少食でも十分な満腹感が得られやすくなるというメリットがあります。
この玄米にプラスして果物と野菜を中心に芋類、豆類、海藻などの植物性食品を食べるのが玄米菜食です。果物や野菜など植物性食品中心の食生活にして動物性食品の摂取を減らせば、心が穏やかになり安定してくるでしょう。
特にうつ症状が強い時、メンタルが落ち込んでいる時は植物性食品を中心にした方が良いと考えられます。なぜなら肉や魚は心に興奮をもたらし、交感神経を過剰にしてしまうからです。うつ状態は既に交感神経は過緊張状態にあるため、交感神経の緊張を緩めるためにも肉や魚などの動物性食品の摂取を一旦減らすことも大事です。
ただし、肉や魚を我慢するよりも自分に正直になった方が心にも体にも良く、心が肉や魚を欲しているのなら、肉や魚を食べることにも意味があることです。ただしメンタルの調子が崩れていて肉や魚を食べたいという気持ちが起こらない時に無理に肉や魚を食べなくても良いことは抑えておきましょう。
玄米菜食で腸活
玄米菜食にすると腸内環境も整っていきます。腸内環境が整うことが私たちのメンタルを回復させ、幸福感に包まれる手助けをしてくれます。自然に根差した食事が、私たちが本来持っている腸内フローラを最適な状態に導いてくれます。その結果、私たちのメンタルも最適化されます。
例えば幸福ホルモンと呼ばれるセロトニンの約9割は腸内に存在します。セロトニンを増やすには腸内フローラを改善するのが早道です。腸内環境が良くなれば感情に多幸感をもたらす他の神経伝達物質も増えます。これが最も簡単かつ安全に私たちのメンタルを改善してくれる方法です。
逆に腸内で悪玉菌が増えるとドーパミンの元となるアミノ酸が代謝されなくなり、ドーパミンが減少してしまうとやる気が失われてしまいます。また楽しみへの欲求や快楽を感じる力も無くなっていきます。昔のように好きなことが減ってきた方は、ドーパミンが不足してしまっている可能性があります。
さらに、悪玉菌の排出物がドーパミンからノルアドレナリンへの変換を阻害します。ノルアドレナリンは私たちの集中力や判断力を向上させる非常に重要な神経伝達物質の1 つです。従ってノルアドレナリンが不足すると好奇心やワクワク感、やる気、集中力といったものが無くなっていきます。
このドーパミン不足とノルアドレナリンの不足が重なると、何事に対しても興味が持てない、やる気が出ない、集中力が続かないといった症状が現れてきます。これはまさしくうつ状態です。つまり腸内環境の悪化が直接メンタルに影響を及ぼしてうつ状態を引き起こすことになります。
さらに腸の乱れは脳だけでなく全身の健康状態とも関連します。なぜならば腸が乱れると免疫力が低下するからです。実際、近年の研究で腸は免疫において 最も重要な臓器であることが分かってきました。なぜなら体において重要な免疫細胞の約7割が腸を中心に集まっていることが明らかになったからです。
なぜ腸に免疫細胞が集結しているのかは、ウイルスや感染菌など外部の侵入者を食い止める前線地帯でもあるからです。腸は体の内部と思いがちですが、実は消化管は皮膚と同じように外の世界と繋がっています。外の世界から体の中に摂り込んだものが胃や腸に送られ、ウイルスや細菌は、口から入り込んで胃や腸から体の中に入り込むのが自然な侵入経路です。だからこそ体は腸に免疫を集める必要があります。腸内環境が悪化していると、この免疫も疲れきってしまい、結果として簡単にウイルスや細菌が体の中に侵入できるようになってしまいます。
このように、心と体がボロボロになり、さらには老化が加速してしまうのは腸に溜まった悪玉菌が原因であり、私たちの心と体は相互に影響し合っているため、心も体も整えることが必要であり、そのためには根本的な腸内環境を整えるのが大切です。
日本の発酵食品で腸活
老廃物を解消する最も効果的なものが腸内環境を整えることです。なぜなら体に溜まった毒素や老廃物をデトックスする最大の経路が排泄だからです。便によって体内の毒素の75%が、尿によって20%が排出されます。腸内環境が整えば老廃物が解消されるため、まずは腸内の善玉菌を増やすことがポイントです。善玉菌は有害な物質を吸着して対外へ排出 する手助けをしてくれたり、悪玉菌の増殖、定着を防いで感染を予防してくれます。
腸活の食べ物といえば発酵食品がその代表格です。発酵食品を食べるとなぜ良いのかは、腸内フローラを良好に保つための乳酸菌が豊富に含まれているからです。幸い日本には古来より数多くの発酵食品があります。日本の発酵食品といえば、納豆、味噌、ぬか漬けなど様々存在しております。ただし納豆は、納豆菌の発酵によるもので乳酸菌は摂れませんが腸内環境を整える善玉菌としての働きはあります。日本にはこれだけたくさんの発酵食品が溢れているということで非常にありがたい環境にあると言えます。日本に住み日本の伝統的な和食を食べているだけで腸内細菌たちを喜ばせることができます。
味噌汁は飲む女性ホルモン
日本人の食卓にはなくてはならない味噌汁ですが、鎌倉時代のお坊さんが発明した超健康的な精進薬膳料理であったと言われています。そもそも味噌という調味料は、血中コレステロールの濃度の抑制から抗酸化作用による老化防止に至るまで、この世のありとあらゆる健康効果が詰まった、まさに人類の英知ということができます。
味噌汁の材料である味噌は大豆から作られ、大豆に含まれているイソフラボンは私たちの体内で女性ホルモンと同じような作用をすることが知られています。女性ホルモンというのは他でもなく、女性らしさを作り出すホルモンです。ハリのある肌やツヤのある黒髪など女性らしさの全てはこの女性ホルモンによって作られています。
女性の場合は、更年期において、閉経によってエストロゲンがほとんど分泌されなくなり、このホルモンバランスの乱れによって生じるのが更年期障害です。年を重ねることによって体内に存在する内因性のエストロゲンは枯渇していきますが、女性ホルモンは外から取り入れることもできます。そこで積極的に取り入れていただきたいのが大豆由来のイソフラボンです。
イソフラボンは、フィトエストロゲンすなわち植物由来のエストロゲンと呼ばれることもあり、男女問わず若々しさを保つために必須の栄養素です。この大豆イソフラボンの効果を得られる食品こそが味噌汁です。味噌汁1 杯にはおよそ6mgのイソフラボンが含まれています。またエストロゲンを摂取するという点で最も効率的な食材は納豆です。納豆には1カップ30gのものイソフラボンが24mgも含まれていて、味噌汁4杯分に相当します。是非とも毎日味噌汁と一緒に納豆を食べるようにしましょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。