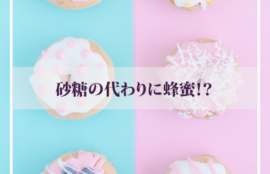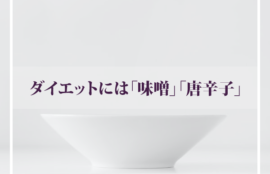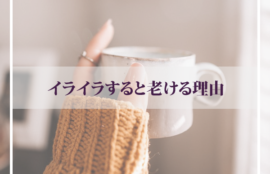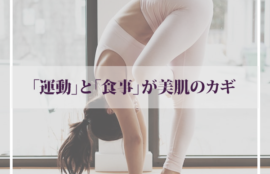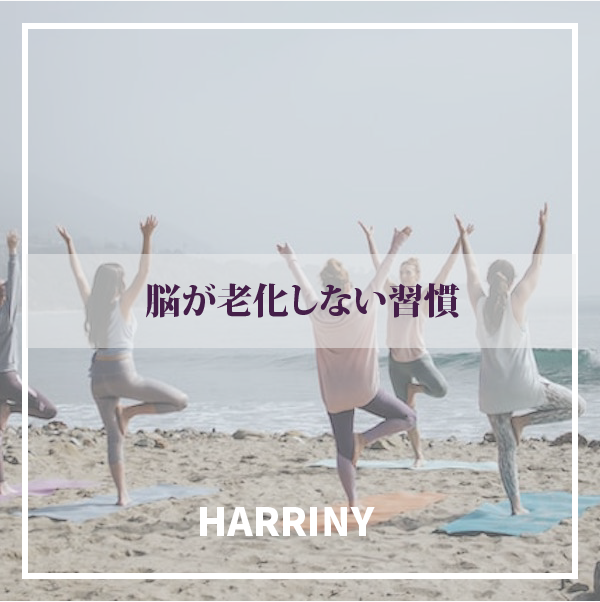
歳を重ねるほど頑固になる人、一方で歳を重ねるほど温厚で優しくなる人がいます。それは老人脳になっているかいないかの差だということが分かっています。また脳が若々しく保つような生活習慣を送っている人は人の気持ちを読む能力がいつまでも衰えないことが分かっています。
この生きる上で非常に重要な「相手の気持ちを読む能力」は、10代で低く、20代で急激に伸び、48歳でピークを迎えます。そして50代ぐらいから周りのことを徐々に気にしなくなる人が出てきます。例えば家族に横暴な態度になったり、店員さんに乱暴な言葉を使うようになったり、自分の思い通りにならないことに憤慨するようになります。それは悪気があってそうなるのではなく、脳の機能が低下して自然とそうなるのです。
また、脳の老化は自分では気付くことができず、通常30代から少しずつ萎縮が始まり、60代半ばになると明らかに萎縮が起き、放置するとどんどん老人脳になっていきます。
特に「相手の気持ちを読む能力」は、人によって振れ幅が大きく、40代でピークを迎える人、70代や80代までそのピークが持続する人もいます。いつまでも脳が老化しない人は、脳の老化を緩やかにする、もしくは積極的に若返る工夫をしています。
人はマインドから老化する
脳を老化させないためには、健康的に運動する、頭を使う、コミュニケーションを取るなどの脳活のようなものを意識するかもしれませんが、それ以上に大きな影響を及ぼすものが私たちのマインドです。
研究では「自分が若い」と本気で思っている人は、実際に脳も体も若くなることが分かっています。実年齢が60代であっても、自分は40代であると思うことを主観年齢と言い、そう思うと40代のような行動をとるようになります。
韓国で行われた研究によると、59歳から81歳の被験者68人の主観年齢と脳の状態を調べたところ、主観年齢を実年齢より若いと答えた被験者には、灰白質の密度が高く、記憶力が良く、うつの傾向が低いことが明らかになっています。
また、ハーバード大学で行われた実験では、70代になる8人の被験者を、22年前のテレビ、ラジオ、本を配置して、さらに当時の内装に仕上げた建物の中で5日間共同生活を送ってもらいました。22年前の自分を意識することのみをルール(主観年齢を22年前と思う)として決めたところ、5日間で手先の器用さが向上、姿勢が良くなる、視力がアップ、見た目が若くなり、考え方が柔らかくなったことが分かっています。つまり自分は若いと思い込んで行動するだけで脳に変化が生まれたことになります。さらに第三者に見た目の年齢を実験前後で判断してもらったところ、たった5日間で3歳も若くなっていました。つまりもっと長い期間過ごせば、さらに若く見られるということが推測されます。
このように自分は若いと思うマインドだけで、脳内のイメージが変化し、生理的反応にまで影響して、健康状態がより良くなっていくことが明らかになっています。
その他の研究でも、オシャレに気を配り、外見が若い人は介護を受けるリスクが低くボケにくいことも示されています。さらに脳のMRI画像の若々しさと見た目年齢には明らかに相関関係があります。つまり重要なのは見た目に気を配る心持ちやオシャレをしようとするマインドが脳の活性化に効果的であり、逆に脳が活性化した結果、若々しい外見が身についてくるということです。
欲は悪いものではない
一般的に欲は悪いものであるというイメージがありますが、若々しく脳を保つためには欲は非常に重要なものです。一般的には食欲などの生理的欲求は、年齢を重ねるごとに減少していきます。その理由は、やる気を生み出す脳内ホルモンであるドーパミンが加齢とともに減少するからです。
さらに欲があった方が長生きできるという研究があります。例えば食欲が旺盛な高齢者の方が長生きする傾向にあり、食の細い高齢者は死亡リスクが2倍以上高まるということが明らかになっています。長生きするためにも欲の原動力であるドーパミンを増やすことが大変重要になります。
このドーパミンを増やすことは実は簡単です。例えば笑顔を作る、体を動かす、好きな音楽を聴く、好きな人の写真を見る、スポーツなど予想外の嬉しいことが起きることに参加する、新しいことに参加するなどの習慣によってやる気が衰えず脳がいつまでも若い可能性があります。
一方で年齢を重ねることに増える欲が幸せに対する欲です。この欲に関係しているホルモンが、別名愛情ホルモンと言われるオキシトシンです。オキシトシンは、人や動物などと繋がった瞬間に出るホルモンです。そして2022年の最新研究では加齢とともにオキシトシンは増えることが明らかになっています。
加齢とともに生理的な欲求は減りますが、人とつながることや人に貢献することでオキシトシン的な幸せを追求するようになります。
生きがいがある人生
脳を若々しく保つために生きがいを持っている人の方が脳の認知機能が高いことが分かっています。生きがいというと大層に聞こえるかも知れませんが、それは旅行するのが生きがい、写真を極めるのが生きがいなど、何でも良いです。喜びや幸せ、楽しく思うポジティブな気持ちが心身にかかるストレスを減らし、様々な病気のリスクを下げ、その好循環が長寿をもたらすと考えられています。
このような主観的な幸福度を上げるためにも生きがいを持つことで、ドーパミンが分泌され快感や幸福感を得たり、意欲が湧いてきたりします。
記憶力ではなく意志力の低下
日本において2025年には認知症患者は約675万人に及ぶとされ、5人に1人が認知症になると予想されています。多くの方が認知症の初期症状は物忘れであると思っていると思いますが、物忘れは記憶力の低下が原因ではなく、思い出すのが面倒という意志力の低下が原因であるとも言われています。40歳を超えると記憶力の低下より先に面倒くさいが現れ、この面倒くさいこそが私たちのすべての思考や行動を抑制する大きな問題となり、認知症の入り口でもあります。
私たちの記憶は芋づる式になっており、思い出したい記憶まで何らかの糸口をきっかけとして記憶の蔦を辿ります。記憶の蔦を辿るのは、脳内では非常に手間のかかる仕事なので、加齢と共に思い出すのを面倒くさくなります。
脳が面倒くさいと思うと、記憶の早期のみならず思考や行動など私たちの活動のすべてを抑制します。思考や行動が抑制されれば全ての知的活動が低下して、物忘れも本格的になってきます。そうなると脳細胞が劣化し、本格的な記憶力の低下が始まり認知症が進みます。
健康な物忘れと病的な物忘れの違い
医療においては、物忘れというのは白髪やシワと同じで加齢現象の一つとみなされています。認知症と健常者の物忘れの違いは、認知症では記憶の全体を忘れてしまうのに対し、 健常者では記憶の一部を忘れるという点が挙げられます。例えば認知症では食事をしたこと自体を忘れますが、健常者の場合は食事をしたこと自体は覚えていますが、何を食べたかを忘れてしまいます。
最近ではうつ傾向が進むと脳内にアミロイドβというゴミが溜まりやすくなることが分かってきました。このアミロイドβは、日本人の認知症のタイプとして最も多いアルツハイマー型認知症の原因として知られています。また面倒くさいは、閉じこもり症候群の生みの親でもあります。意欲が低下し外出が面倒になれば、社会性が失われて引きこもりがちになり、特に高齢者の引きこもりは、認知症の最大の原因の一つです。さらに食事も取らなくなり、栄養バランスが崩れ、脳もエネルギー不足になり認知症が進行してしまいます。
難聴は認知症のリスクを高める
難聴が認知症の発症に関わっているという情報を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。イギリスで行われた調査によると、中程度の難聴がある人は認知症のリスクが通常の1.6倍に上がる結果が報告されています。
2015年に日本 で実施された18歳以上の人を対象にしたアンケート調査によると聴力に問題を感じている人は13.1%という結果が出ています。アメリカのジョンズホプキンス大学のフランクリン博士によると難聴と認知症の関係性は2つの可能性が指摘されています。
一つは、難聴は社会的な孤立につながることです。難聴になると人の声が聞き取りにくくなるため会話が難しくなります。必然的に家族や周囲の人との関わりが減りやすくなり、社会的に孤立してしまうと精神的なストレスを抱えたりして認知症を発症しやすくなってしまいます。
もう一つは、難聴になることで脳の認知能力が低下することです。聴力が衰えて聞き取れない音が増えると 脳は聞き取れなかった音が何であったかを判断するために大きな労力を割くようになります。音を聞き取ることに集中すれば 脳は他の働きをする余裕を失ってしまいます。結果として脳全体の認知機能が下がってしまいます。
このように難聴は認知症のリスクを上げる可能性があることから、大切なのは自分や家族が難聴なのか、いち早く気がつくことです。そしてもし難聴だった場合、補聴器などを使うことで聴力を補強し、認知症リスクを下げる対策を取りましょう。聴力はどうしても加齢とともに衰えてしまうため、聴力の低下は認知症につながると覚えて、早めに対処することを意識しておきましょう。
睡眠がアミロイドβを掃除
アミロイドβを取り除く上で重要なのが睡眠です。睡眠とアミロイドβの関係性に関する研究によると、睡眠不足が続くとアミロイドβがうまく排出されずに脳内に蓄積し、認知症になるリスクが高まるという報告があります。また別の研究によると睡眠不足と脳内にアミロイドβのプラークが蓄積するリスクの間には強い関連性があるということが分かっています。
つまり、睡眠不足だと睡眠中に行われるアミロイドβなどの脳の掃除がきちんと行われません。特に深い睡眠段階である徐波睡眠中に脳の中に溜まっている ゴミであるアミロイドβが掃除されて取り除かれることが分かっています。そして複数の研究によると、徐波睡眠の段階で睡眠が中断されてしまうとアミロイドβが蓄積し、脳組織にプラークが形成されることが示唆されています。
脳が老化する習慣
過剰なストレス
私たち現代人は、日々様々なストレスに晒され、多くの人がストレス過剰の状態になっています。過剰なストレスは脳血流の低下を招き、それによって脳細胞が劣化してしまうと考えられています。
全身の細胞と同じく私たちの脳細胞もまた血液によって栄養されています。脳細胞は他の細胞よりも特に多くの酸素や栄養が必要な部位であり、ストレスによって血流が滞ると酸欠や栄養不足となった脳細胞が死滅してしまいます。脳細胞は1度死んでしまえば2度と再生しないことが知られています。
脳細胞は特に酸欠に弱く、5分程度酸素の供給がストップするだけで壊死してしまい、2度と復活することはありません。このように脳血流の悪化によって脳細胞が死滅することで脳が萎縮して認知症の発症につがってしまうと言われています。
さらに過剰なストレスは、血液をドロドロにしたり、血圧を上げることで脳卒中を招いてしまうリスクもあります。強いストレスを感じると心臓がドキドキしますが、これはストレスの刺激によって大量のアドレナリンが分泌されるためです。アドレナリンは血圧を上昇させるとともに、血中の血球成分の働きを活性化することで血液をドロドロにします。これはアドレナリンによって私たちの体が戦闘モードに突入するためです。
私たちはストレスを感じることで戦闘モードになり、そのような戦闘モードを無理やりまた抑え込むことでさらなるストレスを感じます。このようなストレスの負のループに陥ることで血圧が上がり、ついには頭の血管が高血圧に耐えられなくなって脳卒中で病院に担ぎ込まれことになります。
実際、75歳以下の男女14万人を調査したフィンランドの研究によって、ストレスの多い仕事についている人はそうでない人に比べ、脳卒中を発症するリスクが最大58%も高くなってしまうことが分かっています。また統計によると日本人の 4人に1人が生涯で脳卒中を経験することが分かっていますが、このフィンランドの研究と合わせればストレスの多い仕事についている人の場合、脳卒中のリスクが2 から3人に1人になってしまいます。
実は、脳卒中は日本人の認知症の主な原因の1つです。日本人の認知症のタイプで最も多いのはアルツハイマー型認知症ですが、それに続いて2番目に多い のが脳血管性認知症という認知症です。脳血管性認知症は、その名の通りで脳の血管が原因となる認知症で、具体的には脳中の後遺症として発症することが ほとんどです。脳卒中になれば脳の血管が破裂したり、あるいは脳の血管が詰まることで、いずれにしても広範囲の脳細胞が酸欠になって死滅してしまいます。脳血管性認知症は日本人の認知症の20%を占め、67%のアルツハイマー型認知症に比べればマイナーと言えますが、アルツハイマー型認知症との大きな違いは重篤な合併症があるという点です。
また、アルツハイマー型認知症は物忘れが始まって徐々に症状が進行しますが、脳卒中がきっかけの脳血管性認知症は、ある日突然自分が誰だか分からなくなってしまい会話することができなくなります。さらに脳卒中の部位によっては体の左右どちらかが完全に麻痺して動かせなくなったり、場合によっては全身が完全に麻痺して植物状態に近い状態になることもあり得ます。
このような状態にならないためにも過剰なストレスに晒されてしまわないよう常日頃からストレスマネジメントを心がけることが非常に重要になります。
睡眠時間を削る
私たちは食事や運動をしなくてもすぐに死にはしませんが、睡眠を取らなければわずか2晩の徹夜で精神的にかなり危険な状態に陥ると言われています。このことから睡眠は健康のために最も重要であると言っても過言ではありません。
睡眠時間を削るというのは、時間の前借りに過ぎず、睡眠時間を削れば削るほど寿命が短くなり、結局後で時間や健康を失って後悔することになります。
睡眠を削ることで様々な病気のリスクが上昇することは数多くの研究によって明らかになっています。例えば5万6953人を対象とした研究では、睡眠時間が5時間以下になると睡眠時間が8時間程度の人に比べ、肺炎になるリスクが1.39倍も高なることが分かっています。また睡眠時間が6時間以下では、肥満や糖尿病、心臓病といった病気の有病率が高くなり、さらには事故で死亡する確率も高くなることが分かっています。
さらに4419人を対象とした日本の研究でも睡眠時間が6時間以下の人は、死亡率が2.4倍も高くなることが分かっています。また別の研究では、日本人のおよそ4割の人が、睡眠時間が6時間未満であることが報告されています。
さらに最近では、睡眠不足によって脳が老化するスピードが早まってしまうことも分かってきています。このことは睡眠不足によって脳の活動が低下することは多くの方が経験的に知っていることでしょう。
このように脳機能に異常が出てしまうのは睡眠不足によって、前頭葉の血流が悪くなってしまうためと考えられています。前頭葉は意思力、理性を司る脳の部のため、睡眠不足によって障害されることで理性的に物事を考えることができなくなってしまい、それによってやる気が損なわれてしまったり、普段はしないような非理性的な行動に出てしまったりします。
一方で、イタリアの研究によると何日も睡眠不足が続くとグリア細胞という免疫細胞によって脳細胞が食べられてしまう事実が明らかになりました。私たちの脳にはグリア細胞という免疫細胞が存在しており、普段は脳から出たゴミを食べるお掃除屋さんの役割をしています。一方で私たちの脳細胞には互いにシナプスというネットワークを形成することで、コンピューターのように複雑な処理能力を発揮しています。しかし睡眠不足が続くとシナプスがグリア細胞によって食べられてしまう現象が起きることが確認されています。当然、脳神経同士のネットワークが絶たれ、脳は機能を失ってしまいます。これこそが認知症の症状となり、認知症では記憶にアクセスすることができなくなることで物忘れが出てきて、同時にうまく人に自分の意思を伝えることができなくなってしまいコミュニケーション障害をきたします。
さらに別の研究では、睡眠不足になると脳内のアミロイドβが脳の外に排出され なくなり、アルツハイマー型認知症の発症リスクが高まってしまうことが指摘 されています。アミロイドβは脳から出るゴミの一種で、これが脳内に蓄積することでアルツハイマー型認知症が発症してしまうと考えられています。
実際、2812人の高齢者を対象としたアメリカの研究では、睡眠時間が5時間未満の高齢者は睡眠時間が7から8時間の高齢者に比べて認知症の発症リスクがおよそ2 倍になってしまうことが分かっています。この研究では入眠困難のデメリットについても検証されており、ベッドに横になってから眠るまでの時間が 30分を超える高齢者は、30分未満の高齢者に比べて認知症の発症リスクが 45%増加することも分かっています。
そのため睡眠の質と時間の確保の両方を高めるには、寝ている時よりも日中の活動の方が重要です。なぜならば睡眠は私たち自身の手でコントロールするのが難しいからです。睡眠の質や時間をアップするために私たちが睡眠中にできることと言えば寝具をより自分にフィットしたものに変えることぐらいでしょう。しかし子供を見れば分かる通り日中にしっかりと活動していれば、ぐっすり眠れます。良質な睡眠のためには日中にしっかり運動したり、夕方以降はカフェインを控える、寝る数時間前に湯舟に浸かるなどして眠るための準備をすることが大切です。
脳老化をチェックする
老化現象のスタートは、老眼が始まると言われています。早い人だと40代を迎える頃から老眼の症状が出始め、近くにあるものが見えにくくなってしまいます。以後、胃腸から他の内臓の機能が弱まっていき、そして最終的にすべての内臓の機能がダウンします。そうして人は老衰に至ります。
そのため老眼になったことを自覚し始める前からアンチエイジング対策をとることが必要です。放っておいたらあっという間に老化は進んでしまいます。老化防止のためには、脳の老化を抑制することです。脳はすべての内臓をコントロールするという役割を担っており、脳がおかしくなれば同時に内臓もおかしくなってしまいます。そうならないためには脳を活性化させなければいけません。
脳の老化度がすぐにわかる方法があります。目を閉じた状態で何秒間片足で立っていられるかを測ることで脳の老化度を診断することができます。目安は30秒以上で立っていられればまだまだ脳は若い状態です。バランス感覚が脳の状態と比例しており、30秒以下であれば脳老化が進行しているかも知れません。
ただし30秒以上立てるようにトレーニングすることで、脳を鍛えることが可能です。片足立ちの練習によって、バンランス能力を鍛えることで、短時間でも効果が期待できる方法です。
糖質でボケる
認知症には、脳の糖尿病という異名があることをご存知でしょうか。最近の研究で砂糖の摂取と認知症発症の間には無視できない関係があるということも明らかになっています。UCLAが行った研究によって、砂糖をたくさん摂取することと体内の炎症レベルの上昇との間に関連性があることが明らかになりました。この炎症が脳のもつれやプラークの形成につながり、認知症になりやすくなると考えられています。また脳で炎症が起きてしまうことによって、認知機能が低下してしまったり、認知症のリスクが上がると考えられています。また UCLAの研究に加え、米国精神医学会が行った別の研究でも、砂糖の摂取量が多い人は認知症の低下や記憶障害などを経験する可能性が高いことが判明しています。
ボケたくないとか、認知症を防ぎたいと思うのであれば糖質の取り方には注意しなければいけません。特に糖質の中で避けるべきものは、精製した糖質であり、白米、パン、麺、砂糖と小麦粉で作ったお菓子、じゃがいもです。
この5つには「糖毒性」があり、例えば白米やジャガイモで鍋を焦がしてしまうと洗ってもその焦げは中々取れません。この頑固すぎる焦げをAGEと言い、糖質とタンパク質が結合して二度と分解されることがない物質です。この頑固な焦げは、これらを取ることで血管内に生まれ、血管内のタンパク質であるコラーゲンと結びついて糖コラーゲンというAGEができ、これは動脈硬化の原因になるだけでなく、脳にダメージを与えて認知機能を低下させます。
問題は精製された糖なので、例えば白米ではなく精製されていない玄米や雑穀米を選びましょう。また同様にパンならば全粒粉のパン、麺ならばうどんよりも十割そば、じゃがいもよりは皮付きのさつまいもなど選択するということが非常に重要です。
糖尿病は認知症リスクが2倍
また、糖尿病とその予備軍の人たちは健全な人と比べてアルツハイマー型認知症を発症するリスクが2倍になります。糖尿病の人がアルツハイマー認知症になりやすい原因は、インスリン分解酵素にあると考えられています。
日本の糖尿病患者の95%以上が該当すると言われる2 型糖尿病はインスリンという血糖値を下げるホルモンの働きが悪くなることで発症することが分かっています。このインスリンを分解するときに働くのが、インスリン分解酵素という物質で、アルツハイマー型認知症の原因となるアミロイドβを分解することができます。
高血糖の状態が続き、糖尿病になるとインスリンが大量に分泌されます。つまりインスリン分解酵素は、その大量に分泌されたインスリンを処理することに追われ、アミロイドβの分解にまで手が回らなくなります。その結果として脳内にアミロイドβが蓄積しやすくなります。糖尿病の人は長い年月をかけて脳にアミロイドβを溜めてなくても、認知症を急に発症するリスクがあることが分かってきています。
さらに糖尿病は、アルツハイマー型認知症だけでなく脳血管性認知症の発症リスクも高くすることが分かっています。それは糖尿病の人の血圧が上昇しやすいだけでなく、血糖値が高い状態が続くことによって動脈硬化が進んでしまうからです。動脈硬化が進むことによって脳梗塞を発症しやすくなり、脳梗塞が発症してしまうと脳の血管が障害を受けて脳血管性認知症につながってしまう可能性が高くなります。
食後に1枚のガムを噛む
現代人は咀嚼回数が非常に少ないと言われています。弥生時代には祖先は一食につき4000回も咀嚼していたと言われています。これが戦前には1500回ほどに減少、現代では600回にまで減少しています。咀嚼には非常に大きな利点があります。
私たちの唾液は消化酵素の一つであり、噛んでいる時からすでに消化は始まっています。咀嚼が持つメリットは、消化吸収を良くする効果だけではなく、咀嚼回数が増えると同時 脳が活性化するメリットがあることが分かってきました。これは噛むことで歯と歯が接する感覚や味覚といった複雑な情報が一気に脳に送り込まれ、脳がフル回転するためと考えられています。そのため食後にガムを1枚噛むだけで、記憶力は格段に向上し、認知症が予防できます。
硬い食材ほど脳血流量が増える
噛む食べ物が硬ければ硬いほど脳血流がアップします。ケーキからイカの刺身に至る様々な硬さに相当するゼリーを作って、それを食べて噛んでいる最中の脳血流量を調べた実験では、硬い食材ほど脳血流量が増えたことが分かりました。さらに食事の味によっても脳血流が変化することが分かっています。テスト用のゼリーに少し苦味を加えると脳血流量は減少しています。このことから苦味のない食事ほど脳血流量が増えることが分かります。
タモギタケで認知症予防
金沢大学で行われた2022年の研究によれば、キノコに豊富に含まれるエルゴチオネインという物質の摂取によって、私たちの脳機能が上がることが分かりました。この研究ではエルゴチオネインには主に3つの脳機能の改善効果があることが分かっています。
それはアメロイドβによる神経損傷の保護、記憶力の強化、抗うつ作用の3つです。今や認知症は日本の国民病となりつつあり、2025年には65歳以上の方の 5人に1人が認知症になると言われています。また認知症は要介護の直接原因として脳卒中に継ぐ第2位で、寝たきりの20%が認知症が原因となっています。
そもそも認知症にならないように、かつその進行をできるだけ穏やかにすることが大切です。そこで着目したいのがエルゴチオネインによる神経損傷の保護効果です。認知症のうち日本人に最も多いアルツハイマー型認知症は、脳内にアミロイドβというゴミが溜まることで起きてしまうと言われています。エルゴチオネインによってアメロイドβによる神経損傷をブロックすることで認知の症状を緩和できる可能性が期待されています。さらにエルゴチオネインは、親水性が高く、腸間から容易に吸収されるため口から食べることで簡単に脳に移行し、記憶力の増強やうつ病の予防など様々な効果を発揮することが分かってきました。これはエルゴチオネインに神経細胞の新生、成熟の促進効果があるためであると考えられています。
このように私たちの脳機能を向上させるエルゴチオネインが含まれている奇跡の食品こそがタモギタケです。タモギタケは珍しいキノコですが、スーパーマーケットで簡単に手に入れることができます。山形大学の研究によれば、タモギタケが持つエルゴチオネインの含有量は他のキノコに比べて群を抜いていて、エルゴチオネイン含有量第2位のヒラタケに比べて5倍近い量を誇っています。さらにタモギタケにはビタミンb2やパントテン酸、葉酸といった私たちの血管の健康を守ってくれるビタミンも豊富に含まれています。
また、脳血管性認知症はその名の通り脳出血や脳梗塞といった脳血管性の病気の後遺症として現れる認知症で、65歳以上の日本人の認知症のおよそ20%を占めています。このような脳血管性認知症を予防するためには日頃から血管の健康を保ち、脳梗塞のような病気を防ぐことが大切です。
最強の脳トレは音読
加齢とともに物忘れやうっかりミスが多くなるのは脳からSOSサインです。認知症の予防や脳の老化の予防には毎日の生活習慣が極めて重要です。しかし1分の脳活でも脳を活性化して、老化を防止し認知症を予防する効果があることが示されています。
特に40代ぐらいから衰えが始まるのがワーキングメモリーネットワークです。その衰えを防ぐ方法が、利き手と逆の手を使うことです。脳は新しいことにチャレンジすると活性化するという性質があります。例えば歯磨きをいつもと違う反対の手で行うだけで1分脳活になります。
そしてもっと簡単な脳活が本や新聞を音読することです。実は文章を読む時に様々な脳の領域が活性化しており、特に音読は一度に沢山の脳の領域を使います。目で黙読することで視覚部位を、読んで理解することで前頭前野を、発語して声に出す部位や自分の声を聞く聴覚部位を使うため、一石四鳥の最強の脳活です。さらに音読している時に、脳内ではセロトニンというストレスを和らげてくれるホルモンが分泌されています。また前頭前野の働きが活発化し、アイデアが閃いたり、考えをまとめる能力が高くなります。さらに同時に感情をコントロールしやすくなりイライラしにくくなるとも言われています。
「運動」と「脳」の仕組み
「運動」に様々な病気の予防効果があると言われても、なかなか「運動」を習慣化するのは難しいのが現状です。しかし私たちの身体は本来動くように設計されており、身体を動かすことが生存の可能性を増やすという遺伝子が組み込まれています。
私たちの祖先は、常に飢えとの戦いの中で生き、毎日食べ物を探し、獲物を捕まえ動き回って生きるための食料を探していました。その他、必死に身体を動かして危険な猛獣から逃げたり、住みやすい場所を探したりすること生き延びるために必要でした。
例えば食べ物を食べて美味しいと快楽を感じるのも食べることが生存につながるからであり、つまり生存の可能性を増やすことが快楽やメリットが伴うように脳が設計されているのです。そして運動も生存の可能性を高めるため、脳内神経伝達物質である幸せホルモンの「セロトニン」、やる気、集中力の「ノルアドレナリン」、覚醒物質の「ドーパミン」が分泌されるのです。
脳は1万年前からほとんど進化していないと言われ、そのため生存の可能性を増やした行為と同じことをすれば、脳はそれを繰り返させようと私たちに快楽を与えてくれる仕組みがあります。
一方で現代人は座っている時間が長く、脳の仕組みから考えれば生き残れない状況を作り出していることになります。多くの人が身体に不調を感じるのは、脳と私たちの環境の矛盾にあります。身体を動かすことで生存の可能性が増え、脳から報酬が与えられる、その報酬によって前向きになったり、健康になったりします。
こう考えれば運動によって他の様々な機能を強化できることにもなります。例えば獲物を仕留めるには集中力が必要であり、素早く行動する必要があります。つまり運動が集中力を高め、新しい経験をすることが記憶力を高めることにつながります。
どんな「運動」をすればよいかは重要ではなく、どんな運動でも良いからとにかく身体を動かすことが大切です。まずは楽しいと思える運動からスタートして、そして慣れてより高い効果を期待するのであれば30分程度のウォーキングをしましょう。ポイントは、適度な負荷で心拍数を増やし有酸素運動を心がけることです。また脳が再構築されて構造が変化するまでには時間がかかるため、根気よく、決して諦めずにとにかく続けてみましょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。