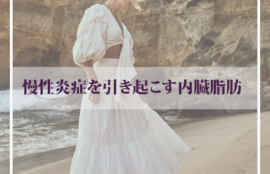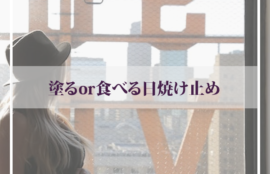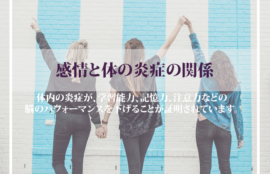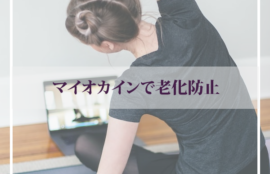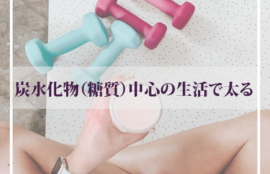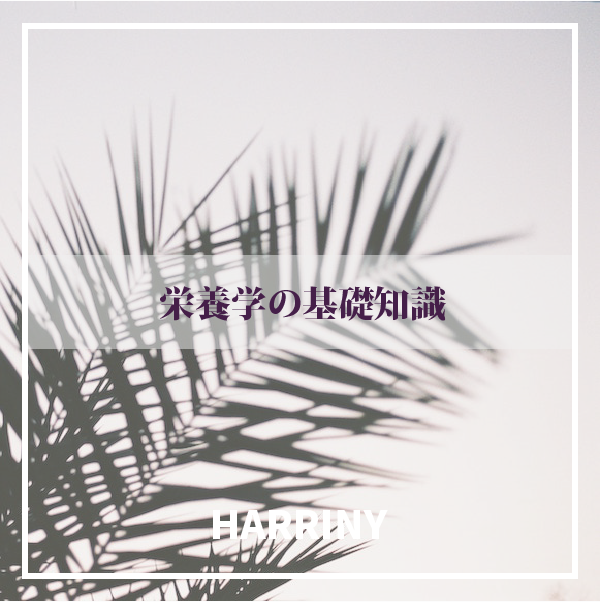
栄養素の中でも特に重要とされているのが3大栄養素がタンパク質、炭水化物、脂質です。私たちの体は、水分を除くとほとんどがタンパク質です。筋肉や骨、内臓、髪の毛、血液など体のあらゆる部分の材料であり、脳の神経伝達物質、ホルモンや免疫細胞、抗体なども全てタンパク質が材料となっています。これらタンパク質、炭水化物、脂質の3大栄養素にビタミンとミネラルを足したものを5大栄養素と言います。
3大栄養素
日本人のタンパク質の摂取量は戦後直後の時代よりも減っており、その原因に豆腐や納豆、味噌といった大豆食品の摂取量が減っていることが挙げられます。タンパク質の摂取量が減ると筋力が落ちるのはもちろん、不眠症や貧血、疲労感、免疫力の低下、肩こりや腰痛など様々な悪影響が現れます。
炭水化物=糖質と思っている人も多いですが、炭水化物は糖質と食物繊維の組み合わせでできています。また炭水化物食品はビタミンやミネラル、ポリフェノールなどの栄養素もたっぷりと含まれています。私たちの健康に悪影響を及ぼすのは、白米やパン麺、白砂糖や果糖ブドウ糖液糖などの精製された糖質の摂りすぎです。精製された糖質は血糖値を急上昇させ、血糖値が急上昇すればインスリンが過剰に分泌されて、逆に低血糖状態になったり、活性酸素が発生して体の酸化を促進させたり、余った糖が脂肪として蓄積されたりします。
脂質は食品に含まれている油脂成分のことです。油自体は、体のエネルギー源やホルモンや細胞膜の材料になったり、生命維持には欠かすことができない栄養素です。この油は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分かれ、抗炎症作用のあるオメガ3や体内の組織を形成するオメガ6は健康に欠かせません。この飽和脂肪酸の中でも中鎖脂肪酸は疲労回復や脳の働きの改善効果が期待できます。一方でラードやバターなどの動物性由来の脂肪酸は、脂肪として蓄積されやすいので摂取量は控えめにしましょう。
5大栄養素
タンパク質、炭水化物、脂質の3大栄養素にビタミンとミネラルを足したものを5大栄養素と言います。ビタミンは3大栄養素と違って体を構成する成分でもエネルギー源でもありませんが、代謝をスムーズに行うために必要を不可欠な栄養素です。
例えば、エネルギーを作るときやタンパク質が体の組織になるとき酵素が働いて化学変化が起こります。この化学変化を代謝と言い、代謝が働くためにビタミンやミネラルが必要になります。ビタミンは全部で13種類あり、脂溶性のビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、水溶性のビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、 ビオチン、葉酸、ビタミンCです。因みに13種類のビタミンの中で体が必要とする量が多い順は、ビタミンC2、ナイアシン、ビタミンEです。ビタミンCやナイアシンは水溶性ビタミンですぐに体外に排泄されてしまいます。
もう一つ私たちの体に欠かせないのがミネラルです。そもそも人は約60種類の元素の組み合わせでできており、内訳は酸素65% 、炭素18%、水素10%、窒素3%です。この4つの元素を組み合わせることで体の96%がつくられ、残り4%の元素がミネラル成分です。中でも健康維持に必須とされているミネラルは 16種類あり、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム、リン、硫黄、塩素、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム、モリブデン、コバルト、これらが必須ミネラルです。ミネラルの働きは様々あり、骨や歯の材料になったり、酵素の成分になったり、代謝を正常化する働きがあります。
また、ビタミンやミネラルの他にも食物繊維やフィトケミカルといった微量栄養素もあります。食物繊維といえば腸活に欠かせない栄養素で、食物繊維は微量栄養素と呼ばれる場合と炭水化物に含めて必須栄養素と呼ぶ場合があります。
フィトケミカルは果物や野菜、豆類、海藻などの植物に含まれている成分で、ビタミンやミネラルとは別の栄養素です。有名なのは人参に含まれてβカロテンやトマトに含まれているリコピンなどのカロテノイド、ブルーベリーに含まれているアントシアニン、大豆に含まれているイソフラボンなどのポリフェノールがフィトケミカルです。基本的にフィトケミカルは抗酸化作用を持っており、果物や野菜、豆類、海藻を積極的に食べている人は寿命が長くなったり、癌になりにくいといった研究結果が世界中で発表されています。
栄養バランスが大切
糖質がまるで人を太らせる悪のように見られがちですが、糖質は生きていくために重要な栄養素の一つであるということを忘れてはいけません。また一種類あるだけではいくら栄養価が高くても体にしっかりと吸収することが困難です。ある栄養素を摂るためにはそれとセットになって働く栄養素を欠かせません。つまり栄養を摂る時には栄養素のバランスを考えることがとても大切になります。一つの栄養素、例えばβカロテンが体に良いからといって、それだけと大量にとっても意味がありません。むしろ一つの栄養素を摂り過ぎることが悪影響を与える場合だってあります。
また和食だけに限らず、洋食の良い点も取り入れて多種多様な食材よって少量ずつバランスよく組み合わせて食べるということが大切です。主食のお米、味噌汁、野菜の煮物という和食が低カロリーで健康的で、洋食と比べてヘルシー、そのようなイメージを持っている人がほとんどだと思います。
しかし健康的な食事は、タンパク質、脂質、炭水化物の3大栄養素をバランスよく摂取できるかどうかで見ることが大事なので、一概にそうとも言い切れない場合もあります。特にご飯に味噌汁、野菜の煮物という内容だとタンパク質や脂質が少なく、理想的な栄養バランスが整っていない可能性があります。
栄養に関する正しい知識
世の中には、重大なリスクが無視されてメリットだけが強調された情報、あやしい健康情報が溢れかえっています。そのため栄養に関する正しい知識を身につけておく必要があります。栄養素の働きや適切な摂取量について知っておくべき事実を確認した上で自ら情報を取捨選択し活用するということが極めて重要です。
しかし、年代性別ごとに1日に必要な栄養素の摂取量は異なり、毎日の食事一つ一つの数値に目を光らせていると大変なので、栄養バランスを整えるコツをおさえておけば必要な栄養素を偏りなく摂取することができるでしょう。
そのコツは、主食、主菜、副菜の3つのお皿をそろえて献立を組むことです。主食はご飯やパンなどから炭水化物、主菜は肉や魚、大豆などからタンパク質と脂質、副菜は野菜や芋、海藻などからビタミンとミネラルなどを摂ります。この3つのお皿を揃えるだけで体に必要不可欠な5大栄養素を満遍なくカバーできるはずです。
また、清涼飲料水などは控えて水を飲みましょう。水は体の機能を保ち、便を柔らかくして便秘になるのを防いでくれたり、血液をサラサラにして脳梗塞や心筋梗塞を予防したりと、健康を支える様々な働きをしています。しかし水をどれだけ飲んでも良いということではありません。水の飲みすぎによって起きるトラブルがあります。
例えば冷たい水の摂りすぎは体を冷やし、胃腸の不調を引き起こすことがあります。また腎臓に負担がかかってむくみが露われたり、多くの女房を出すために血圧が下がる水中毒になってしまったりと水の飲みすぎは健康への深刻な悪影響も心配されます。そのため適切な水分補給を心がけ、摂取量と排出量のバランスを崩さないようにすることが大切です。具体的には、汗や尿、排便によって排出される水分は成人の場合1日約2.5リットルです。水分摂取は、これを基準に食事以外で1.5リットルの水分をとることを目安にすると良いでしょう。ただしコーヒーやアルコールなどの利尿作用の高い飲み物に関しては摂取量より排出量の方が多くなるため、水分摂取量としてカウントはしないで下さい。
また、疲れている時には甘いものを食べると良いとか、疲れているから甘い物が欲しくなるなど、そのような認識が一般的となっているため、そう思っている人は結構多いのではないでしょうか。
それはエネルギー切れによる一時的な疲労に対してのみのことで、むやみに甘いものを食べ続けてしまうと、実はかえって逆効果です。甘いものに含まれる糖質は体内でブドウ糖へと作り変えられて血中に取り込むことで血糖値を上げます。そして上がった血糖値を下げようとインスリンが分泌されます。
つまり糖質を一度にたくさん摂取してしまうと、血糖値が急激に上がってしまい、今度はそれを正常値へと戻すため必要以上にインスリンが分泌されることになります。すると血糖値が急激に低下し、低血糖を引き起こします。低血糖になると脳が働くのに必要な分のブドウ糖が足りなくなり、だるさと疲れいった症状につながります。そして糖質過多の生活を続けていると血糖値の調節が 正常にできなくなり、最終的には常に低血糖の状態になり、自律神経のバランスが乱れ、疲労感、思考力や集中力の低下、イライラや不安感の増加など不調を引き起こします。
また摂取した糖質の代謝がスムーズに行われることも大切です。炭水化物に含まれる糖質はそのままではエネルギーとして使うことができません。糖質は小腸でブドウ糖に分解されることでエネルギー源として使われるようになります。それに働きかけてブドウ糖からエネルギーを算出する手助けをするのがビタミンB1です。つまりビタミンB1が不足してしまうと糖質から効率よくエネルギーを生み出すことができなくなり、脳がエネルギー不足に陥って集中力や記憶力の低下などを招いてしまいます。特に日本人は主食のお米をはじめ、糖質をたくさん摂りすぎているため、ビタミンB1を食事から摂取することを怠らないようにしましょう。
例えばビタミンB1を多く含む食べ物として豚肉、ナッツ、豆類などがあります。またニンニクやネギなどに含まれるアリシンという成分も組み合わせるとさらにエネルギー効率が上がります。逆にビタミンB1不足が慢性化する原因としては、多量飲酒が挙げられます。
このようにビタミンB1は糖質の代謝を助けるビタミンですが、脂質の代謝をサポートするのはビタミンB2です。ビタミンB2には脂質を使って細胞の生まれ変わりや成長を促す働きがあります。また脂質をエネルギーとして燃焼させる手助けもします。つまりビタミンB2をしっかりと摂ることでより脂肪が使われやすい体になります。
また、細胞の再生に関わるビタミンB2は成長期の子供に不足してしまうと、子どもや胎児の発育不良につながります。また粘膜や皮膚、髪の毛や爪の新陳代謝を促す役割もあるため、ビタミンB2が欠乏すると、年齢に関係なく肌荒れや口内炎口角炎などのトラブルの原因となります。
魚・肉・野菜の栄養素
魚(高脂肪魚類)
年々日本人の魚の摂取量が下がっており、2001年には1人当たりの魚の年間消費量が40kgだったのが2020 年には年間消費量が23.4kgにまで減少しています。魚介類は、タンパク質だけではなくビタミンやミネラルの宝庫で、例えば小骨まで食べられる小魚はカルシウムが豊富であり、シジミは鉄分やオルニチン、牡蠣は亜鉛やタウリン、鮎や鰻はビタミンA、青魚はビタミンD がたっぷりと含まれています。特に青魚や鮭に多く含まれているオメガ3脂肪酸は血液をサラサラにしてくれる他、血栓の予防、抗炎症作用、高血圧の予防などに効果があります。
また高脂肪魚類は、いわゆる青魚や鮭、マグロなどの脂質が豊富な魚は、がんのリスクを低下させてくれるということが分かっています。実際、大規模な研究では魚の摂取量が多いほど消化器系がんのリスクが低いことが示されています。また47万8040人の成人を追跡調査した別の研究では、魚をたくさん食べると大腸がんの発症リスクが低下するということが分かっています。脂肪分の多い魚が、がんのリスクを低下させる効果があるのは、ビタミンDやオメガ3脂肪酸などがんのリスク低減につながる重要な栄養素が含まれているからです。
肉
お肉は飽和脂肪酸が多く含まれているため、食べ過ぎれば肥満の元にもなり得ますが、タンパク質を効率よく摂取できる代表的な食材です。タンパク質は体内で長期間貯めておくことができないため、毎回の食事でしっかりとタンパク源を確保しておくことが健康には欠かせません。
また、豚肉には疲労回復効果を期待できるビタミンB群が豊富に含まれおり、牛肉の赤みや羊肉にはカルニチンと呼ばれる脂肪燃焼効果がある栄養素が含まれています。そして鶏胸肉に含まれているイミダペプチドには乳酸を分解して、疲労感を減らす効果や活性酸素を抑えるアンチエイジング効果も期待できます。
野菜
野菜を選ぶときはできるだけ旬を意識するようにしましょう。その理由は旬の野菜ほど美味しくて栄養価が高いからです。野菜を栄養面から分類すると、認知症やがんの予防効果で注目を集めているキノコ類、強力な抗酸化作用で体の老化を防いでくれる赤い野菜、ベータカロテンや葉酸が豊富で抗酸化作用が強い緑の葉っぱ、ネバネバで血糖値を正常に保つ働きをしてくれるヌルヌル系の4つに分けることができます。食事はできるだけ多くの食材をバランスよく食べることが健康の秘訣なので、これら4つからピックアップして食べましょう。
腸活食品がお腹に合わない
お腹の不調を持つ日本人の数は約1700万人にも上ると言われています。お腹が張ったり、便秘や下痢、おならが止まらないなどの症状に苦しむだけでなく、腸の不調は肌の状態にも悪影響を及ぼします。
そのため腸に良い、納豆やヨーグルトや発酵食品を食べることを心掛けている方も多くいますが、こうした腸活食品がお腹に合わない方もいます。腸活をすればするほどむしろ腸内環境が悪化していくタイプの人います。あらゆる健康法に言えることですが、多くの人が実践する健康法が全く合わないということがよく起こります。
腸活を続けていても一向に腸内環境がよくならない方は、まずは悪玉菌の餌になる糖質の摂取を控えることが大事です。腸内環境には、悪玉菌、日和見菌、善玉菌の3種類が存在していますが、悪玉菌が便秘や下痢を引き起こしたり、おならの原因となるガスを大量に発生させたりする菌です。ただ最近では悪玉菌が悪さだけをするわけではないということが分かっているので、完全に悪玉菌を排除してしまえば良いというわけではありません。
悪玉菌の餌となり、腸内環境を悪化させるのは高カロリーかつ糖質過多、脂質過多な食事、つまりジャンクフードです。またフルーツジュースを含め、甘い飲み物や甘いお菓子というのは腸内環境を乱します。当然ながら加工食品もNGです。
また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品や野菜に含まれている水溶性食物繊維は、確かに健康に良い腸活食品です、腸が整っている人であればこれらは善玉菌の餌となって腸内で有効に働いてくれるはずです。しかし腸が弱っていて、悪玉菌優勢の人の腸にこれらの餌が入ってくると、悪玉菌が増加し大量のガスを発生させてしまいます。
このように小腸で吸収されづらく大腸まで届いてしまい悪玉菌の餌になってしまう糖質をFODMAPと言います。FODMAPは、腸内で吸収されにくいという性質を持っているため腸内に糖質がどんどん溜まっていくことになります。その結果、腸内の糖質の濃度が上昇することになり、ドロドロの糖質たっぷりの液体が小腸内に溜まり、その液体を薄めようと血管からどんどん水分が小腸の中へと流れ込んでいくことになります。それが下痢になってしまいます。
そして、そのまま大腸へと向かうと今度はその糖質を悪玉菌が爆食することになります。すると大量のガスが発生し、お腹が張るといった症状やおならが止まらないという症状、また腸管がうまく動かなくなり便秘になってしまうという人も出てきます。
腸内環境改善の手順
腸内環境を改善するためには明確な手順があります。それは善玉菌優勢の環境を作る、そして善玉菌を増やす2ステップです。これを理解しないまま食物繊維が豊富な食品を食べても、悪玉菌がそういった餌を食べてしまうためあまり意味がありません。
今日から野菜を食べるぞと多少野菜を多く食べたところで腸内環境というのは良くなりません。特に悪玉菌が多い方の特徴としては便やおならの匂いが強いことです。まず、腸内環境を根本的に作り変えるためにプロバイオティクスサプリを摂取することがお勧めです。あまりサプリはお勧めしてはいませんが、腸内環境が乱れている場合は整腸剤や腸活サプリを継続的に摂取して腸内環境の改善を図りましょう。
その後、水溶性食物繊維を中心に腸内細菌の餌となる食品を食べましょう。また便秘に悩んでいる人は、低FODMAPを試す前に不溶性食物繊維を摂りすぎていないかをチェックしましょう。不溶性食物繊維は便の傘を増して、便秘の原因になることがあります。不溶性食物繊維を減らして水溶性食物繊維を増やすことで便秘を解消することができます。不溶性食物繊維が豊富な食材は、ブロッコリー、オクラ、さつまいも、ごぼうといった野菜、しいたけなどのキノコ類、枝豆、大豆、おからといった豆類です。
2種類の食物繊維
昔から食物繊維を摂ると体に良いと言われてきましたが、最近では何でもかんでも食べれば良いというわけではないことが分かっています。食物繊維は大きく分けて不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。この2種類の食物繊維をバランスよく摂取することが腸内環境の改善のために重要です。
不溶性食物繊維は緑色の野菜に含まれている食物繊維で、不溶性食物繊維の名の通り水に溶けることができないため、便の傘を増してくれる働きがあります。一方で水溶性食物繊維はその名の通り水に溶けることで便通を良くしてくれます。水溶性食物繊維は便が通りやすくなるための循環油の働きをしていると考えれば分かりやすいでしょう。
厄介なのが水溶性食物繊維をたくさん含んでいる野菜というのはあまり多くありません。一般的に食べられる緑色の野菜のほとんどは不溶性食物繊維を含んでいます。一方で水溶性食物繊維はごぼうをはじめとする根菜や海藻などに含まれています。
植物性の発酵食品
腸内細菌にもってこいの食材が植物性の発酵食品です。お腹の健康のために乳酸菌を摂取すると良いと言われていますが、乳酸菌には動物性乳酸菌と植物性乳酸菌の2種類があります。最近、動物性乳酸菌は経口摂取ではあまり腸の健康に効果がないと言われるようになってきました。ヨーグルトをはじめとする動物性の発酵食品に含まれている乳酸菌が動物性乳酸菌で、腸に届くまでに胃酸などによって分解されて死んでしまうことが明らかになっています。
一方で、漬物をはじめとする植物性の発酵食品が持つ乳酸菌を植物性乳酸菌と言いますが、こちらは胃酸などで分解されることなく生きたまま腸に届かせることができると言われています。
また、お肌と腸内環境の関係は非常に密接で、腸内で悪玉菌が優位になってしまうと悪玉菌が放出する毒素やガスが血液中に溢れ出します。血中に漏れ出した毒素が体中の様々な細胞に蓄積、やがて皮膚の表面にも現れます。こうして皮膚の表面に出てきた毒素がシミやそばかすといったお肌のトラブルの原因になっていると考えられています。
発酵していないキムチ
発酵食品として有名なキムチには、植物性の乳酸菌がたっぷりと含まれていて腸内環境を改善し、体の中から若返るという素晴らしい健康効果があると分かっています。しかしキムチには、発酵という超重要な過程を経ていないものがあります。本物のキムチというのは、白菜に天然の調味料を加えて壺漬けにし1週間ほど乳酸発酵して作られます。最近日本ではこのような発酵を経ていないキムチが売られています。
それはキムチ風の調味料に、安い白菜を漬けたものです。もちろん偽物のキムチは発酵していないため、当然最も体に良い成分である植物性乳酸菌が含まれておりません。実は恐ろしいことに日本の法律では食品表示に植物性乳酸菌が含まれているかどうかを表示する義務がなく、また発酵を経たかどうかを表示 する義務もありません。そのため見た目では、発酵されているかどうかを判断することができません。
本物の発酵キムチは、古くからの伝統的な製法によって作られているので原材料の内訳が非常にシンプルであるという特徴を持っています。白菜や唐辛子、ニンニクなど体に良い健康的自然食品だけで作られていることが特徴的です。一方で偽物のキムチにはキムチ風の味を出すために発酵調味料や増粘剤といった食品添加物が多分に含まれているケースが多々あると言われています。このような自然ではない添加物が含まれていたら、発酵されていない偽物のキムチである可能性があると疑ってかかるべきでしょう。
玄米の健康効果
玄米には大きく2つの健康効果が期待できます。その効果に低FODMAP食で不足しがちな食物繊維を摂取できる、短鎖脂肪酸の中で酪酸だけを増やすことができることが挙げられます。実は玄米は他の短鎖脂肪酸は増やさずに酪酸だけを増やすという珍しい食品です。
主な短鎖脂肪酸は酢酸、プロピオン酸、酪酸の3つですが、一般的には酢酸やプロピオン酸も健康や美容に良いとされていますが、腸の調子が悪い人にとっては害になることもあります。なぜなら過剰な酢酸やプロピオン酸は腸の粘膜のバリア機能を低下させ、そのため腸に穴が開いて血中に毒素が入り込むリーキーガット症候群や過敏性腸症候群の症状が悪化してしまうことが分かっています。
一方で、酪酸には腸の粘膜のバリア機能を高めてくれる他にも、免疫機能の改善に役立ち、全身の炎症を抑えてくれるという様々な効果があります。そのためできる限り酢酸やプロピオン酸の量は減らして、酪酸だけを増やす最適な食材が玄米です。
有機食品の新常識
最近ではスーパーなどで有機食品を見かける機会が多くなってきました。僅かな値段の差であれば、有機マークの付いた方を選んでいる方もいると思います。そこには、有機食品が体にとって良いと思っているからでしょう。
この有機とは、非常に複雑なため定義が難しく、多くの方がイメージとして、小規模農家が地元で生産していて、殺虫剤、除草剤、抗生物質や合成肥料は一切使用されず、もちろん遺伝子組み換えなどないでしょう。また有機認証を取るために時間や努力、そしてコストがかかるため有機食品はどうしても高価になってしまいます。
この有機食品の消費量は増え続けており、有機というマークをつければ売れるため、すでに大企業が参入し、一般的な食品との価格差が縮まったことにより、さらに売れ行きが良くなっています。
しかし、食の健康に関しては有機食品が非有機食品よりも優れているという科学的根拠は殆どないという研究があります。2012年に医学誌で発表された研究では、スターフォード大学の研究者たちが1996年から2009年の13 年間のうち、医学文献に発表された有機食品と非有機食品を比較したすべての研究データを総括して評価しました。223件の評価では含まれる栄養素において有機食品と非有機食品の間に意味のある違いが見出されませんでした。また両者の汚染物質の濃度についても大きな違いは認められませんでした。
さらに同じ研究者たちは他にも14の異なるグループ、述べ13802以上の被験者を対象とした研究を分析し両者の健康への影響を調べましたが、健康増進効果や疾患予防効果などの影響は見られませんでした。
実はこのスタンフォード大学の研究者たちによる研究レビューに対する意見とも見られる研究も医学誌に掲載されています。そこでは有機果物や野菜は非有機のものよりも抗酸化物質がかなり多く含まれ、合成殺虫剤の濃度が低いという点を裏付けとし、有機食品が安全で栄養価が高いと主張されています。
抗酸化物質には、ビタミン、βカロテンなど様々な種類があり、異なる部位で異なる作用をします。これらの名称を聞くと誰もが摂取すると身体に良いというイメージを持つかもしれません。しかしながら抗酸化物質を摂取すれば健康がはっきりと改善するという科学的根拠はなく、残念ながら抗酸化物質の健康改善効果や病気予防効果については一貫した研究結果が得られていません。そしてその研究に用いられた抗酸化物質は有機食品を食べることで得られると予想できる量を遥かに超えていました。そのため、それよりも少ない量の抗酸化物質を食事で得て、健康効果が発揮されるのかは疑問視する声も多くあります。
一方で、有機食品は有機食品より抗酸化物質が少なく、残留殺虫剤が含まれていることが数値として出されていますが、しかし人の健康にどのように影響するかという数々の研究結果からすれば、ほとんど意味をなさない程度と言われています。ちなみに別の医学誌等は有機農作物のタンパク質含有量が非有機農作物よりもかなり少ないことが発表されております。
何れにせよ非有機食品でも健康的な食事はでき、有機食品が占める割合は、アメリカでもまだ4%、欧州でも10%、日本ではそれよりも少ないはずです。そのため有機食品がないから食べないのではなく、非有機食品であってもしっかりと栄養バランスを考えて摂ることが大切でしょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。