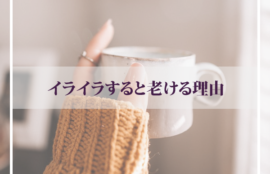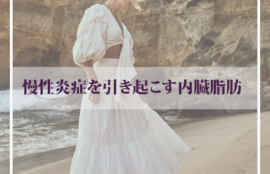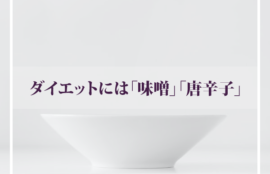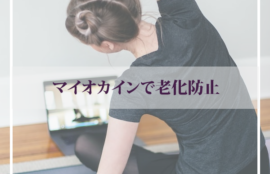炭水化物(糖質)中心の生活がもたらす危険性を指摘した論文がランセットという医学雑誌に掲載され世界中が衝撃を受けました。
この研究は世界18カ国、合計13万5千人を対象として10年かけて食事のバランスと死亡や生活習慣の関係を調査したものです。結論は炭水化物の摂取量が多いグループほど死亡率が高いということです。また脂質の摂取量が少ないほど死亡率が高く、脳卒中の発生率も高いことも分かっています。
また、カロリー制限がダイエットにも血糖値のコントロールにも良いというのは間違った考えです。糖質が肥満と糖尿病の原因であり、痩せるためには糖質制限をする以外の方法はあり得ません。
炭水化物(糖質)で太る理由
太るのは脂肪が原因であり、カロリー制限をすることが必要という常識がありますが、これは間違った結論が世界中に広まった結果です。アメリカの糖尿病学会では、現在は糖質こそ肥満と糖尿病の原因であるとの見方に修正されています。
糖質を必要以上に摂ると、その余ったブドウ糖はグリコーゲンに替えられ、筋肉や肝臓に貯蔵されていきます。そして貯蔵できなくなると脂肪として体内に溜め込みます。つまり糖質を摂りすぎてブドウ糖が余ると太るのです。
逆に糖質を制限するとエネルギー源であるブドウ糖が不足しますが、脂肪(β酸化作用)を燃やしてエネルギーとして使います。結果として痩せていくのです。
古来、人は脂質やタンパク質を摂って生きるようにできていたはずなのに、特に糖質の過剰摂取により肥満や糖尿病などの生活習慣が多発するようになったのが現代人の特徴です。
また糖質が辞められない理由は、脳にあります。糖質を摂って血糖値が上昇すると、ドーパミンやセロトニンが放出され、脳が快楽を得ます。この脳の快楽によって、体が糖質を必要していない時でも、糖質を求めてしまいます。これを糖質中毒と言い、脳が快楽のために糖質を摂ること命令して、自己制御できなくなるのです。
糖質制限しても体に悪影響はありません。人の体は糖質がなくても、筋肉や肝臓に摂り込まれていたグリコーゲンを分解して、ブドウ糖に戻して血中に放出しエネルギー源とします。それが無くなると、中性脂肪がエネルギーとして使われ、一部がブドウ糖として血中に戻されます。この中性脂肪が使われることで痩せていくのです。
注意するべき点は、ダイエットのため、フルーツジュースを朝一杯だけ飲んでいる方いらっしゃいますが、その含まれる果糖はGI値が低いにも関わらず、肝臓でしか代謝できないという性質があります。つまりその他の糖に比べて太りやすいということです。そのため食物繊維などの有効成分と一緒に摂取することが必要なのですが、フルーツジュースにした時点で食物繊維が失われているため、研究によると糖尿病のリスクが上がることが指摘されています。
糖質制限する時に注意する点
糖質を制限する時に、糖質を減らす分、タンパク質と脂質を沢山摂ることが必要です。その時にプロテインなどの人工的な大量のタンパク質を飲むべきではありません。摂りすぎてしまうと腎臓に負担がかかります。なるべく普段の食事から摂るようしましょう。特にタンパク質よりも脂質を6割程多く摂るように心掛けましょう。
糖質制限をして体調不良になってしまうケースの殆どは、糖質制限しただけで、タンパク質と脂質の量が変わらないため、体に必要なエネルギーが不足してしまうからです。しかしながらどの程度の糖質制限するが良いのかは、個々の生活環境などバラバラなため、不調気味だなと思ったら糖分を補給するなどしてまずは試しながら糖質制限することをオススメします。
また、糖質制限により、肉や脂質の食事量が増えて、コレステロールが高くなるという俗説もありますが、これも間違った考え方です。研究によれば、肉や脂質の摂取量が増えても、糖質制限することで、悪玉コレステロールの値が、善玉コレステロールに対して相対的に低くなることが分かっており、むしろコレステロール値は改善するのです。またコレステロールの大部分は肝臓でつくられるため、沢山食べても肝臓がそのバランスを調整してくれ、コレステロールが上昇することはありません。
ダイエットと低血糖
糖質制限という言葉が一般的になり、血糖値が上がりすぎるのはダイエットだけでなく、健康に良くないこともご存知であると思います。血糖値が上昇によって、インスリンが分泌され、その反動で低血糖になってしまう血糖値スパイクが様々な問題を体に引き起こします。
一方で、インスリンは血糖値を下げるだけでなく、脂肪を蓄積するという働きがあります。糖質制限ダイエットは、血糖値を上げないようにすればインスリンが出ずに太らないというものです。しかし低血糖状態は、体を動かすために必要なエネルギー源が少なくなってしまった状態であり、低血糖になると体は食欲を強めたり、無駄にエネルギーを使わないように代謝を下げたりしてしまいます。
つまり、血糖値は上がりすぎるとインスリンが過剰に分泌されて脂肪が付きやすくなり、血糖値は下がりすぎると食欲や代謝が乱れて痩せにくくなる関係があります。多くの人が血糖値の上がり過ぎには気を使いますが、実は血糖値の下り過ぎによって食べ過ぎてしまうことがダイエットに失敗する原因になっていることがあります。
糖質制限で夜間低血糖
このように適度な血糖値の上昇は、食欲を抑えたり代謝を上げたりすることにも繋がります。そのため血糖値を適正範囲内で抑えるということが大切です。
具体的には、約80mgから140mg/dLの間が低血糖と高血糖の問題が起こりにくい血糖値の範囲です。例えば血糖値が60から70になると、甘いものへの欲求、冷えやイライラなどの低血糖の症状が現れます。逆に高血糖になると糖化や酸化のリスクが高くなると言われています。
そして、ダイエットにおいて問題なのが、夜間低血糖です。その通り寝ている時に血糖値が下がってしまう状態ですが、夜中に目が覚める、歯ぎしりをする、悪夢を見るといった問題が起こります。なぜなら低血糖は、体にとって危機的な状況なため、それを回避しようと体を興奮させるアドレナリンが作られて、体が緊張状態なります。つまり夜間低血糖になると睡眠の質が低下します。その結果、食欲と代謝に関わるグレリンとレプチンというホルモンのバランスが崩れて、食欲や代謝が乱れてしまいます。
バランスの良い食事と睡眠
タンパク質や脂質、食物繊維には血糖値を抑える働きがあり、例えばタンパク質や脂質には血糖値を抑えるインスリンの分泌を促す働きがあります。そして食物繊維には、糖の吸収を緩やかにするという作用があり、糖質単体で食べるよりもタンパク質や脂質食物繊維を一緒に取る方が血糖値の上昇は緩やかになります。
一方で、寝不足やストレスが血糖値のコントロールに関わるコルチゾールの分泌を不安定し、血糖値が上がる原因になります。寝不足やストレスを受けると、コルチゾールがたくさん作られますが、そのコルチゾールを作る副腎という臓器が疲弊して、やがてコルチゾールを作らなくなります。このように寝不足やストレスによって血糖値が不安定になることが多く、睡眠を改善するだけで血糖値が安定することが多くあります。
さらに、ビタミンとミネラル不足が血糖値に影響しています。ビタミンC、B、亜鉛、マグネシウムは血糖値のコントロールのために重要な栄養素です。これらの栄養素は不足しやすく、かつコルチゾールの産生に深く関わっています。コルチゾールは腎臓の上にある副腎というところで作られています。寝不足やストレスなどによって低血糖になると、脳から副腎にコルチゾールを作る司令が届き、血糖値が上がります。その副腎の働きに必要な栄養素がビタミンC、B、亜鉛、マグネシウムの4つです。
甘いものを食べたい理由
甘いものを欲する原因は、カロリー不足です。食べる量が少なくてカロリーが不足していると甘いものを過剰に欲するようになります。なぜなら体は手早くエネルギー不足を解消したいからです。基本的にカロリー計算は必要ないですが、カロリー不足の可能性がある人は、カロリー計算をするようにしましょう。
また、過度な糖質制限、もしくは太るからと夕食の炭水化物を抜くと甘いものを食べたくなります。なぜなら体は、カロリーが足りていても、糖質が不足していたら甘いものを欲するからです。糖質制限して、タンパク質や脂質をしっかり取っていても、主なエネルギー源は糖質です。さらに糖質制限で、低血糖になると甘いものを過剰に欲するようになります。低血糖の症状には、異常な空腹や手足の冷え、イライラ、脱力感、夜中に目が覚めるなどが挙げられます。
そして、睡眠不足も甘いもの欲する原因になります。なぜなら寝不足は、食欲に関わるホルモンのバランスを崩してしまうからです。食欲は、レプチンと呼ばれる食欲を抑えるホルモンとグリリンと呼ばれる食欲を強めるホルモンのバランスによって作られています。寝不足になるとレプチンが少なくなってグレリンが増えてしまうということが明らかになっています。また寝不足になると自律神経のバランスが崩れて低血糖になりやすく、疲れやストレスも感じやすくなり、甘いものを欲するようになります。
一方で、女性は鉄不足には注意するようにしましょう。鉄は、炭水化物や脂質などの栄養素からエネルギーを作り出す過程で必要不可欠なミネラルであり、エネルギー源となる食べ物をたくさん食べてもそれがエネルギーに変換されなければエネルギー不足になります。
さらに、亜鉛不足も甘いものを欲する原因になります。なぜなら亜鉛が不足すると味覚が鈍り、刺激が強い甘味が欲しくなります。例えばサラダなど味が薄いものにドレッシングなどをドバドバとかけているなどは、亜鉛が不足している可能性が高いです
最後に疲れ、不安、ストレスも甘いものを欲する原因になります。なぜなら体や脳は疲れをエネルギー不足と解釈するからです。慢性的に疲れを感じている人は、疲れて甘いものを食べている可能性が高いです。不安やストレスも甘いものを欲する原因の一つになります。なぜなら甘いものを大量に食べると、一時的にストレスや不安が軽くなるからです。甘いものを大量に食べるとドーパミンが脳内で作られ、モヤモヤやイライラが軽くなります。さらにドーパミンだけでなく、幸せホルモンのセロトニンの分泌を促すことが分かっています。
コーヒーと甘いスィーツで太る
コーヒーに含まれるカフェインの作用に基礎代謝が上がる効果があります。カフェインを摂取すると交換神経が刺激され、基礎代謝が促進されます。標準的な運動量の場合最もカロリーを消費するのは基礎代謝であり、基礎代謝は1日の総消費カロリーの約60%を占めています。つまり基礎代謝を上げることがダイエットに大切なことになります。またカフェインは脂質の代謝を促進すると言われています。
そして、コーヒーにも食べ合わせがあります。コーヒーには、甘いお菓子が合いますが、それは良くない組み合わせです。実は甘いものは食べ過ぎると中性脂肪に変わりますが、カフェインは糖質がエネルギーに変わる前に中性脂肪に変えてしまう働きがあります。その結果、血液がドロドロになり、その上に苦みのあるコーヒーと甘いものの組み合わせは、甘いものを食べ過ぎてしまう可能性も高くなることが分かっています。またチョコレートにもカフェインが含まれており、カフェインの摂り過ぎになる可能性もあります。
そしてコーヒーに相性の良い食べ合わせがバナナです。バナナにはビタミンB、必須アミノ酸、食物繊維など様々な栄養が入っており、コーヒーと一緒に摂取することで便秘が解消する効果が期待できます。他にも代謝がアップして美肌効果もあります。他にも豆類(ナッツ、ピーナッツ、落花生、アーモンドなど)、特にアミノ酸のアルギニン酸が豊富な食品と一緒に摂るのが良く、体脂肪の減少に効果的です。
甘いものに依存する理由
糖質の過剰摂取は、体内の慢性炎症、片頭痛、不眠症、歯周病、心臓病、免疫低下、腎障害、不安やイライラ、糖尿病などありとあらゆる不調を引き起こす原因になります。糖質が恐ろしいところは、体へのダメージがゆっくりと進み、気がついたら糖尿病になっていた、老化が進んでいたなどなど取り返しのつかない事態になって始めて気づくことでしょう。
この糖質は、中毒になる可能性が非常に高い物質と言われ、アルコールやニコチンなどの依存性物質と同じように、脳や神経を変化させてしまう物質です。糖質は、薬物と同じように欲求や快楽を司る神経伝達物質のドーパミンを脳内に溢れさせます。ドーパミンは心地いい気持ちにさせてくれるため、その快楽を忘れることができずさらなる欲求を満たそうとドーパミンの分泌を求めて、糖質を取りたいという衝動にかられてしまいます。
さらに、糖質を食べると血糖値が急激に上がってしまうため、血糖値を一定に保とうとインスリンが分泌されます。インスリンは急上昇した血糖値を下げて糖質を細胞内に取り込ませてエネルギーに変換する働きをしてくれます。しかし糖質を摂取しすぎるとインスリンは、満腹を感じるホルモンであるレプチンをブロックし、何度もブロックされるとレプチン抵抗性を引き起こし、満腹を感じられなくなってしまいます。その結果、毎回の食事で食べ過ぎてしまうようになります。
一方で、余計に分泌されたインスリンは、脂肪の燃焼を止めて、脂肪を蓄積し始めるという厄介な作用まであります。だからこそ糖質制限の一番の効果は、内分泌系の働きを正常に戻すこと、つまりレプチンとインスリンの働きを元通りにすることに他ならないのです。
体内の糖質の量を減らせばインスリン値が正常に戻ります。インスリン値が正常に戻れば、レプチン抵抗性が解消されて満腹を感じるようになり、自然と食べ過ぎになることをやめることができます。このような糖質制限のメリットは多くのダイエット本で述べられていますが、糖質の依存性に対する対策についてはほとんど触れられていません。糖質依存から抜け出すには行動を変えていく必要があります。
糖質制限を続ける技術
糖質依存は、物質への依存と行為への依存の2つの依存があります。前者は、ドーパミンを分泌してくれる白いご飯や麺類、甘いお菓子などのおいしい食べ物に対する依存のことです。後者はなんとなく冷蔵庫を漁ってしまう、朝にコンビニに 立ち寄るのが習慣になっている、仕事帰りにコンビニでスイーツを買うなど、その行為自体に依存してしまっていること状態のことです。
そもそも、糖質制限が続かないのは、自分の意思の弱さではなく、糖質が神経伝達物質や内分泌系に作用して依存性を発揮してしまう物質だからです。糖質制限を続けるためには、単純な意志の力で行うのではなく、テクニックが必要となってききます。
一度、甘いものを食べたくなったら、糖質を食べるまで収まらないような気がしてきますが、実は糖質依存の症状は一時的なものです。大抵の場合、数十分もすれば甘いものを食べたい、ラーメンを食べたいと言った糖質への渇望は消えていきます。その最も効果的なテクニックは、額や首を冷したり、腹式呼吸を行うことです。
大きな不安やストレスを抱えている時、私たちは本能的な行為に走ってしまい、糖質という簡単に不安やストレスを解消してくれる依存性のある食べ物に頼ってしまいます。この時に、不安やストレスを食べ物に頼らずに解消するためには、心を落ち着かせる神経系である「副交感神経」を活性化させることが必要になります。副交感神経を刺激することで、血圧と心拍を抑えるホルモンが分泌され、欲望に逃げることなく気持ちを落ち着かせることができます。その副交感神経を刺激するテクニックとして有効なのが、冷たさを使うことです。
例えば、冷たいタオルを額、首、まぶたなどに押し当てると血流が脳や心臓に集まり、呼吸や心拍が落ち着き、呼吸や心拍が下がってくると、興奮状態の感情が落ち着きリラックスすることで、暴飲暴食をしたいという気持ちも薄れてきます。
また腹式呼吸を組み合わせることで副交感神経を活性化させることができます。
それでも糖質制限にチャレンジ
日本食は健康的というのも間違った考えです。36年間に渡り日本各地の長寿者が多い村と短命者が多い村を調査した東北大学近藤名誉教授によると、白米を沢山食べているほど短命であると著しています。
効果的に糖質を抑える最も簡単な方法はご飯、パン、麺類などの主食を食べないことです。肉や魚などのタンパク質を多く含む主菜を食べること、オススメは余分な脂肪のない赤み肉です。和牛の霜降り肉のように人工的に太らせたお肉はNG、魚は刺身などシンプルに食べるのが正解です。また豆腐のような植物性タンパク質の大豆製品を摂りましょう。
また、脂質はエネルギー源だけでなく、細胞膜の生成としても欠かせない要素です。良い脂質として、不飽和脂肪酸の「オメガ3」と「オメガ9」の摂取が推奨されています。オリーブオイルや青魚に多く含まれていますので、野菜類と一緒に食べましょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。