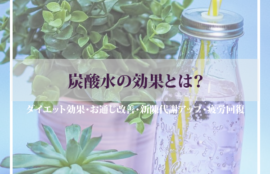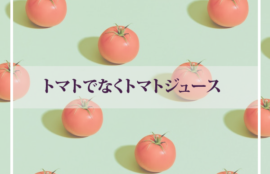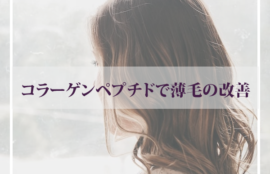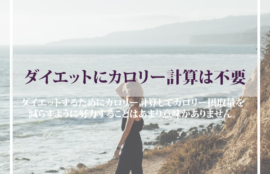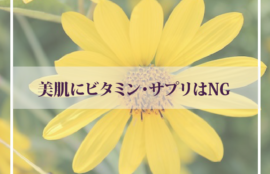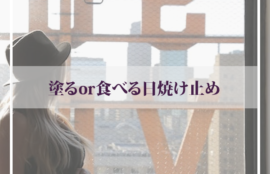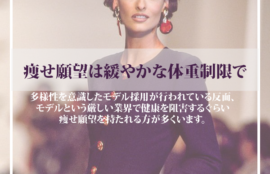タンパク質の力でダイエットに成功し、自律神経や腸内環境も整い、免疫力も向上して、美肌効果や健康的な体を維持することができます。近年、タンパク質の重要性が認識されつつありますが、どうしてタンパク質が重要なのかを理解している方はまだまだ少数です。
私たちの体は主に水分、タンパク質、脂質、ミネラルの4つの成分と微量の糖質の組み合わせでできており、それらが組み合わさって筋肉、内臓、骨、脂肪を形作っています。タンパク質の役割は、エネルギー源となること、体の組織をつくること、体の機能調節・恒常性を維持することです。特に体の各種機能を担っているもの自体がタンパク質でできているため、タンパク質が不足するとそれらがうまく機能しなくなってしまいます。
また、食べ物から摂り入れた脂質や糖質は余分になれば体脂肪として蓄積されます。しかしタンパク質はほとんど貯めておくことができず、エネルギーとして消費されたり、尿として排出されてしまいます。さらにタンパク質はターンオーバーによって少しずつ失われていきます。つまり外から補充を十分に行わなければ結果的に体の部品であるアミノ酸が不足し、タンパク質をつくることができなくなってしまいます。
ダイエットにはタンパク質
ダイエットには糖質や脂質の摂取量、カロリー量などを考えるかもしれません。摂取カロリーより消費カロリーを上回ることを考え、食事制限で摂取カロリーを下げたり、運動で消費カロリーを上げたりします。しかし食事制限や偏食によってタンパク質量が不足すると体内の筋肉が減少し、基礎代謝が下がり、燃費が悪い痩せにくい体になってしまいます。
体の総エネルギー消費量の6割から7割は基礎代謝が占め、つまりどれだけ運動しても基礎代謝が落ちていては十分にエネルギーを消費することができなくなります。この基礎代謝を増やす方法は筋肉量を増やすことです。体型や年齢に見合った標準的な筋肉量を維持することが大切で、年を取れば取るほど筋トレや運動をきちんと行って筋肉量を維持する必要があります。
筋トレには、ジムに通って運動ではなくても大丈夫です。アスリートでない一般的な人の筋肉合成にはウォーキング程度の軽い有酸素運動で十分です。何よりも心がけることは歩くことです。この歩くことにプラスして意識しないといけないことが適切なタンパク質量の摂取です。
タンパク質の基準は、体重×1g/日ですが、ざっくり手のひら一枚分のタンパク質を摂りましょう。例えば鶏肉手のひら1枚分、牛肉手のひら1枚分です。ただし1日必要なタンパク質摂取量は、1日3等分にわけて摂取することが大切です。タンパク質は一度に代謝できる量が決まっており、まとめて摂っても余ってしまうと排出されてしまうからです。またプチ断食を実践している人は、食事可能な8時間の間にヨーグルト、チーズ、納豆、ゆで卵など気軽に摂取できるタンパク質源をこまめに補給しましょう。
このようにタンパク質の摂取は筋肉量の増強だけでなく、基礎代謝量の増加にもつながるためダイエットに効果的です。
ダイエットのための栄養素
タンパク質のカロリーは1gあたり4kcalであり、脂質は9kcal、糖質4kcalです。脂質と比べるとタンパク質のカロリーは半分以下、糖質と比べても血糖値を上げにくいという利点があります。血糖値は糖質を含んだ食材を摂取した時に上がり、血糖値の急上昇は血糖値スパイクと呼ばれ、肥満の原因になります。さらに食べ物を分解する時に消費されるエネルギーが糖質や脂質に比べて非常に高い性質を持っています。この消費エネルギーを食事誘発性熱産生(DIT)と言い、タンパク質の値は糖質の5倍、脂質の30倍にもなります。
このようにタンパク質は、脂質の半分以下のカロリーで、血糖値を上げにくく、食べるだけで消費するエネルギー量が多いため脂肪を燃焼しやすく、食欲を抑える効果があり、まさにダイエットのための栄養素でもあります。
余談ですが、タンパク質の摂りすぎが腎臓に良くないと意見がありますが、現時点では摂りすぎによって腎機能が低下するかどうかについては科学的な根拠はないと考えられています(厚生労働省、医師、研究者など)。腎臓に悪いという根拠は、あくまで慢性腎臓病の方のように腎機能が低下している人を対象にした研究です。またタンパク質を多めに摂って筋トレをする方は、健康診断でクレアチニン値が高く出ますが、これは筋肉量の多い人はクレアチニン値が高く出る傾向があり、腎機能に悪影響が出ている証拠にならないと考えられています。
タンパク質のゴールデンルール
タンパク質には動物性タンパク質と植物性タンパク質があり、その摂取割合にはゴールデンルールがあります。理想的に摂取量の割合は動物性7、植物性3と言われています。
動物性タンパク質には、体内で産生できない9種の必須アミノ酸を含む、全20種類のアミノ酸がバランスよく含まれています。さらに吸収率が95%以上であり、筋肉や臓器など体の材料になるタンパク質を最も効率よく摂取できます。ただし肉の種類や部位によっては脂質オーバーになりやすい側面があります。
植物性タンパク質は、必須アミノ酸を十分に含んでいない食材もあり、吸収率は80から85%程度ですが、脂質が圧倒的に少なく低カロリーで脂肪燃焼の効果を高める働きがあります。中でも納豆は優秀な植物性タンパク質であり、発酵性食物繊維を多く含み、腸の働きを助け、「やせ菌」を増やしてくれる効果があります。
次にタンパク質の摂取する時間は朝夜が効率が良い時間帯と言われています。朝にタンパク質を摂るメリットは、アミノ酸スコアの高い、高タンパクな食事を摂ると、BCAAと呼ばれる筋肉エネルギー源となる3つの必須アミノ酸の影響で、その後ウォーキングなどの軽い運動をした際に、効率的に筋肉を増やすことができるからです。またタンパク質には幸せホルモンのセロトニンや、睡眠ホルモンのメラトニンの元になるトリプファンが含まれているため、朝に摂取しておくと自律神経のバランスが整い、質の良い睡眠につながります。
その他にもタンパク質は朝食に食べるべきという理由は、タンパク質は糖質や脂質と比べて熱として消費されやすく食事誘発性熱産生が高いからです。つまり朝食できちんとタンパク質を摂ることでエネルギー代謝が良くなり太りにくい体をつくることができます。また食事と食事の間隔が最も開くのが睡眠を挟む夕食と朝食間であるため、体内のタンパク質量が減少し筋肉の合成よりも分解の方が優位になるからです。つまりタンパク質量が減少しているタイミングでタンパク質を補給することが大切なのです。
夜にタンパク質を摂るメリットは、タンパク質には成長ホルモンの分泌を促進させるアミノ酸の一種アルギニンやオルニチンなどの物質が含まれているからです。成長ホルモンの役割は、代謝や免疫、認知などに関わる重要なホルモンであり、骨の形成やタンパク質の合成を促す役割があり、体脂肪を減らす、肌のターンオーバーを助けるなど、アンチエイジングにも欠かせないものです。この成長ホルモンは主に睡眠中に分泌されるため、寝る前にタンパク質を摂取しておくことで、効率的に分泌を増やすようになります。
タンパク質ダイエットと腸活
そしてタンパク質ダイエットには腸活が欠かせません。なぜならタンパク質を意識して摂取量を増やすと、腸内環境が乱れるケースがあるからです。腸内環境は痩せやすさと大きく関係しており、動物性タンパク質は消化される際に悪玉菌のエサになる窒素を生み出し、腸内の悪玉菌を活発にします。動物性タンパク質に偏った食生活が続くと悪玉菌が増加し腸内生態系全体のバランスが崩れてしまいます。またタンパク質はほとんどが栄養成分として吸収されてしまうため、食物繊維が不足して便のかさが増えず、腸の蠕動運動が起こりにくくなり便秘の原因になります。
さらに腸の働きは、食べ物の消化、吸収、排泄だけでなく、血液の質にも大きな影響を与えています。血液は肺から取り込んだ酸素と腸から摂りこんだ栄養を乗せて全身の細胞に運ばれます。腸内細菌のバランスが乱れて腸の機能が低下すると、質の悪い血液がつくられ、細胞は質の悪い血液が運んできた栄養は拒否するため、栄養の受け渡しができず、細胞はエネルギー不足になります。そして細胞が働けなくなると体全体の代謝が低下し、届けられなかった余った栄養は細胞の周りにある脂肪に溜め込まれ肥満の原因になります。逆に腸活で善玉菌を増やし腸内環境を改善すれば、血液の質が良くなりエネルギー効率のよい痩せやすい体になります。
ダイエットには「やせ菌」
タンパク質を十分に取りつつ、腸内環境を良好に保つためには、積極的に食物繊維と発酵食品を摂ることです。食物繊維は善玉菌のエサになるため、タンパク質で悪玉菌優勢になりがちな腸内環境を整えてくれます。また腸を刺激して蠕動運動を促してくれるため便秘予防や解消にも有効です。特に便秘で悩んでいる方は便を柔らかくする効果を持つ水溶性食物繊維を意識して摂るようにしましょう。
また腸内細菌の生態系には、できるだけ多くの腸内細菌が活発であることが理想で、多様性を保つことが重要です。そのために特にヨーグルト、納豆、味噌などの発酵性のタンパク質は、菌を元気にして腸内環境の多様性を維持してくる腸活に欠かせない食材です。
一方で、良く勘違いしているケースが、悪玉菌をゼロに殲滅することが腸活であると考えていることです。腸活は、動物性タンパク質が悪玉菌を増やすため、善玉菌や日和見菌の割合を増やすように行なっていくことですが、腸内細菌の理想のバランスは、日和見菌2:悪玉菌1:善玉菌7です。多くの細菌が元気になることで悪玉菌が抑え込まれ腸内フローラの政界系が健全に保たれるようになります。
そして近年、この腸内フローラの中に「やせ菌」と呼ばれる細菌が存在していることがわかってきました。そのやせ菌のエサになるのが水溶性食物繊維の一部です。水溶性食物繊維は腸内で発酵する性質があり、これを食べた善玉菌や日和見菌の活動は活発になります。その中でも海藻類、豆類、根菜類、雑穀類などに含まれる水溶性食物繊維は、腸内細菌によって発酵すると短鎖脂肪酸という酸を生み出します。
短鎖脂肪酸は体中に運ばれると脂肪酸に対して栄養は十分にあり脂肪として蓄える必要がないことを伝えます。脂肪細胞は飢餓が起きた時に備え、エネルギー源をできるだけ脂肪に蓄えようするため、このメッセージが伝わることで細胞内に脂肪を取り込むのをストップするのです。さらに短鎖脂肪酸は交感神経を優位にして、体全体の代謝を活性化し、吸収したエネルギーの消費を促してくれます。このように短鎖脂肪酸は天然の肥満防止システムを起動させるスイッチのようなものです。
タンパク質不足で老化する
美肌を保つためには、まずは適切なタンパク質量を補給できているかどうかを考える必要があります。特にアミノ酸スコアの高い良質なタンパク質をしっかり摂取することが何より美肌の秘訣になります。
タンパク質は、筋肉のみならず、内臓や血液、ホルモン、酵素、免疫物質、皮膚、髪、爪などの全身のあらゆる部位の細胞の原材料となって組織を構築しています。そして全身の細胞は常に新陳代謝によって生まれ変わっており、例えば肌へのタンパク質が不足すればターンオーバーは滞り、肌荒れや乾燥といった肌へのダメージ、シミやシワといった肌の老化につながります。さらに肌や髪の毛といった生命維持にとって優先順位が低い部位はタンパク質が回ってくるのは後回しになります。タンパク質は生命維持に関わる部分から優先的に供給され、少量しか摂取していなければ、内臓のような重要な部位の新陳代謝にタンパク質は使われ、肌や髪の毛まで回ってこないのです。つまり肌や髪はタンパク質の摂取量の影響を最も受けやすい部位になります。
また、若々しい健康的な美肌を保つためには、毎日タンパク質をこまめに摂取することだけでなく、同時にビタミンCや鉄、亜鉛といったミネラルを摂り、肌のハリやみずみずしさを保つコラーゲンの産生を促すことも大切です。コラーゲンを産生する線維芽細胞は年齢とともに減少し、細胞の働きも衰えていきます。そのため年齢を重ねるほどにこれらの栄養素をしっかり摂ることを意識しましょう。
タンパク質の美肌効果
アンチエイジングに極めて重要な栄養素が「タンパク質」です。タンパク質不足になると、肌や髪の材料が不足するため調子が悪くなります。タンパク質が豊富に含まれている食べ物の代表は、赤身肉、レバーなどの肉類、卵、豆類、魚介類などです。また赤身肉やレバーはタンパク質を補給できるだけでなく、鉄分を補給できるので、シミ対策に非常に効果的です。
なんとなく顔色が悪い、シミが増えてきた、くすんでいるなどの悩みの多くは、おそらく鉄分が足りていません。女性の多くが鉄不足になっています。例えば出産後にシミが増えたと感じるのは、出産によって鉄不足が起きているからです。またダイエットで肉を控える方にも多くみられます。肉は効率よく鉄分を摂取できる食材のため減らし過ぎないようにすることも大事です。
一方でビタミンCがシミに効くと聞いたことがあるかもしれませんが、実はビタミンCよりもシミに圧倒的に効くのは鉄分(動物性タンパク質に含む)です。食事には鉄分とタンパク質を補う目的で赤身肉やレバーを積極的に取り入れるようにしましょう。そして美容面では、魚介類の中で赤い色が濃い鮭やイクラに含まれる強い抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、シワに効くと言われています。また卵はタンパク質が豊富な食材です。卵は加熱し過ぎるとタンパク質の有効量が落ちてしまうため、半熟半生で頂きましょう。
タンパク質の疲労回復効果
タンパク質は疲労回復にも役立ちます。疲れると甘いものを食べたくなるのは、血糖値が下がり疲れを感じて不足したエネルギーを手っ取り早く補うために体が糖質を欲するからです。しかし実際は、疲れが倍増することになります。糖質を摂取すると効率的に生み出されたエネルギーが速やかに脳や体に届けられ、一時的に疲れが軽くなって頭が冴えたような感覚になります。しかし血糖値が下がった状態で糖質を摂ると、急激に上昇する血糖値スパイクが起き、膵臓からインスリンが過剰に分泌されます。すると血糖値が急降下して、疲労感やイライラを招いてしまいます。また過剰なインスリン分泌によって余った糖分は脂肪細胞に蓄積されてしまい、肥満の原因になります。
疲労回復に有効な成分は糖質よりもタンパク質です。タンパク質は糖質ほど急速ではないですが、エネルギー源となり、筋肉合成のスイッチとなるBCAA(分岐鎖アミノ酸)が含まれているため筋疲労の回復効果が期待できます。またタンパク質に含まれる必須アミノ酸の一つであるトリプトファンは幸福ホルモンのセロトニンを増やし、脳の活性化や集中力を高める脳疲労も軽減してくれます。さらにメンタルを安定させる働きもあるのでストレスを感じた時にも最適な栄養素です。
ただし、インスリンにも筋肉合成を促す働きがあるためタンパク質と一緒に糖質を摂ることで効率的に筋肉を増やすこともできます。また筋肉は糖質の一種であるグリコーゲンを貯蔵する働きがあり、筋肉を動かす際にグリコーゲンが溜まっていないとパワーを発揮できなくなる点に注意しましょう。糖質を摂りすぎていることが問題であって全てが悪いわけではありません。
動物性だけでなく植物性タンパク質も
2017年に島根大学から発表された研究では、動物性タンパク質と腸内細菌の関係性について調査が行われ、動物性タンパク質の大量摂取によって腸内細菌が減少し、腸内環境が悪化することが明らかになっています。腸はアミノ酸の吸収に関与しているとても重要な臓器であり、その他にも免疫システムの調整や脳機能との関連など筋肉を大きくするため、脳の正常に働かせるため 病気にかかりにくくするためにとても重要な臓器です。
一方で動物性タンパク質だけの摂取ではなく、植物性タンパク質が必要です。なぜなら動物性タンパク質だけ摂取すると骨が弱体化するからです。1998年にアルバータアインシュタイン医科大学から発表された研究によれば、動物性タンパク質の過剰摂取によってカルシウムを骨形成に使うメカニズムが狂うことが分かっています。
動物性タンパク質を摂取することで体内のpHが酸性に傾き、この影響で体内の カルシウムが大量に排出されます。この過程で骨の弱体化が起こることが分かっています。また2001年のカリフォルニア大学の研究では、植物性タンパク質は体を酸性からアルカリ性と変えてくれるため、体外にカルシウムが排出されにくくなることが分かっています。
また、植物性タンパク質が必要な理由に腎臓と肝臓への負担があります。先ほどのメカニズムと同様に動物性タンパク質を大量に摂取することによって、カルシウムが排出されますが、その過程の中で腎臓を経由し尿として排出され、その濾過される過程でカルシウムが腎臓で固まり、腎結石ができるというメカニズムがあります。
さらにタンパク質は大部分が胃で消化され、その後小腸で吸収された後にアミノ酸となり筋肉に取り込まれます。この時に摂取量が多すぎると小腸で吸収されずに体内で窒素に変換されます。窒素は体の中で毒性が強いアンモニアに変換されるため、アンモニアに変換された後は肝臓で毒素を中和し、尿素に変えて腎臓に集められ、最終的には尿として外に排出されるという過程を辿ります。この過程でも肝臓にも腎臓にも負担がかかることになります。
ただし2020年のテヘラン医科大学の研究では32の研究、合計 71万5126名の方を対象に分析が行われ、健康な成人が高タンパク質を摂取したとしても特に影響は見られないという結論が出ていますが、分析された研究の中では動物性タンパク質のみ、過剰摂取によって死亡リスクが上がるというデータが出ています 。その一方で植物性タンパク質に関しては悪いデータどころか、ガンや心疾患の発症リスクを下げるというデータがあり、腎臓、肝臓の健康を考えるのであれば動物性タンパク質を中心とした摂取ではなく、植物性タンパク質も摂取するというのが重要になってきます。
タンパク質とプロテイン
タンパク質を摂るためにプロテインを飲むとお腹を下す方がいます。その原因には大きく2つあり、一つは多くのプロテインに含まれている人工甘味料、もう一つはプロテインのうちホエイプロテインというものに含まれている乳糖によるものです。
純粋なプロテインというのは、牛乳や大豆からタンパク質だけを取り出したカスのようなもののため美味しくはありません。そのためフレーバーとして様々な人工甘味料が含まれています。プロテインを摂る方は糖質制限をしているため、このような味付けは砂糖ではなく人工甘味料よってされています。
この人工甘味料については諸説あり、まだまだ長期的なデータが蓄積されていないため、長期的な健康被害があるかどうかは未知数です。例えば2022年の研究論文では10万人を対象とした大規模調査により人工甘味料の摂取量とがんのリスクに優位な相関関係が認められたということが報告されています。ただしこの研究では人工甘味料を摂取したことが直接ガンの原因になったのかそれとも人工甘味料が豊富に含まれている加工食品を食べることががんの原因になったのかがはっきりしていません。
ただし、人工甘味料によって下痢を引き起こすことについては様々な統計的事実からほぼ明らかになっています。特にソルビトールやアスパルテームをはじめとする人工甘味料の多くは小腸で消化吸収されにくく、そのままの形で大腸に届きます。このような人工甘味料は大腸の悪玉菌の餌となり、腸内フローラを破壊してしまうことにつながりかねません。
最近は、プロテインに人工甘味料が入っていない商品も増えてきています。ただし無添加プロテインはあまりおいしくはありません。
一方で、ホエイプロテインに含まれている乳糖によってお腹を下す方がいます。その場合、乳製品に含まれる乳糖に対する耐性がない可能性があります。実は日本人の85%もの人が、この乳糖不耐症の可能性があると指摘されています。ホエイプロテインの「ホエイ」というのはチーズを作る時に牛乳を起こしてその後に残る液体のことです。
私たちの健康にとってタンパク質というのは重要なもので、必要なたんぱく質を全て食品から摂り入れるためには、相当な量のお肉や豆類を食べなければなりません。また動物性の肉には純粋なタンパク質の他にも大量の脂質が含まれているというデメリットもあります。そのため効率よくタンパク質だけを摂取できるプロテインは、健康維持のために摂取したいものです。また大豆からできているソイプロテインがあり、ソイプロテインは大豆由来のため豆腐と同じで乳糖は全く含まれていません。ただしホエイプロテインに比べてもまずいという欠点があります。またプロテインもまだまだ健康効果については諸説がありますので過剰摂取には注意しましょう。
中性脂肪に変換されるプロテイン
条件付きで食べてはいけないものがプロテインです。天然の食材からタンパク質を適量摂取した方が良いということは言うまでもありませんが、現代人の食 生活にそれを求めるのは難しいでしょう。タンパク質の摂取量が慢性的に不足するよりは、上手くプロテインを利用することが健康長寿のためには大切であるという側面もあります。
しかし、プロテインはそれを飲むタイミングが非常に重要です。プロテインを 健康的に飲むタイミングとして3つのことが明らかになっています。プロテインは夜寝る前と運動後、そして炭水化物と一緒に取ることでその効果を最大化することできます。
筋肉が壊れて再生する過程で筋肥大が起こりますが、特に筋肥大が最も盛んになるのが寝ている間です。つまり夜寝る前にプロテインを飲むことで寝ている間の筋肥大に必要な材料を効果的に細胞に送ることができます。
また、運動後にプロテインを飲むことが、昔から筋トレ後のゴールデンタイムとして知られています。さらに最近ではタンパク質は炭水化物とともに摂取することで最も吸収効率が高まることも分かってきました。例えばラグビー選手やお相撲さんは、米もたっぷり食べまくるのは実は筋肉をつけるという点では非常に合理的な食べ方です。
一方で、最近はプロテインを飲まない方が良いタイミングというのも明らかになってきました。そのタイミングが寝起きです。朝起きた体は飢餓に近い状態にあります。飢餓状態では体は食べたものから最大限のエネルギーを引き出そうとします。そのため寝起きの状態でプロテインを飲んでしまうとカロリー過多になり、内臓脂肪に蓄積してしまう恐れがあります。内臓脂肪と言うと炭水化物や脂質を思い浮かべがちですが、もちろんタンパク質にもカロリーは存在します。タンパク質のカロリーは1gあたり4kcalで炭水化物と同じです。特に朝の空腹時にはカロリーが吸収されやすくなっているため、プロテインによって得られたカロリーが内臓脂肪に変わってしまう恐れがあります。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。