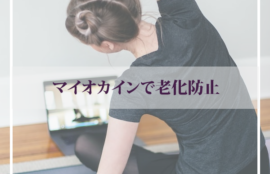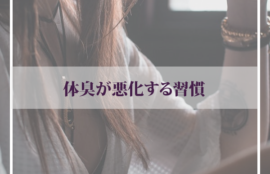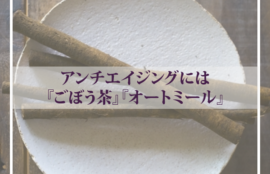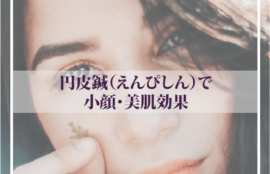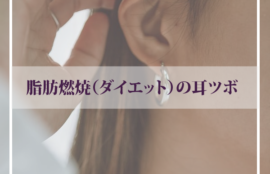最近、どんな美容商品を使っても効果を実感できないと悩んでる人の多くの人が、意識できていない肌を再生する必須の知識があります。その肌再生で最も重要なアプローチは血管のパフォーマンスを上げることです。シミができたからシミ消しクリームを買ったり、肌がカサカサするから美容液を買う、もちろんそれらも決して無駄ではありませんが、肌を再生するのに大事なのは何より体の内側からです。
血管の働きは、美容と健康において大切な要素です。医学教育の発展に尽力したカナダのウィリアム・オスラー博士の言葉に「人は血管とともに老いる」があります。血管は心臓から始まり、頭の先から足の先まで全身に血液を運び、酸素と栄養を行き渡せる働きがあります。また不要となった老廃物を回収することも血管の重要な役割です。
この大切な役割を担うのが毛細血管であり、血管の99%を占め、その毛細血管の長さは地球2周分の10万キロに表面積と約100億本が体にあると言われています。その毛細血管は40歳を境に減少していくと言われ、皮膚の毛細血管を調査した研究では、60~70代の人は20代に比べて、毛細血管が4割も減少する結果となりました。
加齢と共に肝臓や肺などの臓器の毛細血管が減れば、様々な機能低下や病気が起こる可能性だけでなく、体の末梢に酸素や栄養が行き届かなくなり、髪の毛や肌のトラブル、冷えや肩こりなど様々な問題を生じてきます。さらに末梢に栄養が行き届かなくなると、その働きを代償するため心臓がより強い力で血液を押し出そうとするため、これが高血圧の原因となり、さらに動脈硬化、心臓病、脳卒中などの血管の病気を加速させることになります。
そこで大きく注目されているのが「毛細血管ケア」です。毛細血管を若い状態でキープすることで老いや病を防ぎ、アンチエイジングを期待するものです。
なぜ、肌で血管を重視するのか
まず血管には、動脈、静脈、毛細血管の3種類あり、肌の再生に最も関わるのは、血管全体の99%を占める毛細血管です。そして人の皮膚は、外側から表皮真皮、その下に皮下組織があります。毛細血管は、表皮の一番上の層には存在しません。毛細血管は真皮から下にあります。その真皮にある毛細血管の役割には3つあり、細胞に栄養を運ぶこと、細胞に酸素を運ぶこと、そして細胞の中の不要になったゴミや不純物を回収してくれることが挙げられます。
細胞に栄養が入ってこなければ、その細胞は一瞬で機能が停止してしまい、一方で細胞は生きていくために必要なエネルギーを作ってくれているため、酸素が細胞に送られないと代謝もできず、細胞はいつまでたっても再生されません。そうなると老けた細胞になってしまい、結果的に老化に繋がってしまいます。
また、細胞の中には沢山の器官が集まっており、細胞内の器官が劣化して故障したり、異常な状態で作られてしまったタンパク質など、これらが細胞の中には溜まってしまいます。つまり体を構成する細胞は、まさに若々しさや美しさを保つ生産工場であり、しっかり働いてもらわないといけません。もし毛細血管がうまく働かなくなってしまうと、工場のゴミは細胞内に溜まって、細胞自体の仕事効率も悪くなり、どんどん肌は衰えていくことは簡単に想像できるでしょう。また働かない細胞が体内に溢れると結果的に、シワやシミはもちろん肌もたるんで老化が一気に加速します。
このように最近肌の衰えを感じ始めているのなら、肌の外側から何をやっても根本的な解決にはなりません。毛細血管は、体の内側から肌を美しく保つための美容液を届ける役目を担っており、お肌に張り巡らされた毛細血管が栄養や酸素を運んでくれたり、細胞に溜まったゴミや不純物を回収してくれると細胞が若返り、肌を綺麗な状態にしてくれるのです。
冷え性の原因は血行不良
現代女性の約8割の人が悩んでいると言われる冷え性、最近では男性も冷え性に悩む方が多くなっています。冷えは万病の元と昔から言われ、体質だからと言って、放置していると不快な症状や病気を引き起こすことになりかねません。
男女共に、冷えに悩む人が増えている原因としては、運動不足、ストレス過多、偏った食生活、睡眠不足などの生活習慣が大きく影響しています。冷えの症状で多いのが、手足の冷えで、入浴で温めてもすぐに冷えることや、何をしても体が温まりにくいことです。特に女性は冷えの症状だけではなく、足のむくみ、腹痛、頭痛、生理不順、抑うつ感など、さまざまな体や精神面のトラブルなどが併発しています。
女性で冷えに悩む方が多いのは、筋肉量が少ないことや月経・出産・閉経などに伴ってホルモンのバランスが崩れやすいことなどが関係していると言われています。そして個人差があるものの免疫力の低下は、冷えによる血流障害が大きく関係しています。免疫力の低下は、血液がドロドロで循環が悪い状態であり、結果として内臓の働きが弱くなり、ホルモンバランスが乱れます。まずは体全体の血液循環をよくして免疫力を上げていくことが大切です。
冷えによる血流障害は病気のもと
私たちの体には、免疫を始めとする体内の防御機能によって守られていますが、生活習慣の乱れによって免疫力が下がり病気になります。例えば疲れ、体を冷やす、ストレスなどを受け続けると心身に大きな負担が掛かり、免疫力を発動させる仕組みや、生きるために必要なエネルギーをつくる仕組みがうまく働かなくなります。
特に自律神経の一つである交感神経が緊張することで、血流障害、組織破壊により病気になりやすくなります。さらには、白血球の免疫細胞の中でも最も力を発揮するリンパ球が減少するため病気が治らなくなります。このように血流障害は、私たちが想像する以上に大きな弊害を招きます。
私たちが生きるために必要なエネルギーは、細胞内のミトコンドリアと解糖系の2つのエネルギーによって生み出されます。ミトコンドリアは細胞のエネルギー生産工場とも呼ばれています。無理やストレスで起きた血流障害が原因で体が低体温と低酸素状態になると、ミトコンドリアや解糖系のエネルギーを作り出す機能が抑制され、新陳代謝が悪くなり必要なものが不足して、体内の老廃物などの体に悪影響を及ぼす、物質が溜まってきます。
この状態では、病気になりやすく、かつ病気からの回復を遠ざける原因となります。その他にも倦怠感、むくみ、貧血、腰痛、肩凝り、頭痛、アレルギー、糖尿病、不眠やうつ病などの心疾患など、特に女性の症状は、血行不良が生殖機能低下につながり、不妊の一要因になったりすることもあります。
毛細血管の衰えがシミ・シワ・たるみの原因
毛細血管が衰え、ゴースト血管になると肌の細胞に栄養や酸素が巡らなくなり、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸といった真皮の成分を作り出す繊維芽細胞が弱体化して、シミ・シワ・たるみ(STK)の原因になります。また目元には毛細血管が密集しており、血管の衰えによって血行が滞るとクマ、くすみとなってしまいます。さらには毛細血管の衰えによってリンパ管が老廃物や水分を回収しきれなくなり、血管外に漏れ出してむくみの原因になります。
毛細血管は外側が壁細胞、内側が内皮細胞になっており、血管の衰えはこの2つの間に隙間が生じている状態のことです。その隙間から栄養分が血管外へ漏れ出してしまうため、それらを密着させることがしなやかな血管を保つためにも大事であり、そこで注目されているのがそれらを接着させる働きのあるTie2です。
Tie2は、血管にあるタンパク受容体のことで、壁細胞から分泌されるアンジオポエチン-1によって活性化されて、接着剤の機能の働きを担います。しかしアンジオポエチン-1の分泌量は加齢とともに減少してしまいます。そこでルイボスティーやシナモンに含まれる植物エキスがTie2を活性化させる働きを持っていることが明らかになり、注目されています。
加齢で毛細血管がなくなる
健康は質の良い血液が全身に行き渡ることであり、質の良い血液を作るためには腸内環境が大切です。その質の良い血液を全身に行き渡らせるためには心臓と血管を動かしている自律神経を整えることも大切です。
一方で毛細血管のケアがあります。実は血液の質と流れが悪いことで一部の毛細血管が働かなくなってしまうと、その分大きな血管の負担が重くなってしまっています。つまり毛細血管のケアをすることで大きな血管の負担を減らすことができ、結果として質の良い血液を体中に巡らせることができます。
ただし、加齢に伴って大きな欠陥も毛細血管も老化していきます。そしてさらに毛細血管は老化すると消滅します。実際、60歳以上の人の毛細血管の数は20代に比べて40%も減少していることが分かっています。実は私たちの肉体に 存在する血管の99%は毛細血管です。つまり加齢によって全身に血液を送る機能の4割が失われていくことになります。これまで全身の細胞に届けられていた酸素や栄養は4割減り、老廃物の解消に至っても4割は取りこぼされていくことになりかねません。
このような毛細血管の消滅を防ぐ方法、消滅してしまった毛細血管を再生させる方法が運動です。運動の刺激によって消滅してしまった毛細血管が再生していくことが分かっています。同じ年齢によってその健康度合いや見た目に大きな違いが出てきてしまうのは、老化によって失われた毛細血管を再生できている人とそうでない人がいるからだとも言えます。
運動をすると血流が良くなり、この時消滅せずに残っている毛細血管の先端ギリギリまで血液が流れ、酸素が送り届けられるとその刺激を受けて新たな毛細血管が作り出されます。逆に言えば運動しないでいると残っている毛細血管の先まで血液がいかないため、ますます毛細血管は縮こまり、さらに消滅することになってしまいます。
この時の運動というのはハードなものである必要はありません。ウォーキングやランニング、スクワットなど軽めの運動で全身に血液を循環させ、消えそうになっている毛細血管を復活させていきましょう。体を動かすことで腸の蠕動 運動も活発になって、腸の血流も良くなります。すなわち全身の血流が良くなります。それによって腸内環境が良くなり、精神的にもリフレッシュすることでセロトニンの分泌が促進されて、血管が拡張して血流が増えていきます。もちろん自律神経も整います。
また、体内を循環している血液は重力の影響で、その70%が下半身に集まっています。しかし筋肉が弛緩収縮を繰り返すことで下半身に降りてきた血液を上半身に送り返すことができます。この時に使われているのは主にふくらはぎの筋肉です。それ故ふくらはぎは第二の心臓と言われます。
ただ何もしなければ20代をピークに加齢によって筋肉はどんどん落ちていきます。それは上半身よりも下半身に顕著であり、特に大腿四頭筋の低下は深刻で70歳までにはピーク時の約3分の1が失われてしまいます。筋肉量が減ると骨への刺激も少なくなり骨粗鬆症にかかりやすくなってしまいます。
骨が弱っている上に、足腰がおぼつかないとなれば転倒による骨折も起きやすくなります。寝たきりになる原因の1位は脳卒中ですが、2位は骨折です。高齢者の筋肉は1週間動かないでいるだけで20%落ち、5週間動かなければ96%も落ちてしまいます。そのため骨折による療養をきっかけに歩けなくなってしまう人が多いです。
そのため、おすすめしたいのがスクワットです。年齢とともに落ちやすい大腿四頭筋に大きな効果があるだけでなく、全身の筋肉を効率よく鍛えることができます。スクワットで足腰に自信がついてきたらウォーキングをしてみましょう。ただしのんびり歩いていたのではあまり効果は期待できません。血液の流れを良くするためのウォーキングは、次の3つの条件を満たす必要があります。
①一定のリズムで歩く:規則正しいリズムで歩くことで自律神経が 整っていきます。
②視線を上げて歩く:俯いていると首の外形動脈と内径動脈の境目にある副交感神経のスイッチが圧迫されて血流が滞ってしまいます。また軌道が狭くなり呼吸が浅くなってしまいます。そのため交感神経が高くなりすぎ、やはり血流が悪くなってしまいます。
③まとめて歩く:5分くらいの短い時間をちょこちょこ何度も歩くよりも20分くらいまとめて歩いた方が良いでしょう。20分を楽に歩けるようになったら40分60分と時間を延ばしてみましょう。
美肌は身体のメンテナンスから
心身が乱れてお肌の調子が悪くなったり、慢性的な不調を溜め込んで体に疲れや、むくみが生じていませんか?例えば、首や方から「こわばり」が生じて、次にむくみ始め、全身がこわばり、それがお顔の肌荒れやたるみに繋がったりします。お肌の状態は日々変化するため、悪い方向に向かう瞬間を見逃さないこと、つまり風邪のひき始めのように完全に悪くなる前に、疲れやむくみを放置しないことが大切です。
体の「こわばり」を医学的には「筋緊張の亢進(こうしん)」といいます。首や肩がコリやすい人は、精神的に緊張しやすい性格であったり、事務職などで肩と腕に負担がかかりやすい姿勢を日常的に続けていたりすることが多いです。また、姿勢の悪さ以外にも、冷え、偏った食生活、運動不足、ストレス、不規則な生活リズムによる自律神経が乱れるなども原因です。
体を温めることをベースに
いずれにせよ、体調不良の始まりを早めに自覚して解消する必要があります。しかし、姿勢の悪さを直すのも難しいし、ストレスをなくすのも難しいですが、簡単に始められるのが体を温めることです。例えば運動不足の人がいきなりダイエットしても効果が出づらいように、体を温めるベースさえつくっておけば、その後の改善の効果が表れやすくなります。多くの美肌を維持されている方に共通な美容習慣が体を温めていることです。女優さんで腹巻は欠かせないと言われる方もいますし、歌手の方で必ず熱めの朝風呂(42度前後)を取り入れている方もいます。
このようなベースがあってこそ、様々な鍼灸などの体質改善方法が効率的になり、さらに血行や新陳代謝を良くすることで、肌の状態を整え、加えて精神状態も良くなります。美肌のためにスキンケアに莫大な時間をかけるよりも、生活の中に継続できることから始める、そして体の不調のサインを見逃さず早めに対処することが大切です。
体温を上げる大切さ
体温を上げるといっても、「冷え性」だからしょうがないと放置している方が多いです。昔から「冷えは万病の元」と言われているように、身体の冷えを放置しておくと様々な悪影響があります。まず身体が冷えると、血管が収縮し、体内の血液が循環しなくなります。これにより体に必要な栄養や酸素、水や白血球などの免疫物質の流れが滞ります。特に体内の器官に指令を伝える役割を持っているホルモンのバランスが崩れることで、身体の機能に影響をきたしてしまいます。
その代表的な症状が、月経前症候群(PMS)や生理痛、生理不順です。また首肩コリや腰痛を始め、むくみ、肌荒れ、食欲不振、便秘、下痢、疲労感、不眠にまで発展するケースもあります。さらに体の冷えは、ストレスや不規則な生活による自律神経の乱れからも起こります。不規則な生活をすると、身体の器官が正常に働くために機能する自律神経が乱れます。この自律神経は、交感神経と副交感神経で成り立っていますが、適切に切り替えられず、交感神経が常に働いてしまった場合、血管が常に収縮してしまいます。その結果、血行不良となって、冷え性になってしまうのです。
睡眠と体温の関係
深部体温を上げると、その後に自律神経の働き(ホメオスタシス)によって、体温を一定の状態に保つ力が働きます。近年の研究によって、この働きによって入眠がスムーズになることが分かっています。
皮膚表面(特に手足)から熱が放出されると、深部体温が下がり、脳と体を休息させる仕組みが働きます。冷え性の人はこの手足からの熱放散が上手くできないため良質な睡眠が取れず、また自律神経の働きも乱れて血行不良となりますます体が冷えるという悪循環になってしまいます。
この働きを考えれば、入眠1時間〜2時間前に38〜40度のお風呂を済ませると、深部体温と皮膚温度の差が縮まり入眠がスムーズになります。ぬるめのお湯は副交感神経を優位にして心身ともにリラックス状態になり、また体が温まることで抹消血管が拡がり、手足からの熱放散によって深部体温が下がり質の良い睡眠になります。
当院の『統合美容鍼灸コース』は、鍼灸によって自律神経の乱れを整え、インディバ(美容高周波温熱治療器)によって体内深部温度を上昇させることで以下のような効果を得られます。
- 免疫力・抵抗力UPで病気になりにくい身体へ
- 冷え性・むくみ・便秘・生理痛の改善
- 新陳代謝が上がり、美肌(シミ・シワ)・リフトアップに効果、アンチエイジング
- 肩コリ・腰痛など筋肉のコリ解消
- 体脂肪燃焼
- リラクゼーション効果により自律神経症状の改善
- 良質な睡眠へのスムーズな切り替え
血管を強くする「温冷交代浴」
血管を鍛えるためには、血管の内皮細胞を刺激して血管をしなやかにする一酸化窒素(NO)を出す方法があります。内皮細胞は一酸化窒素を分泌して、血管をしなやかにする、血栓ができるのを防ぐ、傷ついた血管を修復し、血管が厚くなるのを防いでくれたりする効果があります。この分泌量を増やすためには、血流をアップさせて内皮細胞に刺激を与えてあげることが効果的です。その方法が筋肉を硬直させて血管を一旦収縮させて、その後に拡張させることで一気に流れ出して血管内皮細胞に多くの刺激を加えることができます。
この方法を効率良くできるのが「温冷交代浴」です。40°くらいの暖かい浴槽と15°くらいの冷たい水風呂に交互に入るのが温冷交代浴です。もちろん暖かいシャワーと冷たいシャワーを浴びるのも温冷交代浴です。この熱い冷たいを繰り返す健康法はギリシャ、ローマ時代から行われてきた健康法で、歴史的にもその健康効果が確かめられています。また温冷交代浴によって疲労回復に効果があるという論文なども発表されています。
体を温めると血管が拡張し、冷やすと筋肉と血管が収縮し、それらを複数繰り返すことで全身の血液の流れが促進し、一酸化窒素が分泌されることで血管を鍛えることができます。
また、血管周辺の筋肉を動かすことで不随意筋である血管平滑筋にアプローチして鍛える方法があります。不随意筋は自分の意思ではコントロールできず、自律神経によってコントロールされています。温冷交代浴は短時間で血管の収縮と拡張を繰り返すため、いわゆる自律神経の切り替えのトレーニングが行われるため、結果的に体が「整う」効果があります。
毛細血管ケアする方法
バランスの良い食事
体は内部体温37度より低い温度の食べ物を摂取すると、体から放散する熱を少なくし体温を上げ、37度より高い温度の食べ物を摂取すると、皮膚表面の血管を拡張させ体熱を放散して、体温をもとに戻そうとする仕組みがあります。このような体温をコントロールするメカニズムを維持するために、バランスの良い食事を心がけることが、冷え性を解消するために効果的な方法です。
おすすめの食材は卵です。卵は完全栄養食とも言われ、必須アミノ酸9種類をバランス良く含んでおり、脂質、ミネラル、ビタミンも豊富に含んでいます。
アボガド、ほうれん草、サツマイモの美容効果
血管を若返らせるために必要な日本人に決定的に不足している栄養素がカリウムです。研究では400人を対象にして、半年から1年の間にカリウムを1.6g から6g摂取してもらい、その結果血管の柔らかさに関するあらゆる数値が飛躍的に改善されていたことが分かっています。そして日本人は、全体的にカリウムの摂取量が少ないと言われています。そのカリウムが足りているか足りてないかを簡単に見極める方法があります。例えば1日に野菜を4種類未満しか食べてない人は、おそらくカリウムが不足していると言われています。
また、世界でもカリウム摂取量が多いと言われる狩猟採集民族の人たちは、1日のカリウム平均摂取量が約10.5gです。日本人は、その1/4、平均値は約2.5g程度となっています。ちなみにWHOが推奨しているカリウムの1日摂取量は3.5gです。このカリウムを摂らなければ毛細血管が正常に機能しなくなり、細胞がゴミだらけになって肌が老け込んでしまいます。
毛細血管は加齢と共に減少していくことが分かっており、20 代をピークに、40代から減少し始め、60代になると20代と比べ40%もの毛細血管が失われると言われています。つまり20代の頃より血管が届ける美容液が半減してしまうことになります。
カリウムが豊富に含まれる食材はアボガドです。アボカドの美容効果が高いのは有名ですが、血管を若えらせるカリウムが豊富という点でもおすすめです。アボカド100g中には720mgものカリウムが含まれており、カリウムが多く含まれる食材の中でも1、2を争うほどです。さらにアボカドに含まれるビタミンEには、体の末端の血管を拡張して血行を促進してくれる効果もあります。
特にビタミンEは、脂質と一緒に食べると効率的に摂取できる栄養素であり、アボガドには脂質が含まれているため、他の食材と組み合わせなくてもアボカド単体でビタミンEを効率的に摂ることができます。
一方ほうれん草には、カリウムが豊富に含まれており、効率的に摂取できる食材の1つです。また、ほうれん草に含まれるβカロテンを摂ると肌の質感が改善する効果が期待できます。
最後のカリウムを豊富に含む、おすすめの食べ物はサツマイモです。サツマイモに限らず芋類は全体的にカリウムの含有量が多く、中でもサツマイモは、100gあたりに含まれるカリウムの含有量は約470mgです。またビタミンCやビタミンA、食物繊維も豊富に含まれるため、肌を再生に導く美容食品と言っても過言ではりません。
こんにゃく
こんにゃくと言えば、腸内環境を良くして便秘を改善する効果があることが有名です。それ以外にも実は最新の研究で、こんにゃくは血管を若返らせてくれることが判明しています。肌が綺麗な人は、肌の毛細血管の血行が良い状態、つまり十分な血流が保たれているということです。毛細血管は全身の隅々まで張り巡らされ、栄養や酸素を運んでくれます。最近では、それらの働きだけでなく、血管の一番内側には血管内皮細胞という一層の薄い細胞があり、そこからはたくさんのホルモンが放出されることも分かっています。そのため肌を復活させるには何より血管を若返らせる必要があります。
一方で、中年期以降では食べすぎやストレスなどによって血液中の脂質バランスが乱れがちになり、血液がドロドロになってしまう原因には、この脂質バランスの乱れに他なりません。こんにゃくには胆汁酸を吸着して血管をキレイにしてくれる効果が期待できます。
ちなみに胆汁酸とは肝臓が分泌している胆汁という液体に含まれている有機酸の1つで、この胆汁酸によって食べ物の油分が分解されることで私たちは脂質を効率的に吸収する ことができるようになります。胆汁酸は肝臓内でコレステロールを原料として作られることが知られており、胆汁酸をたくさん合成すればするほどコレステロールが消費されて、血液中の悪玉コレステロールが減ることを期待できます。最近の研究でもこんにゃくには、腸内の胆汁酸を吸着して体の外に排泄することで肥満や糖尿病までも改善することが判明しています。
エリンギ
血管が加齢と共に傷ついてしまうのは血液中の脂質バランスの乱れが原因ですが、エリンギを食べるとβグルカンという栄要素によって、私たちの血中コレステロールの値が正常化していくことが知られています。さらに日本の研究では、エリンギを1日約100g食べることで血糖値までも正常化してくれることが分かっています。さらにエリンギには、中性脂肪の吸収を抑制してくれる効果もあります。
タンパク質を摂る
冷え性の治療では、胃腸を整えることが大切です。鍼灸では胃腸の働きを良くして、栄養分の吸収を良くしていきます。なぜなら胃腸虚弱で栄養吸収が悪い場合は、熱産生が不足して体温が低下しやすいからです。一方で炭水化物の摂取量の多い人は体動かすと熱が発生しやすくなります。そのため運動量の少ない人は、タンパク質の摂取量を増やすと熱が発生しやすくなります。女性は男性に比べ身体活動量が少ない方が多いので、タンパク質を十分にとることが冷え性に対策になります。
EPAとDHA
体の中で活動している細胞は、血液によって運ばれてきた酸素や栄養素を受け取り、老廃物を血液の中に流すことによって排泄しています。しかし血流が悪くなってしまったり、血管が弱くなったりすると、老廃物がスムーズに排出できなくなります。そのため老廃物の排泄するためにも、血管をきれいにすること、血流を良くしてあげることが重要です。
主に魚に含まれるEPAやDHAは、血管をキレイにし、特にEPAの血液サラサラ効果は科学的にも証明されています。日本では2009年に有名な大規模臨床試験の結果が発表されています。高コレステロール血症と診断されて投薬を受けている患者1万8000人、平均追跡期間は46年の大規模な研究があります。対象者は基本の服薬に加えて EPAを1日あたり1800mg 投与されるグループと、基本の服用のみを継続するグループとにランダムに割り当てられました。高コレステロール血症は、冠動脈疾患を発症する大きなリスク要因の一つで、EPAがどこまでそれを予防できるのかに注目を集めた試験になりました。
結果としてEPAを追加で投与された人はそうでない人と比較して約19%、冠動脈疾患になるリスクが減少したということが判明しました。さらには既に一度、心筋梗塞を起こしたことがある人について、冠動脈疾患発症率を比較するとEPAを追加で投与された人はそうでない人と比較すると約41%もの減少が認められました。
このEPAが含まれているのが、サバ、マグロ、イワシ、サンマなどの背の青い魚です。文部科学省が発表する日本食品表示成分表によるEPA含有量の多い青魚は、1位はサバ、2位はキンキ、サンマ、3位はマグロとなっています。
EPAには、その他にも様々な働きがあり、脂肪に溶け込んだ毒を排除し、細胞膜に柔軟性を取り戻すことによって毒素の排泄を促し、炎症を改善してくれる効果も期待できます。その他にもアレルギー予防、高血圧の改善、動脈硬化や脂質異常症を防いでくれるなどの働きがあります。
一方で、青魚にはDHAも含まれています。DHAも様々な効果が認められており、炎症を抑えてくれる効果が科学的に認められています。さらにDHAは、アルツハイマー病を防いでくれたり、認知機能の低下を防いでくれるということが期待されています。
血管が健康になる麦茶
麦茶には、加齢と共に細くなりがちな私たちの腎臓の血管を拡張してくれる働きがあります。尿は腎臓で血液がろ過されることで作られますが、そのろ過の仕組みは単純化すれば、腎血流の圧力からなっています。つまり細い人血管の中に高い圧力の血液が流れ込むことで、それが尿へとろ過されていきます。しかし無理な圧力で血液をろ過しようとすると組織が壊れてしまいます。このように組織が壊れることで腎臓の細い血管が固まって腎硬化症をきたし、腎不全の引き金になってしまうと考えられています。また年を取れば動脈効果によって硬くなった腎臓の血管に高い圧力の血液が流れ込むことによって腎臓が傷つけがちになってしまいます。そのため年を取ればとるほど腎臓の血管を広げ、腎血管への負担を減らしてあげることが大切になってきます。
そのために飲んでいただきたいのが麦茶です。健康的な成人の被験者に麦茶を 250ml飲んでもらい、その直後の血流の流動性を調べた実験では、麦茶はミネラルウォーターよりも高い血流流動性向上効果があることが分かっています。これは麦茶に含まれるアルキルピラジンという栄養素によって血液が流れやすくなるためと考えられています。このことから麦茶には動脈効果の予防に効果があることが分かっています。また麦茶にはカリウムも含まれていて、日頃の食塩過剰によって上がってしまった血圧を下げてくれる働きもあります。
さらに麦茶は数あるお茶の中でも比較的尿路血石の原因となるシュウ酸の量が少なく、尿路血石を作りづらいお茶というメリットもあります。同じくお茶である玉茶、ウーロン茶、紅茶などにも健康効果はありますがシュウ酸が多いということが知られています。ちなみにシュウ酸カルシウム結石はシュウ酸とカルシウムが結合してできる尿路血石のため、シュウ酸だけではなくカルシウムも制限した方が良いと考えている人がいます。実はカルシウムはむしろ積極的に摂った方が尿路結石はできにくいというエビデンスあります。
実はカルシウムは、私たちの腸の中でシュウ酸と結びつくことで余分なシュウ酸を便として排泄してくれる働きがあります。つまりカルシウムが不足すると便からのシュウ酸の排泄が滞ってしまい、余ったシュウ酸が尿に漏れ出ることでシュウ酸カルシウム結石の原因となってしまいます。そして麦茶はカリウムだけでなくカルシウムも豊富に含まれており、また水分を摂ることは結石を作りづらくする方法の1つでもあります。
ただし麦茶の唯一の弱点が腐りやすいという点です。麦茶にはでんぷん質が含まれおり、これが様々な雑菌の餌になることが知られています。特に1度蓋を開け、口をつけたペットボトルの麦茶は数10分で筋が繁殖するとも言われています。そのため開封した麦茶はすぐに飲み干すことにしましょう。
ふくろはぎの筋肉を鍛える
冷えは、筋肉量が少なく熱をつくることができないこと、血流が悪く熱を運べないことが原因です。体の熱の大部分は筋肉によってつくられるため、背中、お尻、太股などの大きな筋肉を鍛えると、冷え性が改善します。特にふくろはぎは第2の心臓と言われ、血液を心臓に戻すポンプのような働きをしているため、スクワットなどで鍛えると、効果的に血流を改善することができます。
温熱治療
冷えの改善で良く用いられるのがお灸などを代表する温熱治療です。ちなみに当院では、イトオテルミー療法、インディバ(高周波加温治療器)を採用しています。お灸は、ツボを刺激し、温めることで、体の血流を良くして、冷えを改善します。
インディバで毛細血管ケア
そして血管の老化が病気につながること以外にも、誰しもが気になるシワ・たるみ・くすみ、シミ、むくみ、そばかすなども毛細血管の老化によって引き起こされます。結果的に、皮膚に酸素や栄養が届かなくなるため、お肌のトラブルの一因になります。
毛細血管は、加齢と共に、細胞同士の「接着」が甘くなり、血液が途中で漏れ出してしまうため、毛細血管の劣化を引き起こします。しかし日頃から十分な血流があると、細胞がお互いに強固に接着しているため、血液の漏れを防ぎ、健康な毛細血管を保ってくれます。
よって、インディバ(高周波温熱器)で毛細血管の血流を改善することができれば、アンチエイジングにつながります。インディバの深部加温は、身体が外側からだけではなく、内側から温めることができるため、血液やリンパの流れが良くなり、毛細血管の末梢まで酸素や栄養素が補給されやすくなります。さらに細胞や酵素、内臓も活性化して代謝アップに繋がります。
また、インディバは肩凝りや腰痛、冷え性や生理痛、脚のむくみ等でも血流やリンパの流れを改善して症状を軽減してくれます。さらに自律神経のバランスを整える効果もあり、便秘の解消、熟睡できるようになる、精神的な安定など、西洋医学では改善しにくい不定愁訴(ふていしゅうそ)にも効果があります。
お身体の不調でお悩みの方は是非、当院にお越し下さい。東洋医学の知識を基に、お客様一人ひとりに合わせた方法で、お悩みの改善が出来るよう全力を尽くすことをお約束します。
美容鍼でアンチエイジング
血管を健康に保ちたいと思うのならば血流を良くすることが極めて重要です。血流を良くすれば自然と血管は健康になり、その結果ますます血流が良くなり 血管もさらに健康になっていくという好循環が生まれます。
しかし、日本人のおよそ4人に1人が血管が原因で起こる病気、いわゆる血管病によって命を落としています。血管の働きは血流をスムーズに流し、全身の細胞を一つ一つに酸素と栄養を届けることです。しかし血流が悪くなると一つ一つの細胞に生きるための栄養が届かなくなります。その結果、体に様々な不調が現れてしまいます。また血流の悪化は、肌や髪のトラブル、肩こりや腰痛、冷えなどを引き起こします。また日本人の死因の多くを占める心筋梗塞や脳卒中は、実は血管の病気です。その原因が血管の老化、つまり動脈硬化です。
例えば、心筋梗塞は心臓の筋肉が酸素不足になって壊死してしまう病気です。心臓の筋肉がそもそも酸素不足になるのかというと、心臓の筋肉を取り巻いている冠動脈と動脈が動脈硬化で固まり、血液の通り道が塞がれ、心筋に血液を送ることができなくなるからです。
また脳卒中も同じく血管の病気です。脳卒中は脳の血管が詰まったり、破れたりすることによって脳が障害を受ける病気のことで、後遺症を伴ったり、最悪の場合は死に至ります。脳卒中には、脳の血管が詰まったことが原因で起こる脳梗塞、脳の血管が破れたことが原因で起こる脳出血やくも膜下出血があります。
血管の老化が進んでいる人の特徴として血流が悪いことが挙げられます。血流を促進する最も簡単で効果的な方法は体を動かすことでしょう。運動が健康に良いのは血流が促進されるということが大きな理由の一つです。運動をして定期的に汗をかくことによって、血流を促進することができます。
どうしても無理な場合はその代わりとして美容鍼灸を予約するという方法も有効でしょう。実は美容鍼灸というのは私たちに数々のメリットをもたらしてくれます。まずは血流が促進されることで、実際に鍼灸をすることによって全身の血流が促進され、血管内皮細胞の機能が改善されるということが研究によって分かっています。また美容鍼灸を受けることによって、セロトニンやオキシトシンといった癒しを与えてくれるホルモン物質が増えて、さらにストレスホルモンであるコルチゾールも減ることが分かっています。
また頸動脈のような太い血管が通っている首をインディバで温めるということも血流を促進する上で非常に効果的です。さらに首を温めることで自律神経が整うため、体調が良くなるという効果も期待できます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。