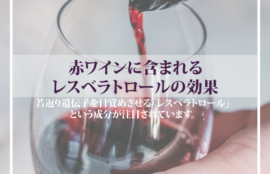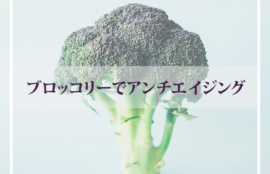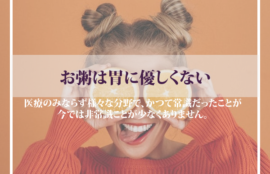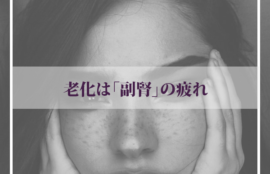病気にかかりやすい人が周りにいませんか?その理由に体が「酸性体質」であるという研究があります。様々な病気にかかりやすい人は、pHが6.5以下の酸性体質になっている人で、病気になりづらい人は、pH7.0以上の「アルカリ性体質」であることが分かっています。
この体内pHの数値は、日々の食習慣で決まり、酸性食品ばかり食べていると、酸性体質になりやすくなり、アルカリ性食品を意識して食べている人はアルカリ性体質になりやすい傾向があります。
酸性体質の人は血液中の白血球の働きが悪くなり、免疫力低下します。白血球は体がアルカリ性であるほど活発に働くことが知られています。
また、酸性体質では、慢性的疲労感などを感じていることが多くなります。筋肉を動かすことで糖分が分解され、疲労物質である乳酸が生成されています。この際に体が正常なpHを保っていれば、乳酸を含む多くの酸は、体内のミネラルによって自然に中和されます。しかし体が酸性に傾いていれば、普段からミネラルが消費され不足します。結果として乳酸が中和されずに蓄積していき、慢性的な疲労を感じるようになります。
このような酸性体質によるミネラル不足は、慢性的な疲労以外にも、特にミネラルの内、ビタミンB群が足りなくなると、皮膚や粘膜の機能が低下して、口内炎、口角炎、舌炎、脂漏性皮膚炎、目の角膜炎などを発症することが知られています。またミネラルが不足すると体内のカルシウムやマグネシウムが溶出していきます。この不足を補うために、体は骨からミネラルを吸収するようになり、骨がスカスカになる骨粗鬆症になる危険性があります。
さらに生活習慣病、痛風、腎結石、動脈硬化、尿結石、脳卒中、認知症などのあらゆる病気を引き起こし、眠気、だるさ、頭痛、便秘も統計的に酸性体質の人に起こりやすいと言われています。そして酸性体質と関係が深いのが癌です。
酸性体質と癌発症の関係が解明されたのは、1931年でがん細胞が酸性条件下で増殖することが分かっており、この研究成果には、ノーベル生理学医学賞が授与されています。その後も様々な研究がされて、体が酸性であるほど癌になりやすいことが多くの文献で指摘されています。
アルカリ性体質になる食事
免疫力を上げ、ミネラルを保ち、体の解毒作用を維持して、病気に負けない健康的な体づくりには、何より体をアルカリ性体質にすることが大切です。そのために必要なアルカリ性食品を選択する必要がありますが、難しいのが食品自体のpHと体に入った後の食品のpHは異なることです。例えば梅干しは食べる前は酸性ですが、食べた後にはアルカリ性に変化します。
このように体内でアルカリ性となる食品があり、生の植物性食物や果物が代表的で、一方で体内で酸性となる食品には動物性食品や加工食品があります。
| pH10.0の高アルカリ食品 | ほうれん草/ブロッコリー/芽キャベツ/赤キャベツ/セロリ/カリフラワー/人参/ポテトの皮/きゅうり/ケール/海藻/アスパラガス/レモン/ライム/すいか/こんにゃく/梅干し/高アルカリイオン水 | 食材そのものを生で食べることがベスト |
| pH9.0のアルカリ食品 | オリーブオイル/レタス/生ズッキーニ/さつまいも/生豆/生なす/アルファルファもやし/生いんげん/ブルーベリー/洋梨/マンゴー/パパイヤ/イチジク/なつめやし/みかん/メロン/キウイ/ぶどう/れんこん/お酢 | 積極的に食べたい食品 |
| pH8.0の弱アルカリ食品 | りんご/アーモンド/アボガド/トマト/とうもろこし/きのこ/かぶ/オリーブ/大豆/ピーマン/大根/パイナップル/さくらんぼ/きび/いちご/あんず/マスクメロン/甘露/もも/オレンジ/グレープフルーツ/バナナ | 調理すると酸性になるので生で食べることがベスト |
| pH7.0の中性食品 | 水道水/ワイン/バター 生クリーム/クランベリー/牛乳/プルーン/ブラックベリー | 食べても無害な食品 |
| pH6.0の弱酸性食品 | ヨーグルト/フルーツジュース/調理したほうれん草/穀物/豆乳/ココナッツ/卵/魚/お茶/インゲン豆/加工ジュース/ライ麦パン/玄米/ココア/アーモンドミルク/発芽小麦パン/オーツ麦/レバー/淡水魚/サーモン/まぐろ/ブランデー | 食べる場合はアルカリ性食品とのバランスに注意 |
| pH5.0の酸性食品 | 煮豆/チキン/ビール/砂糖/フルーツ缶詰/白米/皮なしジャガイモ/白いんげん豆/ひよこ豆/レンズ豆/黒豆/餅/調理されたとうもろこし/糖蜜/ウイスキー | バランスに注意 |
| pH4.0の強酸性食品 | 蒸留水/ペットボトル水/コーヒー/白パン/スポーツドリンク/ピスタチオ/牛肉/ナッツ/トマトソース/ポップコーン/ピーナッツ/日本酒 | 非常に注意 |
| pH3.0の超酸性食品 | 子羊肉/豚肉/貝類/チーズ/炭酸水/紅茶/パスタ/ピクルス/アスパルテーム/チョコレート/加工食品/電子レンジ食品 | アルカリ体質を維持するためには控えめに! |
| pH計測不能の超超酸性食品 | コーラ |
この一覧を見ると中には、食べた方が良い健康食も多く含まれていることが分かります。ヨーロッパの医療界では、酸性食品の割合を20%、アルカリ性食品の割合を80%の比率で摂取することが理想とされています。
酸性体質を改善して体臭を消す
体が臭くなってしまう原因にはストレスや暴飲暴食など様々な原因がありますが、体が酸性に傾いてしまうのもその原因の1つです。現代人は、ストレスや飲酒、睡眠不足などによって酸性体質になりがちです。酸性体質になると脇臭などの原因物質が作られやすくなるため、体が臭くなって周りの人から知らず知らずに疎まれる原因になってしまいます。そのため酸性体質の方が体臭を改善するためには、まず何よりも体をアルカリ性にしてあげることが重要です。
そこで役立つのがお酢や梅干といった酸っぱい食べ物です。お酢や梅干は、食べる前は酸性食品になりますが、それらを食べて消化吸収されるとクエン酸によって体内の乳酸という酸性物質が分解されて体がアルカリ性に変わります。そのためお酢や梅干は、酸っぱいにも関わらずアルカリ性食品と呼ばれています。アルカリ性食品は他には、生姜やネギ、そばなどがあります。いずれも様々な健康効果がある食品ばかりです。
またアルカリ性食品には体臭を改善する他にも様々な効能があることが知られています。例えばアルカリ性食品の健康効果としては、腎臓の機能を健康に維持してくれる効果、体内の老廃物を排泄するデトックス効果、ミネラルによる美肌など様々なものが知られています、
特に腎臓の機能を維持する効果は、加齢とともに弱りがちな腎臓を守るために重要です。腎臓は尿によって老廃物を体の外に出す働きの他、活性型ビタミンDを作って骨を丈夫にする作用や血を作って貧血を予防する作用など、私たちが 健康に生きていくために欠かせない様々な働きを担っています。そして中でも腎臓による3塩基バランス調節作用です。3塩基バランス調節作用は、体の酸性とアルカリ性のバランスという意味です。腎臓は体がアルカリ性に傾くとアルカリ性物質を吸収し、逆に酸性に傾くとアルカリ性物質を吸収するといった風に3塩基バランス調節作用を常にコントロールしています。しかし長年の生活習慣の乱れによって酸性に体が傾き続けると腎臓に大きな負担がかかり続け、腎臓の機能が低下してしまう恐れがあります。
腎臓の機能が低下するとさらに体が酸性に傾き、腎臓が衰えるという悪循環に陥ってしまいます。また体が酸性に傾くと尿が酸性化して尿路結石ができやすくなるというリスクもあります。尿路結石は1度できると再発しやすくて激痛や血尿など様々な恐ろしい症状に悩まされることになります。
アルカリ性食品を食べて、体がアルカリ性体質になれば代謝がアップすることで毒素が排出されるようになり、そうなれば毒素を排出する器官である腎臓も元気になり、非常に高いデトックス効果を期待することができるでしょうます。
さらに梅干を始めとするアルカリ性食品の多くは、ミネラルが豊富で美肌効果をもたすとも言われています。
ミネラル不足の現代人
体のサビであり、老化の原因となる酸化を防ぐためには、適切な抗酸化物質やビタミン、ミネラルが必須であり、糖質が多い食品や異性化糖を避けることが大切です。
この中でミネラルは、体にとって重要な栄養素にもなんとなくしか理解していない方が多い印象です。ミネラルは人の臓器や組織の反応を円滑に働かせるために絶対的に必要な栄養素です。さらにミネラルは体の中でつくることはできず、食物として外から摂取する必要があります。ミネラルはしっかりと摂取できているかどうかが健康を左右するといっても過言ではありません。
体を構成する要素は、酸素、水素、炭素、窒素で約96%を占め、残りの4%をミネラル(無機質)と言います。この僅かなミネラルが体の構成成分や生理機能を調整するなどの重要な役割を担っています。またミネラルの中でも健康を維持するのに欠かせない16種類を必須ミネラルといい、主要ミネラルが7種類、微量ミネラルが9種類あります。
ここで問題になるのが、ミネラルを食物から摂ることが難しくなっていることです。環境汚染などによりミネラル不足の土壌からはミネラル不足の野菜しか取れません。野菜の栄養価は激減しており、例えばほうれん草に含む鉄分は1950年では100mg中13mg、2015年では100mg中2mgになっています。その他人参や大根などの野菜でも80%以上も減少しています。このように現代人の栄養解析をすると鉄、亜鉛、マグネシウムなどのミネラルが不足している人が珍しくない状態になっています。さらに農作物のミネラル不足だけでなく、加工食品の蔓延する事態を悪化させる原因になっています。
天然塩のマルチミネラル
私たち人間が生きていくために必須の要素の一つであるミネラルは、塩をはじめとした無機塩類の総称で、私たちが普通塩と呼んでいるナトリウム以外にもカリウムやマグネシウム、カルシウムなど様々な種類があります。
中でも絶対に摂らないといけないものがナトリウムとカリウムです。ナトリウムとカリウムは、健康にとって必須のミネラルですが、ナトリウムとカリウムのバランスが悪くなってしまうと様々な不調をきたします。そしてミネラルバランスの悪化によって、特に影響を受けやすいのがメンタルです。
例えば、暑い夏の日に汗をかいた時にミネラルの入っていない水を飲むと、血液中のナトリウム濃度が低下し、低ナトリウム血症となります。低ナトリウム血症は、血液濃度が下がることで脳が水によってむくみ、脳機能が障害され頭がボーッとしてきます。さらに低ナトリウム状態が悪化すると動作や反応が鈍くなり、疲労感や頭痛、そして憂鬱など様々なメンタルの悪影響が起こります。
この低ナトリウム血症を予防するために、普段の生活でナトリウムを沢山摂ることが良いと思うかも知れませんが、過剰なナトリウム摂取による血圧の上昇し、血圧が慢性的に高止まりし続けると様々な不調が起こります。
このようにナトリウム濃度は高すぎても低すぎても良くなく、丁度良いバランスを維持するのが重要になります。そのため、おすすめしたいのがカリウムの摂取です。
ナトリウムと同じくミネラルに分類されるカリウムは、ナトリウムとは真逆の効果があり、血圧を下げてくれることが分かっています。つまりナトリウムとカリウムを同時に摂取することで体内のナトリウム濃度が丁度良いバランスに保たれます。またカリウムは血圧を下げてくれるだけではなく、体中の筋肉の状態を良好に保つ働きもします。カリウムは脳と筋肉をつないでいる非常に重要なメッセンジャーの役割をしています。例えば何か動作をしようとした時に神経が興奮することで、その信号が筋肉に伝わって筋収縮が起こります。このような筋収縮のメカニズムに不可欠なミネラルがカリウムです。
このナトリウムとカリウムを同時に摂れるのが「天然の塩」です。天然の海水から作られた塩には、海からの恵みである素晴らしいミネラルの数々が含まれています。また天然塩にはマグネシウムやマンガン、硫黄など、なかなか他の食材からを摂ることが難しい栄養素も豊富に含まれています。このことから天然塩はまさに自然の「マルチミネラル」といっても過言ではありません。
アンチエイジングに重要なマグネシウム
私たちの周りで馴染みのあるミネラルは塩です。塩は生命の起源でもあり、海のミネラルを細胞に行き届かせることが大切です。塩は生活習慣病の元凶とも言われ、血圧が高くしないためにも減塩を指導されることが多くあります。そもそも高血圧の予防や改善のために塩分を控えるように言われるのは、ナトリウム過剰をさせるためです。
しかし、減塩も行き過ぎるとナトリウム不足が欠乏し、低血圧や無気力につながります。大切なのは減塩ではなく、塩分コントロールであり、塩の選び方です。食塩と書かれた塩は、ほぼナトリウムであり、海水からつくられた塩はにがりが含まれており、マグネシウムやカリウムなどが豊富です。海水から作られた塩は、カリウムが多く含まれているため、体内の余分なナトリウムを排出し、ナトリウムだけの精製塩とは全く違う塩です。その他にも亜鉛、鉄、銅、マンガン、ホウ素、クロムなど全21種類のミネラルが含まれているため、体内のミネラルバランスを整え、ホルモンバランスの乱れを修復してくれます。
一方で、生物がエネルギー代謝を始めた時に、最初に使われたミネラルが鉄です。その後の進化の過程で、マグネシウムやビタミンBやCを利用してエネルギー代謝ができるようになりました。つまり鉄はすべての生物のエネルギー代謝において根幹になるミネラルです。そのため鉄が不足すると、いくら他のミネラルを摂っても効果があまり得られないため、まずは鉄とタンパク質を補うことが大切です。
また、健康や美容にとって重要なミネラルは、鉄、マグネシウム、亜鉛、セレンの4種類です。特にマグネシウムは、体の中の細胞や骨に存在し、代謝をはじめとするあらゆる生命活動に関与しています。マグネシウムは、神経系や筋肉の収縮、健康な骨や歯の形成など、体内の酵素反応に欠かせません。また人の活動エネルギーであるATPをつくるためにミトコンドリアで必要な最重要ミネラルです。鉄はこのマグネシウムが不足している状態ではエネルギーを生み出すことができません。
さらに、フランスのマグネシウム研究の権威であるデュルラック博士によると、マグネシウム不足によって老化が加速するとのことです。理由は、70歳では30歳と比べて、マグネシウムの吸収量が2/3に低下するからです。
梅干しのアルカリ性
古くから風邪などで梅干しを食べると良いことを民間療法として伝えられてきました。その梅干しの効能について、科学的な裏付けが得られてきています。特に梅干しの高いアルカリ性が注目されています。
酸性とアルカリ性のバランスのことを酸塩基平衡と言いますが、このバランスを表す数値としてpHが用いられます。PH7.0 が中性であり、一般に体は正常な値でPH7.4程度の弱アルカリに傾いています。しかし細胞に慢性炎症が起きたり、体に長期間ストレスがかかったりなどで、私たちの体は酸性に傾いていくことが分かっています。この体の酸塩基平衡が酸性に傾くことを「アシドーシス」と言います。
アシドーシスになると、だるさや疲労感、免疫力の低下など様々な不調をきたすようになります。さらに消化管でのビタミンB群の吸収が悪くなるため、肌に悪影響が表れてしまい、老化する原因の一つです。
このアシドーシスになってしまった体液を、正常なアルカリ性に戻すためにはアルカリ性の食べ物を摂取するというのが簡単です。梅干しの酸っぱさの原因には、クエン酸という酸があり、食べた後に体の中でアルカリ性の物質に変換されてアシドーシスを補正する方向に 働くことが分かっています。
梅干しの他にもレモン、ぬか漬けなど酸味のある食品の多くは、口から摂取することによって消化吸収されて体内でアルカリの性質を発揮します。このことから疲れが貯まったりなどで自然治癒力が低下している時に、酸っぱい食べ物を食べたくなると言われているのは、このような科学的に背景があるからです。一方で体を酸性に傾かせてしまう食品としては、動物性の肉類やお米、パン、アルコール類などが挙げられます。
梅干しの塩分
塩は健康に悪いと言われがちですが、実際は塩分が不足すると体調が悪くなることもあります。つまり塩というのは多すぎても少なすぎても良くありません。特に過剰に体内の塩化ナトリウムの濃度を高めてしまうのが精製塩です。精製塩は、塩化ナトリウムの濃度が99%以上のもので、塩化ナトリウムだけを大量に摂取することになるため体内のミネラルバランスを崩してしまいます。
一方で、塩化ナトリウム以外のミネラルも豊富に含まれている天然塩の場合は、塩化ナトリウムだけを過剰に摂取することにはなりません。特に副腎疲労がある人は、塩分が不足しがちであるため、適切な塩分の補給が大切です。
梅干しは、ナトリウムだけでなくミネラルも豊富でアルカリ性の食品です。ただし塩分濃度が15%以上のものを選ぶことが大切です。減塩の代わりに保存料や人工甘味料などの本来不要な添加物が入っている減塩梅干しが多くなっています。また天然塩と表示されているものを選ぶようにしましょう。
この塩分濃度15%以上の梅干しは、非常にしょっぱいと感じる方もいらっしゃると思います。そういった場合は少しかじってみて、しょっぱすぎると思えば 途中でやめるようにしてください。塩分はその人の体調に応じて摂るのが基本 で、おいしいと感じれば食べて良いと判断してください。
一物全体食(いちぶつぜんたいしょく)
一物全体食は、1個の食物を丸ごと余すところなくいただく、という考え方です。一物全体食は、古くから仏教などで取り入れられ、民間伝承として受け継がれてきました。近年、その科学的な効果が実証され、栄養学でも再評価されています。
食物を丸ごと食べるということは、当然ながらその栄養素が全て含まれています。例えば一物全体食として有名なものに大根があります。大根は、葉っぱや根も食べることができ、普段捨ててしまうようなところに豊富な栄養素が含まれています。大根の葉にはβ-カロテンが含まれていたり、ビタミンC、葉酸、カルシウムなどが含まれます。
一物全体食では、野菜はできるだけ皮をむかず、葉や根も使い、魚は切り身よりもまるごとの小魚を食べること、そして米は白米よりも、精白しない玄米を食べることが一物全体食の食事法です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。