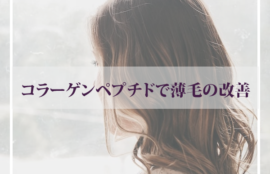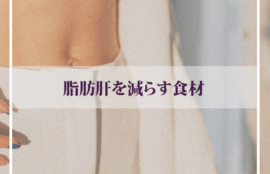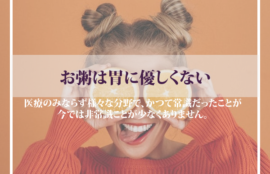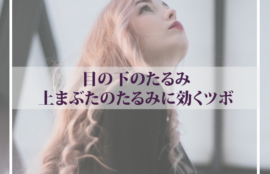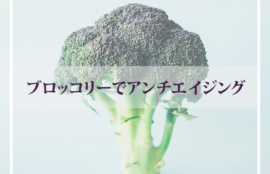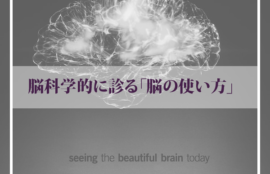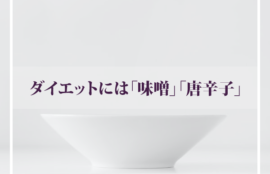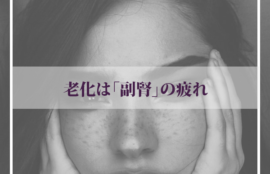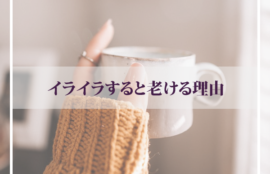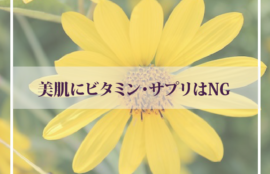体脂肪が増えるメカニズムは、食事で摂ったエネルギーが消費されずに余ると 余ったエネルギーは肝臓で合成されて中性脂肪になります。この中性脂肪が血液中を流れて、体の全身にある脂肪細胞に蓄えられると体脂肪が増えて肥満に繋がります。結局、肥満の原因は食べすぎが大きな原因です。
白色脂肪細胞とリバウンド
ちなみに体脂肪は皮下脂肪と内臓脂肪の総称の言葉です。皮下脂肪は皮膚のすぐ下の皮下組織にできる脂肪のことで、内臓脂肪は胃や腸などの内臓の周りに蓄積した脂肪のことです。一般的に女性は、皮下脂肪がつきやすく、男性は内臓脂肪がつきやすい傾向があります。ちなみに女性ホルモンのエストロゲンが内臓脂肪の蓄積を防ぐことが分かっています。更年期でエストロゲンが急激に減少すると女性も内臓脂肪がつきやすくなるから注意が必要です。
体脂肪は脂肪細胞に蓄積しますが、脂肪細胞には2種類あり、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞分けられます。白色脂肪細胞は全身に多く存在し、余分なエネルギーを蓄積する役割を担っています。特に脂肪がつきやすい下腹部や太ももに白色脂肪細胞が多く存在しています。一方、褐色脂肪細胞は首や肩甲骨、鎖骨など限られた部分に存在し、ミトコンドリアを豊富に含んでいるため、脂肪を燃焼し、熱を作り出す役割があります。褐色脂肪細胞は、加齢とともに減少するため、褐色脂肪細胞の減少が中年太りの原因の一つになります。
一方で、白色脂肪細胞は飢餓状態に備えて脂肪を蓄積しているだけではなく、糖尿病や動脈硬化を抑えるアディポネクチンや食欲を抑えるレプチンなどの善玉ホルモンを分泌しています。しかし白色脂肪細胞が肥大化して肥満になるとアディポネクチンの分泌が低下し、食欲を抑えるレプチンが効きにくくなり、生活習慣病を促進するホルモンを分泌されます。
このような悪玉ホルモンは内蔵脂肪での影響が大きく、内臓脂肪が増えすぎると心血管疾患や脳血管疾患の発症リスクを高めたり、糖尿病、高血圧、動脈硬化を引き起こします。また食べ過ぎて白色脂肪細胞に中性脂肪が貯まりすぎると脂肪細胞が肥大するだけでなく、細胞分裂して数を増加させます。脂肪細胞は、基本的には美容整形でしか除去することはできないため、肥満を経験した人は、白色脂肪細胞の数が多くなっているため脂肪を蓄積しやくなっているため、結果リバウンドしやすい体になっているのです。
体脂肪の減らし方
痩せようと思って食べる量を減らしたり、運動をしたりしても少し体重が減ったと思ったらまた元に戻って全然痩せないと思っている方は、まずは体脂肪と体重は分けて考えなければいけません。例えば体重は、その日計った時間や前日に食べたものや水分量によって変動します。特に水分を保持しやすい炭水化物を多めに食べた時は体重が増加傾向にあります。つまり体重は増えているけど体脂肪は減っていた可能性もあります。
体脂肪を落とす大原則が、摂取カロリーを消費カロリーより少なくすることです。摂取カロリーを減らすとどうして体脂肪が落ちるのかは、人の体はエネルギーが不足すると脳が脂肪を分解してエネルギーを作れという命令を出すからです。
アドレナリンなどの脂肪を分解するホルモンが分泌されると、脂肪が分解されて体脂肪が落ちるようになります。もちろん運動で消費カロリーを上げることで脂肪を落とすことも可能ですが、運動の消費カロリーは意外と少ないため、食事で摂取カロリーを抑える方が効果的です。例えば体重50kgの人が30分間のウォーキングで消費できるカロリーは、約92kcalで、これはバナナ1本分のカロリー、コンビニのおにぎりだと約半分にしかなりません。
具体的にどのくらいの摂取カロリーにしたら良いのかは、基礎代謝よりも多く、 消費カロリーよりも少ないカロリーにすることです。基礎代謝は心臓を動かす、呼吸、体温を保つなどの生きていくのに最低限必要なエネルギーのことです。それに対して消費カロリーは基礎代謝に加えて、NEATや食事や運動などで使ったエネルギーを合わせたものです。NEATは、非運動性熱産生のことで運動以外の日常生活活動による消費エネルギーのことです。例えば通勤や買い物を徒歩で行く、階段を使う、犬の散歩をするといったものです。割合としては基礎代謝が60% 、NEATが25%、食事誘発性熱産生が10% 、運動が5%です。
また、早く痩せたいなら摂取カロリーは基礎代謝よりも少なくした方が良いと思うかもしれませんが、それは体を壊すだけでなく、肌や髪もボロボロになります。なぜなら基礎代謝よりも少なく設定してしまうと脳は命の危険を感じて、体が少ないカロリーで生きていけるように基礎代謝を低下させ、省エネモードになります。基礎代謝が下がると、少しの食事でも消費カロリーを上回るようになります。つまり痩せにくい体になってしまいます。
具体的にどのくらいのカロリーを摂取したら良いかは、男性か女性か、身長や運動強度によっても変わってきます。そして1日に落とせる脂肪の量は 100g程度が限界だと言われています。体脂肪を1キロ落とすのに必要なカロリーは、 7200kcal、1日100g の脂肪を落とすなら消費カロリーよりマイナス720キロカロリーに設定することです。しかし実際1日に 200gの脂肪を落とすのはかなり食事を制限することになり、長期間の継続が難しくなるため1日50gのマイナス 360kcalを設定すると良いでしょう。1日 50gの脂肪なら1ヶ月だとマイナス 1.5kgになります。一方で、1ヶ月に落として良い体重の目安は自分の体重の5%までです。60キロの人だと 1か月に落として良い体重は3キロまでです。
ビタミン、ミネラル、食物繊維不足で太る
ビタミン、ミネラルはタンパク質、脂質、炭水化物の分解や合成を助ける働きがあります。不足するとこれらをエネルギーに変換できないため、体内に蓄積してしまい体脂肪を増やす原因になります。また食物繊維は便秘解消や血糖値を緩やかにしてくれ役割があります。腸内環境が悪い人は肥満になりやすいと言う研究があり、血糖値の急上昇、急降下といった乱高下が食欲を乱す原因にもなります。一汁三菜の主食、主菜、副菜、汁物を揃えた定食型の食事にすることで栄養バランスが整いやすくなります。
一方で食べ過ぎを防ぐポイントは、沢山噛んで一食あたり20分程度をかけて食べることです。なぜなら食事をしてから脳の満腹中枢に信号が伝わるまでに20分かかるからです。また睡眠不足になると食欲を抑制するレプチンの分泌量が減少して食欲を増進するグレリンの分泌量が増加します。その結果、食事量が増えてしまうので、最低でも7時間以上は睡眠時間を確保することが大切です。
基礎代謝を上げる方法
ダイエットと言えばジョギングのイメージがありますが、有酸素運動といった 運動をわざわざする必要はありません。普段運動していない人がジョギングをしたところできつくて継続することは難しいでしょう。また過去に糖質制限をしていて、結果としては痩せなかった方は、もしかしたら基礎代謝が落ちていて消費カロリーが低い可能性があり、食事制限をしても痩せられない体質になっているかも知れません。そのため基礎代謝を上げて消費カロリーを増やすようにしないといけません。
基礎代謝を上げるには、筋トレか褐色脂肪細胞を活性化させることです。効果的に痩せるには筋トレは必須です。食事制限をすると体脂肪が落ちるだけでなく筋肉も落ちてしまいます。基礎代謝全体の約22%を骨格筋が占めており、筋肉を大きくすることで基礎代謝を上げることができます。さらに筋トレを行うと筋肉からイリシンとホルモンが分泌され、イリジンは白色脂肪細胞を褐色化させ、褐色化した白色脂肪細胞はベージュ脂肪細胞と呼ばれ、脂肪を燃焼してくれます。特に筋トレは下半身を鍛えることが大事で、下半身の筋肉は全身の約60から70%の割合を占めていると言われるからです。この大きな筋肉を鍛えることで手っ取り早く基礎代謝を上げることができます。
一方の褐色脂肪細胞を活性化させる方法に寒冷刺激を与えることが挙げられます。具体的な方法はサウナで体を温め、冷水で体を冷やすことです。また家でできる方法なら、湯船をいつもより少し熱めにして体を温めてからシャワーで水をかけると良いでしょう。また褐色脂肪細胞を活性化させるには、肩甲骨のストレッチがおすすめです。肩を回すだけでも良いし、両手を上に上げるだけでもかまいません。
また、褐色脂肪細胞を活性化させる食べ物があります。例えば緑茶のカテキンが褐色脂肪細胞内にあるミトコンドリアを活性化させます。コーヒーに含まれるカフェインが褐色脂肪組織の熱産生機能を高めることが確認されています。スパイスでは、唐辛子のカプサイシンとカプシエイトが細胞を活性化し、生姜のジンゲロールも褐色脂肪細胞を活性化させてくれます。何れも体を温めてくれる食べ物です。サバ、いわし、サンマなどの青魚に含まれるEPAとDHAのオメガ3脂肪酸が褐色脂肪細胞を活性化させるだけでなく、白色脂肪細胞をベージュ脂肪細胞に変えてくれます。青魚以外にも、くるみやエゴマ油に含まれる脂質も同じオメガ3脂肪酸です。
お腹などの部分痩せはできない
お腹周りが痩せるには、一般的に3から6ヶ月かかると言われています。1日 100gの脂肪を落とす人は約3ヶ月、1日50gの脂肪を落とす人は約6ヶ月です。ただ1日100gを落とすことは継続が難しいでしょう。何れにせよ、お腹の皮下脂肪を落とすのは長期戦であることを理解して、無理なくダイエットを継続させることが大事です。
また、脂肪には内臓脂肪と皮下脂肪の2種類あり、内臓脂肪は腸などの内臓の周りに蓄積した脂肪でつきやすく落としやすいことが挙げられます。一方の皮下脂肪は皮膚のすぐ下の皮下組織にできる脂肪で、一度つくとなかなか落ちません。なぜなら皮下脂肪は内臓脂肪と比べて脂肪を分解する細胞の数が少ないからです。そして脂肪の減る順番は、個人の体質にもよりますが、多くの人はふくらはぎ、二の腕、肩周り、太もも、お腹、お尻といった血流量が多い場所から脂肪が分解されます。一番気になるお腹の皮下脂肪は、最後から2番目に落ちるようになっているため、ダイエットを始めて4から6ヶ月頃にやっとお腹が痩せてきます。
皮下脂肪を落とすためには、摂取カロリーを基礎代謝より高く、消費カロリーより低く設定することです。運動を頑張っても、ご飯をたくさん食べると痩せることはできないし、脂肪を燃焼する食べ物や飲み物で痩せやすい体になったとしても摂取カロリーが消費カロリーを上回っていると痩せることはできません。
また、運動だけで痩せるより食事の方が効率よく痩せることができます。実は運動は、思っているよりカロリーを消費しません。例えばペンシルベニア州立大学の研究でも実証されており、食事のみと食事に有酸素運動を加えて3ヶ月で落ちた体重を比較しました。結果は食事のみはマイナス6.3kgに対して、食事と有酸素運動ではマイナス6.8kgでした。つまり有酸素運動を加えても体重はほとんど変わってないことになります。
一方で、お腹の皮下脂肪を落とすために腹筋を鍛えている人は多いですが、実際のところ部分痩せはできません。人間の体には特定の脂肪だけを減らすような機能は存在しません。南イリノイ大学の研究では、お腹周りのエクササイズを行うだけではお腹の脂肪は減らないことが分かっています。
筋トレをするなら大きい筋肉を刺激できるスクワットが良いでしょう。効率よく筋肉量を増やしたいなら、まずは正しいフォームで行うことが大事で、正しいフォームでないと筋肉への負荷が軽くなってしまいます。回数は、1種類のトレーニングを8から12回、もしくは約40秒間行える負荷にすると筋肉がつきやすくなって消費カロリーを増やせます。
また、ながら食べをすると摂取カロリーが増えることが分かっています。研究では、食事に集中するグループとスマホを使用しながら食事するグループ、本や新聞を読みながら食事をするグループに別れて食事を摂ってもらいました。気を散らすことなく食事するグループと比べて、スマホを見ながら食事をしたグループは10%、本や新聞を読みながら食事をしたグループは14%も摂取カロリーが増加していました。これは食べることに意識が行かないことが原因と言われています。何かをしながら食事をすると咀嚼回数が減り、早食いにつながってしまい、その結果、満腹中枢が刺激される前に食事が終わり、満足感が得られず余計に多く食べてしまうからです。
そもそも私たちの食欲は脳の視床下部にある摂食中枢や満腹中枢によってコントロールされています。この満腹中枢は脂肪細胞のレプチンから信号を受け取ることで働きますが、ダイエットによって脂肪細胞が減少するとレプチンの分泌量も減るため、普段食べている量では満腹中枢が働かなくなり、結果いつもと同じ量を食べているのにお腹がいっぱいにならず食べ過ぎてしまいます。
このように痩せれば痩せるほど食欲を我慢するのが難しくなる事は様々な研究で明らかになっています。例えばロックフェラー大学の研究では、人間の食欲は喉が渇いて水を飲みたいという欲求と同等以上に強いということも分かっています。つまり自然と食欲を抑える方法を知らなければ痩せるのが難しくなります。
ダイエット成功のための2つの条件
ダイエット成功のためには、体脂肪を減らして体重を落とすこと、そして筋肉量を増やすことです。当たり前のことですが、意外と実践できている人は少ないです。体脂肪を落として筋肉を増やす、この2つの条件を同時に満たさないといくら運動を頑張っても痩せない状態に陥ってしまいます。
まずは、意外かもしれませんが短い有酸素運動です。有酸素運動は長くやらないといけないと思っている人が多いです。この短い有酸素運動は消費カロリーを稼ぐためにするのではなく、食欲をコントロロールするために行うことを理解することが大事です。そもそも有酸素運動の消費カロリーは、例えば4km走ってもおにぎり1個分に過ぎません。一方短い有酸素運動で食欲を抑えることができることは研究でも明らかになっています。
オーストリアのインブルック大学の研究によると15分の早歩き程度の短い有酸素運動で、女性の97%が食欲を抑えることが確認されています。これに対して長時間の有酸素運動は食欲を乱して太りやすくなることが、米ネブラスカ大学 の研究で分かっています。具体的には45分の長い有酸素運動をすることで、被験者の摂取カロリーは10%も増えています。また効率的に痩せるためには、インスブルック大学の研究では、食事30分前に15分だけ早歩き程度の短い運動を取り入れることが実証されています。
さらに、サイクリングやマシンを使った高い有酸素運動では、食欲が乱れることに加えて筋肉量が減ってしまいます。もちろん時間の長さや負荷のかけ方次第で効果的な場合はありますが、専門的な知識や経験を持っていない一般の人がその点を踏まえて実践することは難しいでしょう。
筋肉量が落ちることを明らかにした研究があり、米ウエイクフォレスト大学が運動なしのダイエットと強度の高い有酸素運動のダイエットを行った場合の筋肉量の減少量を比較しています。その結果、ダイエット中の強度の高い有酸素運動は筋肉を著しく落としてしまうことが分かっています。つまり多くの方が勘違いしている強度の高い有酸素運動は、綺麗に痩せるためには向いていないダイエット方法になります。これらからウォーキングこそが筋肉を維持し、さらに食欲をコントロールしながらカロリーを消費でき、綺麗に脂肪を落とせる運動になります。
綺麗に痩せられる強度の高い筋トレ
筋トレには、強度が高い、低いがあり、軽い負荷の筋トレを延々としている人をジムで見かけますが、これは全く無意味です。強度の低い筋トレの効果がない理由は、それは「漸進性過負荷(ぜんしんせいかふか)の原則」にあります。この原則は、毎回同じ負荷の筋トレでは筋肉は成長しないということを意味して います。同じ筋トレでも強度を上げるためには、まず回数を徐々に上げること、例えば10回3セットを基本にして、クリアできたら次は12回3セットにするといった感じで、徐々に負荷を上げていき、そして重量で負荷を上げていくことも忘れずしましょう。
まず何から始めればいいか分からない人は、どんな種目でもいいから家でできる筋トレを週に2回を目標に習慣化しましょう。具体的には足とお尻の筋トレならワイドスクワット、それからヒップリフト、お腹の筋トレならレッグレイズ、胸と二の腕の筋トレならプッシュアップなど、この辺からトライしてみましょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。