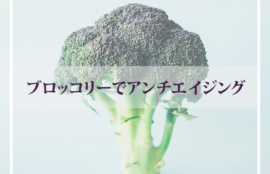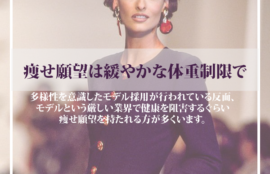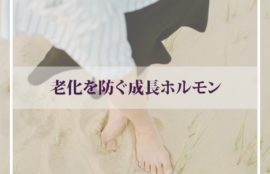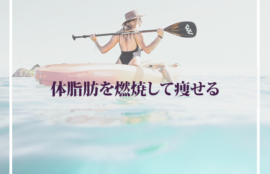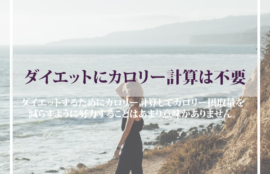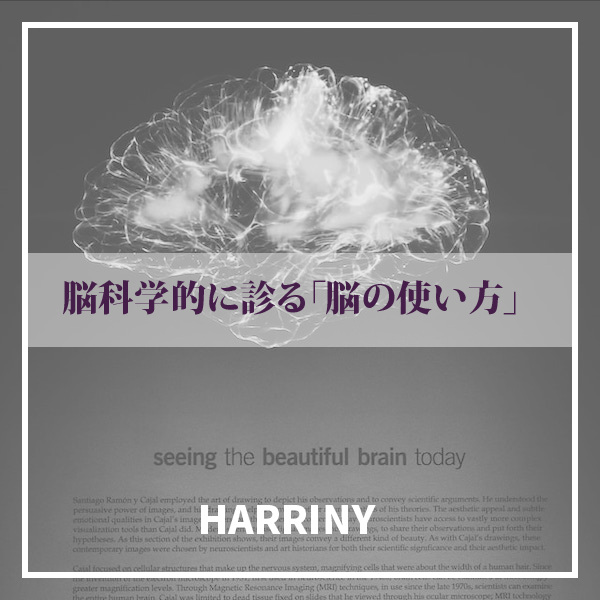
私たちは、脳の使い方を誰かに教わることがありません。その結果、潜在能力を十分に発揮できず、自分は能力が低い、自分は頭が悪いと間違った思い込みをしている可能性があります。一方で世の中には、脳をうまく使えている人もいます。
例えば、脳の使い方がワンパターンにならないように常に心掛けワクワクした気持ちで毎日を過ごし、意識的に行動を変え続けることによって脳をいつも洗練されたクリアな状態にキープできている方がいます。彼らは、常に脳を冴えさせることを意識し、脳を冴えさせる習慣を実行しています。
思考回路が固定化してしまっていると、脳の一部しか使わないことによって行動がパターン化し、思い浮かぶアイデアも考えも固定化され、脳はガチガチの状態にあります。普段私たちは気づかないうちに、脳の特定の領域ばかりを使いながら生活してしまっています。
脳は自分自身を守るために機能しており、危険を避けるために過去に経験してきたことの中から安全なものや楽なものばかりを選択するようにできています。その結果、考え方が次第に固定化してしまうのです。しかし固定観念にとらわれていると脳そのものの進化が止まり、老化してしまいます。脳の老化は、やる気を奪う、引きこもり、認知症、目に見えた老化へとつながってしまいます。
脳の老化の影響
実は、脳の老化が体や見た目に大きな影響を与えます。例えば脳の老化に伴ってホルモンの分泌が減少します。特に成長ホルモンなどの減少は、皮膚のたるみ、骨密度の減少など体の老化現象に密接に関係しています。これらのホルモンの減少は、見た目や身体機能にも影響を与えます。また脳の神経細胞同士の情報を伝達には神経伝達物質と呼ばれる化学物質が使用されており、脳の老化により神経伝達物質の生成や放出が減少し、体の機能や見た目に影響が出てしまいます。
また、脳の老化に伴い脳への血流が低下することもあります。これによって脳への酸素や栄養素の供給が不十分になってしまい、脳の機能が低下してしまいます。脳の血流の低下は、認知機能や運動機能の低下につながり、ひいては体の老化、見た目の老化などにもつながります。
慢性炎症とフレイル
当然のことながら認知症と老化は大きく関わっています。体が若々しい人は脳も若々しいということが分かっており、老化を食い止める習慣を実行してあげることは認知症を予防することにつながります。そして中でも老化を進めるものとして近年注目されているのが慢性炎症です。
慢性炎症というのは老化に伴ってじわじわと長く続く炎症のことです。弱い炎症で気づかないうちに進みますが、様々な病気を引き起こすと考えられています。認知症も慢性炎症によって引き起こされると近年考えられるようになってきています。さらに慢性炎症は、高血圧や糖尿病、肥満、高コレステロール値といった認知症のリスクを高める病気の発症にも大きく関わっています。
そして慢性炎症に加えて老化を進めてしまうもう一つの大きな原因がフレイルです。フレイルとは心身の機能が大きく低下しつつある体が弱っている状態のことです。身体的機能や認知機能の低下が見られ、介護が必要な一歩手前の状態がフレイルです。一旦フレイルになっしまうと老化がどんどん加速してしまうので、筋肉量を維持するとかタンパク質をしっかり取るといった対策が重要です。
この2つにはどちらも共通しているものが多く、お互いに関連し、フレイルを予防するための運動は慢性炎症を抑え、血圧や血糖値を下げることができます。また口のフレイルを予防するための口腔ケアは、慢性炎症を起こす歯周病の予防につながります。認知症を予防するには慢性炎症とフレイルの予防の2つが重要になります。
脳が冴える習慣
脳のブロックを解除する
脳が冴えるというと瞬時に記憶したり、仕事を高速でこなせることだというイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし脳の高次機能は、これまでの経験や思い込みにとらわれないで柔軟な発想ができるということであり、つまり自由な発想力が持てることでしょう。
脳に自由な発想をさせるには、それを妨げている脳のブロックを外す必要があります。実は脳のブロックを外すのは簡単で、常日頃からありがとうと感謝の言葉を口にするだけです。ありがとうとか君がいて助かったよなど、他人に愛情や感謝を伝えることによって脳が自由な発想ができるようになります。
これには脳科学的な理由があります。人の脳はネガティブな感情に一旦縛られてしまうとブロックがかかり固定化されてしまいます。そしてネガティブな感情から思考が固定化してしまうと、脳へ情報を伝達するシナプスの働きがパターン化します。その結果、これまでの経験や知識にとらわれ、新しい発想が生まれにくくなります。
また、感謝や愛情を積極的に伝えることによって私たちの脳内ではオキシトシンというホルモンが分泌されます。オキシトシンは信頼感やつながりを感じることでストレスを低減し、幸福感を高める効果があります。その結果、脳の機能が向上します。そして感謝や愛情を伝えることでストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制されます。ストレスが軽減されることで脳がリラックスし、集中力や創造性が高まります。また感謝や愛情を表現することによってポジティブな感情が活性化されます。ポジティブな感情は学習や記憶、問題解決能力など脳の機能に良い影響を与えてくれます。またポジティブな感情はネガティブな感情を和らげる効果があるため、ストレスや不安が軽減され、脳の働きが向上します。
コンフォートゾーンを抜け出す
脳は何もしなければどんどん怠け放題になっていきます。快適な場所に居続けてしまうと老化が進行していく傾向にあります。脳は神経可塑性という性質を持っていて、経験や環境に応じて構造や機能が変化します。しかし何も刺激を受けない快適な場所では、脳は新しい回路を作り出すことが難しくなって機能が低下しやすくなります。また脳内の神経細胞はシナプスと呼ばれる接合部を通して情報を伝達します。何もしないような状態では、シナプスの数が減少し、情報伝達が効率的に行われなくなります。また何もしない状態では脳の認知機能が低下したり、脳の老化が進む可能性があります。
研究によれば、脳を活性化させる活動や運動を行うことで脳の老化を遅らせることができます。その脳を活性化するための方法が、不愉快な場所に飛び出すという方法です。人は無意識にコンフォートゾーン、すなわち居心地の良い場所を作ってその中にとどまろうとしてしまう性質があります。思い切ってコンフォートゾーンを抜け出すことによって、新しいスキルや知識を習得することができたり、自己成長することができます。痛みなしでは成長することができないし、痛みなしでは何も得ることができないのです。
さらに新たな挑戦や経験を通して揺るぎない自信を築くことにもつながるでしょう。また新しい状況とか変化に適応する能力が鍛えられて柔軟性が向上します。柔軟性は変化の激しい現代において、特に重要な力であると言われています。さらにコンフォートゾーンを抜け出すことによって居心地の良い人とばかりつるむのではなく、新しい出会いがあったり、少々苦手であってもあえて付き合うことによって様々な価値観に触れ合うことができコミュニケーション 能力も向上します。新しいことに挑戦するには、最初は面倒くさかったりとエネルギーが必要です。脳を研ぎ澄まし、老化を防ぐためには不愉快な場所に飛び出すことが時には必要です。
脳の構造を大きく変えるのは運動
運動が健康に良いのは明らかですが、脳にも非常に良い影響を与えます。ランニングやウォーキングなどの運動は、脳を活性化させる働きがあることが分かっています。それは足の大きな筋肉や背中の筋肉を効率的に使い続けることによって、脳がしっかりと刺激されるからでます。
さらに走りながら目にする景色が変化することで脳が活性化します。さらに運動によって全身の血流が向上し、脳への酸素や栄養素の供給が増加します。これによって脳のエネルギー代謝が向上し、神経細胞の機能が活性化されます。また運動はBDNFなどの神経成長因子の分泌を促進します。
神経成長因子は神経細胞の生存や成長をサポートし、シナプスの形成や可塑性を促してくれるため脳の機能が向上します。また運動によってストレスホルモンの分泌が抑制され、ストレスが軽減されることで脳の機能が改善される効果も期待できます。
そしてランニングやウォーキングに加えて、ヨガも非常におすすめです。例えばヨガは集中力や記憶力をさせることができます。その理由に、ヨガのポーズや呼吸法によって脳の活性化が促進されることが原因とされています。またヨガによって脳の神経細胞が活性化され、メンタルが安定することも指摘されています。さらにヨガは、睡眠の質を向上させることができ、脳にとって大切な良質な眠りを与えてくれます。
フロー状態とFF状態
実は、脳は何かに一所懸命取り組んでいる時に最も働いているというのがこれまでの常識でした。しかし近年、脳科学では何も考えずいる時も同じくらい活発に働いていることが明らかになっています。その活動スイッチが、脳幹や島皮質(とうひしつ)と呼ばれる脳の部位です。
例えば、スポーツなどではよく、フロー状態という特別な集中状態なると普段と違うパフォーマンスが発揮できると言われています。そこに入るスイッチが脳幹や島皮質にあると言われています。しかし脳幹や島皮質は無意識領域にあるため、自分で意図してスイッチを入れることはできません。
また、リラックスした状態であるフロー状態とは逆のFF状態もあります。FF状態は、動物が外敵に直面した時のような極度の緊張状態であり、脳内の他のあらゆる回路をシャットダウンして、戦うか逃げるか選択と行動だけにエネルギーを集中します。FF状態になれば、一時的に大きな力を発揮して戦うもしくは逃げることができますが、過度なストレス反応でもあるために慢性化すると、無気力状態に脳が陥ってしまいます。
近年、脳科学で明らかになってきたフロー状態は、「Awe(オウ)体験」の一部だと考えられています。例えば宇宙飛行士が、宇宙から青く美しく光る地球を見ると、自分自身は何者かに生かされていると実感し、深い感謝の念が湧いてくるといいます。こうした心が震えるような感動体験をAwe体験といい、その状態になると脳は活性化し、謙虚な気持ちになることが明らかになっています。Awe体験は大自然の前でちっぽけな自分を感じた時や、徳の高い人の言動に感動した時などに体験することがあります。
脳をサポートする食事
脳の機能をサポートするための食事には条件があります。それは認知機能をサポートする栄養素や成分をしっかりと取ること、腸内環境を整え免疫力をアップし、病気にならない体づくりを心がけること、老化を促す活性酸素の害から体を守る抗酸化物質を取り入れることです。
そして脳の働きを最大化する上で非常に重要な役割を担っているのが食事です。特に 大きな役割として以下の4つの点を挙げることができます。
| 脳が必要とするエネルギーを脳に供給する役割 | 脳内のエネルギーが不足すると脳はスリープ状態になってしまい、その機能は低下してしまいます |
| 脳や体の細胞の材料を供給する役割 | 脳内の海馬は90歳でも新しい細胞が 繰り返し生まれ変わっています。また脳の機能に大きな影響を与えている血流も、血管の健康状態に左右されています。 血管の新陳代謝のためにも細胞の材料を食事から摂取し続けなければなりません |
| 脳や体を老化させる原因を遠ざける役割 | 抗酸化物質が含まれている食品の摂取は、脳や体の酸化、老化を予防する役割があります |
| 良いサイクルを生む体質に体を変える役割 | こうした体質づくりには運動や生活習慣とともに食事が大きな役割を果たします |
認知機能のアップにはLSP
例えば、認知機能のアップには、認知症の原因物質を減らす、通称免疫ビタミンとも呼ばれる LPSという物質が注目されています。さらにビタミンB群、ビタミンDなども重要です。これらの要素は認知機能を低下させる物質を減らしてくれたり、長寿遺伝子を増やしてくれたりします。
そして健康で若々しい体をキープし、できるだけ病気にかからずに暮らしていくためには、免疫力をしっかりと高め、病気を遠ざけることが重要です。体には感染症などの病気から身を守るために免疫というシステムがあらかじめ備わっています。そして私たちの免疫細胞はストレスに弱いという弱点があります。例えば短期的にストレスがかかった場合、免疫力は一時的にガクンと低下します。また長期にわたる慢性的なストレスの場合は、免疫力により深刻な悪影響がもたらされてしまいます。
しかし、その弱点を補ってくれるのがLPSと呼ばれる物質です。LPSは免疫ビタミンとも呼ばれ、免疫細胞を活性化してくれる物質です。土の中の多くに存在する細菌に由来しているため、土壌細菌が多い畑での農作物に多く含まれていす。例えばほうれん草やオクラ、小松菜、きゅうり、レンコンといった野菜にLPSが豊富に含まれています。
このLPSは、免疫細胞を活性化してくれるだけでなく、直接脳に入り込んで脳のマイクログリアという細胞を刺激します。このマイクログリアは、認知症の原因物質であるアミロイドβを食べてくれるという細胞です。このマイクログリアがうまく働かないとアミロイドβが脳に蓄積し、認知症の原因になってしまいます。
LPSは人の体内では作り出すことができません。そのため私たちは食事から摂取する必要があります。 LPSは土の中に多く存在する細菌の成分のため、自然な土地で栽培されたものにはLPSが豊富です。できるだけ無農薬や減農薬栽培された泥付きの野菜を選ぶのがおすすめです。
また、LPSは皮の部分に多く含まれており、食べられる皮はできるだけ剥かずに調理すると良いでしょう。ただしLPSは熱に弱いという特徴を持っています。生で食べられるものはできるだけ生で食べるのが理想です。
食物繊維とフィトケミカル
一方で、免疫力を語る上で必ず欠かせないものが腸の健康です。なぜなら免疫細胞の約70%は腸に存在しているからです。腸が健康であれば老廃物がしっかりと体の外に排出され、腸内細菌のバランスが整い、免疫力アップにつながります。その腸内環境を整えるためには、食物繊維が重要な鍵となります。食物繊維や発酵食品をしっかりと摂取して腸が健康になると免疫力がアップするだけでなく、肥満や糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防改善にも役立ちます。
もう一つの重要な条件が、抗酸化物質を取り入れることです。体の老化を進め 免疫力を低下させるのは、活性酸素という物質です。活性酸素からしっかりと身を守るためには、植物が持っている天然の抗酸化成分フィトケミカルが重要です。ベータカロテン、リコピン、アントシアニンなどがフィトケミカルの一種です。
フィトケミカルは、植物が外敵から自分の細胞を守るために作り出した色素や香り、辛味、苦味などの成分です。実際に、これらの成分は第7の栄養素と呼ばれ、私たちにとって非常に重要なものです。またフィトケミカルは、旬の野菜ほど多く含まれるという特徴があります。野菜や果物の旬を意識して選ぶことも大切です。フィトケミカルは植物にしか含まれていないため、野菜や果物をしっかり摂ることが活性酸素の害から身を守ることにつながります。
野菜や果物をしっかりと食べている人は、若々しく肌や髪が綺麗なイメージあります。それは野菜や果物に豊富に含まれるビタミンやミネラル、フィトケミカルが含まれており、これらの成分には抗酸化作用があって、若々しさを保つことができるのです。
さらに野菜や果物は栄養価が極めて高いです。ビタミンやミネラル、食物繊維などが含まれていて、これらの栄養素は健康な皮膚や髪の成長、血液循環の改善、免疫力向上などに役立ってくれます。また野菜や果物には、炎症を軽減する成分が含まれているという点も見逃せません。
慢性的な炎症は老化や疾患の進行に関連していることが知られています。野菜や果物の摂取によって炎症反応が抑制され、細胞や組織の健康を維持することができます。
脳を活性化するプラズマローゲン
脳が若い人が食べているものが、プラズマローゲンたっぷりの海産物です。プラズマローゲンは、脳を活性化させ、認知症を防ぐのに欠かせない栄養素と言われています。九州大学の報告によれば、プラズマローゲンを摂取すると認知機能が改善するということが分かっています。
プラズマローゲンを含む食材の代表は、ホタテです。ホタテから摂取できるプラズマローゲンには、脳に良いとされているEPAやDHAも含まれていています。またホタテには、疲労回復に効果的なタウリンやアスパラギン酸なども豊富に含まれています。さらにホタテには高品質なタンパク質も豊富に含まれているのに加えて、亜鉛、鉄、ビタミンB12などのミネラルやビタミンも含まれています。またホタテには、抗酸化物質であるセレンやビタミンEも含まれています。
また他にもプラズマローゲンを含む食材として、見た目の若さを維持してくれる海の恵みがタコです。タコには、プラズマローゲンに加えて若さを維持する のに役立つビタミンE、血行を良くするナイヤシン、肌を健康に保つ亜鉛が豊富に含まれています。また肥満防止効果があり、粘膜を保護するビタミンBも含まれています。
ホタテやタコに加えて、プラズマローゲンを含む食材であり、強力な抗酸化作用を持つ魚が鮭です。鮭には、プラズマローゲンに加えて、ピンク色の色素アスタキサンチンが含まれており、アスタキサンチンは抗酸化作用が強く、老化の原因となる活性酸素から私たちを守ってくれる物質です。さらに鮭にはEPA、DHAも豊富に含まれているため、脳にとても良い影響をもたらしてくれます。
脳にとって重要なオメガ3脂肪酸
イワシ、アジ、サンマなどの青魚に含まれるEPA、DHA、あるいはエゴマ油や亜麻仁油に含まれているαリノレン酸といったオメガ3脂肪酸は。老化を溶かす最強の脂です。
オメガ3脂肪酸は、認知症の原因になる脳内のアミロイドβなどの老化物質を 溶かしてくれる働きがあると言われており、さらにオメガ3脂肪酸は脳の中にも存在し、脳の情報伝達の際に重要な働きをしているシナプスや細胞膜の働きを活性化してくれます。また脳の機能を高めてくれるため、加齢とともに低下する記憶力や認知機能の低下を緩やかにしてくれる効果もあります。
ただし注意していただきたいのは、オメガ3脂肪酸は酸化しやすい、つまり熱に弱いです。摂取するにはエゴマ油や亜麻仁といったオメガ3脂肪酸が豊富な油を加熱せずにサラダやその他の料理に直接かけて食べるといった工夫が必要です。
ダークチョコレートで脳機能が高まる
ダークチョコレートを食べ続けることで脳の機能が高まって頭が良くなる可能性が示唆されています。その鍵には、まず脳の血流が良くなるということが挙げられます。実際にフラボノイドが含まれたダークチョコレートやココアを摂取することによって脳の血流が改善されることが研究によって明らかになっています。
脳の血流が改善されれば、注意力が上がったり、記憶力が向上する効果が期待できます。実際にある研究では、記憶力と反応速度を測定する2時間前にダークチョコレートを食べると、その両方が向上したことが分かっています。
またココアやダークチョコレートに含まれているフラボノイドは、軽度認知障害のある高齢者の認知機能を維持し、認知症に進行する可能性を減らしてくれる可能性も指摘されています。さらに2018年の研究では、カカオ70%のオーガニックチョコレートを定期的に48g食べた人たちは、新しいシナプスの結合を形成する脳の力が増加して、記憶力にプラスの影響がもたらされたことも分かりました。またその他の研究でもダークチョコレートを摂取することによって、記憶と学習が強化されることも分かっています。またカカオがたっぷりと含まれたダークチョコレートは BDNFという脳にとって重要な物質を増やしてくれるのではないかと言われています。
BDNFの正式名称は脳由来神経栄養因子で、これは脳や神経系の健康と発達に 重要な役割を果たしているタンパク質です。私たちの脳は神経細胞の塊でできており、非常に複雑な働きをしています。そういった複雑な脳をいつも支える 代表的な栄養素がBDNFです。脳に非常に良い影響を与えてくれ、脳を育ててくれることから、BDNFは脳にとって奇跡の肥料などとも呼ばれています。
例えばBDNFは、脳内のニューロンの生存と成長を支援します。これによって脳を健康に保ち、新しい情報を学習し、記憶する能力をキープすることができます。またBDNFは、シナプスの可塑性を高めてくれます。シナプスは神経細胞間で情報を伝える接続点となるもので、その可塑性とはシナプスの強さや数を調節する能力のことを指しています。これは学習と記憶に対し重要な役割を果たしています。
またBDNFは、新た神経細胞の生成を促進します。特に海馬と呼ばれる脳の部位では、新たな神経細胞の生成が記憶形成や学習に重要であり、BDNFのレベルがこれらのプロセスに影響を与えると考えられています。BDNFは、特に海馬に多く存在し、海馬で神経細胞の働きを活性化してくれることが分かっています。
一方で、年を取るにつれて私たちの認知機能や脳の機能は衰えていってしまいます。そして年を取るにつれて認知症の発症リスクも自然と上がってしまいます。その理由は、年を取るにつれてBDNFが減ってしまうことが挙げられています。つまり加齢による認知機能の衰えを防ぐにはBDNFを増やすことが効果的な予防方法の一つです。
ダークチョコレートを摂取することによってBDNFが増加し、認知機能が高まる可能性が指摘されている調査があります。2014年の大規模な調査では、カカオポリフェノールがBDNFを含む脳の血流を増やし、認知機能を高める可能性が示唆されました。ダークチョコレートを摂取することによってBDNFが、ダークチョコレート摂取前よりも上昇していることが確かめられました。
もちろんBDNFを増やす方法は、ダークチョコレートを食べることだけではありません。例えば代表的なものが有酸素運動になります。有酸素運動を続けることができれば、BDNFが増えて頭が良くなるのは最近の科学の世界ではとても有名な話になっています。
ダークチョコレートの中毒症状
チョコレートには中毒症状があります。全てのチョコレートの原料はカカオの木という熱帯植物で、学術名はテオブロマカカオと言います。ギリシャ語でテオは神、ブロマは食べ物を表し、カカオの木は神の食べ物という意味となります。
カカオの木の実であり、チョコレートの原料であるカカオ豆には、デオブロミンと呼ばれている成分が含まれています。カカオ成分が高いダークチョコレートに含まれているデオブロミンは約800mg、カカオ成分が低いミルクチョコレートにはデオブロミンが約200mg 含まれています。このテオブロミンがカフェインとよく似た働きをしています。
テオブロミンを摂取することで脳が覚醒したり、眠気や疲労感が回復するという効果を期待できます。ただしデオブロミンはカフェインと同じく大量に摂取することで毒性が現れます。テオブロミンを大量に摂取すると食欲低下、発汗、震え、頭痛、血圧の低下、心拍数の増加といった様々な症状が出る危険性があります。どんな健康に良い食べ物であっても食べ過ぎには注意が必要です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。