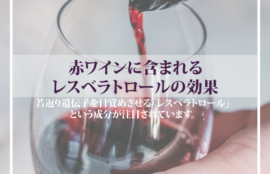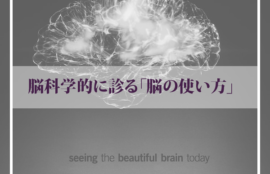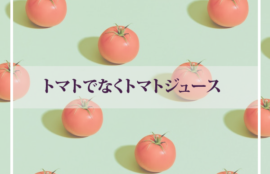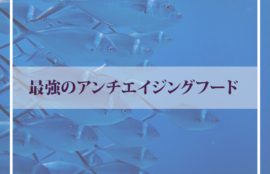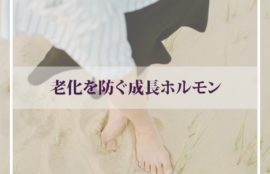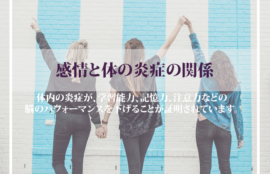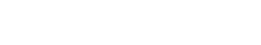病気でないけど、疲れが取れない、体調が悪い、怒りっぽい、落ち込み易いなど、不定愁訴を抱えている人が増え続けています。あまり聞きなれない言葉ですが、それは「副腎疲労」に罹っている可能性があります。
副腎は、腎臓の上に乗っている小さな臓器で、ホルモンを分泌する器官です。皮の部分である副腎皮質では、コルチゾール(ステロイドホルモン)が作られます。あんこの部分の副腎髄質では、神経細胞の興奮を他の神経細胞に伝える神経伝達物質(アドレナリンなど)が作られます。このように副腎の働きは、ホルモンの分泌、血糖コントロール、免疫機能、炎症反応など重要な機能を担っています。
副腎疲労とは
副腎が疲労する原因は、あらゆるストレス、慢性炎症(アレルギー、歯周病、腸内環境、肝機能障害)、偏った食事(血糖値の乱高下)です。特にストレスに対しては、ストレスを受け続けると、自律神経の交感神経と副腎のホルモン(コルチゾール)で対処します。つまり、コルチゾールは身体を戦闘モードに切り替えために、コルチゾールで血圧や血糖値を上げて戦おうとします(交感神経優位)。コルチゾールが分泌されると大量の活性酸素(からだの錆び)が発生しますが、それを防いでくれるのがDHEAです。
このコルチゾールが増えると同時にDHEA(マザーホルモン)も体内で分泌され、急激に上がったコルチゾールレベルを元の状態に戻すように働きかけてくれます。このような理由で、コルチゾールをストレスホルモン、DHEAを抗ストレスホルモンと呼ばれます。このバランスが凄く大切で、過度なストレスが続くとコルチゾールが過剰に分泌し続け、副腎が疲れてDHEAも出せなくなってしまいます。この状態を副腎疲労といいます。
副腎疲労でDHEAの分泌が減少すると、更年期症状の悪化、PMS、太りやすくなる、気力減退、 お肌のハリツヤ減退(老化) などが生じます。特に現代のストレス過多の社会では、この副腎への負担がとても大きくなっています。
副腎の働き
副腎の働きは、様々なホルモン(アドレナリンやノルアドレナリンなど)を分泌して、私たちの心身のバランスを維持することです。そのホルモンの中で最も体を守るために重要な司令塔は「コルチゾール」です。
コルチゾールはストレスホルモンと言われ、ストレスから守ってくれるホルモンで、実に様々な働きに担ってくれます。
- タンパク質や脂肪を分解したり、血糖値を上げたりする作用によってエネルギーを引き出す
- 抗炎症作用や免疫抑制によって慢性炎症を抑える効果
- 睡眠のリズムやストレスをコントロールし、1日の生活リズムを整える
コルチゾールを分泌のメカニズムをHPA軸のフィードバックシステムと言い、脳の視床下部から下垂体へ、そして副腎に命令が伝達することでコルチゾールが分泌されます。つまりこの命令の伝達が上手く行かなくなると、コルチゾールの分泌が乱れ、所謂「副腎疲労」に繋がってしまいます。
慢性炎症、ストレス、運動不足、低血糖、睡眠不足、この5つが全ての病気の根本原因だと言われていますが、その理由は、コルチゾールの分泌を乱すのがこの5つの原因であり「副腎疲労」に繋がる原因だからです。
因みに腸内環境を整えることにもコルチゾールは密接に関係しており、コルチゾールの分泌を整えなければ、いくら腸活しても腸内環境は乱れたままになります。
副腎疲労の根本原因
あらゆる病気を引き起こす「副腎疲労」の根本原因は、慢性炎症、低血糖、睡眠不足、ストレス、運動不足であり、これらを解消する方法は生活習慣の改善しかありません。
副腎疲労と3つのストレス
継続的なストレスを長期にわたって受け続けてしまうと、ストレスに対抗するホルモンであるコルチゾールを分泌している副腎が酷使され「副腎疲労」を招いてしまいます。この副腎疲労によって体の老化が引き起こされたり、脳に毒が蓄積され認知機能が低下したり、認知症の発症へと繋がってしまいます。そのため脳を解毒して、認知症への進行を食い止めるためには副腎疲労の原因となっているストレスを解消する必要があります。
ストレスというと多くの人は人間関係の悩みなどといった精神的なストレスを思い浮かべるかもしれませんが、ストレスには「精神的なストレス」だけではなく「環境ストレス」や「肉体ストレス」を含めた3つのストレスがあります。これらの3つが重なった過剰なストレスが、現代人の副腎に大きな負担をかけ、脳に毒がたまりやすくなる要因となっていると指摘されています。まずはストレスを解消するための第一歩は、何に対して自分がストレスを感じているのかを把握することです。
これらの3つのストレスの中で、一番わかりやすいのは「精神的ストレス」です。パワハラ、人間関係のいざこざ、介護問題など出口の見えにくい苦境による心の負担が「精神ストレス」です。この精神ストレスは自覚しやすい反面、自分でコントロールすることが難しく、終わりがなかなか見えにくいということが、体への負荷を倍増させてしまいます。
一方で、「環境ストレス」や「肉体ストレス」は自覚しづらいという特徴があります。自覚しづらいがゆえに自分ではそれをストレスと感じていないことが大半です。また「環境ストレス」は、例えば大気や食品を通して体内に入る化学物質や金属類、紫外線、睡眠環境などが挙げられます。そして「肉体ストレス」は長時間労働、運動不足、不規則な生活リズムといったものが挙げられます。
現代社会に生きる限り、この3つのストレスからは逃れようがなく、完全にストレスフリーで生きることはもはや難しいと言わざるを得ません。しかしストレスは認知症だけでなく、あらゆる病気の引き金になるということもわかっています。それにも関わらずいくつものストレスを抱えながら、何とか頑張って生きていけるのはストレスに上手に適用する仕組みが私たちの体に備わっているからです。それが副腎と呼ばれる臓器にあります。
副腎は、ストレスを受けた時にコルチゾールと呼ばれるホルモンを分泌し、目の前のストレスに対処しようします。このコルチゾールはもともと人間が狩猟生活をしていた太古の昔からストレスに対抗するホルモンとして大切な役割を果たしてきました。例えば命を脅かす猛獣と戦いでは、突発的なパワーが必要となり、体は脅威というストレスを受けると副腎からコルチゾールを多量に分泌し、血圧や血糖値を急上昇させるとともに体内のタンパク質や脂質を分解し 瞬時にエネルギーを生み出す仕組みを進化の過程で獲得しています。
しかし、昔と今ではストレスの質が全く違い、今では 3つの長く続くストレスによって副腎は、絶えずフル稼働し、コルチゾールを分泌し続けなければならない状態になっています。やがて副腎が働き続け、疲れ果て、コルチゾールが枯渇し、副腎の機能の低下によってコルチゾールの分泌が不安定になっていまいます。この状態を「副腎疲労」と言い、副腎疲労によってコルチゾールの分泌異常が続くと脳と体に大きなダメージが及ぼされてしまいます。
副腎疲労と慢性炎症
体の中で知覚できないレベルの炎症が続いている状態を「慢性炎症」と言い、脂肪肝、リーキーガット症候群、肥満、うつ、老化、不眠を引き起こします。慢性炎症を例えるなら、体の中で火事が起こり続けている状態で、炎症性サイトカインが作られ過ぎて、持続した炎症を沈静化することができず、全身に火事が広がり、組織の繊維化(硬くなり戻らない現象)が起こります。
これにより機能が低下しますが、例えば肝臓で起こると肝硬変になります。特に肥満の方は、炎症性サイトカインの分泌が誘発されて、脂肪組織がどんどん炎症を起こしている状態になっているので注意が必要です。さらに慢性炎症は慢性的に体にストレスがかかっている状態であり、コルチゾールが過剰に分泌してしまう「副腎疲労」を引き起こす原因になります。
このように過剰なストレスによってコルチゾールが大量に分泌されると、慢性炎症が起き体中に毒素が巡ります。私たちの体を構成する細胞と細胞の間にはタイトジャンクションと呼ばれるつなぎ目があり、コルチゾールの過剰分泌によって慢性炎症が起きると、腸壁細胞のタイトジャンクションが緩み、リーキーガット症候群という「腸漏れ」の状態になります。その言葉の通り腸漏れとは、本来閉じているはずの腸の壁のバリアゲートがコルチゾールの過剰分泌が原因の慢性炎症によって、バリアが空いたままになってしまい、毒素や殺菌、未消化の食物粒子が直接血中に流れ込んでしまい、体中を巡ってしまいます。このリーキーガットを起点として様々な不調が引き起こされてしまうのです。
一方で、慢性炎症によるリーキーガットは、脳でも起こります。脳の血管には、血液脳関門と呼ばれるフィルターがあり、脳機能に不要な有害物質などは全てフィルターでろ過されます。しかし慢性炎症が続くと血液脳関門のタイトジャンクションが緩み、毒素が入り込む通り道ができ、その結果有害物質が脳に侵入し脳に炎症を起こしたり、脳に毒素が溜まってしまうことになります。これをブレイン症候群、別名脳漏れ症候群と呼びます。
副腎疲労と低血糖状態
低血糖に良いイメージを持たれているかも知れませんが、食事によって炭水化物を消化し、ブドウ糖を血中に放出します。このブドウ糖は、脳、神経系、赤血球、筋肉などの働きにおける超重要なエネルギー源になります。血糖値は、どれだけブドウ糖が血中に放り出されているかを示す数値であり、これが高いということはエネルギー源が沢山あるとも言えます。
逆に低血糖であれば、エネルギーが足りていない状態であるため、そもそも病気になるリスクが一番高い症状であるとも言えます。一方で糖質が多い食事をすると、一時的に血糖値が上がりますが、その後急降下して低血糖状態になります。いずれにせよ低血糖になると副腎から血糖値を上げようとコルチゾールが分泌されます。これが続くと「副腎疲労」になります。
副腎疲労と睡眠不足
どれだけ寝ていても睡眠の質が悪ければ睡眠不足は解消されません。睡眠の質を決めるのがメラトニンという睡眠ホルモンです。このメラトニンの原料は、セロトニンという神経伝達物質で日中に太陽の光を浴びることで合成されます。またセロトニンの原料になるトリプトファン(アミノ酸)は、食事から摂取する必要があります。このメラトニンが十分に分泌されなくなるのが、寝る前にブルーライトを浴びたり(スマホ)、明るい部屋で過ごしたりすることです。
一方で、代謝の調節や免疫機能を高め、脂肪代謝や認知機能にも作用する成長ホルモンが分泌されるのは、深い睡眠状態に入ったときです。
いずれにせよ睡眠によって様々なホルモンの恩恵を受けることができるのですが、睡眠不足だと、慢性炎症だけでなく、糖尿病、血圧の上昇、食欲が過剰になったりします。この睡眠不足の原因が、ホルモンの乱れ、腸内環境の乱れ、肝臓デトックス機能の低下が挙げられます。
副腎疲労を引き起こす食べ物
副腎疲労を引き起こす食べ物は、小麦、乳製品、砂糖です。小麦には腸を荒らすグルテンが含まれています。グルテンは小麦やライ麦などに含まれているタンパク質で、パンやピザ、パスタやうどんなどの小麦を使った食べ物に含まれています。このグルテンがリーキーガットの元凶であり、小腸の粘膜を刺激して細胞同士のつながりを緩めてしまいます。またこのグルテンはアレルギー症状や炎症の原因になるとも言われています。
乳製品が腸に良いというのは懐疑的な意見が多くあります。確かにヨーグルトやチーズなどの発酵食品は腸内環境を良くする乳酸菌の補給源として知られています。しかし実際にはそうしたメリット以上のデメリットが乳製品にはあるのではないかと言われています。なぜなら乳製品には、カゼインというタンパク質が含まれており、腸に強い刺激を与えてリーキーガットを促してしまうことがあります。さらにカゼインはアレルギー症状の原因となり、花粉やアトピー性皮膚炎などを引き起こす可能性があるとされています。
砂糖がたっぷりと含まれたスイーツや主食の白米、小麦などの炭水化物は腸に住むカンジダ菌と呼ばれるカビの大好物です。このカンジダ菌が腸で繁殖すると、それを排除するために免疫細胞が集まり炎症を起こします。また糖質は、食後の血糖値の乱高下を引き起こし、血糖値スパイクと呼ばれる状態になり、インスリンの分泌量が増えると記憶力が衰えやすくなり、アルツハイマー型認知症の人の脳に多く見られるアミロイドβというゴミが蓄積する可能性も指摘されています。
副腎を元気にするためのポイント
朝食を食べる
副腎疲労からの観点では、なるべく食べた方が良いのは朝食です。朝がだるいからと言って朝ごはんを抜くと、その後血糖値が安定しにくくなってしまいます。ちょっと小腹が空いた時は、バナナやナッツがおすすめです。こういった食べ物には自律神経を整えてくれたり、 リラックスさせてくれる効果もあります。
一方で、副腎疲労の症状がある場合、カカオ成分が高い低糖質のチョコレートやココアは、あまり食べない方が良いです。またコーヒーに含まれているカフェインやテオブロミンに副腎が刺激されてしまい、疲れた副腎に鞭打って働かせることになってしまいます。
また、副腎を元気にするポイントは、腸内環境を整えることです。副腎が弱っていく大きな原因はストレスですが、腸内環境がストレスと密接に関わっています。
腸内環境を整える
腸の調子が良くないと脳がストレス受け、それが副腎に影響してしまいます。そのために避けた方が良いのが牛乳に含まれるかカゼイン、小麦粉に含まれるグルテンです。副腎疲労になりやすい人の特徴として、グルテンやカゼインに過敏な人が多く、こういった人たちがこれらの成分を摂ることで腸の粘膜が炎症を起こしてしまいます。その結果、そのストレスが脳に伝わり、コルチゾールが分泌され続け、副腎が疲弊してしまいます。
実際に、副腎疲労の患者150人を調査した内容では、疲労の次に多い症状が排便のトラブルや下腹部の痛みがありました。つまり、いくら副腎をいたわってあげても腸内環境も一緒に整えていかないと副腎疲労は中々改善されないことになります。
また、腸内環境を改善しないと栄養の吸収もされにくくなります。これも副腎疲労の患者を調べると半分程度の人に抗酸化酵素が減っていることや、8割程度の人が乳酸菌のバランスが崩れているという結果になっています。つまり消化しきれないで栄養が排出され、消化されたとしても腸内細菌が生んでくれる様々な栄養はほとんど吸収できない状態です。
ここで大切になってくるのは食物繊維で、特に腸が弱っている場合は、不溶性食物繊維を多く取ってしまうとより悪化してしまう可能性もあるため、消化の良いバナナ、リンゴ、キウイ、かぼちゃなどの水溶性食物繊維や味噌、麹、納豆、ぬか漬け、甘酒といった発酵食品、消化を助けてくれる大根、パイナップル、キャベツなどを食べるのがおすすめです。
ミトコンドリアを元気にする
ミトコンドリアは、私たちが活動をしていく上で必要なエネルギーATPを作ってくれています。副腎内にもミトコンドリアは存在していて、副腎がコルチゾールを作り出す時にはATPをエネルギー源としてコルチゾールを作り出しています。つまりミトコンドリアの元気がないとATPも上手く作れず、結果的にコルチゾールも作られにくくなります。
ミトコンドリアを元気にするには、深呼吸をする、バランスの取れた食事をする、なるべく運動をする、リラックスした時間を作ることが大切です。まずミトコンドリアがエネルギーを作り出す過程では酸素が必要です。そのためしっかりと深く呼吸をすることでミトコンドリアが活性化され、ATPが作れられやすくなります。
バランスの取れた食事については、ミトコンドリアはマグネシウム、ビタミンB群、クエン酸、ビタミンC、亜鉛、コエンザイムQ10が大切です。そもそも副腎疲労になってしまうとこれらの栄養が吸収されにくくなり、消費も激しくなってしまうため、特に栄養をしっかり摂ることが大切になってきます。
次に運動をすることで筋肉量が増えれば、それに応じてミトコンドリアも増加していきます。そしてリラックスすることも大切です。実は、ミトコンドリアの活動が一番活発になるのは交感神経と副交感神経のバランスが取れた時です。
ちなみに自律神経を整える一番効果的な呼吸法は1分間20回、6秒息を吐いて4秒吸うという方法で、統計的に一番優位に副交感が亢進し、心拍数が減少する結果になっています。ただ呼吸法は、自分に合ったものを選ぶのが良いという意見もあるため、吸った倍程度の時間をかけて吐くことを意識して、自分に合った呼吸法を見つけましょう。
副腎疲労の改善
当院では、頭の鍼、鍼灸、ラジオ波温熱療法(内蔵矯正)で気の巡り、血の巡りを改善し、自律神経を整えて、副腎機能を改善していきます。
頭へアプローチするのは、副腎の中枢(司令塔)は脳の間脳にあるからです。また現代医学では小脳は、生命の維持に重要な自律神経の中枢と関係するほか、呼吸、心拍、体温調節など、間脳(脳幹)は生命維持やエネルギー源に深くかかわる重要なはたらきを遂行する器官だからです。
そして東洋医学の「腎虚」にもアプローチします。東洋医学では、脳を作っている髄は「腎」から発生すると考えているからです。この「腎虚」とは、内分泌系や免疫機能など全般の機能低下によりおこる症状のことです。「腎」はエネルギーを蔵するところであり、水分や体液の調整、身体の成長、調整の働きがあります。
このように東洋医学的にも、西洋医学的にも副腎の中枢の間脳にアプローチをすることが重要です。以上から、頭の鍼で脳にアプローチ、鍼灸治療では「腎虚」の改善を行い、西洋医学的には、ラジオ波温熱療法(内蔵矯正)を行います。
高級美容液に勝る「腎」を補う黒い食べ物
東洋医学で言う腎(じん)をケアするとアンチエイジングが叶います。一方で「腎(じん)」がパワーダウンするとすごいスピードで老けていきます。
東洋医学の「腎」とは、私たちの知る腎臓とは少し違います。東洋医学では体を肝・心・脾・肺・腎の五蔵に還元して表現しています。この中の「腎」とは「腎気」のことです。「気」というのは臓器などに働いている力で、この「気」がないと各臓器は正常に働かないのです。そのため「腎」がパワーダウンするとは、「腎気」が弱っていることであり、その影響を受けている各臓器の働きが悪くなっている状態のことです。
「腎」がパワーダウンすることで起こる症状
「腎」がパワーダウンすることで起こる症状は腰のだるさ、頭が働かない、疲れやすい、抜け毛、耳鳴り、物忘れ、エイジングなどですが、この状態ではまだ西洋医学的な病気ではなく、いわゆる機能性疾患の状態になります。さらに「腎」がパワーダウンすると腎炎、膀胱炎、子宮疾患、難聴などのいわゆる器質性疾患になってしまいます。
かんじんかなめ(肝腎要)という言葉があるように、身体で大事な部分であり、「「腎」のパワーダウンは他の四蔵にも大きな影響を与えます。また「腎」を回復させるのには、時間がかかります。なので「腎」を弱らせた原因を改善しながら、エイジングしないために腎を補う食べ物でケア(養生)しましょう!
腎臓には黒い食べ物
中医学の中には、万物を5つの要素に分けて、五臓や体質の弱い部分を簡便に見つけるための五行色体表(ごぎょうしきたいひょう)という物があります。そこから読み解くと、腎を弱くする食べ物は、「甘い物」、一方で黒い食べ物は、腎を補う作用があると考えられています。
- 黒きくらげ
- 黒ごま
- 黒豆
少しずつ毎日取り入れられてみてください。それが高級美容液に勝るアンチエイジングになります。当院スタッフは黒ごまを野菜炒めやお味噌汁、なんにでも入れています。できることからサラっと軽やかに始めるのが毎日続けられるヒケツです。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。