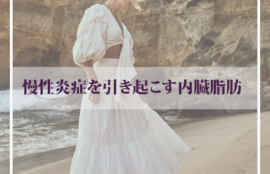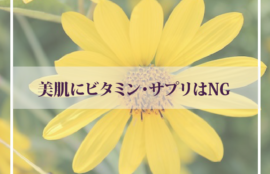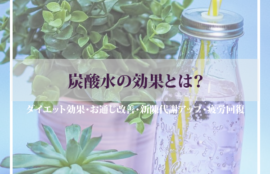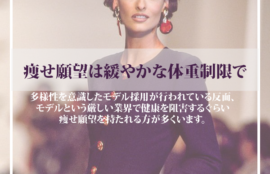世の中には1日1食、〇〇式食事法、マクロビオティック、ベジタリアン、糖質制限などなどたくさんの健康的な食事に関する本が溢れています。しかし万人に有効な答えはなく、私たちには大きな個人差というものが存在しています。
例えば大きいのが遺伝的な要因です。人々の遺伝的背景は多様であり、それぞれの体質や消化機能、代謝率などが大きく異なります。そのため同じ食事法であっても、全ての人に対し効果的であると言い切ることができません。
また私たちは一人一人年齢も違い、年齢によってカロリー摂取量や栄養素の必要量が異なります。例えば一般的に高齢者ほどタンパク質が必要であるということが分かっています。また若い人や成長期の人はより多くの栄養素やカロリーが必要になります。よって同じ食事法が全ての年齢層に対して効果的であるとも限りません。
また、性別の違いも大きく、男性と女性では基礎代謝率や筋肉量、ホルモンバランスが異なります。そのため同じ食事法が男性と女性の両方に対して効果的であるとは言い切れません。さらに今の健康状態やあなたの病歴も食事法の効果に大きく影響します。糖尿病患者や高血圧患者アレルギーを持っている人は、特定の食品や栄養素を制限したり、増やしたりする必要があります。そのため個々の健康状態に応じた食事法が求められます。
一方で、朝ごはんを食べると体に良いかどうかは、未だ専門家の間でも論争が続いています。1日の活動エネルギーのために朝ごはんを食べると良いという意見もあれば、一方で朝ごはんを食べると様々な健康的な弊害が出てくるという意見もあります。こういった対立する意見がある場合、実際に自分自身でやってみてどちらが合っているかを確かめることが非常に大切です。私たちの体の中身もまた一人ひとりで異なり、朝食が体に合うかどうかも人それぞれです。
東洋医学で診る、失敗するダイエット
ダイエットと聞くと多くの人が過酷な運動や厳しい食事制限を思い浮かべるかもしれません。しかし東洋医学の視点からは、このようなアプローチは体と心のバランスを崩し、結果として健康を害する恐れがあります。
なぜ過酷なダイエットは避けるべきか、それは東洋医学では、心と体は密接に関連しており、相互に影響を与え合っているためです。過度に厳しい食事制限や過酷な運動は体にストレスを与え、気の流れを乱し、心のバランスまで悪影響を及ぼすことになります。この不調和が疲労感、やる気の低下などを引き起こし、結果的にダイエットの挫折に至ります。
東洋医学では食事は単に空腹を満たすだけではなく、感情の一環と捉えられます。体質にあったバランスの良い食事を心がけることで体の内側から調和を促し、自然と健康的な体重に導かれます。過度な制限ではなく、栄養バランスを考えた食事が大切です。
また運動が苦手な方でも少しの運動は、体の気の流れを良くし、心身のバランスを整えるのに役立ちます。例えば散歩やヨガなどを取り入れることでストレス解消にもなり、ダイエットにもつながります。
肥満にならない食習慣ダイエット
最初に目指すべき食習慣は、肥満にならない食習慣ダイエットです。数多くのダイエット法が考案されては消えており、カロリー制限や低脂肪食、糖質制限などのダイエット法も科学的な根拠を主張し、一見すると正しそうに見えます。しかし継続できないからダイエットに成功できないと言い、そう言った人がパーソナルトレーナーなどをつけてダイエットを行ったりしています。よく聞くのが、パーソナルトレーナーをつけている期間は痩せることができたのに、パーソナルトレーナーがいなくなったら急にリバウンドしてしまうことがあります。
実はダイエット方法の効果は、研究によってどんなダイエット法を選んでも 差はなく1年間続けることができれば効果は変わらないことが分かっています。つまり基本的には自分が続けやすい方法でダイエットを継続して行うことが何よりも大切です。
例えば、糖質制限しても苦じゃないという方は糖質制限を試し、全体のカロリーを抑えるのが得意だという方であればカロリーを抑えれば良いと思います。他のダイエット法よりも圧倒的に痩せる、圧倒的に体脂肪が燃えるなんていう魔法のようなダイエット法は存在しません。2週間で一気に痩せる、1ヶ月でみるみる痩せるなど、そのようなものは存在せず、1年2年と継続して行っていけるダイエット法こそが正しいダイエット法です。
また、長期間続けることによって健康的に害が出てしまうようなダイエット法は間違いなくよろしくありません。ダイエット法というのは基本的には一生かけてずっと続けていく方法だと考えてください。例えば極端に糖質を減らすといった方法は、結局体調を壊し続けることができなくなってしまいます。糖質以外にも〇〇を極端に制限するダイエットは、基本的には長期間実践するのが難しいものになり、避けた方が無難でしょう。
実際に、1 年間ダイエットを継続することで体の中は大きく変わることが分かっています。食欲を増やすホルモンは減り、食欲を減らすホルモンが増えるといった劇的な変化が起こります。
ダイエットの中には不健康になってしまったり、逆に痩せにくい体を作ってしまうようなダイエットもあります。だからどんなダイエットがダメなのか知っておくと体を健康に保ちながら痩せることができるはずです。
短期間型ダイエット
いつまでに痩せたいなど、短期間での目標を決めてしっかりダイエットに励むのは素晴らしいことですが、短期集中型のダイエットは体に良くないどころか、時には危険なこともあるダイエットです。なぜなら短期集中型のダイエットは、体に必要な栄養が不足することがあるからです。
人が痩せるには、摂取カロリーを消費カロリーより下回る必要があります。つまりたくさん動いて消費カロリーを増やすか、食べる量を減らして摂取カロリーを減らすしか方法がありません。しかし運動をすることで消費できるカロリーはそこまで多くなく、カロリーを大幅に消費しようとすると過酷な運動をすることになります。一方で食事の量を減らす短期集中型のダイエットをしようとすると、食事量を大幅に減らして無理な食事制限をすることになります。すると健康を維持するのに必要な栄養も摂れなくなります。
健康に必要な栄養が摂れないと基礎代謝が落ちるだけでなく、肌や髪のハリ、ツヤなどが悪くなったり、謎の体調不良を起こしたり、女性の場合だと月経不順にも影響します。さらに無理な食事制限はストレスをため込み、摂食障害まで引き起こす可能性があります。そこまでのリスクを犯しているのに短期集中型のダイエットで体重が落ちる理由は、脂肪が減っているわけではなく、水分が抜けるからです。一見、体重は減りますが見た目はそこまで変わりません。しっかり脂肪を落として見た目を変えたいなら、少なくても3ヶ月はかかる長期間のダイエットをお勧めします。
糖質制限ダイエット
よく聞くのは、ご飯やパンを抜いておかずだけ食べたり、麺類を食べるのを止めたりとありとあらゆる炭水化物を抜くダイエット法が糖質制限です。糖質制限ダイエットをすると、初めのうちは体重が減りやすいですが、これも水分が抜けたことによる体重減少です。なぜなら糖質の特徴に水分を保持する働きがあるからです。体から糖質がなくなると一緒に水分も抜けます。さらに筋肉量が落ちて基礎代謝も落ち、つまり痩せにくい体を作ってしまうことになります。
糖質を摂らなくなると筋肉量が減るのは、人間の脳みそは糖質しかエネルギーにすることはできないからです。体に糖質が不足ししていると体は筋肉や脂肪を分解して糖を作ります。つまり糖質制限は、筋肉量が減ることになります。
正しい糖質制限ダイエットであれば、1日60g以下の糖質、緩く糖質制限をしたい人は1日130g以下の糖質を摂取することです。ちなみにご飯150gの糖質の量は約53gです。そして摂取する糖質の質がポイントで、糖質には砂糖や蜂蜜に含まれる単純糖質と、ご飯やパンなどに含まれる複合糖質があります。糖質制限ダイエットをする時は、単純糖質を避けて複合糖質を摂ることが大切です。単純糖質と違い複合糖質は消化に時間がかかるため、血糖値の上昇も緩やかになり、血糖値の上昇が緩やかであれば脂肪も増えにくく、ダイエットに適しています。また複合糖質の中でも玄米や全粒穀物といったビタミンやミネラルが豊富な炭水化物を食べることもお勧めです。
一方で、ケトジェニックダイエットは糖質制限の一種がありますが、一般的な糖質制限よりもさらに厳しくなります。タンパク質、脂質、炭水化物のバランスを3対6対1にして栄養を摂る必要があります。このケトジェニックダイエットは糖質を制限することで意図的に炭水化物ではなく、脂質をエネルギー源とするようにしけて脂肪を燃焼させようという方法です。そのため食事は炭水化物に変わる栄養素の脂質を多く摂る必要があります。この
ケトジェニックダイエットは体質によって合う人と合わない人がおり、体の負担も大きいため挫折する人も少なくありません。さらに体内に残った糖質を抜くために数日、長い人は数週間かけて気分の悪さや眩暈が現れることがあります。そのためケトジェニックダイエットは、長期間のダイエットには向かず、最長でも12週間のみのダイエット方法です。
プロテイン置き換えダイエット
プロテインは筋肉や体の組織を構成するのに必要なタンパク質を豊富に含んでいる反面、タンパク質以外の栄養が不足する傾向があります。その結果、栄養不足を招いて体調不良や リバウンドの原因になってしまう可能性があります。プロテインは飲んだら痩せる魔法の飲み物ではなく、あくまで補助食品です。
栄養バランスの取れた食事をして、その上で食事で足りなかったタンパク質をプロテインで補うと考えて欲しいです。そして置き換えるのなら脂質の高い食べ物と置き換えるのがおすすめです。つまり一食丸ごと置き換えるのではなく、一部を置き換えましょう。
ちなみにプロテインには、牛乳を原料したもの、大豆から作られたものがあり、自分の体に合わないプロテインは便秘になったり、下痢の原因となります。また便秘や下痢、腎臓の機能に問題がある人は、プロテインのようなタンパク質を多く摂ると体調を悪化させることがあるので注意が必要です。体調を崩さないように自分にあったダイエット方法を見つけることも大事です。
ファスティングダイエット
24時間のうち16時間は何も食べず、8 時間の間に何を食べても良いダイエットがあります。このファスティングダイエットが良くないというよりも、ファスティングダイエットの 捉え方を間違っている人が多くいます。ファスティングダイエットは、8時間という食事時間の制限があるから食事の回数が少なくなり、つまり摂取カロリーを少なくすることを目的としたダイエット法です。しかし16時間食事を我慢することで8時間の間に爆食して しまうケースも少なくありません。摂取カロリーを少なくするために16時間断食しているのに、そのカロリーを8時間の間に摂ってしまうと断食の意味がありません。
また、いきなり高カロリーなものや油物を食べてはいけません。断食後の最初の食事は消化に時間がかかるため、胃腸に負担がかかります。さらにファスティングダイエットにNGなことがあり、断食中に甘い飲み物やコーヒー、緑茶を飲んではいけないことです。断食中の甘いものは血糖値を上昇させ、太りやすい体にしてしまいます。またコーヒーや緑茶は、カフェインが多く含まれており、胃腸に負担をかけてしまいます。
カロリー制限で体調不良
カロリー制限をすれば、痩せて美しくなると思われるかも知れません。しかし美容のみならず、健康全般にとってカロリー制限は絶対にやってはいけないことです。カロリー制限による体重減少は、体にとっては不自然なことです。そもそも痩せるために体重を減らさなければならないというところから間違っています。
痩せたいと思っている方の多くが肥満体型に悩まされていることでしょう。そのような肥満体型の原因は、お腹周りや足回りなどについている皮下脂肪や内臓脂肪です。確かにそれらの脂肪を落としてあげることは重要ですが、それ以上に重要なのは、脂肪の代わりに筋肉をつけてあげることです。
カロリー制限は一般的にカロリーの収支をマイナス収支にするために行われ ます。ものすごく単純化すると脂肪はカロリー収支がプラスになれば増えますし、カロリー消費がマイナスになれば燃焼されて減っていきます。カロリー収支というのは運動による燃焼量と食べた分の蓄積量とのバランスで決まります。カロリーをマイナスにするには沢山の運動をするか、あまり食べないかのいずれかをやれば良いというわけです。
特にカロリー消費を促す運動としては有酸素運動が有名です。このためカロリー制限ダイエットにおいては、過剰な有酸素運動と食事制限が推奨されます。ですが過剰な有酸素運動も食事制限もどちらも、美容においてお肌と並んで最も大切な機関である筋肉を分解してしまう恐れがあります。様々な研究によって摂取カロリーが足りていない状態で有酸素運動を1時間以上行うと筋肉が分解され始めるということが分かっています。
強度な有酸素運動の場合は僅か45分だけでも筋肉が分解され始めるという意見も存在します。例えばマラソンランナーは、アスリートとは思えないほど痩せています。オリンピックで金メダルを取るようなランナーはみんなガリガリです。トレーニングの時には大量の炭水化物を摂取しているにも関わらず、ランナーはあのようにガリガリになります。つまり有酸素運動はどれほどカロリーを溜め込んでも、それを消費し尽くしてしまうぐらいカロリー消費の激しい運動です。
どんな有酸素運動を食事制限しながら行ってしまったら、カロリー収支があまりにもマイナスに傾きすぎて脂肪どころか筋力までもが分解されて、私たちの骨格や他の器官にも非常に大きな負担がかかるようになります。もちろん適度な有酸素運動であれば体に良いというのは事実です。筋肉分解や紫外線などのバランスを総合的に考えると、1日20分から30分程度の軽い有酸素運動をすることは、健康にとって非常に有用だと言えます。しかしあくまでしっかりと食事から十分な栄養素をとっていることが前提条件になります。
一方で、カロリー制限には老化防止効果があることが分かっておりますが、ただし過剰なカロリー制限有酸素運動は老化を進めてしまうというのもまた事実です。腹八分目程度の適度なカロリー制限、無理のない範囲の有酸素運動という適切なカロリー管理と運動管理によってより若々しい 肉体を保つということを推奨します。
体重にこだわるダイエットは失敗する
身長から計算される平均体重はすべての人に適用できる普遍的な指標ではありません。骨格の大きさ、筋肉量、体脂肪率などは一人一人全く違います。大きな骨格や多くの筋肉を持つ人は、小さな骨格や筋肉量の少ない人よりも体重が重くなります。女性は、バストやお尻の脂肪の付き方や量も個人個人で全く違います。つまり同じ身長の人でも健康的な体重というのはそれぞれ違うものになります。
また、体重だけを見てもその人の健康状態が良いか悪いか分かりません。例えば体重が正常範囲内であっても不健康な食事や生活習慣で糖尿を発症させているかもしれないし、逆に体重が正常範囲外であっても病気ひとつない健康体なことだってあります。体重は健康状態を正確に反映しているわけではないことを理解することが大事です。
ダイエット≒脂肪!?
ダイエットは脂肪を落とすことと考えている人が多くいます。まず脂肪については、食事から得たエネルギーが体のエネルギー需要を超えた場合、脂肪として保存し、今後に備えます。この蓄えられた脂肪を燃焼するためには、エネルギー消費がエネルギー摂取を超える必要があります。つまり定期的に運動をするか、カロリー摂取量を減らすか、またはその両方を行う必要が出てきます。脂肪がつきやすく、落ちにくいのは体が非常時の備えとして脂肪を最後まで残しておこうとするからです。
一方で脂肪と同じくらい筋肉を嫌う女性もいますが、筋肉はエネルギーを消費する組織で、筋肉は生きる上で必ず必要なものです。この筋肉を維持するためには運動とタンパク質の摂取が必要になります。栄養失調に陥っていたり、運動量が足りない場合、体はエネルギーを節約するために筋肉を分解します。筋肉はエネルギーを消費する組織であるため、筋肉量が減ればエネルギー消費量も減ることになります。つまり体が筋肉を分解し始めるのはエネルギー消費量、摂取量を減らすための反応です。
そして、筋肉量が減ると体力が落ちるだけでなく、基礎代謝率も下がり、エネルギー消費率も低下します。運動をしてもエネルギーがあまり消費されなくなり、体重を落とすのが難しくなります。そもそも筋肉量が減少すると筋力と体力が落ち、日々の活動やエクササイズが困難になり、少し動くだけでぐったり疲れてしまうことになりかねません。そのため、ダイエット中は筋肉量を維持し、可能であれば増やすことを目指すべきなのです。
筋肉を落とす間違ったダイエット
カロリー制限
私たちの体は食事から摂取したカロリーを活動や生命維持のために使用しています。カロリーが不足すると体は脂肪や筋肉をエネルギー源として利用するしかなくなります。これは生存のための本能的なメカニズムで、カロリー摂取が著しく低下すると飢餓モードに入ります。脂肪モードに入ると体はエネルギーを大量に消費する筋肉を分解して、エネルギーに変換します。筋肉は脂肪と比べてエネルギー消費が高いからエネルギーの節約をするために先に筋肉が削られます。
つまり、過度なカロリー制限は体重と一緒に筋肉量も減らしてしまい、筋肉量が減ると基礎代謝も下がり体重が増えやすい体質になるため、リバウンドもしやすくなります。そのため正しいカロリー制限ダイエットの方法は、カロリー制限と筋トレを組み合わせること、もしくは筋トレを先に始めてある程度筋肉量を増やしてからカロリー制限を始めることです。
カロリー制限をするときのポイントは、低糖質高タンパクな食事を心がけることです。糖質の摂りすぎは肥満を招くだけでなく、体を糖化させ体内で酸化ストレスを増加させることになります。またタンパク質は体内でアミノ酸に変わり、筋肉の修復、維持、成長に使用されます。
過度な断食
断食の健康効果の中でもオートファジーという概念が注目を浴びています。オートファジーは細胞が自身の構成要素を分解して再利用するプロセスを指します。オートファジーは、アンチエイジング効果も高く、美容やダイエット目的でプチ断食する女性も増えてきています。
1日16時間程度の断食は確かに美容、健康効果がありますが、間違った方法で16 時間断食をやったり、過度な断食をやってしまうと筋肉を落とすことになります。食事の回数を1日1回2回に減らした場合でも1日に必要なカロリーはしっかりと摂取すること、これが健康的な断食のやり方です。過度な断食は栄養不足を引き起こし、体調不良や免疫力低下、病気のリスクが高まることもあります。またダイエットの面から見ても筋肉量を落とすだけでなく代謝も下がり、痩せにくい体質になってしまいます。また過度な断食でメンタルをやられて、うつ病になってしまったり、拒食症になってしまう可能性もあります。
正しい断食と筋トレを組み合わせることが大事です。断食の時間は最長16時間までにし、1日に必要なカロリーはしっかり摂り、体に栄養が行き届いた状態で筋トレを行うことで 筋肉がつき、筋肉量が増えれば体は引き締まり、体力や代謝も上がり食べても太りにくく痩せやすい体質になります。
筋トレ不足
リバウンドしない健康的なダイエットには筋トレは必須です。いくら食事制限をしたり、お 菓子を我慢しても筋力が不十分だと太りやすい体質のままです。筋トレがダイエットと深く関係する理由は、筋肉は私たちの基礎代謝に大きな影響を与えるからです。
基礎代謝とは、体が日常生活を送る上で必要とするエネルギーのことで、生命活動を維持するために消費されるエネルギーで、体温を維持したり、心臓を動かすために使われます。筋肉は体の中で最もエネルギーを消費する組織であり、より多くの筋肉を持つほど基礎代謝は高まります。筋トレで筋肉を増やせば基礎代謝が高まり、その結果として痩せやすい体質を作ることができます。筋肉を使って運動をすることでエネルギーを消費し、それが体脂肪の減少につながります。
一方でダイエット中に筋トレをおろそかにすると筋肉が減少し、基礎代謝が低下します。基礎代謝が落ちるとカロリーを消費する能力が低下し、リバウンドを引き起こしやすくなります。それだけではなく筋肉量が落ちると体の形状が魅力的なラインから、弱々しく痩せこけたご老人のようなシルエットになってしまうことも珍しくありません。また筋肉量と健康寿命は多くの研究で関連性が示されています。筋肉が体全体の健康、特に血液循環に影響を与えて体を若々しく保ってくれます。
過度な有酸素運動
ダイエットには運動が一番だと意気込み、いきなり激しい有酸素運動を始める人もいます。激しい有酸素運動は長時間のランニング、サイクリング、スイミングなどです。持久系の有酸素運動は大量のエネルギーを消費し、短期間で体重を落とすことが可能ですが、エネルギー消費が激しすぎるあまり筋肉量も減っていくため注意が必要です。
必要としてるエネルギー量が体がストックしているエネルギー源だけで足りるなら問題ありませんが、それだけでは足りない場合、体は筋肉組織を分解しエネルギーを得ます。つまり長時間の無酸素運動を行うと筋肉の分解が進んで筋肉量が減少します。さらに長時間の有酸素運動はストレスホルモンのコルチゾールを大量に分泌させます。コルチゾールが高いレベルで持続すると、その影響で筋肉が分解され、アミノ酸が血流に放出されます。アミノ酸は主に肝臓でグルコースに変換されエネルギー源として、すぐに利用されます。つまりコルチゾールが高いレベルで持続されても、エネルギー供給のために筋肉が分解されるので過度な有酸素運動はダブルパンチで筋肉量が減ってしまします。
ちなみに、筋トレは有酸素運動ではなく無酸素運動です。有酸素運動は強度の弱い運動を長時間行うのに対し、無酸素運動は強度の強い運動を短時間行います。有酸素運動は心肺機能の向上や脂肪の燃焼に役立ちます。
睡眠不足
正しい食事制限と筋トレを継続していたとしても睡眠不足だと筋肉量は順調には増えてくれません。筋肉の回復と成長には良質な睡眠が必要不可欠です。睡眠中は筋肉の微細な損傷が修復され、筋力と耐久力も強化されます。しかし睡眠不足になるとこの修復と回復のプロセスが十分に行われず、筋肉の成長が妨げられてしまいます。また睡眠中は、筋肉の修復と成長を促進する成長ホルモンが最も多く分泌される時間です。質の良い睡眠をたっぷり取ることで筋肉が効率よく修復し、成長します。睡眠不足は筋肉の成長の妨げになるだけで なくストレス反応を引き起こし、コルチゾールを増加させます。コルチゾールは、筋肉の分解を促進し筋肉量の減少を引き起こす可能性があります。
筋トレダイエットを成功させるコツ
筋トレダイエットを成功させるコツは、筋トレに一貫性を持たすことです。筋肉の成長と基礎代謝の向上は、筋トレを一度や二度行っただけで得られるものではありません。効果を最大限に引き出すためには筋トレを一定の頻度で、かつ長期間にわたって継続することが必要です。例えば週2から3回のペースで数ヶ月、数年にわたり筋トレを行うと筋肉量が徐々に増え、基礎代謝も上がります。
そして、筋トレダイエットを成功させるためには、全身のトレーニングを行うことも大事です。筋肉というには全身を均等に鍛えることで体全体のバランスが改善され、スタイルもよく見えます。特定の部位だけを重点的に鍛えると筋力バランスが崩れてしまいます。例えば 胸筋だけを過度に鍛えると背中の筋肉バランスが崩れ、姿勢が悪くなり、肩や背中に負担がかかりやすくなります。全身をバランスよく鍛えることで、日常生活で必要とされる機能的な強さや柔軟性も向上します。
そして、筋トレダイエットを成功させるコツに、強度とボリュームのバランスを考えることが挙げられます。筋肉の成長には、トレーニングの強度とボリュームがとても重要になります。強度を上げてボリュームを落とすか、強度を下げてボリュームを上げるか、どちらも同じ筋トレですが、その効果は全く違うものになります。
強度を上げてボリュームを落とす方法は、筋力と筋肉の大きさの両方を向上させるのに有効的です。この方法は筋肉の神経系の活性化を最大化し、筋肉がより多くの重量を持ち上げられるように訓練できます。筋肉に大きな力学的なストレスを与え、損傷と修復を促すことで筋肉を大きくすることができます。例えば重たいダンベルを持ち上げる動きは、強度の高いトレーニングです。
一方で強度を下げてボリュームを上げるトレーニングは、筋自給力と筋肥大の両方を向上させます。強度が低くても長時間にわたる筋肉の収縮は、筋肉内に乳酸などの代謝物質を蓄積させ、筋肉の成長を刺激します。女性や筋トレ初心者にとっても継続しやすい方法で、筋肉、関節、人体などの損傷を引き起こす可能性も低い方法です。
加齢で筋肉が減る理由
人間の老化のメカニズムは、かなり解明されてきており、最近では筋肉が減る原因が解明されています。具体的には30代以降は、10年ごとに約5%ずつ筋肉が減っていくと言われています。この筋肉が減る原因は主に2つあり、1つ目は不活動による筋萎縮で、これは運動したり動いたりする機会が減ることで筋肉がだんだん縮小してしまうことです。2つ目の原因がサルコペニアで、例え若い頃と同じような活動を続けたとしても筋肉が減っていってしまうという現象です。
このサルコペニアのなぜ起こるのかが九州大学の研究チームによって2023年に解明されました。元々筋肉は再生能力が高い組織であり、筋肉の細胞が傷ついたとしてもすぐに修復される仕組みが備わっています。例えば筋肉が損傷すると筋サテライト細胞が増殖して損傷部に集まって新たな筋肉に置き換わります。これによって筋肉が再生したり、成長したりする仕組みになっています。
この筋サテライト細胞に、増殖のためのスイッチを入れるHGFという物質があり、加齢と共にこの働きが低下します。そしてHGFの形が変化して筋サテライト細胞にくっつきにくくなるため、筋肉の再生のスイッチが入りにくくなります。ちなみにその形が変わる現象のことをニトロ化と呼びます。
さらにHGFには、体を固くする原因である結合組織が増えるのを防ぐ働きもあるため、つまりHGFがニトロ化すると筋肉が減るだけでなく結合組織も増えてしまい、体の柔軟性も失われていくことになります。
このようにサルコペニアの原因がHGFのニトロ化にあることが、今回の研究でついに解明され、ニトロ化したHGFをリセットできればサルコペニアは防げるということが分かります。ただし、どうすれば筋肉量の維持ができるのか、その方法はまだ確立されていません。
栄養と回復の大切さを知る
筋肉を増やすためにはトレーニングだけでなく、適切な栄養摂取と休息も重要になります。特にタンパク質の摂取は、筋トレを行う人にとっては必要不可欠です。トレーニングで損傷 した筋肉の修復と形成にはタンパク質必要で、その必要量は個人差ありますが、一般的には体重1kg あたり1.6から2.2gの摂取が推奨されています。またエネルギー供給源として炭水化物や 良質な脂肪、ビタミンやミネラルも重要になります。筋肉の修復、免疫機能の維持、ホルモンの生成など身体の各種機能にはたくさんの栄養素が必要です。
青魚でダイエット
サバやイワシといった青魚にはオメガ3脂肪酸という非常に体にいい不飽和脂肪酸が含まれています。オメガ3脂肪酸は、血中の悪玉コレステロールを減少させて、ドロドロの血液をサラサラにしてくれる効果があります。このオメガ3脂肪酸の効果を最大化するには、摂取する時間帯が大事であることはご存知でしょうか。
実はオメガ3脂肪酸は朝に取ることで最も血中濃度が高まりやすいことが明らかになっています。従来の栄養学では何をどれくらい食べると良いかという量的、質的な議論が主流でしたが、昨今では時間栄養学と呼ばれる生体リズムに即した多元的な議論が活発に行われています。このような時間栄養学により各栄養素の効能を最大化するために最適な時間が割り出されています。
2013年に行われた研究では、DHAとEPAを朝に摂取した場合、それらを夜摂取した場合に比べて、血液中のオメガ3の濃度が高くなることが分かりました。またDHAとEPAを朝摂取することで、血液や中の中性脂肪の量が、夜摂取するよりも優位に低下することも分かっています。
納豆で痩せる
納豆は、奇跡の食品や万病に効くなど言われ、例えば腸内環境を整え、血糖値の上昇を抑え、がんや脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病を予防し、さらには骨を強くしてくれたり、アレルギーを改善してくれるなどの健康効果があります。
納豆は大豆からつくられるため、当然タンパク質が豊富です。特に大豆に含まれているタンパク質として注目されているのが大豆ペプチドです。タンパク質は、複数のアミノ酸が連なってできる物質です。アミノ酸から構成されたタンパク質が分解される過程で生み出されるタンパク質とアミノ酸の中間の大きさの物質がペプチドです。中でも大豆タンパク質を分解してできる大豆ペプチド は、体の基礎代謝を高めて体脂肪の燃焼を促進する効果があることが分かってきました。
代謝は、生存になくてはならない最低限のエネルギーのことを言います。そして生命を維持するために最低限必要なエネルギーが基礎代謝です。私たちの体脂肪が燃焼されるかどうかは、単純なカロリー計算によって決まります。食事によって得られるカロリーが運動や基礎代謝によって消費されるカロリーを上回れば中性脂肪が蓄積し、下回れば中性脂肪が減ります。つまり中性脂肪を減らしたいのなら食事を減らすか、運動や基礎代謝による消費カロリーを高めるしかありません。
ですが食事を減らすことはあまりお勧めできません。なぜなら食事を減らせば確かに摂取カロリーは低くなるものの同時に摂取できる栄養素も減少してしまうからです。一方で普段から運動習慣がない人が、いきなり運動しようと思っても至難の技です。そこで食事を減らさず、運動もせずに中性脂肪を燃焼する ためには残り1つのパラメーターである基礎代謝を上げるしかありません。
そこで、大豆ペプチドは朝に摂取することで体温を高め、基礎代謝を上げてくれる効果があります。様々な研究により、人は深部体温が 一度上がるだけで基礎代謝が約12%アップすることが分かっています。一般的な成人の基礎代謝量は1400kcal程度であり、その10%は140kcal(おにぎり1個分)にも上ります。
さらに、納豆には納豆にしか含まれない酵素である納豆キナーゼや大豆イソフラボンといった栄養素が大量に含まれています。納豆キナーゼは血管にできた血栓を溶かし、血液の流れを良くする働きがあります。また大豆イソフラボンには女性ホルモンの一つであるエストロゲンに似た作用があり、女性らしい美しさや若々しさを保つのに最重要な栄養素の一つです。
ただし、納豆の食べ過ぎは大豆イソフラボンの摂り過ぎによってホルモンバランスを崩してしまうなど悪影響が出る恐れがあるので、体に良いとはいえ1日1 パック程度にとどめておきたいところです。
また、全ての食べ物に言えることですが、世の中には質の悪い納豆(発酵過程が短かったり、人工的な納豆菌を使っていたり、遺伝子組み換えの豆を使っている)があるため注意が必要です。さらには付属のタレとからしに、添加物が使われていることもあります。
人参で痩せる
人参はダイエットに非常に有益な食材として注目されています。人参がダイエットに有益な理由は、低カロリーで高栄養、食物繊維が豊富、抗酸化作用、水分が多い、血糖値を安定させるなど、様々な特徴をニンジンが兼ね備えているからです。
人参はカロリーが低く、その一方でビタミンA、ビタミンK、ポリフェノールなど体にとって重要な栄養素を豊富に含んでいます。少ないカロリーで満足感を得ながら栄養バランスを整えることができます。つまり少ないカロリーでたくさんの栄養を摂取できるため、ダイエット中でも必要な栄養を確保しながらエネルギー摂取量を抑えることが可能です。また人参は豊富な食物繊維の宝庫です。食物繊維はダイエットに欠かせない成分であり、人参に含まれている豊富な食物繊維は消化を促進し、腸内環境を整えます。これにより体内のデトックスが促され、体重減少に寄与します。さらに食物繊維は、満腹感を感じやすくし、腸の働きを整えて便秘解消にも役に立つため、非常に体重管理に有効に働きます。
また人参の鮮やかな色はβカロテンという成分によるもので、この成分は体内でビタミンAに変化します。ビタミンAは抗酸化作用があり、体の細胞を酸化ストレスから保護する役割を果たします。これは体の新陳代謝をサポートし、ダイエット効果を高める要因となります。つまり抗酸化作用により体の細胞がダメージを受けにくくなり、健康な状態を保ちながらダイエットを進めることができるようになります。
また人参の水分量は非常に高く、ダイエット中に適切な水分補給の助けになります。これにより満腹感を得やすくなり、間食や過剰な摂取を抑える手助けになります。水分は胃を満たして満腹感を与え、さらに代謝をスムーズにする役割があります。さらに人参に含まれるカロテノイドは、血糖値を安定させる効果があります。血糖値の安定はダイエットだけでなく、アンチエイジングにも非常に優秀な働きと言えます。
血糖値が安定することで急な空腹感が減り、ダイエット中の食欲をコントロールしやすくなります。そもそも血糖値の急な上下は空腹感を引き起こしやすく、ついつい食べ過ぎてしまう原因になります。血糖値が安定すると食事の感覚安定し、計画的なダイエットが可能になります。もちろん健康的なダイエットには、ニンジン以外にもバランスの良い食事が必要です。
青さ汁で痩せる
青さとは海藻の一種で青のりの仲間で、青さで作った味噌汁のことを青さ汁と言います。青さ汁は汁物のため、当然消化吸収に良いのですが、水溶性食物繊維という栄養素が含まれています。食物繊維は大きく分けて不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があります。この2種類の食物繊維をバランスよく摂取することが、腸内環境の改善のために重要であることが分かっています。
不溶性食物繊維、私たちが一般に食べるような緑色の野菜に含まれている食物繊維です。不溶性食物繊維は水に溶けることができないため便の傘を増してくれる働きがあります。一方で水溶性食物繊維はその名の通り水に溶けることで 便通を良くしてくれます。水溶性食物繊維は便が通りやすくなるための循環油の働きをしています。
便秘で悩まれている方が、便秘解消のためには不溶性食物繊維ばかり食べるのではなく、水気を持たせてくれる水溶性食物繊維を食べることが大事です。腸の健康のためには不溶性食物繊維によって便の傘を増すこれはもちろん大切ですが、水溶性食物繊維によって流動性を持たせる、このバランス感覚が非常に重要になります。
しかし、水溶性食物繊維をたくさん含んでいる野菜は実はあまり多くありません。一般的に食べられ緑色の野菜のほとんどは不溶性食物繊維を含んでいます。一方で水溶性食物繊維はごぼうをはじめとする根菜や海藻などに含まれています。そして青さも海藻であり、青さは水溶性の食物繊維を豊富に含んでいます。
さらに、青さにはヨウ素やセレンといった一般的な食事からはなかなか摂取しづらい必須栄養素も豊富に含まれています。特にヨウ素は、甲状腺ホルモンの合成に不可欠であり、甲状腺ホルモンは基礎代謝を高めてカロリー消費を促してくれる働きがあります。
心理学を用いたダイエット
20代から50代の女性は、忙しい日常生活の中で無理なく、そして楽しみながら健康的に体重管理をしたいと考える方も多いでしょう。そうした方々にとって心理学を用いたダイエット方法も選択肢となります。
鏡を使った食事法では、鏡に映った食事をしている自分を見ることで自己の行動に対する認識が変化し、食事に対する意識が高まるという心理学的効果があります。自分自身が食べている姿を直接見ることで無意識に食事のペースを送らせたり、食べる量を減らしたりする傾向があるとされています。
鏡に移る自分の姿を観察し、自分がどのように食事を摂り、咀嚼しているかに注意を払い、食べるペースや表情、姿勢に意識を向けます。鏡を見ながら食事をすることで食事中の感情や食欲と自分の関係を深く理解することができます。
例えば食べることへの欲求が本当空腹から来ているのか、それとも他の感情から来ているのかを見極めることができます。すると無意識のうちに食事の量を減らす傾向があり、自分の食べるペースに意識が向くことでゆっくりと食事を楽しむようになります。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。