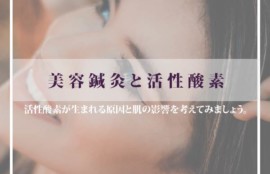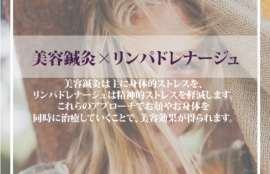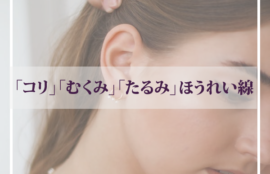顔のたるみの原因には、紫外線の影響や皮膚の弾力低下、筋肉や脂肪の変化などがあります。その中でも実は30代半ばあたりから骨痩せが始まり、それが一気に40代50 代で加速することによって顔がたるんで大きい顔、四角い顔、老け顔になると言われています。
たるみの原因「骨痩せ」
骨は、骨を作る骨芽細胞による骨形成と、骨を壊す細胞による骨吸収がバランスよく行われることによって、毎日少しずつ作り変えられています。つまり骨も新陳代謝しています。しかし加齢とともに、このバランスが崩れて骨形成よりも骨吸収が優位になってしまうと骨がスカスカになってしまいます。例えば骨粗鬆症はそれが悪化した状態で、特に女性は閉経とともに女性ホルモンが減少すると骨粗鬆症になりやすくなります。
このような骨痩せは顔の骨でも同じように起こり、顔の骨が痩せるとその上の皮膚は当然たるみ、そして骨の縁も痩せることによって、骨の穴の部分は全体に広がってしまいます。例えば眼球が入っているくぼみの場所を眼窩と言いますが、眼窩が広がることで目元はくぼみ、鼻の骨のくぼみも広がるため鼻が平らになって低くなっていきます。
さらに、頬の部分の骨も痩せるためほうれい線やゴルゴラインが深くなり、顎の骨が後退して小さくなるから二重顎にもなりやすくなります。一方で額やこめかみの骨も痩せることによって、この部分もくぼんで皮膚もたるみ顔が老け込んで見えるようになります。
このように顔の骨痩せは、顔のたるみやシワを深くし、老け顔の大きな原因になります。基本的には、ほとんどの人が骨は痩せていきます。
骨密度が低下するスピード
アメリカで行われた研究データによると、年代別に腰椎と顔面骨の骨密度を比較した結果、腰椎よりも顔面骨の方が加齢による骨密度の減少する割合が大きいということが分かっています。さらに腰椎の骨量減少は61歳以上の高齢者で認められる一方、顔面骨の骨密度は41歳から60歳の中年層で既に減少し始めることも分かっています。つまり顔の骨痩せは40代から始まり、顔がたるみ出すことになります。
因みに性別によって骨の痩せ方に違いがあり、眼窩が広がっていく度合いを年齢別、性別に調べた結果、男性は年齢に伴って少しずつ目の穴が広がっていくのに対し、女性は中年層の年齢での変化が男性より大きくなることが分かっています。
また、顔全体を細かく分析し、変化を調べた研究では、女性は男性に比べて50歳から60歳の間に最大3倍のスピードで顔が変わることも分かっています。特に下顎の骨の減少が大きいことが分かっており、これがフェイスラインのもたつきに繋がっていくことになります。つまり女性の方が男性より骨痩せは起こりやすく、顔はたるみやすくなる傾向があります。
女性は40,50代で骨が痩せていくのは、特に閉経後は骨密度が低下しやすくなるためです。実際の研究結果でも、およそ40歳あたりまでは20歳をピークとする骨量もなんとか保てていますが、そこから減少するスピードは人によって対策を取るかどうかによって大きな差が生まれます。
一般的には、40代の頭蓋骨は650g程度に対し、70 代になれば280g程度と重さも半分以下になると言われています。骨量が減ると言うことは、頭蓋骨が萎縮している状態になり、風船と同じように顔がたるむことに繋がります。
骨活でお顔のたるみの対策
かかと落とし運動
まず何より骨を作るホルモンを活性化させることが大事です。骨を作るホルモンは確かに加齢と共に減少しますが、骨を作る細胞は軽い衝撃や負荷を意図的にかけることで、その刺激や負荷に耐えようとしてオステオカルシンという骨ホルモンを多く分泌することが分かっています。そのため顔のたるみを予防するために、骨に効率的に衝撃を与える「かかと落とし運動」がおすすめです。両足を肩幅ほどまで開き、つま先立ちで3秒静止し、その後、勢いよくかかとを床に落とす、これがたるみ改善に効果的です。
この運動は体全体の骨に効率よく刺激を加えるということが明らかになっています。かかと落としをすることで脳から骨を作れと指令が出て、骨細胞からオステオカルシンが多く分泌されます。目安としては、かかとの上下を1日50回、連続ではなく、休憩を挟みながらやってみましょう。
骨を作るために必要な栄養素
骨の主成分のカルシウムは99%が歯と骨に、残りの1%が血液に含まれています。血液中のカルシウムが不足すると骨からのカルシウムが使われ、骨が弱くなります。そのため不足分のカルシウムは食べ物で補う必要があります。
顔のたるみの原因になる骨痩せを防ぐためには、骨を作るために必要な栄養素を摂ることです。骨に必要な栄養素はカルシウムで小魚、乳製品、大豆製品に豊富に含まれています。野菜では小松菜、チンゲン菜に多く含まれています。18歳以上の女性は1日550mg 、30歳以上の男性は600mg最低でも必要と言われており、骨粗鬆症予防のためには1日700から800mgは必要と推奨されています。
ただし、カルシウムは体に吸収され難い栄養素である上、カルシウムだけで骨は作られません。カルシウムだけでは吸収効率が悪いため、一緒にビタミンDを取ることで吸収率が上がります。ビタミンDは魚類、特にシラスにはビタミンD、カルシウム、それにタンパク質も含まれており、たるみ改善におすすめの食材です。カルシウムにはビタミンDは必須であり、ビタミンDはカルシウムの合成を助ける栄養素で、体内のカルシウムとリンが沈着する骨の石灰化に働きかけます。
また、ビタミンDは腸管からのカルシウムの吸収を促して、血液中のカルシウムを運んでくれる他にも、骨を作る骨芽細胞の働きを促進して骨の形成を助け、筋力を高めてくれます。そのため、カルシウムはできるだけビタミンDと一緒に取る必要があります。ビタミンDを多く含む食べ物は、鮭、秋刀魚、きのこ類などがあります。
太陽を浴びること
しかし、一番効率よくビタミンDを体内に吸収できる方法は日光浴です。紫外線の肌への影響を考えると紫外線の当たりすぎは逆効果になりますが、ビタミンDを摂取するという点で考えると、夏なら15分、冬なら30分程度、手のひらや足だけでも、程よく太陽を浴びることが大事です。
特に女性の体は閉経後、女性ホルモンの減少によってカルシウムが吸収されにくくなったり、腎臓機能の老化とビタミンD合成の不具合で、より体内のカルシウムが不足していきやすくなり、そのため体は全身のカルシウム量を調整するために既存の骨を溶かしてカルシウムを獲得するため、顔の骨も影響を受けるためたるみの原因になります。
また、ビタミンKもカルシウムを骨に取り込む際に必要なオステカルシンというタンパク質を活性化させる働きがあるため必須です。また骨の形成を促したり、カルシウムが尿中に流れるのを抑え、骨の破壊を防いでくれます。ビタミンKは微生物によって合成されるため、特に納豆などの発酵食品に多く含まれています。その他には海藻類や緑黄色野菜に豊富です。
ガムを噛む
実は、全身の骨の中で顎が真っ先に痩せて縮みます。顎の骨は他の骨と比べても骨代謝が活発で縮みやすくなります。もちろん顔のたるみの大きな原因になり、顎の骨の形成を助ける対策が必要です。
顎の骨の形成に働きかけ、刺激を与えるのに有効なのがガムを噛むことです。ガムを噛むことで咀嚼筋に働きかけ、顎の骨の形成を助けてくれます。1日1回10分間程度噛むだけでも効果的です。ただし嚙み過ぎは筋肥大に繋がるので注意しましょう。
一方で最近の研究では、アミノ酸の一種であるホモシステインが骨の劣化に関わっていることが分かっています。ホモシステインは有害な活性酸素を発生して、ビタミンB6が不足している人に悪影響を与えます。実際、骨粗鬆症の人はビタミンB 6が少なかったり、ホモシステインが多く見られます。ビタミンB6 は、マグロの赤身の刺身、バナナ、鶏胸肉に多く含まれています。
顔のサイズが大きくなる「筋肥大」
顔の実際のサイズが大きくなる原因に、30歳前後から起こる筋肉の肥大があります。これは食いしばり癖などによって噛む時に使う咬筋や側頭筋が肥大したり、顎に力を入れる癖などで下顎のオトガイ筋が発達し過ぎて、顔が大きくなることがあります。
さらに年齢を重ねると骨やせと同時に脂肪が萎縮し、その量が減る上に脂肪を支える靭帯やコラーゲンが伸び、ハリがなく緩んだ皮膚、特に頬、こめかみ、額、口周りに顕著に現れます。そして土台である骨が痩せて脂肪も減るため、皮膚が雪崩を起こし、顔が大きく四角くなっていきます。
たるみの原因「枯渇肌」
肌のたるみの根本原因である枯渇肌は、保湿機能が低下し、肌が慢性的に乾燥している状態を指します。これは皮脂や天然保湿因子の生産が減少し、肌の水分保持能力が低下した時に起こる現象です。
たるみを改善するためには、外側からばかりではなく体の内側から保湿することも大事になります。たるみの原因には、天然保湿因子の減少が挙げられます。天然保湿因子は、肌の角質層に存在する自然の保湿成分のことで、この成分が自然に湿気を保持し、乾燥から保護する役割を果たしています。そのため天然保湿因子の量が減少すると肌は乾燥しやすくなり、その結果たるんできてしまいます。
この天然保湿因子が減少する原因はいくつかありますが、特に環境要因によるものが挙げられます。例えば乾燥した環境や寒冷な天候、紫外線などの外部要因が、肌にストレスを与え、天然保湿因子を減少させます。
一方で、洗顔料でよく顔を洗う人も注意が必要です。天然の油分を取りすぎると肌のバリア機能が低下し、天然保湿因子が減少してしまいます。また肌の弾力を保つコラーゲンやエラスチンの減少の影響もあります。コラーゲンとエラスチンは 肌の構造を支え、強度を維持する重要なタンパク質です。これらのタンパク質が減少すると、肌はその弾力を失い、たるみが生じてしまいます。
肌は適切な水分を保持できていないと表皮の細胞間脂質が十分に機能しなくなり、細胞間脂質が乾燥すると細胞間のスペースが広がり表皮が緩むため、肌がたるんでいきます。また保湿力の低下は、肌表面のバリア機能の弱化につながってしまいます。バリア機能が低下すると、肌はどうしても外部の刺激に対して脆弱になり、その結果炎症や肌のダメージが悪化しやすくなり、肌の老化が加速し、たるみが進行してしまいます。
たるみの最新研究
これまで肌において、たるみと深く関わる部分は真皮だと言われてきました。確かに真皮にはコラーゲンやヒアルロン酸など肌のボリュームを維持したり、エラスチンなど弾力を形作る組織が分断に存在し、それらの加齢による変化をいかに食い止めるかがエイジングケアのメインアプローチでした。
しかし近年、真皮よりもさらに奥の皮下組織に肌のハリや弾力に大きく影響する皮膚維持体(RC)という構造が存在することが明らかになってきました。頬や顎回りの皮下組織は一般的に真皮よりも厚く、この厚みのある組織の中に基礎となる繊維を張り巡らせて肌のハリを土台から支えています。
例えば、肌をグリグリ強く押したりするとこのRCが壊れてしまう可能性が大きく、実はセルライトをグリグリして除去した裏には肌がたるむことも分かっています。
リンの摂り過ぎで骨が痩せる
近年、リンと老化の関係が注目されています。リンはカルシウムと共に骨を構成しているミネラルです。体内のリンの約80%はカルシウムと結合し、水に溶けないリン酸カルシウムを作り、骨の主成分になっています。またリンはDNAや細胞膜の主成分でもあるため、体を維持していく上で絶対に欠かすことのできない重要な物質です。しかしいくら重要であると言ってもたくさん摂れば良いと言うわけではありません。リンは多くの食材に自然と含まれており、普通に食事を送っていれば、まず不足することはありません。逆にリンの過剰摂取に注意しなければいけません。
リンを過剰摂取してしまうと、老化を始めとした様々な問題が引き起こされてしまうということが新しい研究で明らかになっています。特にリンが多いとされているのが食品添加物です。日頃から加工食品やファストフード、スナック菓子などを多く食べている人は、知らず知らずのうちにたくさんのリンを摂取していることになります。そして日々リンを摂りすぎていると腎臓や血管や細胞がダメージを受けて、老化するスピードが加速します。さらにリンによる体のダメージは、慢性腎臓病、動脈硬化、心臓病、脳血管疾患などの寿命を縮める病気を引き起こしていまします。
そして近年、老化加速物質と言われるようになり、リンによって寿命すら左右されることが分かってきています。血中倫濃度が正常範囲内の人およそ4000人を対象とした疫学調査研究では、血中リン濃度が高い人は低い人に比べて7割も死亡率が高くなる結果も報告されています。このようにリンの過剰摂取によって老化が加速し、寿命が縮まってしまうのです。
また、リンは、生活の要となる骨をも老化させてしまいます。リンの過剰摂取は、カルシウムの吸収を妨げ、その結果、骨密度が低下したり、骨粗鬆症のリスクが増加して、例えば足の骨が弱くなって足の老化が加速します。
一方で、リンとカルシウムはどちらも骨をしっかりと強く保つために必要な栄養素であり、体内のリンとカルシウムの量は、常に一定の割合に保たれるようになっています。常に一定の割合に保たれているということは、加工食品などから体内に大量のリンを摂り込んでしまうとリンとカルシウムのバランスが崩れます。するおtバランスを保つために不足して いるカリウムを自分の骨から取り出してバランスを保とうとします。その結果、骨がもろく 弱くなってしまい、骨密度が低下したり、骨粗鬆症などのリスクが高まってしまうとされています。さらにリンは私たちを老化させるだけでなく、体を疲れやすくしてしまうことも新しい研究で指摘されています。どうも疲れやすいという人は、リンの過剰摂取を疑ってみて下さい。
一般的な食材に含まれているリンは有機リンと言われ、こちらはそこまで気にする必要はありません。食品添加物に含まれている無機リンは90%以上が体に吸収されてしまうため、 リンを減らすためには、無機リンをいかに減らせるかが大事です。
良質な睡眠
私たちは睡眠中に体全体の細胞が修復されおり、特に皮膚細胞は睡眠時間中に最も活動的になります。皮膚細胞の新陳代謝が活発になるとダメージを受けた細胞が修復され、新しい 細胞が生成されます。睡眠中、体はコラーゲンの生成も活発的になり、コラーゲンの生成が活発化し、肌質が良くなるとシワやたるみも改善されていきます。
また良質な睡眠は全身の血行を促進し、血行が良くなると酸素や栄養素が皮膚細胞に効率 的に供給され、肌の健康や輝きが向上します。健康的な血流は肌の再生能力を高め、シワの 形成を減少させる効果が期待できます。さらに良質な睡眠をとることでストレスホルモンであるコルチゾールの分泌量が抑制されます。長期間にわたる高いコルチゾールレベルはコラーゲンの分解を促進し、老化を早める可能性があるストレスを軽減します。
さらに睡眠中、体は水分バランスを調整し、余分な水分を排出します。これにより浮腫や乾燥を防ぎ、肌を健康な状態に保つことができます。良質な睡眠をとって体内の水分バランスを整えることはシワの改善にも効果的が期待できます。
上質な睡眠を取るためのコツとしては、寝る2、3時間前は何も食べないことです。食べた ものを消化吸収するプロセスは、消化器官を活発化させエネルギーを消費し、消化中に寝ようとしても体がリラックス状態になれません
睡眠中に消化活動が活発化し、深い睡眠に移行するのが遅くなったり、中断されることもあります。特に重たい食事や高脂肪の食事は、胃や腸での消化に時間がかかります。胸焼けや胃の不快感を引き起こし、快適な睡眠を妨げる可能性があります。さらに胃酸の過剰分泌や 胃酸逆流のリスクもあります。
たるみを悪化させるケア
強い摩擦
マッサージやスクラブなどは肌表面をきれいにし新陳代謝を促進するという意見もありますが、これらの手法は肌にダメージを与え、たるみの原因になることがあります。特に顔の皮膚は薄く敏感なため、強い摩擦によるマッサージやスクラブを定期的に使用すると、肌のバリア機能が破壊される可能性があります。皮膚のバリアが低下すると肌は水分を保持する能力を失い、乾燥しやすくなります。そうなると皮膚の細胞が正常に機能せず、新陳代謝が減少し、結果として肌のたるみを引き起こします。
また、スクラブに関しては、中に含まれる粒子が大きすぎると肌に傷を負わせる可能性があります。特に顔の皮膚は他の部位に比べて薄いため、より大きなダメージを受けやすい部位です。頻繁にスクラブを使用すると皮膚の自然な油分も取り除きすぎてしまい、肌が乾燥することでたるみを引き起こす原因になります。
正しいケアとしては、洗顔やマッサージをする時は強く擦らずに優しくすることを基本に、そしてスクラブは週に一度程度の使用にとどめ、微細な粒子を包むものを選ぶことが大事です。
引っ張る、伸ばす
コロコロローラーで毎日マッサージしている方は、要注意の美容習慣です。皮膚を筋膜や骨に固定しているリガメントという靭帯は、コラーゲン繊維でできていて、引っ張る力に影響を受けやすく、コロコロローラーで引っ張ると伸びたり切れたりして顔がたるみやすくなります。
また、かっさなどの専用プレートで肌を擦り、ゴリゴリ刺激すると靭帯が伸びて たるみを招くことはもちろん、肌に炎症が起き、その炎症物質から細胞を守るためにメラニンを作って細胞に分配し始めます。これが繰り返されることでメラニンが蓄積して色素沈着を招き、くすみやシミの原因になります。
フェイスリフトエクササイズ
顔ヨガで表情筋を鍛えるのもNGです。思いっきり目を見開いたり口を大きく動かしたりする顔ヨガは、表情筋を鍛えてたるみ改善に良いと言われていますが、むしろたるみの原因になる場合があるので要注意です。特に口角を下げる動きは、首筋の左右にある広頚筋を発達させるため、これはフェイスラインを引き下げる筋肉であるため、鍛えると顔がたるみます。
表情筋をある程度鍛えることは確かに大事なことですが、実際にはこれが逆効果となることがあります。表情筋が過度に発達すると、皮膚に対する圧力が増え、これが新たなシワの原因になることもあります。つまり一部の問題が改善されたとしても、それが原因でまた新たな問題が発生する可能性があります。
また、フェイスリフトエクササイズは、肌のたるみ解消法とされていますが、過度に行うとたるみの原因になります。フェイスリフトエクササイズは、顔の筋肉を鍛えることで肌を引き締める効果があると言われていますが、実際には肌に余計なストレスを与える可能性が高くなっています。顔の皮膚は非常に薄く、エクササイズによる繰り返しの伸び縮みにより、皮膚の伸縮性を維持するのに必要なエラスチンが破壊され、肌にハリがなくなりたるみを引き起こします。
顔の皮膚に負担をかけるエクササイズを続けると皮膚が伸ばされ、肌に微細な損傷を引き起こします。そのため既にたるみやエイジングサインが見られる場合には、さらなる肌のトラブルを引き起こす可能性があります。
また、フェイスリフトエクササイズは表情の非対称性を悪化させるという問題もあります。人の顔は左右対称ではないことが多く、数ミリ単位でずれているのが当たり前です。この状態で顔の筋力をトレーニングしてしまうと、さらに顔の非対称性を強調することになります。その結果、歪みが余計に目立つようになります。もともとの自然なバランスを崩すことで不自然なたるみを引き起こすこともあります。
一方で、食生活では特に気を付けたいのが脂抜きダイエットです。肌の潤いのもとであるセラミドなどの細胞間脂質はコレステロールなどの脂質を材料にして作られています。そのため脂を抜いてしまうと細胞間脂質が減ってバリア機能が低下し、肌が乾燥してシワシワになったり、たるみの原因になってしまいます。
間違った日焼け対策
紫外線は皮膚のコラーゲンを破壊し、たるみの要因となることは広く認知されています。コラーゲンは皮膚の主要な構成成分で、皮膚の弾力性とハリを維持する役割を果たしています。紫外線によるダメージは、このコラーゲンの構造を破壊し、結果的に皮膚のたるみを引き起こします。
実は、日焼け止めの使い方が間違っていた場合、肌に悪影響を及ぼす可能性があります。日焼け止めは塗りすぎると皮膚を刺激し、アレルギーや皮膚の乾燥を引き起こす可能性があります。特に化学物質を含む日焼け止めは、皮膚を通じて体内に吸収されます。特に肌が敏感な人やアレルギー反応を起こす人にとって大問題です。
日焼け止めには物理的な日焼け止めと化学的な日焼け止めの2つのタイプがあります。物理的な日焼け止めは酸化亜鉛や酸化チタンといったミネラル成分を含み、これらは紫外線を反射する一方、化学的な日焼け止めには、オクトクリレン、アボベンゾン、オクシベンゾンなどの化学成分を含み、これらは皮膚に浸透して紫外線を吸収し対外に放出することでUVカット効果を発揮します。このオクシベンゾンは効果的な紫外線防御成分である一方、皮膚から体内に吸収されやすい性質を持ち、ホルモンバランスを崩す可能性がある物質と言われています。
一方で、UVAとUVBの両方から皮膚を保護することも顔のたるみを予防する上で重要です。UVAは皮膚の深部に浸透し、皮膚の老化を早める可能性があり、UVBは日焼けや皮膚がんを引き起こします。そのため広範囲の保護またはブロードスペクトラムと表示されているものを選びましょう。
SPF値は日焼け止めがUVBからどれだけ保護してくれるかを示しており、SPFは30以上のものを選びましょう。またSPF値が高いからといって完全に日焼けを防止できるわけではありません。SPF50の日焼け止めでも適切に塗布できていなければ普通に日焼けします。
日焼け止めの効果は使用量に大きく左右され、適切な使用量は体の全身で約30ml、顔と首に関しては約1.5〜2mlを目安にしましょう。これらは一般的な目安であり、日焼け止めは水分や汗、摩擦などで時間とともに落ちます。一般的には2時間後、または泳いだり、大量に汗をかいた後はすぐに塗り直すことが大事です。
たるみを改善する習慣
うつ伏せや横向きで寝ない
横向きで寝ると下になっている片側の頬に強い圧力がかかり、皮膚にシワができやすくなるため、たるみの原因になったり、頬が偏った方向に引っ張られ続けることでたるみが起こりやすくなります。良くあるケースとして顔の左右どちらか半分だけが老けた印象で悩んでいる人や左右非対象の顔に悩んでいる人が多くいます。
実際、研究データによるとうつ伏せで寝ると頬は5mm、目元や口元は3mm以上動くと言われています。一方で枕が高すぎると首にシワが寄ったり、顎が前に突き出して筋肉が緩み、二重顎になってしまう恐れがあります。理想的な枕の高さは、まっすぐ立ってる時の姿勢をそのまま横にしたような状態になる高さの枕を使うことです。
むくみを放置しない
むくみがなぜたるみの原因になるかは、膨らんだ風船おイメージすると分かりやすいです。膨らんだ風船は時間が経つとだんだんしぼみますが、皮膚でもむくみで張った状態が続くとやがて皮膚が伸び切ってしまうことで下へと垂れ下がり、目元やフェイスラインのたるみに変わってしまいます。
むくみが慢性的にならないためには、やっぱり塩分は控えめにすることがまずは大事です。塩分を取りすぎると脳が塩分濃度を下げようとして体内に余分な水分を溜め込んでしまいます。ちなみに、成人女性なら1日あたりの適正な塩分摂取量は88gを目安になります。
また、デスクワークなどずっと同じ姿勢でいることはむくみの原因になります。1時間に1度立ち上がって歩いたり、肩を回したりストレッチして代謝を下げないように定期的に体を動かすようにすると良いでしょう。
そして、無表情もたるみの原因になります。顔の表情を作る表情筋は30種類以上もあり、他の筋肉のように骨と骨をつぐものではなく、表情筋は骨と皮膚をついでいます。実は、私たちは普段の生活の中でその筋肉のうち実は30%しか使ってないと言われています。表情筋が衰えると皮膚を支えられなくなってどんどん垂れ下がってしまいます。最も簡単な表情筋トレーニングは、広角を上げて笑顔を作ることだけです。
骨を丈夫にする
骨を丈夫にする「骨活」がたるみの改善になります。お肌にとって骨が大事なのは、例えばテントで置き換えると分かりやすく理解できます。皮膚や肌の筋肉、脂肪、組織がテントの膜だとすると骨はそれを支えるまさにフレーム部分です。つまり骨組が下ってくると、当然テントは崩れ、顔の肌も一緒で骨がしっかりしてないと皮膚や脂肪や筋肉が支えきれずに一気にたるんでしまいます。
特に骨は体の骨より実は顔の骨の方が痩せて脆くなりやすいことも分かっています。骨が減って萎縮することで眼窩や梨状口が広がってしまうと顔の輪郭が崩れることでたるみが生じ、それに目がくぼんだり、団子鼻になったりします。歯の骨である歯槽骨も痩せやすくて、これが痩せて萎縮してしまうと人中つまり鼻の下が長くなります。骨は顔立ちの印象や老化に直結し、たるみが骨に大きく関係しています。特に頭蓋骨は海綿骨という他の部分の骨より薄い骨でできており、体のどの部分の骨よりも減りやすいと言われています。
特に40歳以降になると骨の再生サイクルが減少します。女性は4、50代になると更年期に入り、女性ホルモンが急激に減少し、骨を壊す破骨細胞の方が活性するため、骨を作り直す細胞の働きが追いつかなくなってしまいます。こうして骨密度が低下していくことで目のくぼみや鼻の下の部分が広くなったり、団子鼻になったり、色々なたるみの原因になってしまいます。
美容鍼でたるみを予防
美容鍼でたるみを改善できるのは、刺鍼によって肌の真皮層や筋肉にダイレクトに刺激を与えていくことができるからです。つまり肌細胞や血管、神経にダイレクトに働きかけることができます。その結果、肌本来がもつ自然治癒力を活性化させ、加齢や生活習慣、ストレスなどで乱れたターンオーバーを正常化することができます。
特に、たるみを予防するのに欠かせない成分が、コラーゲンやセラミドです。刺鍼によって肌の細胞組織を破壊し、細胞修復を働きかることで、コラーゲンやセラミドなどの生成を促すことができます。その結果、肌にハリやツヤが生まれやすくなります。
一方で、美容鍼は顔の筋肉を刺激し、血流を促す効果があります。血行が良くなると、凝り固まった筋肉がほぐれ、同時に本来の位置に戻るため、結果的にリフトアップすることができます。またツボを同時に刺激することでも代謝は活発になるため、老廃物が排出されることでむくみが解消し、本来のフェイスラインの位置に戻ることが期待できます。
さらに、お顔だけでなくお体の調子を整えることが、たるみやほうれい線の予防に必要です。例えば、胃腸が弱り、必要な栄養素がお肌に行き渡らなくなるとたるみやほうれい線の原因になります。そのような場合は体にある胃腸の働きを整えるツボにアプローチすることで、胃腸の栄養の吸収力を高めることができ、その結果、肌まで栄養が行き渡り、シワ、たるみ、くすみや(STK)などの予防に繋がります。
また、鍼に電気を流すことで強制的に表情筋を鍛えたり、凝り固まった筋肉をゆるめて柔らかくしたりすることができます。より美容鍼の効果を高めるだけでなく、より早い効果を期待することができます。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。