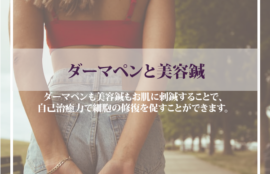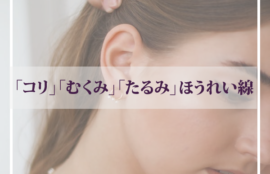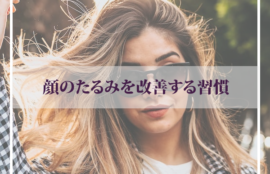体内の炎症や様々なアレルギーに悩まされている方が多くいらっしゃいます。腸内環境を良くし、腸内細菌を労わることで老けずに健康的に長生きするために重要であるというのは一般常識になりつつあります。
腸活という言葉があるように、腸の重要性を強調する研究や論文が多くあり、腸の健康なしでは、健康を語れなくなりつつあります。
こんにち、ヒト・マイクロバイオームの研究は医学で最も注目を集める分野で、生理学の理解に真の革命を起こしつつあり、健康増進と疾病管理に新風を吹き込むだろうと大きな期待が寄せられている。腸内に棲む細菌や真菌は、人体と環境間で起きる相互作用を決め、アレルギーや自己免疫疾患の発症や予防にも関わっている。肥満や糖尿病を引き起こすのも防ぐのも、体内の炎症を抑えるのも悪化させるのもこれらの細菌だ。
腸内細菌が健康と幸福に欠かせないという証拠は豊富にあり、このことは生活習慣や医療、食事にかかわる選択するときには、腸内細菌に与える影響を慎重に考慮する必要があることを意味する
「腸科学」スタンフォード大学微生物学者より
最近になり、「腸」は全身に大きな影響を与えていることがわかってきました。腸は全身の臓器とつながっており、お互いに影響を及ぼし合っているのです。つまり、腸について理解し、腸を整えることは、全身の健康につながり、健やかに長生きするために必要不可欠な課題といえます。
腸を整えることで、今までよくわからなかった体の不調が、もつれた糸がほどけるようによくなります。また、腸の不調や病気の症状がない人でも、腸をリセットすることで、認知症やパーキンソン病などの脳の病気、動脈硬化などの血管の病気、肝臓ガンや大腸ガンなどを未然に防ぐ「未病」の対策として役立てることができます
「新しい腸の教科書」江田証
これらのように腸の重要性が認識される一方で、日本人の腸内細菌の数は戦前に比べて1/3程度に減少しています。その理由のひとつが野菜などから摂れる食物繊維の摂取量が減っていることが挙げられます。
食物繊維の摂取量が減ることで、腸内細菌が減少し、体の免疫力の低下や免疫のバランスが崩れてしまい、アレルギー疾患になっているとの見方もあります。
肌は内臓を映す鏡
「肌は内臓を映す鏡」と言われるように、肌は臓器のひとつであり、その体の内側の臓器と密接に関係しています。例えば吹き出物や肌荒れは、内臓からの信号を肌が伝えてくれているとも言えます。逆に肌が美しくあれば、内臓も健康的な状態であるとも言えます。
このように、肌を美しくするためには体の内側を整えることが必要になります。肌の表面をいくらケアしても、効果が出ないのは「腸」に原因があるかも知れません。腸は体のあらゆる臓器を助ける大黒柱のような存在です。腸は体に入る必要な栄養を吸収し、有害物質や老廃物などを排出し、この2つを判断する重要な役割があります。この役割によって質の良い血液を作り出し、体中に栄養や酸素を届けます。そうすれば肌のターンオーバーも正常になり、肌のくすみが解消され、透明感がアップします。また免疫機能の改善されるため、肌トラブルも良い方向へ向かいます。
特に、表面的な乾燥を一時的に保湿剤などでカバーするのではなく、根本的に肌の保湿機能を高めること、そのために腸内環境を整えることで、肌細胞まで栄養や水分を十分に届かせることが大切です。
この腸の働きは年齢を重ねるごとに低下します。例えば乳幼児の腸にはビフィズス菌が95%以上いますが、何もしなければ60代になると5%前後まで低下します。さらに腸の老化は20代から始まると言われています。年齢とともに腸内環境が乱れやすくなるのは仕方がないことですが、それに拍車をかけるような暴飲暴食は控えて、生活習慣を見直しましょう。
肌と腸内環境
腸内環境と肌の関係が明らかになるにつれて、腸活にはプレバイオティクスとプロバイオティクスが大切だということはご存知かもしれません。
プレバイオティクスは、腸内に住んでいる腸内細菌にエサを与えること、プロバイオティクスは、乳酸菌など様々な菌を腸内に入れていることです。どちらも大切なことですが、腸内環境を整える上でも発酵性の食物繊維(ルミナコイド)をしっかり摂り入れることが大腸に住む腸内細菌の活性を促します。また一定の菌を摂り入れることが肌の水分量を保つのではないかなどの研究が行われており、特に日本ではプロバイオティクスの研究が多くなっています。
いずれも腸内環境を整えることで、腸内の腐敗ガスが低下して、肌の細胞のターンオーバーを促したり、肌の水分量が増えたりすることが分かっています。また腸内環境を整えることで、肌の常在菌が良くなることも注目されています。
まだまだ腸内細菌は解明されていないことが多くありますが、確実に腸内細菌と皮膚の老化や常在菌、水分量などに関係していることが明らかになってきているため、自分ができる腸活からぜひ取り入れてみてください。
腸を整える食物繊維
腸活のためには、食物繊維は、不溶性と水溶性をバランスよく食べることが大事です。「平成28年国民健康・栄養調査」の結果でも、普段の食生活では水溶性食物繊維が不足しやすいことが指摘されており、とくに意識して摂取する必要があります。一般的には「不溶性食物繊維:水溶性食物繊維=2:1」の割合で摂取するのがもっとも健康的とされています。
不溶性食物繊維
・キャベツ、ホウレンソウなどの葉物野菜、キノコ、豆類などに多く含まれる
・便の嵩を増すことで腸を刺激して、便通をよくする
水溶性食物繊維
・海藻、納豆、さつま芋、ゴボウ、大麦、らっきょなどに多く含まれる
・お腹の中でビフィズス菌などの善玉菌を増やす、糖質や脂質の吸収を抑える
お腹が整えば便通が良くなり、ホルモンバランスや交感神経と副交感神経のバランスも良くなります。
食物繊維以外でも、発酵食品やヨーグルトを食べることで、腸内の善玉菌を減らさないようにすることができます。善玉菌が発酵代謝して作り出す物質が、免疫を活性化させるため、健康維持には欠かせません。
一方で、腸内には悪玉菌もあり、砂糖や油、肉、揚げ物など食べ物によって増加します。悪玉菌は腸内で毒ガスを発生させます。また腸のバリア機能が破壊されると、そこから悪玉菌によってつくられた有害物質が血液によって体中に巡るため、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病や、お肌の荒れ、ホルモンバランスの悪化につながります。このようなリーキーガットと言われる症状が大きな問題となっています。
ターンオーバーを抑えるフェノール
腸内環境を良い状態に保つには発酵性の食物繊維が良いことが分かっています。腸内環境が悪ければガスが溜まり、そのガスは体に吸収されていきます。具体的にはアンモニアやフェノールがあり、便秘をしたときに便が臭くなる原因の物質です。このフェノールが肌細胞のターンオーバーを抑えてしまうという研究報告があります。そうなれば、角質が溜まり、新しい肌細胞が生まれず、細胞間脂質が生成されなくなるため、乾燥肌の原因になります。
このように便秘になると肌の状態が悪くなるため、食物繊維を摂ることが大切ですが、特に発酵性食物繊維が善玉菌のエサになりやすいために注目されています。発酵性食物繊維は、腸の中で善玉菌のエサとなって、発酵することで「短鎖脂肪酸」を作り出します。この短鎖脂肪酸が腸内環境を整え、悪玉菌を抑えてくれる働きをします。
この発酵性食物繊維の大半が穀類です。例えば精製していない穀物、特に押麦や大麦、小麦ブラン(外皮)など茶色の穀物に豊富に含まれており、その他海藻、大豆製品などに多く含まれています。
食物繊維はサプリで補うことはできない
腸活という流行りもあり、コンビニなどで腸に良いと言われる食物繊維サプリや乳酸菌の入った飲料や食品を多く見かけるようになりました。しかし、その多くは健康にとってあまり意味のないものであり、それだけ摂れば補うことができていると考えないようにするべきです。
食物繊維とは、食品に含まれる、消化されない炭水化物で、小腸で消化・吸収されずに大腸まで達する食品成分のことです。食物繊維には、水に溶ける水溶性と不溶性の2種類があり、両方をバランスよく摂ることが大切と言われています。
食物繊維は、腸の善玉菌のエサとなり、増殖を促進して健康に貢献します。この善玉金は酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸をつくり出し、結腸の細胞に栄養を与え、炎症を軽減し、過敏性腸症候群、クローン病、潰瘍性大腸炎などの消化器疾患を改善するのに役立ちます。
このように食物繊維は絶対に摂取するべき栄養素に関わらず、多くの人が十分に摂取できていないのが現状です。そこでサプリで補おうとする方が多くいらっしゃいます。
2015年に食物繊維のサプリ効果を検証した論文が発表されており、結論は食物繊維をサプリで摂ることはお勧めできないということになっています。臨床的に意味のある健康上の利益を提供する可能性があるものはごく少数です。食物繊維がもたらしてくれる一部の効果(排便や血糖コントロール)はありますが、サプリで不足で補うことは難しい側面があります。
食物繊維は善玉菌のエサとなり腸内環境を整えてくれること以外にも、死亡リスクが低下する、ダイエット効果、血糖値の上昇を抑えるなどが挙げられます。基本、食物繊維を摂取するには、果物や野菜、それに加えてキノコ類や豆類などにも含まれているので、積極的に食べることをお勧めします。
便秘体質は危険の兆候
腸の働きをよくする、腸の調子を整える、腸の免疫力を高めるというヨーグルトは腸に万能と思い込んでいる方が多くいらっしゃいます。腸には、小腸と大腸があり違った役割があります。
- 消化(小腸)
- 吸収(小腸、大腸の一部)
- 排出(大腸)
- 免疫(主に小腸、大腸の一部)
このように、食べ物の消化や栄養分などの吸収を担う小腸と同じくらい、大腸の排出システムが重要です。その理由は、排泄がスムーズにできなくなれば、老廃物が体内に蓄積し、体の不調を引き起こすことにつながるからです。
排泄には2つの要素があり、栄養分と水分が吸収された後の食物の残りカスの排泄と、食べ物の中に含まれる有害成分や体内で発生する老廃物の排泄です。つまり大腸は有害物質(有害ガス、活性酸素含む)が最後に集まる場所になり、働きが衰えると便秘になるだけでなく、便意そのものが起こらなくなります。
腸は脳神経叢や自律神経との連動によって、本人との意思とは関係なく動いてくれますが、最後の肛門の開閉だけは自分の意思で行う必要があります。
大腸に滞留した便があるにも関わらず、便意を感じなくなっているのに、ヨーグルトの力を借りて排便機能を取り戻すことは不可能です。ヨーグルトは消えた便意を復活させることはできません。つまり、ヨーグルトなどは万能な効果を発揮するわけではありません。
実は、ヨーグルトは日本人が元来食べるものではなく、1945年以降に積極的に乳製品を摂ることになったことが糖尿病増加の一因と指摘されています。またヨーグルトの乳酸菌のことについては評価されていますが、その他の成分についてはあまり触れられていないのが現状です。
例えば、ヨーグルトの脂肪成分は、豆乳と比べてみても、100g中の不飽和脂肪酸やコレステロールの含有量が格段に多く、また動物性乳酸菌は胃や腸の消化液で死滅してしまうため、腸まで生きたまま届く乳酸菌を選ぶか、もしくは植物性乳酸菌を含むキムチや納豆などの食材を多めに摂るようにしましょう。
オリゴ糖で便通が改善する
オリゴ糖の最強の効果は、甘いにも関わらず腸内環境に良い効果を与えてくれるという点です。血糖値を上げてしまう砂糖や悪玉菌の餌になってしまう人工甘味料などは大抵体に悪いというイメージです。一方でたまに食べる甘いものは、心を和ませメンタルに良い影響を与えてくれます。
研究によると甘いものを食べることによって、96.5%もの人が幸福感を感じることが分かっています。このように甘いものによって幸福感が促されるのは、甘いものを食べると脳内でβエンドルフィンという物質が分泌されるためであると考えられています。βエンドルフィンは、脳内モルヒネなどとも呼ばれ、高ぶった気持ちを落ち着けて不安やイライラ感を和らげる効果があります。
多くの甘いものは体に悪いばかりか依存性があり、食べれば食べるほどにもっと甘いものが欲しくなってしまうという注意点があります。しかしオリゴ糖は、砂糖に比べて甘さが控えめで砂糖の甘さを100とすると、大体20から50ぐらいがオリゴ糖の甘さであると言われています。
また砂糖依存症になってしまう原因として、低血糖という原因を挙げることができます。膵臓から大量のインスリンが分泌されることで逆に血糖値が下がりすぎて低血糖になってしまいます。高血糖が長い時間をかけて糖尿病を始めとする合併症を形成するのに対し、低血糖はすぐにでも対しなければ死に至ってしまう体にとっては危険な状態です。そのため低血糖になると体はSOSを発して、血糖を上げるために砂糖を発するようになります。これが砂糖を食べるとより砂糖が食べたくなってしまう仕組みです。
しかし、オリゴ糖は難消化性と言って私たちの胃や腸の中で消化されづらく、消化されないということは、つまり吸収もされないため血糖値を上げづらいと いうことが知られています。実際このような性質からオリゴ糖は、糖尿病患者への食事療法としても使われています。さらにオリゴ糖には、依存性がない上に非常に体に良いという点が挙げられます。
オリゴ糖が持つ腸内環境の改善の鍵には、難消化性であるところに秘密がありますが、消化吸収できない栄養素といえば食物繊維があります。食物繊維は、タンパク質や脂質などと並んで重要な6 大栄養素の1つに数えられていますが、他の栄養素と大きく違う点が消化吸収されないからこそ体に良いという点なんです。
食物繊維は消化吸収されないため便の傘を増したり、便にぬめりを持たせて腸を刺激し便通を良くするといった効果があります。また食物繊維は私たち自身にとっての栄養とはならない一方で、町内の善玉菌の餌になることで腸内環境を改善してくれます。オリゴ糖も、またこのような食物繊維によく似ており、腸内の善玉菌がそれを食べることで高い整腸効果を発揮してくれます。
実際にオリゴ糖が腸内環境を改善してくれることは実験データからも示されています。被験者にオリゴ糖を14日間摂取してもらった実験では、腸内の善玉菌の1つであるビフィズス菌がしっかりと増えていることが確認されています。また同じ被験者にオリゴ糖の摂取を中断してもらったところ、逆にビフィズ菌が減ったことも報告されています。
そして別の研究ではオリゴ糖の継続的な摂取によって、便の回数や硬さ、色などが改善したデータも報告されています。そして、この研究で便の匂いの改善が報告されています。
便の匂いは、腸内細菌が食べ物を分解してできるガスの匂いに他なりません。便の匂いが臭いことは、それだけ腸内で悪玉菌が増えていて腸内が腐敗した食べカスで溢れていることを意味しています。逆にオリゴ糖を摂って便の匂いが改善したことは、腸内で善玉菌が増えて有毒なガスが減ったことを意味しています。
腸内細菌の重要性
私たちの体のあらゆる表面には細菌が住み着き、その9割は腸に住んでいる腸内細菌です。その種類は1000種類以上で100兆個にもなります。腸内細菌は種類ごとに規則正しく並んで全体として集団を形成しており、それが腸内フローラです。
その中で腸内細菌が作り出す酸には腸内環境を綺麗に整える働きがあり、特に短鎖脂肪酸の一つである酪酸は、大腸が正常に働くためのエネルギー源にもなります。また腸内細菌は心臓の健康にも影響を与えていることが示唆されています。さらに血糖値のコントロールにも重要な役割を果たし、糖尿病リスクを下げるのに役立ち、さらには脳の健康にも役立っています。例えば腸内細菌が作り出す神経伝達物質(セロトニンなど)は脳に非常によい影響を与えます。
腸内環境を整えるには、善玉菌をしっかりと増やすことが大切で、善玉菌は消化の吸収補助、免疫刺激など健康維持や老化防止に影響があります。代表的な菌にはビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌などがあります。日経メディカルオンラインは3618人の医師にアンケートを行い、医師が最も処方している腸を整えるための薬は酪酸菌が入った整腸剤で、2番目がビフィズス菌の入ったものだということが分かっています。
酪酸菌は酪酸をつくる細菌の総称で、酪酸や酢酸を作り出し悪玉菌の発育を抑制してくれます。ビフィズス菌は乳酸、酪酸を作り出すことで悪玉菌の増殖を抑えてくれる作用があります。特に酪酸菌は大腸の主要なエネルギー源となり、酪酸により酸素が消費されることで大腸内がビフィズス菌や他の善玉菌が住みやすい環境になります。つまり酪酸菌を積極的に摂取することによって様々な健康効果を私たちにもたらされるのです。
腸活にはルミナコイド
私たちの体に大事な5大栄養素は、エネルギーのもとになる炭水化物、体をつくるタンパク質、それを調整するミネラルとビタミン、そしてエネルギー源のもととなる脂肪があります。これらをバランス良く摂ることで健康を維持することができますが、現代人が不足している第六の栄養素に『ルミナコイド(食物繊維)』があります。不足することで肌荒れ、アレルギーや慢性の湿疹、やる気が出ない、生活習慣病などが引き起こされることが最近の研究で明らかになってきています。
食物繊維を摂ることで肌の水分量を増やしたり、便の量を増やして排便を促したり、腸で免疫力を調整したり、様々な効果が期待できます。食物繊維を多く摂ることを気をつけていても、腸の調子が改善しない、血糖値が高いなどの場合は、第6の栄養素であるルミナコイドが不足しているかも知れません。
一般的に食物繊維には、野菜などの水溶性繊維質のものと、穀類、豆類などの不溶性食物繊維があります。一方でルミナコイドは、胃や小腸で分解されずに大腸で消化された時に短鎖脂肪酸を発生させるものです。短鎖脂肪酸は大腸でつくられる成分であり、酪酸・酢酸・プロピオン酸に分けられます。
短鎖脂肪酸は、腸の蠕動運動のエネルギーのもとになることや、免疫機能を調整することで炎症を抑え、そして血糖値が急激に上がるのを抑制する効果があります。また短鎖脂肪酸が生成されることによってGLP-1(食欲を抑えるホルモン)がつくられるため、過度な食欲を抑える効果もあります。
また、腸内環境が整って短鎖脂肪酸が生成されることで、成長ホルモンの分泌も促進され、肌の線維芽細胞にも働きかけてターンオーバーが促されたり、コラーゲンやエラスチンの産生を促すことが分かっています。肌の表皮の水分量をアップさせるためには、免疫やホルモンの調整が重要になります。
イヌリン、レジスタントスターチ、フラクトオリゴ糖など短鎖脂肪酸もルミナコイドの1つです。イヌリン、レジスタントスターチは今までは糖類という炭水化物としての位置付けでしたが、大腸のどの部分に効果があるかが違うため、これらを含めてルミナコイドと呼ぶようになっています。
腸活の多くは、ビフィズス菌などを外から摂りましょうということ(プロバイオティクス)ですが、もともと腸にいる腸内細菌の環境を整えてあげるも大切です。ルミナコイドのようなプレバイオティクスで腸内細菌の餌をつくってあげることで、短鎖脂肪酸をつくる環境を整えてあげることが大切です。
つまり、例えば食物繊維を摂っても便通が改善しないのは、プロバイオティクスばかり摂っている可能性があります。このように食物繊維は水溶性・不溶性だけでなく、大腸で消化することで短鎖脂肪酸をつくる第6の栄養素がルミナコイドです。
余談ですが、短鎖脂肪酸の生成を促すためには運動も大事な要素です。研究では、ずっと座っている方とラグビー選手を比べたところ、ラグビー選手の方が短鎖脂肪酸の酪酸を生成する能力が高かったことが分かっています。また息が上がるような運動を60分週3回で行うと酪酸を生成する機能が向上することが分かっています。
酪酸菌の健康効果
炎症を抑える
酪酸菌は体内の炎症を抑えてくれる効果があります。炎症は体内に侵入した異物を排除する機能であり、異物が排除されると治る「一時的な反応」を急性炎症と言います。一方で様々な病気の引き金になってしまう慢性炎症があります。
腸内フローラの中には、この炎症を抑制してくれる様々な菌がありますが、その中の代表的なものが酪酸菌です。酪酸菌は制御性T細胞を誘導し、炎症を抑えるのに役立ちます。制御性T細胞は、炎症反応を抑制的に制御し、免疫応答が過剰にならないようにするブレーキの役割を持った細胞です。また酪酸は多くの免疫細胞にも影響を与え、例えばマクロファージやB細胞にも作用して、腸や関節の炎症を軽減してくれることも分かっています。
アレルギーを軽減
日本人の2人に1人が花粉症、アレルギー性鼻炎、アレルギー性皮膚炎など、何かしらのアレルギー症状を持っていると言われています。そんな国民病であるアレルギーを予防・軽減する可能性が酪酸菌にあると示唆されています。
腸とアレルギーには強い関連性があり、喘息や花粉症、アトピー性皮膚炎などには腸内環境が深く関わっていることが指摘されています。例えば腸内環境の働きによって生み出される短鎖脂肪酸が、アレルギー反応を軽減するなどの研究結果が報告されています。つまりアレルギーに苦しんでいる人は腸内環境を整えてあげることで、軽減される可能性があります。
癌の予防
日本人の患者数の中で最も多いのが大腸癌です。女性の癌による死因の1位、男性の3位は大腸癌です。酪酸は遺伝子の発現調整に直接関与し標的癌遺伝子の発現に影響することが明らかになっています。つまり酪酸は癌を抑えてくれる遺伝子を活性化することによって、癌予防に関与する可能性が示唆されています。
酪酸を作るときに利用するのが食物繊維で、食物繊維の摂取量と大腸癌の関係が疫学研究により明らかになっています。例えば食物繊維の摂取量が増えることで、大腸癌リスクが減るということが分かっています。
酪酸菌を増やす方法
酪酸菌を増やす方法は以下が挙げられます。
- いつもの食事に+5gの水溶性食物繊維を追加する
- 酪酸菌を摂れる食べ物やサプリメントを摂取する
- エクササイズで酪酸菌を作り出す
特に水溶性植物繊維の中でも発酵性の高い食物繊維を日々の食事に継続して取り入れることが大切です。また酪酸菌が含む食材は非常に少なく、食品から酪酸菌そのものを摂取することは難しいため、サプリメントなどで補いましょう。
食生活を改善するだけでなく、運動習慣を心掛けることで腸内の酪酸菌を増やすことができます。特に有酸素運動をお勧めします。
インディバ(ラジオ波)で腸活
当院のインディバによる深部加温によって腸内活動を活発化し、腸の蠕動運動を促進します。また腸冷えは、血流の悪化を招き、栄養や酸素が運ばれなくなるため、血管や内臓のはたらきをコントロールする自律神経が乱れます。その結果、交感神経が優位になって、さらに腸の動き悪化させてしまいます。
お腹を温めることで、腸機能を活性化させ免疫力向上が期待できます。さらにインディバの高周波は、3〜7℃体温を上昇させることができるため、その上昇は有酸素運動の約5倍もの温熱効果があります。そのため脂肪を燃焼させる痩身効果だけでなく、便秘改善や生理痛の緩和、自律神経を整える作用、不安やストレスによる緊張の緩和など健康効果も期待できます。
美容鍼灸で腸活
美肌効果
お顔だけでなくお腹に鍼をすることで胃腸の働きを改善することができます。その結果、まず得られるのが美肌効果です。前述したリーキーガットによって引き起こされる症状の1つが、肌荒れや吹き出物です。その理由は、悪玉菌によってつくられた有害物質が血流に乗り体中を巡り、やがて肌から対外へと排出されますが、その際に皮脂や角質と結び付いてしまうからです。
正常な腸内環境であれば、善玉金が悪玉菌より多く存在していますが、ストレスや食生活、生活習慣の乱れにより悪玉菌が増加すると、腸内環境が悪化してお肌に不調が現れてしまいます。このように胃腸と肌は密接に関連しています。腸内環境を整えることは美肌や健康には欠かせないポイントです。
便秘の解消
お腹の鍼によって腸内環境を整えるメリットの2つ目は、食べ物の消化・吸収を良くすることで便秘の解消ができることです。さらに代謝が良くなるため、脂肪が燃えやすく、痩せやすい体を作ることができます。
自律神経を整える
メリットの3つ目がお腹に鍼をすることで自律神経を整えることができます。自律神経の乱れによって、不安や緊張感が高まり、吐き気や多汗、全身のだるさ、頭痛、肩こり、手足のしびれ、動悸、不整脈、めまい、不眠など、様々な症状を引き起こします。
自律神経と腸内環境はお互い影響し合っており、自律神経のバランスが乱れると、腸内環境も乱れ、腸内環境が良くなれば自律神経のバランスも良くなります。つまり腸内環境を整えることで、自律神経の乱れによって引き起こされる様々な症状を改善することができます。
免疫力を高める
また、腸内には100兆個を超える腸内細菌が存在しており、全身の免疫細胞の7割が存在すると言われています。これらを「腸内フローラ(腸内細菌叢)といい、この腸内細菌叢のバランスが保たれていると、免疫力が高まり、風邪を引きにくい健康的な体へと導いてくれます。
このように腸内環境は体の免疫機能と深く関連しており、健康的で美しい体を手に入れるためにも、腸内環境はとても重要です。お腹周辺には複数のツボがあり、ご自身のお悩みによって鍼をするツボも変わってきますので、気になる点はカウンセリング時に鍼灸師にご相談ください。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。