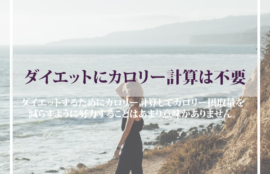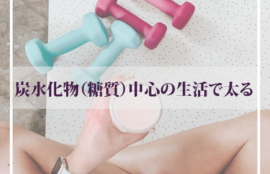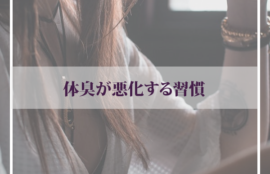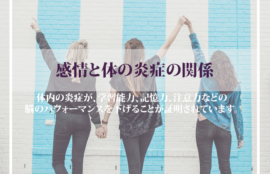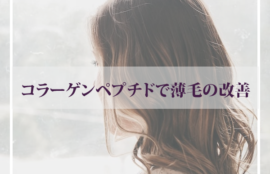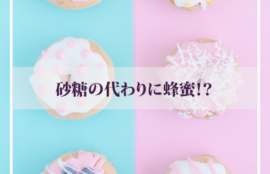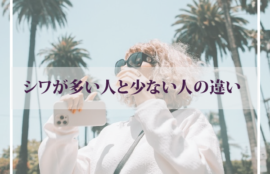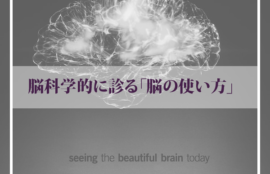あまり知られていない「副腎」のケアをするかどうかで老化の速度が全く異なってきます。年齢ではなく、副腎の疲れが老化やボケ、認知症などの原因になります。なぜなら病気、アレルギー、認知症、生活習慣病、鬱、イライラなどは全て体内に起こる炎症が原因だからです。この炎症を抑えているのが副腎の機能です。つまり副腎の疲れを取ってあげることで病気を防いだり、老化を防いだりすることができるのです。
特に現代人は、過剰なストレスによって、この副腎にたくさんの負担がかかり、体の中で炎症が起こっているものの、副腎が疲れで本来の機能を十分に果たしていないのが現状です。しかし副腎は重度でない限り自分で直せるものです。
副腎疲労
同じ年代でも見た目が若々しい人と老けている人がいます。これは認知症でも同じで、90歳でもしっかりした人もいれば、60歳でぼーっとした人もいます。このような違いは体内の炎症にあります。
本来、私たちの体には炎症を抑える機能があり、そのためのホルモンがコルチゾールであり、それを作っているのが副腎です。しかし炎症を抑えるためにフル回転し続けると副腎が疲れてしまい、その結果様々な不快な症状を抑えられなくなるのです。
例えば、副腎から絶えずコルチゾールが分泌されると、血糖値や血圧が高い状態にキープされます。こういった状態が続くと血管の老化が進み、血栓ができやすくなり、認知症の発症リスクが高まります。また血管が傷つくだけでなく血管が老化し、弾力を失い、血流が悪化して肌がカサカサになる、髪がパサパサになるといった見た目のトラブルや肩こり腰痛などといった不調が現れます。一方で血管が老化する原因には、体に悪いものを食べている、睡眠不足や運動不足といったことも挙げられます。
この副腎の疲れは海外で注目されており「副腎疲労」と呼び、実際に臨床の現場にも副腎のケアが取り入れられつつあります。
老化も慢性炎症の一つ
慢性炎症は様々な症状を引き起こし、上咽頭、炎歯周病、キーガット症候群などに加え、肥満、うつ、老化、不眠などを引き起こすとされています。慢性炎症が体の中で起こり続けていると、炎症性サイトカインというものが作られすぎて、持続した炎症を沈静化することができず火事が燃え広がるようにどんどん全身に炎症が広がってしまいます。
さらに持続的に炎症が起こることで、組織の繊維化が起きてしまいます。線維化は、組織が硬くなって壊れ、もう元には戻らないという現象です。これによって組織の形態自体が変わって機能が低下してしまいます。例えば肝臓で慢性炎症が起きると肝硬変が起きて、肝臓の機能が低下します。
このようなことが肝臓だけでなく、あちこちで起き、慢性炎症が引き金となって炎症が全身に広がっていき、壊れた組織は修復できない状態になってしまう悪循環が起こってしまうのです。
特に注意して頂きたいのは肥満の方、太っている方です。肥満体質の人の体内では、炎症性サイトカインの分泌が誘発されて脂肪組織が炎症を引き起こしていることが分かっています。つまり太っている=慢性炎症が起きている状態だと考えられます。その肥満を解消しないことには体中の炎症を鎮火することはできません。
また、同世代の人よりも自分の見た目が老けていると感じる人も要注意です。なぜなら老化も慢性炎症の一つだからです。実際に細胞が老化すると不要な細胞は細胞死をきたします。その老化した細胞が様々な炎症性サイトカインを放出することが分かっています。つまり老化した細胞が周りの細胞に放火して回るようなものです。これによってその細胞だけではなく、周りの細胞も炎症をしてしまい、老化が進んでいくという負の連鎖に陥ってしまいます。
このように慢性炎症が体内で広がってしまうと、どんどん臓器の機能が低下し、さらに慢性炎症は慢性的に体にストレスがかかっている状態であるため、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌されてしまいます。つまり副腎疲労を引き起こす原因にもなってしまうのです。
副腎疲労のセルフチェック
以下の項目に3つ以上当てはまれば副腎疲労かどうかは分かります。
- 物忘れが多く人や物の名前が出てこない
- 熟睡できず起床しても疲れが取れた気がしない
- 些細なことでイライラしたり怒りやすくなった
- 人に会うのが面倒で外出が面倒
- 風邪や怪我の治りが遅くなった
- 頭がぼーっとしていて新聞や本の内容が理解しにくい
- 更年期症状がひどい
- 性欲を感じない
- 胃炎や下痢、便秘、お腹の張りに悩んでいる
- 食べる量は変わっていないのに太りやすくなった
- 血圧、血糖値が高くなった
- 白髪や抜け毛、肌のシワやシミが増えた
引用:「副腎の疲れをとれば老化もボケも食い止められる」より
美肌と副腎の関係
老化は体内の炎症が原因ですが、炎症には怪我をした時に赤く腫れるなどの「急性炎症」と、長い間持続的におこりジワジワと蝕む「慢性炎症」があります。後者は、私たちの生体組織の機能や構造に異常が生じて様々な疾患の原因になります。副腎が疲れていると、慢性的な炎症がいつまでも消えることがないため老化やボケが加速してしまうことになります。
また、副腎が疲れていると、肌の炎症を抑えるコルチゾールが分泌されないだけでなく、眠れない、眠りが浅い、体がだるい、便秘、下痢、肌の乾燥ややるみ、髪のパサつき、生活習慣病、アレルギーなどの原因になります。さらに頭がぼーっとする、頭がうまく働かないといったブレインフォグ(脳の霧)は年齢に関わらず、副腎が疲れていると起こることが分かっています。
副腎疲労とブレインフォグ
認知症などの脳の病気は、20代であっても仕事や勉強の忙しさなどで睡眠不足が続いたりすると、それがストレスになりコルチゾールが過剰に分泌され、物忘れがひどくなったり記憶力が低下したりするなどの認知症のような症状が現れることがあります。
これを「ブレインフォグ」状態と呼び、霧がかかった状態を意味し、まさに頭の中で霧がかかったようにぼんやりとして、記憶力だけでなく思考力や判断力などが大幅に低下してしまう状態です。例えば文字を何度読んでも頭に入らない、約束したことを忘れてしまう、スケジュールが思い出せないなどを繰り返すうちに、メンタル的にもネガティブな考えに支配されて、うつ病のような症状をきたしやすくなることも、ブレインフォグの特徴の一つです。
副腎の疲れを取る方法
副腎が疲れる原因は、人間関係などの悩みによる精神的なストレス、睡眠不足、疲労、栄養状態の悪い食事などの肉体的なストレス、化学物質、食品添加物、汚い空気などの環境的なストレスです。
その中でも副腎に大きな影響を与えているのが食習慣や食べ物です。なので副腎の疲れを取るための大原則として、悪いものを体に摂らないことです。また副腎の疲れを取るためには、まずは腸の状態を整えて、次に肝臓の負担を取り除くという順番が大切です。
腸の負担を減らす
なぜなら、腸は栄養素の入り口であり、腸の状態が悪ければ栄養素が十分に吸収されず栄養不足になってしまうからです。肝臓は体内のデトックスを担う臓器で、化学物質や重金属などを排除してくれる役割があります。腸が整い、肝臓がよくなることで副腎の機能も回復していきます。
まず、副腎の疲れを取る方法として「副腎疲労外来」で推奨しているのが、グルテン、カゼイン、シュガーの3つのフリーです。グルテンフリーは、小麦やライ麦などに含まれているタンパク質で、パンやピザ、パスタやうどんなどに含まれています。このグルテンがアレルギーや炎症の原因になると言われています。いつも胃腸の調子が悪い、体調が悪く疲れているなどで、グルテンフリーにすることで改善することがあります。
次はカゼインフリーです。カゼインは乳製品に含まれているタンパク質で、牛乳やヨーグルト、チーズなどに含まれています。カゼインはアレルギーや花粉症、めまい、アトピー性皮膚炎を引き起こす可能性があると言われており、特に日本人は遺伝的に乳糖を分解する能力が低い傾向にあるので、カゼインフリーで体調の変化を確認することもおすすめします。
最後がシュガーフリーです。副腎疲労の多くの人が、疲れた時に甘いものを食べるという習慣があります。副腎疲労は、低血糖にならないようにむしろ血糖値を上げた方が良いと思うかも知れません。低血糖にならないようにするのは確かに大切なことですが、空腹時に甘いものや炭水化物を一気に食べてしまうと血糖値スパイクを起こしてしまいます。
血糖値スパイクを起こすと、インスリンが大量に分泌され、その反動で一気に血糖値が下がります。通常はコルチゾールが分泌され低血糖状態になるのを防いでくれますが、副腎疲労があるとコルチゾールの分泌が上手くされず低血糖状態になってしまいます。これが甘い ものをスタートした強い眠気やイライラ、怠惰感の原因になります。それでも血糖値を上げようと副腎は頑張り、これを繰り返しているうちに副腎に負担が掛かり、より副腎は疲弊してしまいます。
さらに、昼間のこうした血糖値の乱高下は、夜の睡眠の質にも影響があるため、ストレスが強い環境にいるときほど血糖値をなるべく一定に保つことが大切です。コルチゾールをなるべく節約するために、甘いものが欲しくても血糖値スパイクを起こさないような食べ物を摂りましょう。また砂糖は腎臓だけでなく様々な生活習慣病を引き起こす原因になるので、真っ先にシュガーフリーにしましょう。
一方で副腎疲労を回復するためには、フィッシュオイルを摂り入れましょう。オメガ3系の不飽和脂肪酸は、炎症を軽減してくれる効果があります。魚の油に豊富に含まれているオメガ3脂肪酸は、炎症を抑えてくれる作用が高く、細胞膜の安定に役立ちます。そのため腸の粘膜の炎症が引き金となるリーキーガットの予防と改善が期待できます。特にオメガ3脂肪酸は魚の中でもイワシやサンマ、サバといった青魚に多く含まれており、これらに含まれるオメガ3脂肪酸はEPAとDHAの2種類があります。
DHAは血液脳幹門を通過するということが知られており、DHAが血液脳関門を通過できるということは、脳にとって欠かせない働きをしている証拠にもなります。実際DHAは神経細胞同士の情報伝達を良くしたり、セロトニンの生成を促したりすることが知られています。またDHAは認知症の予防、脳への炎症抑制などが期待できます。さらにオメガ3脂肪酸は血液をサラサラにすることから体全体の血流も良くなります。
そして炎症の修復に欠かせない亜鉛も一緒に摂りましょう。また副腎が疲れている人は、ビタミンB群が不足している傾向があり、コルチゾールをつくるためには、ビタミンB群が必要になります。このビタミンB群は体の中に貯めておくことができず、常に食べ物から補給する必要があります。
肝臓の負担を減らす
肝臓には解毒機能がありますが、この解毒機能が追いつかないケースが多々あります。そのため体の中に蓄積された毒があちこちで炎症が起きてしまいます。つまり肝臓が疲れると、副腎にも影響してしまうのです。なので肝臓の解毒作用の負担を減らす必要があります。その負担の代表が食品添加物なので、食品添加物が少ないものを選ぶことを心がけましょう。また生活の中で使う、シャンプーや整髪料(パラペン:防腐剤)、歯磨き粉(研磨剤、防腐剤、香料など)にも気をつけましょう。解毒には汗をかくことも大変有効なので、お風呂に入ることや運動を取り入れ、シンプルな生活を送り、肝臓の解毒を積極的にサポートしてあげましょう。
腎臓の負担を減らす
腎臓が老化スピードを決めます。腎臓は「沈黙の臓器」とも言われ、機能が低下しても気づきにくい臓器です。腎臓は、老廃物を尿として取り除く、塩分などの電解質の量を一定にする、血圧を調整する、血液を作るホルモンを出すなどの働きがあります。この中で重要な働きが、血液をろ過して老廃物を尿として排出し体内を綺麗な状態に保つことです。また最近では老化と寿命にも深く関わっていることが明らかになっています。
私たちが健康的に生きるためには、体の外から栄養を取り入れ、不要なものを排出することが大切ですが、上手く排出することができなければ臓器の機能低下や代謝機能が低下して体調不調や老化現象が加速します。また体に必要な栄養素まで尿に排出されるため、病気や老化現象が現れるようになります。
腎臓に悪い食べ物は、菓子パン、洋菓子、インスタント食品、加工食品、揚げ物、肉の脂身、ファストフード、甘いジュースです。これらは一般的に健康に悪い食べ物でもあります。特にインスタント食品や加工食品には、食品添加物としてリンが多く含まれており、天然に含まれているリンと比較して、体で吸収されやすく過剰になってしまいます。また加工食品には塩分が多くふくまれており、腎臓に大きく負担がかかります。塩分やカロリー、アルコールなどの過剰摂取は糖尿病、高血圧、痛風などの生活習慣病を発症して腎臓の負担に繋がります。
例えば、塩分の摂りすぎで高血圧になると腎臓内の細い血管まで高い圧力がかかり、老廃物をろ過するための細胞が破壊されます。その結果腎臓そのものの機能が低下してしまいます。そしてこれはカロリーやアルコールも同じことです。
バランスの良い食事を摂る
副腎を疲労させないために積極的にとってほしいのは、良質なタンパク質と良質な脂質です。タンパク質としては、お肉なら鶏や豚、できればグラスフェットという牧草で飼育している牛肉が良いと言われています。魚であれば、食物連鎖で重金属を蓄積しやすいと言われているマグロなどの大型の魚以外のものをなるべく選んだ方が良いと言われています。特にオメガ3系の脂肪酸を含むあじ、いわしやさんまといったのは青魚が最適です。また魚以外の脂質として、αリノレン酸が含まれている亜麻仁油、ごま油などもおすすめです。
また、ハーブ、スパイスや野菜も積極的に摂りましょう。肝臓は重金属などの有害物質を解毒する器官であり、現代人は様々なストレスで肝臓が疲れてる方が大変多いです。そのため肝臓で解毒できなかった毒素が各臓器に広がって炎症を起こし、これが副腎の負担にもなっています。
そのため解毒作用があると言われているニンニクや生姜、玉ねぎやパクチなどの香味野菜やハーブスパイスなどを摂るように心がけましょう。
一方で、ホルモンの生産過程で大量に消費されるのがビタミンBと言われており、副腎疲労の人は特に不足しやすい栄養素です。ビタミンBを多く含まれている玄米や豚肉、卵、貝類、海藻類を多めに摂るということも大事です。特にビタミンBの一種である葉酸は、造血作用、新しい細胞を作るのに重要な成分です。
同じく副腎が疲れている人の特徴として不足しやすいのがミネラル類です。副腎疲労の人は、正午に不調を抱えていることが多いと言われています。副腎の正常な働きに欠かせないナトリウムやカリウム、ホルモン代謝に必要な酵素を助けるマグネシウム、新陳代謝をよくして免疫を調整する亜鉛、イライラ解消に必要なカルシウムなど、どれも必要な栄養素です。ミネラル豊富な貝類や海藻類も食卓に取り入れてみるとミネラル不足も解消されるのでおすすめです。
因みに副腎は人間の体の中で最もビタミンCを消費する臓器とも言われてい ます。血中濃度を1とした時に、脳はその10倍、白血球が80倍消費するのに対して、副腎は150倍のビタミンCを消費すると言われています。体の組織が修復される睡眠時にビタミンCはより多く消費されます。柑橘類などのフルーツでビタミンCを補給しましょう。
「リン」で老化が加速する
この中でも排出すべきもの食品添加物の「リン」です。このリンが老化を加速させて、人の寿命に大きく影響していることが分かっています。例えば血中リン濃度が正常範囲の人およそ4000人を対象とした疫学調査研究では、血中リン濃度が高い人は、低い人にくらべて死亡率が7割も増加していることが明らかになりました。ここからも腎臓のリンを排出する機能の重要性が分かると思います。
日本では、70代の3人に1人、80代では2人に1人、1330万人以上の方が慢性腎臓病を患っていると言われています。また慢性腎臓病は、心筋梗塞や脳卒中などの心血管病のリスクが高まることが知られています。腎臓の機能低下は初期の段階では自覚症状がほとんどないため、はっきりと症状が現れてからでは治療が難しい側面があります。ただし腎機能が落ちてくると体調や尿に少し変化が現れます。
| 腎臓の状態をチェック | 老廃物が十分に排出されていないサイン |
| 尿が泡立ち、その泡がなかなか消えない 尿が茶色または黒色に近い 尿から強いアンモニア臭がする 水分の摂りすぎではなく、10回/日以上トイレに行く 尿が1日3L以上、または400ml以下しか出ない | 指輪や靴がきつい だるさや疲れを日々感じる 食欲不振や吐き気、全身にかゆみがある 少しの運動で息切れする 貧血や立ち眩みをよくする 汗をほとんどかかない |
腎臓をケアする方法は、1日男性21g、女性18g以上の食物繊維を摂ることです。しかし20g前後の食物繊維を摂ろうとすると、レタスなら1日合計6から7玉食べなければ足りません。食物繊維を摂るための基本は、1日350gの野菜を摂ることです。野菜には食物繊維以外にも、ミネラル、ビタミン、抗酸化物質が豊富に含まれているため、かなり意識的に野菜を食べる必要があります。これに加えて、海藻やキノコ、豆類、果物など食物繊維が豊富に含む食材を積極的に取り入れましょう。
東洋医学で診る「肌の乾燥」
肌が乾燥するのは加齢だけが原因ではありません。東洋医学では肌の乾燥は陰虚症という症候の1つと考えられています。陰虚症とは体にとって必要な潤いや水分が不足している状態で、夜更かしや睡眠不足、慢性病、過度な発汗などによって起こります。
陰虚症になると肌のバリア機能が低下し、外からの刺激に弱くなります。また肌の油膜や真皮部分が減少し、肌の水分が蒸発しやすくなります。これらが肌の乾燥やシワの原因になるため、陰虚症による乾燥肌を改善するには内部からの水分補給だけでなくタンパク質やビタミンなどの栄養もバランスよく摂ることが必要です。
また、睡眠の質を上げることも大切で睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌のターンオーバーを促進し、肌の潤いを保ちます。ケアとしては肌に刺激を与えないように、太谿(たいけい)と湧泉(ゆうせん)いうツボ押しがをお勧めです。また美容鍼もお勧めで、陰虚症による乾燥肌は東洋医学の知識を活用することで改善する可能性があります。

太谿(たいけい):内くるぶしからアキレス腱の間

湧泉(ゆうせん):足の中央部分
美容鍼で副腎疲労を改善
美容鍼というと、お顔に鍼をすると思われるかも知れませんが、体にも鍼をします。当院の「統合美容鍼灸」では、外側からのアプローチだけでなく、内側からのアプローチにも注目し、お客様それぞれの目的の実現に向けて、根本的なお悩みの改善をサポートします。東洋医学の理論に基づき、肌と心と身体の結びつきから、全体を捉え、忙しい現代人に合わせた経絡やツボを使い、体の内側から改善することで、得られた効果は長く継続することができ、本来の美しさを追求できます。
東洋医学では、副腎と似た働きをする五臓六腑の「三焦」があります。三焦の働きは、腎でつくられた気を運ぶ役割とリンパ液を運ぶ役割があると言われています。副腎と同じく気や水を全身に運ぶ働きを通して全身に影響を与えています。
美容鍼では、気の流れを整える「三焦」の経絡やツボを使い副腎疲労の回復を行います。副腎に効くツボは「照海(しょうかい)」と「腎兪(じんゆ)」です。
照海(しょうかい):内くるぶしの真下

腎兪(じんゆ):背骨中心から指2本分外側

【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。