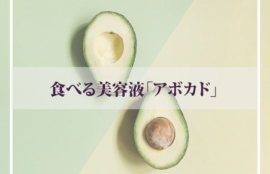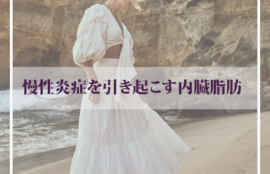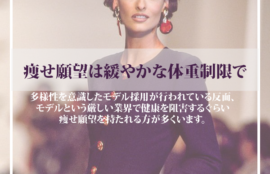近年、パンなどの小麦食品に含まれているタンパク質の「グルテン」が、脳に炎症を起こし、あるいは腸に小さな穴を開けてしまうということが注目されています。また消化困難なタンパク質であるグルテン以外にも、精製された小麦に含まれるのが、血糖の乱高下をもたらすアミロペクチンA、中毒性をもたらすグリアドルフィンです。
グルテンは、人の消化酵素では分解されにくく、ペタペタと腸に張り付くことで腸粘膜を傷つけて炎症を引き起こし、リーキーガットの大きな原因となります。
アミロペクチンAは、小麦の70%を占めている糖質の中の75%を占めている物質であり、急激な血糖上昇をもたらすことが知られています。
クリアドルフィンは、脳のオピオイド受容体というところに結合しモルヒネと同様の作用を引き起こします。その結果ドーパミンが大量に放出されて脳が興奮し、パンをもっと食べたい、ラーメンをもっと食べたいと依存性を引き起こします。
このようなグルテンなどの副作用によって、首肩こりや頭痛、疲労感などの症状が出るとも言われており、これらの悩みがある方はグルテンが原因かもしれません。
グルテンのデメリット
グルテンの強い依存性
小麦に含まれるグルテンには、強い依存性があることが知られています。そのため食べている時は多幸感に満たされるものの、しばらく食べずにいると猛烈な不快感に襲われます。
このグルテンは、胃腸でポリペプチドという小さな化合物に分解されます。小麦ポリペプチドは、アミノ酸が10個以上結合した化合物で、私たちの血液脳関門を通過できる性質を持っています。血液脳関門は、血液中には様々な不純物をろ過して不純物を脳内に入れないための関所の役割をします。小麦ポリペプチドは、関所をいとも簡単に通過し、脳に存在するモルヒネ受容体と結合します。モルヒネに強い依存性があるおと同じく、モルヒネ受容体に結合するグルテンにも当然強い依存性があります。そのため毎日、パンやラーメンを食べていて急に摂取を止めてしまうと、脳は拒否反応を起こして不快感を引き起こします。
また、グルテンによる依存症から抜けて、禁断症状が消えるまでの期間は人によって異なりますが長い人では1ヶ月から2ヶ月かかる人もいると言われています。
脳細胞の酸化
グルテンが脳に炎症を引き起こすことが明らかになっています。近年、頭痛持ちが増えており、病院でも根本的な原因が分からないケースが増えており、長年頭痛に悩まされている背景にグルテンの関わりが指摘されています。
グルテンによってアレルギー反応が起こり、免疫システムが働きます。その時に体内で大量に活性酸素が発生し酸化が生じます。この酸化によって細胞がサビ、様々な不具合の原因になります。例えば老化が進むのもこの酸化によると考えらており、さらには癌や糖尿病の原因になっていることも分かってきました。
さらに、グルテンが原因の活性酸素は、脳細胞を酸化させることも分かってきました。私たちの脳は人体の中で特に酸化しやすい性質を持っています。脳は水分を除くと約6割が脂質であり、残りの約4割がタンパク質で構成されています。脳細胞が活性酸素の害に晒されて炎症が生じると、それが頭痛を引き起こす原因になっていると考えられています。最近では、グルテンを摂取して頭痛を起こしている人の脳をMRIでスキャンしたところ、炎症による変化を撮影できたとする論文が世界5大医学雑誌のランセットに掲載されています。
心にも影響するグルテン
グルテンは、脳だけでなく心にも大きな悪影響を与え、最近では自閉症やADHDといった心の病気の症状の悪化にもグルテンが関与している可能性が指摘されています。
自閉症が社会問題化するアメリカでは、既に自閉症やADHDに対するグルテンの関与が常識となっており、改善のために栄養指導も行われています。また最近ではグルテンの摂取を止めることで、うつ病の改善にもつながる可能性が示唆されています。
腸漏れ(リーキーガット)の原因
最近の研究により、腸に目に見えない細かな穴が開いている人が増えてきていることが分かっています。腸に穴が開けば、食べ物は分解されないまま、腸から漏れ出すことになります。
私たちの胃腸は消化によって炭水化物はブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に分解され最小単位になった後に腸管から血中へ吸収されていきます。つまり免疫系が過剰反応しないように食べ物を異物から自己にする働きがあります。しかし分解されずに腸の穴から吸収されてしまうと、免疫細胞は異物として認識して慢性炎症を引き起こします。
腸に無数の穴が開いてしまうのは、様々な原因が考えられていますが、その一つの原因としてグルテンが挙げられます。グルテンは水を吸うとネバネバとした粘着性を発揮し、これが腸の表面に薄く付着することで、腸の消化吸収を妨げます。すると消化されない異物が存在し続けるため、免疫システムが攻撃を始めます。結果、腸の粘膜において炎症が生じ、炎症が長引けば粘膜細胞で構成される腸壁に傷がつき、細胞同士の結合が緩んで粘膜細胞同士に隙間ができます。そして腸の穴から入り込んだ異物が、血流に乗って体中を巡り、様々な場所で炎症を起こします。その炎症が肩にあれば、肩こりになり、頭にあれば偏頭痛に、膝にあれば膝の関節痛などを引き起こします。
グルテンフリーの注意点
グルテンフリーを実践するにあたって、多くの人がつまずくポイントがあります。それはグルテンフリーを始めると体臭が気になってくることです。
ダイエットにも当てはまりますが、体内でブドウ糖が不足すると体は脂肪を燃焼させてエネルギーを得ようとします。この時に肝臓でケトン体という物質が作られ、ケトン体は水溶性のため血中に溶け出して汗と一緒に出ていきます。このケトン体代謝が起こると体臭となって現れることがあります。また、血液が多く集まる肺にもケトン体は溜まりやすく、肺から出るケトン体が口臭となることもあります。このような現象は、あくまで一時的なもので、体臭や口臭はグルテンフリーを始めてから3ヶ月から半年ほどで消えてなくなります。
グルテン過敏症
結論から言うと、グルテンが体に良くないのは人によります。グルテンを取ることによって便秘になったり、下痢になったり、肌荒れしたり、ニキビができたり、体の疲労感や倦怠感、落ち込みことがある方は注意しましょう。このような小麦アレルギーの方やセリアック病の方は摂ってはいけません。
一般的に、小麦アレルギーは500人に1人と言われ、小麦を摂取するとアレルギーの症状が出てしまいます。小麦アレルギーの方は、アレルギー検査をすれば分かります。またセリアック病はグルテンに対する遺伝性の不耐性です。グルテンを摂ると腸の粘膜に炎症が起きてしまうことで体調が悪くなったりします。セリアック病の方は欧米に多く、150人に1人ぐらいがセリアック病と言われています。日本人は比較的少なくて2000人に1人ぐらいと言われています。このセリアック病は内視鏡の検査、抗体検査によって分かります。
一方で、小麦アレルギーでもなく、セリアック病でもないのに、グルテンに対して過敏に反応してしまい体調が悪くなる人が、世の中にはいるのではないかということが最近言われています。このようなグルテン過敏症は、はっきりとした診断方法も確立していません。小麦アレルギーの即時型反応みたいに小麦 を摂取して、比較的短時間で体調が悪くなる、アレルギー症状が出るのではなく、グルテンを摂取して数日経ってからゆっくり症状が出てきたりします。
このグルテン過敏症の人はリーキーガット症候群を引き起こすって言われていて、グルテンを摂取すると、それが腸壁に着き腸の透過性が高まってしまって、腸の中の毒素とかが体内に吸収されて様々な不調が起こります。
海外の論文だと人口の0.5から13%ぐらいがグルテン過敏症ではないかと言われています。幅は広いですが、グルテン過敏症の方は、結構強い症状が出る人と軽い症状が出る人がおり、これだけ幅があることになっています。自分がグルテン過敏症なのかどうかを調べるのは、小麦を摂取するのを3週間から4週間くらい止めて、それですごく体調が良くなるのであれば、グルテン過敏症の可能性があります。
そもそも小麦は大昔から食べられていました。今になってグルテン過敏症が注目されていますが、グルテンフリーを推奨する人は、今の小麦は品種改良など重ねた結果、グルテンの量が多くなっているから、それが原因だと言う人もいます。そのため昔の小麦は大丈夫だったけど、今の小麦が危険だと指摘する方も多くいます。
しかし、完全にグルテンフリーにするのは難しいですし、その一方で極端に煽る人もいます。例えば炭水化物は体に悪いので完全に糖質オフをずっと続けることを推奨する人もいます。今では完全に糖質オフにすると、その分脂肪の摂取量がすごく多くなり、大腸ガンや悪性の腫瘍ができやすくなる、心臓とか血管性病変になりやすくなるなどの弊害があるというのが段々分かってきています。
他にも、カフェインや牛乳、アルコールを飲める人と飲めない人っていて飲めない人がいます。アルコールが体に悪いことは明らかになっていますし、カフェイン過敏症や乳糖不耐性などでお腹の調子悪くなる人もいます。このように様々な食材が合う人と合わない人がいますので、体の声を聞くようにして、他の意見や宣伝、広告に踊らされないことも大切です。
乳糖とカゼイン
牛乳が持つ栄養素が乳糖とカゼインです。乳糖に関しては、私たち日本人の多くは乳児期を過ぎると乳糖を消化できません。そのため消化不良になりやすい傾向があります。そして牛乳に含まれているタンパク質の80%を占めているのがカゼインで、特に牛乳に含まれているαカゼインは、私たち人間には消化できません。
結果としてグルテン同様、腸内に微小化物が多くなり腸の炎症を招きリーキーガットを引き起こしてしまいます。さらに消化できないためにアレルゲンとなり、遅延性のアレルギーの原因にもなります。
さらに消化できなかったカゼインからはガゾモルフィンという物質が生成さ れます。このガゾモルヒンは、グリアドルフィンと同様、麻薬物質と似た作用をもたらし、依存性を引き起こしてしまいます。
その他にも乳牛の餌に含まれている残留農薬や抗生剤の問題、さらには牛の成長を早めミルクをたくさん出させるためのホルモン注射の問題など数多くの危険性が指摘されています。そのためオーガニックやホルモンフリーの牛乳を試したり、オートミルクなどを選ぶようにしましょう。
食事と肌のトラブル(アトピー性皮膚炎など)
人口の1割ぐらいの人がアトピー性皮膚炎を持っていると言われています。その増悪因子として、生活習慣、ストレス、環境汚染物質、遺伝などが知られていますが、ある食品を摂ることによって悪化するということは歴史的にも知られています。
特に小麦や卵、乳製品などを食べるとアトピーが悪化するということが報告されています。しかし多くの医師や専門家は、食事を変えることに対する限界を感じている、もしくはその有効性に疑問を持っている方も多くいます。なぜなら食事介入しても全く変わらない人が一定割合おり、さらに極端な食事制限によって栄養不足になって、体調が悪くなることも起こり得ます。
特定の食品が必ずしも悪いというのが結論的には言えないのが現状ですが、10件の臨床試験の中の600人のデータをまとめた研究があります。この研究では、直接このアトピーの患者さん、それを介護している人方(親御さん)に対してインタビューし、実際に乳製品、卵、小麦を除去した食事をすることによってアトピーが改善した人が、約半分いたことが明らかになっています。逆に41%の方は薬だけで良くなることが報告されています。ただ薬だけでアトピーの状態が落ち着いているというのは、薬を使い続けるというのが前提になります。
だからこそ、食事で少しでも改善が図れるのであれば食事制限をするのも手です。その場合、血液検査でアレルギー物質を特定することもありますが、実際は検査で陰性であったとしても腸に炎症を起こしていることがあります。そのため検査ベースでやるのではなく、食事を1ヶ月単位で見直しながら、身体の状態を診ていくことが必要になります。
例えば小麦粉、卵、乳製品などの中から、一つ決めて1ヶ月間は絶対食べないようにして、その後にあえて食べてみて肌の状態を確認して、症状が悪くなるのであれば絶対に避けるべき食品であると考えられます。少しずつチェックしていくことで、アトピー性皮膚炎が改善した人も多くいらっしゃいます。
もちろん、全員が食事介入しても改善しないということは明らかですが、普段食事に気をつけていない方は、ぜひ一度チャレンジして、1ヶ月単位で食事をコントロールしてみて下さい。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。