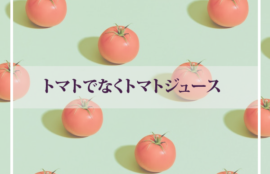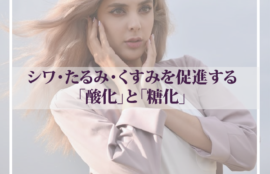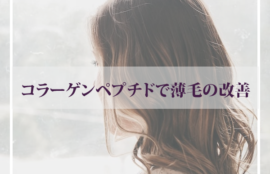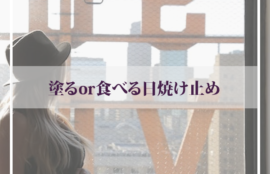近年、ダイエットに関する変化が起こっています。これまでは低炭水化物ダイエットや低糖質ダイエットなど、主栄養素の量を減らすことに主眼が置かれていました。それに対して主栄養素の質に注目した研究がスタンフォード大学で発表されています。
ダイエット方法が変化している
この研究では、低炭水化物食グループと低糖質食グループに分けて12ヶ月後の体重の変化を調査しました。両グループには栄養士が参加し、参加者は超加工食品を避け、未加工または最小限に加工された健康的な食品を自宅で調理するように指導されました。
低脂肪食グループでは、玄米、大麦、オート麦、豆類、脂肪を除いた赤肉、低脂肪の乳製品、新鮮な果物、マメ科植物を摂取し、低炭水化物食グループでは、オリーブ油、サーモン、アボガド、チーズ、野菜、ナッツと種子などの栄養化の高いものが中心に摂取されました。興味深いのは被験者は、好きなだけカロリーを気にせずに食べて良いことになっていたことです。
結果は、両グループ共に平均5kg以上の体重減少、体脂肪率とウエストサイズの減少も示し、1日のエネルギー摂取量が平均500kcalも減少していました。つまり研究では、健康的な炭水化物や脂質という「良質な主栄養素」の摂取がエネルギー摂取量を自然と減らし、体重減少に寄与したことを示唆しています。
これまでのダイエットでは食事量を減らすことにより、エネルギー摂取量を減らし、体重を減らすことが手法でした。しかし良質な栄養素を含む食品であれば好きなだけ摂取しても、結果的にエネルギー摂取量を減らすことができる「新たなダイエット手法」が注目されています。
肥満と老化
体内の炎症レベルを高めてしまう状態が肥満です。肥満は全身の脂肪細胞が慢性的な炎症物質を分泌することから炎症レベルが高い状態になっています。つまり肥満な人ほど全身が炎症に陥っていて、老化しやすいということが明らかになっています。
因みに、痩せている人より太っている人の方がむしろ若く見えることが多いのは、皮膚が引っ張られシワが目立ちにくいことが挙げられます。つまり実際に体が健康で老化を抑制できているわけではなく、単にシワが伸びているから若く見えることになります。基本的には、痩せている方が体内の炎症レベルは低く、それだけ老化が進みにくいことが言えます。
老化を栄養で食い止める
特に摂りたい栄養素がタンパク質、ミネラル、抗酸化物質の3つです。例えばタンパク質は、あらゆる細胞や物質の材料になります。そして亜鉛やカルシウム、マグネシウムといったミネラル、体の酸化を防ぐ抗酸化物質ビタミンも重要です。
例えばタンパク質であれば、厚生労働省の日本人の食事摂取基準によると体重1kgあたり1日に1.0g以上のタンパク質を摂取することが好ましいとされています。つまり体重が 60キロの人であれば1日に60g以上のタンパク質を摂取するのが好ましいですが、これがなかなか難しいです。
例えばタンパク質が豊富に含まれている代表である肉類は、100gあたりのタンパク質含有量は20g程度、豆腐であれば100gあたりのタンパク質含有量は5g程度であり、60gのタンパク質を摂ろうと思うと肉類であれば毎日300g、豆腐であれば1200g食べなければいけません。かなり意識しなければ1日に必要なたんぱく質量を確保するというのはなかなか難しく、意識していない人は全ての人がタンパク質不足に陥ってしまっていると言っても過言ではないでしょう。
食欲を抑えるタンパク質
実はタンパク質の摂取量によって食欲の増減が変わるということが分かっています。1日に必要な十分な量のタンパク質を摂取することができれば、食欲は自然と収まっていきます。逆にタンパク質の摂取量が足りていないと自然と脳はタンパク質を求めてタンパク質が含まれていそうな旨味成分や脂身成分、塩分が多い食材、つまり加工食品が食べたいという状態になってしまいます。
タンパク質の摂取量目安はだいたい体重×1gと言われています。もちろん年齢や性別、体脂肪率などによって変わってきますが、基本的には体重×1gは最低限摂取するようにしましょう。ただ大切なのは、タンパク質の摂取自体が体に良いわけではないことです。食欲センサーを働かせる上で、タンパク質をしっかりと摂取するというは重要ですが、実際健康長寿の人というのは良質な炭水化物を豊富に摂取し、その上である程度の量のタンパク質を摂取するという生活を続けていた方が多いです。
糖質の摂取などは悪者にされがちですが、精製されていない炭水化物や野菜、根菜、果物から摂取する糖質はそれほど悪いものではありません。あらゆるものに言えることですが過剰な量を摂取することは健康に悪いことになるため、タンパク質も食べれば食べるだけ良いというわけではなく、あくまで自分の食欲の範囲内で食べたいなと思える量を食べるようにしましょう。
このようにタンパク質の摂取一つとっても、ただ単純に成分を見ているだけではうまくいかず、タンパク質の摂取量を満たしつつさらに、それを天然の食材から摂る、そして自分自身の食欲センサーに従って、これ以上摂れないと思っ たなら、そこで止める、こういった自分の本能に従った食事が大切です。
これはサプリメントなどにも同様なことが言え、本来の食欲センサーから外れた場所で過剰に栄養を取るということは必ずしも良いことではありません。自分自身が求めている栄養分とは違った量の栄養分が体に入ってきてしまうからです。本来、栄養素というのは全て食事でまかなえるものであり、サプリメントとは食事で栄養素が十分に取れているのであれば必要になりません。
炭水化物と脂質
炭水化物や脂質には痩せるものと太るものがあることが分かってきました。まず痩せる炭水化物は、含まれる「食物繊維の量」が大事で、代表が玄米や全粒粉などの茶色い炭水化物です。
2015年にハーバード大学で発表された調査結果によると、野菜と果物の摂取量と体重の増減の関連について13万3468名の男女を対象に24年間に及ぶ大規模な調査が行われ、野菜や果物の各品目の体重の減少効果の関係が発表されています。
ここから野菜には太る野菜と痩せる野菜があり、最も痩せる野菜は大豆で、その他はブロッコリーやカニフラワーなどのアブラナ科の野菜、ピーマン、芽キャベツ、ほうれん草などの緑色の葉野菜に高い減量効果がありました。一方でジャガイモ、さつまいも、とうもろこしには増量効果が確認されています。
特に大豆に含まれる食物繊維には、満腹感を高め、腸での糖質や脂質の吸収を遅らせて腸内環境を整え、腸内細菌の活動を促すなど、肥満を防ぐ多くの作用があります。さらに含まれるイソフラボンには、脂質の生成を抑制し、脂質の蓄積を減らし、肥満の要因となるインスリン抵抗性を改善する効果があります。
果物には増量効果が認められたものがなく、ブルーベリーやプルーン、いちごなどのベリー系の果物、りんご、グレープフルーツには、食物繊維とともにフラボノイドが豊富に含まれ、いずれも高い減量効果があることが分かっています。このフラボノイドの摂取がエネルギー摂取量を減少させるとともに、筋肉のグルコースの取り込みを増加させることが報告されています。
続いて太る脂質の代表がトランス脂肪酸と飽和脂肪酸です。超加工食品や加工肉に多くふくまれています。一方でオリーブオイルは、最も痩せる脂質であるαリノレン酸を多く含み、熱にも強いため調理油として最適です。またエゴマ油や亜麻仁油をスプーン一杯程度を食材に加えることもおすすめです。
最後がタンパク質で、痩せるタンパク質の代表が鶏肉、ヨーグルト、プロテインです。特にホエイプロテインの摂取によって食物促進ホルモンであるグレリンの分泌が抑えられ、食物抑制ホルモンであるコレシストキニンの分泌が促進させることが示されています。
食欲を刺激する食物繊維
タンパク質と同様に食欲センサーを強烈に刺激するのが食物繊維です。タンパク質と食物繊維をしっかりと摂取することによって食欲センサーを刺激して適度な量で満腹中枢に刺激がいき、お腹いっぱいとなって食事を止めることが できます。食事の中にしっかりと大量の野菜や全粒穀物などを組み込むことによって、食物繊維の量さえ摂取していれば食事は腹八分目程度で止まります。
逆にタンパク質と食物繊維が足りていないから腹八分では満足できず、腹12分目と進んでいってしまいます。ここに意志力は関係ありません。十分量の食物繊維とタンパク質を含んだ食事を食べている限り、意志力を使わなくてもしっかりと腹八分目でやめることができます。
睡眠と食欲
睡眠は食欲に大きく関係することが明らかになっています。睡眠時間が足りていないと食欲が増してしまい、食べ過ぎてしまうことが起こり得ます。そのため食習慣を変えようと思うのではなく、まずは睡眠習慣を正すことの方が大切だったりします。ついつい夜食を食べ過ぎてしまった経験があると思いますが、これも寝不足によるホルモンが原因です。
同様に運動習慣も大切です。運動習慣も睡眠ほどではないですが食欲に影響を 与える生活習慣の一つです。運動や睡眠といった生活習慣は、体内のホルモンバランスに影響を与えます。そして食欲は、ホルモンの影響を強く受け、結果として悪い生活習慣が食欲の暴走につながってしまいます。
脂肪を減らすための食べ方
厳しい食事制限はむしろ健康を害してしまうこともあります。過剰な食事制限によって、エネルギー源である糖質や脂質が不足するため、筋肉や内臓に含まれるタンパク質を分解してエネルギーを得ようとします。このような方法ではなく、健康的に美しくなるためには、緩くても効果が出る安全な方法があります。
調理法
脂肪とカロリーを減らすためには、揚げるよりも焼く、焼くよりも煮る・蒸すです。つまり揚げる→焼く→煮る→蒸すの順で脂肪とカロリーが小さくなり、つまり同じ食材でも調理法によって脂肪とカロリーが変化するのです。
例えば、もも肉を油で揚げると、衣が油を吸ってもともとの肉のカロリーと脂質に油が上乗せされます。一方で焼くや蒸すは調理中に肉に含まれる脂肪が溶け、肉汁として外に出ていくため調理前よりもカロリーや脂質が少なくなります。
青魚
青魚の代表は鯖やイワシといった背中が青い魚です。青魚に含まれるDHAやEPAは体脂肪の増加を抑える効果があることが分かっています。これらは不飽和脂肪酸の一種であり、摂取することで体内に溜まった中性脂肪を減少させ、さらに内臓脂肪を付き難くすることができると言われています。他にも心臓病や脳卒中、糖尿病や癌、認知症の予防にも役立ちます。缶詰の魚でも同じ効果があります。
高野豆腐
高野豆腐は豆腐を冷凍して低温熟成した後、解凍して乾燥させた保存食品です。栄養成分が凝縮されており、タンパク質や脂質(不飽和脂肪酸)が多く含まれています。また白米や麺類などの主食と比べて糖質量も圧倒的に少ないです。高野豆腐にはΒコングリシニンが多く含まれており、これが内臓脂肪を燃焼させ、血液中の中性脂肪を抑える効果が分かっています。さらに脂肪細胞から分泌される善玉物質であるアディポネクチンが増えて内臓脂肪が燃焼されやすくなります。さらに含まれるレジスタントタンパクが肝臓での中性脂肪の合成を抑え、血液中の中性脂肪の上昇を抑える作用もあります。
つまり、高野豆腐は健康にもダイエットにも非常に効果が高いスーパーフードなので積極的に食べてください。
ギリシャヨーグルト
ギリシャヨーグルトは製造過程で水切りという特殊な工程を含んでいます。布や濾過器を使ってヨーグルトから水分と乳製を分離、除去してあります。このろ過プロセスによってギリシャヨーグルトは通常のヨーグルトとは異なり、濃厚でクリーミーな食感だけでなく、このように少し作られ方が違うため、普通のヨーグルトに比べてタンパク質が豊富に含まれ、栄養素が濃縮された低カロリーの食べ物です。
また、高タンパク質のギリシャヨーグルトは脂肪の減少を促進し、ダイエット中でも筋肉の衰えを防いでくれるということが分かっています。ギリシャヨーグルトには共役リノール酸が含まれていて、大規模な研究によれば太りすぎや肥満の人の体重減少や脂肪燃焼を促進してくれるということが分かっています。さらにギリシャヨーグルトには健康的な脂肪が含まれており、これら脂肪はエネルギー源として利用されるだけでなく、満腹感を高める役割も果たしてくれます。
さらに、ギリシャヨーグルトには善玉菌として知られるプロバイオティクスが含まれています。これらの善玉菌は腸内環境を整え、免疫力を向上させる効果があります。腸内環境が整うことによって消化吸収が効率的になり体重管理に役立つとされています。またギリシャヨーグルトにはカルシウムが豊富に含まれおり、骨や歯の健康を維持するだけでなく、脂肪細胞の働きを抑える役割もあり、体脂肪の蓄積を防いでくれることに寄与するとされています。
ただし、市販のギリシャヨーグルトには砂糖が加えられていたりするため、ダイエット効果や健康効果を期待するのであれば、砂糖が加えられていない無糖タイプのもの選んでください。
MCTオイル
MCTオイルとは中鎖脂肪酸(MCT)を豊富に含むオイルであり、中鎖脂肪酸は一般的な油に含まれている脂肪酸とは異なる代謝経路を持っています。中鎖脂肪酸は腸管から肝臓に運ばれて、肝臓で速やかに代謝されエネルギーに変換されます。このため中鎖脂肪酸は脂肪として蓄積されにくい性質を持っています。つまりMCTオイルは体内で速やかに燃えてエネルギーを供給してくれるため、糖質制限をしている際のエネルギー補給としてダイエットで重宝されています。
また、MCTオイルは肝臓で速やかにケトン体という物質に変換され、ケトン体がエネルギー源として利用されるケトーシス状態に導くことができます。ケトーシス状態では、体は脂肪をエネルギー源として利用しやすくなり、結果として脂肪の燃焼が促進されます。そしてケトン体は中枢神経に作用し、満腹感を促すということが報告されており、MCTオイルは食欲抑制効果が期待でき、間接的に食事量やカロリー摂取を減らすことができます。実際にもMCTオイルは体内の満腹感を促進してくれるホルモンであるペプチドYYとレプチンの放出を増加させるということが研究によって示されています。
ある研究では朝食の一部として大さじ2杯のMCTオイルを摂取した人はココナッツオイルを摂取した人と比べて、昼食の食事量が少なくなったという結果があります。また同じ研究でMCTオイルを摂取した場合、中性脂肪やブドウ糖の上昇が少ないということも判明しており、これが満腹感にも影響していると考えられます。
さらに、MCTオイルの摂取は熱酸性効果を高めるということも報告されています。これはエネルギー消費が増加し、脂肪燃焼が促進されているということを意味しており、実際に研究でもMCTオイルを摂取することによって体重やウエスト周囲の脂肪を減らすことができると示されています。
余談ですが、MCT オイルにはこれら以外にも様々な健康効果があることが分かっています。例えばMCTオイルが脳機能の向上に役立つ可能性が指摘されています。アルツハイマー病の患者では、脳がグルコースを効率的にエネルギーとして利用できなくなってしまうということが報告されており、MCTオイルによって生成されるケトン体が、グルコースの代替エネルギー源として利用され、脳機能の改善が期待できます。またいくつかの研究でMCTオイルを摂取することでアルツハイマー病患者の認知機能の一部が改善される可能性が示されております。
また、MCTオイルによって作られるケトン体は、糖質が不足した際に脳のエネルギー源として利用され、かつケトン体の生成が促されることでアルツハイマー病などの神経疾患の予防や改善に効果があります。
一方で、慢性疲労にもMCTオイルが役立つ可能性があります。繰り返しますがMCTオイルは、速やかに代謝されてエネルギーを供給してくれるため、短期間でエネルギー不足を補うことが でき、疲れにくくなる可能性があります。MCTオイルから作られるケトン体は、糖質が不足した際にエネルギー源として利用されるため、脳や筋肉などのエネルギーを必要としている組織に対して持続的にエネルギーを供給してくれます。このために疲れにくくなる可能性があり、MCTオイルを摂取することによって運動中に疲れにくくなる、あるいは運動後の疲労回復が早くなるという研究があります。
リンゴ酢
リンゴ酢(アップルサイダービネガー)には様々な健康上のメリットが報告されています。特にお酢を飲むと痩せるという話を聞いたことがあるかも知れません。実際に酢は様々な形でダイエットに役立ってくれ、例えば酢を摂取することによって食欲が抑えられるという効果が得られることがいくつかの研究で示されています。これはリンゴ酢の主成分のアセト酢酸が糖質の吸収を遅らせることによって、血糖値の急激な上昇を抑える効果があるためです。血糖値が安定することによって、食欲を抑えやすくなると言われています。またリンゴ酢に含まれるアセト酢酸が、脂肪が蓄積するのを抑えてくれるという可能性が指摘されております
さらにリンゴ酢は代謝を向上させる効果があるといくつかの研究で示されており、エネルギー消費が増加しダイエット効果を期待することができます。またリンゴ酢は膨満感を高めることで私たちが摂取するカロリーや食事量を減らしてくれると言われています。この膨満感に加え、食べ物が胃から出る速度を遅くしてくれるということも分かっています。例えばデンプン質の食事と一緒にリンゴ酢を摂取することによって、胃が空になるのが大幅に遅くなり、その結果満腹感が増し、血糖値とインスリンレベルが低下することが示されています。さらに食事にリンゴ酢を大さじ1杯または2 杯加えると体重を減らすのに役立ち、体脂肪率を下げてお腹の脂肪を減らし、血中トリグリセリドを減らすことができるという研究もあります。
これらの効果を示す研究では、144人の肥満の日本人成人を対象に12週間に渡って行われたものがあります。参加した人たちは3つのグループに分けられ、毎日大さじ1杯15mlの酢を飲んでもらったグループ、毎日大さじ2杯30mlの酢を飲んでもらったグループ、プラセボ飲料を飲んでもらったグループに分け、そして彼らにはこの研究の間いつも通りの食事と活動を続けてもらいました。ただしアルコールだけは制限しています。つまりアルコールだけは制限したが、別に食事の内容を健康的なものに変えるとか、激しく運動するとかそういったライフスタイルを変えずに単純に酢だけをいつもの生活に加えるとどうなるかを調べました。
その結果、1日に大さじ1杯15mlの酢を摂取した人は体重が1.2kg減り、体脂肪は0.7% 減、胴囲が1.4cm 減少、トリグリセリドが26%減少したということが分かりました。そして、さらに1日あたり大さじ2杯30mlの酢を飲んでもらったグループは、体重が1.7kgも減り、体脂肪が0.9%減、胴囲が1.9cm 減少、トリグリセリドが26%減ったということが分かりました。一方で酢を全く飲んでいないプラセボグループは、この期間中に体重が0.4キロを増加し、胴囲はわずかに増加しました。
この実験の結果からも酢を飲むということにはダイエット効果があると言えそうです。そして大さじ1杯の人よりも大さじ2杯の人の方が効果高かったということもこの研究から分かります。さらに酢の有名な効果ですが、血糖値を下げ、糖尿病を予防してくれる効果があると言われています。酢はインスリン感受性を改善し、食後の血糖反応を低下させるのに役立つということが分かっています。
チリパウダーチキン
チリパウダーと鶏胸肉には、それぞれ科学的に 脂肪や体重を落としてくれる効果が認められています。鶏胸肉は、低カロリーで高タンパク質な食品であるため、ダイエット中に適した食材です。高タンパク質は、筋肉の修復や成長を助けてくれる役割があります。痩せるためにはしっかりと筋肉を付けることが重要と言うのは存知かと思います。
筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、エネルギー消費量が増加します。これによって脂肪の燃焼が促進され痩せやすい体質になります。さらにタンパク質が豊富な食べ物を食べることで食欲をコントロールすることができます。例えばタンパク質は炭水化物や脂質に比べて消化が遅いため、胃や腸で長く留まります。これによって満腹感が持続し、食欲が抑えられます。
さらにタンパク質を摂取することによって、ペプチドYY、GLP-1などの物質が分泌されることが分かっています。これらの物質は食欲を調節する役割があって満腹中枢を刺激して食欲を抑えてくれるという効果があります。またタンパク質は血糖値の上昇を緩かにするためのインスリンの分泌が安定化します。インスリンが安定することによって血糖値の急激な上下が抑えられ、空腹感や食欲の増加を抑制してくれます。またタンパク質を摂取すれば、膵臓からグルカゴンが分泌されます。グルカゴンは、インスリンとは逆の働きをし、脂肪細胞から脂肪を分解し、エネルギーとして利用することで空腹感を抑える効果があります。
さらに、タンパク質はレプチンとアディポネクチンというホルモンの分泌を促してくれます。これらのホルモンは脂肪組織から分泌され食欲を抑制し、エネルギー消費を促進する働きがあります。
もう一方のダイエット効果が認められているチリペッパーは、唐辛子とも呼ばれています。チリペッパーには様々な種類があり、それぞれ辛さや形状、色などが微妙に異なります。チリペッパーの辛さは、カプサイシンという化学成分によるものです。カプサイシンは熱産生作用や食欲抑制効果、抗酸化作用など健康に良い効果があるとされています。ただし過剰摂取は胃腸への負担や健康に悪影響を及ぼす可能性もあるため、適量摂取することが重要です。
チリペッパーに含まれるカプサイシンという成分は、体内で熱を産生する作用があり、この熱産生効果によって代謝が促進され、エネルギー消費が増加します。その結果、脂肪の燃焼が促進されることによってダイエットに効果的であるとされています。またカプサイシンは胃腸の働きを活発にし、消化を促進するだけでなく、脳内で満腹信号を増強する作用があり、食事の量が自然と減ることでカロリー摂取量を抑えることができます。
また、研究ではカプサイシンがインスリン受性を向上させ血糖値を安定させる作用があるということも示されています。血糖値が安定してくれればエネルギーの消費や貯蔵が適切に行われ、体重管理に役立ちます。さらにカプサイシンは、腸における脂肪の吸収を抑制する働きがあります。これによって摂取した脂肪が体内に蓄積されにくくなり、ダイエットに効果的となります。
ダイエットのためには肝臓を労わる
日本人成人の3人に1人が脂肪肝であると言われています。肝臓は末期状態で機能がかなり低下してからようやく症状が出始めます。このように肝臓は機能が低下しても自覚できないため「沈黙の臓器」とも言われています。脂肪肝は肝臓全体の60%以上が脂肪化した状態でも症状が全く出ません。
肝臓の機能は代謝、解毒、免疫機能です。代謝は栄養素を体が利用しやすいように分解し、合成する働きのことです。肝臓に運ばれた栄養素は生命維持のための必要な物質に作り変えられます。また食べていない時には、貯めた栄養(脂肪)をブドウ糖に変えて、細胞のエネルギー源にしているのも肝臓の大切な働き(糖新生)です。肝臓の機能が低下すると脂肪をブドウ糖に変えることができません。つまり脂肪をエネルギーに変換することができないため、体に必要なエネルギーを食事から摂らざる得ないため、空腹感が強く生じてしまいます。
解毒には、代謝の過程で生まれた有害物質を毒性の低い物質に変えて尿や胆汁の中に排出する機能です。この肝臓の機能が低下すると有害な物質を処理できなくなり、全身に巡って様々な不調を引き起こします。
そして免疫は、身体に入ってきた異物を食べてしまう免疫細胞の80%は肝臓内に存在しています。肝機能が弱まればウィルスなどの外部からの感染に弱くなります。
「脂肪肝」は肝細胞内に脂肪が溜まることですが、この脂肪によって代謝、解毒、免疫を始めと様々な機能が低下します。脂肪がつく原因は、食事(お肉や脂身)で付く割合は15%程度、肝臓で作られた糖質由来の脂肪が25%、最も多いのが皮下脂肪や内臓脂肪で60%を占めています。つまり糖質のもととなるご飯やパン、麺類などの炭水化物の方が脂身よりも2倍のインパクトがあります。特に注意しないといけないのが、脂肪肝が進行して初めて脂肪肝炎(肝臓の炎症)になるのではなく、脂肪肝が軽度の状態でも肝炎になる可能性があることです。
肝臓に脂肪が溜まる理由は、入ってくる脂肪と出て行く脂肪がイコールではないことです。そのため食べ物由来の糖や脂肪、特に糖のもととのなる炭水化物の摂取量を減らすこと、溶けて肝臓に流れ込む皮下脂肪や内臓脂肪を減らすこと、肝細胞の機能に悪さを働く毒を減らすことです。つまり食べるものを気おつけ食事制限と運動で身体の脂肪を落としましょうということです。
東洋医学で診る「二の腕が太くなる理由」
東洋医学では人体をエネルギーが流れる経絡や陰陽五行の理論などを用いて理解し、体内のバランスの乱れが健康問題を引き起こすと考えます。二の腕が太くなる場合、特定の経絡において気の滞りが生じている可能性があります。特に腕には心経、小腸経、肺経、大腸経など複数の経絡が通っており、これらの経絡のバランスが崩れると二の腕に影響が出るとされます。
一方で東洋医学では血の流れも重要な要素で、血の不足や停滞は体内の栄養素や酸素の運搬に影響を及ぼし、結果として脂肪がつきやすい体質につながると考えられます。二の腕が太くなるのもこの血の流れがスムーズでないことによる部分 的な影響とされます。
また東洋医学では、脾は消化吸収を司り、体内の「湿」を制御する重要な役割を担っています。脾の機能が低下すると 体内に「湿」が溜まりやすくなり、これが脂肪として体に蓄積される原因となります。二の腕が太くなることもこの水分と脂肪の蓄積と関連付けられることがあります。全身の気の流れを良くするには、失眠、足三里、関元、中院、合谷のツボが挙げられます。
美容鍼で体重コントロール
太りにくい身体をキープするために美容鍼は効果的です。なぜなら鍼によって身体にアプローチすることで、基礎代謝を上げて脂肪が燃えやすい身体に改善することができるからです。例えば、おなかや足などのツボに鍼でアプローチし、内臓の働きや新陳代謝を高め、老廃物や水分の排出を促進させて代謝機能を改善します。
その他にも、耳には食欲を抑制するツボ、腕には自律神経の乱れを整えて過剰な食欲を抑制するツボがあります。また、自律神経のアンバランスで睡眠不足にならないように、鍼治療によって『副交感神経』と『交感神経』の活動のバランスを調整することができます。
鍼で体重コントロールすることは、心身への負担やストレスが少なく、健康的な状態を維持しながらキレイになることができます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。