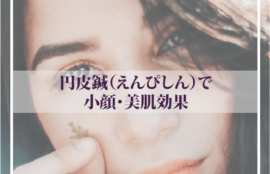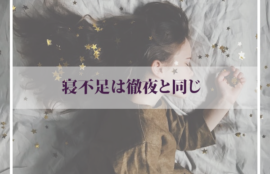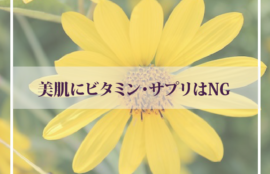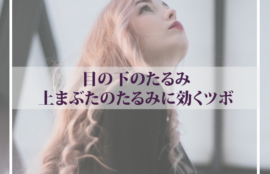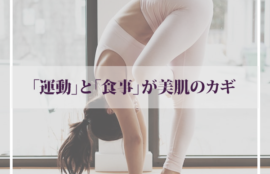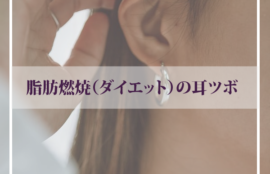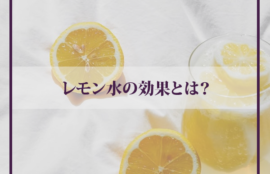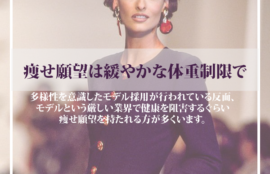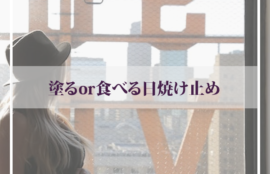筋肉量が私たちの寿命や健康寿命に非常に大きな影響を与えます。実際に、筋肉量が寿命や健康寿命に影響を与えることは、複数の研究によって示されています。筋肉の低下は加齢とともに進行し、筋力が低下し、衰弱してしまった状態をサルコペニアと呼びます。
サルコペニアは、身体機能の低下、転倒や骨折のリスクの増加、そして最終的には死亡リスクの増加につながります。2018年の研究では、筋肉量が多いことが全死因リスクの低下と関連していることが示されています。また2014年の研究でも、筋力の低下やサルコペニアが死亡リスクを増加させると結論付けられています。また別の研究では、筋肉量と骨密度が高い女性が最も低い死亡リスクを示していたことも分かっています。これは筋肉量をしっかりと高くキープしておくことによって生存率が高まる可能性を示唆しています。
また、がんは日本人の死亡要因の第 1位で、2人に1人以上ががんになってしまうのが現実です。さらに2015年から2039年にかけて、がんになる人が増加すると予想されています。日本のがんの死亡者数はここ30年で2倍に増加していることも分かっています。
しかしがんの予防に関しての知見は、格段の進歩を遂げており、がんは高血圧や糖尿病と同じく生活習慣病の一つとみなされるようなってきました。その予防方法が体の慢性炎症を抑えることであるとの結論が出ています。そして慢性炎症を抑えるためには、環境要因や生活習慣を変えることが必要です。これらによって90%のがんは予防できるという見解になっています。
筋トレなどの定期的な運動
改善すべき生活習慣の一つが運動です。定期的な運動ががんを予防してくれることは以前の調査からも明らかになっていました。しかし、まだがんにかかっていない人に、がん予防のために運動しましょうとアドバイスしても、始められる方はまだまだ少ないです。
そして運動の中でも、特に筋トレががん予防に絶大な効果を発揮すると考えられています。筋トレの重要性に関する知見の集積の高まりは、ここ20年余りで 腸内環境が健康の鍵であると認識されるのと同じく、加速度的に進んでいます。
実は私たちの体の中には、毎日5000から1万個のがん細胞が現れていますが、それでもがんにならないのは免疫細胞がそのがん細胞をきちんと退治するからです。逆にがん細胞が免疫細胞の網の目をかいくぐって増殖したのであれば、10年から20年の間に免疫機能が低下している状態が続いていたことになります。つまり長期にそのような状態を放置しない限り、目に見える形のがんになるまでには中々進行せず、がんにならないということはそれほど難しいことではないのです。
例えば、免疫細胞を成長させ、十分な機能を発揮させるための栄養素としてビタミンC、ビタミンD、亜鉛、セレン、鉄、タンパク質などが必要です。一方で、これらの栄養素が不足するような食事が長期間続いてしまうと免疫力は当然のことながら低下し、さらに慢性のストレス、運動不足、睡眠不足などでも免疫力を落とします。
また体内の炎症を放っておくとがんになるリスクが上がることに加え、老化スピードが加速する、あらゆる病気のリスクが上がる、メンタルや脳の老化が起こる、謎の体調不良が発生、など私たちの体調不良や健康上の悩みのほとんどがこの炎症によって引き起こされています。
これらの生活習慣を改善することに努めれば、がんは予防可能な疾患であると 全米一の患者数を治療するがんセンターのUniversity of Texas MD Anderson Cancer Centerの論文にも記載されています。
そして、筋トレにがん予防効果があると考えられています。実際に約8万人を平均9.2年経過観察して、運動と死亡率の関係を見た研究によると、筋トレをした人たちはがん死亡率の優位な低下が認められています。ちなみに有酸素運動のみの人は癌死亡率の低下は認められませんでした。このことからがんを予防するという観点から言えば、有酸素運動よりも筋トレの方が効果的であると言えるでしょう。
なぜ筋トレががん予防につながるかは、がんは体の中で慢性炎症が持続することによって発生するため、筋トレによって全身の慢性炎症が改善するためです。筋トレで筋肉からマイオカインと呼ばれる物質が放出されます。この物質には炎症を抑える物質が含まれているため、筋トレを繰り返すことによって全身の炎症が改善していきます。
このマイオカインに炎症を抑えてくれる効果があると報告されたのは2004年であり、その後も研究が進み、現在までにマイオカインは600個以上発見されています。さらにマイオカインの一つであるイリシンという物質には、抗がん効果があることが期待されています。
また、筋トレによって筋肉を積極的に動かすと、全身にリンパ液がスムーズに流れて、リンパ液の中に存在している免疫細胞が急速に私たちの体内を駆け巡り、がん細胞がいないかどうかのパトロールが行われるようになります。
さらに、筋肉は免疫細胞に常に働きかけ、免疫細胞と会話をしているということも分かっています。筋トレで分泌されるマイオカインは、筋トレによって小さなダメージを受けた筋肉組織の修復を促すようにと免疫細胞にメッセージを送ります。そして筋肉細胞から放出されるマイオカインで最も多い物質は、インターロイキン6と呼ばれるものです。これは運動強度に比例して分泌量が増加し、炎症を抑えるサイトカインの産生を高めてくれます。その結果インターロイキン6は、筋肉を修復しながら内臓脂肪を減らす作用も発揮し、慢性炎症を抑える炎症効果を倍増させてくれる効果をもたらします。そして現在では、筋肉によって誘導されるインターロイキン6の抗炎症効果は、がんの進行を遅らせる効果も期待されています。
一方で、加齢とともに私たちの筋肉は加速度的に失われていき、筋肉の低下は早くも30代から始まります。そして筋トレなどをしなかった場合は、平均年間250gずつ筋肉を失っていきます。さらに50歳を超えて筋肉を維持するための運動をしていない場合は、身体的な衰えは著しくなります。
また筋トレをやるタイミングは、朝空腹時がベストです。なぜなら朝空腹時に筋トレすると成長ホルモンの分泌が最も刺激されやすいと言われています。成長ホルモンは、脂肪燃焼を促進してくれたり炎症を抑えてくれたり、細胞のダメージを修復してくれたり、体の疲れを取ってくれる働きがあります。
腸内細菌の重要性
腸内細菌とは、人の消化管に生息する多種多様な微生物の総称です。私たちが食べたものを消化するのを助けるだけでなく、免疫力や健康にも影響します。腸内細菌の総数は約100兆から1000兆個にも及び、人体の全細胞数を上回るほどの数です。腸内細菌は研究されていない部分が多くありますが、私たち の体にとって重要な役割を担っており、例えばアミノ酸や食物繊維などを原料として、ビタミンB群やビタミンKなどの物質を生成します。
このように腸内細菌は私たちが食べたものから必要な栄養素を作り出すことができ、これにより主要なビタミンの不足から守られています。また栄養素の吸収を促進したり、食物繊維を分解してエネルギーに変換したり、脂肪酸を作って腸壁を保護したりとその働きは多岐にわたります。
また東洋医学では、へその下に位置する臍下丹田(せいかたんでん)を生命エネルギーの源泉として重要視してきました。さらに医学の父ヒポクラテスもすべての病は腸から始まるという言葉を残しています。
一方で、腸内細菌の重要な役割に、体に悪影響を及ぼす細菌やウイルスなどとの戦いが挙げられます。腸は食べ物から栄養を吸収する器官ですが、胃から肛門まで続く長い構造であり、細菌やウイルスなどの侵略者に対抗する要塞でもあります。腸は生命を維持するために必要な栄養を体内に取り込む一方で、有害な物質が体内に侵入するのを阻止する役割を担っています。
このような状況で腸内細菌である善玉菌が腸内に広大なコロニーを築きます。このコロニーには同じ種類の微生物が集まり、栄養素を原料にバクテリアなどを駆逐する抗菌物質や酵素などを製造し、腸壁からの侵入を防御します。さらに腸内細菌は、食物繊維から酪酸という脂肪酸を生成し、有害物質が体内に浸透するのを抑制します。
食物繊維は、人間の消化酵素では分解できない植物性の成分のことで野菜や果物などに多く含まれます。酪酸は短鎖脂肪酸の一種で、腸壁の細胞にエネルギーを供給したり、炎症を抑えたりする働きがあります。
腸内環境を改善
最新の疫学研究によって腸内環境を改善し、自己免疫を高く保つことによってがんの発症を防ぐことができることが分かってきています。
私たちの体の中では日々多くのがん細胞が出現し、これががん化するには10年以上の期間を必要とするため、免疫力を高く維持できていればがん細胞は駆逐され、がんの発症を防ぐことができます。つまり長期にわたり自分の免疫力が 低下していたのを放置してしまっていたというサインでもあります。
そして免疫がうまく働かなくなる原因として、腸内環境があります。私たちの腸の中には体中の免疫細胞の70%が存在しており、腸こそが免疫の肝心要になります。当然腸の環境が乱れてしまえば、免疫力は低下、その結果がん細胞を排除することができずがんになってしまうことになります。
また腸内細菌は、腸の中の免疫だけではなく、全身の免疫系を適切な形で維持するためにも重要です。例えば腸内で悪玉菌が増加してしまうと、有害な物質を生み出し、免疫が過剰に反応して炎症を起こします。この炎症が持続的に起こっている状態ががんを生み出すということも研究によって分かってきています。
腸内環境を乱してしまう原因は多々ありますが、どのような食品を選ぶ習慣が あるのかという長期的な食生活の影響が、腸内細菌の組成に最も大きな影響を 与えます。仮に遺伝的にがんになりやすい腸内細菌を受け継いでいたとしても、日々の食生活にきちんと気をつけることによって、がんになるリスクを減らすことができます。そして食事によってがんを予防するといった時には2つのアプローチがあります。一つ目はがんのリスクを下げてくれる食材を食べること、二つ目はがんのリスクを上げる食材を避けるということです。
がんのリスクを下げてくれる食材
食生活を変えることによってがんのリスクは上がったり下がったりすることが 研究から分かっています。その中でがんを予防する食べ物があります。
野菜と果物
野菜や果物が健康に良いのは十分に分かっていると思いますが、がんを防ぐと いう観点から外せません。実際に研究結果からも、あらゆるがんの予防のために野菜や果物の消費を重視するという提言がなされています。
一方で野菜の平均摂取量は減少しているにも関わらず、サラダの消費量は年々増加し続けて1985年と比較してなんと2019年には3倍にもなっています。多くの人が、コンビニやスーパーで野菜をできるだけ摂取しようとサラダを買っています。
しかし、残念ながらこれらのサラダはカットされ滅菌された加工食品です。さらに添加物がたっぷり入ったドレッシングと一緒に食べると体にとってマイナスの影響の方が大きいでしょう。
健康を心掛けるのであれば、カットした野菜や冷凍の野菜、果物を使用するのではなく、生の野菜や果物をホールフードの状態から家庭で調理して摂取することを心がけなければいけません。
水溶性食物繊維
野菜と果物が健康に重要である最大の理由は食物繊維を摂ることができるからです。善玉菌などの有益な腸内細菌は食物繊維が好物であり、当然食物繊維が不足してしまえば餌がなくなり、善玉菌の量は減少します。その結果がんを防ぐためにとても重要な腸内環境が乱れることになります。
食物繊維には水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があります。不溶性食物繊維は、水に溶けない食物繊維であり、ごぼうやセロリなどの筋っぽい成分で腸内細菌を持ってしてもなかなか分解することができません。野菜に含まれているのは不溶性食物繊維がメインです。もちろん野菜を食べて不溶性食物繊維を摂取するのが重要であるというのは間違いありませんが、同時に不足しがちな水溶性食物繊維をしっかり意識して取るということも重要です。
実は腸内細菌がより喜ぶのは、水に溶ける水溶性食物繊維です。水溶性食物繊維は、海藻や里芋などのネバネバした成分です。データ的にも日本人は不溶性食物繊維よりも水溶性食物繊維の方が不足しがちであることが分かっています。
椎茸、えのきだけ、舞茸、なめこなどのキノコ類には、βグルカンと呼ばれる食物繊維が大量に含まれています。βグルカンは様々な薬効作用を持ち、免疫力を活性化し、がんや感染症から体を守る能力を向上させてくれる働きがあると知られています。例えば週に3回以上えのきだけやしめじを食べる人はほとんど食べない人と比較して、胃がんや大腸がんのリスクが減少するエビデンスもあり、がんの抑制や免疫力アップも期待できます。
一方の昆布、わかめ、ひじき、海苔などの海藻類には豊富な栄養素が含まれて、海藻を摂取することによって腸内細菌に良いとされる水溶性食物繊維を摂ることができます。その結果、腸内を整え、便秘予防や肌を美しく保つ効果もあります。また水溶性食物繊維は水分によって量が増えるため満腹感が得られやすく、かつ低カロリーで血糖値を抑える効果まであります。
ブロッコリー
ブロッコリーは、腎臓病や糖尿病などの慢性疾患の発症リスクを抑えつつ、さらにはがんのリスクも抑えてくれる素晴らしい食品です。ブロッコリーの健康効果の多くは含まれているスルフォラファンによると考えられています。
スルフォラファンは、ブロッコリーを始めカリフラワーやケール、芽キャベツなどを含むアブラナ科の野菜に多く含まれていることで知られています。このアブラナ科の野菜を刻んだり噛んだりすることで生成される天然由来の化合物のスルフォラファンには、抗炎症作用があることが分かっており、心臓病や糖尿病などの慢性疾患のリスク軽減に役立つと考えられています。
さらにフリーラジカルによるダメージから細胞を保護する抗酸化作用があります。この抗炎症作用も抗酸化作用もどちらも老化防止に役立つ重要な作用です。さらに解毒作用もあると言われており、体内の酵素を活性化し、有害な化合物を解毒して細胞を保護することが知られています。
そして、がんのリスク低減効果もあり、例えば試験管における実験ではスルフォラファンが乳がん細胞の大きさと数を最大75%減少させることが示されました。さらにある動物実験ではマウスにスルフォラファンを投与すると前立腺がん細胞を死滅させ、治療の体積を50%以上減少させることが分かりました。ただし人を対象とした実験では、スルフォラファンを抽出したサプリメントではそこまで効果がなく、むしろ害があることも示されている研究もあります。このことからも食品はサプリで摂るのではなく、ブロッコリーを食べることが大切です。
さらに調査を進めると、ブロッコリーをたくさん食べている人は大腸がんのリスクが低くなる可能性があることも分かってきています。大腸がんは日本人のがん死亡数が、男性で第3位、女性で第1位であり、男性は 27,098人、女性は 23,560人の方が大腸がんで亡くなっています。また男性はおよそ11人に1人、女性はおよそ13人に1人が一生のうちに大腸がんと診断されています。
豆類
この豆類も大腸がんのリスクを下げる食品です。ある研究では大腸腫瘍の既往歴のある1905人を追跡調査し、調理した乾燥豆を多く摂取した人は、腫瘍の再発リスクが低下する傾向があることが発見されました。
実際にがんなると食事の影響は小さくなりますが、そんな中でも再発リスクを低下させることができることは、非常に強力な効果だと言えます。また動物実験ではラットに豆類を与えた後に大腸がんを誘発させると、がん細胞の発生が最大で75%ブロックされることが分かりました。実は、なぜ豆類にここまでの大腸がん抑制効果があるのかは分かっていません。一説によると含まれている食物繊維が、大腸がんのリスクを低下させる栄養素として注目を集めています。
ベリー類
ベリー類に含まれている植物性色素のアントシアニンには強力な抗酸化作用があり、これが多くの慢性病のリスクを低下させ、さらには老化防止にもつながると言われています。さらにアントシアニンが、がんのリスク低減と関連する可能性があると指摘する研究もあります。
ある人の研究では25人の大腸がん患者にビルベリーエキスを7日間投与した ところ、がん細胞の増殖が7% 減少したが確認されています。別の小規模な研究では口腔管の患者にフリーズドライのブラックラズベリーを与えたところ、がんの進行が抑えられたというデータもあります。
また、ベリーの健康効果は種類によって異なり、例えばブルーベリーは抗酸化物質が豊富で、イチゴはビタミンCが豊富です。またクランベリーなどには尿路感染症の予防など、特定の健康効果が期待できるものもあります。
エキストラバージンオリーブオイル(酸度が0.8%以下)
オリーブオイルとがんに関する研究は非常にたくさんあり、例えば19の研究からなる大規模なレビューでは、オリーブオイルを最も多く摂取している人は、摂取量が最も少ない人に比べて乳がんや消化器系のガンの発症リスクが低いことが示されています。また別の研究では世界28カ国のがん罹患率を調べたところ、オリーブオイルの摂取量が多い地域では大腸がんの罹患率が減少していることが分かりました。
人参
日本人の2人に1人は、癌にかかり、3人に1人は癌で亡くなると言われています。癌は、現代社会の大きな健康課題の一つであり、その予防と治療には多くの研究が行われています。その中で食事とがん予防の関連性についての研究が進んでおり、特にニンジンがその一端を担っていることが明らかになってきました。
人参のがん抑制効果には、その豊富な栄養素と抗酸化成分が大きく関与しています。人参に含まれているベータカロテンは、体内でビタミンAに変換されて、細胞をフリーラジカルから保護します。このフリーラジカルは、DNAにダメージを与え、がんの発生を引き起こす可能性があります。このためフリーラジカルを中和するビタミンAは、がんの発生を予防する可能性があると言われています。もちろんビタミンAに限らず、抗酸化物質はDNAを保護する作用があります。
また人参には、ポリアセチレンという成分も含まれています。これは免疫システムを強化し、細胞の健康を維持するのに役に立ちます。特にポリアセチレンは、がん細胞の成長を抑制する効果が研究で示されています。これにより健康な細胞が正常に機能し続け、がんの発生を防ぐのに寄与します。
さらに人参に含まれている食物繊維は、消化器系の健康を維持し、特に大腸がんのリスクを低減すると言われています。食物繊維は腸内の余分な物質を取り除く役割を果たし、これにより有害な物質が腸壁に長時間接触することを防ぎます。
高脂肪魚類
いわゆる青魚や鮭、マグロなどの脂質が豊富な魚が、がんのリスクを低下させてくれることが分かっています。実際ある大規模な研究では、魚の摂取量が多いほど消化器系がんのリスクが低いことが示されています。また、47万8040人の成人を追跡調査した別の研究では、魚をたくさん食べると大腸がんの発症 リスクが低下するということが分かっています。脂肪分の多い魚には、ビタミンDやオメガ3脂肪酸などがんのリスク低減につながる重要な栄養素が含まれています。
さつまいもの
さつまいもは、糖分がたっぷりの芋でとても甘くておいしいですが、実はがんを予防する効果があります。特に紫芋の皮が、がん予防に効果的です。紫色の植物にはアントシアニンという青色の色素があり、アントシアニンは植物が日光などの有害な刺激から自分の身を守るための物質で、非常に高い抗酸化作用が確認されており、癌を予防する抗酸化物質です。
アントシアニンと癌の関係について調査した実験によると、アントシアニンを 与えることで大腸癌を優位に抑制することができると分かりました、さらにこの研究では私たちが食べ物から摂取する焦げである食品中のAGEsをアントシアニンが無毒化してくれることまで分かっています。
がんのリスクを上げる食材
世の中には、がんを予防する効果を謳った食材やサプリメントなどがたくさん 溢れています。しかし食べるだけでがんにならない食材やサプリメントというものは世の中に存在していません。実際には、がんになる確率をほんの少し下げてくれる食材が存在しているだけです。
超加工食品
加工食品は長い間保存できるように多くの添加物が使われています。実際にフランスの研究でも加工食品の中でも、特に高度に加工された超加工食品を食べる割合が大きい人ほど死亡リスクが高いということが明らかになっています。
超加工食品には、温めるだけで食べられるレトルトフードやカップ麺、菓子パン、スナック、ソーセージ、アイスクリームなど日常にあるものがほとんどです。そしてハムやソーセージベーコンなどの加工肉は発がん性があることが明らかになっています。例えば加工に使われる化学物質や高温で焼いた際に発生する発がん性物質などに問題があります。例えば毎日50gの加工肉を食べ続けると大腸がんになるリスクが18%増加することが分かっています。
超加工食品は、簡単に言ってしまえば便利で安くて美味しいものです。超加工食品は製造段階から他の食品群とは全く異なっており、多くの場合トウモロコシや小麦などの植物性食品、通常の料理で使用されることがないブドウ糖液糖のような様々な糖質、そして加工された油及び加工されたタンパク質が原材料の中心です。もちろん自然の食品に比べ風味やうま味が少なくなっているので、香りや旨味の成分を担う香料や化学調味料も添加されています。さらに口当たりをよくしたり、保存期間を長くするために様々な添加物を加えます。
実は超加工食品の消費量は年々増加しており、それに伴って様々な健康被害が増大しているという現実があります。例えば超加工食品を摂取することによって体内に炎症が起き、心血管疾患のリスクの増加、がんのリスクを高める研究結果が増えています。例えばフランスの成人10万人の疫学研究から食事中の超加工食品の割合が10%増加することに全がんリスクが12% 、乳がんのリスクが11%増加することが示されています。
また、超加工食品は高カロリーにも関わらず、栄養価が低いものが多くて、過剰摂取するとエネルギーの過剰摂取につながり、肥満のリスクが高まります。そして肥満は、糖尿病、心血管疾患、がんなどの慢性疾患のリスクを高めてしまうということが分かっています。
さらに超加工食品は、低コストで生産でき、高収入を上げられる商品のため、各社はどのような味に至福の喜びを感じるのかを徹底的に研究しつくしています。綿密に糖分、脂肪分、塩分、旨味成分などを配合し、飽きることなくまた繰り返し食べたいと思う絶妙な味に仕上げられています。
ブドウ糖果糖液糖
ブドウ糖果糖液糖は、ジュースなどの清涼飲料水、ヨーグルト、めんつゆ、焼肉のたれ、ドレッシングなど甘みを加えた方が美味しくなるほとんどの商品に入っています。ブドウ糖果糖液糖が広く使用されているは、単に安いからです。現在使用されている糖質の実に40%以上がブドウ糖果糖液糖です。そして現在、ブドウ糖化糖液糖の原料は主にトウモロコシです。
別にトウモロコシは自然の食品なので問題ないのと思われるかも知れませんが、日本に輸入されるトウモロコシのほとんどがアメリカもしくはブラジル産のものです。そしてアメリカやブラジルで作られているトウモロコシの90%は、遺伝子組み換えトウモロコシです。
遺伝子組み換え食品に関しては、その安全性に関してまだ結論が出ていない状態です。しかし日本人はその安全性が定かではない大量の遺伝子組み換えトウモロコシを原料とした食品、つまりブドウ糖果糖液糖が含まれている加工食品を大量に消費しています。
ブドウ糖果糖液糖は高濃度のため肝臓への負担を始め、様々な弊害を引き起こします。例えば加糖を大量に摂取することは、確実に腸内環境を悪化させる原因となります。さらには加糖には発がん性があるということも示されています。
人工甘味料
多くの清涼飲料水やドレッシングなどに砂糖の代わりとして、人工甘味料が使用されるようになってきました。あるドレッシングには、ブドウ糖果糖液糖が入っていないと記載されていても、実は代わりに人工甘味料が含まれているものがあります。
特にカロリーオフ、カロリーゼロと書かれた食べ物の大半には人工甘味料が使われていると考えて間違いありません。有名なものにはアスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースなどの人工甘味料があります。これまで人工甘味料は体に悪いというエビデンスはそんなにありませんでしたが、最近は人工甘味料の悪影響を示す研究が出てきています。
例えば、人工甘味料を含んだ飲み物と死亡率の上昇との間に関連性があるということが示されています。毎日250mlの人工甘味料入りのドリンクを飲むことと心臓血管疾患による死亡の間に関連が認められました。さらに10万人以上を対象としたフランスの研究では、アスパルテームとアセスルファムカリウムの摂取が全がん疾患のリスク、肥満関連がんのリスク、特に乳がんのリスクを上げてしまうということが示されました。
これらの結果を受けて、アスパルテームについては世界保健機関(WHO)傘下の国際がん研究機関(IARC)によって2023年7月に初めて「ヒトに対する発がん性を持つ可能性」のリストに掲載されることになっています。
ヨーグルトのリスク
近年の研究でヨーグルトを含む乳製品は、がんを促進するという報告が相次いでいます。ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌や酵母を混ぜて発酵させることで作られる発酵食品です。そのヨーグルトに含まれる乳酸菌が腸内環境を整える効果があると考えられています。 また腸管免疫系を活性化させることも分かっています。またヨーグルトに含まれるカルシウムは、乳酸と結びついて乳酸カルシウムになり、牛乳で取るカルシウムより吸収が良くなります。
しかし、ヨーグルトは近年急激に増加している大腸がんや乳がん、前立腺がんの原因になる可能性が指摘されています。医学会でもヨーグルトの良し悪しはかなり論争が繰り広げられています。その関連性を強める興味深い研究があり、国立がん研究センターガン対策研究所の予防関連プロジェクトによると、約4万3000人の男性を対象に行った追跡調査では、牛乳やヨーグルトその他乳製品などの摂取量と前立腺がんの発生率が関係することが判明しています。そして4万3000人を調査している期間中に前立腺がんを発症してしまった人は329人いました。
その発症した人たちは、特に乳製品を好んで食べていた傾向がありました。牛乳はもちろん、ヨーグルトやチーズなどの乳製品を積極的に食べていたことが分っています。またヨーグルトなどの乳製品ががんの原因になるのは、カルシウムと飽和脂肪酸による影響があるのではないかと示唆されています。
ある研究で病気とカルシウムの関係を調べたところ、1日のカルシウム摂取量が多い人ほど心血管死亡率が上昇し、がんでなくなってしまう確率も増加することが分かりました。また牛乳なら1000mg、牛乳4本分を毎日欠かさず飲んでいる人ほど、がんになりやすく、そして死亡率が上がりやすいことも明らかになっています。
牛乳は牛の母乳であり、本来乳児にとって最も理想的な食品ですが、同時に多くの発がんウイルスが母乳を通じて感染した例があります。つまり牛乳を低温殺菌という方法だけで飲用することが良いのかは科学者たちの論争にもなっています。しかも発がん性ウイルスは、本来の宿主と違う宿主に感染すると発がん性が格段に上がる傾向があります。つまり牛には無害なウイルスであっても、人に感染すると発がん性を持つ場合があることが考えられます。
また、牛乳の生産方法にもがんリスクを高めている要因があります。実は病気になっているメス牛がかなり多くおり、その治療のために投与される抗生物質 や消炎剤が牛乳の中身に混じっていることあります。
さらに現代の酪農システムでは生産効率を上げるために妊娠中の牛からも搾乳しているケースがあります。妊娠すれば胎児を守るために血中の卵胞ホルモンと黄体ホルモンの濃度が高くなり、妊娠中の牛から搾った牛乳には、これらのホルモンが相当含まれています。これらのホルモンは乳がんや前立腺がん、卵巣がんや子宮頸がんなどホルモン系の悪性腫瘍の原因になると考える医学者が沢山います。
そのため、安全なヨーグルトを選ぶことが大事であり、その代表がラクトースフリーのヨーグルトです。ラクトースは乳糖のことで、乳糖が体内で分解されるとガラクトースがつくられ、これが体にダメージを与えると言われています。
このガラクトースは、人が全く利用できない糖で体に蓄積されると体温で熱せられてAGEsという老化物質になります。細胞が老化することは細胞や組織の機能が落ちることであり、その結果がん細胞が増加してしまいます。
また、ラクトースを分解できない体の人が多くおり、現在日本の成人男女の約4分の1、推定2000万人が乳糖を分解できない乳糖不耐性とも言われています。ラクトースを分解できる人の場合、摂取された乳糖は小腸にある乳糖分解酵素 で分解され小腸の粘膜から吸収されます。しかし分解できない乳糖不耐性の人は、ラクトースが小腸で分解されず、そのまま大腸に運び込まれてしまうため、乳糖を体に悪影響を及ぼすガスに変換することで大腸を不必要に働かせ、ひどい腹痛や消化不良などを引き起こします。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。