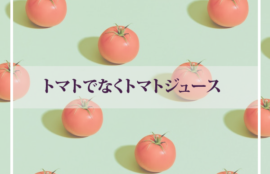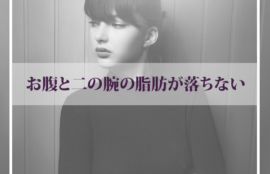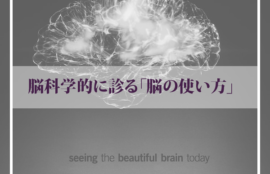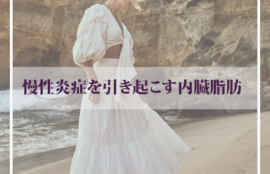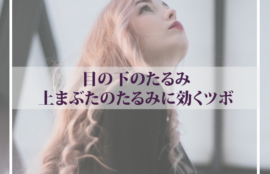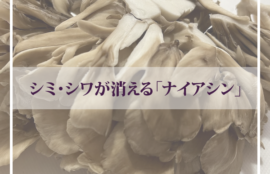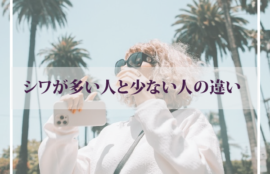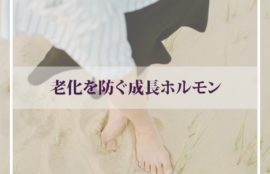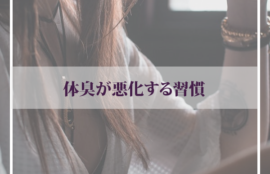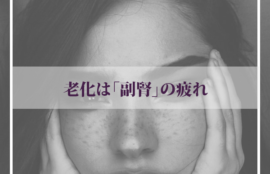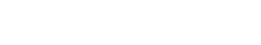お肌、健康のためにサプリを服用している方が多いですが、その副作用や効果についてあまり知られていません。サプリや健康食品の多くは、医薬品に比べて厳密なテストが行われているわけではなく、なんの根拠もない商品も多くあります。
また中高年の方が継続的に摂取したリスクについてはっきりしたことが言える専門家の方がいない状況です。年をとれば代謝が落ち、体内の水分量が減り、肝臓と腎臓の機能が落ち、体内で処理できなくなるため若い頃より副作用が出やすくなります。
また、薬の効果については、NNT(治療必要数)からある程度判断できますが、サプリには基準がなく、そもそも実験データも少なく、大きな結論を出すことができません。
正しい知識を身に付ける
世の中には美容・健康に関する本が沢山あり、本によってまるっきり正反対なことを言っていることもあります。糖質制限をしているのに思ったほど体重が落ちない、ジムに通っているのに健康診断で引っかかったなど、健康思考に気つけて努力しているにも関わらず、なぜかあまり成果が得られない方が多くいらっしゃいます。健康的に痩せられる方法や病気や老化を予防する方法など試しても一向に効果が出ないのは、正しい知識と正しい情報に基づいた美容・健康法を選んでいない可能性があります。
医学の世界は日進月歩であり、新しい発見に合わせて私たち自身の知識もアップデートしていく必要があります。時代遅れの健康法や誤ったダイエット法など、過去の常識が今は非常識になっていることがあります。
また、私たちの身の回りには間違った食の常識が溢れかえっています。朝ごはんを食べないと元気が出ない、牛乳を飲むと骨が丈夫になる、果物をデザートに食べるのは健康的、栄養不足はサプリメントで補おう。このような根拠のない食の常識が世の中に溢れかえっているのは、残念ながら政府や食品業界のプロパガンダに流されているからに他なりません。
例えば、朝ごはんを食べる習慣がつけばそれだけ多くの食品が売れることになります。またアメリカは日本に向けて家畜の餌となる穀物や肉や果物を多く輸出したいという意図があるため、日本人が肉食となって乳製品を積極的に摂取し、果物をたくさん食べてほしいと考えています。このような意向に日本政府は従い、日本には遺伝子組換えされた穀物を餌にして育った牛肉や農薬防腐剤まみれの果物が大量に輸入されています。
また、日本における健康サプリメントの市場はもはや年間1兆円とも言われています。日本人がサプリメントを飲めば飲むほど儲かる企業が存在するわけです。何が言いたいのかと言えば、私たちの食生活は人間の健康ではなく、食糧生産のシステムと結びついています。巨大企業が私たちの健康を食い物にして儲かっているというのは日本に限らず世界で見られる縮図です。
私たちは自分の健康は自分で守らなければなりません。自分の健康を守るためには世の中に広まっている食の常識に流されるのではなく、正しい知識を持って自分の頭で考えて、日々の食生活を自分で決めることがとても大切です。
サプリの摂りすぎ
美肌や健康に良いと言われるサプリの9割は全く飲むメリットがありません。さらに人体に害があると結論づけられたものも多くあります。マルチビタミン、ビタミンC、カルシウム、ビタミンA / βカロチン、フィッシュオイル、ビタミンE、ビタミンB群など、どれも一度は飲んだことあるサプリかもしれませんが、これらのサプリがあまりオススメできない理由があり、これらを知った上で飲み続けるのかを判断して頂ければと思います。
特にビタミンなどは食事から摂ることを基本として、不足していると感じるのであれば、サプリを活用することをオススメします。
マルチビタミン
これまでの研究では、目立ったメリットは確認されておらず、人体にリスクがあるとの結論もあります。2006年ジョンズホプキンス大学では、マルチビタミンに関する過去のデータ(20件)をまとめ、その効果について大きな結論を出しています。その論文では、マルチビタミンやミネラルのサプリが、慢性病や癌の予防になると信じるに足る証拠がないということでした。また東フィンランド大学で2011年に発表された論文では、高齢女性において、ビタミンやミネラルの一般的な使用は総死亡リスクの上昇と関係があったとされています。
ビタミンやミネラルは食事で摂ることが基本です。また特定の栄養素の過剰摂取は健康を害する可能性があります。例えばビタミンAなどの脂溶性ビタミンの場合は、油に溶けて脂肪に蓄積されて、頭痛、眩暈など原因になることが指摘されています。鉄ビタミンの過剰摂取は、肝臓や心臓に影響を与え、亜鉛は吐き気などが起こるケースがあります。
自然の食事によって食物繊維、ファイトケミカル、ポリフェノールなどの栄養素、未知の栄養素も摂ることができます。食べ物を噛んで唾液を出し、咀嚼の刺激が脳へ伝わり消化液が分泌され、消化管を通って動かし、消化酵素が出て吸収されるプロセスの中でまだ解明されていない要素がたくさんあります。
一方で、必要な栄養素が足りていない現代人にとってマルチビタミンを摂るべきではないかという専門家も多くいます。なんとなく不調が続く場合は、ある特定の栄養素が不足している可能性があります。食事から栄養素を摂ることを基本にしつつ、足りない栄養素を特定のサプリで補うことも必要でしょう。しかし過剰摂取にならないようにどんな栄養素を摂ればよいか判断するのは難しいことがあるため、そこでマルチビタミンミネラルで補うことも現代人にとっては必要なことかも知れません。
余談ですが、マルチビタミンミネラルは回数を分けて飲む方が効果が高くなります。例えば水溶性ビタミンは長時間体の中に残らず、尿として排出されやすいからです。またビタミンCは、寝てる間に吸収率が20%上がることも分かっており、寝る前に飲むのが効果的です。脂溶性ビタミン(ビタミンA,D,E,K)は、油が多い食事と一緒に摂ると吸収率が上がり、逆に空腹時には吸収が落ちる事が分かっています。
ビタミンC
ビタミンCは美容に良いのは、ビタミンCは強力な抗酸化物質だからです。ビタミンCは肌に酸化ストレスを齎し、老化させるフリーラジカルを中和させる作用、つまり肌をダメージから守る作用があります。またビタミンCは、皮膚細胞でのコラーゲン生成にも不可欠な物質です。
またビタミンCは免疫機能を高めてくれ、リンパ球や白血球の生成を促進してくれます。そのため風邪の予防に効く、美肌に良いなど様々な効能があると言われ、日本で最も売れているサプリのひとつです。
しかし信頼性の高い論文を見る限りビタミンCの効果はほとんど期待できません。例えば1940年代から2004年までのビタミンCの研究をした論文結果から結論を結びつけると、一般人がビタミンCをいくら飲んでも風邪の予防効果はないとの結論に至っています。また老化についても科学界で統一された見解がなく、今のところよくわからないというのが結論になっています。
ビタミンCの必要量は1日あたり50から100mg程度と言われています。しかし抗酸化作用を期待するのであれば1日3000mg程度大量に摂取しなければならないという説があります。しかしそんな大量のビタミンCを摂取した場合、腎結石などのリスクもあり、いずれにせよ過剰摂取がリスクになる栄養素が多くあるため注意する必要があります。
ここでの話はあくまでサプリの効果についてです。ビタミンCは体内で合成することができないため十分な食事摂取が必要です。ビタミンCの抗酸化作用は炎症を軽減し、老化の原因であると言われるフリーラジカルに対抗するための役割もあります。また2018年に発表された研究では、ビタミンCのレベルが低いことがアレルギーを持つ人々によく見られることも示唆されています。
カルシウム
多くのメーカーは、骨が強くなる、骨粗しょう症を予防すると効果を宣伝していますが、米ノースカロライナ大学が行なった調査によると、大量のカルシウムを摂っても骨密度に違いが出ないという結論を発表しています。さらに70代以上の方が摂取した場合は逆に骨密度が低下することも分かっています。さらに血管や心臓に大きなダメージが出るとの報告も多数あります。2010年に行われた大規模な調査(約2万4千人の中高年)では、心筋梗塞のリスクを86%増加させることが明らかにされています。
またアメリカノースカロライナ大学とジョンズホプキンズ大学が共同で行った研究によると、カルシウムをサプリメントで過剰に摂取すると動脈の石灰化が進み、心臓病のリスクを高めることが明らかになっています。また研究段階ですが、サプリメントで摂取したカルシウムは、実際には骨にはほとんど摂り込まれていないことが指摘されており、血液中に残ったカルシウムが血管の中で石灰化していると推測されていいます。
さらに別の研究では、45歳か75歳の2000名以上を対象として6年から10年をかけて行われた研究では、カルシウムを摂取した人は大腸ポリープが増える傾向にあることが分かっています。さらにカルシウムをサプリで摂取すると腎結石になりやすいことが分かっています。食事では野菜などに含まれるシュウ酸がカルシウムの吸収を調節します。しかしサプリの場合は、この調整機構が働かずに過剰に吸収されて腎結石のリスクとなってしまいます。またビタミンには水溶性と脂溶性ビタミンがあり、後者は水に溶けずに尿として排出されないため過剰症の恐れがあります。過剰症になる恐れのあるビタミンがビタミンDやEです。
ビタミンA/βカロチン
ビタミンAは、肌の健康を維持し、粘膜を強くして細菌から身を守るために必要な成分と言われています。βカロチンは、緑黄色野菜に多く含まれる色素で体内でビタミンAに変換され、癌の予防や活性酸素を取り除くなどでサプリが販売されています。
ビタミンAは、体にはたくさん必要なビタミンではなく、偏った食事になってない限りサプリメントで補う必要はほとんどありません。東京医科歯科大学の調査によるとビタミンAは過剰摂取すると骨粗しょう症のリスクが上がるという結果が出ています。さらに長期間に渡って過剰摂取をすると、頭痛、脱毛、肌荒れなどが指摘されています。また妊婦さんが過剰摂取すると奇形児発生リスクも上がると言われています。
また、2012年にコクラン共同計画が行なった研究では、約24万人のデータを元に、抗酸化物質が健康に良いのかを調べましたが、それらのサプリを摂取すると早期死亡率が3〜10%上がることが分かっています。その理由は、ビタミンAは摂取すると簡単に体内から排出されない性質があるからです。例えばビタミンCは、水に溶けやすく、不要なものは尿から排出されますが、ビタミンAは油にしか溶けないため、体内で使われない分が蓄積して、肝臓にダメージを与えるからです。
フィッシュオイル(DHA・EPA)
オメガ3、DHA、EPAなど、血液サラサラ、認知症の予防など健康に良いとの認識を持つ方が多くいます。確かに過去の研究でも有用性が確認されていますが、健康的な人がフィッシュオイルと摂っても意味がないという研究(2012年ヨアニナ大学のおよそ6万9千人分ものデータをまとめたメタ分析)があります。またフィッシュオイルは異常に劣化しやすい成分です。酸化したフィッシュオイルがどれだけ体に悪いかは研究例が少ない現状がありますが、酸化した脂質が心疾患のリスク要因になることが分かっています。
一方でオメガ3 脂肪酸は、血液をサラサラにしたり、コレステロールを下げる効果があります。特EPAは摂取をすることによって、心臓の病気のリスクが低下したり、血圧が低下したという報告は多数あります。お魚は冷たい海水の中でも自分の体が血栓で固まらないように血液がサラサラになる脂を持っていると考えることができます。
しかし、サプリから摂るよりも実際の魚から摂った方が健康のメリットが大きいというデータがあります。週に4回以上お魚を食べている人は、そうではない人に比べて心臓の血管が詰まってしまう病気のリスクが大幅に低下したというデータが あります。そしてお魚の摂取量が1週間にたった100g増えるだけで、心臓の病気になるリスクが5%ずつ低下していくデータもあります。
私自身は魚の缶詰をよく食べます。缶詰は、よくできていて日光を通さないので脂が酸化してしまうのを防ぐことができたり、魚の栄養素を缶詰に密封した状態で火を加えるので、重要な成分が漏れ出ていかないというメリットがあります。忙しく料理がする時間のない方は、お魚の缶詰を摂取することをお勧めします。
ビタミンB群
ビタミンB群とは、ビタミンB6、ナイアシン、葉酸などの成分をまとめたものです。これらは人体が正常に働くために欠かせない栄養素であり、美容に良いと言われたりします。しかし体に良いというデータはほとんど発表されておらず、様々な副作用が明らかになっています。
特にビタミンB6とB12は注意が必要です。ビタミン B群は代謝を上げたり、酵素を生み出すのに必要な時の補酵素としても大切な栄養素です。しかしビタミンB6とビタミンB12 を必要以上に摂取し続けると肺がんリスクが倍増するという報告が出ています。
アメリカで行われた研究では、過去10年間に1日平均20mgのビタミンB 6を摂取していた男性は、摂取していない人に比べて肺がんのリスクが1.8倍、ビタミンB 12でも肺がんの発症リスクは2倍以上という結果になりました。さらに喫煙者だとその差が大きく、ビタミンB 6で約3倍、ビタミンB 12で約3.7倍に上昇する結果になっています。
また、アメリカ心臓協会によると、ビタミンB群は心疾患を減らすという根拠はなく、逆にナイアシン、葉酸、ビタミンB6などは、体内のホモシステインを増やす副作用があると発表されています。ホモシステインは、体内でタンパク質が代謝された後に出る残りカスのようなもので、酸化しやすい性質を持った物質です。この物質が増えることで心疾患リスクが増えることが分かっています。また白内障リスクも指摘されています。
ビタミンE
ビタミンEは強力な抗酸化物質であり、老化を促進するフリーラジカルから細胞を守ってくれます。フリーラジカルは酸化ストレスと呼ばれるプロセスを通じて細胞の寿命を縮めます。フリーラジカルは細胞に結合して、内部のタンパク質やDNAに損傷を与えることによって老化を促進すると考えられています。
2018年の論文では、臨床的に心血管疾患が確認された1002人の患者の中でビタミンEの摂取量が少ないことが細胞の老化の増加に関連していることが分かっています。
このように抗酸化作用が高く、アンチエイジング効果や癌の予防効果が言われていますが、2010年代からの研究では、癌のリスクを高めているのではないかと考えられています。例えば2011年の研究では、ビタミンEと前立腺癌の増加の関係が発表されたり、他にも飲み続けると寿命が縮むことが分かっています。ビタミンEもビタミンAと同じく、体外へ排出されにくく、肝臓にダメージを与えるからです。
このビタミンEは、抗酸化力が高く活性酸素を抑える働きがある若返りのビタミンとしてサプリメントとしても人気です。しかし日本の厚生労働省が調べたところによると、ビタミンEを必要以上、1日当たり400IUを数年間摂り続けた人は、前立腺がんのリスクが高くなっています。しかもサプリメントでの摂取の場合は、摂取量が基準値内でもリスクが高くなっています。このことは、サプリメントのビタミンEと食品から摂るビタミンEには何らかの違う影響がありますが、その因果関係の原因はよく分かっていません。
アメリカ国立がん研究所が2007年に行った被験者1万1,000人での調査では、マルチビタミン剤を摂取した男性は、摂取しなかった男性に比べて進行性の前立腺がんによる死亡率が倍増していたことが分かっています。また2011年にミネソタ大学が3万9000人以上を対象に行なった調査でもビタミン剤のサプリメントを摂取した女性は、摂取しなかった女性に比べて死亡率が高いことが明らかになっています。
ビタミンD
慈恵医科大学の研究では、東京都内で健康診断を受けた約5000人の方を対象にビタミンDが足りているかを調べました。その調査では、98%の方がビタミンDが低下していたことが分かりました。ビタミンDは、骨を強くするビタミンであり、カルシウムの吸収を促進して骨を強くします。それだけではなく、抑鬱といって気分が落ち込んでしまうのを改善する効果が期待されています。
中高年の女性に多い骨粗鬆症の患者さんに、このビタミンDを薬として摂取することが推奨されています。ビタミンDは、国際単位で大体1日900単位摂らないといけないと言われていますが、日本人の平均の食事からは大体600単位程度しか摂れていないと言われています。
また、ビタミンDは食事以外にも、日光を浴びることで合成されます。このため美肌を意識している方は、ビタミンDが不足しがちになります。例えばビタミンDの欠乏がうつのリスクと相関していることが分かっています。その他にも様々な健康効果が確認されています。ただし摂りすぎによるリスクも指摘されており、ビタミンD協議会では、成人は医師の監督なしに1万IUを超えて摂取しないように注意を呼びかけています。
鉄分
特に、サプリに含まれる鉄分はがんのリスクを高める原因になると考えられています。例えば台湾で30万人以上の被験者が参加した研究では、血中鉄分値が高いほどがんのリスクが高くなることが判明しています。理由として鉄分と結合したフェリチンの量を示す「血清フェリチン値」が高くなると、鉄分がDNAのテロメアを短くして、染色体が不安定になり、DNA損傷が増えることが知られています。この過剰な鉄分によってがん化しやすいのが大腸であり、過剰な鉄分の最終到着点が大腸だからです。吸収されない鉄分は腸内で悪玉菌の栄養となり、大腸の免疫力が低下、炎症が慢性化して大腸がんのリスクが高くなるためです。
多くの人が鉄分は、ビタミンCやEのように有益な作用しかないと考えています。しかし鉄分は必要以上に摂ると逆に体の毒になり、その必要な鉄分量は人によって違います。鉄分の必要量は、性別、年齢、遺伝子の3条件によって変わります。例えば女性は生理があり鉄分過剰を気にすることはありませんが、男性は多くの場合に鉄過剰になりがちです。また鉄分を遺伝的に吸収しやすい人もいます。
全てのサプリに注意
日本よりもさらにサプリメントが一般的なアメリカでは、カルフォルニア州公衆衛生の研究チームが10年かけて有害な成分が否定できないサプリメント776製品を調査しました。その結果、そのすべてで無許可にも関わらず、医薬品の成分が使用されており、さらにそのほとんどはその成分が入っていることをラベルに表記していませんでした。
さらに14製品には人への使用が許可されていない抗うつ剤や心疾患になる危険性のため、2010年に販売禁止された成分が入っていました。またプロテインにもステロイド剤が入っていて表記がされていないものが大半でした。一方日本で日本薬剤師会が3年かけて行なったトクホの商品の調査では、無雑作に選んだ21の商品の内、5つの商品は摂取しても体内で解けなかったことが指摘されています。
脳に蓄積する鉄分
鉄分は血液の材料になり、生きていく上で必要不可欠な栄養成分です。しかしどんな栄養素でも過剰な量は毒となります。放置された鉄材が錆びるように、私たちの体に存在する鉄も放っておけばサビて、そのサビが脳に蓄積することが分かっています。例えばアルツハイマー病の主原因となる脳内のヘモジデリンやアミロイド斑は、錆びた鉄が蓄積したものです。さらに鉄は酸化によって細胞のDNAを損傷することも知られています。
私たちの体では、フェリチンやトランスフェリンなどのタンパク質が鉄と結合することによって体内の他の分子の酸化を防いでいます。しかし血中の鉄分が増えすぎると遊離した鉄が体内に蓄積し、特に脳神経系に影響を与えます。病気を発症した脳内を調べると鉄分沈着量が共通して多いことが分かっています。
例えばアルツハイマー病では、記憶を司る海馬に障害が出ますが、調べてみると鉄分が海馬に過剰に沈着していることが分かります。また男女でアルツハイマー病の発症年齢が違うことも鉄過剰が原因であることが分かります。アルツハイマー病を発生しやすい年齢は、男性の方が5年程度早いですが、閉経後の女性になると鉄分値が急上昇するため、60歳以降では女性の方が男性より50%以上高くなります。
鉄過剰の健康リスク
過剰な鉄分摂取は免疫力の低下により慢性的な感染症やがんを引き起こす可能性が指摘されています。ウイルスや微生物病原体は、鉄分が大好物であるため、体内ではフェリチンやトランスフェリンなどのタンパク質が鉄を捉えることでこれらの病原体と戦っています。これらのタンパク質は病原体を検知すると免疫反応により体温を上げて炎症反応を惹起させます。体温が上がるとフェリチンの鉄分を捉える力が上がり、血中の鉄分値が下がります。
近年、鉄分補給を開始した発展途上国で胃腸感染症が増えているのも、補給された鉄分が胃や腸の病原菌の餌になってしまうことが原因だと考えられています。
逆に、鉄分の摂取量を減らすことで腸内病原体の成長を抑えることができ、これが多くの病気の治療法として昔から用いられてきた瀉血の根拠(現代では医学的な根拠はないとされている)ではとなっています。
一方で、台湾で30万人以上の被験者が酸化した研究では、血中鉄分値が高いほどがんのリスクが高くなることが判明しています。その理由は、鉄分と結合したフェリチンの量を表す血中フェリチン値が高くなると、DNAの損傷が増えるためだと考えられています。
鉄過剰を避ける
鉄は必要以上に摂ると逆に毒性を発揮し、鉄の必要量は人によってまちまちです。鉄の必要量は、性別、年齢、遺伝子の3条件によって決まります。
多くの女性は生理により貧血気味になるため鉄過剰になることは少ないです。しかし男性は鉄過剰になりがちです。特に要注意なのは遺伝的に鉄分を吸収しやすい方がいます。体には余分な鉄を排出するシステムが備わっていないため、鉄分を効率的に吸収する仕組の人体内に鉄がどんどん溜まっていきます。ヘモクロマトーシスやサラセミア症候群などの鉄過剰症候群を引き起こしやすい方は、慢性的な疲労感、関節痛、うつなどの症状を引き起こす可能性があります。
特に赤身肉に含まれる鉄分量はどの野菜よりも多く、肉類が持つ鉄分であるヘム鉄は、野菜由来の鉄分よりも効率的に吸収される特徴があります。またヘム鉄には野菜の鉄分吸収を高める相乗効果があります。また動物性タンパク質は老化のリスク因子であることも指摘されています。これは肉類に含まれるメチオニンというアミノ酸が抗酸化作用のような体内のアンチエイジング機能を低下させてしまうことが原因としています。2006年にフィンランドで行われた研究では、メチオニン摂取量が多い被験者では、心臓発作の危険性が2倍高くなることが報告されています。
一方で、ポリフェノールなどの抗酸化物質は体の老化などを抑制する働きがありますが、抗酸化物質を謳っている加工食品には注意する必要があります。これらの加工食品は鉄分が大量に添加されており、さらに鉄分吸収を促進するビタミンCが添加されているものがあります。最近の研究では食品に添加されたビタミンCによって死亡率が高くなることも報告されており、ビタミンCの過剰摂取によって鉄の吸収効率が異常に亢進し、体内の鉄貯蔵量が高くなってしまいます。
女性はビタミンC、男性はビタミンE
日本において2025年には認知症患者は約675万人に及ぶとされ、5人に1人が認知症になると予想されています。認知症の進行を予防するためにはビタミンを摂取することが挙げられます。最近、各ビタミンの効能が女性と男性で異なることが分かってきています。認知症予防のためのビタミンは男女によって違い、女性の場合はビタミンCを、男性の場合はビタミンEがお勧めです。
研究によると、ビタミンCを積極的に摂取した女性は、認知症のリスクが10分の1にも低下する報告が出ています。一方で男性では、ビタミンCによる認知症リスクの差はないことが分かっています。これは女性には、認知症の遺伝的な危険因子の一つであるApoE4を持つ方がいるためと考えられています。ApoE4を持つ女性は生まれつき認知症の発症リスクが高いですが、血中のビタミンC濃度が高いと将来の認知機能低下のリスクを軽減できる可能性が指摘されています。
一方で、男性にはビタミンEです。女性はビタミンEの血中濃度と認知症の発症リスクに相関は認められなかったものの、男性は血中のビタミンE濃度が高いほど認知症の発症率が低いことが分かっています。
ただしビタミンCは水溶性ビタミンのため、摂りすぎても尿として排出されますが、ビタミンEは脂溶性ビタミンのため、摂りすぎても尿として排泄することができません。何れにせよビタミンCもビタミンE も良質な天然の食材から適度に取るのが一番です。
24種のサプリの健康への影響を評価した最新の研究
代表的な24種のサプリの健康への影響を評価した最新の研究では、飲んでも飲まなくても健康への影響はなかったと結論が出ています。むしろ健康を害するサプリもあり、その1つがカルシウムです。カルシウムをサプリで摂取すると腎結石のリスクが高くなることが指摘されています。食事では野菜などに含まれるシュウ酸がカルシウムの吸収量を調整してくれますが、サプリのみではこの調整が働かず、過剰に吸収されてしまうからです。
また、多くの人が飲むマルチビタミンサプリも注意が必要です。ビタミンには水溶性と脂溶性ビタミンがあり、後者は水に解けず尿で排出されないためか過剰に摂取してしまう可能性があります。特にビタミンDやEは摂り過ぎによって死亡率が上昇することが確認されています。
唯一摂るべきサプリとして挙げられたのが「葉酸」です。葉酸は妊娠している方が摂取することで胎児の正常な神経発達が促され、脊髄の先天障害を予防する効果があると知られています。ただし長期的に摂取し続けると大腸ガンのリスクになる可能性も指摘されているため、摂り過ぎには十分注意が必要です。
何れにせよ、足りない栄養素はサプリで補えば良いと考えるのではなく、バランスの良い食事を心がけましょう。
輸入レモン、オレンジなどの柑橘類
ビタミンを取るために柑橘類を選ぶことがありますが、日本では使用が禁止されているポストハーベスト農薬が、輸入レモンやオレンジなどに沢山使われています。ポストハーベストは収穫後に使用される農薬のことで、殺虫剤、防カビ剤、殺菌剤などの名目で利用されています。そのため果物の表皮に多くの農薬が残留していると考えられています。
農薬などの化学物質が複数同時に使われた場合や体内に入った場合にどのような影響があるのかとうことが誰にも分かりません。通常、農薬や食品添加物などの合成化学物質が体内に入るとそれらは科学的な反応を起こします。化学物質の安全性は単体でしか確認されていないため、どの化学物質とどの化学物質がどんな反応を起こすかということについては完全に未知数です。
なぜ日本禁止されているものが輸入されているかというと、食品添加物として認められているからです。そのため、できるだけオーガニックで国産のものを選ぶようにしましょう。
当たり前ですが、サプリに頼るのではなく、加工されていないものを摂り、野菜は多め、肉と魚は生育環境が良いものを選ぶこと、柑橘系のオーガニック果物、そして運動習慣が健康にとって最も良いものであることは昔も今も変わりはありません。
野菜と果物が最強
世の中には健康に良いとされている食べ物が多くありますが、エビデンスが不十分であったり、専門家の間でも意見が分かれる食べ物が多くあります。その中で健康効果がしっかり認められているものが野菜と果物です。良くわからないサプリを飲む前に、エビデンスのある野菜と果物を食べることを基本としましょう。
私たちの健康に野菜と果物がどれだけ良いかを明らかにした様々な研究があります。例えば20201年に果物と野菜の摂取量と死亡率の関係を明らかにした研究によると、摂取量が多いほど死亡率が低くなるとおいう結果になっています。具体的には、1日に5サービング(一食分で食べる量)の果物や野菜を食べていた人は、2サービングの人に比べてすべての原因による死亡リスクが13%低下しました。アメリカの成人で1日に果物や野菜を食べる量は2サービング程度と言われているため、しっかり果物や野菜を摂る必要があります。
ほうれん草やケールなどの葉物野菜、ブロッコリーや芽キャベツなどのアブラナ科野菜、にんじんやベリー類などのβカロテンが豊富な食品が最も健康に良いと言われています。特に葉物野菜はビタミン、抗酸化物質、ミネラルなどの栄養が豊富であり、いくつかの研究では脂肪燃焼を助けてくれることが示されています。さらに緑の葉野菜を食べると、含まれるフィロキノン、ルテイン、葉酸が認知機能の低下を遅らせるのではないかと考えられており、脳年齢が11歳も若くなることが明らかになっています。
さらに2022年に行われた日本人を対象とした研究でも野菜や果物に健康効果があることが確認されています。横浜市立大学と国立がん研究センターは共同で、40から69歳の男女9万4,658人を対象にして約20年間に渡って、野菜と果物の摂取量と死亡リスクとの関連を調べました。海外の研究と同様に摂取量が多い人は死亡リスクが低いということが明らかになっています。この研究を受けて1日に野菜は300g以上、果物は140g以上摂取するのが望ましいとしています。
野菜と果物はほとんどの食事や軽食に含まれる栄養素が自然にパッケージ化された供給源であり、私たちの心と体を健康に保つために不可欠です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。