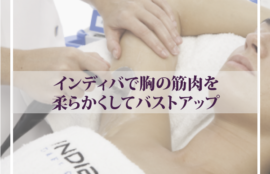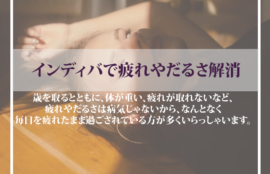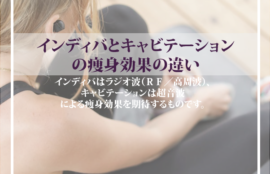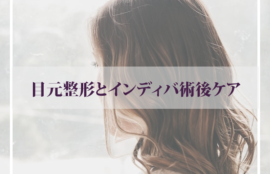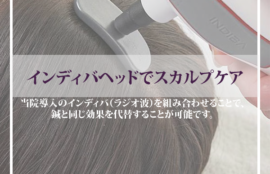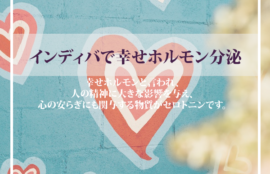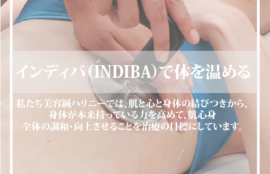腎臓の重要性が広く認識されるようになり、腎臓機能が悪くなると老化スピードが加速してしまうことも分かっています。例えば尿の色が濁っているもしくは白っぽい、尿が泡立つ、夜中に何度もトイレに行く、どれか一つでも当てはまっている場合は、腎臓が弱っているかも知れません。
腎臓の役割
私たちの体に存在しているおよそ37兆個の細胞が、血液で運ばれてきた栄養や酸素を受け取り、老廃物や二酸化炭素を血液に戻しています。また血液中には、尿素、窒素、クレアチニン、尿酸といった様々な老廃物が流れており、このような血液中にたくさん存在している老廃物を掃除してくれるフィルターが腎臓です。血液に乗って運ばれてきた老廃物は、腎臓の糸球体という組織でふるいにかけられて不要なものは尿として体の外に排泄されます。
このように私たちの体は、腎臓が作り出す尿によって、血液に乗って運ばれてくる全身の老廃物を排泄していますが、腎臓の機能が低下したり、腎臓が老化してしまうと体の中の老廃物をうまく排泄することができなくなり、脳や心臓、肝臓などの全身の臓器が本来の働きができなくなります。そしてこれが老化の大きな要因になると指摘されています。
多くの人が体の老廃物は、便によって排出されていると思っていますが、実は便の成分のほとんどは消化管を通った食べ物のカスや腸内細菌の死骸などです。それに対して腎臓から排泄されるのは全身の臓器を巡った血液に含まれる細胞の老廃物で、さらに体内の毒素も腎臓から排泄されています。つまり全身の老廃物をしっかりと排泄し、体内をキレイにしてくれる臓器こそが腎臓であり、腎臓から適切な尿が作られることが極めて健康上重要な役割を担っています。
また、腎臓は老廃物を尿として出すこと以外にも骨を丈夫にするために重要なビタミンDを活性化するなど様々な重要な働きを担っており、特に重要な働きが塩分濃度の調整です。毎日様々な食事が塩分濃度が一定ではないにも関わらず体内の塩分濃度は常に一定に保たれています。これはまさしく腎臓がどれくらい尿に塩分を排出するかを調節しているからです。
腎臓病は、慢性腎臓病という腎臓の機能が慢性的に低下してしまう病気であり、現在日本の慢性腎臓病の患者数は 1300万人を超え、成人のおよそ8人に1人が慢性腎臓病であると言われています。慢性腎臓病が進行すると腎臓による塩分濃度の調節ができなくなるため、人工的に血液から塩分を抜いたり、足したりする必要があります。これが人工透析で病院に週3回数時間通わなければいけないとても大変なことです。慢性腎臓病になって透析を受けなければならなくなる事態を避けるためには何よりもまず腎臓を健康的に保つ必要があります。
腎臓の衰えのチェック
腎臓には、第一に血液をきれいにするという役割があります。また腎臓は人体の6から7割を占める水分をコントロールしています。腎臓の機能が低下すると水分のコントロールがうまくいかなくなり、様々な不調が現れるようになります。他にも腎臓には、血圧を一定に保ったり、血液を作るように指示を出したりといった様々な役割があります。
近年、慢性腎臓病の方が増えており、実に成人の5人に1人が罹患し、年齢が高くなればなるほど患者の割合は増えている現状があります。次のチェックリストに一つでも当てはまる項目があれば、腎臓の衰えが進んでいるかもしれません。
- 疲れが抜けなくなった
- 胃もたれがないのに吐き気
- 皮膚のかゆみ
- むくみがひどい
- 尿の量や頻度が多い
- 集中力が低下
その他の腎臓のチェック項目
- 高血圧
- 血糖値が高め
- 顔色が悪いと言われる
- 健康診断でクレアチニンチが高いと指摘された
- 健康診断で尿蛋白が見つかった
疲れが抜けなくなった
腎臓の機能が落ち始めた時に出てくる症状の一つ目が疲れやすさです。疲れやすさには様々な原因が考えられ、ストレス、グルテンによる全身の慢性炎症などがあります。しかし疲れやすさが短期間ではなくずっと続いている場合は、腎臓の機能低下を疑う必要があります。
腎臓が悪くなると疲れやすさが出てくる原因の一つとして体内に老廃物が溜まってしまうことが挙げられます。腎臓は血液の中から余分な老廃物をろ過することで尿を作っています。このような腎臓の浄水機能が弱まってしまうと体に老廃物が溜まってきます。老廃物が溜まれば、体に様々な不調が出てきます。
また腎臓の機能が落ち始めて、疲れやすさが出る原因として老廃物の蓄積と並んで重要なのが貧血です。
腎臓には血液を作るという非常に重要な働きがあります。成人の体内で血を作る場所は一般に骨髄ですが、実は腎臓ではエリスロポエチンという造血に欠かせない要素が産生されています。
赤血球は血の赤い成分であり、酸素を運ぶ働きをする血球で、一方白血球は免疫に関わる細胞です。これらは全て骨髄の中で最初は造血幹細胞として生まれます。この造血幹細胞が大人になるにつれて赤血球や白血球と言った、それぞれの役割を持った血球へと分化します。 この造血幹細胞が赤血球に分化するために必要なのがエリスロポエチンです。
つまり、腎臓の機能が低下するとエリスロポエチンが低下して、造血幹細胞が赤血球に分化することができなくなります。赤血球は体中に酸素を運搬して二酸化炭素を回収してくれるゴミ収集車としての役割があるため、このように赤血球が減って、貧血になると全身の細胞におけるガス交換が滞ってしまいます。細胞の活動において酸素が不足してしまうと細胞は窒息し、疲れやすさの症状として出てきます。
ただし女性の方は生理の関係で貧血になりやすく、その貧血の原因として代表的なものに鉄不足が挙げられます。もし生理に問題がなく、鉄もちゃんと摂っているにも関わらず貧血の症状が出た場合は、腎機能の低下を疑いましょう。
胃もたれがないのに吐き気
吐き気もまた様々な病気によって引き起こされます。吐き気があるからと言って一概に腎臓病だとは言い切れませんが、腎臓病によって吐き気が出るのは体内に蓄積した老廃物によって脳のオート中枢が反応してしまうため考えられています。
皮膚のかゆみ
皮膚のかゆみもまた全身に蓄積した老廃物によって起こります。腎臓の機能が低下すると血液がろ過できなくなります。血液に老廃物が蓄積するとその老廃物が全身の細胞に巡ります。当然皮膚の細胞にも老廃物が溜まり、ターンオーバーによってその毒素が表面に出てきます。そうなると皮膚のかゆみや色の変化などが出てきます。また老廃物が溜まった皮膚は当然老化します。特に腎臓機能の低下はお肌の美容にとっても大敵です。
さらにこのような症状が進むと尿毒症という命に関わる症状にまで発展する可能性もあります。尿毒症は腎機能が正常の1/10にまで低下してしまった状態で、ほとんどのケースで透析導入が必要となります。
むくみがひどい
健康診断でタンパク尿を調べる項目がありますが、タンパク尿検査では尿の中のアルブミンという物質の量を調べています。アルブミンは、血液中に存在するタンパク質のことで、正常であれば腎臓の中でろ過されることはありません。 しかし腎臓の機能が低下すると腎臓のろ過の働きをする部分が緩み、尿にアルブミンが出てしまいます。これがタンパク尿の正体です。
血液中に存在するアルブミンは、血管の中に水を引っ張ってくる作用があり、アルブミンが血液中にないと血管の中から水分子がどんどん漏れ出します。水分子を引き寄せて水漏れを防止するのが血管内に存在するアルブミンの役割です。腎臓の機能の低下によってアルブミンが尿に出てしまうと血液中のアルブミンが不足します。すると血管内に水分子を溜めておくことができなくなり、水がどんどん血管外に漏出します。血管外に漏出した水は、脂肪や筋肉、皮膚などの血管外の組織に溜まり、その組織が水によって膨れ上がりむくみの原因になります。
尿の量や頻度が多い
多尿の症状は腎臓病が進行していく中でも最も初期に出始める症状の一つとして知られています。これは腎臓における尿の濃縮力の減退によるものだと考えられています。人にとって渇きは危機的状況の一つのため、体の中に水分を沢山蓄えており、腎臓はなるべく尿の量を最小限に抑え、かつ尿の中に出す老廃物を最大化するために尿を濃縮します。しかし腎臓が悪くなると尿の濃縮力が落ちて尿がだんだん水っぽくなり、多尿になっていきます。一方で頻尿もあり、腎臓が悪くなると多尿に加えて頻尿も出てきます。尿の量が増えればそれだけ膀胱に尿が貯まりやすくなり、当然トイレに行く頻度は上がります。
集中力が低下
腎臓病による集中力の低下には、体内に溜まった毒素が原因の場合もありますが、もう一つの原因が睡眠障害です。実は腎臓が悪くなると私たちの体内時計が狂ってしまうことが知られています。その原因はまだ未解明ですが、このような体内時計が狂ってしまうことで夜間の中途覚醒や睡眠の質の低下といった睡眠障害が現れてしまうことが分かっています。
腎機能が低下する習慣
サプリメント
サプリメントの注意点が過剰摂取です。特に40代以降で腎機能が低下している場合は、サプリメントの成分によっては血中濃度が上昇し過剰摂取になりやすいことが挙げられます。例えばビタミンA、ビタミンC ビタミンEなどは、過剰に摂取してしまうと逆に体の酸化を促進させてしまうということが分かっています。
その他にも、ビタミンDやカルシウムも過剰摂取してしまうと、血液中のカルシウム濃度が非常に高くなり、高カルシウム血症を引き起こして消化管の不調や喉の渇きなどに繋がります。また漢方薬も、サプリメントと同じく精製の段階で無機リンが加えられており、いくら健康に良くても過剰な摂りすぎには注意しましょう。
赤身の肉
長生きにお肉が良いと言われる根拠は、高齢者に不足しがちになって いるタンパク質が豊富なことにあり、また幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌を促してくれるからです。
年を取ると痩せていることが大きなリスクなるため、タンパク質をしっかりと摂取して筋肉量を維持することが大切であり、お肉にはタンパク質をはじめとした沢山の栄養素が含まれています。
ただし、腎臓という観点では、肉類を過剰にも注意が必要です。動物性タンパク質に含まれているメチオニンというアミノ酸は、摂りすぎると腎臓に悪影響を齎すというデータがあります。ただしメチオニンでも、大豆、豆腐、枝豆などの植物性タンパク質に含まれている場合は、ほとんど吸収されないため腎臓に負担をかけません。タンパク質と言っても動物性タンパク質と植物性タンパク質の2種類があり、このバランスが大切です。そのほかにもブロッコリーやアスパラガス、そばやアボカドに植物性タンパク質が多く含まれています。
水分不足
頻尿や尿漏れ、むくみが気になるので水分を控えめにしている場合は、脱水のリスクが高まってしまいます。そして脱水が起こると、軽度の場合は、めまいやフラつきが現れ、中程度になると頭痛や吐き気、体温上昇などが現れ、高度になると意識障害、痙攣、臓器不全といった症状が現れます。
そして、脱水は腎臓にダメージを与え、腎臓への血流が減少して血液中の老廃物がろ過させずに蓄積して炎症を起こし、腎臓にダメージを与えます。また腎臓に悪影響を与えるリンは、尿中に排泄されますが水分が少なくなり、リン濃度が高くなると腎臓にタメージを与えます。
ちなみに、コーヒーや緑茶は、利尿作用があるカフェインが含まれているため、カフェインによって水分が排出されてしまうため逆効果になってしまいます。
糖質・リン
炎症も腎臓の機能を低下させてしまうことが分かっています。血管が老化し、硬くなってしまった状態を動脈硬化と言いますが、腎臓に存在しているたくさんの毛細血管に動脈硬化が起こることで、腎臓の機能が低下します。当然食べ物が腎臓に非常に大きな影響を与えますが、特に糖質はなるべく控えるようにするべきです。
糖質によって腎臓の血管が傷つき、腎臓の機能が低下してしまうということが明らかになっています。なぜなら糖質が小腸から吸収されると、血液中のブドウ糖が増え、その量が多い高血糖になると、ブドウ糖が血管の壁にある内皮細胞に入り込んでダメージを与えます。そこで活性酸素が発生し、細胞を錆びつかせ、老化の大きな原因となります。
さらに、内皮細胞に入り込んだブドウ糖は、細胞の中のたんぱく質と結合しAGEという物質となり炎症を起こします。その炎症によって活性酸素が発生し、血管の内部にAGEがこびりつくとその周りも酸化してダメージを受けます。そしてダメージを負った血管は、厚く、硬く、もろくなっていき動脈硬化が起こります。
一方で、加工食品に含まれているリンを過剰に摂取し、血中のリンの濃度が上がってしまうと腎臓に対する悪影響をはじめとした様々な体の不調が現れるようになります。またリンが近年では老化を加速させる物質であるということも明らかになっています。
リンを減らすためには、食品添加物に使われている無機リンを摂らないことが大切です。加工食品に多く使われる無機リンは、食品中に元々含まれている有機リンと比較して腸から吸収されやすく、血中のリン濃度を上昇させることが分かっています。
内臓脂肪型肥満
過食や運動不足などによって内臓脂肪が蓄積した内臓脂肪型肥満は、リンゴ型肥満とも呼ばれており、特徴はお腹がぽっこりと出ていることが挙げられます。この内臓脂肪型肥満は、腎臓に悪影響を与えてしまうということが分かっています。
米国腎臓学会の学会誌に発表された研究では、内臓脂肪型肥満の人はそうでない人に比べ腎臓の機能が低下して血圧が高めであり、年齢が進むと慢性腎臓病を発症するリスクが高い傾向にあるということが分かっています。健康診断でメタボと診断されていたり、お腹周りが気になる人は、普段の食生活を見直して内臓脂肪をできるだけ減らすようにと心がけて下さい。
トイレを我慢する
トイレを我慢してしまうと体に様々な不調が起こってきます。トイレを我慢することで、まず一番初めに負担がかかるのが膀胱です。膀胱は尿を貯めておく場所であり、トイレを我慢すれば我慢するほど膀胱は膨らみます。このように膀胱に負担がかかると、多くの場合膀胱に炎症が起きる膀胱炎になります。さらにそこに感染が重なると膀胱内で細菌が増殖し、尿管を通って腎臓に逆流すると腎臓にも細菌が感染します。このように膀胱からの逆流によって腎臓が感染してしまうことを腎盂腎炎(じんうじんえん)と言います。腎盂腎炎が繰り返し起こることで腎機能が低下することが知られています。
水分摂取を控える
トイレを我慢してはいけないという対策として、トイレに行きたくならないように水分摂取を控えてしまう方がいます。特に年を取ると喉の渇きを感じにくくなり、体が脱水状態に陥っていることがよくあります。夏場になって高齢者の熱中症が問題になる原因の一つと考えられています。
また、水不足によるデメリットとして何より怖いのが腎血流の低下です。腎血流とはその名の通り腎臓に流れ込む血の量のことです。腎臓は血液をろ過する 浄水器ですが、浄水器はそこに水が流れ込んでこなければ浄水作業を発揮することができません。水分摂取を控えて体が水不足になると水の来ない浄水器と同じように腎臓がその機能を最大限発揮することができなくなります。
腎機能を改善する飲み物
グァバ茶
グァバは、パパイヤやマンゴーなどと並ぶ代表的な南国の果物の1つで栄養化が高いことから世界的にもスーパーフードとして知られています。グァバ茶は焙煎したグァバの葉やグァバの実を抽出して作ったお茶のことで、様々な健康効果があるとして注目されています。中でもグァバ茶には高い腎機能の保護効果があることが知られています。
日本人の透析患者数は年々増え続け、全国で35万人もの方が週3回病院に通って1回数時間の人工透析を余儀なくされています。また新たに透析を始めた患者さんの数も年間4万人以上にも及び、今後も腎臓を悪くして透析をせざる負えなくなる方はどんどん増えていくことでしょう。
そんな透析になってしまう原因の第1位は実は糖尿病であり、平成10年以降透析の原因のトップを締め続けその割合は、全体の43%の約半数の人が糖尿病が原因で透析になっているのが現状です。逆に言えば透析になるような重度の腎不全を予防するためには、その原因である糖尿病を予防することが不可欠になります。日本では糖尿病の可能性が否定できない予備群も含めると糖尿病の患者数は全国で2000万人もいると言われており、その数は年々増え続けています。
グァバ茶には、タンニンやケルセチンといった数々のポリフェノールがたっぷりと含まれていて、これらのポリフェノールの中には糖質を吸収しやすい形に分解する酵素を阻害してくれる働きのあるものがあります。そのため食前や食中食後にグァバ茶を飲むことによって糖分の吸収が穏やかになり、食後血糖を下げてくれる効果が期待できます。
実際に、40歳以上の被験者にグァバ茶を飲んでもらい、食後の血糖値を調べた実験では食後の血糖値の優位な低下が認められています。糖尿病の中でも食習慣を始めとする生活習慣の乱れが原因とされる新型糖尿病は、食後血糖の大幅な上昇である血糖値スパイクが大きな発症要因の 1つと考えられています。食前から食後にグァバ茶を飲むことによって血糖値スパイクを抑えることができれば、それだけ糖尿病の予防効果が期待できます。
さらに腎臓を保護してくれる効果についてもグァバ茶は有用性が高いことが示されています。糖尿病腎症を患っているマウスにグァバ茶の熱水抽出物を7週間経口で投与した実験では、傷ついた腎臓の組織が有意に減少することが分かっています。また正常なマウスへの糖の負荷試験でもグァバ茶の熱水抽出物の投与によって血糖値の低下が認められることから、グァバ茶には高い糖尿病腎症予防、治療効果があるということが分かります。
そしてグァバの効能は、腎臓を守ってくれる作用だけではありません。糖尿病は血糖の変動だけではなく、肥満や高血圧などの様々なリスクファクターがあることが知られていますが、グァバ茶はこれらを予防することで関節的にも糖尿病の発症を防いでくれることが期待できます。例えばグァバの葉や果実には、豊富なカリウムが含まれています。私たち日本人の多くは日頃の食生活から塩分がどうしても過剰になってしまいがちですが、グァバ茶を飲むことで含まれるカリウムが体内の余分な塩分の排泄を促し、血圧を調整してくれる作用があります。
また、グァバ茶のポリフェノールによって糖の吸収が緩やかになれば、それだけ中性脂肪に変換されるエネルギーも減ってダイエット効果を得ることができるでしょう。平均年齢56.1歳の男女およそ1万人を調査した研究では、標準体重の人に比べて肥満の人は2型糖尿病を発症するリスクが6倍も高いことが分かっています。さらにこの研究では、遺伝的なリスクがあり、かつ肥満の人はそうでない人に比べ2型糖尿病を発症するリスクが14.5倍にも膨れ上がることが分かっています。さらに40歳から69歳の男女 4647人を18年以上に渡って追跡調査した日本の研究では、BMIが30以上の肥満では、死亡リスクが1.36倍に上昇することも分かっています。
リンゴ酢
リンゴ酢は腎臓に悪いという噂を、1度は聞いたことあるかもしれません。しかしリンゴ酢は腎臓に決して悪くなく、腎臓の健康のためにむしろ摂取していただきたい飲み物です。しばしばリンゴ酢が腎臓に悪いと言われるのは、リンゴ酢に豊富なカリウムが含まれているからです。ですがカリウムは腎血管の高すぎる血圧を下げてくれるため、むしろ腎臓の健康には良いです。ではなぜカリウムが含まれるリンゴ酢が腎臓に悪いと言われているのか、その理由は腎臓の機能が衰えていってしまうとカリウムが尿として排泄できなくなってしまうためと言われています。カリウムが排泄できなくなり、血液中にカリウムが溜まってしまうと重篤な不整脈のような病気が起こってしまうことが知られています。そのため透析をしている腎不全の方などは厳しいカリウム制限が指導されています。ですが、これはあくまでも腎不全に陥ってしまった場合です。検診などで多少クレアニン値の高値を指摘されたぐらいでは、まだ腎臓は腎不全の段階に陥っておらず、健康的な習慣によって腎機能を取り戻すことが可能です。
また似たような話に腎臓が悪い人はタンパク質を取らない方が良いという説もあります。これもカリウムと同様に腎機能が悪化した人だけに当てはまり、多少腎臓が衰えているぐらいではタンパク質を制限する必要はないでしょう。私たちの体の中では常にタンパク質が合成、分解されて新陳代謝が起こっています。腎不全になるとタンパク質の新陳代謝で出たゴミが血液に溜まり、カリウムの時と同じように様々な病気を引き起こしてしまいます。特に筋肉量が減りがちな中高年以上では、タンパク質は食物繊維と並んで重要な栄養素となってきます。
東洋医学×インディバで腎臓ケア
東洋医学の「腎」の臓は、西洋医学の腎臓とは異なり、腎臓そのものだけでなく、膀胱や耳も含みます。また水分の代謝にも大いに関係しますが、重要な働きとして生命の根である「精」を蔵していることが挙げられます。「精(先天の精と呼ぶ)」は、生まれながらに持つ体質的な精力のこととして考え、年齢を重ねる(老化)、病気で体力が低下などして腎機能が低下し、腎臓病など腎機能になんらかのトラブルが出てくると、体が冷えやすくなったり、寒気を感じやすくなったりします。
その他に東洋医学的な「腎」の弱りは、冷え、首肩こり、腰痛、霞目、手足のむくみ、リンパの腫れ、不安感、疲労感、倦怠感などの症状に現れます。
東洋医学では「腎陽(じんよう)」とも言い「腎には体をポカポカと温める働き」があると考えられています。
築賓(ちくひん):膝裏のシワと内くるぶしを結んだ線の下から1/3に当たる部分

そして腎機能を高めるツボとして代表的なのが「築賓(ちくひん)」です。腎機能が弱っている人は、ここを押すと強い痛みを感じますが、下半身の血流を改善し、冷えや、足のむくみ、腰痛などの緩和にも効果的です。「築賓」腎経のツボで、ふくらはぎの内側に位置します。
湧泉(ゆうせん):土踏まずの前の方の中央にあって、足の指を曲げたときに最もへこむところ

足裏の「湧泉(ゆうせん)」も冷えに効くツボとして、よく知られています。「湧泉(ゆうせん)」は、腎経の起点であり、足先から全身の血行を促進するツボです。
腎兪(じんゆ):背骨中心から指2本分外側

そして腰にある「腎兪(じんゆ)」は、脊椎(背骨)の両わきを通る膀胱経に属する「兪穴」の一つで、自律神経と内臓のつながりに作用するため、内臓疾患の治療には欠かせないツボです。特に腰痛治療に使われる定番ツボでもあり、腎兪への刺激は、腎臓の血流を直接増やす効果や腰痛の改善にも役立ちます。
これらは、腎機能が落ちている人にとって、大変有用なツボです。腎臓の血流が低下すると、体が冷え、血流が悪くなれば、腎臓のろ過機能は低下して、体内に老廃物が溜まります。そのため、インディバで温めながら、これらのツボを刺激することで、冷えや腎臓への血流を改善し、腎機能の向上に繋がります。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。