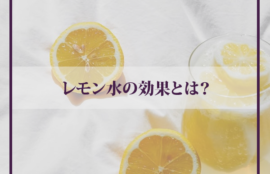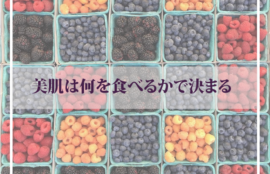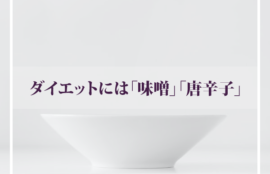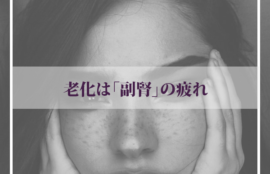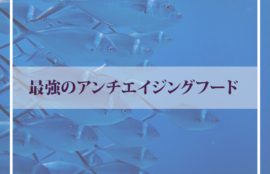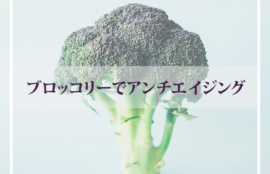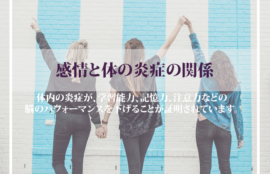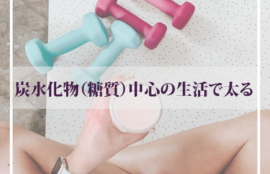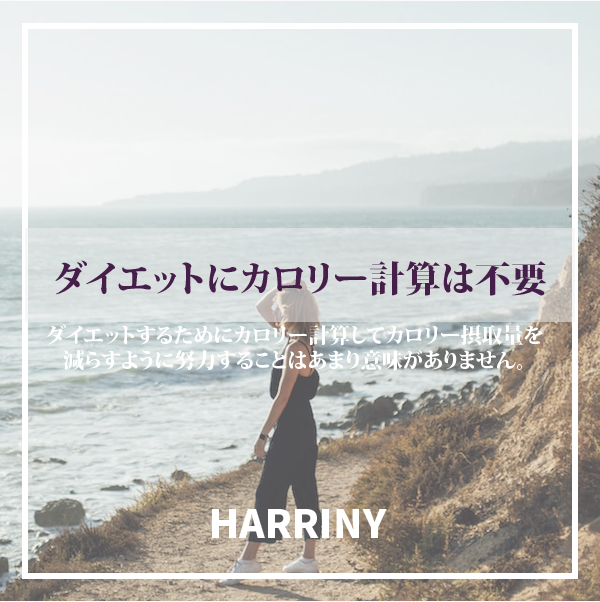
ダイエットするためにカロリー計算してカロリー摂取量を減らすように努力することはあまり意味がありません。つまりカロリー計算する意味はありません。
なぜなら、私たちの体はカロリーが多ければ太る、少なければ痩せるという単純なものではないからです。食品の多くにカロリーが記載されているため、ついついそれを確認することもあるでしょう。その背景には、摂取カロリーより消費カロリーの方が多ければ痩せるという「カロリー神話」が根付いているからです。このようなカロリー基準のダイエットは古い考え方です。古い常識をアップデートしましょう。
カロリー神話の誤解
ダイエットをして痩せるためには、摂取カロリーをできるだけ減らし、摂取カロリーを減らすためには食事回数を減らさなければならないと考えている方はとても多いのではないでしょうか。しかし結論から言えばダイエットに、カロリー計算は全くの無意味です。
カロリー神話の誤解の一つに、カロリーはどんな食べ物からとっても同じカロリーであるということが挙げられます。当たり前ですが、100kcalのプリンと、100kcalの魚を同じ量を摂っても体への影響は同じであるはずがありません。このように100kcalをどんな食べ物から摂っても同じと考えるのは大間違いです。私たちの体はもっと複雑で、同じカロリーでも体重に与える影響は全く異なります。また食べ物の質によっても、ホルモン、脳内化学物質、代謝などに全く異なる影響を与えます。このようにカロリーに“質”があり、それは体重を増やすカロリーもあれば、体重をあまり減らさないカロリーもあるということです。
そもそも、食品のカロリーとは食品に含まれている糖質やタンパク質、脂質を燃やした時に発生する熱量の合計です。その表示されているカロリーはどのように決まっているかというと、その値は実験室で計測された値であり、単に放出しているカロリーの燃焼量を証明しているにすぎません。要はその食品をただ燃やした時に発生する熱量がカロリーであり、体内でどのように消化吸収されて、体内でどのような働きをするのかは全く考慮されていません。人の体は実験室でもないし、計測上同じ値だったとしても、カロリーの“質”は全く異なるのです。
仮に200kcalのおにぎりを食べたとしても、体内で200kcalのエネルギーが生まれるわけではありません。また人によって消化能力も代謝能力も違い、同じ200kcalのおにぎりを食べたとしても、人それぞれ発生するエネルギーが違います。もっと言えば、糖質のカロリーと言っても、ブドウ糖もあれば加糖もあります。また油1gのカロリーは9kcalで統一されており、体に良い必須脂肪酸のオメガ3も有害なトランス脂肪酸もカロリーで見れば、同じキロカロリーです。しかし健康への影響は、体に良い油と悪い油で全く違います。
このようにカロリーをベースにして、ダイエットや健康を考えること自体が間違っていると言えます。食事を抜いてカロリー制限をするダイエットは、本人にとっては達成感があり、頑張って1日 1食に抑えたという気持ち的にはダイエットが上手くいっているような気がしてしまいます。しかし食事を抜いたり、食べ物が偏ることが続くと内臓機関の働きが衰えてしまい、一度衰えた機能は中々元の状態には回復しません。
断食のように食事を摂らない期間を決めて、内臓を休ませることを目的に食事制限を実施するのは健康的な効果がありますが、断食明けはお粥や豆腐などの胃に優しいものを食べる必要があります。このように1日2 日内臓を休めるだけでも、内臓の働きが回復するまでには時間がかかります。
ただ体重を減らすことを目的とした食事制限をして、内臓器官の働きを弱めて、空腹に耐えられなくて胃腸に負担がかかる食事をしてしまうと、当然内臓に大きな負担がかかってしまいます。
カロリー制限によるダイエット法は、摂取カロリーを消費カロリーよりも少なくするのが基本的な方針となりますが、人の体は、算数のように単純に測れません。私たちは起きている時も寝ている時も呼吸や内臓の活動、体温調整など様々な働きでエネルギーを消費しています。これらの基礎代謝で全体の6割の エネルギーを消費しています。
カロリー 制限をして基礎代謝に必要なカロリーを下回ってしまうと体は飢餓状態になったと判断し、体に入ってきた食べ物を蓄える機能が強化されます。つまり体内に入ってくるカロリーが少なくなると飢餓スイッチが入って、炭水化物を皮下脂肪に作り変えて蓄えようするため、食べていないのに痩せないとか、食べていないのにむしろ太ったことになります。
さらにダイエットを辞めた時はもっと大変になります。飢餓スイッチが入った状態で通常の食事に戻るため、体は摂取した食事をどんどん脂肪に変えて蓄えようとします。つまりリバウンドすると元の体重以上に太ってしまうのは、カロリー制限をしたことにより、体がよりエネルギーを蓄えやすい体質に変化してしまうからです。
本来ダイエットというのは、痩せるための食事方法ではありません。炭水化物や脂質の摂りすぎという不健康な食事から健康的な食事に戻すことが本来の意味でのダイエットであり、栄養バランスの優れた食事と最適な食事回数を心がけていれば、体は自然と最適な体重に落ち着いていくものです。
カロリー制限で体重が増える
単純に食べる量を減らすと、むしろ体重が減るのではなく太ることがあります。その理由は消費カロリーにあります。摂取カロリーを減らすと、一緒に消費カロリーまで落ちます。例えば、消費カロリーが2000kcalで今の摂取カロリーが2200kcalだから太るので、1500kcalにすれば−500kcal分脂肪が燃焼するので痩せるというのは間違った考え方です。
こんなことは80年前に行われた研究でも明らかになっていることです。この研究は戦争中の飢餓状態がどんな影響があるのか、回復させるためには何をするべきなのかを調べた研究です(ミネソタ飢餓実験)。被験者の普段の摂取カロリーを3000kcalから半分にして半年間生活してもらうと、肉体的に疲弊したり、精神的に落ち込んだり、代謝が落ちて冷えに悩むなど体に害を及ぼす結果が現れています。体重は予想されていた半分しか落ちていない結果になっています。安静時代謝量が40%低下し、体力も心拍数も平均体温も血圧も下がってしまうという結果が報告されています。
体重を維持している方の場合、例えば普段の摂取カロリーが3000kcalであれば、消費カロリーも3000kcalになっているはずです。その摂取カロリーを半分にすれば、消費カロリーの不足分1500kcalは体脂肪や筋肉を燃やしてエネルギーにする必要があります。この1500kcalは体脂肪に換算すると約0.2kgになり、1ヶ月で約5kg、1年で72kg脂肪が減る計算になります。しかし実際そんなことはあり得ません。
また、摂取カロリーを減らしているのに体重が増加するのは、摂取カロリーに合わせて体が適応して省エネの体になるため、摂取カロリーが余ってしまうからです。さらに、その状態で摂取カロリーが増えた場合、体の貯金(脂肪)として蓄えられます。それがリバウンドです。これがカロリー制限に失敗する理由であり、むしろ代謝を下げ、消費カロリーを下げ、体重を増やしてしまうダイエット法なのです。
カロリー制限でホルモンバランスが乱れる
ダイエットしようと思うのにできない、ですがそれは「ホメオスタシス」という体を現状維持しようとする機能があるからです。この機能が働くと、空腹ホルモンが増加して、お腹がすいたと四六時中感じやすくなり、食べても満腹になりません。さらにカロリー制限をやめてもすぐに戻らないのです。そのため消費カロリーが落ちていて、以前と同じ食事でも太りやすい体になっているのに、以前より食べてしまうことになります。さらに脳の感情を司る部位を活性化させ、意志力を発揮する部位を抑制することも分かっています。つまりカロリー制限によって、欲望に負けやすい脳に変化し、空腹を感じやすく、満腹感も得ず、消費カロリーも減るという散々な目に遭うのがこのダイエット法です。
ダイエットには栄養バランス
食べ過ぎたり、太りやすくなる原因は「脳」にあると言われています。食事制限は食べたいけど我慢することですが、栄養バランスを考えた食事で脳のホメオスタシス(食欲や体重を調整する機能)にアプローチすることで、脳の機能不全を解消して、自然に食欲や体重を調整することができます。
そこで大切なのが自律神経とホルモンを整えることです。栄養バランスが良い食事は、自律神経とホルモンのバランスを整え、自然と食欲が安定して食べる量が適正になります。逆に栄養バランスが悪ければ、自律神経とホルモンのバランスが崩れて食べ過ぎてしまうのです。
また、糖質制限をされている方も多いですが、糖質は太る、血糖値を上げると健康にもよくないことから始められます。しかし糖質制限は自律神経のバンラスを崩す典型的な栄養バランスが悪い食事方法でもあります。なぜなら糖質制限は、食べ物から糖質を摂らない分、体内で血糖を作り出す必要があります。それが「糖新生」で、タンパク質や脂肪を原料に肝臓で糖分が作られる仕組みです。この糖新生には自律神経が関与しており、糖質制限で糖新生が過剰になることで、交感神経が過剰に緊張して自律神経が乱れてしまいます。
一方で多くの論文で睡眠時間が短い人ほど食欲が増して食べ過ぎてしまうという結果が出ています。短くなる原因は睡眠の質にも関係しており、歯ぎしり、目が覚める、肩こりがひどいなどは、寝ている時に血糖値が下がる夜間低血糖)が原因ともされています。就寝中は血糖値が下がらないように仕組みがあるのですが、ストレスや糖質制限などにより体内で血糖値を上げようとコルチゾールがつくられ、肝臓に働きかけて血糖値を維持しようとします。しかしコルチゾールは血糖値だけでなく、体全体を興奮させるため目が覚めるなど睡眠の質を下げることになり、その結果食べ過ぎてしまうのです。
食事回数と食事時間
栄養バランスに優れた食事とは、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルの5大栄養素をバランスよく摂取することです。そして最適な食事回数は、もちろん個人差はありますが、基本的には人の体に備わっている自然なサイクルに合わせて、昼の12時から夜の20時までに2回を目安に食事をするのがおすすめです。
朝の4時から昼の12時までは排泄の時間のため、摂取する食べ物は胃腸を刺激して、排泄を促してくれる果物くらいに制限した方が望ましいです。逆に夜の20時から朝の4時までは、代謝や修復の時間帯であり、夜20時までに摂取した栄養素を体内で分解吸収して、体を作り変えるのに最適な時間となります。この時間帯に食事をして、余計なエネルギーを食事や消化に使ってしまっては代謝や修復を効果的に行えず、健康的な状態を保てません。
一方で、昼の12時から夜の20時までこそが消化期間が活発に働く、食べるのに適した時間です。この時間帯に栄養バランスに優れた食事を摂取して、消化吸収、代謝修復、排泄のサイクルを体の自然なリズムに合わせて行う結果、私たちの体は健康的な状態を維持できます。このサイクルに合わない不健康な食生活を続けていると、なんだか疲れが取れない、いつもだるい、常にイライラしたりストレスを感じる、1日 1食なのになぜか太るといった様々な不調を感じてしまうことでしょう。
ダイエットにはメンタル安定
「食べたいのに食べれない」というストレスはコルチゾールと呼ばれる食欲を強めるホルモンを作り出すことになります。それがカロリー制限、糖質制限、食事制限であり、それはストレスとなり、メンタルを崩す成功率の低いダイエット方法です。人は禁止にすると余計食べたくなるという心理的リアクタンスという特性があります。普段は我慢できていても、寝不足やストレスなどが重なると食欲が爆発し、我慢している分だけ反動で食べ過ぎてしまうのです。
そのためにも栄養バランスの良い食事が大切なのですが、もっと簡単にできる方法として1日の食事の1割を甘いものにして心を満たすことです。甘いものを上手く食事の中に取り入れてメンタルを安定させた方がダイエットに成功しやすくなります。
当たり前ですが、食事は栄養を満たすだけでなく、心を満たす作用もあります。甘い食べ物は脳内でセロトニンというホルモンを分泌して幸福感を作ってくれます。またセロトニンは食欲を抑える働きもあるため、食べ過ぎを防ぐことにもつながります。
良質なカロリーの食べ物
質の良いカロリーは、結論から申し上げると「たんぱく質」と「脂質」です。特に太りたくない方やダイエットをしている方ほど、なるべくたんぱく質と脂質からカロリーを摂取しましょう。
その理由は、体のインスリン(肥満ホルモン)が増えることで太るのですが、それはインスリンが体に糖分や脂肪を蓄えるという働きをしているからです。最もインスリン量が多くなる食べ物が、砂糖、麺、パン、白米などの精製された炭水化物です。一方でたんぱく質と脂質は炭水化物(糖分)に比べて、分泌されるインスリンの量が少なくて、太りにくいからです。
農林水産省によると1日の摂取カロリーの目安は、活動量の少ない成人女性で1400〜2000kcalです。しかしたんぱく質や脂質が中心の人と炭水化物が中心になっている人では太り方が全く異なります。
研究では、カロリー計算せずに良質なたんぱく質と脂質を中心にカロリー摂取するだけで、カロリーや量もあまり気にせずに痩せることができるということも分かっています。ちなみにたんぱく質や脂質を中心にすれば満足感を得られるため食べ過ぎになることも少なくなります。一方で精製された炭水化物は食欲が満たされることがないため、ついつい食べすぎになるということになります。
良質なカロリーの注意点
良質なカロリーであるたんぱく質と脂質が多く含まれているのは魚類です。肉類の多くも良質なカロリーになりますが注意点があります。
牧草を食べて育ったグラスフェッドビーフと穀物を中心に食べて育ったグレインフェッドビーフがあり、前者は健康に良いことが研究で明らかになっていますが、後者はその逆になります。この両者が健康に与える影響が異なるため、同じ赤み肉でも、体に悪いもの、良いものがあるのです。
また、油にも飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、オメガ6脂肪酸、オメガ3脂肪酸など沢山の脂肪酸がありますが、当然同じように健康に良い油と、健康に悪い油があります。この中で積極的に摂るべき油は、オメガ3脂肪酸です。
オメガ3脂肪酸の健康効果
オメガ3脂肪酸は必須脂肪酸と言われており、生きるために重要な脂肪酸ですが、体内でつくり出す(合成)ことができません。つまり食事から摂取するしかないのですが、日本人は圧倒的にオメガ3脂肪酸が不足しているという報告もあります。
オメガ3脂肪酸が多く含まれる食べ物の代表格は脂肪の多い魚であるイワシ、ニシン、サバ、アンチョビ、マグロ、天然サーモンなどです。またこれらの魚には良質なたんぱく質も多く含まれています。週に1から2回程度魚を食べることによって大きな健康効果を得られるでしょう。ちなみに養殖より天然の魚は、オメガ3が多い傾向があり、有害な汚染物質で汚染される可能性が低くなるため、できれば天然の魚を選びましょう。
魚以外では、ナッツです。特にくるみはオメガ3脂肪酸をたっぷり含んでいます。また植物性由来のくるみなどは、全死因死亡リスクが低下することも研究で明らかになっています。
そして同じ植物性由来でα-リノレン酸(ALA)が多く含まれているのが亜麻仁油です。亜麻仁油はそのままサラダにかけて食べることをおすすめします。亜麻仁油以外でも、チアシードオイル、フラッスシードオイルなどがあり、オメガ3脂肪酸が多く含まれるオイルです。ただしオメガ3脂肪酸は酸化しやすい油のため、炒め物で利用できないため、オリーブオイルなどの酸化しにくいオイルを炒め物には使いましょう。
バランスの悪い食事でダイエット!?
痩せるためにはバランスの良い食べ方をしなければならないという考え自体が間違った考え方です。現代の栄養学では、日々必要とされる栄養素の量が細かく規定されており、タンパク質は1日何グラム、摂取カロリーは何calまでとか、細かな計算が必要です。厚生労働省などが示している1日の必要栄養量の表を摂ろうとすると、必然的に食事量は多くなってしまいます。
しかし、人類の歴史を俯瞰すれば、毎日同じ量の栄養を摂って生きてきたわけではありません。自然界を見渡せれば、夏と冬で手に入る食べ物は全く異なり、必要とされる栄養素も違ってきます。つまり毎日同じようなバランスのとれた食事をすること自体、私たちの身体にとっては不自然なことかも知れません。
現代は飽食の時代とも言われ、健康のためには意識して少食にすることが不可欠です。しかし少食にすれば1日に摂れる栄養素の絶対量は少なくなります。だからこそ少食にすればするほど食べるもの一つ一つを慎重に選ぶ必要があります。
気軽にスーパーで買えるものとして「鯖缶」を勧めている研究者が多います。私たちの脳の60%は脂質で構成されており、その機能維持のためにはオメガ3が必要です。良質なオメガ3は青魚といった食材から摂ることが必要ですが、鯖缶には1/4食べることで1日に必要なオメガ3が十分に摂取できると言われています。また免疫力アップに欠かせないビタミンDも多く含まれています。さらに鯖缶一つで、牛乳1/2カップ分のカルシウムとリブロース1枚分のタンパク質が摂れるとも言われています。
食欲抑制にはタンパク質
ダイエットに取り組む多くの方に知られているのが、低カロリーで高タンパク質な鶏胸肉です。
タンパク質は、筋肉の修復や成長を助けてくれる役割があり、筋肉量が増えることで基礎代謝が向上しエネルギー消費量が増加します。これによって脂肪の燃焼が促進され、痩せやすい体質になります。さらにタンパク質が豊富な食べ物を食べることで、食欲をコントロールすることができます。なぜならタンパク質は炭水化物や脂質に比べて消化が遅いため、胃や腸で長く留まるため満腹感が持続し食欲が抑えられます。一方でタンパク質を摂取することによって、ペプチドYYやGLP1などの物質が分泌されると分かっています。これらの物質は食欲を調節する役割があり、満腹中枢を刺激して食欲を抑えてくれるという効果があります。
また、タンパク質は血糖値の上昇を緩やかにするため、インスリンの分泌が安定化します。インスリンが安定することによって、血糖値の急激な上下が抑えられて空腹感や食欲の増加を抑制してくれます。さらにタンパク質を摂取すれば、膵臓からグルカゴンが分泌されます。グルカゴンはインスリンとは逆の働きをし、脂肪細胞から脂肪を分解しエネルギーとして利用することで空腹感を抑える効果があります。
そして、タンパク質はレプチンとアディポネクチンというホルモンの分泌を促してくれます。これらのホルモンは脂肪組織から分泌され食欲を抑制し、エネルギー消費を促進する働きがあります。これらの様々な理由からタンパク質を摂取すると食欲が抑えられるので、鶏胸肉などのタンパク質はダイエットの強い味方であるということが分かります。
サツマイモで痩せる
サツマイモは、健康的に痩せられる食材ですが、おやつに甘いお菓子を食べてしまう人が置き換える場合という条件付きです。サツマイモは、その甘みからも分かる通り、高い糖質量を誇っています。サツマイモ100gの糖質量は、およそ30g、100gあたりの糖質が35gの白米と大差ありません。しかしサツマイモは、豊富な食物繊維を含むことから白米や甘いお菓子よりも糖の吸収が穏やかで、そこまで血糖値が上がりづらいというメリットがあります。血糖値の上がりやすさを示す指標であるGI値で比較すると、白米が88と非常に高いのに対し、さつまいもは55と非常に低く、抑えられているのが分かります。
また適量であれば甘いお菓子にはない数々の健康効果が認められています。特にヤラピンという非常に珍しい栄養素が含まれており、ヤラピンには高い整腸作用があり便秘を予防してくれる効果が期待できると言われています。またサツマイモの皮にはクロロゲン酸という抗酸化物質が含まれており、老化を予防してくれます。
逆に太るアーモンド
一般的に痩せるために有効だと考えられている食べ物の中でも食べすぎてしまうと逆に太ってしまう注意が必要な食べ物があります。逆に太る意外なダイエット食品はアーモンドです。アーモンドは食物繊維やタンパク質が多い上に、腹持ちが良く食欲を抑えてくれることから健康的に痩せられる食品というイメージをお持ちの方も多いでしょう。それはあくまで適量の場合の話に限り、どんな薬も飲みすぎれば毒となるようにどれほど体に良い食べ物であっても過剰に食べてしまっては健康を害する原因となってしまいます。アーモンドは良質 であるとはいえ良質な脂肪が含まれており、カロリーが高い食品の1つです。
例え糖質では無くとも、消費エネルギーをはかに上回る摂取カロリーは体脂肪へと変換されてしまうため、運動せずにアーモンドを食べすぎてしまうのは逆に太る原因になってしまいます。アーモンドの適量は1日20から30粒程度とされています。
ちなみに適量であれば、アーモンドには体重を減らしてくれる効果があることは科学的にも証明されています。慶応義塾大学の実験によれば、毎日25粒のアーモンドを食べ続けるだけで食事や運動習慣を変えなくても開始から半年で平均3.4kg痩せたことが報告されています。
食事前にコップ一杯のレモン水を飲む
白米やパン、甘いお菓子などの糖質を摂るとブドウ糖に分解されて血液に流れ込みます。糖質は血糖値を急激に上げますが、膵臓からインスリンが分泌されてブドウ糖が細胞の中に運ばれてエネルギーとして消費されていきます。しかし余ってしまったブドウ糖はインスリンの働きによって中性脂肪となって体内に蓄積し、肥満の原因になります。つまり太らないためには、ブドウ糖を余らせないように血糖値の上昇を緩やかにする必要があります。
レモンには血糖値の上昇を緩やかにする効果があり、ブドウ糖が中性脂肪に変わるのを抑える働きがあります。国内外の多くの研究でレモンが血糖値の上昇を抑制する効果があることが確認されています。例えば食事前に30mlのレモン水を飲んだ人は、飲まない人に比べて食後30分の血糖値の上昇を20%以上も抑えることができるという研究結果があります。これはレモンに含まれるポリフェノールやクエン酸が関係していると考えられています。またレモンの香りや刺激は、交感神経に作用して満腹中枢に働きかける効果もあり、空腹ホルモンのグレリンを抑え、満腹ホルモンのレプチンの分泌を促します。さらに痩せホルモンと言われるアディポネクチンの分泌も促進されます。
因みにレモンに含まれているビタミンCやエリオシトリンには高い抗酸化作用があります。抗酸化物質は、老化やがん細胞の増殖の原因となる活性酸素の発生を防いでくれるので、レモン水を飲むことで美容面や健康面にも良い効果が期待できます。
ダイエットの難しさ
ダイエットの難しさは、個人差や男女差が大きいことです。どのダイエットが自分に合うかを試すことが大切です。例えばリーンゲインズダイエットは合わなかった人が、日替わりダイエットは合っていたし、さらにイートストップイートも全然問題なかったという人もいます。世の中にある方法を試して、確かめることが自分に合ったダイエットが分かるようになります。特に女性でダイエットによる副作用が出た場合は、軽めのダイエットに変更することが大切です。
なぜなら、ダイエットでホルモンバランスが乱れる方が2割程度いると言われているからです。例えば食欲が異常に増える、冷え性の症状が現れることがあります。ダイエットで女性の生理に関わるキスペプチンの分泌量が減ると、脳が影響を受け、その結果、生理のサイクルや代謝の乱れ、食欲爆発に繋がったりします。
つまり、女性のダイエットでは、軽めのダイエットから試して、ホルモンバランスの乱れに注意しながら自分に合ったダイエットを選択することが大切です。もしホルモンバランスの乱れを感じるのであれば、摂取カロリー(食べる量)を減らさないようにして、食事を摂る時間帯を制限するなどしましょう。
また、激しい運動とダイエットを組み合わせないことも大切です。身体に不調が表れているのに、さらに激しい運動で身体を追い込むのは身体にとってストレスになってしまいます。もし激しい運動を組み合わせる場合は、運動の強度を調整して短時間で行うことを心がけましょう。
そして、タンパク質の量は意識的に増やしましょう。タンパク質を分解してアミノ酸が生成され、それが女性ホルモンの原料になります。そのためタンパク質量が不足すれば、ホルモンバランスの乱れに繋がります。
最後に大切なのが睡眠です。ホルモンバランスはストレスに左右され、ダイエット中はストレスへの抵抗力が下がるため、特に睡眠不足でダイエットすると疲労が溜まったり、代謝が落ちたりします。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。