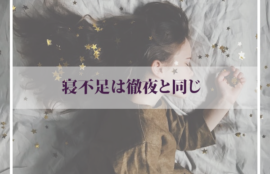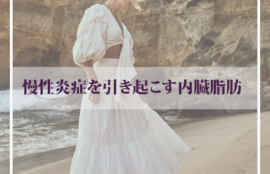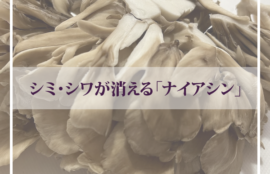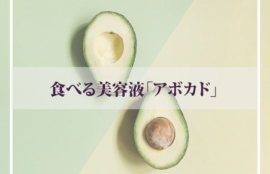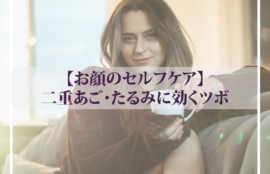どんな健康的な食品であってもデメリットが必ず存在しているため、バランスの取れた食事が1番大切です。まず重視するべきなのは、自分に合っているかどうかです。例えば納豆を食べてお腹を壊す人もいれば、発酵食品を食べて余計に腸内環境が悪くなってしまう人もいます。どんな健康食品にも必ずデメリットが存在し、例えば牛乳は前立線がんのリスクを上げることが分かっています。同じように非発酵大豆製品(豆腐類、高野豆腐、油揚げ、豆乳)には、膵がんの罹患率の上昇が確認されています。
実際、2020年6月に公開された国立がん研究センターのデータを見ると17年という長期間の研究で、他の膵がんに関連する危険因子をなるべく取り除き調査した結果、非発酵大豆製品の摂取において膵がんの罹患率が有意に上昇するという結果になっています。
さらに、前立線がんを発症している人が大豆製品を摂取することで最大で1.76%も前立線がんの死亡率が増加してしまうという報告も国立が研究センターから発表されています。またハーバード大学公衆衛生大学院の見解では魚に危険性があり、その有害性について魚は敵か味方かという記事をオンラインで発表しています。体に良いと言われているナッツやコーヒーもカビ毒があり、食べすぎれば体に害になることは明らかで、完全に安全で体に良い食べ物はないと言っても過言ではありません。
そのような食品のメリットデメリットを理解し、色々なものを少しずつ食べるのが一番良いと言われています。自分の体に特別合ってない食品でなければ、多少のリスクは受け入れて何でもバランスよく食べることが大切です。
バランスの取れた食事とは(1975年型の食事)
私たち日本人にとってバランスの取れた食事は、健康型の和食です。この研究は国立がん研究センターが2017年に発表した内容で、日本人の生活習慣病の予防と健康寿命を伸ばすために、どんな食事内容が良いかを調査したものです。
研究では、沖縄を含む全国10か所の地域、40歳から60歳の男女8万人を対象に特定の食品だけではなく、食事内容全体と死亡リスクの関係を14.8年もの間調べました。その結果、健康型の食事のスコアが高いほど全死亡リスクが2 割程度減少、特に循環器疾患が28%、心臓疾患25%、脳血管疾患は36%も減少するという結果になりました。
そして欧米食では、全死亡リスクが最大で12%低下、循環器疾患、心疾患、脳血管疾患についても同様に12%程度死亡リスクが下がり、発がん率に関しては健康型が5%から9%程度しか下がっていないのに対し、欧米型では9から13%と健康型よりも低くなるという結果になっています。確かに欧米型でも死亡リスクが下がっていますが、スコアが1番高いグループでは少しリスクが上昇していることから、ここでも偏った食事は返って死亡リスクを上げてしまうことが分かります。
このようにバランスの良い食事として挙げられる健康型の食事は、1975年に食べられていた食事内容になります。健康型の食事の大きな特徴は食材の種類と調理方法が豊富なことが挙げられます。
- 多様性:様々な食材を少しずつ食べる。主菜と副菜を合わせて3品以上を揃える。
- 調理法:煮る、蒸す、生を優先し、次いで茹でる、焼くを使う。揚げる、炒めるは控えめに。カロリーや脂肪を抑える調理法を工夫する。
- 食材:大豆製品や魚介類、野菜、漬け物、果物、海藻、キノコ、緑茶を積極的に摂取し、卵、乳製品、肉も食べすぎにならないように摂取する。
- 調味料:だしや発酵系調味料、醤油、味噌、酢、みりん、お酒を上手に使用し、塩や糖分の摂取量を抑える。
- 形式:一汁三菜、主食、汁物、主菜、副菜×2を基本として様々な食材を摂取する。
1975年型の食事で体に起こる変化
具体的に、1975年の食事を摂ると体に起こる変化は、実際にマウスと人の研究で分かっています。国民健康栄養素データを元に2005年、1990年、1975年、1960年、それぞれ一週間分の献立をフリーズドライにし、8ヶ月マウスに与えるという実験が行われました。その結果、2005年の食事群と比べて90年、75年の食事群では内蔵脂肪の量が少なく肥満になりにくいことが分かっています。これに加えて75年の食事群では、脂肪肝のリスクが低く、糖尿病発症リスクも1番低いという結果になりました。
1975年の和食が他の献立と違っていたのは、砂糖、豆類、果物、海藻、魚介類、たまご、香辛量の使用量が多かったこと、食材の種類が1番豊富でジュースなどの思考品は少ないというのが特徴でした。ちなみに寿命に関しても1975年の和食グループが1番長く、あえて老化を促進させたマウスの実験では、年を取るごとに差が見られるようになり、老化が1番遅くなっていました。さらに学習記憶能力も1番高くなり、加えて寿命も1番長かったという結果になりました。
これらはマウスの実験ですが、この研究の後、人のデータも取っています。実験では、20歳から70歳の軽度の肥満者を現代食群と1975年型食の2つのグループに分け、1日3食を28日間食べてもらいました。1975年型の食事を摂取した人は体脂肪体重ともに優位に減少し、悪玉コレステロールの改善、糖尿病の指標となるヘモグロビンA1cが減少、さらにHDLコレステロールが増加する結果になりました。つまり体重も減っただけじゃなく、その他の成人病に関係することに関しても改善されたことになります。
また、肥満ではない人でも同じように実験を行い、ここに運動も取り入れると75年のグループの方がストレスが軽減され、運動のパフォーマンスが上がりました。さらに腸内細菌にまで影響があり、悪玉菌の減少も確認され、人間にとっても1975年の和食は寿命を伸ばす可能性があることが分かっています。
この結果は100歳以上で元気な高齢者にも共通する内容でした。このように見ていくと特に栄養を気にするよりも、とにかく種類をたくさん取ることが結果的にバランスが良い食事につながっています。食品の多様性と健康寿命の関連を調査した研究では、食品の多様性の指数が0.1増加すると健康寿命は約4年も長くなるということが分かっています。この結果から見ても色々な食品を満面なく食べることは、バランスの良い食事に直結し、健康な食生活を送る上で1番大切とも言って良いほど重要なことです。
逆にあれも危険これも危険という情報を全て鵜呑みにして食品の種類を減らすことこそが食の多様性を減らし、バランスを崩してしまう大きな要因になりかねません。食品のデメリットだけを鵜呑みにしないことが大切です。
海藻を食べるとがんになる!?
海藻を食べると甲状腺がんのリスクが上がるという都市伝説があります。しかし海藻は適量を摂取する分には甲状腺がんを始めとするがんのリスクが上がるということはまずありえません。むしろ海藻は、毎日食べることによってがんの予防効果があることが科学的に実証されています。
なぜ海藻が甲状腺がんのリスクになるなどといった都市伝説が生まれてしまったのか、その根拠になっているのが国立がん研究センターの研究です。この研究では40歳から69歳の日本人女性約5万人を対象とした調査の結果で、確かに海藻の摂取量と甲状腺がんの発生との間に正の相関が見られるということが分かりました。
この研究では海藻類を毎日食べる女性では、週2日以下の人に比べて甲状腺がんのリスクが1.4倍になることが示されており、中でも乳頭がんという種類のリスクは1.7倍にも上がるということが報告されています。確かに研究結果だけを見れば海藻を食べるのはリスクに思えてきてしまうかもしれません。
甲状腺がんは、10年生存率が9割を超える比較的安全な癌の1つですが、がんの進行度によっては甲状腺の切除が必要になるなど決して侮ってはいけない病気の1つです。しかし研究にはいくつかエビデンス上の問題が存在しています。その問題は、適切に管理された臨床試験ではなく被験者のアンケート調査の回答を元にしていること、海藻の摂取頻度は分かっても摂取量が分からないこと、実際に摂取している海藻の種類が分からないこと、この3つに分けることができます。
研究内容の問題
まず1つ目は、どれほど研究内容が優れていてもそもそもの基礎となるデータの信憑性が低ければ、研究結果全体の信頼性が失われてしまいます。初めのうちはちゃんと回答していたアンケートだったかも知れませんが、途中で適当になる方もいるでしょう。さらに週に何回海藻を食べますかという質問に対し本当に明確に事実を答えられるような人は少ないでしょう。このようなことからアンケート調査というのは必然的に信頼性の低いデータの集まりとなり、それを総合して得られた研究結果もエビデンスレベルの低いものとなりがちです。
さらに重大な問題が2つ目の海藻の摂取量が分からないという点です。実は別の研究によってヨウ素の摂取量が増えることで甲状腺に悪影響が出るということは確認されていて、それについては医学的なエビデンスが確立されています。ヨウ素は甲状腺ホルモンの材料であるため、食べるとその多くが甲状腺に取り込まれます。そのためヨウ素不足だと甲状腺ホルモンの産生不足で体の元気が なくなってしまいますが、逆にヨウ素を摂りすぎても甲状腺ホルモンの合成が低下してしまうということが知られています。
このようなことから問題となっている研究では、ヨウ素の摂取量が甲状腺がんの原因となっているのではないかと仮定されています。しかし肝心の海藻の摂取量が分からなければ当然、ヨウ素の摂取量を割り出すこともできません。また海藻の種類によってヨウ素を含んでいる量は大きく異なります。そのため3つ目の食べた海藻の種類が分からないというのも大きな問題です。
例えば、ヨウ素の含有量だけで見てみると最もヨウ要素含有量の多い昆布と、ヨウ素の少ない海藻の1つの海ぶどうではヨウ素の差に歴然とした差があります。具体的には昆布のヨウ素含有量が1gに13.1mgに対し、海ぶどうのヨウ素含有量はわずか0.8mgです。
実際、国立がん研究センター自身も、この研究について直接ヨウ素摂取と甲状腺がん発生との関連を検討できなかったところがこの研究の限界ですとコメントしています。
また、海藻類の摂取に伴って他の良くない物質を同時に摂取してしまっているという可能性が考えられます。例えば海藻類には、塩気の多いものや多量の糖分で味付けされているような料理がたくさあります。そのような体に悪い海藻料理を頻繁に食べることで甲状腺がんを含む様々な病気のリスクが上がってしまっているという要因が考えられます。
重要なのはあくまで適量を健康的な調理法によって食べるのであれば、海藻はむしろ積極的に日々の食生活に取り入れたい食材であるということです。私たち成人の1日のヨウ素の推奨摂取量は130mgとなっており、ヨウ素の含有量が 圧倒的に多い昆布とひじきにのみ注意すれば、ヨウ素の摂りすぎによって甲状腺機能が低下する心配はないでしょう。
海藻の素晴らしいメリット
フコイダンによるがん予防効果
海藻を食べることで得られるのはがんの予防効果です。フコイダンは、海藻特有の成分のことで、これは水溶性食物繊維の一種です。水溶性食物繊維というのは私たちの腸内環境を良くしてくれるなど、そもそも体に良い作用が沢山あります。それに加え、フコイダンにはがんのアポトーシスを促してくれる作用があります。
アポトーシスというのは細胞が自ら死滅することを意味します。つまりフコイダンには、がんを予防したり、すでにできてしまったがんを縮小させる効果が期待できます。実際、フコイダンをがん細胞に与えた実験では、がん細胞の増殖が抑制されたということが分かっています。フコイダンは水溶性食物繊維のため、胃で分解されることなく生きたまま腸まで届き、そのままの状態で吸収されることで効果を発揮することができます。実際に癌を患いるマウスに、フコイダンを添加した餌を与えた実験では、フコイダンを投与されたマウスは、そうでないマウスに比べ明らかに生存期間が長くなったことが分かっています。
さらにアメリカの研究では、フコイダンに私たちの人体に対する悪影響がないことが確認され、すでに臨床応用も始まっています。ある病院では末期がんを含むがん患者82 人にフコイダンを飲用してもらったところ、そのうち8割の患者で容態の改善が認められたことが報告されています。
さらにフコイダンは、私たちの体に存在する免疫細胞を活性化することで免疫力を高めてくれる効果もあります。免疫細胞はウイルスや細菌のみならず、異常増殖してしまったがん細胞も駆逐してくれます。さらに最近の研究報告では、フコイダンを口から食べることで胃がんの原因となるピロリ菌を除去してくれる効果があることも示されています。さらにフコイダンは胃潰瘍や胃炎といった胃粘膜の炎症を修復してくれる作用もあります。
そして水溶性食物繊維であるフコイダンは、胃だけではなく、私たちの腸にとっても優しいと言える物質です。水溶性食物繊維は、便通を滑らかにする、善玉菌の餌になるなど腸内環境を整えるために様々な高能があることが分かっています。さらに最近では、フコイダンを始めとする水溶性食物繊維が肥満の予防にも良いということが分かっています。
私たちの腸の中には短鎖脂肪酸という脂肪燃焼を促す脂肪酸を作り出してくれる善玉菌が住みついており、水溶性食物繊には短鎖脂肪酸を作り出してくれる菌たちを増やしてくれる作用があると言われています。
このフコイダンは、海藻の中でも昆布やワカメ、藻といった褐藻類と呼ばれる海藻類類に含まれています。特にお勧めがもずくです。昆布はヨウ素の含有量が多すぎるため、食べすぎによって甲状腺機能の低下のリスクがあるというのはま事実ではあり、やはりワカメやもずくのような他の海藻の方がより安全です。中でももずくを酢であえたもずく酢であれば、酢が持つ健康効果も含めて得ることができます。
またメカブはもずくと似ており、いずれも同じ褐藻類ですが全く別の種類の海藻になります。そもそもメカブはワカメの根元の部分のことを言います。ワカメが健康に良いということは、すなわちその根元の部分であるメカブまた健康に良いということになります。それだけではなくメカブには、ワカメの数倍のフコイダンとミネラルが含まれているとも言われており、新鮮な生の状態のものであれば不飽和脂肪酸のEPAも豊富に含まれています。これは根元であるメカブには生殖細胞が存在し、細胞分裂が繰り返し行われることで栄養が凝縮しているためだと考えられています。
特にメカブに含まれるミネラルには海藻由来のカルシウムやマグネシウム、カリウムといった様々な栄養素がバランスよく含まれており、まさに食べる天然のマルチミネラルと呼ぶことができます。
心疾患の予防効果
海藻には心疾患も予防できる効果があることが分かっています。日本人の死亡原因の中で心疾患による死亡の13%が心筋梗塞を始めとするいわゆる虚血性心疾患によるものであると言われています。そして研究によって海藻の摂取が多い人ほど、虚血性心疾患の発症リスクが低いことが分かっています。
がんや心疾患の既往がない40歳から69歳の男女8万6113人を調査した研究では、男女ともに海藻類を多く食べる人ほど虚血性心疾患の発症リスクが下がることが分かっています。この研究では男性の場合、最大0.76倍、女性の場合、最大0.56 倍、血性心疾患のリスクが下がることが報告されており、海藻をよく食べる女性は全く食べない人に比べリスクがおよそ半分にまで減少することが分かりました。
このように海藻の摂取によって虚血性心疾患のリスクが下がる理由としては、水溶性食物繊維による血液サラサラ効果や血圧を適正値まで下げてくれる効果が関係しているとされています。さらに研究で分かったことは、このような虚血性心疾患のリスク低下は、ワカメや昆布といった食材のみならず、のりを食べることでも得られることです。意外なことにのりには、多くのタンパク質が含まれており、一般的な焼きのり100gあたりのタンパク質量は41gで、これはタンパク質源として有名な鶏胸肉のおよそ2倍の量に当たります。一説には、のり2枚で茹でた大豆15gに相当するタンパク質が取れてしまうとも言われています。
さらにのりには、非常に豊富なビタミンB1、B2が含まれているのも特徴です。ビタミンB1、B2は、糖質を効率よくエネルギーに変えてくれることで肥満予防や疲労回復に効果があることが分かっています。おまけにのりには、肝臓を強化してくれるタウリンも含まれいるため、内臓の中から体を元気にする作用 が期待できると言えます。
【コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。