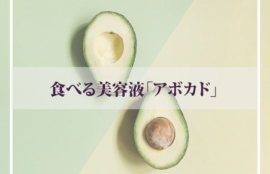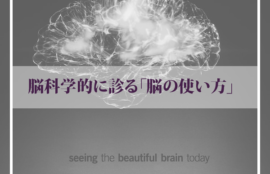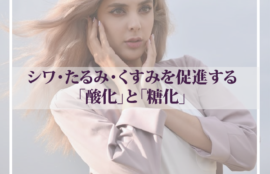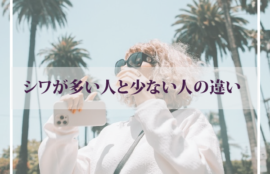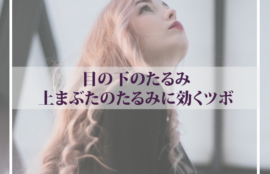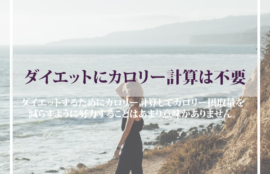脂質の一種である脂肪酸には3つの分類があります。一つは脂肪酸の長さによる分類です。この分類では飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸を含む長鎖脂肪酸、MCTオイルの主成分である中鎖脂肪、酸菌が作り出す短鎖脂肪酸の3つに分けられます。もう一つの分類は、炭素と水素の二重結合の有無による分類です。二重結合がないものを飽和脂肪酸、二重結合が一つのものを一価不飽和脂肪酸、二重結合が複数あるものを多価不飽和脂肪酸と言います。
そして最後の分類が不飽和脂肪酸の二重結合の位置による分類です。二重結合の位置によってn-3系やn-6系のようにオメガ3やオメガ6といった脂肪酸の名前が付けられます。
この中で体に良い脂質は短鎖脂肪酸と中鎖脂肪酸、そして長鎖脂肪酸の中で不飽和脂肪酸の3つです。このうち短鎖脂肪酸だけが食事から取ることができません。逆に摂取してはいけない体に悪い脂肪酸は長鎖脂肪酸の中の飽和脂肪酸だけです。しかし食事から摂取するほとんどの脂肪酸は長鎖脂肪酸のうち体に悪い飽和脂肪酸です。
飽和脂肪酸はなぜ体に悪いのか
食事からとった脂肪酸は、リンパ管や血中に入り、主に肝臓において代謝されます。この代謝の過程で飽和脂肪酸は悪玉コレステロールという物質を増やしてしまう働きがあります。コレステロールは細胞の膜を形成するために不可欠な物質であり、細胞に栄養や酸素を受け渡す毛細血管の細胞である血管内脂細胞にとって細胞膜は非常に大事なものです。そのような毛細血管にコレステロールを運んでくれるものがLDLです。コレステロールは血液には溶けることができず、コレステロールはLDLやHDL といった水に溶けやすい物質と一緒に血液中を流れていきます。
これらのうち血中から肝臓へ戻るコレステロールをHDLコレステロール、肝臓から血液中に出ていくコレステロールをLDLコレステロールと言います。しかしLDLコレステロールは、傷ついた血管壁を修復する過程で繊維化させ硬化させてしまいます。このように血管が硬化することを動脈硬化と言います。
最近では、悪玉コレステロールよりも小さい超悪玉コレステロールが問題になっています。超悪玉コレステロールは悪玉コレステロールよりさらに小さく血管壁の内側に潜り込んでアテロームという粥状のプラークを作ります。このプラークが血管を細くし、そこに詰まった血液の塊がアテローム血栓となって様々な病気を引き起こします。つまり代謝されることで悪玉コレステロールや超悪玉コレステロールを上げてしまう飽和脂肪酸は、間接的に動脈硬化やアテローム血栓のリスクファクターとなります。
このような飽和脂肪酸を多く含む食材の1つが牛タンで、100gあたりの飽和脂肪酸量はおよそ7.5gで、これはホイップクリームとだいたい同じぐらいの飽和脂肪酸量が含まれています。そしてあん肝は海のフォアグラとも呼ばれており、カロリーは100gで400kcalもあり、フォアグラと同じようにあん肝の持つ脂肪酸のほとんどが飽和脂肪酸です。またカマンベールチーズに含まれている飽和脂肪酸は100gあたり15gです。これは牛タンのおよそ2倍です。
悪玉コレステロールと酸化LDL
悪玉コレステロールが動脈硬化を促進するというのが定説でしたが、最近では毛細血管に関する細胞レベルのミクロな研究によって実は私たちの動脈硬化の 原因は悪玉コレステロールではなく、酸化LDLという別の物質であることが分かってきました。
従来、心筋梗塞や脳血管疾患などの原因となる動脈硬化は、血中の悪玉コレステロールが増えることだと考えられてきました。私たちの細胞に栄養や酸素を届けている毛細血管は髪の毛の1/10ほどの細さしかなく、その中を塩分や老廃物など様々な物質が流れています。そのため毛細血管の内壁には微小な傷がついています。そのような毛細血管内の傷を修復するために体ではコレステロールが用いられます。コレステロールは血管内壁に存在する血管内皮細胞の細胞膜の原料となるため毛細血管にとってコレステロールは一種のバンドエイドの役割を担います。
そしてそのようなコレステロールを肝臓から血管へと運んでくれるのがLDLです。私たちの血液は水からできており、当然油は溶けることができません。そのため血液中では LDLやHDLという運び屋と一緒に存在しています。このうち肝臓から血液に運ばれるものをLDLコレステロール、その逆をHDLコレステロールと呼びます。
従来は、LDLコレステロールが血管にコレステロールを沢山運ぶことで血液がドロドロになり動脈硬化が促進されると言われてきました。このためLDLコレステロールは悪玉コレステロールと呼ばれていました。しかし最新の研究により動脈硬化の原因となるのはLDLコレステロールではなく酸化LDLという別の物質であることが分かっています。
酸化LDLとはその名の通りLDLコレステロールの運び屋であるLDLが酸化してしたものです。酸化というのは一言で言うと物質が錆びてしまうこと、つまり何らかの原因によってLDLが錆びつくことで毛細血管において動脈硬化が促進されてしまうのです。
体のミクロな機能を観察する最新の研究により、酸化LDLが発生する要因には内因性と外因性の要因の2つがあることが分かってきました
LDLコレステロールには様々な大きさのものがあり、中でも非常に小さいものをsd-LDLと呼びます。sd-LDLは非常に小さく血管の壁を通り抜けて血管壁の内側に入り込みます。sd-LDLは血管壁の中に本来存在してはいけないものであるため、それが血管壁内に入り込むことで大量の活性酸素が発生します。この活性酸素は非常に強い酸化力を持っており、血管壁内に忍び込んだsd-LDLを一瞬で錆びつかせてしまいます。こうしてできるのが内因性の酸化LDLです。
一方で外因性の酸化LDLは、私たち自身が酸化コレステロールを食事から摂取することで増加すると考えられています。この酸化コレステロールは、酸化LDLとは別の物質です。そもそも食品には沢山のコレステロールが含まれていますが、例えば卵にはコレステロールが沢山含まれているから体に悪いと言われたことがありましたが、実は食物中のコレステロールは血中脂質にあまり関与しないことが明らかになっています。
そのように私たちの体にとって本来、害のないコレステロールはあくまで酸化されていない場合です。食物の中で酸化されてしまった酸化コレステロールは外因性の要因によって酸化LDLを上昇させるため、通常の食品中のコレステロールと違い危険な物質です。酸化コレステロールはコレステロールが食品の加工中に加熱処理を受けて酸化したものであり、食品加工の段階で酸化するため、インスタントラーメンやレトルト食品などの加工食品に大量に含まれています。このような加工食品に含まれる酸化コレステロールを摂取すると、体内に入った酸化コレステロールは正常なLDLまで酸化させてしまいます。
このようにして内因性と外因性の2つのメカニズムによって血管壁内に侵入した酸化LDLを体の免疫システム、主にマクロファージという免疫細胞によって除去されます。このマクロファージは抗体によって外敵を攻撃するB細胞や細胞を直接攻撃することで外敵を排除するT細胞と異なり、外敵を丸ごと飲み込んでしまう貪食作用という免疫機構を持っているのが特徴です。
しかし、酸化LDLは敢えてマクロファージに食べられることで血管にさらなる害を及ぼします。なぜなら酸化LDLを食べたマクロファージは泡沫細胞という別の物質に変化するからです。泡沫細胞とは大量の酸化LDLを取り込みすぎた マクロファージが泡状に変化してしまった細胞のことで、泡沫細胞は過剰な活性酸素を産生するのに加え、アテロームと呼ばれるドロドロの塊を形成します。そしてこのアテロームが血管の内壁に沈着することで動脈硬化が進むというのが最新の研究で分かっています。
血液検査の数値について
悪玉コレステロールと呼ばれるLDLコレステロールは、全身にコレステロールを運び、血液中のコレステロールを増やします。血液中のコレステロールの増加は、血液をドロドロにして血管にダメージを与えます。同じコレステロールでも善玉のHDLコレステロールの低値は良くありません。HDLコレステロールは、コレステロールを肝臓へ回収し血液中のコレステロールを減らしてくれるコレステロールです。
LDLコレステロール÷HDLコレステロールの値は1.5以下が理想だと言われています。また新たに注目されているレムナントコレステロールがあり、検査項目の総コレステロールからLDL、HDLコレステロールを除いたものです。このレムナントコレステロールがプラークを最も作るコレステロールです。プラークは、血管にできるコブのことで、動脈効果を引き起こします。プラークは、免疫細胞のマロファージがコレステロールを食べることで生じます。そしてマクロファージは悪玉コレステロールの4倍のレムナントコレステロールを食べると言われています。
動物実験で血管のプラークの70%がレムナントコレステロールによるものだったことも分かっており、レムナントコレステロールが高いと糖尿病のリスクが高まることも分かっています。もう1つの脂質の項目、中性脂肪の高値も良くありません。中性脂肪は悪玉コレステロールを増やし、善玉コレステロールを減らすことが分かっています。
肉食のウソ
肉を毎日食べていては健康的ではないとか、病気のリスクが高まるのではというイメージを持っているのではないでしょうか。しかし科学的根拠のほとんどが、肉の脂に含まれる飽和脂肪酸を大量に食べると体に悪いが適量ならば健康に良いとしています。ただ肉の種類はとても多く、含まれる栄養素の量は種類など様々な要因により、大きく異なります。
一方で、糖質制限ダイエットに関して、ご飯さえ食べなければ肉はどれだけ食べても良いといった情報があります。しかし肉の摂り過ぎは、血中の中性脂肪や悪玉コレストロールを増やしたり、肝臓や腎機能に負担をかける恐れがあります。結局何だって摂り過ぎは良くはありません。
肉
ほとんどの研究で家禽肉は健康に良いことが示されています。家禽類のタンパク質は消化されやすく、カロリーに占める割合も低く、そして脂質の多くが不飽和脂肪酸です。2009年アメリカの国立がん研究所の研究者たちにより、肉の摂取と死亡率に関係があるかどうかの調査が行われました。鶏肉などの白身肉の摂取量がもっとも多い人々で、全死亡率、特にがんによる死亡率が、白身肉の摂取量が最も少ない人々よりも低いということが分かっています。
一方で、牛肉や羊肉といった赤身肉は、ほとんどの科学研究の結果では、赤身肉も含め肉は健康に悪いから食べるべきではないと言い切ることはできません。例えば2014年に発表されたある研究では、赤身肉の摂取量がもっとも多いグループでは、最も少ないグループより全死因の死亡率が29%高いとされました。この研究で赤身の摂取量がもっとも多い人々は、毎日1から2食分食べる、摂取量が最も少ない人々は週2食分程度食べるという定義でした。週2食分程度の赤身肉を食べる人々は、この結果を見て赤身肉が体に悪いから食べる量を減らそうとは思わないのではないでしょうか。
グラスペットビーフ
日本ではあまり牧草飼育の牛肉というのは生産されていません。一方でニュージーランドなどでは牧草飼育を国を上げて行っている場所がたくさんあります。日本でも近年、牧草飼育の重要性というのは多くの方に知られるところになってきました。
一方でグラスペットとよく似た表現にグレインフェッドビーフというものがあります。グラスペットは牧草だけを食べて育った牛の肉のことですが、一方で日本の国産牛や和牛は、牧草だけではなく穀物を与えて育てられていることから穀物を意味するグレインの名前をとってグレインフェッドビーフと呼ばれています。
グレインフェッドビーフはそもそも穀物を食べて育っている牛ということで普通に飼育されている牛とそこまで差があるわけではありません。グレインフェッドと書いてあるものは、脂肪が乗って美味しいなどといったメリットはありますが、健康効果が高いとは言えません。
一方でグラスフェッドビーフは、様々な健康上のメリットがあります。例えば牧草のみを食べて育つということで脂肪分が少なく赤みが多い肉質になります。この脂肪分が少ないというのは、牛肉の脂肪分である飽和脂肪酸が心疾患などと関連があることが疑われていることから考えると大きなメリットです。また脂肪分が少ないということは、それだけ逆にタンパク質の量が多いということでもあります。
また、量が少ないとはいえ当然脂質が含まれていますが、含まれている脂質も 良質な脂質だと言われています。例えば魚に含まれている不飽和 脂肪酸のオメガ3脂肪酸もグラスペットビーフは豊富だと言われています。その他に非常に珍しい脂質である共役リノール酸も多く含んでいます。この共役リノール酸はまだ研究が進んでいる最中ですが、非常に高い健康効果を持つと言われています。
さらに、グラスペットビーフは鉄分やタウリンといったミネラルを通常の牛肉の約3倍も含んでいる研究結果があります。こういった豊富なミネラルやビタミンを含んでいるため、疲労回復に役立ってくれたりと様々な健康効果を与えてくれます。さらに牧草由来のβカロテンやビタミンE などの抗酸化物質もたくさん含まれています。
一方で安全性が高いというのもグラスペットビーフがおすすめできる理由の一つです。通常飼育されている牛は、抗生物質の投与やホルモン剤の投与など、あまり良くないと言われている育てられ方をしている可能性があります。グラスペットビーフはこういった抗生物質の投与やホルモン剤の投与が行われている可能性が極めて低くなります。
どんなお肉を食べるべきか
牛肉、豚肉、鶏肉を食べるべきかを確認しましょう。牛肉には積極的に取りたいミネラルである鉄のほかに亜鉛などのミネラルが豊富です。飼料をふんだんに与えて太らせた霜降り肉よりグラスペット、牧草飼育の赤身肉の方が良質な脂肪酸であるオメガ3脂肪酸が多く含まれています。ただし牛の飼育の際に、ホルモンや抗生物質を使用されています。実際アメリカ牛にはエストロゲンなどのホルモン剤や抗生物質が使用されており、それらによる乳がんや前立腺がんのリスクも指摘されています。この飼育の際のホルモン剤や抗生物質に関しては日本、ヨーロッパ、オーストラリアの牛肉は比較的安全だと言われています。
豚肉は多くの栄養素を豊富に含んでいる食材で、タンパク質と鉄はもちろんエネルギーの代謝を助けるビタミンB1、肌や体内の粘膜を健康に保つためのビタミンB2、そして筋肉の生成や血液の産生をサポートするビタミンB6も含んでいます。特に注目すべきはビタミンB1を大量に含んでいる点です。例えば豚肉100gを食べるだけで日本の成人男性が1日に必要とするビタミンB1の量の85%を摂取することができます。また豚肉に含まれているビタミンB1は、加熱によっても容易に壊れることがなく体内での吸収率も非常に良いです。
鶏肉の一つの特徴は他の種類の肉に比べて消化しやすいことです。また鶏肉には体に必要なアミノ酸が多く含まれ、その中にメチオニンという特別なアミノ酸があります。メチオニンは肝臓の働きを向上させ、脂肪肝の予防に役立つとともに体全体の老化を遅らせる効果もあります。さらに鶏肉にはイミダペプチドというアミノ酸が結合した成分が含まれています。この成分は疲労を軽減する効果があると言われています。例えば鶏胸肉の50gにはイミダペプチドが 200mgも含まれているため、鶏肉は栄養価が高い食べ物と言えるでしょう。こちらも豚肉同様、疲労回復に優れていますので筋トレの後のタンパク質摂取源として有効活用することができます。
その他にもラム肉や馬肉、ジビエなどの肉があります。ラム肉は鉄分や亜鉛が豊富で、Lカルニチンという脂肪燃焼効果の高い成分も含まれています。馬肉はタンパク質量が牛肉に匹敵する栄養満点の肉で鉄分の宝庫です。カルシウム も多く含みます。またジビエ料理で鹿肉は高タンパクで鉄分も豊富です。さらに自然環境で育った野生動物の体は天然の栄養豊富な食事と運動によって作られているため、食用の肉と比べて栄養価が高いというのもポイントです。
魚
魚の身も肉です。肉を食べることは不健康的だと主張する人たちのほとんどの場合は、魚などの飽和脂肪酸があまり含まれない肉は良いとされています。実際に地中海食をはじめ、科学的根拠のある多くの食事では果物、野菜、オリーブオイルなどの不飽和脂肪酸が多い油に加えて、魚を摂取することが推奨されています。
しかし魚の肉の中でも健康意識の高い人々にとっては極力避けるべきとされているのがマグロです。長く生きするマグロの体内には水銀が蓄積され、それを多量に摂取すると子どもはもちろん大人でさえ脳に障害が起こる可能性があります。また一度体内に入ると排出されにくいという特徴を持っています。他にもサメやメカジキといった長く生きて、大きくなった魚ほど体内の水銀量が多いです。
また別の研究では魚・魚油による心疾患リスク、魚に含まれる水銀、ダイオキシン、ポリ塩化ビフェニルの摂取による健康リスクに着目して、魚を食べるべきか食べないべきかの調査が行われました。ほとんどの健康的な大人にとって水銀の含有量に関わらず、魚を食べることの利益の方が大きいという結果になりました。
妊婦さんに関しては一切魚を食べるべきではないというわけではなく、オメガ3脂肪酸が少なく、水銀が多い魚を食べないように気をつければ、魚はほどほどに食べることの利益がリスクを上回るという結果になっています。
塩
塩は健康に悪いという説が一般的になっており、確かに塩分の摂取が高血圧の人にとって良くない可能性を裏付ける根拠があります。例えば2014 年に医学誌に発表された研究によると、10万人以上のデータを基に、塩分摂取量が多い人の方がそうでない人より血圧がかなり高いということが分かりました。さらに同じ研究グループは塩分摂取量が特に多い人々では、心臓発作や心不全、脳卒中の発症率が高いということも報告しています。
一方で、実際は塩分が足りていない人々が多く存在している可能性も指摘されています。塩の摂取量は多すぎてもいけないが少なすぎても健康に悪く、先ほどの研究では塩分の多い 食事をしている人々と塩分の少ない食事をしている人々との比較もされています。その結果、塩の摂取量が1日3g未満の人々は、安全圏とされる3から6gの人々、7g以上の人々よりも死亡リスクや心血管事象のリスクが高かくなりました。他の研究結果でも塩分は通りすぎても少なすぎても心臓や血管の病気にかかりなくなる可能性が高いという結論が出ています。
そして最近行われた塩の摂取が高血圧の人とそうでない人に異なる影響を及ぼすかどうかを調査する研究では、高血圧の人の場合は塩分の摂取量が安全圏内だった人々よりも過剰 摂取した人々の方が心疾患の発症率や死亡率がはるかに高くなり、しかし正常血圧の人々は塩分摂取量が多くても、それらのリスクは高くなかった。そして意外なことに高血圧の 人は塩分の過剰摂取以上に塩分の不足による悪影響の方が大きい可能性が示唆されました。
病気になりたくなければ減塩しなさい、血圧が高いなら塩分を摂るのを控えなさい、その指示に従い塩分の摂取を極端に減らしてしまうことは果たして本当に正しいのか、むしろ有害である可能性が明らかになっています。
スイカの種とミカンの筋
スイカの種は全部噛み砕いて食べましょう。実はスイカの種にはα-リノレン酸という不飽和脂肪酸の一種が豊富に含まれています。α-リノレン酸はn-3系の不飽和脂肪酸で青魚に含まれているDHAと同じオメガ3の一種です。このオメガ3には善玉コレステロールを増やしてくれる働きがあります。善玉コレステロールは血液中の増えすぎたコレステロールを肝臓に戻してくれる働きがあるため間接的に悪玉コレステロールや超悪玉コレステロールによるタメージを食い止めてくれます。
ミカンの白い筋には、細胞の中から若返る物質の「ヘスペリジン」が含まれています。スイカの種を吐き出すのがNGであるようにこのようにミカンの筋を取ってしまうのも大きな間違いです。むしろミカンが持つ栄養素の主役はこのヘスペリジンにあります。ヘスペリジンは、血中の悪玉コレステロールや超悪玉コレステロールを下げてくれる以外にも、細胞内の活性酸素を除去して細胞を若返らせる抗酸化作用や血圧の上昇を抑える効果、また抗アレルギー作用まであると言われています。
老化を遅らせるスイカ
スイカには非常に優れた抗炎症作用があります。スイカを中心とした3ヶ月間の抗炎症食によって過体重や肥満の成人の炎症レベルが低下した研究もあります。このような効果は、抗炎症作用、抗酸化作用に優れたリコピンやコリンといった優れた栄養素を豊富に含んでいるからです。
他にもスイカはカリウムを豊富に含んでおり、食事でとりすぎた塩分を尿中に 排泄する働きがあります。さらにスイカに含まれているシトルリンという成分は、血流改善の効果があります。またスイカにはビタミンCが豊富に含まれており、抗酸化作用によって老化が促進するのを防ぐ効果を持っています。このビタミンCは、コラーゲン生成を促進するという働きもあります。
一方で、スイカにはβカロテンも含まれており、体内でビタミンAに変換され、目の健康のために 重要な働きをし、強力な抗酸化作用によって体内が酸化するのを防いでくれます。因みにビタミンAはサプリメントなどで摂取するとむしろ健康に悪いなどと言われているため、摂取方法は基本的には野菜など食材からそのまま直接摂るのが良いと言われています。
地中海食が長寿をもたらす理由
ブルーゾーンという言葉を聞いたことがあるでしょうか。ブルーゾーンとは世界5大長寿地域のことを指し、イタリアのサルデーニア島、日本の沖縄、アメリカのロマリンダ、コスタリカのニコヤ半島、ギリシャのイカリア島などが該当します。こうしたブルーゾーンのリストを見ると長寿地域のいくつかが地中海の島々であることに気づきます。これらの島々の多くで地中海食が食べられていることから、今の地中海食ブームの要因になっています。
しかし、地中海食は良いことだけではなく、特に地中海食で多く食べられる穀物は健康にとって大きなマイナス要素なることが分かっています。穀類を食としているイタリア人は関節園の発症率が高く、特にサルデーニア人は自己免疫疾患の発症率が高いことで知られています。
そのためブルーゾーンの住民は、地中海食を食べているから健康で長生きなのではなく、穀物をたくさん食べているにも関わらず健康で長生きできる秘訣を持っていることになります。
そして意外なことに、彼らが食べないものに大量の動物性タンパク質が挙げられます。このことは8年間に渡って行われた大規模な調査でも、動物性タンパク質の摂取量が少なかったグループは、動物性タンパク質の摂取量が多かったグループに比べて炎症マーカーが低く、全身の炎症が起こりづらいことが分かっています。
肉が体に良い、悪いの論争は様々なファクターが絡んでおり、結論には至っておりませんが、何れにせよ食べ過ぎには注意して、バランス良い食事を心がけることが大事と言えます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。