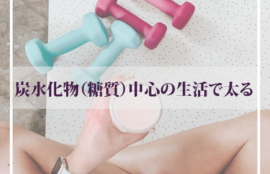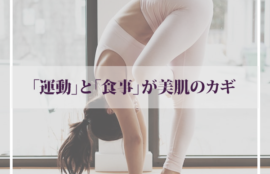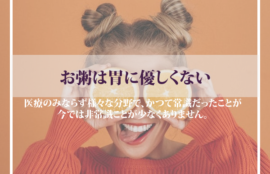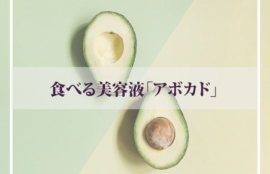実は光と睡眠の関係で、光によって睡眠の質が下がり、それによって9倍も肥満のリスクが高くなってしまうことが分かっています。寝る前にスマホやパソコンを見ちゃいけないとか、部屋を暗くして寝た方が良いとかありますが、睡眠のメカニズムに光はどう関係して、どうして人は眠くなるのかを理解することがまずは大事です。
私たちの脳には色々な部位があり、その部位が情報を伝達し合うことで起きたり、眠ったりしています。睡眠にとって特に大事なのは脳の奥の視床下部の中にある視交叉上核という1から 2mmほどの大きさの組織です。視交叉上核は両目の視神経が交わる場所の少し上にあり、体内時計と言われるサーカディアンリズムを生み出しています。
体内時計であるサーカディアンリズムは、24時間周期で睡眠と覚醒を繰り返すリズムのことで、光による明暗や出勤時間などの社会生活、食事や睡眠環境などで調整されています。その中でも1番強力な効果を持つのが光です。人間を光も時計もない真っ暗な洞窟の中で生活させると人は大体25時間周期で生活するようになります。人間の本来のリズムは25時間であり、サーカディアンリズムによって24時間周期で起きたり眠ったりするということになります。
朝日を浴びると夜寝むり易くなるのは、朝光を浴びてから14時間後くらいに睡眠ホルモンのメラトニンが作られるからです。人が眠くなる理由に疲れによる脳と体を休ませて、体の機能を一定の状態に保とうとするホメオスタシスと言われる働きによるものと、その日の疲れにはあまり関係なく一定の時間になると眠くなるというサーカディアンリズムによるものがあります。
サーカディアンリズムには視交叉上核がとても大きく関係していて、目で光を感じた14から16時間後くらいに視交叉上核が松果体と言われる脳の真ん中にある部位にシグナルを送ります。そして睡眠ホルモンのメラトニンを作ることで眠くなります。しかし夕方から夜の間に両目に光を浴びることで視交叉上核が朝や昼間と勘違いしてメラトニンの生成が遅れたり、分泌が止まったりしてしまいます。つまり夜にスマホやパソコンを見ちゃいけないのは、夜に強い光を目に浴びることで視交叉上核が混乱してしまうからです。
例えば、19時から22時までブルーライトカットのスマホでゲームをしたグループと、ブルーライトをカットしないスマホでゲームをしたグループを比べた実験では、ブルーライトをカットしないスマホを使ったグループのメラトニン分泌が止まり、分泌量が上がるまで時間がかかったという結果が出ています。
睡眠と肥満の3つの関係
睡眠不足だと誘惑に負けやすくなる
私たちの意思力は無限にあるわけではく、限界がある意思の力は忙しい時や悩みを抱えている時、また寝不足の時にはその力が消耗してしまいます。ダイエットという強い意志を必要とする目的を達成するためには、忙しい時期を避けたり、悩み事などのストレスが少ない状態を作ること、そしてしっかりと睡眠を取ることがとても大切です。
寝不足で意思の力が弱まるのは、欲望をコントロールしたり、目標を立てて計画的に実行するなど冷静な判断をして行動するには、脳の前頭前皮質という部分が大きく関わっています。睡眠不足によって脳への血流の低下が起こり、前頭前皮質の機能が低下してしまいます。
意思決定や自己コントロールに必要な前頭前皮質や頭頂葉の血流が睡眠不足後は減ってしまっています。つまりダイエットには食べたい衝動を抑えながら目標を立てて計画的に行う実効力が必要ですが、これを成し遂げるには当然、前頭前皮質の力が睡眠不足で弱まってしまいます。
睡眠不足によってホルモンバランスが崩壊
胃から分泌されるグレリンによって食欲が湧き、高肥満ホルモンと言われるレプチンが脂肪細胞から分泌されて食欲を抑制します。しかし睡眠不足になるとグレリンが増えて、レプチンが減少します。例えば2日間で4時間しか寝ていない状態だと血中のグレリンが28%増加し、レプチンが18%減少して、空腹感や食欲も23%増加することが分かっています。
また、シカゴ大学の研究では睡眠不足が4日続いた後では糖尿病や新血管疾患などを悪化させる血中の遊離脂肪酸が15から30%を上昇し、脂肪をもっと摂りたいという欲望が強まるためによりジャンクフードを食べたくなってしまうことが分かっています。
その他にも、アメリカのピッツバーグ大学で高校生245人を対象に、年齢、性別、人種、BMIと独立して睡眠とインスリン抵抗性との関係を検討した研究では、睡眠時間が短いことでインスリン抵抗性指数が高くなることも明らかになっています。インスリン抵抗性が上がることは肥満になりやすくなることでもあります。因みに6時間睡眠の人が、一晩に1 時間睡眠時間を増やすだけでインスリン抵抗性が9%改善するという報告もあります。
睡眠時間が短いと活動時間が増えてエネルギー消費して痩せると思っている人もいますが、実はその反対で寝不足によってどんどん太りやすい体へと変わってしまいます。アメリカのコロンビア大学が2005年に行った30から60歳の男女5000人を対象に調べた研究によると、平均7から9時間の睡眠時間の人に比べて4時間以下の睡眠の人の肥満率は 73%も高く、5時間睡眠の人でも肥満率は50%高いことが分かっています。
寝不足で基礎代謝が落ちる
基礎代謝は、内臓を動かした、呼吸をしたり、体温調節したり、生きているだけで消費するカロリーのことです。基礎代謝量は1日のカロリー消費の中でも半分以上を占めており、1日の全消費カロリーの 7割を占める基礎代謝量に大きく関わっているのが成長ホルモンです。成長ホルモンは新陳代謝を行うだけでなく、体温を上げたり、中性脂肪を分解して筋肉の修復もしてくれます。
この成長ホルモンの7から8割は、眠り始めの3時間に分泌され、この3時間を逃すと成長ホルモンはほとんど分泌されず、結果的に代謝が落ちてしまいます。つまり睡眠不足になると意志力が弱くなり、余計なものを食べ、ホルモンバランスが崩れて太りやすくなり、さらに代謝も落ちてどんどん太りやすくなります。そしてそこに光が大きく関わっており、9倍太りやすくなることになります。
実際に衛生写真から80カ国の中で最もよる明るい国を選んで、WHOが出した肥満率と人口照明との関係を調査した研究があります。ちなみに生活レベルの差も考慮し、裕福差、近代化レベル、食料の消費量など肥満に関わる別の要素を調整して研究は行われました。その結果、女性で72%から73%、男性で67から68%肥満率が増加し、夜間照明が最高レベルの国は最低レベルの国と比べて肥満率が9倍も上昇することが分かっています。
日本はもちろん夜間照明最高のグループに入っており、これまでにも動物実験では夜明るいと太る現象は確認されていましたが、人間で夜間の人口照明と肥満の関係が研究されたのは、この研究が初めてです。その後の研究で同じ国の人間同士でも明るい部屋で寝る人は、暗い部屋で寝る人に比べて肥満率が33%上昇するなど太りやすい傾向にあり、夜間の人工照明はジャンクフードと同じくらい危険だということが分かっています。
さらに目を閉じた状態で通過する光の割合は5から10%あり、アメリカのノースウエスタン大学医学部が20代の健康な男女20人を対象にした睡眠状態の観察研究では、寝室の光は目を閉じていてもまぶを通して目から入り、交換神経が優位になって睡眠中の心拍数や血圧が上昇し、インスリン抵抗性が増えて血糖値に影響を与えるという結果になっています。このように夜間の人口照明は光害とも言われるくらい私たちの健康にとって害があるものが明らかになっています。
良質な睡眠と東洋医学の関係
良い睡眠は美容と健康において欠かせない要素です。そして眠っている間に脂肪を燃焼させることができることが分かっています。それが夜間の体内活動を最大限に活用することです。
睡眠中の脂肪燃焼は、体が休息している間にエネルギーを効率的に消費し、脂肪を燃やすプロセスを指します。実は深い睡眠中に成長ホルモンが分泌され、これが脂肪燃焼を促進します。また適切な睡眠は、代謝を維持し、食欲を抑えるホルモンのバランスを整えることにつながります。またプチ断食はインスリンレベルを低く保ち、脂肪の燃焼を促進します。また体は外部からの脂肪よりも体内の脂肪をエネルギー源として使うようになります。これにより睡眠中でも脂肪燃焼が進みます。
一方で東洋医学では睡眠は、体の回復と再生に不可欠な時間と考えられています。夜間にしっかりと休息を取ることで体内のエネルギーの流れが整い、五臓の働きが最適化されます。これにより脂肪燃焼や代謝の効率が向上し、健康的な体重管理が可能になります。
また気は生命エネルギーであり、体内のあらゆる機能を支えています。気の流れが滞ると代謝が低下し、脂肪が蓄積しやすくなります。気の流れを整えるためには規則正しい生活習慣やストレス管理が重要です。例えば寝る前にリラックスする時間を設けたり、瞑想や深呼吸を行ったりすることで気の流れをスムーズに保つことができます。
一方で東洋医学では血の流れも重要な役割を果たします。血液は栄養素を全身に運び、老廃物を排出する役割があります。血の流れが滞ると代謝が低下し、脂肪燃焼が効率的に行われません。適度な運動や鉄分やビタミンCを含む食事を摂取することで血の流れを改善し、脂肪燃焼をサポートすることができます。
五臓の働きと脂肪燃焼
東洋医学の五臓は、それぞれが体内の特定の機能を司っています。脂肪燃焼に関連する主な臓器とその働きは次の通りです。
| 肝 | 血液の循環と解毒を助け、脂肪の代謝をサポートします。肝の働きを改善するためにはストレスを減らし、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。 |
| 心 | 血液循環を司り、全身の酸素供給を助けます。心の健康を保つためには規則正しい生活習慣とストレス管理が必要です。 |
| 脾 | 消化吸収を助け、栄養素全身に供給します。脾の機能を高めるためには消化に良い食事を取ることが大切です。 |
| 肺 | 呼吸を通じて酸素を供給し、体内の気を調整します。深呼吸や軽い運動が肺の働きをサポートします。 |
| 腎 | 体内の水分バランスとエネルギー貯蔵を管理し、代謝を助けます。腎の健康を保つためには十分な休息と栄養のバランスが必要です。 |
このように東洋医学の視点を取り入れることで睡眠中に脂肪を効率的に燃焼させ、気血の流れを整え、五臓の働きを最適化することで全身のバランスを保ち自然な脂肪燃焼を促進します。
睡眠の質を下げない人工照明との付き合い方
夜間にメラトニンの分泌を妨げず、作業に支障をきたさせないために必要な照度は100 から200ルクスの、本は読めるけど字を書いたり、細かい作業をするにはちょっと足りないくらいの明るさです。また赤や黄色といった色温度が低い暖色系は、青白い蛍光灯に比べてメラトニンの分泌を制限しません。夕方から夜にかけての就寝前には、なるべく200ルクスくらいの照度で、オレンジ系統の照明を使うとメラトニンの合成が抑制されずに深い眠りにつくことができます。さらに就寝時間の30分くらい前から寝室の照明は、地下駐車場の通路よりちょっと暗めの30ルクスまで照明を落とすとより効果的です。
また、寝る時は部屋の中を真っ暗にするのではなく、睡眠の深さと就寝中の照明の影響を調べた結果、照度が0.3 ルクスで睡眠深度が最高になり、30ルクスと0ルクスの真っ暗闇では同じくらい眠りが浅くなることが分かっています。この結果から睡眠中は0.3から1ルクスがベストと言われています。ちなみにトイレの中の照明も3から5ルクスと、かろうじて物が見える薄ぐらい程度にしておくと睡眠の質の改善になります。
ブルーライトを避ける
いくら部屋の暖色系の照明に変えて照度を落としてもブルーライトを見ていたら意味がありません。どうしてもスマホやパソコンを見たい場合は、ブルーライトをカットするメガネを使うと効果があります。ヒューストン大学の研究では、午後6時くらいからブルーライトをブロックするメガネをかける生活を2週間してもらい、睡眠の質を調べたところ、メガネをかける前のメラトニンの分泌量が平均16.1pgだったのに対し、ブルーライト軽減メガをかけた後では25.5pgと約58%も上昇しています。ちなみに実験では睡眠の質が上がったことはもちろん、睡眠に入る時間も10分以上早くなり、認知テストの結果までアップしています。
シーツや寝室の色を変える
私たちの目にはオプシンという青緑赤の光の色を捉えるタンパク質があり、そのおかげで赤から紫まで色を感じることができます。このオプシンが皮膚にもあることが分かっており、目隠しをしていても赤い部屋と青い部屋では脈や血圧に変化が出たという結果もあります。私たちは無意識のうちに肌で色を感じており、実際にイギリスで2000世帯の寝室の色と睡眠時間を調べた調査では、睡眠時間が最も長かった部屋の色は青、次にクリームイエロー、緑の順だということが分かっています。逆に睡眠時間が最も短いのが紫、茶、灰色の順で、青と紫の間では2時間もの睡眠時間の差がありました。そのため中間色の緑は1年を通して寝室に適した色だと言えます。
緑は目のピントが自然に合うため目の筋肉を弛緩 させて緊張を解きほぐし、気分の安定につながります。ちなみに紫はインスピレーションの色と言われていて、脳を刺激する色です。また青と赤のように退避する色は、人を落ち着かない気分にさせます。茶色も人を孤立した気分にさせて、これらの色のシーツを選ぶと悪夢をよく見ると言われています。
また、緑と言えば観葉植物を室内に置くことも良いです。植物は蒸散というプロセスを通じて定期的に水分を放出し、この水分が周囲の空気に加わり、室内の湿度を一定に保つ効果があります。適度な湿度は肌にとって重要で、乾燥が皮膚の老化やシワなどを引き起こす場合があります。湿度が適正に保たれるとこれらの問題が 防がれ、肌が柔らかく、健康的な状態を維持しやすくなります。
また、観葉植物の緑色は心理的に平和な気持ちや安心感を与えます。緑色はリラクゼーションと安心感を促進する色で、ストレスホルモンのレベルを低下させる効果があります。このように観葉植物はただ美しいだけでなく、心地よい環境を作り出します。このような環境は心理的ストレスの軽減はもちろん、良い気分や高い活力につながり、ポジティブな心の状態は身体の機能にも良い影響を与え、免疫システムの強化にもつながります。
睡眠へ導く食べ物
さつま芋
さつま芋には、ビタミンB6、マグネシウム、カリウムなどの栄養素が含まれており、特にビタミンB6はトリプトファンという成分の代謝に関わり、それがセロトニンという神経伝達物質の合成に役立ちます。セロトニンは、幸せホルモ ンと呼ばれ、眠りを誘うホルモンであるメラトニンへと変わるため、睡眠の質を良くする助けになります。
また、さつま芋には複合炭水化物を含んでおり、ペンシルバニア大学の研究では、これが睡眠の途中で起きる状態を軽減することに関連していることを明らかにしました。また複合炭水化物は消化がゆっくりと進むため、血糖値が急激に上がることを防ぎ、血糖値が安定していると夜中に目が覚めることが少なくなります。一方でさつま芋は食物繊維も豊富で、これが消化を助けて長時間満腹感を保つため、夜中にお腹が空くことが少なくなります。
適量としては、中サイズのさつま芋1個分、約200gが目安で、就寝の1から2時間前に食べると、その栄養素が消化吸収されて睡眠中の体の安定をお手伝いしてくれます。
脂肪の多いお魚
特に脂肪の多い鮭、マグロ、マス、サバなどがおすすめです。脂肪の多いお魚は、特にオメガ3脂肪酸という脳機能と新血管系の健康をサポートする脂肪を豊富に含んでおり、睡眠の質にプラスの影響を与えることが様々な研究で示されています。
また脂肪の多いお魚にはオメガ3脂肪酸だけでなく、ビタミンDも豊富に含んでおり、米カリフォルニア州にある小児病院栄養代謝センターの論文によると、この2つの強力な組み合わせは、セロトニンの生成を増加させることが証明されています。さらにベルゲン大学などの論文では、6ヶ月間、週に3回サーモンを食べた人たちは、お肉を食べた人よりも早く眠りにつくことが分かっています。
一方で、お魚は高タンパク質の食品としても素晴らしく、タンパク質はセロトニンの材料となるトリプトファンの供給源となります。また睡眠の規則性と深さについての研究から、オメガ 3脂肪酸をたくさん摂ることが睡眠の規則性を良くし、睡眠を深くすることが分かっています。
豆腐
豆腐には、神経と筋肉をリラックスさせるマグネシウムやトリプトファンの供給源となるタンパク質、そのトリプトファンをセロトニンに変換するのを助けてくれるカルシウムがたっぷり入っています。
また豆腐には、セロトニンを増やす植物性エストロゲンの一種である大豆イソフラボンを豊富に含んでいます。実際に東北大学などが行った研究によると、20歳から78歳までの1076人の日本人を対象に、イソフラボンが睡眠の状態にどのような影響を与えるかを調べた結果、イソフラボンの摂取量が多い人たちは最も低い摂取量の人たちと比べて最適な睡眠時間を取れる確率が1.84倍になることが示されています。さらに睡眠の質についても1.78倍になると報告されています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。