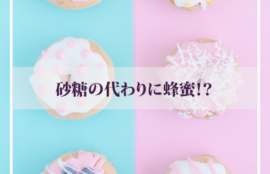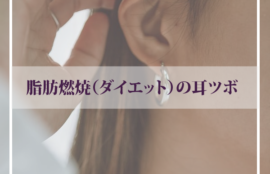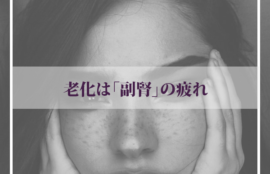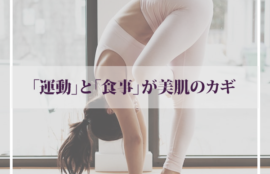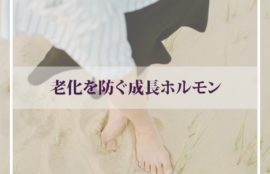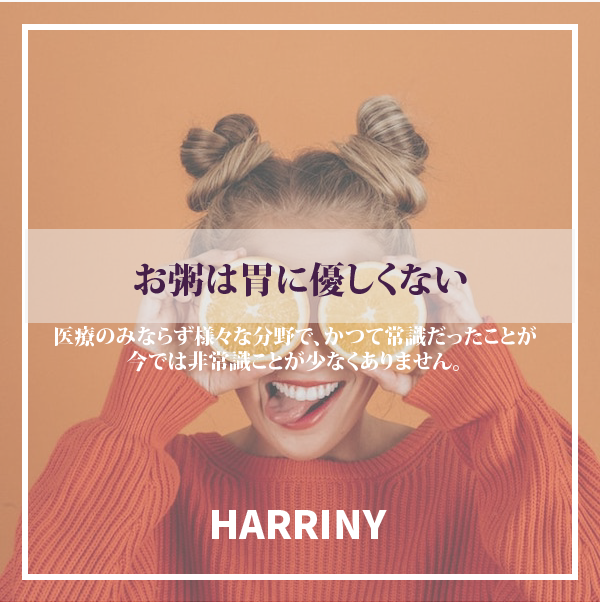
風邪を引いたとき、胃の調子の悪い時に「お粥」を食べることが当たり前とされていますが、実はあまり好ましくありません。おかゆを食べて余計にしんどくなる経験をしたことありませんか。
うどん、そば、ご飯、おかゆなどの炭水化物(糖質+食物繊維)と言われるものは、胃での消化にかなり時間が掛かります。例えば、ご飯は10時間、パンは6時間もかかります。人の消化管の構造から考えると、炭水化物(穀物)は消化が苦手で、肉は30分もあれば簡単に消化されます。
少し話が逸れましたが、風邪を引く、胃潰瘍などで胃壁が悪い状態で「お粥」 を食べると、胃の働きはしばらく止まります。それを「糖反射」と言います。食べ物が胃の中に入ると、胃液と胃酸の2種類の消化液が分泌されます。
胃液の中には、タンパク質成分だけに作用する消化酵素が含まれ、タンパク質を小さなサイズに分解して、小腸での栄養吸収をしやすくしています。胃の中では、糖や脂の消化酵素は存在してはいません。そのため糖が胃に入ると一時的に活動停止するか、または動きが微弱になります。これが糖反射で糖分過多の食べ物であれば、小一時間胃の活動は休止してしまいます。しかし休止している間でも胃酸は出続けます。
胃酸は強い酸性を示す消化液なので、胃酸は少なすぎても多すぎてダメで、バランスがとても重要な物質です。そのバランスが崩れると、胃炎や胃潰瘍などの様々なトラブルに見舞われます。その胃酸が食道まで上がれば、逆流性食道炎になります。
胃のトラブルは過剰な糖質
糖質の高いものを食べると、いわゆる胸焼けを起こします。その時、胃は胃酸で溢れ、そして胃酸が分泌されても糖質はまったく消化されません。このように胃の多くのトラブルの理由が、過剰な糖質の摂取です。胃潰瘍のみならず、胃の調子が悪い時に、糖質の高いお粥を口に入れると「糖反射」が起こり、胃の活動が停滞し、後から入る食べ物も無消化のままで胃内に留まることになります。結果、腸内で他の栄養を十分に吸収できい、胃酸過多による胃炎や胃下垂になることも考えられます。
弱った胃で栄養を上手く吸収するためには、卵などのタンパク質補給してください。また気軽に摂れるのがプロテインです。
梅干しのメリット
私たち日本人にとって非常になじみがあり、とても身近にある食材の梅干しには隠されたメリットが多数存在しています。風邪をひいた時などにお粥に梅干しを入れて食べたことがないでしょうか。古くから私たち日本人は風邪の時に、梅干しを食べることのメリットが民間療法として知られていました。そのような梅干しの効能について、科学的な裏付けが得られてきました。1日1つ梅干しを食べるだけで、様々な健康効果を期待することができます。
体をアルカリ化する
梅干しが自然治癒力を上げるメカニズムには様々なものがありますが、突出しているのが梅干しの高いアルカリ性です。体の中での酸性とアルカリ性のバランスのことを「酸塩基平衡」と言いますが、このバランスを表す数値としてpHが用いられます。PH7.0 が中性であり、一般に私たちの体は正常ではPH7.4程度の弱アルカリに傾いています。
細胞に慢性炎症が起きたり、体に長期間にわたるストレスがかかったりなどにより、私たちの体は酸性に傾いていくということが分かっています。体の酸塩基平衡が酸性に傾くことをアシドーシスと言い、アシドーシスになると体のだるさや疲労感、免疫力の低下など様々な不調をきたすようになります。
さらにアシドーシスになると、消化管でのビタミンB群の吸収が悪くなることも知られています。ビタミンBは私たちの皮膚の健康を大きく左右する栄養素のため、ビタミンの吸収が悪くなればそれだけお肌に悪い影響が現れます。
このようなアシドーシスによる健康被害を食い止めるために、体を酸性化する 原因である慢性炎症やストレスを取り除くことはもちろん大事です。しかし慢性炎症や長期的なストレスは、あくまで長期的に作用することによって体を酸性に傾かせるものであるため、生活習慣を変えただけですぐに改善されるものではありません。そのためアシドーシスになってしまった体液を、正常なアルカリ性に戻すためには手っ取り早くアルカリ性の食べ物を摂取することがおすすめの方法です。
梅干しの酸っぱさの原因はクエン酸という酸です。クエン酸は食べる前は酸っぱい酸性ですが、食べた後体の中でアルカリ性の物質に変換されてアシドーシスを補正する方向に働きます。梅干しの他にもレモン、ぬか漬けなど酸味のある食品の多くは、消化吸収されて体内でアルカリの性質を発揮します。このことから疲れが溜まるなどして自然治癒力が低下している時に酸っぱい食べ物を食べると良い言われているのは科学的にも正しいということが分かります。
一方で、体を酸性に傾かせてしまう食品として動物性の肉類やお米、パン、アルコール類などが挙げられます。つまり一般に私たちがよく食べる食材の多くが酸性であると言えます。私たちの身の回りの食べ物のほとんどが酸性食品であるため、何も意識しないとどんどん体がアシドーシスになってしまいます。
血液をサラサラにする
梅干しが持つアルカリ性以外の健康上のメリットの一つとして血行促進作用が挙げられます。最近の研究によって梅干しを加熱することでムメフラールという血液をサラサラにしてくれる物質が生成されるということが分かりました。出血を止めるための血小板や様々な免疫細胞は、血管を通って傷ついた臓器などに運ばれます。しかし、それらの細胞を運ぶための血液がもしドロドロであれば、大渋滞している道路で救急車が前に進めないのと全く同じように、毛細血管内でも大渋滞が起き、免疫細胞がうまく傷ついた部分に運ばれなくなります。血液をサラサラにしてくれるムネフェラールは、血液がドロドロであることで生じる様々な害を取り除いてくれるという大きなメリットがあります。
ただし、このムネフェラールは加熱した梅にしか含まれていないため、梅干しや生の梅にはさほど多く含まれていません。そのためムネフェラールを効率的に摂取したい場合は加熱、加工した梅肉エキスが最も効率的だと言われています。
乳酸を分解する
梅干しの健康効果として疲労回復効果が挙げられます。疲労が溜まればそれだけ免疫力が低下し、自然治癒力もまた下がってしまいます。梅干しには、アルカリ性を発揮するクエン酸の他にリンゴ酸という酸も豊富に含まれています。このリンゴ酸が筋肉に溜まった疲労物質である乳酸を分解してくれます。
例えば、沢山歩いて次の日にふくらはぎが筋肉痛になるのは、働いた筋肉で乳酸が生み出され、蓄積してしまうということが原因です。梅干しに含まれるリンゴ酸には、この乳酸を除去してくれる働きがあります。
植物性食物繊維
梅干しの効能の一つが腸を整える効果です。腸を整えるために乳酸菌が大事であると言われているのは聞いたことあるかと思います。乳酸菌には、動物性乳酸菌と植物性乳酸菌の2つがあり、動物性乳酸菌はヨーグルトなどに含まれている乳酸菌であり、口から摂取しても大腸に届くまでに消化され、死滅してしまうと考えられています。そのため積極的に摂取すべきは、植物性乳酸菌であると最近言われ始めています。
この植物性乳酸菌は、小腸などで消化されず、生きたまま大腸まで届いてくれ ます。この植物性乳酸菌そのものは善玉菌ではありませんが、大腸にいる善玉菌の餌となり、腸内環境が改善され、腸内細菌層のバランスを良好にしてくれる、とても大切な作用があります。
最近では、肌の健康は腸からと言われているほど腸と肌は密接に結びついていることが分かっています。腸内環境に悪玉菌が沢山発生してしまうと悪玉菌が作り出した有毒なガスが腸管で吸収され、血液を巡り、全身の細胞に漏れ出してしまいます。このような有毒ガスが皮膚の細胞に染み出せば、肌荒れをはじめとした見た目の老化を促進してしまいます。
また、腸は肌だけでなく脳とも密接な関係があるということが分かっています。このような腸と脳の密接な関係は「脳腸相関」とも言われます。例えば、緊張するとお腹を壊してしまうのは、脳の信号がお腹の調子を悪くしてしまう例の一つです。逆にお腹の調子が悪くなることによって脳に悪影響を与える場合も多々あります。
梅干しには、この植物性乳酸菌が大量に含まれており、さらにカテキン酸という殺菌作用のある栄養素も含まれています。このカテキン酸が腸内の悪玉菌を駆逐する働きがあることも分かってきています。
血糖値スパイクを抑止する
自然治癒力を高めてくれる梅干しの効果に、血糖値スパイクを抑止してくれることが挙げられます。梅干しに含まれているオレアノール酸は、植物が持つ天然のトリペルペンです。トリテルペンとはポリフェノールの一種で、中でも梅干しが持つオレアノール酸は、三大機能性トリテルペンの一つに位置付けられ、抗がん作用や抗炎症作用など様々な健康効果があることが報告されています。特にオレアノール酸で注目したいのが、腸管における糖の吸収を抑え、血糖値の上昇を緩やかにしてくれる効果です。
私たちが糖質を単体で摂取すると腸管で糖が急速に吸収され、それが血液中に漏れ出すことで急激に血糖値が上昇します。このような血糖値の急激な上昇を 血糖値スパイクと言い、血糖値スパイクはそれ自体がストレスとなって有害な活性酸素を大量に発生させます。活性酸素は細胞を錆びつかせてしまう性質があるため、血糖値の上昇を緩やかにすることは活性酸素の発生を抑制し、細胞を若返らせてくれる作用があります。細胞が若返ればそれだけ自然治癒力は向上するため、自然治癒力を維持してくれるという働きがあります。
高血圧の予防効果
塩分の過剰摂取によって高血圧なるのが心配という方にも梅干しで塩分補給するというのは非常に理にかなった方法です。そもそも血圧が高くなる原因は体内のホルモンが大きく関わっています。そのホルモンは、アンジオテンシンIIと言うホルモンで、これが過剰になると血圧が高くなります。このホルモンの働きを梅干しが抑えてくれることが分かっています。
実験では、このホルモンの働きを梅干しを摂取することによって8から9割も抑えることが示されています。
脂肪燃焼効果
梅干しに含まれているバニリンと言う成分が脂肪の燃焼を促進することが分かっています。このバニリンは、梅干しの香りの成分で、加熱することによってバニリン量が増えるということも分かっています。
また含まれているクエン酸には、糖や脂肪をエネルギーに変換するのを補助する効果があります。つまり代謝が上がり、その結果脂肪が燃えやすい体になっていきます。実際、梅干しを週に3個以上食べる人は、食べない人に比べてBMI値が低いという結果も出ています。
老化防止効果
老化防止効果がある食材というのは様々ありますが、その中でも日本人の体に合うのが梅干と言われています。梅干しが老化防止に役立つ理由は、主に含まれている抗酸化成分の梅リグナンにあります。梅リグナンの強力な抗酸化成分が老化の原因となる体内の活性酸素を除去してくれます。
体調が悪い時に避けるべきもの
栄養ドリンク
栄養ドリンクは体に良いとは言えません。確かにタウリンやアミノ酸などの栄養素が含まれていますが、そのような栄養素のメリットをかき消してしまうぐらい大量の糖分や人工甘味料、そしてカフェインが多く含まれているからです。
特に、糖分は脳の受容体にくっつくことである種の快楽物質を生み出します。そのため甘いものを食べると一時的に疲労感がなくなるように感じます。これは程度の差こそあれ、麻薬と同じです。また糖分のみならずカフェインも麻薬と同じような作用があります。カフェインを飲むと眠気が覚めると言われますが、これはカフェインが私たちの眠気を催す脳の受容体を占拠して眠気を感じられなくするためです。つまり体は疲れ切っていて寝たいにも関わらずカフェインがその眠さを覆い隠すことであたかも元気になったように錯覚します。
さらに、栄養ドリンクに含まれているアミノ酸などの栄養素は、本来なら食事から摂取すべきものです。人工的に精製されたものは健康的にはやや劣るというのはプロテインを始めとした全ての栄養素に共通して言えることです。
カフェイン
体調が悪い時は飲まない方が良いのがコーヒーです。コーヒーに含まれている数々のポリフェノールは、血圧の上昇を抑えたり、体内の活性酸素を無毒化してくれます。ですがコーヒーにはポリフェノールと同時に多量のカフェインも含まれています。
例えば風邪を引いて熱が出ると汗をかきます。また体調不良が続くとあまり食べ物が喉を通らなくなるのでどうしても水分不足になりがちです。私たちは1日に取る水分の約半分を食事から摂っていると言われています。食事が減れば水分も減ってしまうため、体調が悪くなると水不足に陥りがちになります。このような時に積極的に水分を取る必要がありますが、コーヒーを飲んでしまうとカフェインによって水分吸収が阻害されてしまいます。
コーヒーを沢山飲むとトイレに行く回数が増える経験をしたことがあると思います。これはカフェインによって、腎臓での水の再吸収が阻害されるためです。尿を作る過程で腎臓が血液をろ過し、その濾過された原液からさらに水を再吸収することで体内に水分を保っています。コーヒーを飲むとこの再吸収が阻害されてトイレが止まらなくなります。せっかく飲んだ水分が全部尿で出てしまったら当然体は水不足に陥ります。これらはコーヒーのみならず、カフェインが入っている飲食物全般に当てはまります。
ステーキ
体調が悪い時に栄養を付けるためステーキを食べることが逆効果になるかも知れません。ステーキには、タンパク質と同時に動物性の脂分も多く、消化に時間がかかるというデメリットがあります。ステーキは、胃におよそ4時間から5時間ほど滞留すると言われており、つまりステーキを食べた後の胃は長時間も稼働をし続けなければなりません。もちろん健康な状態であれば胃は4時間から5時間ぐらい問題なく、食べたものを消化してくれます。
体調が悪い日はステーキをはじめとする消化に悪いものは控えて、なるべく消化の良いものを食べましょう。タンパク質というとお肉のイメージが強いかもしれませんが、タンパク質が豊富でありながら消化に良い食べ物というのも結構存在します。例えば脂肪の少ない鶏胸肉で作ったつくねもタンパク質が豊富でありながら消化に良い食べ物の一つです。また豆乳や豆腐も非常に消化が良くかつタンパク質が豊富なため、おすすめです。
間違った食生活の知識
医療のみならず様々な分野で、かつて常識だったことが今では非常識ことが少なくありません。例えばバランスのよい食事(PFCバランス)は、炭水化物6割、脂質2割、タンパク質2割とされていました。今でも病院食などではこのバランスで献立がつくられていますが、このバランスに医学的、科学的な裏付けはありません。単に米を主食とする私たちの食習慣から決められています。ちなみにアメリカでは三大栄養比率という概念は廃止されています。
さらに多くの研究者が一般的なPFCバランスは適切なものとは言えないと断言しています。実際、この栄養バランスに沿った食事をした被験者たちの間で糖尿病が増えたという調査結果が導かれたことがあり、このPFCバランスでは糖質の摂取量が多すぎるんじゃないかと言われています。
人の本来の栄養バランスとして旧石器時代の人類が食べていた栄養バランスを考え、タンパク質3、 脂質6、糖質1が適正なバランスではないかと提唱している先生がいます。つまり、一般によく言われている栄養バランスでは、糖質の摂取が多すぎであり、また脂質が足りなさ過ぎることになります。確かに、一般的な認識では糖質は人間が活動する主要なエネルギー源になるものとされていますから、糖質を摂取しないとエネルギー不足で動けなくなってしまうことが心配になる 方もいらっしゃるかもしれません。
脳は人間が消費するエネルギー全体の20%を占めており、しかも脳はブドウ糖しかエネルギーにできないため、脳のためには糖質を取ることが必要だと、これまで言われてきました。しかし、これは間違いだということが分かっています。
また、人の栄養素で大切なのが脂質とタンパク質で、摂取を減らすべき栄養素が糖質です。人は糖質を摂らなくても、タンパク質を摂ることで、体内でブドウ糖を作り出せます。これを「新糖生」と呼びます。
ただし、いくら糖質が体に良くないからと言っても、糖質を全く取らないのもまた好ましくありません。その理由は、赤血球がエネルギー源にできるものがブドウ糖だけだからです。そのため1日あたり180gの糖質が必要ということが分かっています。
しかし180g の内、肝臓で作られてそのまま体内で使われる糖質もあります。肝臓が1日に作る糖質量は150g、人の体に必要な糖質量から肝臓が作っている糖質量をと差は30gです。つまり30gだけ食事から糖質を補う必要があるというのが根拠になります。糖質量の30gは、ご飯に換算してお茶碗半分ぐらい、それ以上は人の体にとって余分な糖質であり、体の中で余った糖質は 中性脂肪になって蓄積されていきます。
また適切な脂質とタンパク質が摂れてさえいれば、炭水化物(糖)の必要摂取量はなくても健康に生きていけます。その分、脂質とタンパク質を増やしカロリー不足にならないように気をつけましょう。さらにブドウ糖ではなく脂質から分解される脂肪酸(脂質)がエネルギーになる過程で生まれるケトン体をエネルギーとして使うようにすることで、生活習慣病などの予防効果が期待できます。
一方で、ご飯やパンといった主食をしっかり食べる、つまり炭水化物6割の食生活が良いと教えられてきましたが、その6割以上はほぼ糖質で過剰摂取です。糖質は直接に血糖値に影響を与える唯一の栄養素です。過剰摂取によって糖尿病や動脈硬化のリスクが高まります。
従来のバランスの良い食事では、血糖値に異常を起こし、健康になるためのタンパク質と脂質が決定的に不足しています。日本人に決定的に足りていない栄養素がタンパク質と言われています。さらにこれらの必要な栄養素が足りなくなると、素早くエネルギーになる糖質を体は強く求めます。
糖質制限によって、ダイエット、美容、アンチエイジングだけでなく、さまざまな病気の予防・改善や健康増進に効果が期待できます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。