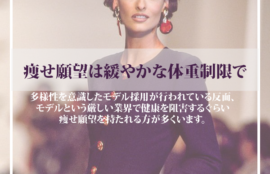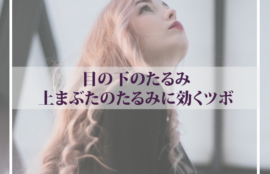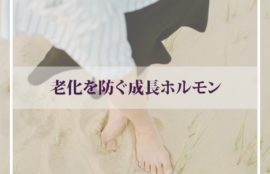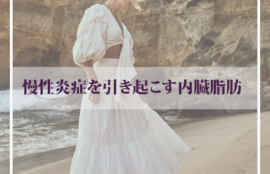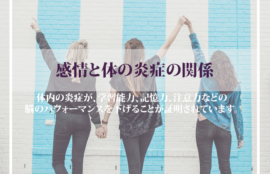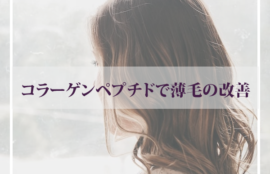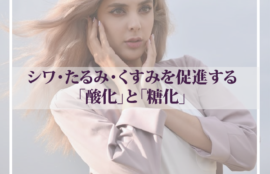暑くなってくると体の臭いが気になる方は、汗をかくのを避けたいと思っているかも知れませんが、その汗自体がどういう風に変化するかによって臭いの元になります。そのため適切なケアで臭いを減らすことができます。また一般的に男性よりも女性の方が6から8倍香りに敏感と言われています。
加齢臭の基礎知識
加齢臭は、中年期以降に体から発生することがある独特な匂いのことです。この匂いは加齢に伴う体内の変化が影響しており、汗や皮脂の成分が変わることで発生します。加齢臭が発生する場所は、特に背中や脇、首回りなどです。加齢臭は、一般的に中高年特有の体臭を指しますが、近年は30代でもこの匂いを発する人が増えています。
30代の加齢臭は生活習慣の乱れが原因であることがほとんどです。食生活の欧米化で資質の摂取が多くなり、体内での脂質代謝が活発化し、それが皮脂として分泌され、皮脂に含まれる脂肪酸が菌に分解されると加齢臭の原因物質のネナールが生成されます。ノネナールはリノール酸という皮脂の成分が酸化し、状態が変化したものです。加齢やその他の原因で皮脂の成分バランスが変わるとリノール酸が増加し、それが酸化する量も増えることなり、その結果としてノネナールが増えて加齢臭が強くなります。
また、加齢と食事の他にも体の基礎代謝が低下すると皮膚の新陳代謝も鈍くなり、皮脂や古い角質が堆積しやすくなります。新しい皮膚細胞の生成が遅れると皮膚の保湿力が低下し、乾燥しやすくなります。皮脂や古い角質が皮膚表面に堆積すると皮膚表面のpHが変動し、バクテリアが繁殖しやすくなります。その結果加齢臭が発生してしまいます。
ちなみに皮膚表面のpH変動は、皮膚の表面のpH値が変わることを指し、pHは物質の酸性もしくはアルカリ性を示す指標で、0から14の範囲で表されます。pH7を中心にそれより低い値は酸性、それより高い値はアルカリ性を示しています。新陳代謝の鈍化により皮膚のバリア機能が低下すると、外部刺激からの保護能力が低くなり、例えば紫外線や摩擦などの外部ダメージを緩和することができず、皮膚の劣化を早めてしまう可能性もあります。代謝の低下は、皮膚の健康と機能に大きな影響を与えており、スキンケアや生活習慣の見直しをして皮膚の新陳代謝を上げることは加齢臭対策にもなります。
また、ホルモンバランスの変化が加齢臭を発生させることもあります。女性の体内ホルモンバランスは思春期、妊娠、更年期などに応じて大きく変動し、主要なホルモンのエストロゲンとプロゲステロンがあります。この2つのホルモンバランスが女性の体調や皮膚の状態に大きく関わっています。女性は更年期になると卵巣機能が衰え始め、徐々にエストロゲンの分泌が減少します。エストロゲンは、皮膚の保湿や新陳代謝、コラーゲンの生成をサポートする役割があり、エストロゲン量が減ると皮膚の乾燥や代謝が低下し、皮膚のバリア機能も弱まります。
皮膚の表面に皮脂や古い角質が堆積しやすくなると、それが原因で加齢臭が発生することもあります。さらにエストロゲンの減少に伴い、皮脂の分泌量や成分が変わることになり、特にリノール酸が増加し、それが酸化することでノネナールが生成されます。
また、皮脂や汗古い角質などの不純物を洗い落とさないとそれが加齢臭の原因になることがあります。皮膚は毎日外部環境からの汚れ、皮脂、汗、古い角質などを皮膚表面に付着させており、これらの不純物が適切に取り除かれない場合、皮脂が酸化したり、常在菌のバランスが乱れたりします。過剰に蓄積された皮脂は空気中の酸素と反応して酸化し、ノネナールを生成させ加齢臭を強めてしまいます。
皮膚上には、数百から数千の常在菌が生息しており、常在菌のバランスが保たれていると皮膚は健康を維持することができますが、例えばコリネバクテリウムの菌は汗腺周辺に多く存在し、汗中のアミノ酸や脂質を代謝し、脂肪酸、アンモニアなどの物質を生産します。これらの物質はツンとした匂いをしていて、量が多いと加齢臭を強めてしまいます。皮膚の新陳代謝が正常だと上層部の古い角質は自然に剥がれ落ちますが、不適切な洗浄でこれらが皮膚上に堆積すると古い角質が微生物の餌になり、これらも皮膚の常在菌バランスを崩す可能性があります。
汗、皮脂、殺菌が臭いの原因
基本臭いは、汗と皮脂と汚れが混ざった時に出てきます。その臭いは、皮脂が酸化した臭い、雑菌が増殖することよって臭いが発生するということが分かっています。そのため汗をかいたなあと思うときに制汗シートなどで小まめに拭くことが大事です。
ただし、シャワーなどの頻繁に洗うということオススメできません。なぜなら私たちの肌には常在菌が存在し、常在菌が皮脂を分解して、それによって肌の大切なバリア機能の要になるものを作ってくれるからです。その他にも常在菌はPHを分解して酸性に傾け、肌のバリア機能を保つという働きがあります。また常在菌の中には、その皮脂とか汗を分解したときに嫌な臭いや香りを発生するものがあります。洗い過ぎによって肌の常在菌のバランスが崩れてしまったりするとこのようなことが起こります。
そして、汗をかいた時に通気性の悪いものを着ていると、そこで蒸れて臭いが起こるということがあります。そのため汗を吸うようなタイプの下着をつけるとか、通気性の良いものを着ることが臭いを防ぐということにもなります。
一方で、頭皮の臭いが気になるという方も多く、これは皮脂が増えることによって起こります。皮脂は汗と違い、皮脂が酸化することよって臭いを発します。また皮脂が沢山あることで雑菌が増えて臭いの原因となります。まずは皮脂をしっかり落とすということが大事です。最近は湯シャンが流行っていますが、頭皮が脂っぽくって匂いが気になる方は、皮脂は落ちづらいので洗浄剤を使って皮脂を流すことが大事です。ただし取り過ぎる事もあまり良くないため、予洗いをしましょう。予洗いはシャンプーする前にお湯で頭皮や髪の毛を先に洗ってあげることです。もちろん油は取れないですが、汚れが先行して落ちるため、洗浄剤の頭皮への刺激を最小限にすることができます。
さらに、体の洗うとき耳を洗うのを忘れる人がいます。耳は立体的になっているため、皮脂が溜まりやすく臭いの元になります。
一方でお口の臭いが気になる方が増えています。特にマスクすることによって口呼吸になるとお口が乾燥し、唾液が出にくくなり雑菌が増える原因になります。お水を小まめに飲むことで口臭は軽減されると思いますが、それでも臭いが気になる方は、歯周病が隠れている可能性があります。
臭いのピークは30代、40代
臭いはおじさんやおばさんに特に多いというイメージがあると思いますが、臭いは実は30代や40代の女性でもかなり出ています。臭いの原因は汗、皮脂、蒸れで、これらの臭いは30代ピークということが分かっています(ロート製薬の研究)。なぜなら10代とか20代に出ていたスイート臭という若い人特有の香りが30代から減ってくるからです。
例えば、赤ちゃんから良い香りするのは、ラクトンと呼ばれる成分が出ているからです。10代では、ラクトンC10とラクトンC11が1:2に出ていますが、残念なことに20代ではこのラクトンC10はほとんど少なくなり、ラクトンC11だけになります。そして30代になるとどちらもほとんど出てこなくなります。
ラクトンで有名なのが、Guerlainというブランドの香水であるMITSOUKOです。1919年に発売されてからのロングセラーの香水です。トップノートがベルガモットの香り、ミドルノートがローズやジャスミンの甘い香りです。この香水には、ラクトンの香気成分が含まれ、この成分が初めて合成された香水がミツコと言われています。
ストレス臭
ストレスが体臭の原因になります。ストレスが溜まる交感神経優位になり、発汗が促されます。また交感神経優位になると口の中は乾き、雑菌が増えて口臭の原因になることがあります。
このストレス臭は、資生堂の研究員が発見し2018年に発表された匂いで、まだ解明されていない部分が多くあります。研究では緊張状態にある人から同じ匂いがすることが突き止められており、交感神経が優位になっていたり、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールが唾液中に増えることで生じると考えられています。
この発見は2017年に発表した「ノネナール(加齢臭)が皮膚ガスとして皮膚表面から放出されている」という知見に続く皮膚ガスの研究成果です。
実は私たちの皮膚からは様々なガスが排出されており、この皮膚ガスは体の表面から発生する揮発性の物質の総称のことで、匂いのない二酸化炭素から臭いのあるアンモニアまで様々なものが含まれています。例えば皮膚ガスは体調や加齢、食べ物などによって変化することが知られていましたが、緊張によっても変化することがストレス臭の存在によって明らかになりました。
現在、ストレス臭の主要成分はジメチルトリスルフィドとアリルメルカプタンの2つであるところまで突き止められています。これらを抑える技術が開発されれば、ストレス臭を抑制できるようになるかもしれません。
体臭は生活習慣で決まる
特にお肉を食べことが多い方は体臭がきつくなります。これはお肉に代表されるようなカロリーが高いものは、汗腺の働きを活発にするからです。またニンニクや香辛料も同じで、もともとニンニクには硫化アリルと言うニオイの元になる成分があり、それが体臭として出てきてしまうことがあります。
逆に、これを食べるとニオイがなくなる食べ物はありません。よく言われるのが果物を食べるとその果物の臭いで体臭がよくなると言われていますが、可能性ゼロではないかも知れませんが確実ではないです。
また、甘い物を食べるとビタミンB12っていうビタミン群を消費します。ビタミンB群は皮脂分泌を調整するビタミンでもあり、甘いものを食べると消費されて分泌が逆に調整できなくなってしまいます。そうなれば元々30代40代というのは、皮脂の蒸れ感などが頭皮に出てくる年代になるので、甘いものを食べ過ぎてしまって皮脂分泌が過剰になって、頭皮の臭いの原因になってしまう可能性あります。
このような食習慣がどのように体臭に影響するかを調べた研究があります。マッコーリー大学では、体臭が変化する原因を突き止めるために食事を調べられました。その内容は様々な食生活をしている男性に、48時間白いTシャツを着てもらい、この間はシャワーや香水を禁止して、1時間軽く運動をしてもらいました。その後、そのTシャツを18から30歳までの女性に臭いをチェック(食生活によって良い臭い、魅力的、健康的などの項目を10点満点で採点)してもらいました。
その結果、肉を食べる人は臭いが強くなる傾向があったり(健康的な人の匂いは、肉を食べるとクサくなるのではなく、良い匂いが強くなる)、野菜やフルーツを食べる人の方が良い匂いだったり、良質な油、卵、豆腐を食べる人は良い匂いに変わったことが挙げられています。つまり健康的な人ほど、魅力的かつ多くの人に好まれやすい匂いになることなどが分かっており、体臭を改善してくる物質を食事から吸収できと考えられています。さらに精製された炭水化物によって体臭がキツくなることも分かっています。つまり炎症を起こしやすい食生活をすることで体臭がクサくなるのです。
逆に、腸内環境と便通を整えることで、体臭が抑えられることができるということが分かってきています。食べ物が腸の中で分解される時に、臭いのもととなるガスが出ます。便秘や便通が悪くなると腸にガスが溜まり、腸がその毒素を吸収し、これが体臭の原因になると言われています。
加齢臭は体の酸化
加齢臭は自分では気がつくことが難しく、匂いは自分で思っている以上に周りに影響を与えるものです。加齢臭の原因には、体の酸化が挙げられ、さらに糖尿病、高血圧などの生活習慣病予備軍になっている可能性があります。特に注意しなければならない加齢臭の原因は油の酸化です。
私たちの体を構成しする細胞の一つ一つを覆う細胞膜は油でできており、油は免疫力を高めたり、エネルギー源となったり、他にも重要な役割を担う必須の栄養素です。体に必要な油は、主にオメガ3系とオメガ6系の脂肪酸から合成されるリン脂質、タンパク質、コレステロールで作られています。またオメガ3やオメガ6は体に必須のエイコサノイドの原材料にもなります。エイコサノイドは、血小板の凝集、動脈壁や気管支の収縮・弛緩、血液の粘度など体内のあらゆる調整を担う非常に大切な物質です。しかしオメガ3とオメガ6は体内で作ることができません。そのためオメガ3とオメガ6は必須脂肪酸と言われています。他にもオメガ9という重要な脂肪酸もあります。
この3 種類は、魚や植物由来の油に多く含まれており、不飽和脂肪酸としてくくることができます。そしてオメガ3とオメガ6は1対4の比率で摂ることが望ましいです。なぜなら現代の食生活ではどうしてもオメガ6に偏りがちとなり、オメガ3が不足するからです。このオメガ3はサバやイワシといった青魚や海藻、豆類に多く含まれています。一方でオメガ6はゴマ油、菜種油、コーン油など家庭でも外食でも多用されている油に含まれています。
逆に摂っていけない脂肪酸は大きく二つに分けることができます。一つはバターやチーズ、ラードといった動物性の脂肪酸です。これらは飽和脂肪酸と言い、体内でも固まりやすく大量に摂取すれば血液がドロドロになったり、動脈硬化を促進します。そして絶対に摂ってはいけないのが、トランス脂肪酸です。トランス脂肪酸は自然界に存在しない油で、植物油を工業的に加工して固形にしたものです。トランス脂肪酸は糖尿病をはじめとして、心臓疾患や脳卒中などの生活習慣病の一因と指摘されています。
また、同じ種類の油であっても使う条件次第で良い油にも悪い油にもなります。例えばオメガ3、オメガ6、オメガ9の不飽和脂肪酸には酸化しやすいという欠点があります。中でも最も酸化しやすいのがオメガ3です。
青魚が当たりやすいのは、大量に含まれているオメガ3が酸化して古くなるからです。酸化した魚は、独特の嫌な臭いを発します。酸化した油を取り込むと、体の防御反応として嘔吐や下痢といった症状が起きることもあります。
さらに酸化しやすいのはオメガ6で、170度で急速に酸化が始まります。170度は揚げ物の温度で、菜種油やコーン油など一般的にオメガ6の油で食材を揚げているため、根本的に揚げ物には問題があると言えます。このように揚げ物は酸化した油まみれの食べ物です。一方でオリーブオイルに多く含まれているオメガ9は、240度で酸化が始まりますが、酸化しにくいため、炒め物はオリーブオイル、ゴマ油は仕上げの香り付けが安全な食べ方です。
加齢臭の原因は酸化ですが、体が酸化する原因に活性酸素にあります。酸化した油、つまり酸素が結びついた脂肪の分子は過酸化脂質と呼ばれる毒性の強い物質となります。これが体内に取り込まれると活性酸素が発生して周囲の細胞を酸化させてしまいます。
細胞が酸化すれば、血管や細胞の機能が損なわれて 破壊されて、さらに活性酸素は細胞内にも侵入して細胞の核にあるDNAを傷つけてしまいます。そして細胞が変異するとがん細胞へと変化します。
特に40歳を過ぎると酸化に対する抵抗力が低下し、体内で過酸化脂質が増えるとノネナールという物質が皮膚に発生します。このノネナールこそが加齢臭の原因となります。つまり加齢臭が発生している時点で、体中は活性酸素で溢れる状態です。
加齢臭を発生させないようにするためには、動物性タンパク質と動物性脂肪を なるべく取らないようにすることです。特に唐揚げなどの揚げ物は、動物性タンパク質と動物性脂肪を酸化した油で揚げるため、過酸化脂質たっぷりの食べ物です。また重要なのが体の酸化を食い止めてくれる抗酸化物質を多く含む食べ物、つまり野菜を積極的に食べること加齢臭の予防に大切です。
加齢臭とミドル臭
体臭は口臭の1.4倍、足の匂いの1.5倍とも言われています。特にミドル世代と言われる35歳から50代半ばの年齢を指す世代(男女共)に多い体臭が、ミドル臭とも言われています。このミドル臭と加齢臭は、匂いの成分が全くの別物です。
加齢臭は、皮脂の中に含まれているノネナールという成分が原因です。このノネナールは、実は若い年齢でも多少分泌されていますが、特に40代以降になると増え、一番の理由は加齢が原因です。加齢によって体の抗酸化力が衰え、体内の脂質が活性酸素で酸化した状態、いわゆる過酸化脂質になり、さらに厳密に言うとノネナールの原因と言われるパルミトレイン酸も同じように酸化され、この酸化した2つが混ざり合うことであの独特の匂いにな ります。
一方で、ミドル臭(ミドル脂臭)の原因は加齢臭とは違い、ジアゼチルという成分が原因です。ジアゼチルは、ヨーグルトやチーズなど発酵食品の匂いの成分です。ジアセチルは、人の汗の中に含まれている乳酸菌が肌の表面にいる常在菌の一つのブドウ球菌によって代謝分解されることで発生し、頭頂部や後頭部の匂い成分である中鎖脂肪酸と結びつくことでミドル臭になります。またミドル臭は加齢臭と比べて、その拡散力は約100倍もあると言われています。このミドル臭を予防するためには、何より生活習慣でミドル臭を発生させる原因を知ることです。
ミドル臭いは、汗に含まれた乳酸菌がブドウ球菌によって代謝、分解されて発生するため、その乳酸菌が出ないようにすればミドル臭は抑えられます。しかし40代以降になると、特に乳酸の代謝が遅くなり、汗に含まれる乳酸の量もその分増えてしまいます。
また、コンビニ弁当やレトルト食品は、ミドル臭の原因になります。なぜなら糖質や脂質を必要以上に多く摂取すると皮膚表面で分泌される皮脂の量が増加し、匂いの原因となる細菌が増殖するからです。さらに匂いの原因物質のジアセチルが増殖するのに加えて、食品添加物を摂り過ぎて栄養が偏ると、肌の表面にいるブドウ球菌まで増殖することが分かっています。さらに栄養バランスが悪くなると血液もドロドロになり、血行が悪くなると体内で乳酸が増えることまで分かっています。つまり汗の中の乳酸の量が増えることになります。
また、40代以降の女性の場合、女性ホルモンの減少がミドル臭の原因の一つになります。40代以降で女性ホルモンのエストロゲンとプロゲステロンの分泌量が減ってくると更年期障害が現れます。更年期障害の代表的な症状としてホットフラッシュがあり、急に顔が熱くなったり、汗が止まらなかったりすると、その汗には乳酸がたっぷり含まれており、その汗が皮脂と混ざり合ってジアセチルを大量に発生してしまいます。
さらに過剰なストレスを感じると体内で活性酸素が発生し、これによって皮脂が酸化して匂いを発したり、ストレスで自立神経が乱れていることで乳酸を含む汗を多く出す多汗症を引き起こします。
ミドル臭を抑える方法
ミドル臭いを抑える方法は、消臭効果のあるシャンプーを使うことです。ただ消臭効果といっても何でも良いわけではなく、ミドル臭のもとになるジアスチルを洗い落とせるフラボノイド含有の植物エキスが配合されたものを選びましょう。ミドル臭は、頭頂部や後頭部、 耳の裏やうなじから発生するので、意識してしっかり洗いましょう。
そしてミドル臭を抑える重要なことの一つに質の良い汗をかくことが大事です。汗には質の良い汗と悪い汗の2種類あり、血液から作られている汗は、汗腺を通って体の外に出てくる水のようにサラサラした良い汗です。一方で悪い汗は、ろ過機能が低下し、汗腺が休眠状態に陥って血中のミネラル分や乳酸などが血管に戻らずに汗とともに出てきてしまったベタベタした汗です。このような乳酸を多く含んだ汗は、肌の表面にいるブドウ球菌が乳酸を分解して、ミドル臭を発生させてしまいます。
汗腺のろ過機能がきちんと働いて良い汗がかけるかどうかは、実は年齢ではなく、どんな環境で生活するかによって個人差が出てきます。汗腺も筋肉を使っていないと衰えるのと同様に、あまり汗をかかない生活をしていると汗腺のろ過機能が退化して良い汗がかけなくなってしまいます。運動や入浴などで積極的に汗をかき、汗腺を刺激する生活を続けることで汗腺のろ過機能を高めることができます。
一方で、ミドル臭対策にはアルカリ性食品が効果的です。梅干しや緑茶、海藻類、リンゴなどのアルカリ性食品を積極的に摂るようにしましょう。梅干しには抗酸化作用が高いポリフェノールが豊富に含まれており、緑茶に含まれるカテキンには、消臭、抗酸化作用があります。海藻類には乳酸の酸性を抑制する効果があり、リンゴには消臭効果の高いポリフェノール、エピカテキンやクエルセチンが含まれています。
特に海藻類の中でおすすめは「めかぶ」です。めかぶのヌメリ成分であるフコイダンは、アンモニアや硫化水素といった悪臭を放つ物質を効果的に体外に排出するのをサポートしてくれることが分かっています。その他にもフコイダンは、腸の消化管粘膜を保護してくれるため、体内の悪臭成分がリンパ管を通って体中に行き渡ることを防いでくれます。
加齢臭を改善するための生活習慣
運動習慣
運動は全身の新陳代謝を活発にする効果があり、筋肉を動かすことで血流が良くなり、酸素や栄養素が体中にしっかりと届くようになります。また老廃物の排出もスムーズになり、加齢臭を緩和することができます。運動で汗をかくと新陳代謝も活発化し、皮膚のターンオーバーも整います。ターンオーバーが正常になると、古い角質や過剰な皮脂が堆積することも無くなります。また汗によって体内の老廃物や不要な物質が排出されると皮脂の過剰分泌も改善されます。
ストレスケア
人間の体は大きなストレスがかかると戦うか逃げるかの選択をしないといけ なくなり、副腎からストレスホルモンであるコルチゾールを大量に分泌します。コルチゾールは過剰に分泌されると筋肉の分解を促進し、新陳代謝を低下させる作用があります。その結果、皮脂や古い角質が皮膚上にとどまりやすくなり、これが加齢臭の原因になります。
また、長期的にストレスがかかると交感神経が過剰に刺激され、汗腺が積極的に働くようになります。つまり汗の分泌量が増加し、加齢臭が強くなります。運動で流す汗は、デトックス効果がありますが、冷や汗のように不自然な形で分泌される汗は体臭のもとになります。
人体にはエクリン汗腺とアポクリン汗腺の2つの感染が存在し、エクリン感染は体全体に広がっていて、運動や暑さで発汗します。エクリン汗腺からの汗は、主に水、塩そして一部の代謝物質からできています。エクリン汗腺から出る汗はそんなに臭くなく、エクリン汗腺から出る汗は、体温を調節する役割とデトックス効果があります。
一方で、アポクリン汗腺は脇の下や陰部、乳首の周辺などに存在し、ストレスや興奮時に活動化します。アポクリン汗腺から出る汗は、脂質やタンパク質を多く含んでいて、鼻にツンとくる匂いをしています。つまりストレスが原因で出てくる汗は加齢臭を強めてしまいます。
加齢臭の改善に効果的な食材
ニンニク
ニンニクは匂いが強いから余計に加齢臭が悪化させると思われるかも知れませんが、ニンニクには硫黄化合物が多く含まれていて、これが加齢臭を改善してくれます。ニンニクに含まれる硫黄化合物の中で最も代表的なものはアリシンで、ニンニク特有の香りや風味を出している成分です。アリシンには、抗、抗酸化、抗炎症、血流改善などの様々な効果があります。アリシンの抗菌作用は強力で、細菌の細胞膜機能を破壊し、細菌の増殖や活動を阻害します。さらに細菌に酸化的ストレスを与え、生存と増殖を妨げるとも言われています。
さらに、アリシンの抗酸化作用は、体内の活性酸素やフリーラジカルを中和し てくれる効果があります。酸化的ストレスから体を守り、アポクリン汗腺からの発汗を抑えることができます。またアリシンの抗炎症作用で皮膚の健康を促進することもできます。
皮膚が炎症を起こすと新陳代謝が乱れ、皮脂の過剰分泌や古い角質の蓄積が起こることがあります。皮膚の状態が悪くなると加齢臭も悪化しやすくなるため、アリシンは皮膚炎症を予防、改善し加齢臭を改善する効果も期待できます。一方でアリシンには、血流をスムーズにする働きもあります。アリシンは体内で 硫化水素という物質の生成を補助し、この硫化水素には血管をリラックスさせ広げる作用があります。硫化水素が活性化すると血流が向上し、血液や栄養素が身体の各部位にしっかりと届くようになります。ただしアリシンは熱に弱い特性を持っているため、アリシンを最も多く取れる方法は、ニンニクを生のまま食べることです。また過剰に摂取すると胃痛や胃もたれ、下痢などの症状を引き起こすことがあるから注意が必要です。
ニンニクを消臭できる甜茶
甜茶は名前に甘いという字が使われていることからも分かる通り、独特の甘みのあるノンカフェインのお茶になっています。甜茶には体臭予防効果があるということが知られています。ニンニクは食べることで口臭のみならず、おならや体臭まで臭くなることが知られていて、匂いが気になるから控えていますという方も少なくないでしょう。しかしニンニクには癌予防を始めとする様々な健康効果が実証されており、臭いが気になるからと言って食べないのは非常にもたないこととも言えます。
そこで飲んでいただきたいのが甜茶です。ニンニクにはアリシンという栄養素 が含まれ、アリシンには疲労回復効果から血流の改善効果に至るまで素晴らしい効能がたくさんあります。しかしアリシンは私たちの体の中で代謝されると、アリルメチルスルフィドという物質に変化します。この物質こそが臭いや大衆の原因になります。ある研究によるとアリルメチルスルフィドは、ニンニクを食べるや否や、口腔粘膜から肝臓に至るまで体全体で発生することが確認され ています。つまりニンニクを食べると息が臭くなるだけでなく、汗が臭くなったり、体中が臭くなってしまうのはこれが原因と考えられています。
しかし、甜茶はアリルメチルスルフィドに対する消臭効果があることが実証されています。アリルメチルスルフィドに対し、消臭効果を持つ植物を探索した研究では、消臭植物の中でも特に甜茶抽出物に最も高い消臭効果があるということが確認されています。この研究では甜茶の持つポリフェノール成分が高い消臭効果の鍵であることが確かめられていて、ニンニクを食べる時は甜茶を一緒に飲んでおくことで体臭を軽減できる効果が期待できます。
さらに甜茶には口臭の原因の1つであるメチルメルカプタンに対する消臭効果まであることが分かっています。メチルメルカプタンは歯周病菌が大量に作り出すことで有名です。この物質は排泄臭や生ゴミ臭とも表現される通り、周りの人が我慢できないほどの強烈な異臭を発生させることで有名です。このような強烈さからメチルメルカプタンは、一般的なブレスキア用品では消すことが困難であるとされています。しかしメチルメルカプタンもまた、甜茶によって軽減できることが知られています。
さらに甜茶には消臭効果の他にも、花粉などのアレルギーを予防する効果や肥満を予防する効果などがあります。例えばアレルギーを持つマウスに甜茶を投与した実験では、体内からのヒスタミンの放出が減ったことが明らかになっています。アレルギーの多くはヒスタミンという物質が過剰に放出されることが原因で、甜茶は副作用のない天然の抗ヒスタミン薬です。一方で肥満のラットに甜茶を約2ヶ月間飲ませた実験では、血糖値や体重が改善するということも分かっています。
紅生姜
紅生姜は、生の生姜を酢漬けにしたもので日本料理によく用いられる食材です。生姜の辛味成分ジンベロールは、抗酸化作用や抗炎症作用があります。体内の有害物質を中和し、皮膚の老化や体臭の原因となる物質を抑制する効果が期待できます。ジンゲロールが熱により変化するとショウガオールという物質を生成し、このショウガオールにも抗酸化作用や炎症を抑制する効果があり、皮膚を健康維持に貢献してくれます。
また、紅生姜に含まれるジンベロールやショウガオールには、血液の循環を良くする作用があり、血液の凝固活性を抑えることで血液をサラサラにしてくれます。紅生姜の摂取により血流が改善されると体温の上昇や新陳代謝の促進が期待でき、冷え性の改善やデトックス効果を実感することができます。ただし紅生姜には体を温める作用があるため、過度に摂取すると体温が上昇することがあります。また胃腸が弱い人は、胃の不快感を感じることがあるので、紅生姜の摂取量には十分気を付けてください。
大豆製品
大豆製品の主要な成分であるイソフラボンは、植物性のエストロゲンとして知られる化合物です。女性ホルモンのエストロゲンと同じ働きをしてくれます。加齢に伴い体内のエストロゲン量が減少すると皮脂の生成が活発化し、加齢臭が強くなりやすくなります。
イソフラボンがエストロゲンの働きをカバーしてくれると皮脂生成の活性化を抑えることができ、皮脂の生成を適正なレベルに保つ効果が期待できます。大豆製品には、納豆、豆腐、味噌、豆乳など様々な種類があり、イソフラボン含有量は異なりますが、納豆や味噌は比較的高いイソフラボンを含んでいます。納豆の1日の摂取目安は、一般的には1から 2パックが適量とされており、納豆にはビタミンK、納豆キナーゼなどの健康成分が豊富に含まれています。
ただし、大豆製品は適量を摂取すれば健康に良いですが、過剰に摂取するとホルモンバランスを乱すことがあります。一部の研究ではイソフラボンが甲状腺機能に影響を及ぼす可能性も指摘されており、特にヨウ素摂取量が不足している場合や甲状腺の問題が既にある場合は注意が必要です。
おならが臭い原因
おならの平均回数は、1日20回ぐらいと言われています。おならには、大きく分けて2つの発生の仕方があります。一つ目は飲み込んだ空気がおならとして出るパターンです。空気を飲み込むとある程度はゲップとして出ますが、ゲップとして出なかったものが腸の方まで行き、おならとして出る事があります。もう一つは腸の中で腸内細菌が食べ物を分解発酵してガスを発生させて、それがおならを発生させるということがあります。
1つ目のパターン多いのが、ドカ食いや早食いすると食べる時に一緒に空気を飲み込んでしまい、それがおならになってしまいます。また炭酸水やビールなどを飲んでいると、ゲップで出ないものがおならの原因になります。
もう一つのパターンは、通常は大部分の栄養素(糖質、タンパク質、脂質)は小腸で吸収されますが、何らかの要因で消化吸収されなかった場合、ある程度は大腸の方へ向かうことが挙げられます。大腸には沢山の腸内細菌がおり、腸内細菌の餌になって分解されてガスが発生します。そのガスの大部分が無臭のメタン、水素、二酸化炭素です。
これら以外のガス、例えばアスパラガス、ブロッコリーなどに多く含まれる物質の「ラフィノース」は消化が悪く、消化吸収されなかったものが大腸に行ってそこで 腸内細菌の餌になって発酵して臭いガスが出るということがあります。また主に肉などの動物性タンパク質を大量に食べた時に大腸でアンモニアを発生、臭いガスが発生することがあります。
何れにせよドカ食い、早食いをすると大量の食べ物が一気に入ってくるので小腸で吸収されにされにくくなり、消化吸収が不十分のまま大腸の方に行って腸内細菌の餌になって発酵してガスが出る事が起こります。そのため、よく噛むことで咀嚼されて、口の中でアミラーゼなどの消化酵素が分泌され、咀嚼によっても消化液が反応します。
一方で、日本人に乳糖不耐症の人が多く、牛乳、ヨーグルトなど乳製品は、通常であれば乳糖はラクターゼという酵素で分解されて吸収されます。しかしラクターゼという酵素は赤ちゃんの時はしっかりあるのですが、加齢とともに減り、特に日本人は大人になるとラクターゼの量が減って、乳糖不耐性になりやすいと言われています。乳糖不耐症の人が乳製品を大量に摂取すると、ラクターゼで分解されなかった乳糖が大腸で腸内細菌の餌になって分解されてガスを 発生させるということがあります。
それ以外では、多いのが過敏性超症候群です。過敏性腸症候群は、緊張したりストレスを感じたりとかするとおならを大量に発生させたり、下痢や便秘になったりします。
また機能性胃腸症、クローン病、潰瘍性大腸炎、強皮症などの膠原病、糖尿病の方などもおならが多くなります。特に糖尿病によって細い血管がダメージを受け、腸が働かなくなることがあります。このような特定の病気の場合には、お医者さんで治療することが大事です。
特にFODMAP食は、特定の人にとっては小腸で吸収されにくいため、その中で食べ物が浸透圧で水を引き込んで下痢をしたり、消化管の蠕動運動が亢進して腹痛がしたり、大腸で腸内細菌の餌になって分解、発酵してガスが出ると言われています。具体的にFODMAPには、ごぼう、ニンニク、アスパラガス、ネギ、玉ねぎ、きのこ類、納豆、キムチ、ヨーグルト、牛乳、チーズ類、小麦、大麦、ライ麦、大豆、とうもろこし、りんご、スイカ、桃、なし、ジュース(果糖ブドウ糖液糖)などが挙げれます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。