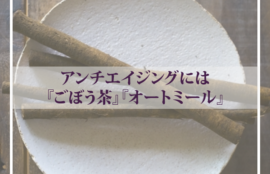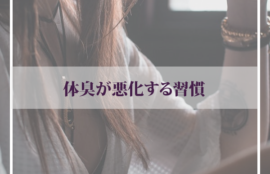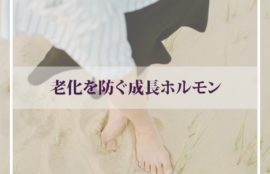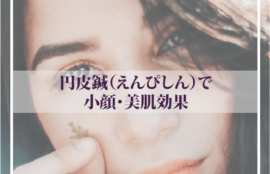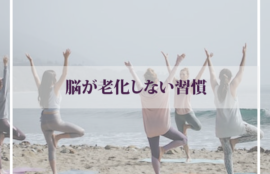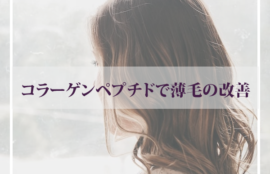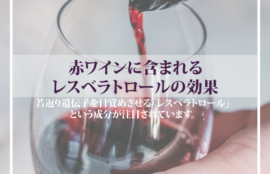昨今の最新遺伝子研究の中で、腸内細菌と病気・老化との関係が次々と明らかになっています。その中で腸内細菌は体質、性格などに左右する全身の司令塔の役割があることが分かっています。心の不安、高血圧、肥満、糖尿病、アレルギー、感染症、認知症、肝臓病、子宮内膜症などまで、腸内細菌との密接な関係があります。
私たち現代人は、高脂肪食(食生活の欧米化)、食物繊維不足、抗生物質、食物添加物、下剤、ストレスの増大、運動不足などの影響で腸内(細菌)フローラが乱れから、腸内の慢性炎症に悩まされ、それらが病気の発生要因や悪化要因になっています。
腸には人体に存在する免疫細胞のおよそ7割が集中しており、ウイルスやがん細胞から私たちの体を守ってくれています。それだけでなく腸と脳、腸と心には繋がりがあり、「脳腸相関」という言葉があるように、腸はあらゆる臓器には密接な関係があります。
腸内フローラの改善
腸内フローラの改善は肉体的な健康だけでなく、精神的な健康にも大きく影響しています。腸内細菌をうまく育てることで、心身の健康を保ち、健康寿命が決まり、人生の質が決まると言っても良いでしょう。心も体もすべては「腸」次第なのです。
この腸内フローラを整えるためには、食生活の改善が必要になります。もちろん食物繊維を多くとったり、ヨーグルトを食べたりすることは大切ですが、食事の内容と同じくらい大切なのが、食事のタイミングです。
まず、腸内フローラ改善のためにまず避けたいのが朝食を抜くことです。その理由は、排便のベストタイミングを逃してしまうからです。食事を摂ると大腸が大きく収縮して胃結腸反射が起こりますが、この反射が起こりやすいのが朝食時なのです。そのため朝食を抜くと、この反射が起こりにくくなり胃の蠕動活動が滞りがちになり、便秘から腸内フローラが乱れ、様々な体調不良や病気を引き起こす原因となります。そのため少量でも良いので必ず朝食は摂るようにしましょう。
しかし、忙しく朝食を食べる時間がない方、空腹健康法を実践されている方にオススメなのが「朝一杯の炭酸水」です。空腹になった胃に炭酸水を飲むと、その重さで胃が下がり、胃の下と通る「横行結腸」を刺激することができます。この刺激によって腸の蠕動運動を促すことができます。さらに炭酸水には二酸化炭素の気泡が多く含まれており、この気泡が蠕動運動を促してくれます。
また、夕食は就寝の3時間前までに済ませましょう。腸のゴールデンタイムは夜10時から2時までで、その時間に深い眠りにつければ、「副交感神経」優位になり腸が活発化して善玉菌が悪玉菌を駆逐して、腸内フローラが良好な状態に回復します。
そして、食事は多品目を摂ることが健康に良いのは、栄養バランスだけでなく、腸内で育つ細菌の種類に影響するからです。偏った食生活をしてしまうと、同じような腸内細菌しか育たちません。このように腸内細菌が偏り、乱れた状態を「ディス・バイオーシス」という腸管粘膜のバリア機能や免疫力が低下する原因になります。
健康的な腸内フローラを育てるために必要な食品をまとめましたので、ぜひ意識的に摂って下さい。
| 水溶性食物繊維 | 海藻、コンニャク、もち麦に多く含まれ、便を柔らかく性質があり、便通を良くしてくれます。特にごぼうには水溶性、食物生繊維の両方が多く含まれているのでオススメです。 |
| 発酵食品 | ヨーグルト、味噌、納豆など。善玉菌のエサになるのみならず、腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑える働きがあります。 |
| オリゴ糖 | バナナ、玉ねぎ、はちみつ、納豆や絹ごし豆腐に多く含まれ、善玉菌の中でも「ビフィズス菌」や「乳酸菌」のエサになります。 |
| オメガ3系脂肪酸 | 青魚や亜麻仁油に多く含まれ、腸の炎症を鎮め、善玉菌が増えやすい環境を整えてくれます。 |
これらの4大栄養素をバランス良く摂るためには、和食です。和食には、水溶性食物繊維が豊富な根菜や海藻、納豆やぬか漬けといった発酵食品、オメガ3脂肪酸を多く含む青魚があります。また日本では古くから砂糖の代わりとしてオリゴ糖を含むハチミツが調味料として用いられてきました。つまり普段から和食を摂っていれば、意識しなくても腸を良好な状態にできていているはずです。
食物繊維の基本的な知識
食物繊維とは食品に含まれる消化されない炭水化物のことです。小腸で消化吸収されずに大腸まで達する食品成分です。食物繊維には水に解ける水溶性食物繊維と水に解けない不要性食物繊維の2種類があり、この両方をバランスよく摂取することが重要だとされています。
食物繊維は腸の中で、私たちの健康にとても有益な働きをしてくれている善玉菌の餌となって善玉菌の増殖を促進し、健康に様々なプラスの効果をもたらす可能性があります。また善玉菌は短鎖脂肪酸という体にとても重要な物質を作り出してくれます。短鎖脂肪酸は、血腸の細胞に栄養を与えることができ、腸の炎症を軽減し、過敏性腸症候群、クロン病、潰瘍性大腸炎などの消化疾患を改善するのに役立ちます。
食物繊維は排便を促進してくれたり、腸内環境を整えてくれることに加えて、死亡率が下がることが分かっています。研究では食物繊維の摂取量が多い人は、少ない人に比べて早期死亡率が23% 低下、さらに癌の発症率は17%ほど低下することが分かっています。そして食物繊維の摂取量が1日10g増えるごとに早期の死亡率が11%ずつ減って行くことまで分かっています。
また、9万人以上の日本人を対象とした研究でも同様の結果が報告されていて、食物繊維の摂取量が多い人は摂取量が少ない人に比べて、男性で20%、女性で18%死亡リスクが低いことが明らかになっています。
このように食物繊維は、摂取するべき栄養素であるにも関わらず多くの人は食物繊維を十分に摂取できていません。果物や野菜、豆類、芋類、キノコ類、海藻類などの食物繊維が豊富なものを食べることが大切ですが、特に生の野菜や果物には抗酸化作用のあるビタミンCが豊富に含まれています。
有害物質の多くは活性酸素という老化を引き起こす原因であるため、抗酸化作用のあるビタミンCは、この活性酸素の発生を抑えてくれるため、ビタミンCを豊富に含む生の野菜や果物は解毒に大変有効です。
そして食物繊維には水に解けない不溶性食物繊維と水に解ける水溶性食物繊維の2種類があり、理想的なバランスは不要性食物繊維が2、水溶性食物繊維が1になります。特に意識していただきたいのが水溶生食物繊維を意識的に摂るということです。実は、現代人は不要性食物繊維と水溶性食物繊維を大体4対1ぐらいの割合で摂取していることが調査によって分かっています。つまり多くの人は不要性食物繊維ばかり摂取しており、水溶性食物繊維が基本的に足りていないことになります。そのため理想的な割合に近づけるためには、水溶性食物繊維の摂取量を私たちは意識して増やさねばなりません。
ちなみに食物繊維が豊富に含まれている食べ物の代表である野菜には、不溶性食物繊維がメインで含まれており、野菜だけを食べていれば水溶性食物繊維は 十分だとは到底言えません。水溶性食物繊維が豊富に含まれている食べ物には、海藻類のひじき、のり、ワカメ、昆布、もずく、めかぶなどがあります。他にはこんにゃく、じゃがいも、里芋、長芋などの芋類にもたっぷりと含まれています。また果物で言えばイチゴ、みかん、アボカドなどにも水溶性食物繊維が豊富に含まれています。
食物繊維の黄金比は2対1
食物繊維の理想的なバランスは不溶性食物繊維が2、それに対して水溶性食物繊維が1です。現代人は不溶性食物繊維と水溶性食物繊維をおよそ4対1ぐらいの割合で摂取しているということが調査によって分かっており、多くの人は不溶性食物繊維ばっかり摂取し、水溶性食物繊維が基本的に足りていません。例えば野菜は、不溶性食物繊維がメインで含まれており、野菜だけを食べていれば水溶性食物繊維は十分とは到底言えません。
水溶性食物繊維が豊富に含まれている食べ物は、ひじき、海苔、わかめ、昆布、もずく、メカブなどネバネバやツルツルしている食べ物です。また野菜の中でも、モロヘイヤやオクラなどネバネバ系の野菜には水溶性食物繊維が豊富に含まれています。他にも、こんにゃく、ジャガイモ、里芋、長芋などの芋類、大麦やオートミールにも水溶性食物繊維が含まれています。
これらの水溶性食物繊維には、体内の毒素を吸収して便と同時に排出させる働きが期待できます。また不溶性食物繊維には、腸にこびりついた汚れを掃除しながら便をカサ増しする働きがあります。
酪酸菌の健康効果
日経メディカルオンラインによると、医師3618人に最も処方している腸を整えるための薬は酪酸菌が入った整腸剤で、2位がビフィズス菌の入った整腸剤でした。酪酸菌は酪酸をつくる細菌の総称であり、酪酸や酢酸をつくることで悪玉菌の発育を抑制してくれます。また大腸の主要なエネルギー源になり、酪酸により酸素が消費されることで大腸内がビフィズス菌や他の善玉菌が住みやすい環境にしてくれます。ビフィズス菌は乳酸、酢酸をつくり出すことで悪玉菌の増殖を抑制してくれます。
特に酪酸菌を積極的に摂取することで、様々な健康効果が期待できると考えられています。まず代表的な効果が炎症を抑えてくれることです。炎症は、体内に侵入した異物を排除する機能であり、異物が排除されると治る一時的な反応を急性炎症と言います。一方で慢性的な炎症は様々な病気の引き金になってしまいます。
酪酸菌は制御性T細胞を誘導し、炎症を抑えることに役立ちます。制御性T細胞は、炎症反応を抑制し、免疫応答が過剰にならないようにするブレーキの役割を持った細胞で、人の免疫にとって重要な細胞です。そのほかにもマクロファージやB細胞などにも作用して、腸や関節の炎症を軽減してくれることも分かっています。さらにアレルギーを軽減してくる効果があると示唆されています。なぜなら喘息や花粉症、アトピー性皮膚炎には腸内環境が深く関わっていると考えられており、例えば腸内細菌の働きによって生み出される短鎖脂肪酸という物質が、アレルギー反応を軽減するなどの研究結果が報告されています。
腸を強化・修復する「短鎖脂肪酸」
近年の腸内細菌の研究で、私たちの健康や病気は腸内細菌による影響が大きいことが分かっています。つまりどのような腸内細菌が働いてくれるかによって私たちの健康は決まります。
その中で、腸内細菌が食物繊維やレジスタントスターチを処理する過程でつくられる「短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸、プロピオン酸)」は、エネルギーや大腸の粘膜の炎症を抑える効果があります。また大切な役割として、脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、アドレナリンなど)の濃度をコントロールすることも分かっており、精神の安定にも大きく関わっています。
なぜ、腸で生まれる物質が脳内で合成される物質に関与するのかは、例えばストレスを受けると、脳から腸へ情報が伝達されてお腹が痛くなるのと同様に、腸から脳への伝達が短鎖脂肪酸によって行われるからです。つまり腸内細菌がしっかり短鎖脂肪酸を合成してくれなければ、感情や情緒が不安定になってしまいます。
また、腸内には体全体の70〜80%の免疫システム、免疫細胞が配置されています。体にとっての毒素は吸収されずに体外へ排出されます。この吸収するのか排出するのかの選別作業を腸内細菌と免疫細胞が共同で行っています。その時に炎症を抑える腸の防御システムを強化・修復するのが短鎖脂肪酸です。
このようにエネルギー、腸内環境の悪化を抑える、免疫力、メンタルの維持に深く関わるのが短鎖脂肪酸です。
だたし、腸内環境が乱れていれば、短鎖脂肪酸がつくられても吸収されないのであれば意味がありません。故に短鎖脂肪酸の便中の濃度が腸内環境の指標になり、短鎖脂肪酸が多く排出されるほど腸内細菌の多様性がないとも言えます。
便が柔らかい、または下痢である方は、短鎖脂肪酸の排泄量が多い傾向があります。つまり便秘の方より腸内環境が悪く、全身の炎症反応が高い可能性があります。便中の短鎖脂肪酸濃度が高い方は、腸内細菌内の悪玉菌の比率が上がり、肥満や心血管疾患のリスクが高まります。
大腸にはフラクトオリゴ糖
意識的にフラクトオリゴ糖を多く取り、大腸にいる酪酸菌を増やすことで、結果的に体内の炎症が抑えられ、アレルギーや自己免疫疾患が抑えられることができます。酪酸菌こそが腸内の門番であり、それを増やすのがフラクトオリゴ糖です。
一般的には腸活には納豆、ヨーグルト、キノコが良いなどが腸に良いと言われていますが、むしろ腸活には酪酸を増やす食物繊維を沢山食べること以外に必要はありません。食物繊維には様々な種類がありますが、ここで言う食物繊維は胃と小腸で分解されないものです。判断が難しいのは分解されなくても酪酸菌を増やさないものが沢山あるからです。以下に簡単にまとめてます。
| イソマルトオリゴ糖 | 小腸で分解・吸収されるため酪酸菌とビフィズス菌を増やしません |
| ガラクトトースを含むオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖(ヨーグルトや牛乳)、乳果オリゴ糖、ラフィノース(ビートオリゴ糖)など | ビフィズス菌を増やすも、酪酸菌はあまり増やさない。イソマルトオリゴ糖に比べて少し値段が高いものは、これら3種のオリゴ糖を主成分としている |
| フラクトオリゴ糖 | 酪酸菌の他に、ビフィズス菌、アッカーアンシア菌を増やします |
オリゴ糖以外に食物繊維についてもまとめておきます。
| 難消化性テキストリン | 糖の吸収を穏やかにするため、トクホ食品や機能性表示食品によく使われています。酪酸を増やす効果については報告されていません |
| βグルカン(きのこや麦類など) | 酪酸菌を増やしません |
| グルコマンナン(こんにゃく)、寒天・アルギン酸(海藻などの食物繊維) | 酪酸菌を増やしません。ただし海藻にふくまれるフコイダインは酪酸菌を僅かに増やします。 |
| レジスタントスターチ(難消化性でんぷん) | ご飯や加熱したジャガイモを冷ますことでできる分解されにくいデンプンで、日頃から食べているものですが、酪酸菌を増やすことはありません |
| セルロース | 植物に含まれる硬い繊維ですが、ほとんどが大腸で分解されます。酪酸菌を増やすことはありません |
| ペクチン | りんごなどの果物の果皮に含まれている繊維で、酪酸菌を増やすことはありません |
| ラフィノース、スタキオース(大豆) | 酪酸菌を増やしません |
このように日常的に食べ、腸活に良いと言われている食物の多くは、酪酸菌を増やす効果はありません。つまりこれらをどれだけ食べようとも腸内フローラを改善して酪酸菌を増やすことがないのです。
フラクトオリゴ糖を含む野菜で、簡単に手に入れられる野菜はゴボウ、菊芋、ヤーゴンなどのキク科食物の根に大量に含まれています。またネギ、玉ねぎ、にんにくにも含まれています。理想的に量は1日100gですが、オリゴ糖配合のシロップもありますが、様々な商品が販売されており、酪酸菌を増やすオリゴ糖を選んでください。フラクトオリゴ糖を意識的に摂取して、大腸の酪酸菌を増やし糖質制限を適度にして健康管理をして頂ければと思います。
オリゴ糖で肌質が改善
甘いものが肌荒れの原因になってしまうということは美容に気を使う全ての人にとっては常識になっていることでしょう。私たちのお肌の細胞は非常に繊細で、甘いものを食べるとその翌日には、ニキビや口内炎といった皮膚や粘膜のトラブルが出てきてしまいます。砂糖のような甘いものが肌荒れの原因になってしまう理由としては次のようなものがあります。
- 皮脂が過剰に分泌されてしまう
- ターンオーバーが乱れる
- エイジスによる皮膚細胞の老化
特に甘いものによる皮脂の過剰分泌は、お肌のトラブルの最大の原因であるとも言えます。甘いものを食べて皮脂の分泌が過剰になってしまうのは、糖質が脂肪に置き換わって余分な分が皮脂として出てしまうといった様々な理由が考えられます。
また甘いものは、ドーナツやケーキなどトランス脂肪酸のような体に悪い油を使ったものが多く、それらの油によって皮脂が分泌されてしまうとも考えられるでしょう。実際1ヶ月砂糖抜きの生活をした実験では、皮脂の分泌量が劇的に減ることが分かっていて、甘いものが皮脂を大量に分泌してしまうことは明らかです。
そして甘いものを食べて血液がドロドロになってしまえば、お肌の細胞にまで血液が届かなくなってしまいます。血液はお肌に酸素や栄養素を運んでくれる大切な役割があり、そのような血流が阻害されることでお肌のターンオーバーが困難になります。
お肌のターンオーバーは内側から新しい細胞が生まれて、外側の古い角質が剥がれ落ちる現象のことのため、栄養や酸素が足りなければ当然、内側から新しい細胞は生まれてきません。そうなると古い角質層だけが溜まり、肌が老化していくことになります。
さらにエイジスという、言わば焦げが皮膚の細胞に溜まることでシミやくすみの原因になってしまいます。またエイジスはお肌の大切なコラーゲンを破壊し、肌の潤いや弾力が失われ、シワやたるみの原因になってしまいます。
オリゴ糖には、様々なお肌へのプラス効果があることも知られており、実は腸内環境が良くなると悪玉菌が作り出す毒素が減るため、お肌に良い影響を与えてくれることが分かっています。オリゴ糖には善玉菌を増やす働きがあり、相対的に悪玉菌が減るため、体の内側からお肌を綺麗にしてくれます。
さらにオリゴ糖には、アトピーのような辛い肌荒れ症状を改善してく効果があることも分かっています。アトピー性皮膚炎の患者にオリゴ糖を与えた実験では、アトピー性皮膚炎の重症度を下げる効果があることも分かっています。
遺伝的な研究では私たち日本人の3人に1人が、アトピー性皮膚炎にかかりやすい体質を持っていることも報告されており、1度かかると治すのが非常に難しい皮膚の難病の1つです。
オリゴ糖でぽっこりお腹が凹む
お肌の状態と共に私たちの外見の美しさを決める重要な要素の1つが、やはり体型です。しかし甘いものを食べると太るというのは今更言うまでもないですが、甘いものを食べて血糖値が急激に上がると大量のインスリンが分泌されて、それらの血糖が一気に中性脂肪に変換されてしまいます。こうして作られた中性脂肪が、どんどんお腹や足に溜まっていき肥満体型が形成されます。
このような肥満体系を改善したいのであれば、甘いものを止めるのが必須になりますが、それは頭では分かっているが止められないのが人間の弱いところです。そんな時に砂糖をオリゴ糖に置き換えていくのがおすすめです。
オリゴ糖は、血糖値を上げず、当然中性脂肪に変換されて太ることはありません。そもそもオリゴ糖は、腸で吸収されないため脂肪にならないのは当然です。それどころかオリゴ糖には腸内環境を改善することで脂肪を燃やしやすい体質になるメリットまであります。これは短鎖脂肪酸が脂肪燃焼をサポートしてくれるためです。徐々にオリゴ糖に置き換えていくことで少しずつ体を糖のない食生活にしていきましょう。
短鎖脂肪酸は痩せ菌
善玉菌の代表は、ビフィズス菌、乳酸菌、酪酸菌です。どの菌も水溶性食物繊維などを餌として食べて、短鎖脂肪酸を生成します。短鎖脂肪酸によって腸は弱酸性に保つことができ、悪玉菌を抑制し、有害な菌の増殖を抑えて、悪玉菌の出す酵素の働きも抑えることができます。
その効果は、腸の活動を活発にして消化吸収を助け、セロトニンなどの幸せホルモンが順調につくられます。さらに免疫機能を活性化させて、アレルギー症状を起こしにくくします。
そして、短鎖脂肪酸の役割として、脂肪細胞に脂肪を取り込まないように働きかけることものです。つまり脂肪燃焼を高め、代謝がアップして痩せやすい体になります。短鎖脂肪酸を出すビフィズス菌、酪酸菌、バクテロイデス属の菌を「痩せ菌」とも言われています。一方で脂肪をつくって溜め込むように働く「デブ菌」もいます。痩せ菌が多いとたくさん食べても太りにくく、デブ菌が多いと太りやすい傾向があります。
また、痩せ菌と呼ばれる理由に、短鎖脂肪酸はGLP-1というホルモンの分泌を促し、ブドウ糖の代謝をよくする働きを持っているからです。このようにダイエットをする前に腸内環境を整えて痩せ菌を増やすことが大切なのです。
乳酸菌は体に良い!?
大腸の酪酸菌を増やすことが体の健康にとって大切ですが、一方で乳酸菌が体に良いことを聞いたことがあるでしょう。乳酸菌はヨーグルトや漬物などに入っている乳酸をつくる細菌です。ブドウ糖から乳酸菌をつくると酸性が強くなって他の微生物は生育できなくなります。この乳酸菌は食べてもほとんど胃酸で死んでしまします。そのため乳酸菌は本来、大腸や小腸で僅かにしか存在しない細菌のため、健康効果は全くないとも言われています。
乳酸菌は体に良い、免疫力を上げるというのは科学的な根拠に乏しく、有効性を証明する医学論文は殆どありません。ヨーグルトなどが体に良いのは、含まれているタンパク質やオリゴ糖が健康に良く、その栄養成分によって免疫力がアップしますが、酪酸菌を増やす食物繊維を摂る方がはるかに高い健康効果があります。
腸内環境と良質な水
私たちの体の60%は水分でできており、水は体内で非常に重要な働きをします。例えば有害な毒素や老廃物を排泄して新陳代謝を活発にします。また血流が良くなれば栄養素が全身に送られ、エネルギー代謝を高めてくれることから、肥満の予防やダイエットにも水分摂取は欠かせません。
体内の水分は毎日少しずつ入れ替わり、約2週間かけて全ての水が入れ替わります。一口に水といってもお店で売られている水は大まかに4つの種類があります。
| ①ナチュラルミネラルウォーター | 特定の水源から採取された地中でミネラル分が溶け出した地下水で濾過、沈殿、加熱、殺菌以外の処理をしていない |
| ②ナチュラルウォーター | 特定の水源から採取された地下水で、濾過、沈殿、加熱、殺菌以外の処理をしていない |
| ③ミネラルウォーター | 濾過、沈殿、加熱処理のほか保存殺菌や紫外線殺菌、ミネラル分の調整などをしている |
| ④ボトルドウォーター | 河川水や水道水を処理した水や水道水 |
ナチュラルミネラルウォーターは、腸内環境を整えてくれるミネラル成分が含まれ、特にカルシウムは腸の蠕動運動を活発にして、腸内に溜まった脂肪と便を一緒に押し出してくれます。またカルシウムは脂肪燃焼を促進したり、脂肪の吸収を抑えたりする働きもあり、体脂肪が減らすことが分かってきています。
睡眠の乱れは腸にある
理想的な腸内環境は、多様な腸内細菌がある状態です。バランス良い食事を心がけることで、腸内細菌の多様性もつくられます。
最近の研究で、睡眠の乱れと腸内細菌の組成の間に明確な関連があることが分かりました。腸内細菌の多様性が高い人ほど睡眠の質が高く、多様性が低い人は、睡眠までの中途覚醒までの時間が短い、つまり長く眠れないとう結果になりました。慢性的な睡眠不足が腸内環境の悪化を促進する可能性が示唆されています。
寝つきを良くし質の良い睡眠を得るための簡単な工夫は、寝る前に自律神経をリセットする深呼吸を10回行うことです。昼間優位になった交感神経から副交感神経が優位な状態をつくるために、唯一意識的にコントロールできることが深呼吸だからです。
また、1日3食によって休むことなく消化活動を続ける胃腸に、間欠的ファスティングを行うこともおすすめします。間欠的ファスティングは食べて良い8時間と食べてはいけない16時間に分けることで、腸内の掃除の働き(MMC:空腹期強収縮群))を促進できるからです。掃除がなければ腸内の環境が悪くなることは当たり前のことです。
これらも面倒臭いと思った方には、朝一番で白湯(可能であればレモン水)を摂取しましょう。朝起きた時に失われた水分を500ml程度摂ることで、脱水状態になっている体を潤すことが大切です。
腸内環境を整える美容鍼灸
このように腸の不調が、メンタルへの影響だけでなく、アレルギーや様々な病気の原因にいます。健康的な腸内フローラを育てることで、腸内環境が整い、健康な体を維持することができます。
また、鍼灸治療すると、多くのお客様が施術直後から腸が働き出し、その動きが活発になると感じられています。このように鍼灸治療は胃腸の活動を促進することができます。ぜひ食生活の見直しと鍼灸治療を併用して、より健康で質の高い生活を手に入れて頂きたいと思っております。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。