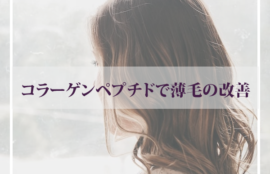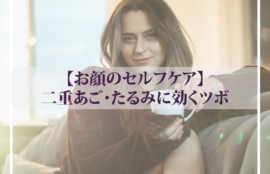良質な油を摂ることが健康的に生きるために重要です。その良質な油がオメガ3脂肪酸です。オメガ3脂肪酸は必須脂肪酸と言われていますが、私たちの体内で合成することができません。そのため食事から摂取しなければならないのですが、日本人の多くがオメガ3脂肪酸が不足しています。忙しい方は、オキアミオイル、クリルオイル、魚油などのサプリなどでぜひ補給しましょう。
オメガ3脂肪酸が不足しているサイン
オメガ3脂肪酸が不足しているサインは以下です。
- 肌が乾燥しがち
- 日々の倦怠感を感じる
- 集中力が続かない
- 夜がなかなか眠れない
- 関節が痛む
- 肌にハリがない
- 爪が脆い
- 頭がぼーっとする
これらに当てはまる方は、オメガ3脂肪酸を意識して摂る必要があります。それでは科学的根拠に基づいて、その理由をお伝えします。
オメガ3脂肪酸の基本知識
まず脂肪酸と脂肪は違いがあります。脂肪酸は脂質の主な構成要素であり、他の様々な物質と結びつくことで脂質を形成します。このオメガ3脂肪酸には、α-リノレン酸(ALA)、ドコサヘキサヘン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA)があり、ALAは主に植物性の食品に、DHAやEPAは主に魚介類などの動物性食品に多く含まれています。DHAは頭が良くなる、EPAは血液サラサラになるなどで知られています。
オメガ3脂肪酸のメリット
オメガ3脂肪酸には摂取するべき強力なメリットがあります。
- 体内の炎症を減らしてくれる
- うつ病などのメンタルの不調を改善してくれる
- 肝臓を癒し、睡眠の質を上げる
- 血流を促し、肌トラブルを軽減してくれる
体内の炎症を軽減
炎症とは、傷や感染、アレルギーなどの反応によって、その影響を受けた場所が赤く腫れて熱を持ち、痛みを感じたりする状態です。怪我をすれば、体の生理反応によって、血液や白血球がその部分に修復作業を始め、急性の炎症が起こることで様々な病原菌から体を守る役割があります。
しかし、問題なのは糖尿病、心臓病、肥満などの病気のリスクに関連している慢性的な炎症です。研究では長寿の方の多くが体内の炎症レベルが低いことが分かっています。また慢性的な炎症は体重の増加にも繋がっていると考えられており、ダイエットするためにはまずは体に起こっている炎症を取り除くことが必要です。さらに学習能力、記憶力、注意力を損なうことも分かっています。
オメガ3脂肪酸の摂取量を増やすことで、この炎症を関連する物質、炎症性エイコサノイドやサイトカインなどの物質を減らすことができます。
メンタルの不調を改善
人生の幸福度を高めるためにはメンタルの維持が重要です。肉体的な健康と精神的な健康は密接に関係しており、この2つが健康的であってこそ健康になれるのです。例えば現代病のうつは、糖尿病、心臓病、脳卒中のリスクを高めることになります。同様に肉体的な不健康は精神疾患のリスクを高めることにもなります。
オメガ3脂肪酸を定期的に摂取している人はうつ病などの精神疾患になる可能性が低いことが研究で示されています。オメガ3脂肪酸がなぜメンタルの不調改善につながるのか、その仕組みは明らかになっていませんが、オメガ3脂肪酸が脳内のセロトニン及びセロトニン受容体に影響をもたらすことが理由ではないかと考えられています。また体の炎症を抑える効果によって改善するのではなにかとも考えられています。特にEPAが一般的な抗うつ薬と同じくらい効果があることも研究で分かっています。さらにオメガ3脂肪酸の摂取量を増やすことで、加齢に伴う認知機能の低下を遅らせることや、アルツハイマー病のリスクを下げることも分かっています。
肝臓と睡眠にも効果
オメガ3脂肪酸は肝臓の脂肪を減らしてくれることが研究で示唆されています。特に現代人の多くが、中性脂肪が肝臓に溜まってしまう疾患である脂肪肝に悩まされています。脂肪肝は慢性肝疾患の最も一般的な原因になりますが、オメガ3脂肪酸によって、特に非アルコール性脂肪肝疾患の患者の肝臓に蓄積した脂肪と炎症が減ることが示されています。
睡眠のトラブルにもオメガ3脂肪酸が効果的です。摂取することで睡眠の長さが長くなることや、睡眠の質が向上することが分かっています。DHAが不足すると、睡眠ホルモンであるメラトニンが減少してしまいますが、補給することでメラトニンの量を増え眠りやすくなると考えられています。
肌トラブルを軽減
血液の流れが悪くなると肌全体に必要な栄養が届かなくなることで乾燥や肌トラブルの原因になります。オメガ3脂肪酸には、血流を促す働きがあり、ターンオーバーを整え、さらに腸内環境も整えることができ、肌トラブルを予防する効果があります。またオメガ3脂肪酸の中性脂肪の合成を抑える働きによって、コレステロールを減少させことも分かっており、代謝を上げて脂肪の燃焼効率が向上するという研究もあります。
頭痛も軽減
頭痛に悩む全体の人口の12%の頭痛は原因が分かっておらず、原因が分からないので対処もできないという状況があります。その中でオメガ3脂肪酸によって頭痛を軽減することが研究で示唆されています。
慢性頭痛に悩む男女51人に対して、1日1.5gのオメガ3を60日間飲み続けることによって頭痛が75%軽減したという大学での実験データがあります。実験では、オメガ3脂肪酸によって頭痛の頻度が月6回以下に減少、さらに起きたとしてもその辛さが75%軽減したとのこと。なぜ効くのかは様々説があり、DHAやEPAがセロトニンセクターとして作用しているとも言われています。
ただし、オメガ3脂肪酸をコンビニなどのサプリで摂ることはNGです。ハーバード大学の研究では、薬としてつくられていない市販のサプリの殆どが酸化しており、老化の原因などに繋がってしまいます。
オメガ3脂肪酸は朝食で
サバやイワシなどの青魚にはオメガ3脂肪酸という非常に体に良い不飽和脂肪酸がたっぷり含まれています。オメガ3脂肪酸は 血中の悪玉コレステロールを減少させ、ドロドロの血液をサラサラにする効果があります。このオメガ3脂肪酸の効果を最大化するには、摂取する時間帯が大事です。実はオメガ3脂肪酸は、朝に取ることで最も血中濃度が高まりやすいことが明らかになっています。従来の栄養学ではなく、生体リズムに即した食べ方、つまり各栄養素の効能を最大化するために最適な時間があります。
2013年に行われた研究では、DHAとEPAを朝に摂取した場合には、それらを夜摂取した場合に比べて、血液中のオメガ3の濃度が高くなることが分かりました。またDHAやEPAを朝摂取することで血液や中性脂肪の量が、夜摂取するよりも優位に低下することも分かっています。
オメガ6脂肪酸が慢性炎症の原因
オメガ6などの悪質な油の摂取が体内炎症の原因になります。オメガ6は、サラダ油などに大量に含まれており、私たち現代人の一般的な食生活において大量にとってしまいがちな油です。
ただしオメガ 6には、白血球を活性化させる働きがあり ます。白血球は体外から侵入してくと異物と戦う免疫細胞で、それを活性化させるのは免疫力をアップするという点では悪いことではありません。本来、炎症とは白血球が外からの攻撃に抵抗している状態、つまり白血球も炎症もそれ自体は悪いものではありません。しかし過剰にオメガ6を摂取していると白血球が活性化しすぎて自分自身を攻撃してしまったり、ずっと同じところで炎症を引き起こしたりしてしまいます。これが慢性炎症につながり、老化を引き起こしてしまいます。
体内の炎症レベルを調べる検査の一つにCRPというテストがあります。この数値の値が基準範囲の数倍になってしまうという人が意外に多くおり、炎症レベルが高いということは、軽度な炎症が慢性的に体の中で続いているということを表しています。そして軽度の炎症が慢性的に続くと、アルツハイマー型の認知症の発症が早まる可能性が高いという研究結果があります。また脳内の炎症がアルツハイマー型認知症の原因だとする仮説まであります。
さらに慢性炎症が動脈硬化の進行を早めるということも医学的に分かってきています。動脈硬化はすなわち血管の老化で、最終的には全身の老化にまでつながってしまいます。
DHAサプリには注意
私たちが食事から摂取する脂肪酸には大きく分けて不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸の2種類があります。このうちバターなどの飽和脂肪酸が体に悪く、オメガ3などの不飽和脂肪酸は体に良いというのがこれまでの定説でした。しかし最近ではこの不飽和脂肪酸は食べ方によっては、私たちの脳に悪影響を及ぼすことが分かってきています。
不飽和脂肪酸のうち、オメガ3やオメガ6は健康維持に必須であるにも関わらず体内で合成することができません。オメガ3はEPAやDHAなど青魚から取れる多価不飽和脂肪酸ですが、特にDHAは私たちの脳を蘇生する重要な成分であり、脳細胞の健康を保つために非常に重要な栄養素です。
そのためDHAのサプリメントなどを摂取している方も多いかもしれませんが、このような多価不飽和脂肪酸は非常に酸化しやすいという特徴をもっています。
酸化によって細胞が酸化すると、その酸化した細胞がフリーラジカルという極めて高い酸化力を持つ物質を生み出して、さらにその周りの細胞まで酸化させてしまいます。つまり品質の良くない安物のサプリの場合、そのカプセルの中に入っているDHAは全て酸化しており、酸化した多価不飽和脂肪酸からはアルデヒドという副産物が生成されます。アルデヒドはアルツハイマー病の特徴である脳内の粘着質プラークの生成に関わっているという説もあり、脳のエネルギーを生み出すミトコンドリアにとって有害物質となってしまいます。
美肌になるスキンケア食材
青魚
肌をキレイにするという観点から、外せない脂肪の多い魚はサーモン、ニシン、イワシ、アジ、サンマです。こういった脂肪の多い魚には、肌をしなやかに保湿するために必要な成分のオメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。実際にオメガ3脂肪酸が不足してしまうと乾燥肌の原因になるということが研究で示されています。
オメガ3脂肪酸は、肌のバリア機能をサポートし、バリア機能が向上することで肌の水分保持力が高まり、乾燥や外部刺激から肌を守ってくれます。またオメガ3脂肪酸は、赤みやニキビの原因となる炎症を抑えてくれます。さらにオメガ3脂肪酸には抗炎症作用があり、炎症はアトピー性皮膚炎やニキビ、乾燥肌などの肌トラブルに関与しているため、炎症を抑制し、肌の健康を維持することが期待でき、紫外線の悪影響からも肌を守ってくれる役割もあると考えられています。
一方で、脂肪分の多い魚は肌に重要な抗酸化物質の一つであるビタミンEを含んでいます。ビタミンEには、強力な抗酸化作用があり、肌の老化を防ぎ、炎症を抑制し、皮膚のバリア機能をサポートしてくれます。特に活性酸素は肌のコラーゲンやエラスチンを破壊し、シワやたるみを引き起こすため、ビタミンEの抗酸化作用がフリーラジカルを中和することによって肌の老化を防ぎます。また皮膚のバリア機能が強化されることで肌の水分保持能力が向上し、乾燥や刺激による肌のダメージを防いでくれます。
ナッツ類
ナッツは、栄養がぎっしり詰まった天然のマルチサプリメント、それ以上の存在だと言えます。なぜならタンパク質、脂質、炭水化物など食事に必要な3大栄養素を全て含んでおり、その上でビタミンやミネラルも豊富で、ナッツを食べるだけで生命を維持することができるとも言われています。卵が完全栄養食と言われますが、それは新たな生命を作り出すために必要な栄養素が詰まっているからです。ナッツ類も同じで、新たな命がそこから芽吹いてくる種であり完全栄養食です。
また、ナッツに含まれている 脂質というのは非常に健康に良い資質であり、カロリーが高いからといって避けるべきものではないことが分かっています。これは多くの研究で証明されており、含まれている脂質の種類によって体に与える影響というのは大きく変わっており、カロリー表示だけを見てその食材が健康に良いとか悪いとかダイエットにいいとか悪いとか議論することはできません。
実際ナッツをたくさん食べることによって減量に成功したという報告も多数寄せられています。ナッツに含まれている脂質の中でも有名なのはオメガ3系脂肪酸です。むしろ積極的に取るべき資質のため、カロリーが高いからといってむやみに避ける必要はありません。
ナッツ類の全般的な健康効果に関して、一掴みのナッツを定期的に食べる人はナッツを全く食べない人に比べて30年間全死因の死亡率がなんと20%も低かったという研究結果があります。この結果はトータル10万人以上の看護師医療従事者を追跡調査した結果、分かったことでありかなり信憑性が高いデータと言われています。
アボガド
アボカドには不飽和脂肪酸であるオレイン酸が豊富に含まれています。オレイン酸は皮膚のバリア機能をサポートし、保湿効果を高めることが研究で示唆されています。その研究では、700人以上の女性が参加し、特にアボカドに含まれる脂肪を多く摂取することが、よりしなやかで弾力のある肌と関連しているということが分かっています。
また、アボカドにはビタミンE、ビタミンCも含まれています。これらの強力な抗酸化作用により、肌のコラーゲンやエラスチンにダメージを与え、シワやたるみを引き起こす活性酸素の害を防ぐ働きがあります。またビタミンCはコラーゲンの生成に必要な栄養素であり、コラーゲンは肌の弾力と構造を維持するために重要なタンパク質です。ビタミンCがコラーゲンの生成を促進することで、肌の弾力が向上しシワやたるみの予防に役立ちます。さらにビタミンCには美白効果があり、ビタミンCはメラニンの生成を抑制しシミやそばかすを薄くする効果が あります。これはビタミンCがチロシナーゼという酵素の働きを抑制することでメラニンの生成の過程に影響を与えるためです。
カカオパウダー
カカオパウダーやダークチョコレートの原料はカカオですが、カカオの肌への効果を示す研究があります。抗酸化物質を多く含むココアパウダーを毎日6から12週間摂取したところ 参加者の肌がより厚くより潤うということが確認されています。また肌荒れが少なくなり 肌の血流がアップしたということも確認されていて、より多くの栄養素を肌に届けることができ、肌の状態が改善すると考えられます。
また別の研究では、1日に20gのダークチョコレートを食べると紫外線のダメージを防ぐことができたことも確かめられています。さらにその他の研究でも、シワやお肌の状態の改善など同様の結果が観察されております。
プロテイン(タンパク質)
肌にとってタンパク質がとても重要です。タンパク質はアミノ酸という基本単位から構成されており、アミノ酸は肌の構造と機能に必要なコラーゲンやエラスチンなどのタンパク質を作るために使用されます。これらのタンパク質は肌の弾力や構造を維持し、肌を健康的に保つために必要です。当然タンパク質が不足してしまうとお肌がカサカサになったり、お肌の状態が悪くなったりといった肌のトラブルが発生してしまいます。
またタンパク質は、皮膚の修復や再生を助ける働きがあります。皮膚がダメージを受けたり 傷ついたりした場合に新しい細胞が生成するためにはタンパク質が必要です。タンパク質の必要量は、成人の場合体重1kgあたり約0.8gのタンパク質を摂取することが推奨されています。例えば体重60kgの成人は1日に約48gのタンパク質が目安です。しかし毎日きちんと摂取するというのは結構大変なことです。
そこで一般的に高タンパクと言われている食材にどれくらいのタンパク質が含まれているのかの目安を覚えておきましょう。例えば高タンパクで有名なお肉やお魚、豆類には100gあたり約20gのタンパク質が含まれています。また高タンパクで有名な卵1個には6g、納豆1パックには8gのタンパク質が含まれています。もちろん食材からしっかりとタンパク質を摂ることが大事ですが、タンパク質が不足してしまうくらいなら、プロテインで補った方が良いと思います。プロテインに関しては賛否両論あるというのが事実なので、何れにせよ食品から摂ることを意識しましょう。
αリノレン酸で老化!?
植物由来のオメガ3系脂肪酸であるαリノレン酸は、亜麻仁油などに含まれているということで健康効果が注目されています。しかし最新の研究によると中高年以上の方がαリノレン酸を取りすぎた場合には、アルツハイマー病やうつ病の発症リスクが増す可能性があると示唆されています。
実はαリノレン酸は食事から摂取しても直接体内で利用することができません。食事で摂取された後、DHAやEPAに変換する必要があるため非常に効率が悪く、しかも加齢によって変換効率が衰えることが分かってきています。αリノレン酸をEPAに変換する効率は、健康な若い男性の場合であっても僅か8%と推定され、DHAに変換される変換率に至っては0から4%程度であると言われています。つまり健康的な若い男性であっても、亜麻仁油をいくら摂取したところで脳のDHAは全く増えない可能性があります。
一方で、女性の場合は男性よりも2.5倍ほど変換率が高いと言われておりますが、それでも20%に過ぎません。女性も男性と同じく加齢によって、この変換効率は落ち、特に女性は閉経とともに変換効率が激減することが知られていて、これが閉経後の女性で急速に認知症のリスクが上がる理由だと主張する研究者もいます。
さらに、αリノレン酸をEPAやDHAに変換する酵素は、オメガ6であるリノール酸を炎症物質であるアラキドン酸に変えてしまう酵素でもあります。つまり変換効率を上げようとして、この酵素を増やしてしまうと逆にリノール酸がアラキドン酸に変換され、副産物である大量の炎症物質が酸性されて細胞の老化が進むと指摘されています。あくまでも天然のイワシやサバから良質なDHAや EPAを摂取しつつ、その上で亜麻仁油などの自然食品から適量のαリノレン酸を取り入れることが大事です。
良い油と悪い油
脂質は肥満や動脈硬化の原因になると言われてきましたが、脂質は健康を支える要素であることが認識されるようになってきました。しかし脂質にも良い油と悪い油があり、正しい選び方、使い方をする必要があります。
悪い油の代表はサラダ油です。サラダ油には9種類(紅花、ゴマ、米、コーン、菜種、綿実、大豆、ブドウ、ひまわり)あり、どれも避けた方が良いでしょう(ベーゴマここなめだいぶヒマ)。これらにはオメガ6が多く含まれており、炎症を引き起こすことが知られており、アレルギー、がん、糖尿病、うつ(精神疾患)だけでなく、心筋梗塞、脳梗塞を起こす原因にもなっています。またサラダ油だけでなく、ドレッシングにもオメガ6が多く使われています。一方で良い油の代表が、えごま油や亜麻仁油などのオメガ3系油です。
油・脂の選び方
油はダイエットの天敵であるという共通認識がありますが、一方で脂質は三大栄養素の一つです。脂質は体を動かすエネルギーだけでなく、体をつくる材料でもあります。脂質はビタミンA,D,E Kなどの脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きもあります。そのため脂が不足すると肌ツヤがなくなり、髪がパサつくことになります。
アブラには様々な種類があり、無自覚に摂り続けると健康を害してしまう可能性があります。肉の脂身やバターなどの常温で固体の「脂」とサラダ油やオリーブオイルなどの常温で液体の「油」があり、また動物性のものよりも植物性のものがヘルシーであるというイメージがあります。
しかし、アブラの性質を決めているのは、その構成成分である「脂肪酸」です。この脂肪酸には以下の4つがあります。
| 脂肪酸名 | 含まれる食材 | 内容 |
| 飽和脂肪酸 | 牛脂やバターなど常温で固体の油に多く含まれる | コレステロール値を上げて動脈硬化のリスクを高める作用がある。 一方で摂りすぎないと、脳出血の発症率が高まるという報告がある |
| n-3系脂肪酸、オメガ3系脂肪酸 | 魚(DHA,EPA)、えごま油、亜麻仁油などに多く含まれる | DHAは脳の血流を良くして活性化させ、EPAは動脈硬化や心筋梗塞のリスクを下げる |
| n-6系脂肪酸、オメガ6系脂肪酸 | コーン油や大豆油、お菓子、インスタント食品、加工食品にも多く含まれる | 摂りすぎるとアレルギーや動脈硬化を起こすリスクが高くなる |
| n-9系脂肪酸、オメガ9系脂肪酸 | オリーブオイルや菜種油などに沢山含まれている | コレステロールを下げる作用を持つ |
どんなアブラもこれらの複数の脂肪酸で構成されていて、その割合がアブラによって違います。例えば植物油で有名なパーム油はオメガ9系よりも飽和脂肪酸が多く含まれています。そのため摂り過ぎるとコレステロール値を上げて、動脈硬化のリスクを高めてしまう作用があります。このように単に動物性だから健康に悪い、植物性だから健康に良いとは限りません。
いずれにせよ脂は、魚などからオメガ3系を中心に摂り、その他は摂りすぎが健康に良くないため程々にしましょう。ポイントは悪い油が使われている加工食品はなるべく控えましょう。
脂質中毒!?
悪い油(脂質)の摂り過ぎは様々な不調を引き起こす原因となります。糖質中毒に比べて脂質中毒はまだ知られていません。脂質を摂り過ぎてしまう理由の1つに、飢餓に備えて体が食べなくても大丈夫なようにエネルギーを蓄える機能があるからです。そのエネルギーの源になる脂肪を蓄えるために効率的なのが脂質を摂ることです。
穀物などに含まれている炭水化物や、肉や魚に含まれるタンパク質は1gあたり4kcalですが、脂質は1gあたり9kcalです。そのため脂質を美味しいと感じる味覚を持ち、積極的に摂ろうする本能があります。
一方で、あらゆる食に、脂質を添加して味がまろやかにしたり、作りたてに近い美味しさを感じてもらうためにご飯類や麺類にも悪い油がどんどん加えられています。自炊で「食材」と「調理の過程」から脂質に気をつけた食生活を送っていない限り、過剰に脂質にさらされた食生活になってしまっています。
2018年に九州大学の研究グループが、舌の「脂肪味」という6つ目の味覚(甘味、塩味、酸味、苦味、うま味)が存在していることを発見しました。この脂肪味は他の味覚に比べて弱く、脂肪が多い、少ないという量を感じる力に個人差があります。さらに脂肪を大量に摂り続けていると、脂肪を感じる味蕾(みらい)の細胞がさらに鈍くなることが分かっています。つまり脂肪を大量に摂取していることに気付かない状態になり、知らぬ間に脂質中毒になっている可能性があります。
脂質中毒にならないように大切なのは、質の悪い油を過剰に摂取しないことです。外食産業や加工食品に多く使われている安価な油や劣化して酸化した油は、私たちの体を酸化させて、体の炎症を引き起こします。特にトランス脂肪酸は、動脈硬化や心臓疾患、アレルギー、ガンとの関連性も指摘されています。
余談ですが、琉球大学の研究グループから、玄米に含まれる「ガンマオリザノール」という成分が、脳内報酬系を回復させて、脂質の中毒症状を抑えてくれるという研究が発表されました。玄米は白米よりも食物繊維が豊富で血糖値の上昇も緩やかな健康的な食材です。
脂質と脂肪酸
一般的に脂質には、脂肪酸やコレステロール調理に使う油などが含まれています。この脂肪酸には長さによる分類、結合の種類による分類、二重結合の場所による分類の3つの分け方があります。
脂肪酸は、カルボキシル基という分子構造に炭素と水素がくっついてできています。この炭素と水素の連なりがまるで鎖のように見えることから、脂肪酸はその長さによって短鎖脂肪酸、中鎖脂肪酸、長鎖脂肪酸の3つに分けることができます。また脂肪酸の炭素と水素の結合には単結合と二重結合の2種類があります。二重結合を全く持たない脂肪酸を飽和脂肪酸、二重結合を一つ持つ脂肪酸を一価不飽和脂肪酸、そして二重結合を2個以上持つものを多価不飽和脂肪酸と言います。
そして、脂肪酸の結合の位置による分類で、不飽和脂肪酸はその二重結合の位置によってn-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸などに分類されます。オメガ3脂肪酸は 鎖の一番後ろから3番目に二重結合を持つものを指し、同じようにオメガ6 脂肪酸は鎖の一番後ろから6番目に二重結合を持つ脂肪酸を指します。
このように鎖の長さによる分類と飽和・不飽和による分類とは全く別の概念のため長鎖脂肪酸の中にも飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。一方で中鎖脂肪酸はその多くが体に良いとされています。MCTオイルは中鎖脂肪酸が100%の脂質で、長鎖脂肪酸に比べて素早く消化吸収されエネルギーになりやすいという特徴があります。他にもココナッツオイルなども中鎖脂肪酸が過半数を占めています。
一方で、短鎖脂肪酸は大腸の中で腸内細菌によって作られる脂肪酸です。腸内細菌の善玉菌の代表的なものにビフィズス菌がありますが、この菌がオリゴ糖や水溶性食物繊維を発酵することで短鎖脂肪酸を作り出してくれます。この短鎖脂肪酸は、脂肪の蓄積を防ぎ、代謝を上げて痩せやすい体を作ってくれます。また脳に直接働きかけることで食欲を抑えたり、満腹感を持続させるといった効果もあります。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。