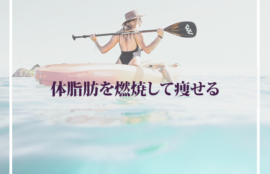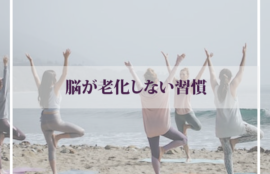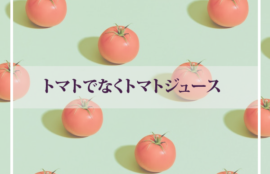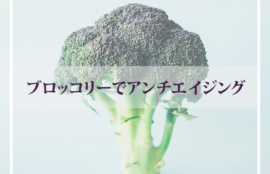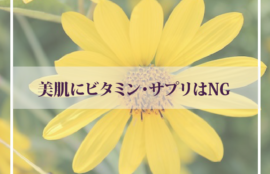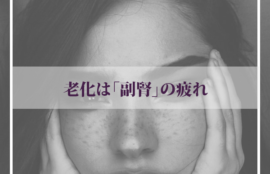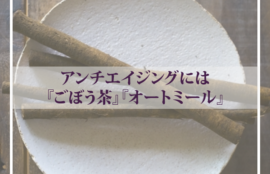炎症とは、傷や感染、アレルギーなどの反応によって、その影響を受けた場所が赤く腫れて熱を持ち、痛みを感じたりする状態です。しかし炎症はなくてはならない生理反応で、例えば病原菌、毒素、外傷が体にストレスをかける時、短期的に起きる炎症は、体を守るために重要な機能です。
怪我をすれば、体内で血液や白血球が怪我をした部分に押し寄せ、修復作業を始めます。傷を直すために一時的に急性の炎症が起こりますが、問題となるのが慢性に起こっている炎症です。なぜ問題になるかは、脳が体内の炎症から悪影響を受けることが分かっているからです。
慢性炎症対策が大事な理由
2016年、慶應大学医学部のチームが高齢者(日本に住む85から110歳1554人)を対象とし、血液検査で全員の肝機能や細胞の劣化といった老化の指標をチェックしたところによると、一般的な高齢者に比べて体の炎症レベルが低いことが確認されています。この結果から、健康的に年を取るには「炎症対策」が最も大事なことであることを示していると結論づけています。
その他の研究でも、慢性炎症は糖尿病、心臓病、肥満などの増加に関連していることが明らかになっており、腸の不調、ガン、アトピー性皮膚炎、花粉症、気管支喘息など様々な病気にも関連していることが分かっています。
特に近年、うつ病は心の問題と考えられてきましたが、うつを発生させる直接的な原因はストレスといった心の問題ではなく、体の中で起こっている慢性炎症であるという根拠がいくつも示されるようになってきています。うつは現在では、脳内で起こる慢性炎症が原因であるということが有力な説になりつつあります。つまりメンタルが弱る、メンタルが不調というのは、脳の慢性炎症が大きく関わっていることが考えられます。
また、慢性炎症は病気だけでなく老化を加速させることも分かっています。一方でなんとなく体調が悪いやいつも疲れているなどの謎の不調の背景にも慢性炎症が大きく関わっていることが約5万人を対象にした調査で明らかになっています。
慢性炎症で老化する
アンチエンジングのためには、体の酸化を防ぐ必要であります。この参加の原因が細胞の炎症です。私たちの体を構成している37兆個の細胞は、細胞膜によって 包まれており、炎症とはこの細胞膜に傷ができた状態のことです。細胞膜が傷ついてしまうと、細胞内に大量の活性酸素などのフリー ラジカルが進入して、体を錆びつかせて、老化が進んでしまいます。
この細胞の炎症を引き起こしているのが慢性型のアレルギーです。牛乳や卵アレルギーというのは、すぐにアレルギー反応が起きて、体中が痒くなったりする急性型のアレルギーです。一方で問題なのは、慢性型アレルギーです。慢性型アレルギーは、急性型アレルギーのように、すぐにわかりやすい症状が現れるわけではなく、なかなか気づきにくいという問題があります。
慢性型アレルギーは、特に腸の炎症を引き起こし、細胞膜の炎症によって酸化が進んだり、細胞内に栄養が届きにくくなります。最悪、細胞膜を傷つけて癌の原因になることもあります。
どうすればなかなか自分では気づきにくい慢性型アレルギーを引き起こす食べ物を特定するために、自分の体の声にしっかりと耳を傾けることです。例えば、食べたものを全部書き留め、体がだるいとかなんとなく気持ちが悪いといった感覚があった時に、数時間前に自分が何を食べたのかをチェックすればある程度判断できます。他にも、世間では一般的に良いとされている健康法が、自分には合わないなとか、自分に合った健康法がわかるようになります。私たちには一人一人個人差があり、一般的に良いとされている方法であっても、自分には合わないというケースが結構あります。
体調不良と慢性炎症レベル
体内の炎症が、学習能力、記憶力、注意力などの脳のパフォーマンスを下げることが証明されています。例えば多数の研究で、炎症を起こす物質を注入されたマウスが、学習記憶を司る脳の部分で認知能力が低下することが示されています。しかも炎症を注入した場所は脳ではなく体でも同じような反応が起こっています。つまりどんな炎症も認知力低下につながることを示しています。
例えば、なんだか調子が悪い、よく寝たはずなのに疲れが取れないといった謎の体調不良は、体の中の炎症反応が原因かもしれません。これを裏付ける研究として、2017年にカロリンス研究所のチームが行なった約5万人を対象にした研究によると、謎の体調不良を抱えている人は体内の炎症レベルが高かったということが報告されています。
睡眠不足が慢性炎症の原因
慢性炎症を引き起こす原因は、食事が大きな割合を占め、過剰なカロリー摂取、加工食品の食べ過ぎ、食物繊維不足、塩分の過剰摂取が挙げられます。これに加えて睡眠不足やデジタル機器や人工照明も慢性炎症の原因になることが知られています。
私たちが人工照明やパソコンの光に夜遅くまで当たっていると、もともと備わっている体内時計が狂ってしまいます。これが睡眠のリズムを狂わせ、熟眠の時間が減少してしまいます。睡眠の質が落ちることで慢性炎症が起こる原因になります。
イギリスのサリー大学が行った調査では1週間6時間以下の睡眠で過ごし、最後に1日徹夜しただけで炎症や免疫系代謝ストレス反応に関連する711もの遺伝子の発現に影響しました。他にも遺伝子の外日リズムが不規則になっていた多くの遺伝子において約24時間周の振動の幅が収縮し、40 時間の徹夜では十分に眠っていた人たちの7倍の影響を受けたという結果があります。
また、2010年に奈良県立医科大学が行った調査では、夜に電気をつけっぱなし、特に明るい光での睡眠は動脈硬化の進行を促し、最も明るい群では心筋梗塞のリスクを10%、脳梗塞のリスクを11.6%も増加させるという結果になりました。この他にも2022年3月にノースウエスタン大学の発表によると、明るい照明をつけたまま寝ると心拍数が増加し、インスリンの抵抗性が増加することも分かっています。また別の研究でも寝ている時に明るい状態だと肥満のリスクも上がることが分かっています。
慢性炎症を引き起こす否定的な感情
悲しみや怒りなどの否定的な感情は、免疫系の機能を損なう可能性のある体内の炎症レベルの上昇に関連していることが研究で分かっています。この研究は220人の被験者を対象に行われ、研究者は2週間にわたって被験者の感情を追跡しました。その結果、被験者の否定的な気分が蓄積されるほど炎症レベルが高くなることが示されました。
一方で、ポジティブな感情は炎症レベルの低下に関連していましたが、ただし低下したのは男性のみで、女性には優位な差は見られなかったことが挙げられます。ここで示唆されているのは感情はコントロールがある程度可能であることです。例えば怒りを感じても、受け流すことができれば炎症を低下させることができます。実際の研究でもネガティブな物事に直面しても、落ち着いたり、元気だった人は炎症リスクが低いことも分かっています。
つまり、言い換えればストレスそのものが問題ではなく、ストレスに対する反応であるため、その捉え方を変えたり、受け流したりすることができれば炎症のリスクが減ります。
感情と炎症の関係を理解するための追加研究が進められており、それが健康を広く促進し、慢性的な炎症、障害及び病気を予防することが将来可能になると予想しています。
ストレスと慢性炎症
精神的ストレスは体の炎症の引き金になります。この精神的ストレスは、自分でも気づかないことあり、人間の脳は物理的なストレスと精神的ストレスを区別することができません。物理的ストレスは、騒音、暑さ、寒さ、密集など、精神的ストレスは、人間関係、パワハラ、モラハラなど今のようなストレス社会では毎日炎症が起きる環境にいることになります。2017年には、がんや心臓病、そして糖尿病やうつ病など様々な病気の発症にストレス誘発性の炎症が関係しているという研究が発表されています。
一方で考えられる原因の一つが腸内環境の悪化です。腸管内膜は、細菌や病原体、毒素などが腸管から血液に侵入することを防ぐバリアの役割があり、そのバリアが損傷するとリーキーガットと呼ばれる減少を引き起こします。この腸管内で長期的に炎症反応が起こると体中に様々な不調が表れます。
また、夏場の炎天下における熱さによるストレスによっても体内の炎症が起こります。熱さによって放熱を促進するため、胃や腸管、そのほかの内臓での血流が減少し、皮膚へより多くの血液を循環させようとします。血流の減少は、酸素量と腸粘膜上皮細胞で利用可能なエネルギー量の減少につながり、その結果リーキーガットを引き起こし、その結果毒素や病原体が血流へ侵入してしまいます。
その他には、加工食品やジャンクフードなどの食生活によっても体内の炎症は引き起こされます。もちろん睡眠不足もです。
さらに現代人にとって必須のツールであるインターネットや人工照明が炎症を引き起こすこともよく知られています。その理由は、特に夜間にこれらから出る光が人の体内時計を狂わせ、睡眠リズムを乱し、炎症から体を回復させる睡眠を妨げるからです。ある研究では毎晩6時間以下の睡眠で1週間過ごした場合、炎症や免疫系、ストレス反応に関連する711個の遺伝子の発現に影響が出たことが報告されています。
そして、内臓脂肪過多の状態も慢性炎症の原因になると考えられています。余分な内臓脂肪からは炎症物質が分泌され、内臓は毛細血管に近く、その炎症物質が血液を通じて全身を巡り、体内のどこかに落ち着くことが繰り返されると慢性炎症の原因となってしまいます。
糖質過多で慢性炎症
体の痛みの原因として、体内で処理できないレベルの糖質過多になって炎症反応が生じているケースがあります。
通常、皮膚や髪だけでなく、骨や筋肉、それをつなぐ腱などの細胞は、毎日細胞分裂をして新しく生まれ変わっています。しかし糖質過多になると、体内のたんぱく質や脂質と糖とが結びつき、変性する「糖化」が起こります。つまり糖を取り過ぎると、たんぱく質と結合し、筋肉や血管などの体の大部分を変質、老化させることになります。その結果、筋肉や血管は、硬くなり伸びが悪くなります。その他にも、慢性炎症による症状の一例として以下が挙げられます。
- 首肩こり
- 倦怠感
- 血管の病気
- うつ症状
- 免疫力の低下
そもそも糖質とは炭水化物の一種であり、糖質+食物繊維の総称です。精製された炭水化物よりも、玄米や全粒粉パンなどの精製されていない炭水化物を食べましょうというのは、白米などの精製された炭水化物は、食物繊維が除去されてより糖質に近くなっているからです。一方で精製されていない炭水化物は、食物繊維が残っているため、それが血糖値の上昇を抑えてくれます。
慢性炎症は、一過性の炎症反応が長期間持続して慢性化した状態で、生体組織の構造に異常が生じて様々な疾患の原因になります。慢性的な炎症がある状態とは、継続して体が攻撃を受け続けている状態で、体の免疫システムが戦い続けている状態でもあります。結果として、白血球が臓器や組織まで攻撃して全身の機能が下がっていくと言われています。
一例を挙げると、心臓病、癌、クローン病、糖尿病、関節炎、潰瘍性大腸炎などの腸疾患に関係していることが明らかになっており、また動脈硬化を加速させることも分かっています。
また、慢性炎症はうつ病などのメンタル疾患を引き起こすとも考えられており、慢性炎症によってサイトカインとう炎症性の物質が分泌されて、それが脳に悪影響を与えるという説があります。
マヌカハニーでアレルギー対策
最近の研究でアレルギーの多くは、体の中で免疫のアンバランスが起こることで引き起こされているのではないかと考えられています。私たちの体は外から異物が入ってきた時に、排除しようという働きがあり、体の炎症を起こして排除します。例えば花粉症では、スギ花粉が入ってきた時に、鼻水を出したり、涙を出して異物を外に出そうという体の働きがあります。
この免疫で排除するシステムで働くのがリンパ球です。このリンパ球の中には異物を排除させるリンパ球とリンパ球の働きを抑えるリンパ球の2つがあります。この2つのバランスが保たれているからこそ、異物を排除して、排除し終わったらそれを治めることができます。このバランスが崩れて、免疫を推し進めるものだけが強くなり、免疫を抑えるリンパ球が少なく、もしくは 動きが悪くなってしまうことによって異物を排除しても必要以上に炎症が続いてしまう状態がアレルギーです。
この炎症を抑えるリンパ球のことをTreg細胞、もしくは制御性T細胞という風に呼ばれています。このTreg細胞を増やすことがアレルギーを抑えることができると考えられています。このTreg細胞を増やしていくことがアレルギーを抑えることだということまでは分かっていますが、この細胞を増やすためには、腸内細菌が生成する短鎖脂肪酸の中でも酪酸が重要な働きをすると言われています。
この酪酸が増えることによって、Treg細胞が増えることが分かっています。この酪酸を増やすのが食物繊維ですが、特におすすめなのがマヌカハニーです。マヌカハニーは、非消火性のオリゴ糖が含まれており大腸までしっかり届きます。さらにマヌカハニーは、胃潰瘍などを抑えることが分かっており、胃腸の調子を整える働きがあります。マヌカハニーの選び方としては、メチルグリオキサール(MGO)と書いてあるもの選びましょう。
花粉症とビタミン
私たちの体には、異物が混入した時に異物を撃退する免疫機能が備わっています。風邪を引きやすい人はこの免疫機能が弱っている可能性が高いです。一方花粉症の場合はさほど有害ではない花粉に対して、免疫機能が過剰に反応してしまうため体を痛めつけてしまうレベルで免疫機能が働いています。この風邪と花粉症は免疫機能の低下と過剰反応という逆の現象が起きています。そのため免疫機能の不具合を調整してあげるための必要な栄養素は同じとなります つまり免疫機能の不具合を調整して、体内で炎症が起きたら、炎症を鎮めるという抗炎症作用を高めて上げることが大切です。
免疫機能を正常に整えてくれる代表的な栄養素は、ビタミンAとビタミンDです。ビタミンAは粘膜を強化してウイルスや細菌の侵入を防いでくれる効果が期待できます。また免疫機能そのものを高めてくれる効果もあります。ビタミンAはレバーや卵に含まれている他、緑黄色野菜に含まれているベータカロテンは体内でビタミンAに変換されるため、人参、かぼちゃ、ほうれん草なども積極的に食べましょう。
ビタミンDに関しては、2019年に東京慈恵会医科大学を中心とするチームが発表した研究によると、ビタミンDの錠剤を取っているグループはインフルエンザや気管支炎、肺炎などの感染症の発症が約2割も少なかったと発表されています。特に血中のビタミンDが欠乏している人が、ビタミンDの錠剤を摂取すると感染症の発症が約7割も減ったとの報告もあります。またビタミンDも免疫機能を高めてくれるため積極的に摂取していきたいビタミンです。
一方で、免疫細胞を増やすためには亜鉛が効果的です。亜鉛は免疫細胞に高濃度で含まれているミネラルであり、免疫細胞を増やしたり、免疫反応を改善してくれる効果があります。亜鉛は、牡蠣や豚レバー、牛肉、煮干し、海藻類などに含まれています。
慢性炎症を抑えてくれる食材
セロリ
セロリは抗炎症作用のある食べ物の中では王様と言って良いくらいの効果があります。その成分がルテオリンとアピゲニンといったフラボノイドです。ルテオリンには抗酸化作用によって細胞を炎症から守ってくれる他にも血中の尿酸値の濃度を下げる、炎症が起こることで上がってしまう血糖値の抑制、動脈硬化の抑制、炎症の原因になる肥満の抑制作用などがあります。これらの作用は体内で炎症を引き起こす物質を抑制したり、脂肪組織における炎症性サイトカインレベルを低下させることが分かっています。
一方のアピゲニンには、ルテオリンよりもさらに強力な抗炎症作用があり、その効果はステロイド抗炎症剤と同程度の抗炎症作用があることが分かっています。実際のデータでも炎症性サイトカインと言って体内の神経系に炎症を引き起こすインターロイキン-1βという遺伝子を抑制し、抗がん作用でも注目を集めている物質です。これに加えてセロリに含まれるアピールセネリンといった香り成分には、精神を落ち着かせ、イライラや頭痛を和らげる効果があります。さらに抗炎症作用のあるβカロテンも含んでいます。
アボカド
アボカドは、心疾患も予防してくれる上に抗炎症作用もあることが知られています。実際、人の調査で明らかになっていて、ハンバーガーとアボカドを摂取させたグループでは、体内の炎症マーカーが減少したという結果になっています。他にもアボカドに含まれるAV119という糖類の一種という成分には、皮膚細胞の炎症を軽減する効果が確認されています。また1998 年のフランスの研究では、変形関節症の患者164名にアボカド成分を含んだ薬を 6ヶ月間投与したところ、痛みと膝の機能が良くなったという結果になっています。
アボカドには、アボカド不添加物が含まれていて、この中にTGF-βという物質が軟骨がすり減るのを防いだり、すり減った軟骨を修復する作用があり、軟骨の変性の修復や予防をしてくれることが分かっています。 2016年にもポーランドで4822名を対象に同じような実験を行い、その結果もほぼ同等なものになっています。ちなみにこの効果をアボカドから摂る場合、1日半分程度のアボカドを食べることが推奨されています。
生姜
生姜には、400種類の天然の化学成分が確認されていて、漢方にもよく利用されています。この内、慢性炎症に作用してくれるのは生姜に含まれるジンベロールという生姜特有の成分で、特に神経系の慢性的な炎症を抑える作用が確認されています。生姜を生のまま摂取すると、慢性炎症を引き起こしアレルギーや喘息の原因物質となるロイコトリエンの形成を抑える効果があります。またジンゲロールは、加熱や乾燥によってショウガオールにという成分に変化し、この成分にもプロスタグラジンという慢性炎症の原因の一つになる物質を抑える効果があります。
サーモン
鮭に含まれているアスタキサンチンとEPA、DHAが強力に体を慢性炎症から守ってくれます。EPAとDHAは、腸の炎症を抑え、血管や脳の炎症からも体を守ってくれます。この2つは慢性炎症を抑えてくれる料理には欠かせない成分であり、心血管保護作業、アレルギー性皮膚炎や糖尿病の抑制、炎症からの細胞保護作用、体内の炎症の原因となる脂肪肝の抑制など、様々な慢性炎症から体を守ってくれます。
これに加えてアスタキサンチンにも抗炎症作用があり、その抗酸化力はビタミンCの6000倍、抗酸化ビタミンであるビタミンEの1000倍の作用がある上に、通常フラボノイドは数時間で体外へ排出されてしまいますが、アスタキサンチンは体内に3日程度留まってくれます。さらにアスタキサンチンは普通の抗酸化物質と違い、細胞の活性酸素の除去をしてくれます。こういった強力な抗炎症作用によって様々なストレスから発生する活性酸素による炎症性サイトカインを抑制してくれることが分かっています。
もち麦
全粒穀物の摂取において人の研究で分かっていることは、全粒穀物を摂取することで様々な炎症マーカーが低減することが分かっています。もち麦には大麦に比べて発酵性食物繊維のβグルカンが豊富に含まれており、このβグルカンには腸の炎症を抑える効果や体内の炎症を抑えてくれる短鎖脂肪酸を増やしてくれる効果あります。腸内環境を改善しないと慢性炎症は解決できないと言って良いくらい腸内環境は慢性炎症と深く関わっています。実際に大麦やもち麦を食べることで善玉菌が増えることも人の研究で明らかになっており、主に腸のバリア機能に大切な酪酸を作ってくれる腸内細菌が増えることが分かっています。
りんご
りんごを1日1個食べると、その抗炎症作用によって体の慢性炎症が取れていくと考えられています。例えば、風邪を引いた時に擦りりんごを食べると良いというお話を聞いたことがありませんか。そのような民間療法は、その抗炎症 作用によって慢性炎症を打ち消してくれるのみならず、風邪によって熱が出すぎてしまった時に下熱してくれる作用や喉が痛い時に、その痛みを和らげて消炎鎮痛作用もあると考えられています。これがりんごを1日1個食べると医者いらずになると言われる由縁です。
そのりんごを食べ続けると癌にかかりにくくなるということが言われています。国立がんセンターが示している癌を防ぐ12箇条によれば、食生活の工夫だけでも癌の約30%が防げると言われています。そして中でも癌を防いでくれる素晴らしい食材こそがりんごです。りんごが持っている抗がん作用は、実はりんごの皮に存在しています。
抗酸化作用を持つプロシアニジンというポリフェノールがお肌の細胞に働きかけることで美白効果を得られることを挙げましたが、このプロシアニジンはりんごの皮の部分に多く存在していると考えられています。プロシアニジンが含まれたりんごの皮を食べることで美肌効果のみならず、癌細胞が増殖するのを抑えてくれることが分かってきています。
人間の胃癌の細胞に、プロシアニジンを与えて培養した実験では、癌細胞のDNAが断片化して細胞自体がアポトーシスを起こすことが確認されました。アポトーシスは、細胞子や細胞自殺と訳されることもある、細胞が自分自身を死滅させることで生態を守ろうとする働きのことです。私たちの体では普段からアポトーシスが頻繁に起こっており、古くなって年を取った細胞というのは増殖の時にエラーを起こしがちになります。
そのようにエラーを起こした細胞は、将来的に癌化する可能性があります。このように癌化する可能性のある細胞は、 あらかじめアポトーシスによって自分自身で消えてくれるようにDNAにプログラムされています。多くの癌細胞では、このようなアポトーシス機能自体にエラーが起こっています。そのため細胞分裂でエラーが起きても自分自身を消去することができず、エラーが起きたまま増殖していってしまいます。
先ほどの研究では胃癌の細胞にプロシアニジンを一緒に与えることで、このようなアポトーシスを誘導することができると分かりました。つまりりんごを食べるだけで癌細胞の失われた細胞死のスイッチをもう一度押し直すことができることになります。
慢性炎症を抑えるオイル
慢性炎症を抑える効果的な方法が運動です。運動をすることで筋肉から生理活性物質であるマイオカインが分泌されて、これによって炎症が抑えられることが分かっています。ただし過剰な運動は逆に炎症を増加させることがあるため、何事も適度に行うことを意識してください。
運動を継続するのが難しい場合は、エキストラバージンオリーブオイルを食事で摂取することが簡単にできる効果的な方法です。研究によるとオリーブオイルに含まれる一価不飽和脂肪酸は体内の炎症を引き起こすインターロイキン-6や腫瘍壊死因子などの炎症マーカーの作用を減らす効果が分かっています。具体的には30件の研究を分析したメタアナリシスによってオリーブオイルを毎日摂取することによって炎症マーカーであるC反応性タンパク質とインターロイキン-6が減少することが分かっています。
また、オリーブオイルに含まれるオレオカンタールという物質は、強力な天然の抗炎症効果があり、炎症を抑えるために用いられるイブプロフェンという薬と同じ作用が確認されています。オレオカンタールは副作用のない誰でも簡単に摂り入れることができる天然の抗炎症剤です。一方でオリーブオイルが炎症を引き起こす遺伝子タンパク質をブロックするのではないかと考えられています。
脳を若返らせるエキストラバージンオリーブオイル
脳細胞は、丸く大きな頭と1本の長い尻尾からできており、イメージとしてはオタマジャクシのような形をしています。大きな頭を細胞体、長い尻尾を軸索と言います。細胞体が脳神経細胞の本体であり、軸索の方は電気信号を流すコードのような働きをしています。細胞体で作られた脳の電気信号がこのコードを通って他の細胞へと伝えられ情報が速やかに伝わります。コードの部分である軸索にはミエリン鞘いう絶縁テープのようなものが巻かれており、絶縁体の役割を担うことによって私たちの脳細胞はより速いスピードで脳の電気信号を別の細胞に伝えることができます。
このミエリン鞘を形成しているものがエキストラバージンオリーブオイルに含まれている一価不飽和脂肪酸です。エキストラバージンオリーブオイルをたっぷり使う食事として地中海食が有名ですが、長期的に続けることによって健康を維持できるのみにならず、脳のサイズが大きくなるという研究があります。さらにバルセロナの研究チームが行った研究では、週に1リットルのエキストラバージンオリーブオイルを摂取した被験者の認知機能が向上したという結果が出ています。おそらく大量に摂取したエキストラバージンオリーブオイルの一価不飽和脂肪酸が大量のミエリン鞘を形成し神経細胞の情報伝達スピードが上がったためと考えられています。
オリーブオイルの選び方
日本で販売されているオリーブオイルにはエキストラバージンオイルとピュアオイル(オリーブオイル)があります。この違いはオリーブオイルを圧搾してオイルを絞り出すはじめのものがエキストラバージンオイルで、何回も圧搾して絞り出したものがピュアオイルです。選ぶべきオリーブオイルはエキストラバージンオイルで、オリーブの実を圧搾してろ過しただけの生のオイルです。化学的な処理が加えられていない非常に品質が高いオリーブオイルであり、含まれるポリフェノールの抗炎症能力が比較にならないほど高い効果があります。
注意しなければならないのは、スーパーに並ぶエキストラバージンオイルのほとんどが国際的な基準に合致していません。その理由は世界と日本で基準が異なるからです。この国際的な基準は大変厳しく、日本は独自の基準でエキストラバージンオイルと名乗ることが可能で、国際的な基準未満のものであっても、日本ではエキストラバージンオイルとして売られているのが実情です。そのため国際基準を満たしているかどうかを確認する必要があります
そのオリーブオイルの選び方として、まずはボトルの色です。オリーブオイルにとって光は大敵で、太陽光だけでなく蛍光灯の光であっても長時間当たると酸化し劣化が進みます。そのため品質の高いエキストラバージンオリーブオイルは、容器のボトルの色が薄いものなどはありません。多くが濃い緑色などの光を通さない色になっています。
次にボトルの材質も大切です。プラスチック容器のエクストラバージンオイルをスーパーなどで見かけますが、これも劣化の原因になります。必ず瓶のボトルのものを選びましょう。そしてボトルに認証マークがあるかをチェックしましょう。
| DOP | 生産や加工、栽培などが全て同じ地域で作られたものしか認められず、製造方法なども厳守 |
| IGP | 生産加工調整のうち少なくとも一つの工程が特定の地域で行われている |
| EUオーガニック認定 | 栽培から生産加工まで専門機関で定期的に検査を受け、原材料の95%以上がオーガニックであることを証明 |
| ICEA | イタリアの有機栽培認証機関が有機栽培を認証 |
| 有機JAS認定 | 禁止農薬や化学肥料、遺伝子組換え技術などを使用していないことなどを遵守 |
また、信頼できる選び方として、国際オリーブオイルコンテストの受賞オリーブオイルを選ぶことです。基本的に産地や生産者や製造方法など信頼できるものしか受賞されていないので安心して買うことができます。日本ではオリーブジャパンというコンテストがあるので、受賞歴のあるオイルを選びましょう。
オメガ3系オイルの健康効果
オリーブオイルと同様に炎症を抑える効果が確認されているオイルがオメガ3系オイルです。具体的には亜麻仁油、えごま油、クルミオイル、チアシードオイルが挙げられます。
オメガ3系オイルの健康効果については、既に膨大な医学研究があり、よく知られた内容としては、オメガ3の摂取量を増やしたことで心臓発作による死亡率が70%低下した研究があります。
オメガ3系オイルは、炎症性エイコサノイドやサイトカインなど炎症に関連している物質を減らしてくれることが確かめられています。ただしオメガ6系オイルは逆に炎症を引き起こすので注意してください。オメガ6系オイルの代表は、サラダ油、コーン油、大豆油、ゴマ油で、値段が安く、様々な加工食品や外食産業で使われているため、摂りすぎないようにしましょう。
一方で、オメガ3系脂肪酸を定期的に摂取している人は不安神経症やうつ病になる可能性が低くなることも示唆されています。なぜこのような効果が現れるかハッキリと結論は出ていませんが、オメガ3系脂肪酸が、脳内のセロトニンおよびセロトニン受容体に影響をもたらすことが理由ではないかと推測されています。また脳の炎症を抑えるためうつ病などの症状が改善するのではないかと考えられています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。