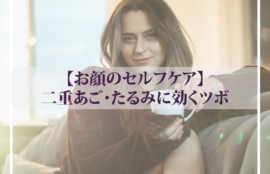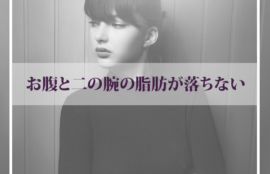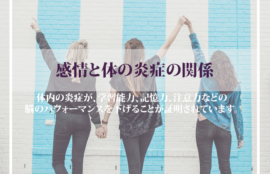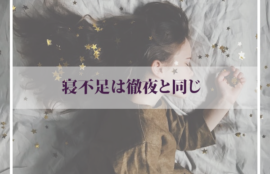砂糖の代替品として蜂蜜を食べると健康に良いと聞いたことがあると思います。しかし砂糖と蜂蜜に何ら違いはないということは多くの人は知りません。他にもグラニュー糖、ココナッツシュガー、メープルシロップなども違いはありません。これらは全てグルコース分子(日本ではブドウ糖)と果糖分子できており、多くの方が蜂蜜などは、砂糖よりも健康的だと勘違いして糖質を過剰に摂取しているのです。
もちろん蜂蜜などには、ビタミンなどの栄養成分や抗酸化物質が多く含まれていることは事実です。しかし蜂蜜に大量に含まれているブドウ糖と果糖の影響を考えればビタミンや抗酸化物質の健康効果はあまり価値がないのも事実です。糖質が悪いということから糖質制限している場合、正しい知識に基づいて血糖値コントロールをできている方は非常に少ない状況です。
糖質を正しく理解する
健康に悪影響なのは血糖値スパイクと果糖スパイクです。血糖値スパイクは血中のブドウ糖の濃度が急激に上昇することで、果糖スパイクも同じく、血中の果糖の濃度が急激に上昇することです。結果として細胞が必要とする以上の糖質が全身に巡ることになり様々な身体的精神的な不調が出てしまいます。
私たちの生命活動に必要なグルコースは、必要不可欠なエネルギー源ですが、細胞内に過剰に供給されると問題が起きる原因になります。ブドウ糖が細胞内に溢れるとミトコンドリアは直ぐにエネルギーに変えていきますが、余分に溢れ出ると小さな分子であるフリーラジカルを放出します。つまりブドウ糖を細胞に与えるスピードが速くなりすぎると、結果として生まれるフリーラジカルが体内で危険な連鎖反応を始めてしまいます。
このフリーラジカルは触れたもの全てにダメージを与え、DNAを改変して有害な遺伝子を活性化させて変異を起こしてがんを発生させることもあります。また細胞膜に穴を開けて、正常に機能している細胞を機能できなくしてしまう作用もあります。人の体はある程度であればフリーラジカルに対処できますが、血糖値スパイクを繰り返してフリーラジカルの量が増えるとコントロールできなくなります。
この状態を体の中で中和できない「酸化ストレス」の状態にあると言います。酸化ストレスは、心臓病や糖尿病、認知低下、老化の原因になります。また果糖が体内にあるとブドウ糖だけの状態よりも酸化ストレスが増加します。このように果糖を含む甘い食品が特に悪いとされているのは、酸化ストレスを増加させてしまうからです。
一方で、ミトコンドリアの機能が低下してブドウ糖を効果的にエネルギーに変えられないようになると、栄養を摂取しているにも関わらず、細胞が飢えて臓器が機能不全に陥ります。体のだるさ、朝起きれない、疲労感が取れないという状態が続き、次第に臓器がダメージを受けて生活習慣病に繋がります。さらに血糖値スパイクは「糖化」を齎します。
体の焦げである「糖化」は、1912年フランスの科学者メイラードによって発見され、グルコースが別のタイプの分子にぶつかる時に「褐変」が起こることから「メイラード反応」と名付けられました。細胞の分子が糖化されるとダメージを受けて損傷してしまいます。ブドウ糖をたくさん体に与えれば、それだけ糖化は頻繁に起こり、結果として老化スピードが速くなります。
果糖を正しく理解する
血糖値以外にも気をつけなければいけないことがあります。血糖値の定義は血中のグルコースの濃度です。つまり血糖値で測ることができるのはグルコースの濃度だけです。ブドウ糖は更に糖度が増した果糖に変化します。つまり正確に測るためには血中の果糖の濃度も測る必要があります。
果糖を食べると一部はブドウ糖に戻りますが、残りは果糖のまま血流に入ります。この果糖分子はブドウ糖より10倍も速く物質を糖化し細胞にはるかに大きなダメージを与えます。白米やうどんなどのデンプン質で果糖を含まないグルコースのみの炭水化物より、ケーキやクッキーなどの甘い果糖を含む炭水化物の方が体に悪いのは酸化と同じく、糖化のスピードも速めてしまうからです。
当たり前ですが、ブドウ糖の過剰摂取だけでも酸化や糖化が起きてしまうのに、ブドウ糖の何倍も酸化や糖化を促進させる果糖を多く摂取すれば過剰なフリーラジカルが発生してしまいます。果糖が恐ろしいのは、白米とケーキの血糖値のあがり方「血糖値スパイク」はほぼ同じですが、実は背後に目に見えない「果糖スパイク」が起きているため、明らかにケーキを食べる方が体に悪影響を与えます。そして酸化と糖化が合わせることで体内が全身性の「炎症」状態になりやすくなります。
このような慢性的な炎症は、脳卒中、慢性呼吸器疾患、心臓病、肝臓病、肥満、糖尿病などあらゆる生活習慣病を引き起こします。世界保険機関(WHO)は、炎症が原因の病気を「人間の健康に対する最大の脅威」としています。世界中の5人に3人が炎症が原因の病気で死亡していると言われています。
蜂蜜の健康効果
蜂蜜には酵素からポリフェノールに至るまで150種類以上の栄養素が含まれていると言われています。蜂蜜が持つ健康効果の中で注目すべきは抗酸化作用です。細胞に存在するミトコンドリアは、エネルギーを産生する過程で 活性酸素という副産物を生み出します。この活性酸素は肌の細胞を錆びつかせ、錆びた皮膚の細胞は、シミやくすみとなって沈着します。この活性酸素を除去して細胞を若返らせてくれるものこそが蜂蜜の持つポリフェノールです。また抗酸化作用の他にも、胃腸の炎症を抑える抗炎症作用もあります。
さらに蜂蜜には、動脈硬化を促進してしまう悪玉コレステロールを下げる効果もあります。コレステロールにはHDLコレステロールとLDLコレステロールがあり、このうちLDLコレステロールは肝臓にある油ギトギトのコレステロールを血液中に連れ出してしまうことから悪玉コレステロールと呼ばれたりもします。
悪玉コレステロールが高いと、それだけ血液がドロドロになるため体には様々な不調が起こります。そのうち特に問題となるのが動脈硬化という毛細血管が硬くなり狭くなってしまう現象です。毛細血管が狭くなればそれだけ血圧が高くなり、血管壁は傷つくことになります。傷ついた血管が修復される過程で血管壁はますます硬くなります。この動脈硬化が進行すると閉塞性動脈硬化症や心筋梗塞、脳梗塞といった様々な病気を引き起こしてしまいます。
成人を対象にしたある研究では蜂蜜含有飲料を摂取したグループでは、血流量が優位に増加してくれることが分かりました。このことからも蜂蜜にはドロドロになった血液をサラサラにしてくれる効果があると言えます。このように蜂蜜が血液をサラサラにするのは、蜂蜜の中に含まれているコリンという成分が血管を拡張させて血圧を下げ、血管壁への悪玉コレステロールの沈着を防ぐためと言われています。
さらに蜂蜜の効能として忘れてはならないのが免疫力をアップさせる作用です。古くは、蜂蜜は火傷にも効くとされ、様々な地域で民間療法として用いられていますし、痛み止めとしても用いられています。これには科学的な根拠に基づいたものであり、痛みを感じるメカニズムは様々ですが、その一つにプロスタグランジンという物質による急性炎症の駆除があります。
怪我をすると壊れた組織を修復したり、そこから入り込む雑菌を退治するために多くの免疫細胞が集まります。すると免疫細胞が分泌するサイトカインという物質によって毛細血管が拡張、毛細血管を形作っている血管内細胞同士の結合が緩みます。このように緩んだ細胞の間から免疫細胞や免疫に関わる様々な物質が組織に浸潤していきます。
こうして組織に浸潤する物質の一つがプロスタグランジンです。プロスタグランジンは、主に炎症部位に発熱や痛みを起こす生理活性物質です。入り込んだ雑菌は熱に弱く、逆に免疫細胞は温度の高い場所で活性化するため、プロスタグランジンが発熱を促すことで免疫細胞が外敵を駆除するのをアシストします。
一方で生活習慣の乱れやストレスなどによって慢性炎症が起こると免疫細胞が暴走してプロスタグランジンが意味もなく分泌されます。このように持続的にプロスタグランジンが分泌されることで頭痛や肩こり、腰痛などの慢性的な不快な症状が出ると言われています。
蜂蜜には抗プロスタグランジン作用があり、経口摂取したり、直接痛い場所に塗布することでプロスタグランジンによる不快な痛みを鎮めてくれる効果があります。
蜂蜜の美肌効果
蜂蜜に含まれている豊富なポリフェノールは、お肌の健康にとって非常に効果的です。ハチミツにはコリンという物質が豊富に含まれており、コリンは細くなった毛細血管を広げてくれる働きがあります。特に加齢によって細くなってしまった毛細血管が広がれば、その中に流れる血液が通りやすくなり、肌の細胞にきちんと酸素や栄養が行き届くようになります。もちろん血液がたくさん 供給されれば同時に水分もたっぷり供給されるため、カラカラに干からびていたお肌の細胞がどんどん瑞々しくなっていきます。
一方で、蜂蜜にはケンフェロールやケルセチン、バニリン酸やP-ヒドロキシ安息香酸など、良質なポリフェノールが含まれています。これらポリフェノールには抗酸化作用があり、ハチミツに含まれる数多くのポリフェノールが活性酸素を無毒化してお肌の酸化を抑制してくれます。
また、手というのはお肌と同じぐらい私たちの年齢を表す重要な部位です。そんな手の中でも特に大切なのが爪です。ハチミツには、ビタミンBやビタミンCと違って水に溶けにくい脂溶性ビタミンのビタミンEも豊富に含まれています。ビタミンEには、爪の血行を良くしてくれる働きがあります。爪の血行といっても爪そのものには血管が通っていません。あくまで爪の根元にある爪を作る部分です。ビタミンEによって血行が高まることで爪がツヤツヤで綺麗なピンク色になることが知られています。
ただし、ビタミンEは脂溶性ビタミンのため、尿として排泄することができません。そのため摂り過ぎると重篤症状を起こすことがあります。しかしハチミツに含まれる天然のビタミン Eであれば自然な量が含まれていますので、適量であれば蜂蜜を食べてもビタミンE中毒になる心配はありません。
蜂蜜で腸内環境の改善
私たちの腸内には、善玉菌や悪玉菌といった様々な菌が生息しています。このような菌のバランスを腸内細菌層と言い、当然悪玉菌よりも善玉菌がたくさんいた方が腸内フローラは良いとされています。しかし生活習慣の乱れや悪い食習慣によって腸内環境は乱れ、特に加工食品に汚染された現代人の腸は、悪玉菌によって大きく乱れていると考えられています。
このような腸内の乱れを改善してくれるのが蜂蜜です。蜂蜜に含まれているオリゴ糖やグルコン酸といった栄養素は、腸内の善玉菌の大好物のため、腸内細菌層が善玉菌優位になってくれます。さらに最近の研究でグルコン酸は有機酸の一種であり、悪玉菌の増殖を抑制してくれる作用もあることがわかってきています。ハチミツに含まれるオリゴ糖とグルコン酸を摂り、善玉菌が優位になると腸内環境はみるみる改善されていきます。腸内環境が改善されれば、お肌にも良い影響を与えてくれます。
多くの方が、スキンケアなどの外側のケアを頑張っていますが、内側のケアができていない方がいます。お肌の内側のケアというのは他でもなく腸内環境を改善することに他なりません。腸内環境が悪くなってしまうと悪玉菌が優位になり、悪玉菌が生み出すガスによって腸が毒素でいっぱいになってしまいます。
腸がガスでいっぱいになってしまうと、おならでガスを出してもガスの排泄が間に合わず、腸管壁から有毒ガスが漏れ出し、毛細血管に吸収されていきます。すると有毒なガスが血液に溶けて全身の細胞に運ばれ、全身に有毒ガスが漏れ出せば、当然私たちの皮膚にもそのような有毒ガスが運ばれてしまいます。
そして、最終的には有毒物質がお肌の細胞に蓄積することで、お肌が内側からボロボロになってしまいます。肌が内側からボロボロになってしまったら外側からどれだけ高級な美容液や乳液を塗ったところで意味がありません。
蜂蜜によって身体に起こる変化【最新研究】
蜂蜜は貴重なもので、1匹のミツバチが一生かけて集められる蜂蜜の量は、小さじ1/12 杯ぐらいです。例えば450gぐらいの瓶の蜂蜜を作るのに200万匹の蜂が必要だと言われています。また1 匹のミツバチが蜂蜜を作るためには約9万キロを移動して集めてくると言われており、蜂蜜そのものの存在がとても貴重なことに間違いありません。この蜂蜜の生産量が激減しており、入手できる本物の蜂蜜を入手するのが非常に難しくなってきてるのが現状です。
一方で、蜂蜜の健康に対する様々な効果が明らかになってきており、例えば糖尿病や肝硬変などの様々な慢性疾患に良い影響を与えることが報告されています。さらにそれらの痛みの管理やストレスを軽減するなども報告されています。
これまで報告された健康効果の中でも、特に人の記憶力を高めたり、脳神経の炎症を抑えるなど脳の健康について良い影響を与えることが続々と報告されています。また体が有害な刺激を受けた時に、体が自然防御反応を示すことに対して、その体の有害反応を起こさないように抑える働きが確認されています。例えば騒音は、長時間聞かされ続けると鬱になったり、認知機能が低下することが分かっていますが、蜂蜜を摂取するとで騒音に対する影響を緩和し、その不快感を和らげるメカニズムを蜂蜜が引き起こすと考えられています。
実際、蜂蜜を摂取するとストレスホルモンのコルチゾールや、脳から出る副腎皮質刺激ホルモンが下がることも分かっています。その結果、抑うつの行動が極端に少なくなることが挙げられます。
一方で、蜂蜜にはフェニル酢酸というアミノ酸含まれており、それを摂取することによって脳内のBDNF(脳由来神経栄養因子)が作られるようになって脳機能を改善することが確認されています。つまり抑うつの効果を軽減するってことにつながってくるのではないかと推察されています。
また蜂蜜には、フラボノイド、フェノールなどの抗酸化物質が豊富に含まれ、炎症を強く抑える効果があり、さらに体の中の酸化を防ぐことにもなります。例えば脂質の酸化を抑えたり、酸化を抑える酵素の活性を上げるスーパーオキシドディスムターゼやグルタチオンなど体の中の錆を取る酵素の活性を活性化させることができることになります。
実際、蜂蜜を食事に取り入れた時に、脳の重要な領域(視床下部など)に、酸化ストレスに対するその抵抗性というのを示すことが確認されています。つまり抗酸化物質が減ったり、過酸化脂質のレベルが下がる、その痛みに対する感受性、食欲に対する行動が変わるってことも起こります。このように蜂蜜の様々な影響によって、幸福感を増したり、全体的な健康効果を上げるのに非常に有用なものであるということが改めて認識されてきています。
純粋蜂蜜以外の蜂蜜
純粋蜂蜜とは加工処理を一切行っていない天然の蜂蜜のことを指します。一方で体に悪い果糖ハチミツがあります。果糖ハチミツとは、ハチミツに水飴や果糖などを加えて加工したもので、一言で言えばただの水飴です。純粋蜂蜜の基準は、果糖の含有量が100gあたり60g以下のものを指します。
100gあたり60g以上の果糖が含まれているハチミツは、蜂蜜が本来持つ健康効果を台無しにします。他に生成蜂蜜という分類の蜂蜜がありますが、果糖ハチミツほどの有害性はないもののあまりお勧めはしません。生成蜂蜜は、特有の臭みを消すためにタンパク質やビタミンといった栄養素がろ過されて除かれています。
また、純粋蜂蜜の中にも表示されてはいない加工が施されているステルス加工ハチミツがあります。例えば安物の中国産の蜂蜜には人工的に過熱することで水分を蒸発させた蜂蜜というのが存在します。これは水分量が多いとハチミツは発酵してしまうため、賞味期限が短くなるため安価に流通させるのが難しくなるためです。つまり大量生産を実現するために質の悪いハチミツは加熱によって水を蒸発させているため、むしろ有害な成分を持ってしまう恐れがあります。
ハチミツをはじめ牛乳やフルーツジュースなどを加熱すると糖の熱分解によってヒドロキシメチルフルフラールという物質が生まれます。この物質は近年に発見されたため、安全性に関する研究があまり進んでおらず、健康に害がある可能性が指摘されています。また加熱処理したかどうかを表示する義務はありません。そのため安価な中国産の蜂蜜は加熱処理されていると考えられます。
低品質なハチミツの見分け方
サラサラでなく、ドロドロの蜂蜜は良質な蜂蜜の証しです。天然の蜂蜜はミツバチによって、採取された花の蜜を主成分とします。花の蜜の糖分の大半はスクロースという糖ですが、巣の中でブドウ糖や果糖オリゴ糖などを様々な糖に分解されていきます。このように天然の純粋蜂蜜にも多少の果糖が含まれていますが、果糖の含有量を見分ける方法が冷たいところで固まるかどうかを見る方法です。果糖の含有量が多いと寒い場所でもサラサラな状態を保ちます。一方で果糖の含有量が少ない蜂蜜は、寒いところではすぐに固まります。
色の薄い蜂蜜
天然の純粋蜂蜜は様々な花から取られため、濃い茶色から透明に近い黄色まで 様々な色があります。この中でも最も栄養が高いのが色の濃い蜂蜜です。色の濃いハチミツほど多量のミネラルやポリフェノールを含み抗酸化作用が強いためです。もちろん天然の純粋蜂蜜であれば色の薄い蜂蜜も体に良い健康効果が期待できます。
蜂蜜は1日に大さじ2杯程度
ハチミツはどんなに健康に良いとは言え、果糖をはじめとする糖分が含まれています。カナダのトロント大学の研究によると、蜂蜜は糖質が多いものの適度であればむしろ血糖値を下げる効果があることが分かっています。この研究では大さじ2杯の蜂蜜を毎日食べることで血糖値やコレステロール値などが改善し、心血管代謝を健康に保つことに役立ったという結果が出ています。
因みに赤ちゃんに蜂蜜を食べさせてはいけません。蜂蜜に生息するボツリヌス菌によって、乳児ボツリヌス症が引き起こされ最悪の場合呼吸が止まる可能性があります。
血糖値が上がる理由
ご飯、パン、麺類といった炭水化物の中に入っている糖分が血糖値を上げる原因になりますが、一方でタンパク質や脂肪は食べても血糖になることはありません。食事から得た糖は、腸から吸収されて肝臓に送られます。糖の一部をグリコーゲンとして肝臓に蓄えます。このグリコーゲンとして蓄えられなかった残った糖分が血糖として血液中に放出されます。糖尿病の人は、食べた糖が全て血液中に流れてしまい血糖値が急上昇します。
また、ストレスや寝不足、体調不良など食事以外の要因でも血糖値が上がる可能性があります。なぜなら体内にはコルチゾールやカテコールアミン、グルカゴンなど血糖値を上げる働きを持っているホルモンが多く存在するからです。例えば寝不足になるとコルチゾールやカテコールアミンと呼ばれるホルモンが沢山作られます。コルチゾールは、脂肪やタンパク質から血糖を作り出す反応を促し、血糖値が上がったりします。
空腹時の血糖値は、主に肝臓のグリコーゲンと糖新生というメカニズムによって支えられています。空腹になると膵臓がグルカゴンというホルモンを作り、肝臓に作用しグリコーゲンを分解して血液中に流すことで血糖値を上げる働きがあります。
糖新生は、タンパク質や脂質から血糖を作るメカニズムです。血糖値が下がってくると、脳から副腎へ指令が送られてコルチゾールというホルモンが作られます。このコルチゾールが糖新生を促して血糖値を維持します。糖質を摂らないと常に糖新生によって血糖値が維持しようと働き、結果として糖新生が起こらなくなると、食欲が乱れて食べ過ぎになってしまいます。
また、腸内環境が悪いと、全身の炎症が引き起こされ、インスリン抵抗性と呼ばれるインスリンが効きにくい状態になると言われています。他にも腸内ではGLP1と呼ばれる血糖値を下げるホルモンが作られていますが、腸内環境が悪くなると、このGLP1が必要量を作られなくなり血糖値が上がりやすくなります。
ブドウ糖の貯蔵庫
血中のブドウ糖や果糖が増えてミトコンドリアが機能不全に陥らないようにするために、膵臓がインスリンを分泌して余分なブドウ糖を体内の貯蔵庫にしまい込みます。第一の貯蔵庫が肝臓、第二の貯蔵庫が筋肉で、これらで貯蔵しきれない糖質は、第三の貯蔵庫である脂肪として体に付きます。上記で述べた果糖は脂肪でしか蓄えられません。さらに果糖から作られた脂肪は、動脈硬化や心臓病を引き起こす悪玉コレステロールを増やす作用があります。ここからもカロリーが同じ食品でも果糖を含む甘い食品を食べる方が体に与える有害性が遥かに大きいことが分かります。
世の中には、「無脂肪」などと謳っている加工食品が多くありますが、それらにはショ糖が多く含まれています。そのため体内で消化されるとショ糖に含まれる果糖が脂肪に変わり、結果として太りやすくなります。
正しい順番で食べることが大事
野菜から食べることを心がけている方が多いと思いますが、血糖値を上げないためには、何を食べるべきで何を食べてはいけないということよりも、食べ方の方が大事です。2015年アメリカのコーネル大学が発表した論文によると、デンプン、食物繊維、糖、タンパク質、脂肪を正しい順番で食べるだけで、血糖値スパイクが73%減り、インスリンスパイクも48%減ったことが発表されています。このように同じ食事でも食べ方によって全く違う影響があることが分かります。
正しい順番の食べ方は、最初に食物繊維、タンパク質、脂肪、デンプンと糖です。仮にデンプンや糖を先に摂ってしまうと、すぐに小腸に入りグルコース分子に分解されるため、瞬く間に血中に入って血糖値スパイクが起きてしまいます。逆に食物繊維から食べると、食物繊維の十分な力を利用することができます。
その1つがデンプンをグルコース分子に分解するα—アミラーゼという酵素の活動を抑える働きです。2つ目が胃に入った食べ物が小腸に流れていくスピードを遅くすることができこと。最後が小腸の内側に粘着性のある網を作り出し、グルコースが血中に入ることを抑える働きです。この3つの働きよってグルコースの分解と吸収のスピードを緩めて血糖値曲線をなだらかにしてくれます。
このように食物繊維を先に食べることで、脂肪を含む食品を胃から小腸に流れていく速度をゆっくりしてくれるため、最後に炭水化物を摂ることがベストです。結果としてデンプンと糖を食べられる上、さらに体への影響を小さくすることができます。さらにインスリンの分泌量も減るため素早く脂肪燃焼モードに戻りダイエット効果も期待できます。また2017年にミシガン大学で行われた研究によれば、血糖値がなだらかな人は、カロリーを沢山摂っても血糖値スパイクを繰り返している人よりも脂肪が減りやすいことが分かっています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。