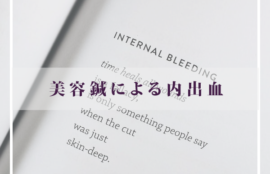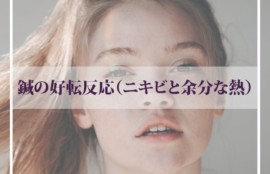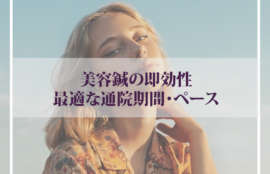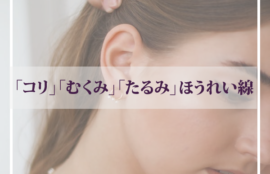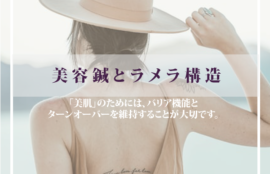いわゆるブルドッグ顔というのは、目の下や上瞼を始め、口元がたるみ、ほうれい線やマリオネットラインが深く入っている状態のことです。顔のたるみの原因は、表情筋が弱ったり、脂肪が原因になるだけでなく、肌の状態もその1つです。つまりお肌のハリや弾力のために欠かせないコラーゲンやエラスチンの状態が影響します。また加齢による骨の減少や水分や老廃物によるむくみも顔のたるみの原因になります。
表情筋と皮下脂肪について
顔にも表情筋と言われる筋肉があり、それが年齢と共に衰えます。実は表情筋は、日常の生活では3割程度しか使われていません。そのため放っておくとどんどん衰えてしまいます。
また、たるみが気になって脂肪を減らそうと無理なダイエットをすると急激な体重の減少により、皮膚が短期間で縮むことでたるみが悪化することがあります。さらに筋肉量の低下も伴って皮膚の支えが失われてたるみが生じやすくなります。そして加齢で弾力がなくなった皮膚の下の脂肪の層が増えすぎると、今度は筋肉が脂肪を支えきれなくなり、顔がどんどん下に崩れ落ちるようにたるみます。そのため適度に表情筋を鍛えることは最低限必要ですが、肌は非常に繊細なため強く擦りすぎたりして筋組織が壊れてしまうことがあります。
一方で、筋肉や脂肪の状態が仮に良くても皮膚のハリや弾力が足りなければ、当然お肌がたるみます。このハリの源となるコラーゲンを膠原繊維、エラスチンは弾力繊維と言い、どちらもタンパク質の一種です。これらが真皮の層で 網目を作っており、この編目の中がヒアルロン酸で満たされて初めて弾力が生まれます。
光老化と骨密度
肌のハリや弾力がなくなる原因が光老化です。光老化は紫外線のuvaが皮膚の奥の真皮に侵入し、コラーゲンやエラスチンなどの繊維を破壊されることで皮膚の弾力やハリが失われたるみが引き起こされてしまいます。しかし確かにコラーゲンとエラスチンを守るためには紫外線対策は必要ですが、実はたるみの原因の1つに骨痩せがあります。顔の皮膚や筋肉、脂肪といった組織との間に隙間ができると、骨と組織のくっつく力が弱くなって緩み、重力の影響で垂れて下がっていきます。
特に頭蓋骨の中でもブルドッグ顔を作る原因になる骨は、顎と頬の骨です。顎が痩せて後退すると口回りの皮膚が垂れたり、口角が下がったりしやすくなります。そして頬骨が縮小すると頬が下がるのはもちろん、顔全体の締まりがなくなります。
骨痩せは、骨密度が下がることで起きますが、特に女性ホルモンのエストロゲンが減少することが大きな要因です。エストロゲンは、コラーゲンとエラスチンを作る上で大切なホルモンであり、特に女性の場合40代に訪れる更年期で激減し、閉経後さらにエストロゲンの分泌量は減ってしまいます。そのため40代になってブルドッグ顔で悩む人が増えてきます。
一方で骨密度が低下する理由に、必要な栄養の不足が挙げられます。骨に必要な栄養といえばカルシウムですが、血中のカルシウム濃度が足りないと新しい骨の生成が止まるだけではなく、今ある骨のカルシウムが奪われることになります。
その他にもたるみ予防のために骨密度を上げる方法としてはウォーキングや ジョギングなどの有酸素運動、ウェイトマシンを使った筋力トレーニングが効果的です。また水泳のように過重負荷の少ない運動は骨密度の向上には不向きです。
また成人女性が1日に必要とするカルシウムの摂取目安量は、600mgから650mmで、牛乳だけで換算するとコップ3杯分程度で十分可能です。ただし栄養バランスを考えるとそれだけだと不十分で、骨ごと食べられる小魚や大豆製品も組み合わせて食べるようにした方が良いでしょう。
しかし、カルシウムは単体ではあまり吸収されにくいためビタミンDを同時に摂ることが必要です。ビタミンDは、血中のカルシウム濃度を高めて骨の生成をサポートしてくれる成分です。さらに骨を作る細胞と分解する細胞の調整役にもなってくれます。つまり骨の再生と修復に役立ち、骨密度を上げるのに必要不可欠な栄養素になります。
一方でビタミンDは食べ物からはあまり摂取できないため、日光浴によってビタミンDをつくる必要があります。ビタミンDは、主に皮膚に紫外線が照射されることによって合成される特徴を持つ成分です。ビタミンDを体に取り込むという点では日本人の平均的な肌タイプの場合、国立環境研究所の推奨では 10分程度の日光浴で十分とされています。ある研究によると紫外線を浴びて皮膚がメージを受け始めるまでの時間は、ビタミンDの1日に必要な分が作られるまでの時間の4倍から6倍ぐらいと言うことが分かっています。そのため10分程度、顔以外の箇所に当てると良いでしょう。
むくみとたるみ
むくみは肌を構成する筋肉やコラーゲン、それに脂肪などの組織の機能低下を招き、組織の結びつきを緩めてたるみを助長させる大きな原因の1つになります。またストレスは、むくみの原因になり、ストレスを感じると人の体内には ストレスホルモンが分泌され、そのストレスホルモンは炎症反応を引き起こします。この炎症が続くと体の中に体液が溜まりやすくなり、そうなると血管が広がってしまい周りの組織に体液が漏れ出すことになり、それがむくみになります。
一方で、実はストレスは自律神経を乱してしまいます。つまりストレスが自律神経を乱し、自立神経が乱れると体内の水分調整や循環がうまくいかず、むくみやすくなり、その結果たるみに繋がってしまいます。
東洋医学で診る「たるみやほうれい線」
たるみやほうれい線に対して顔のリンパマッサージや筋膜リリースをしても なかなか効果が出ないと感じることはありませんか。それは顔の表情筋やリンパの流れだけではなく、体の内側からのケアが必要だからです。
たるみやほうれい線の原因の 1つにこめかみや顎の周りの凝りや老廃物の蓄積、首肩こりがあります。これらは血液や気(エネルギー)の流れを防ぎ、顔の表情筋にも影響を与えます。またこれらは東洋医学でいう「寒飲停留証」の症状です。
寒飲停留証とは、冷たい飲食物や冷気などによって胃腸の働きが低下し、水分や食べ物が消化されずに停滞する状態のことです。多くは肺や脾が冷えることによって水湿が停滞するためです。寒飲停留証があると顔にも水分や老廃物が溜まりやすくなり、たるみやほうれい線ができやすくなります。
さらに寒飲停留証は、全身の気血の巡りを悪くし、冷えやむくみ、疲労感、消化不良、便秘などの不調を引き起こします。このように寒飲停留証は顔の老化だけでなく健康にも大きな影響を与えます。具体的に寒飲停留証になる生活スタイルは次のようなものが挙げられます。
- 冷たい飲み物やアイスクリームなどを好んで食べる
- 冷房や扇風機などで体を冷やす食事の量が多いか少ないか不規則である
- 運動不足や睡眠不足であるストレスが多く、気持ちが落ち込みやすい
寒飲停留証を改善するには、まずは生活習慣の見直しと体を温めることが大切です。また寒飲停留証に有効なツボを刺激することもおすすめです。寒飲停留証に効くツボは次の3つです。
三陰交:下半身の冷えやむくみ、生理不順などに効果

足三里:胃腸の働きを整え、冷えや疲労感を改善

腎兪は:腎の働きを補い、冷えやむくみ不眠などに効果

また、美容鍼もおすすめです。寒飲停留証を改善することでたるみ、ほうれい線の解消につながります。寒飲停留証を改善した後は顔のケアを行って顔のリンパの流れをよくしましょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。