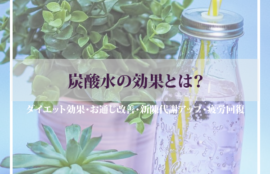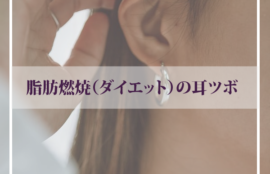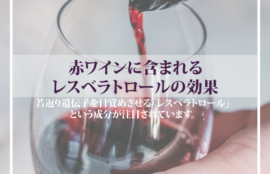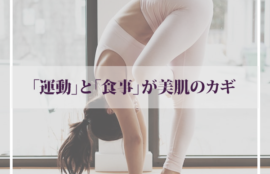食べる薬とも言われる「ごま」は栄養素が高く、タンパク質、ビタミン、ミネラル、セサミンなどの抗酸化物質、食物繊維、脂質など、健康で生きるための必要な栄養素が凝縮されています。さらに炎症を軽減し、血糖値のコントロールも担うなど様々な効果をもたらしてくれます。
これらの効果は、「ゴマリグナン」と呼ばれる健康成分が含まれているからです。このゴマリグナンには、高い抗酸化力があり、細胞の炎症を抑えて肝臓を保護する、抗がん作用などの働きがあります。またスプーン2杯のごまには、牛乳1本分、豆腐1/3丁分のタンパク質が含まれ、さらにほうれん草100g分の鉄分、生わかめ70g分の食物繊維が含まれています。
「ごま」の栄養価の高さ
「ごま」には科学的に証明された様々な健康上の利点があり、小さな一粒に凝縮された食物繊維を摂取することで腸が整い死亡率が下がることが知られています。大さじ3杯約30gには3.5g程度の食物繊維が含まれており、これは1日に摂取すべき食物繊維量の12%に相当します。簡単に食べ物にふりかけるだけで補えることができるため、お手軽に始めることができます。
また、「ごま」には抗酸化物質も多く含まれており、その中で有名なのが「セサミン」です。活性酸素などによって体の細胞や遺伝子が酸化し、ダメージを受けて、体が錆びついていくことで老化が始まりますが、「セサミン」などの抗酸化物質を摂取することで、活性酸素などによる酸化やダメージを防ぐことができます。
ある研究では、セサミンが体の炎症を抑えてくれる可能性も示唆しています。セサミンは、体内に吸収されると肝臓の代謝を活性化させ、高い抗酸化作用を持つようになることが知られています。またごまの抗酸化物質には、セサミンの他、セサモリン、セサミノールといった成分が含まれています。これらの成分を総称してゴマリグナンと呼んでいます。ゴマリグナンは肝臓まで届いて、抗酸化作用を発揮する数少ない抗酸化物質です。
ゴマリグナンは、老化防止や肝機能の向上、がん予防にも効果があると言われ、また血中の悪玉コレストロールの低下が期待できるオレイン酸、カルシウム、マグネシウム、ビタミンEなどが含まれています。
このような数々の栄養素が凝縮して小さな粒に入っていますが、それらの栄養素は硬い種皮の中に詰まっており、ゴマの栄養素の恩恵を受け取るためには種皮を破壊して吸収率を上げなければいけません。なのでゴマを食べるときは、是非すり潰して使用しましょう。
ちなみにゴマを擦らずに食べれば食物繊維のような効果が得られます。またゴマは加熱するとセサモールやセサモール二量体という、セサミンと同じように抗酸化作用を持つ成分に変わります。
さらに、「ごま」は約20%がタンパク質であり、50%が脂質です。脂質は体に良いとされている不飽和脂肪酸(リノール酸、オレイン酸)が多く含まれており、コレステロールが含まれていない特徴があります。いくつかの研究では「ごま」を定期的に食べることによって、心臓病の危険因子である高コレステロールとトリグリセリドを減らすのに役立つ可能性が指摘されています。
その他にも、「ごま」の特徴である炭水化物が少なく、高品質なタンパク質、健康的な脂肪が多いなどにより、血糖値コントロールに役立つ可能性があります。糖質は、タンパク質や脂質と一緒に食べると血糖値の上昇が緩やかになるため、例えば白ごはんに「ごま」をふりかけて食べるだけで血糖値の上昇が緩やかになります。
このように、私たちが健康的に生きる上で絶対に必要な栄養素が非常に多く含まれており、様々な健康効果をもたらしてくれます。
今すぐケアしたい酸化と糖化
酸化と糖化に対抗するためにオススメしたい食材こそがごまです。ごまには、セサミンをはじめとする抗酸化物質が含まれ、抗酸化物質とは、その名の通り酸化を抑える力を持った物質のことです。酸化を引き起こす物質は、酸素が体内で様々な分子と結びつき、高い酸化力を持つ酸素に変わった活性酸素、そしてフリーラジカルと言うついになっていない電子を持つ不安定な分子があります。この活性酸素もフリーラジカルも、日常生活を送る中で自然に作られてしまいます。
もちろん体にもそれらを除去する能力は備わっていますが、加齢とともに衰えてしまいます。それを補助してくれるのが抗酸化物質です。抗酸化物質は、活性酸素やフリーラジカルの酸化力を抑える、活性酸素やフリーラジカルの発生自体抑える、酸化によって受けた細胞の損傷を修復するといった働きがあります。
さらに抗酸化物質は糖化を抑える効果があります。なぜなら糖化によってエイジス(AGEs)が作られる過程には酸化が変わっているからです。結びついた糖とタンパク質は、まずアマドリ化合物という物質になります。いわばエイジスの一歩手前の物質です。
このアマドリ化合物が活性酸素やフリーラジカルによる酸化、さらに脱水といった化学反応を経ると初めてエイジスに変わります。つまり酸化が起きなければエイジスはできません。そのため糖化を抑えるためにも抗酸化物質を摂ることが非常に大切です。つまりごまは、高い抗酸化力を持つが故に酸化も糖化も抑えることができます。
セサミンの持つ肝保護効果
肝臓はたくさんの仕事をしている臓器で、主な働きは3つあります。一つ目は、食べ物から摂り込んだ栄養を使いやすく加工する「代謝」機能。二つ目は、体内に入ってきた細菌や食品添加物などを分解する「解毒」機能。三つ目は、脂肪の消化吸収を助ける「胆汁の生成」機能などの作用があり、休みなく働いています。
しかし、年齢とともに肝臓は疲れて痛み機能が落ちます。特に解毒を行う時に大量の活性酸素を生み出すため、肝臓は酸化ストレスに晒されやすくなります。こうした負担を抑えるのがセサミンの肝保護効果です。抗酸化物質のほとんどは体に入ってすぐに活性酸素と戦い、小腸で吸収されますが、セサミンは肝臓まで運ばれてから抗酸化物質に変身します。そして肝臓の活性酸素を取り除いたり、アルコールを分解するのを助けたりと肝臓の負担を和らげてくれます。
ごまは朝活にも効果的
ごまには、食物繊維が豊富に含まおり、特にセサミンが腸の善玉菌を増やすことも研究で明らかになっています。セサミンを摂取したマウスの腸内フローラを遺伝子レベルで調べたところ、善玉菌が増えていたという結果が得られています。善玉菌がしっかり働き、腸が健康になることは感染症対策はもちろん、心の健康にも関わっています。
ストレスを感じるとお腹が痛くなったりするように腸と脳はつながっており、これは脳腸相関と呼ばれる関係があります。ホルモンの分泌などによって腸には脳に働きかける効果があることが科学的に分かっています。
血管の健康を保ち、中性脂肪や血圧を下げる
ごまは、血管の健康に役立つ成分も豊富に含まれています。とま一粒の約半分を占める油脂は不飽和脂肪酸で、動脈硬化を引き起こす悪玉コレステロールや中性脂肪を下げてくれる良い油です。
研究では、ごまを2ヶ月取り続けて、悪玉コレステロールが約10% 、中性脂肪が約8%下がったというデータもあります。また、ごまに含まれているマグネシウムには、血圧を下げてくれる降圧作用もあります。さらにゴマリグナンやビタミンEには、降圧作用の他に血管保護作用もあり、しなやかで若々しい血管を保つのにも効果的です。若々しい血管を保つことで全身に栄養が行き渡り、全身の細胞も若々しくなります。
骨が丈夫になる
ごまには、骨と関節を保護、強化する作用のあるミネラルも豊富に含まれています。実はごまのカルシウムは牛乳の約10倍もあります。カルシウムは骨の主成分として有名なミネラルであり、骨量や骨密度は骨の中のカルシウム濃度で決まります。このカルシウムの吸収を助けたり、必要なところまで行き渡らせたりするのはマグネシウムの役割です。そのため骨を丈夫にするにはカルシウムのほかにも、このマグネシウムも十分に摂る必要があります。このカルシウムとマグネシウムが豊富なごまは、まさに最強の骨強化食材です。
貧血の悩みも解消
女性に多い貧血の悩みも、ごまの造血効果で解消できます。貧血は女性にとってはポピュラーな病気で、中でも鉄欠乏性貧血は女性全体の4割とも言われています。貧血からくる疲れやイライラの解消にも、造血に役立つミネラル豊富なごまがおすすめです。
造血ミネラルとして、まず挙げることができるのは鉄です。鉄は血管細胞の一つである赤血球を作る役目をしています。そしてこの鉄から赤血球を作るのを助けるのが銅です。つまり貧血を防ぐためには鉄と銅、この2つをしっかりと摂取する必要があります。その点においてごまの中には、鉄も銅も含まれており、貧血対策にオススメです。ごま30gで、亜鉛は1日の必要量の1/4、銅は1日の必要量に十分な量を摂ることができます。
血糖値の急上昇を抑える
ごまに含まれている豊富なタンパク質と食物繊維には、血糖値を抑えてくれる効果もあります。タンパク質も食物繊維も消化に時間がかかるため、穏やかに吸収され、血糖値は緩やかに上昇します。
ごまで補える栄養素
タンパク質を補う
タンパク質の補給にもごまはおすすめの食材です。年齢とともに骨の衰えや筋肉量の低下、髪や肌のカサつき、またタンパク質は免疫の抗体の材料でもあるのでウイルスや細菌から体を守るのに不可欠です。植物性タンパク質といえば大豆ですが、ごまは豆腐の約3倍に当たる100gあたり20gものタンパク質を含んでいます。胃に負担なく摂れるごまは、タンパク質摂取にオススメの食材です。
亜鉛を補う
亜鉛は微量ミネラルと言い、1日の摂取量は僅かですが体にとって大切な働きをしています。ごまは100g当たり5.9mgの亜鉛を含み、肉類の中では比較的亜鉛の多い牛肩ロースの1.3倍もあります。
細菌やウイルスから体を守る免疫機能は亜鉛のサポートによって活性化しますが、亜鉛が不足すると免疫機能が十分に働かず、風邪などの感染症にかかりやすくなってしまいます。また皮膚細胞の新陳代謝や髪の主成分であるケラチンの合成を促すのも亜鉛の働きです。
これまで亜鉛は普通に食事を摂っていれば必要量を摂取できると言われていましたが、最近は化学肥料によって土壌の質が変化したため、土の中の亜鉛が不足し、普通に食事を摂っているだけでは亜鉛が摂れなくなってきています。またお酒をよく飲む方もアルコールの分解には亜鉛が使われ、その分亜鉛が不足しがちになります。
ビタミンB群を補う
ごまには、ビタミンB群がたっぷり入っており、まさに天然の若返りサプリと言えます。このビタミンB群のうち、ビタミンB1(チアミン)、ビタミンB3、ビタミンB6、ビオチンがごまには含まれています。
ビタミンB1(チアミン)は、糖質を燃やしてエネルギーに変える他、皮膚や粘膜を健やかに保つ作用があるビタミンです。ビタミンB3は糖質の他、脂質やタンパク質を燃やしてエネルギーに変えたり、皮膚や粘膜の新陳代謝を促したりする効果があります。不足すると消化不良や皮膚トラブルが起こる他、認知症リスクも高まると言われています。
ビタミンB6は、タンパク質からエネルギーを生み出す他、筋肉を作るのにも使われます。ビオチンは健やかな肌に必要な栄養素で、健康な髪と頭皮の維持にも役立ちます。
飲む薬「コーヒー」
コーヒーは健康に悪いというのは過去の話で、1日3杯ぐらいのコーヒーを飲む習慣は健康に良いということが常識になりつつあります。そのきっかけとなったのが、2012年の米医学誌に発表された内容で、コーヒーを1日6杯以上飲む人は男性で10%、女性で15%総死亡リスクが低下し、心臓病、呼吸系疾患、脳卒中、感染症、糖尿病などによる死亡リスクの低下が認められています(2017年に全データ解析でも同様以上の結果が確認)。
このように飲むだけで死亡リスクが減少するというデータがあるものは、サプリだけではなく、薬においてもほとんどありません。また40万人以上の大規模調査でもコーヒーは寿命を伸ばすことが確認されています。さらに2015年に行われた日本人を対象にして行われた9万人以上の住民に対する18.7年の長期間の健康調査(経過観察)において、コーヒーを飲む人と飲まない人を比較すると、コーヒーを2杯/日で15%、3〜4杯/日の人は24%総死亡リスクが低下したという結果となりました。
また、コーヒーは老化の2大原因である脳卒中と認知症のリスクを下げてくれることが分かっています(2009年、2011年発表論文)。コーヒーは脳内の抑制神経伝達物質の働きを弱め、気分を高揚させ、脳の機能を刺激すると考えられているからです。さらに2011年に行われた研究では、1日4杯以上のコーヒーを飲む女性(5万人、25年間追跡)は、うつ病のリスクが20%低い結果が発表されています。
このようにコーヒーは数多くの予防効果が研究されており、その中で最も多く研究されているのが肝臓病に対する研究です。これらからコーヒーはほとんど全ての原因による肝機能障害を改善させることがこれまでの膨大なデータから確認されています。そしてコーヒーには糖尿病を予防してくれる効果(クロロゲン酸の糖尿病予防効果)があるというのが110万人以上のデータで証明されています(2010年糖尿病専門誌)。
コーヒー含まれるカフェインは体の中にあるリパーゼという酵素を活性化させる作用があります。リパーゼによって脂肪(トリグリセライド)が遊離脂肪酸とグリセロールに分解され血液中に流れて筋肉で燃焼されます。また血行促進、代謝の向上などのダイエット効果があります。同じくクロロゲン酸(コーヒーポリフェノール)も脂肪の分解や蓄積を防ぐ効果があります。
また美容面では、抗酸化作用により酸化を防ぐ効果があるためシミやシワ、たるみなどのアンチエンジング効果もあります。
カフェイン中毒(カフェインオーバードーズ)
カフェインは眠気を吹っ飛ばして脳をクリアな状態に変えて、エネルギーを高め、集中力を 高め、生産性を高め、私たちが長時間何かに没頭することを可能にします。そのためいとも簡単に多くの人がカフェインに依存してしまいます。カフェインはアルカロイドの一種であり、かなり強力な精神刺激性のドラッグであると言われています。
実は、カフェインに対する強さや弱さには個人差が大きく存在しています。遺伝的に高カフェイン感受性の人はカフェインに弱く、最も敏感な人で1日100mg以下のカフェイン(コーヒー1杯から1.5杯分)でさえも不眠や焦り、心拍数の上昇などが起きます。中カフェイン感受性の人は1日200 から400mgまでのカフェイン(コーヒー2から3杯分)なら副作用が起きない方です。大多数の人はここに含まれるため、多くのガイドラインでは1日のカフェイン量が300mgから400mgあたりに設定されています。そして低カフェイン感受性の人は非常にカフェインに強く、1日に500mg 以上のカフェイン(コーヒー5杯以上)を飲んだとしても何も起きない、寝る前にコーヒーを飲んでもぐっすり眠れるレベルで、全人口の約10%がここに入るとされています。
そして大きな問題となるのがカフェインの過剰摂取です。これはカフェインオーバードーズと言われています。基本的にカフェインは1日あたり約300から400mg程度までなら 摂取して良いとされています。これは1日あたり約4杯程度のコーヒーに相当します。この量を超えて摂取するとカフェインの過剰摂取が発生する可能性があります。
コーヒーを飲み過ぎた場合の副作用
どんなに体に良いものであっても、食べ過ぎ、飲み過ぎは体に良くありません。何でも適度にバランス良くが基本です。アメリカ医師会では2、3杯を標準として、10杯は飲み過ぎとしています。また心臓の健康に関する35万人以上の参加者のデータを調べた研究では、1日4杯までは効果があるとされています。このあたりが参考になると思いますが、カフェインに強い人、弱い人もいるため、自分の体がどの程度カフェインに強いのかに応じてカーヒーを飲む量を決めてください(例えば夜眠れなくなるなど)。
- 腎臓に負担がかかる
- 胃が荒れる
- 不安やストレスが増す
- カフェインで睡眠不足
- カフェインで疲れやすくなる
腎臓に負担がかかる
「コーヒーの消費と慢性腎臓病の発症に関連する代謝物」という論文では、コーヒーの飲み過ぎは、腎臓への負担が大きく、慢性腎臓病を発症するリスクが高い可能性があることが指摘されています。その根拠は、約3800人を調べたところ、コーヒーの摂取に関連する41の物質が見つかり、そのうち3つの物質が多いほど慢性腎臓病を発症するリスクが大幅に高くなることが分かっています。またカフェインの利尿作用が腎臓に良くないのではないかとの指摘もあります。また腎機能が低下している方は、コーヒーに含まれるカリウムをうまく排出ことができないため、負担が大きいと言われています。
胃が荒れる
コーヒーで「胃が荒れる」というのは、コーヒーに胃を荒らす成分が入っているからです。その成分はカフェインと苦味成分のクロロゲン酸です。この2つには胃の粘膜を刺激して胃酸の分泌を増やす性質があるため、胃の粘膜が傷ついてもおかしくないと考えられています。また下痢を招く作用もあるため、欧州食品安全機関はカフェインの摂取量を1日400mg未満(コーヒー4から5杯)と提言しています。カフェインが体に与える影響は個人差が大きいため、無理して飲む必要はありません。
不安やストレスが増す
カフェインを摂取すると頭が冴えるというのは、それは疲れを感じさせる脳内化学物質のアデノシンの働きをカフェインがブロックするからです。同時にアドレナリンも分泌されるためエネルギーが高まります。一方でカフェインを摂り過ぎるとカフェイン誘発性不安障害、つまり不安を引き起こされることがあります。例えばカフェインを摂ると、めまい、下痢、不眠症、頭痛、心拍数の増加、イライラする、ストレスかかる、メンタルが落ち込むなどの症状がある場合は、自分にカフェインの適量がどの程度なのか見極めていく必要があります。
カフェインで睡眠不足
カフェインの過剰摂取によって夜眠れない方は、正午19時以降はコーヒーを飲まない方が良いかもしれません。カフェインというのは私たちが想像している以上に、体の中に長く居座り、カフェインが体内に残っていると睡眠の邪魔をします。
例えばアメリカ睡眠医学会によるとカフェインの半減期は約5時間です。半減期とは、薬成分の血中濃度が半減するまでの時間のことを指しています。つまり午後7時に食後に100mgのカフェインを含むコーヒーを一杯飲んだ場合、5時間後の寝ようかという深夜12時にも、体内に50mgのカフェインが残っていることになります。
カフェインの半減期が約5時間ならば深夜12時に寝る人ならば、その10時間前すなわち 午後2時に100mgのカフェインを含むコーヒーを1杯飲んだ場合は、深夜12時にはまだ100mgの半分の半分、すなわち25mgのカフェインが体内に残っているということになります。そのカフェインの影響と戦いながら眠らなくてはいけないということになります。
またジャーナルオブスリープメディスンの研究によると、就寝前6時間以内にコーヒーを飲むと、睡眠時間が1時間短縮されるという指摘もあります。体内にカフェインが就寝時に残っていると、身体の回復、記憶の強化、徐波睡眠とレム睡眠の量などに影響があります。結果的に睡眠の質、睡眠時間が足りないなど様々な悪影響が出てしまいます。
カフェインで疲れやすくなる
また日常的にカフェインを摂取し続けると疲れやすくなってしまうという大きなデメリットも発生します。実際にカフェイン入りのエナジードリンクを飲んだ人たちを対象に行われた研究によると、エナジー ドリンクは数時間にわたって脳の覚醒度を高め気分を上げてくれるものの、参加者は翌日いつもよりも疲れていることが多かったことが分かっています。
この理由には、アデノシンという物質が関わっています。この物質は、眠りたいという欲求を高める睡眠物質であり、私たちに疲労感を覚えさせる疲労物質であるとも言われています。このアデノシンは起きている間、脳の中で着々と増え続けており、そのアデノシンの量が多ければ多いほど私たちは疲労を感じ、眠たくなります。そしてアデノシンは脳に寝なさいと命令する睡眠信号を出しています。
ここでカフェインを使えばアデノシンから出る疲労信号、睡眠信号を消して眠気を覚ますことができます。アデノシンは受容体と呼ばれる 脳の疲労センサーにくっつくことによって疲労信号、睡眠信号を出すことができます。つまりカフェインを取ればそのたびに疲労物質アデノシンをブロックして、疲労感が和らいだり、集中力が高まります。しかし薬でも何でも飲みすぎると耐性がつくようにカフェインを摂り過ぎるとだんだん耐性がついてきます。
体の外からカフェインを注入して、カフェインがアデノシンの働きをブロックするため、脳は疲労センサーを増やしてしまいます。そして疲労センサーが増えるためアデノシンがたくさんの疲労センサーに結合するようになります。その結果以前よりもアデノシンの働きが強くなり、より強く疲労を感じるようになります。
ただし、カフェインをだいたい1週間から2週間程度やめることができれば数が減ることが分かっています。その結果、疲れやすかった状態から普通の疲れにくい状態へと戻ることができます。そのため疲労感の強い人はカフェイン断食をして、疲労センサーを一旦リセットすることもお勧めです。
カフェインによる依存性
コーヒーに依存症があり、その依存症の原因がカフェインです。コーヒーを飲むと脳の奥深くにある辺縁系に存在する報酬系という部分からドーパミンと呼ばれる快楽物質が放出されます。もちろん覚醒剤やモルヒネ、コカインを摂取した時に放出されるドーパミンの量と比べれば、カフェインを摂取した時のドーパミン量は少なく、コーヒーの依存性は薬物より深刻なものではありません。ですが体はコーヒーを飲み続けることで、カフェインの耐性が生まれてしまいます。
最初はコーヒーを2杯飲むだけで目が覚めて、十分な覚醒効果が得られていたはずが、同じ覚醒効果を得るために1日に3杯4杯、1日に5杯6杯とより多くのカフェインの摂取量が必要となってきます。そしてカフェインの耐性ができた人がコーヒーを急に飲まなくなると頭痛や疲労感、不安、イライラ、震えなどの不快な症状が現れるようになります。いわゆる禁断症状というもので、禁断症状を避けるためにはコーヒーを飲み続けなければなりません。
また、カフェインを過剰摂取するとアドレナリンが大量に 放出されて心拍数が上がり不整脈が起こることもあります。薬物より依存性は低いと言え、やはり カフェインの過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性があります。
カフェインの子供への影響
最近の研究では子供の発育における徐波睡眠と成長ホルモンの役割が明らかとなっています。除波睡眠とは、睡眠直後の最初の90分に現れる深い眠りのことで、この時に成長ホルモンが大量に放出されることが分かっています。つまり深い眠りが子供の成長には欠かせません。しかしカフェインを摂取すると脳が覚醒して不眠になったり、不安やイライラから眠りが浅くなる可能性もあります。特に夕方以降にカフェインを摂取すると睡眠の質と量が低下して、成長ホルモンの分泌が不足してしまうことが考えられます。
カフェインの胎児に影響
できれば妊娠中はできるだけカフェインを摂取しない方がいいでしょう。公式的な見解としては、妊婦の摂取するカフェインの胎児への影響は科学的には分からないとされています。
コーヒーを1日何杯飲むのか、カフェインを含む飲み物をどれだけ摂取するかによって胎児への影響は変わり、もちろん体質によっても影響に違いがあります。悪影響を及ぼす決定的な証拠がないとしても、逆に悪影響を及ぼさないと 断定できる証拠もありません。できるだけリスクを減らすのが正しい判断と思います。
カフェインは胎盤を自由に通過するため、妊婦がコーヒーを飲めばカフェインは胎盤を通って胎児の脳と体を直撃します。通常カフェインを分解するのは肝臓の役割ですが、胎児はまだ肝臓が十分に発達していないため、高濃度のカフェインにさらされることになります。結果として流産、早産、発達障害などの問題も指摘されています。
また妊婦がカフェインを摂取することで不眠や不安といった症状を患うと、ストレスホルモンと言われているコルチゾールが分泌されます。コルチゾールも胎盤を通過して胎児の脳に悪影響を及ぼす可能性があります。
アメリカの研究チームがサンフランシスコで妊娠中の女性1063人を調査したところ、カフェインが含まれる飲料を1日2杯以上飲んだ妊婦は、全く飲まなかった妊婦に比べて流産が2倍に増えたと報告しています。コーヒーを飲んでも流産のリスクは上昇しないと主張する論文もあるため明確に断言することはできませんが、リスクを示す研究がある以上、安全を優先した方が良いでしょう。
また授乳期のカフェインの摂取も要注意です。カフェインは母乳にも含まれてしまうため授乳期の母親がカフェインを摂取すれば、赤ちゃんもカフェインを摂取してしまいます。新生児もまだ肝臓の働きが十分ではないため、基本的に妊娠中から授乳期にかけてカフェイン摂取はできるだけ控えるという判断が望ましいと言えます。
コーヒーで老化する
朝食の後には1杯のコーヒーを必ず飲んだり、仕事のお昼休憩が終わる時に目覚めの1杯としてコーヒーを必ず飲むという習慣がある人はかなり多いと思います。実際にカフェインには、脳の神経を刺激し、集中力を高めてくれたり、やる気を起こす作用があります。またカフェインには血管を広げて血行を促進する作用もあるため、脳に流れ込む血液の量が増え、脳の働きが良くなる効果も期待できます。
ただし注意しなければならないことが飲み過ぎです。言い換えるとコーヒーを飲みすぎることによるカフェインの過剰摂取になります。眠気を飛ばすために毎日コーヒーが欠かせ ないという人、そんな人はおそらくカフェイン中毒に陥っており、カフェインを過摂取による老化が加速しています。
ただしコーヒーは、健康に良い飲み物であり、コーヒーに限った話ではなく、全ての健康に 良い食べ物や飲み物にも言え、健康に良いからと言って過剰に飲み過ぎ、食べ過ぎはいけません。あくまでも適度な量を長期間に渡って摂取し続けることが重要だということを絶対に意識して欲しいです。例えばコーヒーを1日3倍程度と適度な量摂取している分には老化が予防し、様々な病気や死亡リスクが下がったりと健康に良い影響をもたらしてくれます。
例えば2014年にドイツとフランスの研究者が合同で実施した実験では、カフェインがアルツハイマー型認知症を予防する効果を明らかにしています。またカフェインの利尿作用は、体内の老廃物の排泄を促進し、毒素を体外に出すといった効果も期待できます。さらにカフェインが含まれているコーヒーや緑茶は、抗酸化作用が強いポリフェノールなどの栄養素も含まれているため、老化予防、癌予防、認知症予防など様々な健康効果を期待できます。
ただし、カフェインは諸派の剣でもあって、適度な量を摂取している分には何の問題もなく、むしろ脳の働きが良くなったりしますが、カフェインを過剰に摂取すると老化が加速することが分かっています。またカフェインは、コーヒーだけに含まれているわけではなく、意外にも たくさんの食べ物や飲み物に多く含まれている物質です。
例えば、カフェインを多く摂取してしまうことのデメリットの1つとして明らかになって いるのが骨粗しょう症が促進してしまうリスクです。2021年に、イギリスの専門メディアに掲載された研究によると、カフェイン入りのガムを6 時間噛み続けたグループは、ノンカフェインのガムを噛んでいたグループと比較して尿に含まれるカルシウムの量がなんと77%も増えてしまったという結果が出ています。丈夫な骨を作るのに必要不可欠なカルシウムが、カフェインを継続的に飲み続けることで体の外に漏れ出てしまう結果としてカルシウム不足が引き起こされ、骨がスカスカになってしまうのです。
また2021年オーストラリアで実施された研究では、6 時間で800mgのカフェインを摂取すると尿に含まれるカルシウムの量がほぼ2倍になることも明らかになっています。カフェイン800mgは大体コーヒー7から8杯分に相当します。ただし1日のカフェインの摂取量が400mgを超えてくると骨粗しょう症のリスクが高まってくる可能性も指摘されています。カフェイン400mgは、大体コーヒー3から4杯分ぐらいに相当します。
またカフェインに依存すると骨粗しょう症のリスクに加えて肌がボロボロになって老ける可能性も指摘されています。2014年のポーランドの研究論文で、カフェインを摂取することでコラーゲンの生成が阻害されたことが明らかになっています。コラーゲンは、肌の弾力や水々しく保つためには必要不可欠な成分ですが、その大切なコラーゲンがカフェインの過剰摂取によって作られにくくなってしまうため、肌がたるんでシワになり見た目が老けることになります。
さらにカフェインがもたらす老化現象は他にもあります。アメリカの専門雑誌に掲載された論文では、カフェインを過摂取することで、ビタミンB群や鉄分、マグネシウムなどの 様々な栄養素の吸収が妨げられる可能性も指摘されています。特にカフェインは、ビタミンB6の吸収を阻害してしまう恐れがあります。ビタミンB6は免疫機能を正常な状態に維持したり、皮膚や粘膜のターンオーバーの促進や血球の形成をサポートする役割などがあります。ビタミンB6が不足することで免疫力が落ちてしまい、風邪や感染症にかかりやすくなってしまう他、肌のターンオーバーが遅れて、肌が荒れてしまう可能性もあります。また赤血球が不足すれば貧血状態になり、全身が栄養不足に陥り、疲れやすい体になってしまいます。
このようにカフェインを過剰に摂取すると栄養バランスが整った食事をしていても、うまく栄養素を摂り込めずに不健康な体になって老化が進んでしまう恐れがあります。こちらの研究では、カフェインの摂取量が約300mgを超えてくると栄養素の吸収が阻害されるリスクがあると指摘されています。カフェイン300mgは、大体コーヒー3杯分ぐらいに相当します。
そしてカフェインの過剰摂取は、メラトニンの合成を阻害してしまうことから良質な睡眠が取れなくなってしまうリスクもあります。夜にしっかり眠れなくなると睡眠中に成長ホルモンが分泌されなくなってしまいます。成長ホルモンはダメージを負った細胞を修復したり、炎症を沈めてくれる効果があります。ただしカフェインが体に悪いからといって必要以上にコーヒーや緑茶を避ける必要は全くありません。あくまでもコーヒーや緑茶をあまりにも飲みすぎた場合、過剰摂取してしまったカフェインが悪さをしてしまう危険性が指摘されているだけです。具体的にはコーヒーは 1日に3から4倍程度に抑えたり、緑茶を夕方以降は飲まないようにするなどして、カフェインの健康効果が得られるような飲み方を意識しましょう。
コーヒーの効果をアップする
コラーゲンパウダー
コラーゲンは体内の主要なタンパク質の一つであり、皮膚、骨関節、筋肉などに存在しています。加齢とともに自然にコラーゲンの生成は減少し、皮膚のシワやたるみと皮膚の老化、関節痛を引き起こすとされています。
コラーゲンパウダーに関しては、いくつかの研究によってコラーゲンパウダーを摂取することで皮膚が健康的になり、皮膚の弾力性が改善され、シワが減少することが示されています。
例えば、2014年の研究では8週間に渡り、コラーゲンパウダーを摂取した女性の皮膚の弾力性が優位に改善したと報告されています。また別の研究ではコラーゲンサプリメントを摂取することで肌の弾力性、保湿性、コラーゲン密度が高まることも指摘されています。このような研究を参考にすれば、コラーゲンパウダーを補給することでシワやといった老化現象を軽減できる可能性があると言えます。
また、皮膚の健康だけでなくコラーゲンパウダーを補給することによって、関節痛が和らぐ可能性があります。関節を包む軟骨は、コラーゲン繊維でできています。加齢によって肌のコラーゲンが減少するのと同様に全身の軟骨にも構造変化が起こります。その結果、関節に炎症が起こる関節炎によって関節が痛んでしまうことがあります。また年を取ることによって膝の関節や股関節の関節に問題が生じ痛みを感じてしまう人がたくさんいます。歩くことが困難になってしまったり、転倒しやすくなり骨折してしまい、そのまま車いす状態になる可能性もあります。
このコラーゲンサプリメントを摂取することで関節炎による関節痛の症状が 改善されることがいくつかの研究で示されています。例えば2008年の研究では 24 週間にわたってコラーゲン製品を摂取した患者は、プラセボ群に比べて関節痛が大幅に減少したと報告されています。
さらに、コラーゲンパウダーは加齢による骨量の減少を防ぐ可能性もあります。骨もコラーゲンタンパク質の繊維でできており、加齢とともにコラーゲンの生成量が減少すると骨量が徐々に減少し、骨粗鬆症などの骨の病気になる可能性があります。いくつかの研究はコラーゲンサプリメントが骨密度の低下を予防してくれる可能性を示しています。例えば1年間に渡りコラーゲンサプリメントを摂取した女性の骨密度が優位に改善したことが報告されています。
プロテイン
海外などではコーヒーに プロテインを入れるというのは結構人気の飲み方になってきています。プロテインコーヒーを摂取することのメリットは、1日に必要とされるタンパク質を補うことができるという点です。多くの人のタンパク質不足が深刻な問題となっており、筋肉をはじめ血管や内臓、皮膚、髪、爪など体の大部分はタンパク質で構成されています。その総重量は体重の30%から40%にも上ります。特に筋肉においては水分以外の約80%がタンパク質によって作られています。
タンパク質が不足すると、分かりやすいのは皮膚や髪、爪への影響です。例えば髪の主成分であるケラチンはタンパク質から作られます。タンパク質が不足してしまうと髪の成長が遅くなり、薄く、弱く、乾燥しやすくなる可能性があります。
また、皮膚もタンパク質に大きく依存しています。特にコラーゲンとエラスチンという2つの重要なタンパク質は皮膚の弾力性と強度を保つ役割を果たしています。タンパク質が不足すると皮膚の乾燥、シワ、弾力性が失われるといったことが起こる可能性があります。また爪は、主にケラチンというタンパク質から作られています。タンパク質が不足すると爪がもろくなったり、成長が遅くなったりする可能性があります。
一方で問題となっているのはタンパク質不足による筋肉の減少です。タンパク質は、筋肉の主成分であり、体内で新たな筋肉組織を作るためにも必要です。また日々の活動で自然に破壊される筋肉組織の修復にもタンパク質が使用されます。タンパク質が不足すると体は筋肉組織を維持するのに十分なタンパク質を提供できなくなってしまいます。これによって筋肉の量が減少し、筋力が低下します。
さらに、タンパク質が不足すると慢性疲労に陥ってしまったり、タンパク質は免疫系の重要な要素のため、タンパク質が不足してしまう、免疫力が低下してしまう恐れもあります。
そのためコーヒーにプロテインを入れて飲むという習慣を身につけることによってタンパク質不足を補ってあげましょう。もちろんタンパク質は肉や魚、たまごといった自然な食品から摂った方が良いのがベストですが、タンパク質が不足してしまうぐらいであればプロテインを活用してでもタンパク質を補った方が良いと考えられます。
このプロテインコーヒーを摂取することのメリットは、タンパク質を補えることだけではなく、効率的に体重を落とすことができると示唆されています。タンパク質は空腹感を抑えて満腹感を促進してくれるため、コーヒーに加えることによって満腹感が長く続き、その日に食べる全体量を減らせる可能性が高まります。また適度なタンパク質をしっかりと摂取することによって体脂肪を減らしつつ筋肉量を維持することができることも分かっています。
また、コーヒーに含まれているカフェインには、それ自体にも体重を減らす効果が認められています。例えば代謝社を高め空腹ホルモンのレベルを下げて、満腹ホルモンのレベルを上げることを示唆する研究が報告されています。
オリゴ糖
オリゴ糖のメリットとしてまず挙げられるのは、腸内環境を整えてくれるという効果です。オリゴ糖は糖類の一種ですが難消化性のため胃で消化されず、大腸までしっかりと直接届き、ビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌の餌となってくれ、腸内環境が整います。腸内でしっかりと善玉菌が増えてくれると、お肌がツヤや免疫力がアップしたりと様々なメリットがもたらされます。
またオリゴ糖は砂糖よりカロリーが低く、難消化性で血糖値を上げにくいため、 痩せたいと思っている人やダイエットをしている人にとっては強い味方となってくれるでしょう。さらに腸内環境を整えて便秘を改善してくれることもダイエットにはプラスに働きます。
またオリゴ糖の中でも、例えばフラクトオリゴ糖は血糖値の上昇を緩やかにしてくれることが分かっています。これは糖質の消化吸収を遅らせる働きがあるためで、糖尿病の予防に役立ったり、ダイエットに役立つとされています。さらにフラクトオリゴ糖を摂取することで、腸の中で酪酸という物質を作り出し、酪酸菌が増えることで、体内炎症を抑えるのに非常に役立ってくれることが分かっています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。