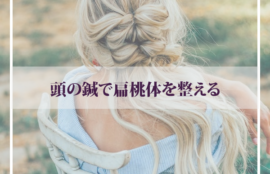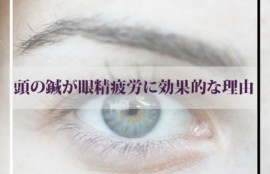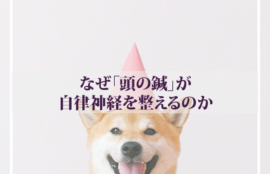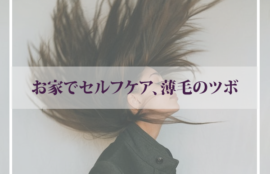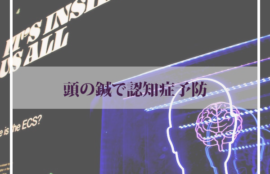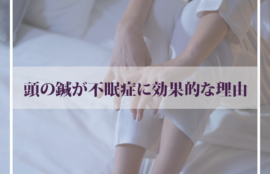寝なかった分、週末に寝れば良いってわけではなく、睡眠不足が続くと睡眠負債と言って、睡眠不足は実は借金のように積み重なっていきます。1日だけ寝られなかったら1日だけの負債で済みますが、2週間寝られなかったらそれは2週間分の負債が溜まり、1日しっかり眠っただけでは睡眠負債は返済できません。例えば8時間寝ないといけない人が6時間しか眠れていなかったら、その分の睡眠負債がどんどん貯まっていきます。
睡眠負債の現状
この大きな負債が溜まっていく睡眠負債とは、慢性的な睡眠不足の状態が蓄積されて心身へ支障をきしている状態のことを示します。睡眠時間には個人差があり、職種や日中の活動量によって変わりますが、一般的には6.5時間から7 時間程度とされています。経済開発機構OECDの調査によるとアメリカ、イギリス、フランスを初めとする多くの先進国、そして同じアジアの国、中国では1日の平均睡眠時間が8時間を超えている一方、日本は7 時間22分と最も短くなっています。
また、厚生労働省の調査によると40代男性の睡眠時間は11.3%が5時間未満、5時間以上6時間未満が37.2%、そして40代女性は5時間未満が10.6%、そして5時間以上6時間未満が41.8%と40代の男女半数が6時間以下の睡眠時間でした。また睡眠で休養があまり取れていないと答えた人の割合も40代が30.9%となっていて、20代から50代までの中で最も多くなっています。
日本人の睡眠不足による経済損失は約15兆円とも言われ、睡眠の質を調査した内容では、眠りが浅いと答えた人は全体の44%に登り、その内17%の人は不眠 症の経験があると答えています。睡眠時間が5時間を切る日が続くと、脳はチューハイを数杯飲んだ時と同じくらい機能が低下してしまいます。
これだけにとまらず免疫力の低下も確認されており、5万6953人の女性を対象にした調査によると、睡眠時間が5時間以下の人は、8時間前後の人たちに比べて肺炎になるリスクが1.39倍、風邪のリスク2.5倍 から3倍、乳がんのリスクが1.62倍、男性では前立線がんのリスクが2.08倍になるという報告も上がっています。
睡眠不足による影響は、様々な悪影響があり、脂肪や糖の代謝が悪くなり、交感神経の緊張が続き、血圧も上がり、睡眠時間が6時間以下の人は肥満、糖尿病、心臓病の有病率の上昇、さらにうつ病、事故、自殺のリスク上昇が挙げられます。4419人の日本人男性を調査した自治医科大学の研究では睡眠時間が6 時間以下の人は、7から8時間の人に比べて死亡率が2.4倍高くなるという報告まで出ています。
睡眠負債の体への影響
睡眠不足になると疲れやすく体がだるくなり、なかなか起きれない、やる気が出なくなります。また2003年に睡眠不足がパフォーマンスにどのような影響を与えるかを調べた実験(パソコンの画面かボタンが光るとすぐにボタンを押すという簡単な集中力が必要な実験)では、反応の正確性と押すまでの速さを測定しました。全員8時間ぐっすりと眠った後、グループ1は72時間、つまり3日間ずっと起きているグループ、グループ2は毎晩4時間だけ寝るグループ、 3は毎晩6時間寝るグループ4は、毎晩8時間眠れると分けて計測しました。
毎晩8時間眠ったグループ4では、パフォーマンスに何の問題もありませんでしたが、3日間徹夜したグループ1では、24時間後にミスが5倍になりました。そして毎晩4時間寝たグループ2と毎晩6時間寝たグループ3では、3日間完徹したグループ1と同じくらいのパフォーマンスの低下が見られ、ミスが5倍に増えました。そしてグループ3の6時間睡眠では、10日後にグループ1と同じレベルまでパフォーマンスが低下したことが分かっています。
徹夜したグループは24時間後に、8時間睡眠より4 時間少ないグループでは、4時間×6日間で24時間、8時間睡眠より2時間少ないグループ3では2時間×10日間で20 時間、どのグループもほぼ同じ時間分の睡眠負債でパフォーマンスが同じように落ちるという結果になりました。
睡眠不足になるとカナダのウェスタン大学での研究で睡眠不足後の脳をMRIで検査して脳の血流を調べた研究では、同じ人を使って通常の睡眠後と睡眠不足後の認知テストを受けている最中の脳内の状態を比べた結果、後者では血流の流れが歩くなり、意思決定や問題解決、記憶で重要として知られている前頭葉と頭頂葉の活動が睡眠不足後は減ってしまうと考えられています。そのため認知力や判断力が低下し、ネガティブな感情や衝動に走りやすいということになると考えられています。
睡眠中に脳のお掃除
私たちが眠くなるのは起きている間に分泌されるアデノシンという物質が関係しています。このアデノシンが脳に蓄積されて、私たちは眠気を感じ、眠くなります。そしてアミロイドβと共に寝ている間にアデノシンは掃除されますが、睡眠の質が悪かったり、睡眠時間が取れないとアデノシンが脳から完全に取り除かれず、翌日も残ったままになってしまいます。そして次の日も睡眠不足でアデノシが溜まり、また寝不足でアデノシンが溜まっていくという負のスパイラルに陥って、これが心の病に繋がります。
アデノシンは、私たちのやる気を引き出したり、快感や多幸感、運動や学習、感情、意欲、記憶、理性、理解といったことに影響を及ぼすドーパミンの分泌を抑えてしまう効果があります。実際にドーパミン欠乏状態になると、うつ病無気力、集中力の低下ストレス障害、不安障害、適応障害の症状が出ることが分かっていて、これは睡眠不足の症状とも見事に一致しています。さらにドーパミンが出ないと不眠にもなりやすく、寝不足、睡眠負債の蓄積、不眠の悪化、さらに寝不足というように眠れないスパイラルに入ってしまいます。
大切になってくるのが睡眠時間よりも睡眠の質です。当然睡眠時間もきちんと取った方が良く、ハーバード大学の調査では7時間から8時間の睡眠時間がベストということが分かっています。また睡眠の質を上げることで短い時間でアデノシンやアミロイドベータの脳のゴミを処理できることも分かっているため、睡眠の質を上げることは睡眠時間と同じように大切です。
マイクロスリープ
ベッドに入って目を閉じたら次の瞬間寝ている人は、もしかしたら気絶しているかも知れません。この場合の気絶は、睡眠負債が溜まることによって脳の血流が阻害されて、一時的または突然の意識障害が起こる状態を言います。一時的とはいえ、意識消失を起こしている状態であり、もちろん気絶したことは本人は覚えていません。そして呼びかけてもなかなか起きないという特徴があります。
そして気絶した状態だと起きた時、頭がボっとしている、手足がしびれている、寝てから何回も目が覚める、朝起きてから3時間くらいでひどく眠気に襲われるなどの状態が挙げられます。睡眠負債のない健康な人だと普通は布団に入ってから10分から20分くらいは寝るまでに時間がかかると言われています。
また、質の悪い睡眠が続いて睡眠負債が大きくなっていると精神的にも肉体的にも疲労が溜まり、活動していない時に強い眠気に襲われます。電車の吊り革に捕まって立ったまま寝てしまって膝がガクッと落ちた人を見たことありませんか。日常で体を動かさない時、例えば会議中とか電車の中など、刺激がなくなった途端眠くなって寝てしまう状態では、睡眠不足に陥っているサインです。その 状態は眠りに落ちるというよりも一瞬だけ意識が無くなるマイクロスリープという現象です。
マイクロスリープが起こると数秒から数分間脳が外からの情報を取り入れなくなり、視覚情報だけでなく全ての近がシャットアウトされ、全く反応しないと いう危険な状態です。本人は起きているつもりですが、このような状態になると作業や思考力の低下を招き、作業中のミスやトラブルの原因になります。ちなみに眠気を感じたら10から20分の仮眠を取ることがマイクロスリープの予防には効果的です。
睡眠負債を解消する
朝起て3から4時間後という午前中の時間は、脳が最も活発に働く時です。この朝の時間に眠くなるのは、睡眠負債が溜まっていると考えられます。朝7時にきる人だったら10時や11時頃、この頃に眠くなる人は睡眠負債が溜まっているかも知れません。
また、睡眠負債が借金であるというイメージから休日に少しでも日頃の負債を返済したい、たくさん寝て日頃の睡眠不足を補っておきたいという人は多いですが、睡眠がお金と大きく違うところは貯蓄できないことです。また一気に返済できないこともできません。そして休日に2時間以上寝てしまうことは、それ自体が睡眠不足のサインです。これは別の睡眠不足を引き起こしてしまいます。
時差ボケは、時間枠が違う外国へ旅行に行った時に体内時計が狂い、夜なのに眠れなかったり、昼間なのにぐったり疲れてしまったりという現象のことです。休日に余分に寝ることが時差ボケになってしまうのは、体内時計は24時間の睡眠と覚醒のリズムで体温や血圧などの自立神経ホルモンの分泌等の生理活動に関わっているからです。つまり週末や休日に2時間余分に寝てしまうということは、その平日のリズムを崩してしまうことになります。この休日に2時間余分に寝て体内時計が狂ってしまう現象を「社会的時差ボケ」と呼びます。
1年中時差ボケを経験している国際線の客室乗務員を対象とした研究によると、脳の学習と記憶に関する部が実際小さくなっていることが分かっています。これは時差ボケのストレスで脳の一部が破壊されたためと見られています。
また、社会的時差ボケになりやすい人は、がんや2型糖尿病などのリスクが平均よりもかなり高くなることが分かっています。例えば平日に6時間溜まった睡眠負債を土日で一気に3時間ずつ寝て返済しようとすることは社会的時差ボケを招き、逆効果になることから避けるべきです。スタンフォード大学医学部精神科西野教授によると1日40分の睡眠負債を取り戻すのには約3週間かかるとのこと。
明治薬科大学の駒田准教授によると、休日に平日の睡眠不足を一気に解消しようとするのではなく、平日に30分早く寝て睡眠時間を増やすようにすることが推奨されています。つまり睡眠はコツコツと返済していかないといけません。どうしても早く寝ることが難しい場合は、休日も平日と同じ時間に起きて夜の睡眠に影響を与えない範囲で午後3時までに1から2時間程度を目安として昼寝をすることを駒田准教授は提案しています。
また、体内時計が狂ってしまったら屋外に出て太陽の光を浴びると体内時計がリセットされます。眠くなるホルモンのメラトニンは太陽光を浴びてから14時間後に再分泌され、朝日を浴びることは体内時計をリセットして夜眠るためにとても大事です。
照明をつけて寝る
照明をつけっぱなしで寝ていませんか。それは朝にも関係しており、カーテンをしないで寝ることも同じです。照明などの光を浴びて寝る人は、そうでない人に比べて抑鬱状態、動脈脈効果、体重の増加が起こりやすいことが分かっています。これは奈良県立医科大学で行われたケーススタディーで、2010年から約3000人の被験者に、手首に腕時計型の光を感知する機器を付けて寝てもらった研究で明らかになっています。
この結果は、睡眠中に分泌されるメラトニンというホルモンが、光が当たることによって分泌が滞り、それによって自律神経やホルモンが乱れることによって体にストレスが掛かり、それで太りやすくなったり、動脈効果が起こるのではないかと言われています。
つまり、夜はしっかり暗くして寝ることが大切で、夜の明かりをつけて寝るだけでなく、カーテンを開けて寝ることにも注意しましょう。朝早くから明るくなる夏の時期は、光を当たっていると睡眠サイクルがおかしくなることも言われています。
甘いものをやたら欲しくなる
睡眠不足だと太りやすくなるのは、睡眠が食欲をコントロールするホルモンと関わりがあると考えられているからです。アメリカのコロンビア大学が2005年に行った30から60歳の男女5000人を対象に調べた研究によると、平均7から9時間の睡眠時間の人に比べて、4時間以下の睡眠の人の肥満率は73%も高いことが分かっています。
スタンフォード大学の調査によると睡眠時間が8時間の人に比べて5 時間しか寝ていない人は、食欲が湧くホルモングレリンの量が15%多く、食欲を抑えるホルモンレプチンの量が15%少ないという結果が出ています。つまり起きている時間が長いとその分、私たちの体は甘いものや脂肪を沢山確保するように促して、それらを少しでも多く貯めようとしてしまいます。
一方で、よく寝ることで基礎代謝を上げることができます。基礎代謝は内臓を動かしたり、呼吸をしたり、生きているだけで消費するカロリーのことです。私たちの基礎代謝量を上げてくれるのは成長ホルモンという就寝してから3時間経たないと分泌されないホルモンです。これが少ないと基礎代謝量が上がらず太りやすくなってしまいます。
睡眠のための環境を整える
快適な睡眠のための基本は、寝る時には部屋を暗くすること、そして静かな環境を作ることが大切です。部屋を暗くするのは寝る時だけではなく、夕方から少しずつ照明を落として暗くしていくようにすることがお勧めされています。メラトニンの分泌を活発にさせるために、スマートフォンやタブレットなどのブルーライトも寝る1 から2時間前には見てはいけません。また一般的には18から22度のちょっと肌寒いくらいの室温が最適とされています。
また、フレグラントを寝室に使うことも効果的です。睡眠のために一番おすすめなのがラベンダーです。ラベンダーは昔から神経を落ち着かせたり、痛みを和らげたりして睡眠に導入する作用があると言われています。代替医療研究によるとラベンダーの香りを嗅ぐことで脳波にリラックスした時に現れるα波が見られることが分かっています。またラベンダーは神経伝達物質のGABAを刺激し、メラトニン分泌を助ける働きがあることも分かっています。
ミネソタで79人の大学生を対象に行われた睡眠の研究では、ラベンダーの香りを嗅ぐことが脳の神経細胞に作用し、睡眠の質が向上することが証明されています。また質の良いラベンダーのエッセンシャルオイルを染み込ませたハンカチやラベンダーのポプリをベッドサイドに置くと睡眠薬を飲んだのと同じ効果が得られます。一方で温かいカモミールティーも寝る前に飲むと良いと言われています。カモミールは抗酸化作用があるフラボノイドを持ち、精神を落ち着かせる働きがあります。
睡眠の質を上げる
睡眠の質を上げるためには、まずは換気をきちんとすることです。臨床研究で室内の二酸化炭素のレベルが1000ppmの濃度に達すると脳が軽い血状態になり、パフォーマンスが下がると言われています。実際に米国環境健康科学研究所が発表した内容によると、CO2濃度レベルが600ppmから1000ppmに増加 すると、人のパフォーマンスや意思決定力は約20%低下し、1400ppmでの平均 低下率は50%、さらに2500ppmでは低下率は65%となることが分かっています。そして換気していない締め切った部屋で寝ていると4000ppmまで上昇してしまうことが実験で明らかになっています。
東京消防長の調べでも3000ppmを超えると頭痛やめまい、ひどい時には吐き気を起こし、6000ppmを超えると意識を失うこともあります。睡眠中の 4000ppmは危険レベルと言っていいほど二酸化炭素が上昇していることになります。
具体的に換気する方法は、例えば6畳の部屋なら窓とドアの2箇所を開けて風通しを良くすれば、5分くらいで換気ができます。実際にデンマーク工科大学が行った研究では、換気をすることで目覚めが良くなり、睡眠の質を計測した結果でも改善している結果になり、さらに気分の向上、集中力アップ、思考力テストの得点上昇などの報告も上がっています。
思い出の写真を見返す
夜眠れない人の多くは寝る前に考え事をして嫌なことを思い出してしまうのではないでしょうか。嫌な記憶は質の良い睡眠にとっては大敵です。私たちの脳や体というのは、実は目の前で起きていることと頭の中で起きていることの区別ができません。
例えば山を歩いて急に熊が出てくれば驚いて恐怖します。ですが私たちは熊が出なくても物音がしたり、獣の匂いがすると熊が出てくるかもしれないという 恐怖に怯えます。そこに熊が存在しないにも関わらず、脳が作り出した空想に怯えます。これと同じで私たちの脳内の嫌な記憶もまた私たちを怯えさせます。
実際、嫌な記憶を思い出すだけで体が臨戦体制に入り、ストレスによって脈が早くなったり、血圧が高くなってしまうことが分かっています。良質な睡眠のためにはリラックスが不可欠であり、交感神経が高まっているとよく眠れなく なるのは当然のことです。
しかし誰しもが経験的に知っている通りで嫌な記憶というのは思い出さないようにしようと念じれば念じるほど頭から逆に離れなくなってしまいます。そこでお勧めなのが強制的に良い記憶を思い出すようにすることです。子供の頃の楽しかった思い出など誰しもが良い思い出、楽しかったなという思い出を持っているはずです。そのような楽しかった思い出の写真をベッドの横に置いて寝る前に眺めるようにしましょう。
さらにおすすめなのが、その写真の中の思い出を言葉に出して、実際に唱えることです。あの時は家族で旅行に行ってこんなことがあったな、などと声に出すと脳や体を私たち自身が発する言葉によって簡単に騙すことができます。楽しかった思い出の写真を見なが、その時の風景やポジティブな気持ちを言葉に表すことで気持ちが本当に楽しくなり前向きになることができます。
こうすることで不安や嫌な記憶が頭から追い払われ、交感神経が静まって眠りにつきやすくなるでしょう。ちなみに美しい虹や花、動物などの写真を見るだけでも心がリラックスすることが分かっています。
30から50代の男女を対象に様々な写真を見せて心の動きを測定したトロント 大学の実験では、私たちは子供の笑顔や色とりどりの花といった微笑ましい写真を見るだけで副交換神経がアップすることが分かっています。一方でゴミなどの写真を見た被験者は反対に交感神経が高まるのみならず疲れやすくなっ たり、集中力が低下するといった症状が見られています。
ただし注意していただきたいのはスマホで写真や動画を見るのはNGです。スマホの画面は強烈なブルーライトを発するため脳を覚醒させてしまい、睡眠の質を下げてしまいます。
睡眠薬のリスク
健康のために食事や運動と並んで大切なのが睡眠です。多くの方が健康のために睡眠にこだわっているかと思いますが、睡眠の質をアップするためHOWTOを実践してもなかなか うまく寝つけない方も多いと思います。実は統計的にも日本人の5人に1人が不眠の症状に悩まされていることが分かっています。
不眠は加齢と共に増加し、特に中高年になると一気に不眠に悩む人が急増します。そして60代以上になるとおよそ3割の人が何かしらの睡眠障害を持つようになるというデータもあります。現代は寝ることが難しい時代で、様々なストレスによって私たちはどんどん眠れなくなっています。
このような不眠に関する悩みから多くの人が睡眠薬を使用しており、しかし睡眠薬と一口に言っても、その種類は様々存在しています。睡眠薬には入眠を促して眠りに入りやすくするタイプ、眠った後の途中の覚醒を抑えるもの、そして睡眠の質を深くするものなど様々なタイプあります。しかし睡眠は、科学的に未解明な領域で、まだまだ分かっていないことが多くあります。自分にどのような睡眠薬が本当に必要なのかをきちんと把握できている人は稀です。また医者の間でも睡眠薬の使い方について、その確立された方法論が存在していません。そのため睡眠障害で精神科に行って全く自分に合っていない睡眠薬を処方されてしまう人もいるでしょう。
このように自分に合わない睡眠薬を飲むことは、逆に不眠を助長してしまうことになりかれません。例えば眠りに入りづらい入眠困難を持っている人が、眠りが持続する効果がある睡眠薬を飲んでもあまり意味はありません。むしろ起きたい時間に起きれなくなったり、起きても頭がぼっとしたり、睡眠のリズムが狂ってしまうなど睡眠に悪影響を与えてしまいます。さらに睡眠薬自体が持っている様々な副作用のリスクがあります。最近では副作用が少ない睡眠薬が次々と開発されていますが、そのような新薬の多くは病院に行かなければもらえず、薬局で買うことはできません。
一方で、不眠治療を専門とする医者は、日本には数えるほどしかおらず、多くの場合睡眠が専門ではない内科などが睡眠薬を処方しているというのが現状です。そして多くの患者さんが睡眠薬を使ってでもなんとか眠ろうとし、そこで医師は睡眠薬を出してくださいと言われたら、別に専門ではなくとも睡眠薬を出してしまう医師は多くいるでしょう。
このような現状の中で、日本で高齢者に対して最も多く処方されている睡眠薬はマイスリーであると言われています。マイスリーはベンゾジアゼピン系という強い副作用を持つ従来の睡眠薬とは違って副作用が少ないため、安全に使えると言われがちです。確かにベンゾジアゼピン系で見られるようなふらつきなどは少ないため医者にとっては処方しやすいと考えられます。
しかし、全く副作用がないというわけではありません。睡眠薬には効き方による分類の他に体内でどのように作用するかという薬理作用の違いによる分類も存在します。睡眠薬は大きく分けて次の2つがあり、脳の機能を低下させることで眠らせるタイプ、自然な眠気を促すタイプです。前者の脳の機能を低下させることで眠らせるタイプは、眠りを促すというよりはむしろ脳を強制的に麻痺させて昏睡状態にするというのがより正確な言い方です。つまり麻酔とかアルコールと同じように強制的に脳をシャットダウンしてしまいます。
自然な眠気を促すタイプよりはすぐに眠れるというメリットがある一方で、自然な眠りではないため、当然副作用も強いと言えます。ベンゾジアゼピン系に比べ、副作用が少ないと言われるマイスリーは、前者の脳の機能を低下させることで眠らせるタイプであり、それなりの副作用があることが知られています。マイスリーは長期に渡って使い続けることで、物忘れや夢遊病、夜間の異常行動といった副作用が出ることで有名です。このようなマイスリーの副作用の多くは、長期に渡る使用で出てくるという点です。短期的には、マイスリーで副作用が出ることは少ないため、知識のない内科などは副作用を気にせせずに処方することもあるでしょう。
そして、もう1つの問題が精神的な睡眠薬依存です。従来のベンザジアゼピン系がタバコや薬物と同じく高い身体依存があったのに対し、マイスリーのようなベンゾジアゼピン系ではないお薬には身体依存はありません。しかし私たち人間は体が依存していなくても、心で依存してしまう動物です。例えばギャンブル依存症などはその最たる例であると言えます。
マイスリーにもまた精神依存のリスクがあり、多くの人が1度使うとやめられなくなってしまうというデメリットがあります。睡眠障害を持っている人が睡眠薬によって眠れるようになると今度は、逆に睡眠薬なしでは眠れない体になってしまいます。このように精神依存が形成されてしまうことで、マイスリーを長期間に渡って飲み続けることになり、様々な副作用が起きてしまいます。そのためマイスリーを始めとした脳機能を強制的に低下させるタイプの睡眠薬の使用はおすすめできません。
また、医師の診断の元、処方されている睡眠薬を飲むのではなく、最近では薬局などで市販の睡眠薬が簡単に手に入るため、こちらに依存している人が多くいます。しかし睡眠薬は気軽に飲んでも良い薬ではありません。まずは睡眠の質を向上するためのテクニックや寝付きに良くするためのテクニックを活用して、それでもどうしても眠れないのであれば医師に相談するといった手順を踏んでください。
安眠のための鍼灸治療の効果
鍼灸の不眠に対する効果には、概ね2つの考え方があります。一つが自律神経の作用で、そのメカニズムには体性自律神経反射が挙げられます。これは鍼灸による刺激が脳の視床下部に伝わることで自律神経の調整を促す反応です。
特に不眠の状態の多くが、交感神経が優位になっているため、それを鍼灸の刺激作用によって調整して、その効果を期待するものです。また鍼灸の刺激が、脳内に伝わることで、セロトニンなどの神経伝達物質を分泌を促すことで、睡眠のリズムを整えることが研究でも確認されています。
一方で東洋医学では、気の作用から不眠を考えます。日中は「陽」、夜間は「陰」の状態から気の切り替わりが上手くできないため不眠になると感考えます。つまり寝るときに陽の気が強すぎるため眠れなくなる状態になるため、ツボの刺激により「陰」「陽」を調整することで不眠を治療します。
このような不眠症への鍼灸治療の効果の研究は世界中で報告されています。例えば、頭や手足のツボに鍼灸刺激を行うことで不眠症の改善、うつ気分の状態などの改善も報告されています。さらにストレスホルモンのコルチゾールの減少、幸せホルモンのセロトニンの増加も確認されています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。