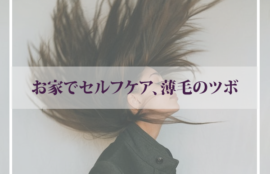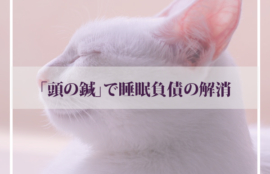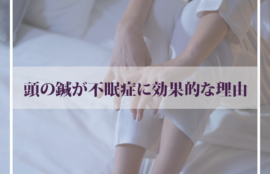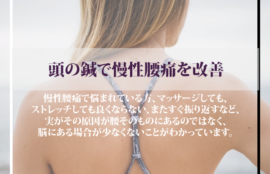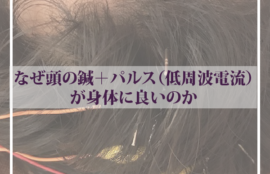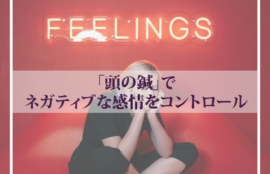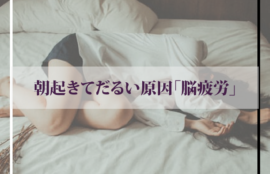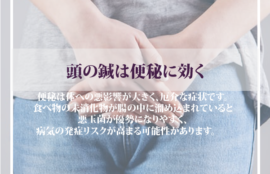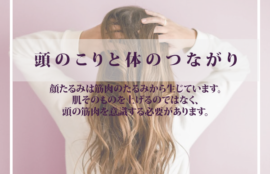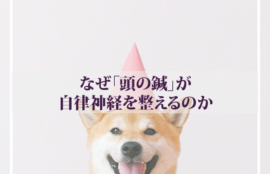日本人の4人に1人が頭痛に悩んでいると言われています。この頭痛にはいくつかの種類があり、頭痛の種類によって治療が異なります。誤った治療をすると酷くなる場合があります。
ヘッドマッサージのお店の中には、「全ての頭痛にヘッドマッサージ(頭皮マッサージ)が良い」という宣伝文句を書いているところがありますが、ヘッドマッサージしてはいけない頭痛があります。
今回は頭痛の種類と症状に加え、頭痛の種類に応じた治療を解説します。
頭痛の種類と症状
頭痛は大きく分けて2つあります。
- 一次性頭痛:ストレスや生活習慣
- 二次性頭痛:脳出血や脳腫瘍がなどの病気による
頭痛の症状は頭痛の症状は、重大な病気の前兆の場合もあり、決して頭痛を軽視してはいけません。病気と関係する二次性頭痛の代表例は、くも膜下出血、脳腫瘍、脳出血などを伴うものです。「激しい痛み」「手足の麻痺やしびれ」「吐き気や嘔吐」が表れた場合は、直ちに救急車を呼んでください。とは言っても、頭痛全体の90%以上が一次性頭痛(機能性頭痛)になります。
治療の対象となるのは、一次性頭痛と言われるストレスや生活習慣によるものです。さらに、おおまかに「緊張型頭痛」「偏頭痛」「群発性頭痛」の3種類に分かれます。
| 種類 | 原因 | 症状 | 対策 |
| 緊張型頭痛 | ・ストレスや長時間のデスクワークなどで、血行が悪くなることが原因 ・肩こりや首のこりを伴うことが多い ・男性より女性のほうが1.5倍程度多い割合で生じる | ・頭全体が締め付けられるような痛み ・一定の痛みが継続する ・後頚部から後頭部の筋肉が緊張して痛みを伴う | ・頭皮マッサージやストレッチ ・入浴(39度ぐらいの温度) ・適度な運動 |
| 偏頭痛 | ・神経伝達物質により、血管が圧迫されて血液の循環が悪くなることによって痛みが生じる ・脳の血管が拡張することで起こる ・20~40歳代の女性に多い | ・ズキンズキンと脈を打つような痛み ・月に1~2回、多い人では週に1回程度で起こる ・1回あたりの痛みは数時間程度の場合が多い | ・頭皮マッサージ、その他のマッサージ、運動、入浴は控えた方が良い ・こめかみや首を冷やす ・静かで暗いところで安静にする |
| 群発頭痛 | ・目の後ろを通っている内頸動脈が拡張して炎症が起きるためではないかと考えられている ・正確な原因は不明 ・女性よりも男性に多く見られる | ・目をえぐられるような激しい痛み ・片側のみ起こる ・一年のうち決まった時間や時期に起こり、痛みは15分から3時間程度続く | ・専門医の診察が必要 ・飲酒は控える ・規則正しい生活を行う |
「緊張型頭痛」も「偏頭痛」も、精神的なストレスが大きな原因と考えられていますが、激しい痛みを伴い筋肉などが緊張して血流が悪くなります。その結果、筋肉が疲労し、神経が刺激されて痛みが生じます。
当然、頚部や肩のこり、眼精疲労、疲労感などを伴うケースが多くみられます。さらに、この疲労やストレスの蓄積が筋肉や神経だけでなく内臓の働きまで徐々に低下させてしまうことも珍しくありません。激しい痛みを伴ったり、痛みが改善されない場合は、専門医の診察が必要です。
緊張型頭痛への「頭の鍼」の効果
日本人の頭痛の中で最も多いのがこの緊張型頭痛です。緊張型頭痛は、圧迫感のある痛みが頭の左右両方に起こることが多いです。痛みはそこまで強くありませんが、短時間~数日間続くことがあります。
この緊張型頭痛は、首や肩の筋肉のコリにより引き起こされます。例えば長時間同じ姿勢を続けるディスクワークや、パソコンやスマホで目を酷使することで生じます。また精神的なストレスで首や肩の筋肉がこわばることでも起こります。
「緊張型頭痛」の場合は、鍼やヘッドマッサージで血行を良くすることが効果的です。血行を良くすることで、頭痛緩和、ストレス解消、自律神経を整える、不定愁訴緩解などの効果が期待できます。
緊張型頭痛を改善するツボ
後頭部の頭痛や首の凝りや疲れからくる頭痛に有効なツボです。
玉枕(ぎょくちん):後頭部にある出っ張り(外後頭隆起)の左右にある凹み
天柱(てんちゅう):後頭部のうなじの生え際部分の外側のへこんだところ

偏頭痛への「頭の鍼」の効果
偏頭痛は文字通り、頭の片側だけが突然ズキズキと痛む頭痛です。「偏頭痛」は、ヘッドマッサージは控えた方が良いですが、偏頭痛に対する鍼の効果については、今現在も多くの研究が進められており、様々な研究結果から鍼治療が有効なのではないかと言われています。
頭痛の原因は、ペプチドやヒスタミンこれらの神経伝達物質により、血管が圧迫されて血液の循環が悪くなることによって痛みが生じます。あるいは脳の血管が拡張することによって頭痛が生じます。このように「偏頭痛」は血管の拡張と炎症が関わっているため、鍼によって頭の血流を良くしすぎてしまうと、むしろ悪化させてしまう場合があります。
そこで急性期の炎症を起こしている頭部への刺激は最低限に抑えて手先・足先や下半身を中心に血流を改善させていくのが効果的です。例えば足へお灸をすることで、末端を温めるような治療をします。「片頭痛」は痛くて辛い頭部に注目しがちですが、身体の状態の確認がまず大切です。
「偏頭痛」は、東洋医学用語でいう「下虚上実」です。「下虚上実」とは文字通り「下半身が虚弱で足が冷えることで上半身が過度に充実」している身体状況になります。つまり過度に頭に血が上る病態なので、頭部の血を四肢末端に戻してあげることを考えるのです。
偏頭痛を改善するツボ
「万能のツボ」と言われ、頭や目、首、肩の不調に効果があり、痛み全般にも効果があるとされます。
このツボを押すと、脳の血流量がアップすることが分かっており、この時脳内では痛みを抑えるオピオイド(鎮痛物質)が分泌されて頭痛などが和らぐとされています。
合谷(ごうこく):親指と人差し指の骨の付け根の間で骨と骨の間にあるくぼみ

生理と頭痛(月経関連偏頭痛)
女性に頭痛持ちの人が多いといわれていますが、特に生理前後に頭痛が起こることがあります。その理由は、生理前のホルモンバランスの変動が関係していると考えられています。
西洋医学的には、卵胞ホルモンの分泌が急激に減ると、脳内のセロトニンやカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)という神経伝達物質のバランスが変化します。
CGRP の強力な血管拡張作用により、一気に血管が拡張して炎症が起こり、頭痛が起こりやすくなると考えられています。またセロトニンは、血管収縮のコントロールや痛みの抑制作用を持つ物質であるため、その減少によって頭痛などの痛みに過敏な状態になります。
一方、東洋医学では生理により、体の血液が不足することで頭痛になると考えます。この貧血に近い概念が「血虚」という状態です。血液(赤血球)は酸素を全身に運ぶ役割がありますが、血が不足して、酸素を運べなくなると、脳細胞が酸欠状態になり頭痛が起きます。
対処法として、暗めの静かな部屋で、横になって休み、冷たいタオルで冷やす、少し圧迫したりすると、頭痛が和らぐことがあります。基本的には温めると逆効果なので注意してください。 生理に伴う頭痛には、鍼灸治療によって自律神経を整えることで、生理に伴う頭痛を悪化させるホルモンの分泌を抑えることができるため、症状は和らぎ改善していきます。
生理痛を改善するツボ
生理痛の緩和・生理不順・婦人科系のトラブル・冷え性改善などに効果があります。
三陰交(さんいんこう):足の内くるぶしの一番高いところから指4本分上の、すねの骨の後ろ側にあるくぼみ
照海(しょうかい):足の内くるぶしの一番高いところから親指1本分下、内くるぶしの真下のくぼみ

様々な疾患は「慢性化」すると、改善・回復が長引く事がわかっています。全国で慢性の痛みで悩まれている方は、2600万人とも云われ、約25%くらいしか治療に満足していないと云われています。それだけ慢性化すると改善・回復が難しいと云う事を物語っています。
【最新研究】慢性緊張型頭痛には鍼治療
慢性の緊張型頭痛に対して古代中国の治療法が効果を発揮するという興味深い 研究が神経学の専門誌に掲載されています。慢性緊張型頭痛とは、月2日以上頭が重くて痛むような頭痛が続く状態で、この頭痛はストレスや筋肉の緊張などが原因となって起こると考えられています。慢性緊張型頭痛は、一般的な頭痛の中でも最も多く見られるタイプであり、世界中で約3億人が悩んでいるとも言われています。
慢性緊張型頭痛の治療には鎮痛剤や抗うつ薬などが使われますが、これらの薬には副作用があったり、効果が十分でなかったりする場合があります。そこで鍼治療が注目されており、鍼治療は一的な頭痛や慢性緊張型頭痛に有効である可能性が高いことがこれまでの研究で示されていました。
しかしこれらの研究は鍼治療の種類や回数、期間などが統一されていなかったり、擬鍼治療との比較が不十分だったりするなど問題点がありました。そこでこの研究では、鍼治療が慢性緊張型頭痛に有効であることを示すために、より厳密な方法で鍼治療の効果を検証しています。
この研究には、慢性緊張型頭痛を持つ成人がランダムに2つのグループに分けられ、一方のグループは深く鍼を刺す治療を受けました。この針治療では頭や首や肩の筋肉に関係するツボに鍼を刺し、得気の感覚を得ることを目的としました。もう一方のグループは浅く鍼を刺す治療を受け、この鍼治療では頭や首や肩の筋肉のツボに浅く鍼を刺し、得気の感覚を得ないことを目的としました。
どちらのグループも週に2 回、8週間に渡って鍼治療を受け、鍼治療前と鍼治療後の2ヶ月と8ヶ月で頭痛の頻度が半分以下に減った患者の割合を比較しています。
この研究の結果は、深く鍼を刺す鍼治療が、浅く鍼を刺す鍼治療よりも慢性緊張型頭痛の頻度を減らす効果が高いことが示されました。また鍼治療後の2ヶ月で深く鍼を刺す治療を受けた患者の68%が頭痛の頻度が半分以下に減ったのに対し、浅く鍼を刺す治療を受けた患者は50%でした。さらに鍼治療後の8ヶ月でも深く鍼を刺す治療の効果は持続していることが確認されています。
また、鍼治療の副作用はどちらのグループもほとんど報告されておらず、この研究の意義は鍼治療が慢性緊張型頭痛に対して、安全で持続的で有効な治療法であることを示したことになります。鍼治療は得気の感覚を得ることで頭や首や肩の筋肉の緊張を緩和し、自立神経を整え、頭痛を改善すると考えられています。このように鍼治療は薬に頼らずに頭痛を予防する方法として患者にとっての選択肢となりえます。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。