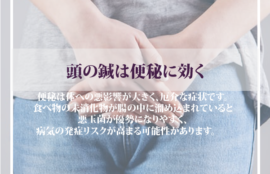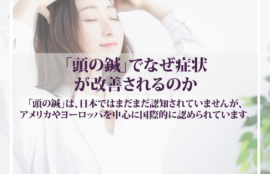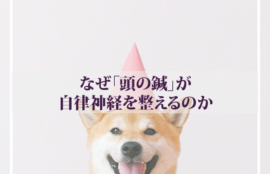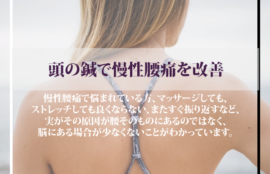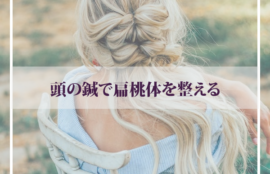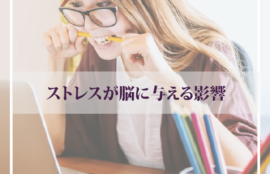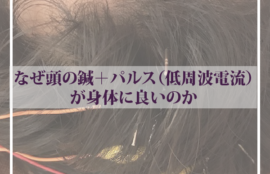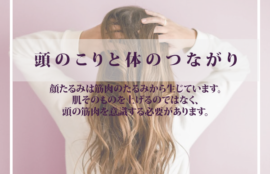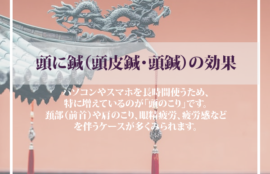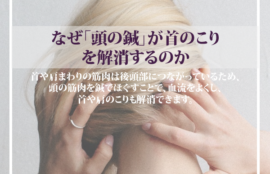現代社会はストレス社会とも言われており、そのため現代ならではの様々な問題や症状に悩む人が沢山います。特にストレスによって、なぜかイライラする、体調がすぐれない、疲れがなかなか取れない、気力がない、落ち込むなど病気でない不定愁訴を抱えている人が多くなっています。
最新の脳科学の研究
ストレスを受けると交感神経過緊張になり、内分泌系である副腎機能が低下を引き起こします。交感神経過緊張によって、イライラしやすいなどの感情的になるだけでなく、血圧が不安定になる、慢性疲労、頭痛などの慢性疼痛が症状として表れます。
また、副交感神経の機能低下は、胃・十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群、腹部膨満、便秘などの症状が現れ、そのほかにも不安障害、パニック障害、うつ病、糖代謝の異常を引き起こします。
最新の脳科学の研究によると、
- ネガティブな感情をコントロールする
- 興奮を鎮める指令を出す
- 痛みの回路の抑制する
のは、前頭部脳領域の前頭前野と呼ばれる場所だと解ってきています。前頭前野は「脳の司令塔」と呼ばれ、考える、記憶する、判断する、コミュニケーション、新創造、行動や情動を整理する、感情をコントロールするなどの重要な働きを担っている部位です。
この前頭前野がストレスを受けると、人の判断、意欲、興味を司っているため、機能が低下してやる気がなくなります。また不安、悲しみ、自己嫌悪、恐怖などの感情も司っているため、不安などの自律神経症状が惹起されたりします。特に前頭前野は、神経伝達物質のドーパミン、セロトニンなどによって支えられています。
特にセロトニンは、心のバランスを整える作用のある伝達物質であり、セロトニンを増やすことで精神的な安定が得られることから「幸せホルモン」と呼ばれています。セロトニンが不足すると、睡眠と覚醒のリズムが乱れる、自律神経が乱れ、慢性的な疲労を感じたり、朝起きられない、イライラするなどの症状を引き起こしたりします。
感情年齢と感情老化
歳を重ねると共に感情のコントロールが難しくなり、嫌なことをずっと引きずったり、昔ほど感動しなくなったりと自覚がある場合は、感情が老化している可能性があります。加齢によって体力が落ちていく健康面の衰え、名前が思い浮かばないなどの脳の衰え、シミやシワが増えていく見た目の衰えなど老化がありますが、これ以上に感情の老化がすべての老化の元凶であることはあまり意識されていません。
感情年齢は思考力、感情、性格、理性などを担う前頭葉の萎縮と密接な関係があります。ワクワクする、ドキドキするなど好奇心、やる気を出すなどの気持ちの切り替えをするなどを担うのが前頭葉です。つまり感情の老化を防ぐと言うのは、前頭葉の老化を防ぐことになります。この前頭葉の老化、つまり萎縮は何もしなければ40代頃から始まり、どんどん進行して感動しなくなったり、やる気が出なくなったり、メンタルが落ち込みがちになるなど状態になります。このような状態になると健康や見た目の老化が一気に加速していきます。
感情の老化を防止する
脳も筋肉と同じように使わなければ急速に老化していきます。歳を取って感情の感度が鈍くなり、気持ちが弾まなくなるのも感情の老化の大きな特徴です。具体的に感情年齢を若く保つための方法は、新しいことにトライすることです。若い頃は何事も経験だからと新しい事にチャレンジしたり、失敗を恐れずに始めてみたりしますが、年齢と共にだんだん臆病になっていきます。結果的に変化のないマンネリした生活が訪れて、感情の老化が進んでしまいます。心に活気がある人が見た目まで若々しく見えるのは、自分が楽しいと思う事や気持ちやワクワクするときめきを探し続けているからです。
この他にも、実は料理をすることが脳を活性化することが分かっています。食材を選んで分量を決める、素材を洗う、野菜の皮を剥き適当な大きさに切る、炒める、煮込む、調味料で味を整えるなど沢山の工程があり、手順、調理時間、効率を頭の中で計算して作業しなければならず、脳がフル稼働します。ぜひ料理をして脳の老化を防ぐことをオススメします。
前頭葉を鍛える大切さ
若い時に比べて頭の回転が落ちてきたと感じる、脳の老化が気になり始めたら、脳の萎縮が加速しているかも知れません。脳の萎縮は前頭葉から始まり、加齢ともにその萎縮は加速していきます。前頭葉は私たちの意欲や感情のコントロールなどを司っている非常に重要な脳の領域です。
前頭葉が老化することによって意欲が低下し、物事への関心が薄れ、自分で考えようとしなくなり、脳がどんどん使わなくなることで、言語能力や計算能力と言った知能そのものが衰え始めます。その脳の老化が、体の老化、見た目の老化、メンタルの老化へと繋がります。
特に生活に変化をつけていない人ほど前頭葉の萎縮が加速しています。そもそも前頭葉は想定外のことに対処する時に活性化する脳の領域です。そのため毎日同じで変化のない生活を繰り返していると衰えていっています。
健康のためにウォーキングするのであれば、同じコースではなく違うコースを試してみる、行きつけのお店だけでなく、新規開拓を心がけるなど少しの変化でも構いません。変化を付けるためには毎日実験だと思って行動するマインドが大切です。新しいことにチャレンジすることで、いろんな発見、たくさんの経験を重ね、脳をいつまでも若々しく保つことができます。
使う言葉で行動が変わる
私たちの使う言葉が、私たちの行動に影響します。特にネガティブワードである「老けた」「歳を取った」「若くない」「疲れた」「嫌だ」「できるわけない」はNGです。
ニューヨーク大学では、学生を2つのグループに分けて、言葉の羅列で文章を作ってもらうという実験を行いました。1つ目のグループには「グレー、孤独、忘れやすい、退職」など年配者のような言葉、2つ目のグループには「喉が渇いた、きれいな、プライベート」などのニュートラルな言葉で文章を作ってもらいました。そして移動してもらったところ、年配者のような言葉を使ったグループのメンバーの歩くスピードが遅くなることが分かっています。つまり使った言葉がその後の行動に影響を与えるということです。どういう言葉を使うかで無意識に私たちの行動が変わってしまうことが示されています。
例えば「疲れた」という言葉を使えば、実際にはそこまで疲れていなくても脳が勝手に疲れた状態を作り出し、本当に疲れた状態になることも考えられます。しかしながら実際に疲れているのに疲れていると言えないのもストレスです。
そこでマイナスの言葉を使った後に「でも」を付けることが大事です。例えば疲れた。でも頑張った。疲れた。でもその分成果が出た、という風にマイナスの言葉に「でも」を付けるだけで、日本語の性質上必ずプラスの言葉が来ます。そして脳は文章の一番最後に来た情報を印象に残しやすい性質があるため、すべてプラスに変えることができます。
ポジティブ・アファメーション
ポジティブ・アファメーションとは、ポジティブで幸せな感情や思考態度を自分 に植えつけ、ネガティブで役に立たない思考を排除することを目的とした短い フレーズを何度も繰り返すことです。例えば、「私は今日も健康で元気」「私の努力は必ず報われる」「私は最高の人生を手にできる」「私のやっていることには全て意味と目的がある」「私は人生に感謝し、自分の人生に満足している」など、短いポジティブなフレーズを何度も繰り返すのがポジティブ・アファメーションです。
このポジティブ・アファメーションは、トップアスリートや世界を牽引する企業家なども行っている方法で、科学的な効果も認められています。ポジティブ・アファメーション行うことで自己効力感が高まり、自尊心が強化され、ネガティブな思考パターンが減り、それによってストレス、不安が軽減されるということが分かっています。
例えば2015年の研究によれば、アファメーションはストレス反応を低下させ、身体的健康を改善し、認知的なパフォーマンスを向上させる可能性があると指摘されています。この研究では、アファメーションを行うことで心理的ストレスと身体的ストレスの両方が優位に軽減されると結論付けられています。また2011年に行われた別の研究では、健康的な行動を取りやすくするために、アファメーションを活用することが推奨されています。この研究においては、アファメーションを行うことによって、質の良い食事を摂る、定期的に運動するなど、より健康的な行動を選択する可能性が高まることが分かっています。つまりポジティブなフレーズを何度も呟いていると健康的な行動を選択する可能性が高まると考えられています。さらにアファメーションを行うことで幸福感が高まるということも分かっています。
なぜこのような言葉によって、プラスの効果が得られるのかと言うと、それはシンプルに言葉や口癖は、私たちに大きな影響を与えるからです。例えば私たちがいつも使っている言葉や口癖は、自己認識と自己イメージに大きな影響を与えます。例えば「私はいつもミスをするダメな人間だ」「私は何をやったってダメなんだ」という口癖をあなたが持っていると、それが自分自身を否定的に見る傾向を強めてしまいます。さらにネガティブな口癖を持っていると脳の中でネガティブな思考パターンが強化されてしまいます。逆に自分に対するポジティブな口癖は、自尊心を高め、自己効力感を強化する働きがあります。これは脳が繰り返し聞く言葉やフレーズに対して敏感に反応し、それを真実として受け入れる傾向があるためです。
ポジティブ・アファメーションは超簡単で、主語+現在系の動詞の形で、ありたい自分について定期的に声に出して繰り返すだけです。例えば「私は、心豊かな人生を実現するため仕事を懸命にやる」などといったフレーズが考えられるでしょう。
ハルエルロッド氏が書かれた「人生を変えるモーニングメソッド」の中でも人生を確実に変える習慣として朝一にアファメーションを行うことが推奨されて います。
“あなたが囚われている思い込みはいつでも書き換えられる。僕たちは誰でも無意識のうちに思考や思い込みや行動をプログラミングされている。プログラミングの内容は他人から言われたこと、自分に言い聞かせていること、人生の経験など良いことも悪いことも含めた様々な影響の結果である。最初から幸せな成功者になるようなプログラミングを持っている人もいるが、ほとんどの人は人生を困難にするプログラミングを持っている。だから意識的にプログラミングを変えないと潜在能力が押し潰され、恐れや不安や過去の縛りに従って生きるはめになる。プログラミングは、いつでも変更や改善が可能だ。アファメーションを使って、どんな時も自信を持って行動し、成功する人間になれるようなプログラミングを始めよう”
人生を変えるモーニングメソッド/ハルエルロッド
感謝することの科学的メリット
感謝することには科学的に様々なメリットが認められています。例えば感謝することで副交感神経の働きが活発になることが分かっており、ストレスや緊張、不安などが和らぎます。また感謝することで睡眠の質が向上することも分かっています。なぜなら感謝の気持ちを持つことで、不安が和らぎ、交感神経の高まりが抑えられて良質な睡眠とすることができるからです。
感謝している事柄を寝る前にリストアップすることで、数週間後に朝の目覚めがすっきり、気分が良くなったという研究報告があります。感謝の習慣を持つ人は、寛容で抑うつになりにくく、不安や孤独を感じにくい傾向があり、相対的なEQ(心の知能指数)も高い傾向があります。
また、感謝の気持ちを持つ訓練を数週間行ったところ、幸福度がアップし、楽観的になり、頭痛が減少したなどが報告されています。実験では、週の出来事で感謝していることを書いたグループ、毎日のイライラや不快なことを書いたグループ、そしてポジティブ、ネガティブに関わらず影響を与えた出来事を書いたグループに分けると、感謝していることを書いたグループはより楽観的になり、生活の満足度や幸福感がアップしたという結果になりました。
他にも感謝することで脳の機能が向上し、免疫力が高まり、寿命が伸びることが分かっています。そのため、小さな事柄でも感謝する習慣を身につけましょう。
苦しい時に役立つ知識
人生には山あり谷ありで、嬉しいこともあれば悲しいこともあります。嬉しい時は何もしなくても前に進んでいきまが、悲しい時や辛い時などうまくいかない時は中々うまく前に進みません。そのような時にむやみに力任せに進んだところでただいたずらに体力を消耗してしまうだけです。実はそんな時にこそ役に立つ知識があります。
限界効用逓減の法則
限界効用逓減の法則は、もともと経済用語でしたが現在では心理学などを様々な場面で使われるようになった概念です。限界効用逓減の法則は簡単に言えば、私たちを満足させるものの総量が増えても、私たちが主観的に感じる満足度は徐々に減少するという法則です。
例えば好きな異性にプレゼントをもらった時、初めての時は飛び上がるほど嬉しかったでしょう。ですが毎回デートでプレゼントをもらい続けていると、例えそのプレゼントの量や値段が上がったとしても満足感は徐々に徐々に下がっていきます。また初めの頃は近所の公園で会うだけでも嬉しかったのに会う回数を重ねていくにつれて満足できなくなります。
このような時に限界効用逓減の法則を知らなければ、自分の気持ちが冷めてしまったのかなとかこの人は運命の人じゃないのかもしれないといった間違った判断を下してしまうことがあります。ですが限界効用逓減の法則を知っていれば、満足感が徐々に減ることやあまり嬉しくなくなることは自然の摂理ということが分かります。
他人は自分を気にしていない
日本人は生まれつき人の目を気にしがちな民族だと言われています。日本列島という小さい島の中で生きていくためには他者と調和して、時には自分の意見や個性を押し殺す必要もあったのかも知れません。
多くの人が人の目を気にしてしまうのは、他人が自分を気にしていると思っているからではないでしょうか。ですが自分が思っているほど案外人はあなたのことを気にしていません。他人は自分を気にしていないという事実を常に意識すると人生は変化します。なぜなら自分の好きなように生きるようになるからです。
誰にでも欠点はある
真面目で誠実であることは素晴らしいことですが、たまに真面目さが行き過ぎで完璧主義になってしまう方もいらっしゃいます。誰にでも欠点はあり、どんな完璧主義の人でも周囲に不完全な人がいたらその人の欠点を認めることが必要です。
多くの人が、自分自身の欠点を認めることができません。少し厳しい言い方になるかもしれませんが、あなたは決して特別な人間ではありません。周りの不完全な人間と同じようにあなた自身もまた不完全な人間です。こうして自分自身の欠点を認めることで窮屈な完璧主義から自由になることができます。そうすれば肩の力を抜いて人生をもっと楽に生きていくことができるでしょう。
レジリエンスを高めて即立ち直る
何か辛いことがあった時、まるで世界で自分だけが苦しい思いをしているような気になってしまいます。ですが世界には約80億人もの人が存在しており、今この瞬間に苦しい思いをしているのは決してあなただけではありません。実はこのように誰にでも辛いことがあると思うだけであなた自身のレジリエンスが高まるという心理学の研究があります。
このレジリエンスとは、回復力やしなやかさを意味する言葉です。木の枝は少しぐらい体重をかけても手を離せばすぐに元のまっすぐな状態に戻ってくれます。これは木が持つしなやかさのおかげです。私たちもまたこのようなしなやかさ、つまりレジリエンスを持つこと で回復力をグッと高めることができます。そのレジリエンスを高める鍵こそが誰にでも辛いことがあるという言葉です。
もっと頑張れるはNG
メンタルが崩壊してしまう絶対にやってはいけない考え方がもっと頑張れるという考え方です。頑張れると思った時点でメンタルは崩壊寸前です。そもそも私たちは順風満帆な時に頑張ろうなんて思いません。頑張ろうと自分に言い聞かせる時点で既にピンチに立たされています。
よし頑張ろうと自分に喝を入れることは確かに一度ぐらいなら有効なケースもあります。ですが一度自分に喝を入れて頑張ったにも関わらず、さらに頑張りのブースターを注入しようとすることは、メンタルをズタボロにしてしまう原因になりかねません。こうして多くの真面目な方々がうつ病や過労死といったメンタルブレイクに陥ってしまいます。大事なのは、自分の身の程を知り、自分の身の丈に合わない努力はせず、適切な休憩によって常に自分自身をメンテナンスすることです。
また、空気を読まなければいけないと考えることもNGです。私たち日本人は、特に空気を読まなければならないと考えがちな民族であると言われています。なぜ、その場の空気を壊してしまうのが怖いのでしょうか。人に嫌われてしまうのが怖いのです。ですが空気を読まなければ、維持できないような人間関係なんて所詮、その程度の人間関係です。そんな人間関係は、今後長い人生を生きていく上で重要なものにはなりません。本当に重要な人間関係は空気なんて読まずとも居心地のいいような関係です。どうでもいい人間関係を維持するために空気を読んでメンタルをすり減らす暇があったら、是非とも自分にとって 居心地のいい本当の人間関係を探しに出かけましょう。
副腎疲労とは
副腎とは、腎臓の上に乗っている小さな臓器です。その働きは、ホルモンの分泌、血糖コントロール、免疫機能、炎症反応など多岐にわたる機能があります。例えば人がストレスを受け続けると、自律神経の交感神経と副腎のホルモン分泌によって対処するようにできています。つまりストレスに関わるあらゆる精神的な問題にも対処できるようにするのがその役割です。
しかし、現代社会に起因する様々なストレスによって副腎への負担が大きくなり、ホルモンの生産性が低下している状態が「副腎疲労」という症状です。この副腎の中枢は、脳の間脳にあるので、つまり「脳の司令塔」にアプローチすることで、副腎疲労を回復することができます。
メンタルと腸内環境
幸せホルモンなどとも呼ばれるセロトニンが減少してしまうことで人の心身には様々な悪影響が起こります。セロトニンは脳内の神経伝達物質であり、感情 や気分をコントロールする働きがあります。セロトニンがドーパミンやノルアドレナリンといったストレスと関係する神経伝達物質を調節し、正しく作用すればメンタルの安定に良い作用があります。
一方で、セロトニン減少により起こる症状として、気分の落ち込み、イライラ、不安を感じる、向上心の低下、無気力、不眠、うつ症状、パニック障害などの症状や疾患を引き起こしてしまうことが分かっています。特にセロトニンは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を促進する作用があるため、不足してしまうことで不眠などの睡眠障害につながってしまうことがあります。
また偏った食生活で栄養が偏り、体内でセロトニンが合成できず、メンタルが不安定になる場合があります。セロトニンを増やすには、その生成を助ける役割を持った必須アミノ酸であるトリプトファンを摂取することが大事です。大豆製品、乳製品、肉類、魚類なのトリプトファンが多く含む食材です。さらにトリプトファンからセロトニンが作られる際には、ビタミンB 6が必要になります。このビタミンB6は食事からも摂取できますが、その多くは腸内細菌により合成されます。つまり腸内環境が悪化し、腸内細菌の働きが悪くなるとセロトニンがうまく合成されなくなります。
また、自律神経とも関連が深い腸内環境は、強いストレスなどで自律神経の乱れが生じると、そのまま腸の調子も悪くなり、セロトニンの低下を誘発します。腸はメンタルにも大きな影響をおよぼす臓器であり、セロトニンを分泌しやすくするためには自律神経と腸内細菌を整える食事を意識しすることが大切です。
メンタルと食品添加物
食品添加物が過剰に添加された食品を超加工食品と言います。最近では超加工食品とメンタル疾患の関連性を示す様々な文献が登場してきました。特にこのような研究の中でエビデンスレベルが高いとされているのが、食品添加物の過剰摂取とうつ病の関係です。一般に食品添加物は食品の発色を良くして見た目を良くしたり、保存性を高め長時間置いておいても腐らないようにするために 添加されます。このような食品添加物には、亜硝酸ナトリウムや防腐剤、合成甘味料などがあります。これらはいずれも腸内環境に悪影響を齎すと考えられています。
一方で、腸内細菌層が腸から遠く離れた脳に大きな影響を与えることが分かっています。このように腸内の環境が脳に与える影響を脳腸相関と言います。例えば、緊張したり、嫌なことがあった時に下痢をしてしまうのは、過度なストレスによって自律神経が乱れ脳腸相関によって、それが腸に伝わり腸の働きが狂ってしまうことで起こります。これは脳腸相関の内、脳から腸というベクトルの例であると言えます。脳腸相関はあくまで一方向性ではなく両方向性の作用です。つまり腸内環境がメンタルに与える悪影響があります。
コンビニ弁当やスーパーのお惣菜に使われている食品添加物の多くは、腸内細菌のうち悪玉菌の餌となってしまうことが知られています。悪玉菌は消化吸収を助け、腸内環境を改善する善玉菌と違い食品添加物などを餌にして、それを分解する過程で毒素やガスなどを生み出します。生み出された毒素やガスの一部がおならになりますが、一部はそのまま腸管に吸収されて血液中に漏れ出します。この腸から漏れ出した毒ガスは、皮膚や脳などの様々な細胞に蓄積していきます。このように細胞に蓄積した毒素がお肌のシミやそばかす、脳細胞のゴミといった様々な悪影響として現れてきます。さらに悪化した腸内環境は、脳腸相関によって脳に直接悪影響を及ぼします。最近では腸内環境の悪化が、うつ病を引き起こす可能性についても指摘されています。
砂糖がうつの原因!?
脳が生存し、正常に機能するために糖分は欠かせません。脳は24時間に62g のグルコースを必要とすることが分かっています。しかしお菓子やソフトドリンクなど精製糖が添加された不健康な加工食品を口にすると、脳が過剰な量のグルコースで溢れます。この糖分が脳内に炎症を引き起こし、うつ病につながることがあります。一方で高GI値の炭水化物も体内で糖質と同じ形で処理されてしまうため、同じ理由でうつ病のリスクを高めます。
そして、人工甘味料もうつ病と関係していると考えられています。ある研究の結果、主にダイエット飲料を通じて人工甘味料を摂取する人は、ダイエット飲料を飲まない人よりもうつ病になりやすいことが分かっています。さらに悪いことに複数の研究を通じて気分を調節する神経伝達物質の濃度を変えてしまうことから、人工甘味料は脳にとって毒になることも実証されています。
特にアスパルテームは有害であることが証明されており、2017年にアスパルテームに関する複数の研究を再調査したところ、アスパルテームは脳内でドーパミンとノルアドレナリンとセロトニン、いわゆる幸せを感じさせる神経伝達物質の合成と分泌を抑制することが分かりました。加えてアステルパームが酸化を引き起こすために、脳内でフリーラジカルという有害な物質も増えてしまい、 酸化ストレスによって細胞を損失し、さらには脳の炎症を引き起こし、脳がうつ状態に陥りやすくなります。もちろん全ての甘味料が有害であるとは限りませんが、スクロースなどアスパルテーム以外の甘味料もうつ病を引き起こす、または悪化させる恐れがあると示す証拠が多く見つかっています。
心の安定には「幸せホルモン」
人の行動に大きな影響を与える脳内物質である「セロトニン」と「オキシトシン」は、幸せホルモンとも呼ばれ、この2つの分泌量が心の安定、つまり人の幸福感に影響を与えることが分かっています。これらのホルモンの分泌量を意図的に増やすことができれば、イライラが解消されたり、ストレスが軽くなるなどの効果が期待できます。
一方で、女性ホルモンとの関係性も指摘されおり、女性は生理前に何らか鬱々とした気分になってしまうのは、セロトニンが低下するからとも言われています。セロトニンが不足してしまうと疲労やイライラ感、仕事への意欲低下や不眠などの症状をきたしてしまいます。
「セロトニン」は、自律神経を整える、不眠症を軽減する役割を持つ脳内物質で、その分泌量がうつ病と関係していると考えられています。「オキシトシン」のストレスの緩和や、感染症の予防まで幅広い役割があると考えられています。
いずれも規則正しい生活を続けること、毎日適度な運動という当たり前の習慣をコツコツ続けことでセロトニンの分泌を促す第一歩です。また良好な人間関係や動物とのスキンシップもオキシトシンの分泌を促してくれます。
また、頭の鍼が脳幹に働きかけて、これらの分泌量を増やす可能性が示唆されています。国内外問わず、薬が効かない心の病(うつ病など)にも鍼灸治療に効果があるということは広く知られています。また心の症状だけでなく体の症状である頭痛、肩首こり、目まい、不眠、頭痛、動悸、疲れやすさなど症状などにも科学的根拠に基づいた効果検証が進められており、薬で対応できない症状への代替治療としても様々な国で活用されています(NIH:米国国立衛生研究所)。
頭の鍼の特徴
当院の頭の鍼は、前頭前野の活性化、交感神経過緊張の抑制、副腎機能を向上させる、脳内物質分泌の促進ために行います。そのため「究極のヘッドスパ」コースのポイントは、置鍼(鍼を打って置く)時間を長くし、パルスによる低周波刺激を与えることです。特に下記の症状の方におススメするコースです。
- イライラなど感情の起伏が激しい(易怒性)
- 気力がない(意欲の低下)
- 落ち込みやすい(情緒不安定)
- 疲労感(脱抑制)
- 集中力、思考、判断力の低下(注意障害)
- 慢性頭痛
- 睡眠障害
- 生理周期の乱れなど
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。