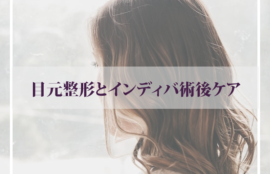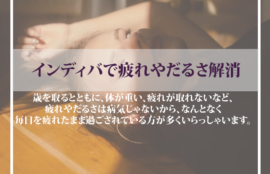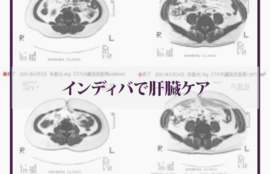どんな健康法を試しても、内臓温度が低いままであれば無駄になる可能性があります。体を冷やしてはいけないと良く言われますが、それは内臓を冷やさないことが重要なのです。
そもそも内臓温度とは、一般的な体温計の数値(体表面温度)とは異なり、体表面温度より内臓温度1から2℃高く、37.2から38℃ぐらいが理想と言われています。この温度より低いと内臓の動きが悪くなり、健康のための体の機能がうまく働かなくなります。
生活習慣病のリスクだけでなく、肩こり、腰痛、便秘や胃もたれ、自律神経の乱れからイライラ、集中力の欠如など様々な不調の原因となります。一方で内臓温度を上げることであらゆる不調を遠ざけることができるのです。
内臓の冷えチェック
内蔵のチェックの仕方は簡単で、おへそより少し上にある溝落ちに手を当てて、手のひらより冷めたければ内臓が冷えている可能性が高くなります。おへその上下の温度を確認する方法もありますが、女性は子宮も冷えていて比べられないこともあるので、温度を比べるならおへその上下ではなく、溝落ちと脇を比べてみると分かりやすいでしょう。
また、内臓ではなく脂肪が冷たいという可能性もありますが、確かに脂肪は熱伝動率が低いからお腹周りに多くついていれば触ると冷たく感じます。ただし腹周りの脂肪が冷えている場合は、その奥にある内臓も冷えてると考えて良いでしょう。
一方で、ダイエットの話でよく出てくる基礎代謝は、内臓が冷えると基礎代謝が下がると言われています。基礎代謝は、簡単に言うと生きていくために使われる必要最低限のエネルギー量のことです。また基礎代謝を上げるために筋肉量を増やそうとよく言われていますが、実は基礎代謝の内訳を見てみると筋肉が2割を占め、肝臓も2割を占めています。さらに胃腸や膵臓、腎臓などの消費割合も合わせると内臓だけでかなりの基礎代謝量になります。内臓が冷えると内臓の働きが低下して代謝が落ち、消費できるカロリー量が減り、余ったエネルギーが脂肪として付いて、燃焼できずに蓄積されていきます。
内臓の冷えは脂肪以外にも、例えば風邪を引きやすくなります。人間の体は冷えを感じると交感神経が有意に働いて、熱を逃さないよう血管を収縮させます。これは体温を保つための働きですが、血管を圧迫するため、当然血の巡りは悪くなります。そして腸の中には風邪のウイルスと戦う免疫細胞の約7割が集まっていると言われており、交換神経が優位で血流が悪い状態は、腸の働きを低下させ、つまり免疫機能の働きも弱めてしまいます。
さらに免疫細胞は、風邪のウイルスだけでなく、毎日数百から数千個できると言われているがん細胞から体を守る役割もあります。このような免疫機能は、体温が0.5度下がるだけで約35%免疫力が低下すると言われています。ちなみに体温35度台は、がん細胞が活発に活動する温度と言われています。また腸の動きが悪くなると便秘トラブルも増えるため、将来的に健康を害す可能性も高くなります。
内臓の冷えで起こる4つの影響
内臓の冷えが心や体の不調を引き起こす大きな要因になっています。例えば運動することで体内に熱が発生しますが、運動不足で体内で熱が生まれにくくなり内臓が冷えやすくなります。またストレスや環境の変化によって自律神経が乱れ内臓の冷えが引き起こされます。血流をコントロールしている自律神経が乱れると内臓に熱が運ばれなくなり内臓が冷えてしまいます。またパソコンやスマホなどで悪い姿勢を続けて骨格が歪み、血流が悪くなったり神経が圧迫されたりします。その結果、肩こりや腰痛といった悩みだけでなく、自律神経の乱れを引き起こして内臓の冷えの原因になります。
内臓が冷えがもたらす体への悪影響には、①自律神経の乱れ、②各内臓機能の低下、③免疫機能の低下、④代謝が落ちることが挙げられます。
①自律神経の乱れ
自律神経は体を健康に保つ司令塔の役割を担っています。私たちの体には、環境が変化しても体温や血液量、免疫機能など体を健康的な状態に維持する「ホメオスタシス」という能力が備わっています。例えば暑い時は汗をかき体温を下げ、寒い時には震えて体温を上げようとします。このホメオスタシスを維持するために内臓、代謝、体温などの体の機能をコントロールする役割が自律神経にあります。
健康な人は、体の表面温度より内臓温度の方が1から2度高く、約37.2から38度くらいが理想的な内臓温度と考えられています。この内臓温度より低くなってしまうと自律神経は適切な温度を保とうと働きますが、ずっと低い状態が続くと自律神経の負担が大きくなり過ぎて上手く機能しなくなります。これが自律神経が乱れた状態、かつホメオスタシスが機能しない状態、つまり心身の健康的な状態に保つ機能が正常に働いていない状態です。
この結果、疲労、頭痛、不眠、便秘、やる気の低下などの様々な不調が起きてしまいます。
②各内臓機能の低下
内臓の温度が適正体温よりも低くなると寒さで内臓の働きが鈍くなります。内臓の働きには、栄養を取り込んでエネルギーに変えることや、体内に入ってきた毒素を中和することが挙げられますが、これらの動きが鈍くなることで食べ物の消化や吸収、解毒などの内臓機能がうまく働かず不健康な状態に陥ってしまいます。
③免疫機能の低下
体に入ってきた病原菌と戦う免疫細胞も、また内臓が冷えていると良いパフォーマンスを発揮できなくなります。内臓温度が理想的な状態であれば免疫機能は正常に働きます。逆に体内の温度が下がっている状態であれば、免疫機能の働きも下がり体内に侵入してきたウイルスなどの外敵にしっかりと抵抗できなくなります。その結果、風邪やインフルエンザなどにかかりやすくなります。
④代謝が落ちる
体温調整や呼吸など無意識的に行われる生命活動よって消費されるエネルギー、いわゆる基礎代謝も内臓の冷えによって代謝が落ちてしまいます。基礎代謝は私たちのエネルギー消費量の6から7割を占めており、基礎代謝が落ちると体全体で消費するエネルギーが激減してしまいます。つまり太りやすく痩せにくい体になります。さらに基礎代謝が下がることで体に熱が生まれにくくなるため、内臓がさらに冷えやすくなるという悪循環に陥ります。
内臓を冷やしてしまう原因
内臓温度が低いままでは、健康に良いことに取り組んでいても、エンジンが不調のままうまく走らない車を無理やり動かそうとしていることと同じです。体調不良、肩こり、腰痛、頭痛、疲れ、冷え性、便秘など不調の原因の多くが内臓温度が低いことと関係しています。
内臓が冷えているかどうか簡単にわかる方法がおへそを挟んで上と下で手を当てることです。上に当てた手よりも下に当てた手が温かかった場合は、内臓が冷えている可能性が高くなります。
また体温が高くても内臓温度は低い方が多く、内臓を冷やしてしまう原因が、体を冷やす食習慣、血流を悪くする生活習慣、自律神経を乱す日常です。
内蔵と美容の関係
体の隅々に栄養を届ける役割は血液が担っていますが、体の中心である内臓が冷えて血行が悪くなると肌に必要な水分や栄養も届かなくなります。乾燥はもちろん、シワ、たるみ、くすみ(STK)も出やすくなります。特に肌の新陳代謝が悪くなるためくすみやシミなどの肌トラブルが目立つようになります。
内蔵を冷やさないためには、腹巻きを巻くことも大切ですが、多くの人の場合、内臓が冷える要因の生活習慣の中でも食生活が関係しているケースが多くあります。冷たいものを飲んだり、食べたりってこともあり、また栄養が不足していることもあります。
体を冷やす生活習慣
体を冷やす食べ物は直接体を内から冷やします。注意すべき食材として夏野菜、南国の野菜や果物があり、水分が多い食物ほど体を冷やす作用があります。また生野菜だけという過度な食事制限もストレスとなって自律神経の乱れに繋がります。自律神経が乱れるとホメオスタシスが正常に働かなくなり、血流が悪くなれば熱が運ばれなくなり、少しづつ内臓温度を下げていくことになります。特にダイエットしても効果がないのであれば、内臓が冷えきって基礎代謝が低い可能性があります。ただし何事も極端に解釈して食べ物を制限すると内臓を冷やすだけでなく、必要な栄養素も摂れていないということになります。生野菜を大量に食べるのではなく、温野菜にしたりスープにして食べたりすることで、内臓を温めて基礎代謝を向上させるために適量を食べることを意識しましょう。また体を温めてくれる食材として根菜類(ごぼう、れんこん、イモ類)があります。
一方で、朝は1日の中で一番体温が低いため、ヨーグルトを食べて冷やしたり、冷えたお水を飲むのも避けましょう。また足が冷たくて眠れないので靴下を重ね履きしたり、タイツを履いたりして防寒対策をしている方は多いと思います。この習慣は内臓を冷やす原因になります。
靴下やタイツで足を締め付けてしまうと、血管が圧迫されて足先から下半身にかけて血流が悪くなり、体全体の血行も悪くなって内臓の温度が下がってしまいます。一方で化学繊維でつくられた靴下などは摩擦が生じて静電気を発生して、自律神経に悪影響を与える可能性が指摘されています。どうしても手足が冷たくて寒い時は、サイズが大きい綿製品の靴下を履きましょう。
内臓温度を上げるメリット
老化を防ぐ
内臓温度を上げると体内の活性酸素を増えすぎないようにできるため老化を抑制することができます。一方で内臓温度が下がれば、抗酸化酵素の働きが鈍るため活性酸素が体内で増え過ぎて老化を加速させます。
私たちが1日に取り込む酸素の約2%が活性酸素になると言われています。この活性酸素は様々な病気の原因だけでなく、血管や皮膚などの老化を促進させ、動脈硬化、シワやシミといった老化現象を引き起こす原因となります。
また、内臓温度を保つことで、新陳代謝が活発になり細胞が入れ替わり、疲れにくい体づくりと、老化を防ぐことにもなります。また血流を良くして内臓温度を上げることで脳が活性化します。
痩せやすくなる
内臓温度が1℃低下すると基礎代謝が15%低下すると言われており、代謝が落ち痩せにくくなる一方で、内臓温度が上がれば、基礎代謝がアップして消費カロリーが上がり、食事量が変わらなければそれだけで痩せやすくなります。また内臓脂肪が落ちやすい状態にもなります。
免疫力アップ
私たちの体の免疫システムの防御力を維持するには、内臓温度を上げることが大切です。内臓温度が1℃下げれば免疫力は30%減少しますが、1℃上げると免疫力は5倍にアップすると言われています。免疫力が上がれば様々な病気を予防することができます。
身体を温める食材
根菜類
特に体を温める食べ物を摂るべきですが、それを見分ける方法があります。1つ目は土の中で育つもの、いわゆる根菜類です。根菜は冷えに良いと知られており、水分量が比較的少ないため体を冷やしにくく、ビタミンやミネラルも豊富で血行を促す働きがあります。玉ねぎやニンニクは根菜類とは違いますが、同じ土の中で育つ野菜として体を温めると言われています。
体を温める食材として最も有名なものは生姜です。胃腸の冷えによる内臓機能低下防止のために古来より小薬として使われていた実績があります。一方で納豆やキムチなどの発酵食品には、酵素というものが多く含まれており、この酵素は代謝を促す働きがあり、血行が良くなって体が温まります。
そして暖色の野菜や果物などの赤、黄、橙、黒などの温かい色味の野菜や果物は体を温める効果が期待できます。かぼちゃやニンジン、果物はりんごやブドウが挙げられます。実はトマトやナスは体を温める野菜ではありません。水分が多く含まれており、多く含まれるカリウムは利尿作用があるため、熱を体外へ出す働きがあるためです。
寒い地域で取れる食材
寒い地域で取れる食材は体を温めるものが多いです。例えば青森で取れるりんご、山形で取れるサランボもその1つです。一方、マンゴ、バナナなどの南国フルーツは体を冷やすことになります。また温かい地域で取れる砂糖キビも体を冷やす性質を持っており、砂糖キビから生成される砂糖も同じです。
また砂糖には、砂糖大根いわゆるビートから作られる甜菜糖という種類のものがあり、この甜菜の一大生産地となっているのが北海道です。厳しい寒さの北の台地で収穫できることは、つまり体を温める効果が期待できることになります。このように砂糖でも原材料の産地が違うだけで、温めるか冷やすかに違いがあります。しかも甜菜糖には、オリゴ糖が豊富に含まれており、オリゴ糖は腸内で全玉菌を増やすために働いてくれます。内臓を温めるだけじゃ なく腸内環境を整えて便秘解消、免疫アップまで期待できます。ちなみにビタミンEが豊富な食材は、血行を良くする効果の他、細胞を傷つける活性酸素を取り除く働きも期待できます。ビタミンEはナッツなどの種類や、かぼちゃなどの緑王食野菜にも多く含まれています。
内蔵を温める呼吸法
内蔵を刺激する呼吸法に横隔膜を動かす方法があります。横隔膜は胸とお腹の境を区切るドーム上の呼吸筋膜で、この筋肉の下に肝臓や胃腸、膵臓、腸、腎臓などが付いています。横隔膜は息を吸う時に収縮して下方に引き下がり、つまり横隔膜の下についている臓器をぐっと押し下げます。そして息を吐く時に横隔膜が緩んで押し下げられた内臓も弛緩します。この動きが内臓のマッサージになります。普段人は意識していないと胸式呼吸をしていると言われて います。内臓を動かすためには吸った時に、お腹が膨らむ複式呼吸が大切です。
やり方は簡単で、まず仰向けに寝っ転がり、膝を立ててお腹の上に手のひらを当てます。鼻からゆっくりと息を吸って、お腹が膨らんでいるかをしっかり確認しましょう。吸った後はまた鼻からゆっくりと息を全て吐き切ります。この時お腹がへこんでいくのをしっかり手のひらで確認しましょう。何回行うかは自分が気持ちよく感じる、無理のない範囲で良いでしょう。呼吸の長さも自分に合わせたもので良いですが、吐く時は吸った時の2倍の長さをかけて行いましょう。例えば4秒かけて吸ったら8秒かけて吐くって感じです。深く息を吸ってゆっくり吐く複式呼吸は体の隅々まで酸素を送り、血管を緩め、流れもよくする効果が期待できます。また副交感神経も優位になるため、夜寝る前のリラックスにもおすすめです。
一方で、しっかり内臓を動かしたいなら運動がおすすめです。筋肉を鍛える目的ではなく五臓六腑にアプローチすることに特化した運動が陰ヨガです。運動量が多く筋力アップが目的の陽ヨガとは違い、陰ヨガはゆったりとした動きで心身の調整ができます。筋肉や股関節をじっくりとほぐす動きが多いため、全身の血の巡りを良くする効果が期待できます。
インディバで内臓温度を上げる
当院の医療向けインディバでは、高周波温熱機器を使用する温熱療法により、体の深部から細胞を温め、内臓の温度を高めます。
内蔵温度が高まると内臓機能が改善し血液やリンパの流れが良くなることで、代謝が上がり、基礎代謝アップ・脂肪燃焼・アンチエイジング・自律神経を整えるなど様々な効果が期待できます。さらに治療法が困難であった冷え性、更年期障害、便秘や肥満、疲労の改善、不妊や生理痛、PMSなど婦人科系機能の改善が期待できます。
また、血液循環の改善により、老廃物が流れると同時に痛みの元となる発痛物質が取り除かれ、痛みやコリが緩解します。また血行が改善することで、疲労物質の代謝や脂肪の燃焼を促進します。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。