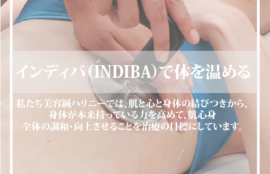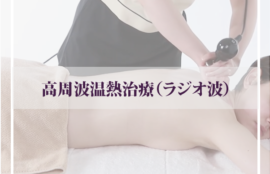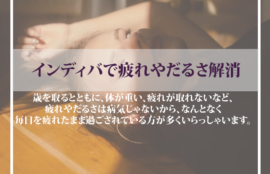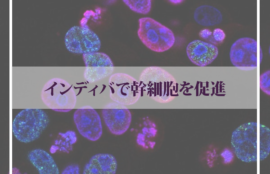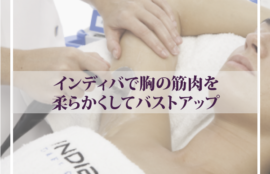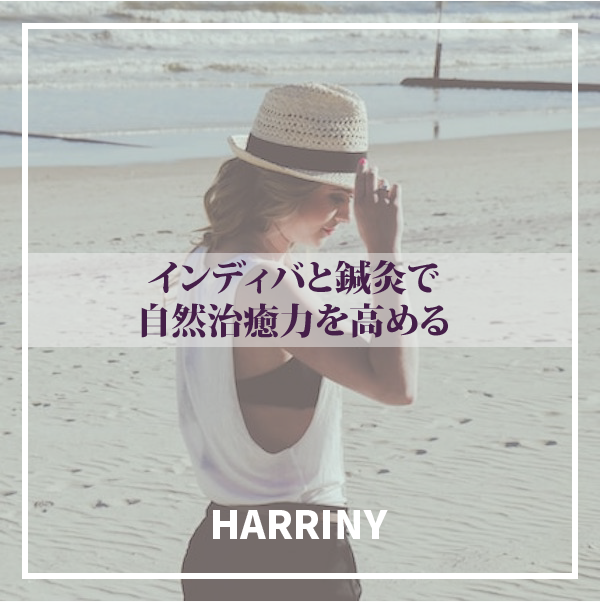
私たちの身の回りには、健康に関する沢山の情報が溢れています。そして厄介なのが医師や研究者などの専門家の間でも意見が分かれていることです。一体何が正しいと戸惑ってしまっても無理はありません。
しかし、結論から言えば誰にでも当てはまる正しい健康方法というのは世の中にありません。つまり人にはそれぞれに合った健康方法が存在しているということです。私たち一人ひとりの遺伝子、腸内細菌、ミトコンドリアの働き、性格、後天的情報などによって相性が異なり、本当に自分に合った健康法を見つけるということが重要です。
何をすれば、自分の体調が良くなるのか、何を食べれば健康的に過ごすことができるのか、自分の体の声にしっかりと耳を傾けながら、私たちは自分に合った健康法を実践する必要があります。
自然治癒力とは
古代ギリシャ時代の意志であり、医学の父とも呼ばれるヒポクラテスは自然治癒力こそが最良の医者であるという言葉を残しています。そもそも私たち人類が医学と呼んでいるもののほとんどが対症療法です。対症療法とは、病気に伴う症状を和らげる治療のことで、病気を根本から治すことはできません。
例えば、風邪をひいた時に飲む解熱剤は、風邪のウイルスをやっつけてくれる薬ではありません。一般に大人が罹る風邪の多くはライノウイルスというウイルス感染によるものですが、現代の科学技術を持ってしてもこのウイルスに対する特効薬は実現されていません。つまり風邪は、私たちの自然治癒力によって治すしかない病気です。そして風邪の他にも、胃腸炎やアレルギーなど根本的な治療法がなく、私たちが自然治癒力で治すしかない病気というのは本当に沢山存在します。
この自然治癒力は残念なことに加齢によって低下していきます。加齢によって自然治癒力が衰えれば、様々な病気に罹りやすくなってしまう上に、そのような病気が治りにくくなってしまうというデメリットもあります。しかし自然治癒力が上がる素晴らしき食べ物があります。
自然治癒力と聞いて多くの方が免疫力を思い浮かべるかもしれません。もちろん免疫力も自然治癒力の一つですが、免疫力だけが自然治癒力ではありません。 例えば、止血機構には免疫細胞とはまた違う血管内の凝固系というシステムが働いています。また切ったり擦れたりして傷ついた皮膚が自然と修復されていくのも自然治癒力の力ですが、このような皮膚の再生を創傷治癒と言い、これにはコラーゲンやタンパク質を構成する繊維芽細胞が関わっています。この線維芽細胞も免疫系とは別の自然治癒力の一種です。このように自然治癒力は、いわゆる免疫力を含めた病気や怪我を治す能力全般のことです。
このような自然治癒力を維持するためには、それ相応の栄養が必要です。つまり自然治癒力を高めるためにはバランスの良い食事を心がけるべきであるというのは言うまでもありません。
自然治癒力が働く体づくり
私たちの体には自然治癒力が備わっています。自然治癒力は人間や動物の体が持つ自然に傷や病気を治す力のことです。この力は免疫システムや代謝機能、細胞の再生能力などの働きにより維持されています。少し体調が悪かったとしても自然治癒力が働くのであれば、放っておいても症状は回復し、病気になることはありません。しかし現在は自然治癒力が弱まってしまっている人が沢山いるというのが現状です。
この自然治癒力の低下を防ぐには、例えば良質な睡眠が必要です。十分な睡眠を取ることで免疫力が向上し、疲労回復や細胞の修復が促進されます。また適度な運動も重要です。適度な運動を行うことで血行が促進され、免疫力が高まり、自然治癒力が高まります。その他にも適度な休憩で体の疲れを取り、ストレスを適切に軽減することなどが自然治癒力を高める上で重要なことです。
体調不良は免疫力の低下
病気でもないのになんとなく体調が悪い時の原因の一つとして考えられているのが免疫力の低下です。免疫は体を健康に維持していくためのシステムの一つ で、細菌やウイルスを始めとする外敵を排除するのみならず、体内で生まれた 異常細胞も駆逐する重要な働きがあります。
実は体の中では、毎日4000個もの癌細胞が生まれていることが知られています。ですが全ての人が癌になるわけではなく、免疫細胞が生まれた癌細胞を毎日取り除いてくれています。しかし毎日同じように能力を発揮できるわけではなく、非常に繊細なものであるため、栄養バランスが崩れたり、十分な睡眠が取れていないと、その能力が低下します。
コルチゾールがメンタルに影響
免疫力が低下して起こる意外な症状にやる気が起きないということが挙げられます。無気力は、うつ病などのメンタルが原因ではなく、免疫力の低下が原因であるとも考えられています。私たちのメンタルは、多少のストレスがかかっても、体内で分泌されるストレスホルモンのコルチゾールによってメンタルをストレスから守ってくれます。コルチゾールが低い方が良いと言われるのは、コルチゾールそのものが悪いのではなく、コルチゾールが高い≒ストレスが沢山かかかっていることを意味しているからです。
つまり、コルチゾールが高いということは本来ストレスに対して、体の防衛機構が働いているということを意味しています。しかしコルチゾールにも副作用があり、それは免疫力を低下させてしまうという作用です。ストレスによって 免疫力が低下していると当然体力も低下し、より頑張ろうとすれば当然無理が出ます。こうして無理を続けることによって、それがやる気の低下などのマイナスの症状に繋がり、このような無気力がさらに続くと燃え尽き症候群のようになる恐れもあります。
免疫力とお肌トラブル
免疫力が低下で起こる意外な症状が荒れた肌です。毎日スキンケアをしているにも関わらずお肌がキレイにならない場合は、免疫力の低下が原因かもしれません。そもそも肌は体内に侵入してくる病原体の最初の壁です。肌は体の内と外の境界線であり、常にウイルスや細菌、埃などの異物に晒されています。そのために皮膚のバリア機能があり、皮膚のバリア機能を維持するものこそが免疫力です。
免疫力が低下してバリア機能が弱まると、簡単に異物が体内に侵入して、お肌のトラブルの原因となります。このようにお肌のトラブルの原因が免疫力の低下だとすれば、いくら外側からスキンケアしたところで改善はしません。あくまで内側から免疫力を高めない限り、お肌の状態はよくなりません。
もちろん、これ以上異物を侵入させないために適切なスキンケアを続けるということは重要ですが、それと同時に内側から免疫力を改善するということも重要なことです。免疫力が正常に回復して、それを維持することができれば、お肌のトラブルは自然と良くなっていきます。
首・肩こりは免疫の暴走
肩こりの直接的な原因は、長時間同じ姿勢、緊張して強張ったりすることで首から背中にかけての筋肉が硬くなって、血行が悪くなって引き起こされます。また筋肉への血流が悪くなれば、当然筋肉へ酸素や栄養素が運べなくなり、同時に乳酸をはじめとした疲労物質が筋肉に蓄積していきます。このような老廃物が肩や首の痛みにつながり、肩こりに発展します。このような単純なコリであれば、姿勢を良くしたり、ストレッチをすることで血流が改善し、比較的簡単にコリを取ることができるはずです。
しかし中々コリが取れない場合は、免疫力の低下を疑う必要があります。なぜなら痛みは炎症の一種であり、肩こりが続くということは炎症が長く続いているということを意味します。炎症は免疫のバランスが崩れることで起こること が知られており、長く続く肩こりの背景には免疫力の低下が隠されていると考えることができます。さらにこのような痛みが続くと、それ自体が肉体的なストレスとなってコルチゾールが持続的に分泌されるようになり、それによってさらに免疫力が低下、体中の炎症が酷くなってストレスが増加するという悪循環に陥ってしまいます。
このような悪循環を止めるためには、免疫力のバランスを調節して体内の炎症を止めるしかありません。炎症は本来ならば、私たちの体を守ってくれる大切な役割がありますが、免疫力が低下しバランスが崩れると必要ではない異常な炎症を起こしてしまうことがあります。このように必要ない炎症が起きてしまうことを慢性炎症と言います。慢性炎症が生活習慣病をはじめとする様々な病気の原因になるだけでなく、免疫バランスが悪くなると肩こりのような他にも様々な害が体に齎されてしまいます。
自然治癒力が低下する食べ物
何を食べるべきかというのは個々で違いますが、一方で何を食べないべきかについては万人共通ではないでしょうか。なぜなら何を食べないかというのは生物学の基礎原理があるからです。万人に共通する食べてはいけないものは、自然界にない食べ物、原材料名の多い食べ物、国産の野菜、不自然な製法で作られた油です。
自然界にない食べ物についてのシンプルなポイントは、なるべく自然なものを摂り、不自然なものは摂らないようにすることです。例えば絶対にとってはいけない食品が米、パン、パスタなどの白い食べ物、そして砂糖です。砂糖の原料であるサトウキビも米、小麦は自然のものですが、精製された白い状態では存在しておりません。糖質を取りすぎると血糖値が上昇します。さらに脳内ホルモンの分泌が狂い、細胞を傷つけ、あらゆる機能を阻害します。さらには病気のリスクが高まり、老化が促進します。
原材料名の多い食べ物
上述した自然界にない食べ物以外にも、食べてはいけないもととして食品添加物があります。日本人が1日に食べている食品添加物は80種類以上あるという説があるほど、普段摂取している食品には何かしらの食品添加物が含まれています。食品添加物には着色料、香料保存料、酸化防止剤、増粘剤、乳化剤など様々な種類があります。これらの添加物は食品の見た目や味を良くしたり、賞味期限を伸ばしたり、食感を改善したりなど様々な目的で使用されています。
これら食品添加物の摂取が多くなることによって一部の人にはアレルギーや過敏症状を引き起こす可能性があります。また過剰な添加物摂取による長期的な健康への影響が懸念されています。さらに組み合わせによっては化学変化で発がん性が現れるものなど、食品添加物同士の問題もあり、長期的に見たとき人体にどんな影響をもたらすのかは誰にも分かりません。
そこで最も簡単に食品添加物を最低限に抑える方法は、ラベルの原材料のリストが短い食品を選ぶということです。 そしてなるべく姿形が思い浮かぶ原材料だけを使った食品を選ぶことが大切です。
国産の野菜について
健康のことを考えて野菜は必ず国産のものを選んでいたという方は多いかもしれません。しかし安全だと思っている日本の野菜の農薬使用料は世界1位2位を争うレベルです。例えば特性が強いネオニコチノイド系の農薬は使用を禁止している国も多くありますが、日本では禁止されていません。また同様によく使われるグリホサート農薬も発がん性が指摘されていて、さらに有機リン酸系の農薬は神経や呼吸器系に支障を来すと指摘されています。
さらに野菜には、農薬だけではなく化学肥料の問題もあり、化学的に合成された不自然なものである以上、農薬と同じような側面があります。解決策は信頼できるお店で、そもそも農薬や化学肥料を使わない野菜を選ぶということでしょう。
選択に難しいのが、オーガニック野菜です。過去にオーガニック野菜が健康に良いのかどうかを調べた研究があります。例えばスタンフォード大学が240件のデータを精査したメタ分析においては、オーガニックと通常の方法で作られた野菜の間に目立った違いが見られず、栄養価や農薬の残留レベルなども微妙な違いしか確認されなかったことが分かっています。一方で他の研究などではオーガニック野菜の方が栄養素が高く、重金属の量が少ないなどと結論付けられている研究もあります。
何れにせよ、オーガニックとか無農薬にこだわりすぎて野菜を食べられなくなってしまっては本末転倒なので、できることであればオーガニック野菜とか無農薬野菜を摂取することを意識するのが良いでしょう。
不自然な製法で作られた油
脂質や油は体の中で細胞やホルモンの材料となり、エネルギー源にもなる必須な栄養素であることは間違いありません。当然脂質であれば何でも良いというわけではなく、良質なものを選ぶということが重要です。
その悪い油の代表がトランス脂肪酸です。スナック菓子や菓子パンなどでファストスプレッドやショートニングといった表示がされています。これらのトランス脂肪酸に関しては、極めて体に悪いということが分かっています。
そして一般的によく使われている安い植物油にも注意が必要です。これらにはオメガ6という成分が多く含まれており、血液凝固作用、血栓促進作用、炎症促進作用、アレルギー促進作用などが確認されています。現代人は総じてオメガ6を摂り過ぎており、無自覚の内に体内で炎症やアレルギー反応が起きていると言えます。
食の大原則
自然治癒力が働くためには、大きく分けて野菜を中心とした食事「デトックス型」と、肉や魚を中心とした食事「栄養補充型」の2つを意識した食事が大切です。今体に不調を感じている人は、どちらか一方に偏ってしまっているはずです。
食の原理原則は、悪いものを避ける、良質なものを摂る、そしてしっかり出す、です。悪いものを避けるというのは、体の毒になるものを極力食べないように するということです。体に悪いものの代表は白い砂糖、ご飯、小麦製品、質の悪い牛乳や肉、化学調味料や農薬を使った食べ物、遺伝子組み換え食品などが挙げられます。
しかし食事はもちろん栄養を摂取する役割もありますが、家族や友人などと人間関係を有効に保つという役割も果たしています。そのため家族でご飯を食べる時は徹底的に気をつけるように意識し、友人などと一緒にご飯を食べる時はある程度妥協して、外食を楽しむことを優先するなどと切り分けましょう。
何を食べればいいのか
まず考えてほしいのは「解毒」か「栄養補充」か自分がより必要としているのはどちらかということです。解毒と栄養補充は食の原理原則の良いものを摂る、しっかり出すに当たります。
デトックス型は、玄米、菜食、マクロビオティックなどに代表される食べ方で、動物性食品は食べたとしても魚や卵、鶏肉のみ、あるいは全く動物性食品は摂らずに野菜と豆、玄米が主な内容の食事のことです。野菜も豆も玄米もポリフェノールに代表されるヒトケミカルや食物繊維が豊富であり、この食べ方に切り替えると体の排泄力が高まります。一方でこのデトックス型のデメリットは、穀、芋類、糖類を摂り過ぎるため、糖尿病のリスクが上がってしまうことです。また肉類、魚類、卵などはほとんど摂らないため、タンパク質不足を始めとした栄養不足になってしまうということです。
栄養補充型に向いている食べ方は、肉、魚、卵といった動物性食品を積極的に摂る一方で、お米などの穀類はほとんど摂らない食べ方です。その代表が糖質制限食です。またパレオダイエット、ケトジェニックなど様々なジャンルがあり、動物性食品には体に必要な脂質、タンパク質の他ビタミンやミネラルも豊富に含まれているため栄養不足で体が弱っている人に適してい ます。しかしデメリットも存在しており、大気汚染、土壌汚染、海洋汚染が進む現代では動物が育つ中で摂り入れた有害物質を、その動物の肉と一緒に摂る危険性があります。例えば肉にホルモン剤が使われたり、魚に水銀が含まれていることは知っている通りです。
どちらにもメリットとデメリットがあるので、両方をバランスよく摂り入れることが大切でしょう。どちらかが絶対的に正しいということではなくて、それぞれのメリットとデメリットを考え合わせて良いとこ取りをするということが必要でしょう。
免疫を上げる分岐差アミノ酸
そして自然治癒力が働く体、つまり病気にならない体を作るための方法として 最も重要なのが、やはり毎日の食事です。免疫細胞も食べた食事によってできています。中でも免疫細胞の主な材料となるのはタンパク質です。良質なタンパク質をたくさん摂ることで免疫細胞が強くなり、逆にタンパク質が不足すると免疫細胞が減少して、体に様々な不調が現れます。
食事から摂取したタンパク質は体に入ると20種類のアミノ酸に分解されます。この内の9種類は、私たちの体内で作ることが出来ず、それらを必須アミノ酸と言い、食事でしか摂ることができません。そして特にバリン、ロイシン、イソロイシンの3つのアミノ酸は、分岐差アミノ酸とも呼ばれます。
この分岐差アミノ酸は、筋肉の強化や肝機能の向上に働くと共に、免疫細胞の一つである好中球の働きを改善てくれる作用があります。好中球は体内の白血球全体のおよそ半数以上を占め、主に細菌感染から体を守ってくれる重要な免疫細胞です。さらに分岐差アミノ酸は主にウイルス感染から体を守ってくれるナチュラルキラー細胞も活性化するということが知られております。もちろん非必須アミノ酸の中にも免疫細胞の働きをサポートしてくれるものがあります。例えばアルギニンという非必須アミノ酸は、体内で異物を飲み込んでくれるマクロファージという免疫細胞を活性化してくれるということが分かっています。また同じく非必須アミノ酸のグルタミンは、様々な免疫細胞の増殖を促すという作用があります。
免疫力アップのために1日に推奨されているタンパク質の摂取量は、体重1kgあたり1gです。体重が60kgの人であれば1日60g以上のタンパク質を摂りましょう。
免疫力アップのためのビタミンD
免疫細胞がその能力を十分に発揮するために効果の高いビタミンがビタミンDです。ビタミンDは骨代謝に働く以外にも免疫機能を調節するという大切な役割があるということが最近分かっています。
ビタミンDは体内に細菌やウイルスが侵入すると、免疫細胞を活性化し、攻撃の指令を出すとともに、過剰な免疫の暴走を抑制して炎症を防いでくれる役割を担っていることが分かりました。
しかし日本人の約8割がビタミンD不足に陥っているという統計があります。日本人の食事摂取基準によれば、ビタミンDの摂取量の目安は成人で1日8.5gとなっており、日本人のビタミンDの平均摂取量は僅か6.6gしかありません。
ただしビタミンDは、脂溶性ビタミンであるため沢山食べても尿として排泄することができませません。そのためサプリメントなどで大量に摂取することはおすすめできないため、ビタミンもアミノ酸も含む全ての他の栄養素と同じように天然の良質な食材から摂取するのが大事です。ビタミンDは、特に鮭やイワシなどの魚介類、干し椎茸などのきのこ類に豊富に含まれています。
免疫細胞を増加させるエキナセア
アメリカでは、人気のハーブの一つとなっており、主に免疫力を向上させてくれる効果があることが知られています。私たちの免疫には、好中球やマクロファージなど様々な種類の免疫細胞が関係していますが、エキナセアには免疫細胞の絶対数を増加する作用が知られています。またマウスに、エキナセアからの抽出物を与えた実験では、インフルエンザウイルスに対する予防効果も認められています。
抗酸化作用のあるナスリン
茄子にはポリフェノールの一種であるナスリンが含まれています。このナスリンには優れた抗酸化作用に加えて、老化の抑制作用やがんの予防効果まである とされています。ナスリンが持つ抗酸化作用によって、体内の酸化を抑え、細胞が錆び、引いては細胞の老化を止めて自然治癒力を上げてくれます。
また、ナスにはナスリンの他にも、ルチンやヘスペリジンなど毛細血管を補強する働きのある栄養素が含まれています。
ただし、ナス科の植物には、植物が捕食から身を守るために持っているレクチンという物質が含まれています。このレクチンは植物毒とも呼ばれ、人によっては食べることで腸の粘膜を刺激し、下痢などの症状を引き起こす恐れがあることが分かっています。乳糖不耐性やグルテン不耐性などと比べ、そこまで日本人には多くないと言われているレクチン不耐性ですが、もしナスを食べてお腹を下したという経験のある方は気を付けて下さい。
様々な食材を採り入れる
健康に配慮した食事を構築する際、根本的な要素は体に対してポジティブな影響を及ぼす食品を選定することです。体に良い影響を与えるとされる野菜や果物など、健康に良い食品を選んで食事に取り入れることが何より大切です。ここで重要なのは個々の成分に固執するのではなく、食品全体としての価値を重視するというアプローチです。食品に含まれる一つ一つの栄養素だけに注目するのではなく、食品全体がどのように健康に良いのかを考えることが大切です。
例えば、緑黄色野菜は一般的に体に良いとされていますが、その中に含まれるβカロテンやリコピンといった成分それ自体が体に良いわけではありません。緑黄色野菜が健康に良いのは、その中に含まれるβカロテンやリコピンだけではなく、他の栄養素や食物繊維など様々な要素が組み合わさっているからです。これは健康的な食事を実践するにあたり、トマトがリコピンを豊富に含んでいる、あるいはニンジンがβカロテンを含むという点に過度に行動する必要はないということを意味しています。つまり特定の成分に拘るのではなく、バランスよく様々な食品を摂ることが健康的な食事の基本であるということです。健康を良くするためには多様な食品をバランスよく食べることが大切であり、特定の成分だけに頼るのではなく、いろんな食材から栄養を取るべきです。
サプリメントではなく食材で栄養素を摂る
人参が健康に良いということを解説するためにβカロテンが含まれているから 健康に良い、ビタミンCが含まれているからお肌をプルプルにするなど、こういった話を聞くと、だったらサプリメントで摂取すれば楽で効果的で良いのではと考える方がいらっしゃいます。ですがあまり良い方法ではありません。
例えば、1970年代までには生活習慣とがんの発症との相関について調査した研究から、緑黄色野菜や果物を多く摂取している人の中では、胃がんや肺がんの発症率がという結果が報告されていました。ここから人々は、これらの食品に含まれているβカロテンががんの予防に役立つ可能性があるのではないかと思うようになりました。
この流れを受けて1990年代には、喫煙者やアスベストに暴露している人々を 対象にβカロテンとビタミンAのサプリメントがどのような効果をもたらす のか検証するランダム比較試験が行われました。つまりがんのリスクが高いとされる喫煙者やアスベストに触れている人に対して、βカロテンとビタミンAのサプリメントが、がん予防に効果があるかどうか調査するための科学的な試験が行われました。この試験の結果、驚くべきことにβカロテンおよびビタミンAの摂取が肺がんを予防するどころか、実際には肺がんのリスクを増加させることが判明しました。
これにより当該研究は倫理的な問題が生じ、研究を続けることが参加者の健康に悪影響を及ぼす可能性があると考えられるとして予定よりも早く中止されました。さらにβカロテンが死亡率や心筋梗塞のリスクを増加させる可能性も報告されました。さらに、その後の研究ではβカロテンの摂取が、女性に対して男性以上に健康被害を及ぼす可能性が指摘されました。βカロテンに関する多くの他の研究も行われており、それらを統合したメタアナリシスでは、βカロテンのサプリメント摂取が膀胱がんの発症率を約50%増加させるとともに、 喫煙者の場合は肺がんと胃がんのリスクを10%から20%を増加させるとされています。加えてβカロテンをサプリメントとして摂取することが、死亡率を約7%増加させる可能性があることや、アルコールを摂取する人にとっては、脳出血のリスクが高まることも示唆されています。
これらの研究結果から学べる教訓は、緑黄色野菜を摂取することは病気のリスクを低減する一方で、それらから抽出されたβカロテンという成分を単独で摂取すると健康に良いどころか病気のリスクを増加させる可能性があるということです。
このような科学的な知見が積み重なることで、健康を考慮する上で成分に固執するのではなく、食品全体としての価値に焦点を当てることが重要であるという認識が広まりつつあります。特定の栄養素だけを取るのではなく、野菜や果物などの食品全体としての栄養バランスを考えることが健康にとって重要なんです。
インディバと鍼灸で免疫力アップ
鍼灸で免疫力がアップする理由には、血流の改善、免疫細胞を活性化することが挙げられます。鍼灸治療では、体のコリを取り、血流の巡りを改善し、インディバやお灸で血流を促進して体温を上げ、免疫力を上げる効果が期待できます。また鍼灸刺激が免疫系の器官や組織などに働き、サイトカインや神経由来物質を介して免疫細胞の活性を調節することが示唆されています。一方で鍼灸刺激は、ストレスによる免疫抑制の防止効果も示唆されています。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。