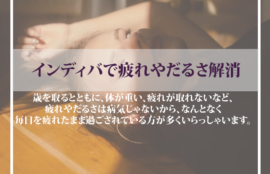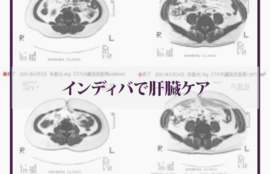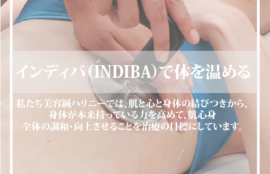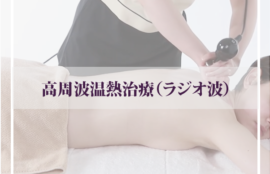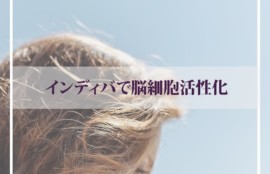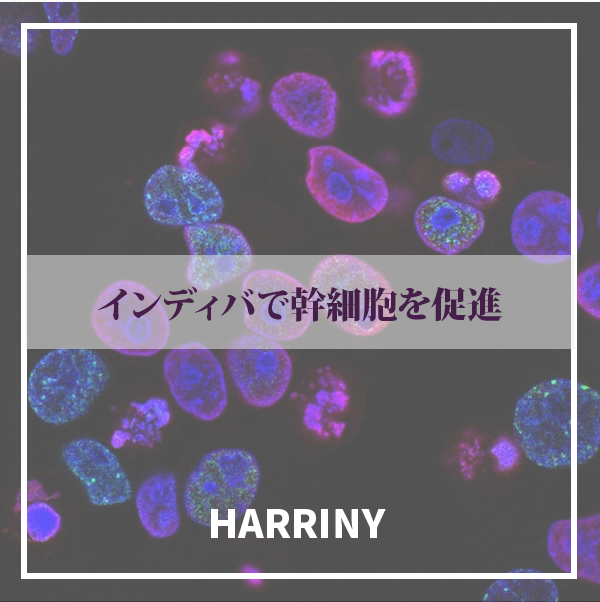
化粧品原料として「ヒト幹細胞(幹細胞培養上清液)」が美容業界で注目を集め続けていますが、「幹細胞」そのものをコスメに配合することは法律で禁止されており、「幹細胞コスメ」も幹細胞そのものが入っているわけではありません。また「幹細胞コスメ」という表記も誤解を招くため、化粧品や広告に使用することが禁じられています。
一般的に「幹細胞」そのものは病気やケガなどの再生医療に使用され、「ヒト幹細胞培養上清液」はアンチエイジング目的の治療や化粧品に使用されることが多い現状です。ちなみに再生医療に関しての法律的なガイドラインである「再生医療の安全確保法」によって、規制されたのが「加工した細胞」です。つまり細胞を使うこと自体に規制が厳しくなり、その抜け道として「細胞培養上清液」という呼び名が使われるようになった背景があります。このようにマーケットベースによって幹細胞コスメなどに商業転用されていった背景があるため、エビデンスベースの効果効能を疑う方が多いのも現状です。
ヒト幹細胞とは
私たちの身体は数十兆個の細胞で構成され、細胞の多くには寿命があり、日々生まれ変わり続けています。その生まれ変わりを維持する機能が「幹細胞」の働きです。幹細胞には、自己複製能(何度でも分裂して同じものを作り出す能力)と多分化能(自分とは違う様々な機能細胞になる)の2つを兼ね備え、その機能によって細胞が死滅しても新たな機能を持った細胞を供給し続けています。
このような幹細胞の機能を応用しているのが再生医療です。一方で美容業界でも幹細胞の再生能力は注目されており、肌の若返りを目的とした美容医療だけでなく、化粧品などにも応用されています。
また、再生医療の代表的な治療方法が幹細胞の移植療法と呼ばれているものです。骨髄や脂肪から幹細胞をつくり、それを身体に戻すことで創傷治癒の働きを活性化することができます。その創傷治癒の働きを担うのが「エクソソーム」という成分です。エクソソームの働きは、細胞から細胞へ情報を伝達する物質であり、この物質が細胞の再生を促していると考えられています。
老化すると細胞自体の機能が低下しますが、その機能低下の1つにエクソソームの分泌の低下が挙げられます。また情報伝達物質を受け取る細胞自体(線維芽細胞など)にも受け取る能力が低下することが明らかになっています(ロート製薬の研究)。
アンチエイジングの鍵「幹細胞」
アメリカサンディエゴにスクリプス研究所というラボがあります。ここではマウスを用いて幹細胞の老化防止効果を実証する実験が行われています。実際この研究所から幹細胞が出すシグナルを老化モデルマウスが受信すると、老化モデルマウスの寿命が延びたという報告があります。これは幹細胞を利用することで老化を人為的に防止できる可能性が見えてきたということです。
幹細胞が出すアンチエイジングのシグナルの正体はエクソソームという小さな脂質、二重膜に入ったマイクロRNAであることが分かってきており、このマイクロRNAを幹細胞が大量に放出し生物の老化を防いでいるのではないかと考えられています。幹細胞が出すエクソソームは組織にとって非常に良い善玉のエクソソームであり、壊れたり老化したりした組織を修復し、免疫機能を調整、老朽化した血管を蘇らせたりできるのではないかと言われています。
ヒト幹細胞コスメとは?
まず再生医療や美容医療で幹細胞を用いる際には、ヒトの脂肪などから幹細胞を採り出し増殖させる必要があります。このときに使われるのが培養液です。その増殖した幹細胞を取り除いた「上澄み液」には、成長因子や様々な生理活性物質(サイトカイン)などが含まれており、ターンオーバーの促進、肌のハリやツヤ、透明感をアップさせる効果が期待できます。
幹細胞コスメは、幹細胞を培養する際に精製される「上澄み液」を配合した化粧品のことです。「上澄み液」には、細胞自体は含まれないのでどんな人にも使用できると言われています。
この培養上清液には脂肪由来、歯髄由来、臍帯血由来、胎盤由来、骨髄幹細胞など、様々なヒト幹細胞培養上清液が存在します。これらは由来先によって効果効能が変わるとも言われています。例えば化粧品会社が多く研究している脂肪幹細胞は、皮下脂肪に存在しており、コラーゲンやヒアルロン酸の促進する働きがあることが分かっています。また骨髄幹細胞は肌の損傷や炎症を修復する機能があります。一方で幹細胞コスメには、日本国内や海外で生産されているものがあり、培地(培養液)や有効成分(成分割合や量)が不明なものが多く、その安全性などが明確に記載されているものを選びましょう。このため、よく分からない幹細胞培養上清液による化粧品によって、幹細胞コスメを否定する方が多くなっています。
この幹細胞培養上清液には、①炎症の抑制、②ダメージを受けた細胞を保護、③幹細胞を必要な場所に誘導する、④新たな血管をつくる機能があると言われ、幹細胞培養上清液に含まれる成長因子や様々な生理活性物質(サイトカイン)の働きにより、細胞の活性化や組織の再生促進、血流改善などの効果が期待できると考えられています。
具体的に美容面では、ターンオーバーを促しハリ・ツヤ感の向上、肌質改善、シワの防止や改善、色素沈着やくすみ、シミなどの予防、抗炎症作用による老化予防、コラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸の生成を促し、ハリと弾力回復が期待できると言われています。
老化のペースメーカーは腸管と腎臓
ミトコンドリアの主な役割は酸素呼吸を行って物質を酸化し、その時に放出されるエネルギーを利用してATPを合成することだと言われています。このATPとは生物のエネルギー源であり、私たちの貴重なエネルギーを生み出す働きがミトコンドリアにはあります。細胞内のミトコンドリアは、酸素の力を使って糖分や脂肪アミノ酸を分解し、効率的にATPやエネルギーを作ってくれます。
ただし、ミトコンドリアが活性化し過ぎると活性酸素が大量に発生し、臓器障害や老化、そして最終的には死に繋がってしまいます。
さらにミトコンドリアによってアンチエイジングの鍵を握っている臓器がどの臓器かということも分かってきています。それはミトコンドリアを非常にたくさん含んでいる腸菅と腎臓です。腸管と腎臓はいずれも栄養素を貪欲に溜め込む機能を持っています。もともと腎臓は腸管の一部から派生してできた臓器で、 排泄するべきゴミと溜め込む栄養素を選別する機能を果たしています。
この腎臓ではナトリウムとグルコースを細胞内に取り込むSGLT(グルコース共輸送体)という輸送タンパク質が活発に働いており、糖分をたくさん摂取することで尿の中に一旦排泄されたグルコースをSGLTの機能によって腎臓がどんどん再吸収します。このように腎臓というのは腸管と似て、栄養を吸収する働きもあります。
貪欲な臓器である腎臓や腸管で栄養素が次から次へと吸収されると、その貪欲ぶりは他の臓器にも伝染します。つまり体のあらゆる臓器が栄養素を貪欲に吸収しなければという状態になってしまいます。結果としてあらゆる臓器が過剰に栄養素を吸収し、肥満や糖尿病、高血圧などにつながってしまいます。そしてこれらの肥満や糖尿病、高血圧や心不全が慢性化、長期化するとミトコンドリアが疲れてきて臓器の機能が落ちてしまいます。すると老化が進むだけではなく、メタボや糖尿病の人はそうでない健康体の人に比べて1.3倍もがんの発症 率が高いと言われています。
メタボの人は腸管と腎臓にダメージが蓄積され 、肝臓がんや腎臓がん、膵臓がんを引き起こしてしまう可能性があります。なぜなら過剰な栄養によりミトコンドリアが頑張って活動しすぎた結果、体内に活性酸素が噴出してDNAが傷つき、その修復のエラーが起き、特定の臓器に老化とがん化をもたらしてしまうからです。
腸管と腎臓が老化のペースメーカーであり、実際最もスピーディーに老いが進む臓器は腸と腎臓です。腸と腎臓は、私たちが食事をする度に毎日休まず使うことになり、過剰に負担がかかり、臓器の老いが進んでしまうのです。
この老いを止めるために重要なのは、細胞の中にある質の悪いタンパク質や古くなったミトコンドリアを新陳代謝することです。その鍵を握るのがオートファジー、つまり腹八分目を意識することで腸管と腎臓に過剰な負担をかけることを避けることができます。さらにはオートファジーによって、質の悪いタンパク質を新陳代謝することもでき、結果として腸管と腎臓の老化防止に役立ちます。
腎臓にダメージを与える「無機リン」
腎臓について語る上で避けて通れない栄養素がリンです。自治医科大学分子病態治療研究センター抗加齢医学研究部黒尾誠教授は、かつてマウスの遺伝子操作の実験中、老化が加速する突然変異マウスを偶然に誕生させてしまいました。この突然変異マウスは、何らかの理由で老化が加速しているのかもしれないと考え、6年がかりで壊してしまった遺伝子を同定、そして10年近くかけてこの遺伝子がリンのハンドリングに重要な役割を果たしていることを突き止めました。
リンは生命の維持に欠かせない元素ですが、リンが体にたまりすぎると老化が進んでしまうことが分かっています。そのため体にはリンの摂取量に応じて適度に排泄を促して体にリンがたまらないようにする仕組みがあります。
先ほどの遺伝子は、この働きを機能させるための重要な遺伝子で、欠損することで尿からリンが排出できなくなり、老化が極端に加速してしまったのです。逆に食事をコントロールして、リンの摂取量を減らせば、この遺伝子欠損マウスの老化症状は消えて寿命も伸びます。
確かに通常のマウスは、リンの摂取量に応じて尿と一緒にリンを排泄することができるため、大量のリンが体にたまることはありません。しかし尿を作る腎臓だけは高濃度のリンに晒され、リンをたくさん摂取しすぎると腎臓はダメージを受け、腎臓の老化がどんどん進んでしまうのです。
そもそも現代人の食生活は明らかにリンの摂りすぎで必要量の倍以上のリンを食品から摂取しています。さらに問題なのは食品から摂取しているのに匹敵する量のリンを食品添加物から知らないうちに摂取しています。
通常、食品中のリンのすべてが体の中に吸収されるわけではありません。ですが食品添加物のリンは無機リンというリンで、ほぼ100%体に吸収されることが分かっています。
例えば、コンビニで購入するサンドイッチや弁当、惣菜の食品表示ラベルを眺めると、添加物の中にリン酸塩という物質が入っていることがあります。これが人工的に作られたリンです。この人工的に作られた添加物のリンはできる限り避ける必要があることを覚えておきましょう。
またさらに抑えておいていただきたいのが動物性食品よりも植物性食品に含まれているリンの吸収率が低いという点です。食品中のリンの含有量は、タンパク質含有量に比例します。つまりリンを制限するとタンパク質制限食になってしまいます。
インディバで細胞活性療法(Active cell therapy)
肌の新陳代謝、疲労した筋肉の回復などにも「幹細胞」が必要となります。怪我をして組織がダメージを受けたときも、壊れた組織を補充する能力を持った細胞が必要になり、こうした能力を持つ細胞が「幹細胞」です。
インディバは、すでに増殖しつつある「幹細胞」を刺激し、「ヒト間葉系幹細胞」の増殖の促進を加速させることができます。そのためインディバは「細胞活性療法(Active cell therapy)」と呼ばれることもありあます。
インディバの持つ周波数であり0.448MHzが「細胞膜の電位と透過性」を整えて、細胞内外にある「イオンの移動を適正化」します。このイオンは細胞の浸透圧を調節、筋肉の収縮に関わる働き、神経の伝達に関わる働きなど身体にとって重要な役割をしています。身体を整えること、身体を動かすことにイオンバランスの平衡は深く関係しており、イオンは多くても少なすぎても身体の調整機能は低下します。
インディバは、細胞の淀みを無くし、細胞をクリーンな状態導くことができます。細胞レベルから整え、細胞に働きかける、つまり「細胞」を元気にすることができるのがインディバ の「細胞活性療法(Active cell therapy)」です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。