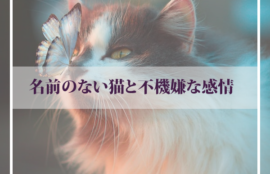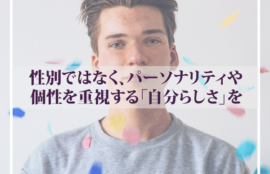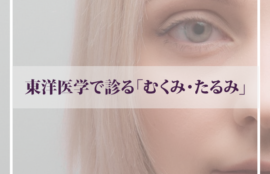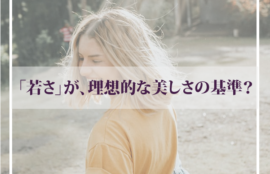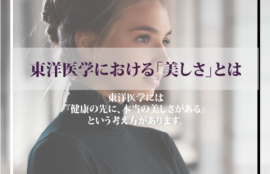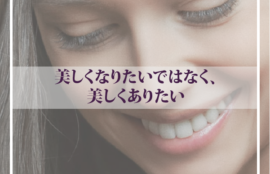世界中のアンチエンジング研究で注目されるのが細胞老化(セネッセンス)です。細胞老化が老化を加速させ、様々な病気の発症に影響を与えていることが分かってきています。私たちの体には約37兆個の細胞があり、分裂を繰り返しながら成長し、老化していきます。
その分裂する過程で、DNAに修復不可能なほど大きなダメージを受けたり、傷ついてしまうと細胞は癌化を防ぐため分裂をしなくなります。その細胞分裂を止めた細胞をアポトーシス(細胞死)と言い、自ら死を選んで壊れるか、免疫細胞によって食べたれたりして、通常は体には残りません。
しかし、細胞老化によって分裂を停止した細胞の中には、なぜか死なずに、臓器や組織の中に残って蓄積していくものがあります。老化細胞が蓄積(細胞老化随伴分泌現象/SASP)すると、慢性炎症の誘発、癌や動脈硬化、心血管疾患、糖尿病、白内障などを発生することが近年の研究で分かっています。
一方で、体に悪影響を及ぼしても増殖を止めない細胞の癌細胞があります。この癌細胞の増殖を止める働きが細胞老化にあることが分かっています。細胞老化は、免疫細胞を呼び込んで不要になった細胞を死滅させたりするだけでなく、周囲の細胞を活性化させて傷ついた組織の修復を促したりして体を守る働きもあります。
このように癌細胞にブレーキをかける役割だけでなく、周りに炎症を起こしてしまうのが細胞老化なのです。この細胞は若い人にも存在し、若いときにはがんの抑制や傷の修復など体を守る働きのほうが強く、加齢とともに増加し、老化をさらに加速させて、臓器に影響を与えているのではないかと考えられています。
細胞老化を防ぐ
同じように肌の老化にも細胞老化(セネッセンス)が見られ、コラーゲンの元にとなる繊維芽細胞を破壊し、表皮の厚み(弾力)も低下して老化が進むことが確認されています。そのため、この細胞老化を蓄積させないことアンチエンジングには大切です。その細胞老化が蓄積する原因が、ストレス、紫外線、大気汚染、喫煙などダイレクトに肌に影響を及ぼす因子です。
また、細胞老化が蓄積しないようにするためには、肥満を防ぐことが第一に挙げられています(大阪大学微生物病研究所遺伝子生物学分野原英二教授)。さらに定期的に適度な運動、ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動によって生活習慣病を防ぎ健康維持に役立つばかりか、細胞老化の蓄積を防ぐこが分かっています。
老化細胞とテロメア
私たちの体には約37兆個の細胞あり、その細胞の多くは分裂しながら入れ替わることで常に若々しさを保っています。しかし細胞は無限に分裂し続けることできず、細胞は分裂のたびにDNAが短くなり、やがて細胞は分裂をしなくなります。この細胞分裂のたびに短くなっていく構造こそが「テロメア」で、命の回数券と呼ばれる所以です。
体では毎日約1兆個もの細胞が入れ替わっているとも言われており、この細胞分裂は遺伝情報であるDNAがコピーされ全く同じDNAを持った細胞がもう一つできることで起こります。このDNAがコピーされる時、DNAの末端にあるテロメアは自らを差し出すことでDNAの本体が短くなるのを防いでいます。しかしテロメアがある一定以上短くなると、細胞は分裂できなくなり、二度と分裂しなくなった細胞が「老化細胞」です。そして細胞が老化すれば、当然体全体も老化し、その代表的なものが皮膚で老化細胞が増えればそれだけお肌が老化していくことになります。
テロメアが短くなる原因
血管の老化
テロメアの長さをキープすることができれば、細胞を若々しく保つことができ、健康寿命を延ばすことできますが、しかしテロメアが短くなる原因が大きく分けて3つあります。
その一つが毛細血管にあります。毛細血管の内側には、血管内皮細胞という細胞があり一つの層のようになっています。血管内皮細胞は血圧や血流などの変化に対応し、また動脈硬化を予防する重要な役割をしています。しかし加齢や高血圧、喫煙などによって血管内脂細胞がダメージを受けると血管内皮細胞は頻繁に分裂増殖をしなければならなくなり、このためテロメアがどんどん短くなり血管内細胞はあっという間に老化してしまいます。
こうして老化した毛細血管は、動脈硬化や脳卒中心筋梗塞などの致命的な病気の原因となるだけでなく、細胞老化が毛根で起これば白髪や薄毛の原因になり、免疫細胞で起これば病気に罹りやすくなります。このように細胞老化は体中のすべての臓器において起こります。さらに近年の研究では、この老化細胞から炎症作用や発がん促進作用のある様々な物質が分泌されていることも分かっています。
慢性炎症と肥満
テロメアを短くする原因は、慢性炎症です。炎症は体の防御反応とも言われ、通常の炎症であれば、次第に症状は治り病気や怪我は回復します。このような比較的早期に治る炎症を「急性炎症」と言います。一方で慢性炎症は、本来は一定期間が過ぎれば治るはずの炎症反応が長時間持続し、慢性化した状態を言います。
この慢性炎症が起こっていると、その周囲の正常な細胞たちがそれを察知し、炎症性サイトカインを発します。その部分に体中の免疫細胞が集まりダメージを受けた細胞や組織を修復していきますが、その修復が細胞分裂に他なりません。つまり炎症性サイトカインによって細胞分裂が活発になった細胞では通常よりも早いスピードでテロメアが短くなっていきます。さらに分裂頻度が高ければそれだけDNA にコピーミスが起こる確率も高くなり、がん細胞も発生しやすくなります。
一方で、細胞老化引き起こす最も危険な原因が肥満です。私たちの体には食べ物などから摂取した脂肪を蓄えておく脂肪組織があります。この脂肪組織からは脂質代謝を行うためのアリポサイトカインが分泌されます。肥満の人の脂肪組織では、脂肪細胞が肥大増殖しているためアリポサイトカインの分泌が異常に亢進します。これにより全身の炎症が進み慢性化することが分かっています。つまり肥満の人は、全身で軽度な慢性炎症が続いている状態であり、慢性炎症によって細胞老化も進みます。
糖化とAGEs
糖化は食事などから取った余分な糖質が、体内のタンパク質に結びつき大事なタンパク質が変性劣化してしまうことです。この劣化したタンパク質をAGEs(最終糖化産物)と言います。これを簡単に言うと体の中で起こる焦げです。この焦げであるAGEsが、お肌に蓄積すると皮膚の細胞のターンオーバーの働きが抑制され老化していきます。老化した肌からはコラーゲンやエラスチンといった成分が失われ、肌の弾力や水分が減少し、シワやたるみ、くすみ(STK)に発展します。つまりAGEsが蓄積した組織では、その組織の修復のために細胞分裂や増殖を繰り返し、それが高頻度になることでテロメアがどんどん短くなって 老化細胞が増えていきます。
このAGEsは、血糖値が高い状態が続くほど体内で産生される量が増えることが分かっています。このため糖尿病の人は、血糖値の高さと肥満という2つの要因によって糖化に加えて慢性炎症のリスクも非常に高いことが分かっています。
活性酸素とフリーラジカル
テロメアの長さを短くする原因の最後の一つが酸化です。ミトコンドリアは、細胞が取り込んだ酸素とブドウ糖を使って体が活動するためのエネルギーを産生しています。しかしエネルギーを産生する過程で、フリー ラジカルや活性酸素といった有害な物質も作り出しています。このフリーラジカルや活性酸素は、非常に不安定な物質のため正常な細胞から電子を奪ってしまう働きがあります。
この電子を奪う反応を「酸化」と言いますが、体には通常フリーラジカルや活性酸素を除去する抗酸化物質があります。しかし抗酸化物質は不規則な生活や加齢によって年々低下していきます。20代で100あった抗酸化物質は、40代では半分、60代では1/4以下になると言われています。そして抗酸化作用のバランスが崩れ、酸化が優勢になってしまった体の状態を酸化ストレスと言います。この酸化ストレスは細胞そのものを傷つけてしまう作用があります。糖化は体が焦げる現象で、酸化は体が錆びる現象です。そのため炎症や糖化と同じく、酸化ストレスで細胞が傷つけばそれを修復するために細胞分裂が促されてテロメアの 短縮が進んでしまいます。
細胞呼吸と毛細血管
息を吸って息を吐く呼吸を生物学的には「肺呼吸」と呼びます。一方でミトコンドリアが酸素と栄養素からエネルギーを生み出すプロセスのこと「細胞呼吸」と言います。ミトコンドリアは不眠不休で細胞呼吸を行って、エネルギーを生み出し続けていますが、老化や肥満、ストレスなどが原因で作業効率が下がったり、その数そのものが少なくなったりします。
この細胞呼吸をしっかりと行うことが大事なのですが、そのためには私たちの全身に張り巡らされた毛細血管が重要な役割をしています。ミトコンドリアが細胞呼吸を行うためには、酸素と栄養素が必要になり、細胞呼吸によって排出された二酸化炭素や活性酸素などの老廃物は速やかに回収されなくてはなりません。この運搬と回収という重要な役目を担っているのが毛細血管です。
この毛細血管は非常に細く髪の毛の1/10ほどの細さしかないにも関わらず、全身の血管の99%が毛細血管で占められています。毛細血管もまた加齢によってダメージを受け、血液が漏れ出すといったトラブルが頻繁に発生するようになります。このようなトラブル続きの血管のことをゴースト血管と呼びます。このようなゴースト血管はダメージ初期であれば「血管新生」によって毛細血管を新しく増やすことができます。
この血管新生に大事なのがホルモンバランスを整えることです。ゴースト血管を健康な血管に生まれ変わらせるためには、ノルアドレナリンとコルチゾールという2つのホルモンを 厳密にコントロールする必要があります。ノルアドレナリンは交感神経が優位になると分泌されるホルモンで、適度な分泌であれば意欲や集中力をアップするのに役立ちます。しかし過剰に分泌されると作用が長期化しやすくなり、ストレスがより高まり慢性化するようになります。すると今度はストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールまでが大量に分泌され交換神経がますます優位になるという負のスパイラルが生じてしまいます。こうしてノルアドレナリンやコルチゾールの過剰分泌が亢進すると交感神経はますます優位になり、毛細血管はさらなるダメージを受けます。
ストレスホルモンを制御する
ノルアドレナリンとコルチゾールの過剰分泌を制御するためには、ストレスを避け交感神経と副交感神経のバランスを整えることです。
私たちの体には、基礎代謝というエネルギーを消費する仕組みがありますが、実は脳でも同じことが起こっています。脳には思考していない時でも稼働しているネットワークがあり、それを「デフォルトモードネットワーク」と言います。この状態で脳は何かあったらすぐに動けるようにスタンバイしており、脳はエネルギーを着実に消費しています。しかもデフォルトモードネットワークは、脳を活発に動かしている時よりもエネルギー消費量が20倍も多いことが分かっています。
このデフォルトモードネットワークの稼働時間が増えて多くのエネルギーが消費されると、 脳内で酸化が起こり、老廃物が多量に排出されます。これらの老廃物がストレスとなってコルチゾールやノルアドレナリンといったホルモンが過剰に分泌されてしまいます。このデフォルトモードネットワークをオフにするためには、その最適な方法が、今ここにだけ集中することです。代表的なものに自然の中で運動すること、ヨガなどマインドフルネスと呼ばれるものが有効になります。
オートファジーと腹8分目
テロメアの長さを維持して現行寿命を保つためには健康的な食事が不可欠です。しかし特別な食事をする必要はなく、栄養素をバランスよく取り、腹八分目に抑えることが大切です。現代人の多くは塩分や糖分を摂りすぎており、反対に食物繊維や抗酸化作用の高い物質は 不足しています。栄養バランスが偏った食事、不適切なカロリー摂取は、体の内部環境にとっては大敵であり、特に腹八分目に抑えるというところが非常に重要です。
なぜなら、私たちの細胞内には代謝の過程で発生したタンパク質の不良品がたくさん存在しており、このような不良品をリサイクルする体の仕組みである「オートファジー」があるからです。このオートファジーは、一般的には断食やプチ断食によって作動します。
特に体に余計な負担をかけず、かつオートファジーを作動させる食事法として「カロリーリストラクション」があります。カロリーリストラクションとは、5大栄養素を中心にバランスを十分に確保しながら、毎食の総摂取カロリー量を標準の7割から8割程度に制限する食事法です。この食事法によって程よく空腹時間ができ、短いながらオートファジーが作動してくれ、さらに全身の細胞を若返らせるアリポネクチンという善玉アディポサイトカインが増加します。
また、カロリーリストラクションにはテロメアを保護する効果があることが最近分かってきています。研究ではカロリーリストラクションによって長寿遺伝子がオンになることが判明しています。この長寿遺伝子にはテロメアを保護する働きがあり、カロリーリストラクションによって細胞の老化スピードが緩慢になる可能性が示唆されています。
細胞老化を持たない椿
レッドカメリアは細胞老化を持たない植物です。シャネルはウィーン天然資源及び応用生命科学大学と10年以上にわたり細胞老化(セネッセンス)の研究を進めています。
カメリアの葉にはアントシアニンというポリフェノール成分があり、それが細胞老化を持たない原因ではないかと考えられています。シャネルは、このレッドカメリアの植物エキスを肌に浸透させればSASPが蓄積したり、伝搬したりしないのではないかと研究し、細胞老化の第一段階において優れた効果を発揮することを発見しています。
それがレッドカメリアペタルエキスと言われるプロトカテク酸という抗酸力が高い成分です。この成分が、微小循環という細胞分裂や細胞の伝搬を改善することが分かっています。つまり細胞老化を遅らせることができる成分になります。
アンチエイジング医学
老化を遅らせることができるのではないかと言われている物質が「NMN」です。この物質によって、当たり前とされている人生のあり方や社会の構造を根本から変えてしまう可能性が示唆されています。
私たちの細胞は日々消滅と再生を繰り返しており、細胞が傷ついたり、エネルギー補給ができなかったりなると、細胞の修復や生存のためにサーチュイン遺伝子が働くことで、体の正常な機能が保たれます。このサーチュイン遺伝子の働きに関わる物質が「NAD(ニコチンアミドアデニンシヌクレオチド)」です。老化するとこのNADが激減するため、細胞の修復のスイッチが押されず、老化を進め、不調や病気が引き起こされるメカニズムの正体だと考えられています。
そこで体内でNADに変換する栄養素として「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」という物質が注目されています。このNMNは、エビやブロッコリーなどにほんの僅かだけ含まれている栄養素です。このNMNを定期的に補給する細胞としない細胞を比較すると、補給しない細胞は、細胞の修復を止めてしまうことが研究で明らかになっています。
一方で、老化細胞を除去する薬の研究も始まっています。昨年、東京大学の中西教授らの研究グループは、抗がん剤としてすでに治験が始まっているGLS1阻害薬(アメリカで研究中の抗がん剤)に、老化細胞を除去する効果があることを発見しました。年老いたマウスに1ヶ月間その薬を投入したところ、マウスの筋力がアップし、さらに肺や腎臓肝臓の機能を改善させるという効果が確認されました。まだ動物実験の段階で課題は多いですが、中西教授は腎臓病や糖尿病などの老化による病気を治療する薬として、早ければ20年以内での実用化を目指しているということです。
【NMNの最新情報】
2022年10月、アメリカ食品医薬品局(FDA)から、NMNを食品サプリメントとして販売することを推奨しないという声明が出されました。一方で日本の厚生労働省は「NMNは非医薬品、つまり食品である」という公式見解が示されています。
このNMNはNAD+の前駆体であり、経口摂取が可能なことから、減少するNAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)を補う成分として注目されています。NAD+は、ミトコンドリアでのエネルギー産生をはじめ、ホルモンの合成や脂質の分解など様々な酵素反応に必要な補酵素として使われています。そして2020年以降、人でNMNの効果を検証した臨床試験の論文報告が多くみられ、人への応用に向けての研究やその成果に対する社会的期待がますます高まっています。
このような声明が出されたのは、NMNを医療用医薬品の新薬として開発する企業があり、新薬開発には莫大な研究開発費用がかかるため、開発企業を保護する目的の措置ではないかと言われています。2020年以降、NMNの医薬品としての後期開発が視野に入ってきた中、医薬品開発企業のビジネスや権利を保護するという側面があると考えられています。
日本国内の最新老化研究
理化学研究所脳神経科学研究センターの神経幹細胞研究チームが行った研究では、神経幹細胞を基軸に人の記憶力を若返らせることができるかに迫り、マウスを使った研究で記憶力の若返りは可能であることが証明されています。
記憶力の若返りの鍵となるのは、神経幹細胞を活性化させることです。脳にはニューロンと呼ばれる神経細胞が多数存在し、情報を伝えたり処理したりする役目を担っています。このニューロンのもとになるのが神経幹細胞です。
大脳は側頭葉、頭頂葉、前頭頂、後頭葉に分けられ、側頭葉と頭頂葉は胎児の時から発達します。この発達に関わっているのが神経幹細胞で、胎児の頃に最も活発に発達します。しかし脳が発達していくのに反比例するように、その力は徐々に衰えます。私たち大人の脳には神経幹細胞は少ししか残っておらず、休眠状態でほとんど働いていません。
この神経幹細胞は、僅かながら海馬歯状回にも存在しています。実験に使うマウスの脳も基本的には人間と同じ仕組みです。そこでマウスを使い、大人の脳でどれくらいニューロンが新しく生まれているかをまず調べました。ちなみにニューロンの誕生は、ニューロン新生と呼ばれます。
人にすると30代前半のマウスの脳では、まだニューロン新生は比較的活発に行われていました。しかし30代後半になるとニューロン新生は減り、そして人の40代50代にあたるマウスのニューロン新生もどんどん減っていき加齢による変化が確認されています。
そこで眠っている神経幹細胞を胎児期の頃のように、もう一度活性化させることができないかと研究チームは考えました。そこで胎児期の神経幹細胞を活性化させるには、plagl-2という遺伝子の役割が大きいことが分かっており、大人の神経幹細胞でplagl-2を活性化してみると新しいニューロンが生まれることが分かりました。また同時に老化した大人の神経幹細胞で働く遺伝子dyrk1aという遺伝子の存在も発見しました。このdyrk1a遺伝子の働きを抑制することでも新しいニューロンが生まれることも掴んでいます。
研究では、人ならば60代にあたる19ヶ月齢のマウスにiPaD(plagl-2とdyrk1a)を使うと、人にすると10代くらいに当たる1から2ヶ月齢まで記憶力が回復したことが分かっています。
老化細胞を除去する
2022年11月に世界的に有名な科学誌ネイチャーにも掲載された東京大学医科学研究所の研究があります。その研究では中西教授ら研究チームは、老化細胞を除去することに成功しています。この研究では、年を取ったマウスに免疫チェックポイント阻害剤という薬を使うことで老化細胞を取り除くことができました。また老化細胞を取り除いただけでなく、実験ではマウスの運動機能も若返っています。
そもそも老化細胞とは加齢により体内に蓄積するもので、がんや糖尿病などを発症させる要因です。人の体内に存在する約60兆個の細胞は、日々分裂と再生を繰り返すことで人は健康を保っています。しかし血管の老化や体内の糖化などによって、新たな分裂をしない細胞ができ、それが老化細胞と呼ばれています。
体内の免疫力が正常であれば、老化細胞も免疫によって自然に排除されます。しかし免疫力が低下し、多くの老化細胞が蓄積すると排除が間に合わなくなってきます。また免疫の攻撃を避けようと働く存在があり、攻撃を免れた老化細胞は増えてしまいます。免疫の攻撃を避けるのはPD-L1というタンパク質で、この働きを阻害する薬を使用するとマウスの肺、肝臓、腎臓の老化細胞が3分の1になり、筋力がアップし、肝機能も回復したことが分かっています。
研究で使われた抗PD-L1抗体は、がんの治療でも使用されているため、人に使われた実績があります。老化細胞の除去に関しては、マウスの実験段階ですが、人にも応用できる日は相当遠くないかも知れません。この方法が人に採用されれば、健康寿命は平均寿命まで伸ばすことも可能と言われています。
また老化細胞の除去については、セノリティクス薬と呼ばれる老化細胞除去薬が臨床実験の段階にあります。特に期待されているGLS1阻害剤は、がんの治療薬として、アメリカで治験が行われています。まずはがんの治療薬として使用されることで、老化の治療薬としても使えることが期待されています。また他にも失明の原因となる黄斑変性症や肺繊維症に対抗するセノリティクス薬の試験も行われています。
日本でも政府主導で老化細胞に対抗する道筋が作られており、その計画(ムーンショット計画)の一つに、100 歳を目指した健康寿命延伸医療の実現があります。ここでは炎症誘発細胞、いわゆる老化細胞の除去が対象となっており、有名大学数校が2040年までに加齢によって起こるあらゆる病気を一掃させようと研究を進めています。
闇雲な食事制限はいらない
闇雲な食事制限はいりませんが、その分体に良いものを食べることが基本です。質の良いものを食べれば体はそれに応えてくれ、体と肌が若返る食べ物をいくつか紹介します。
納豆
納豆は日本独特の食品で古代から健康と美容に良いとされています。1 日1パックを食べることを習慣化すれば、細胞が若返るでしょう。納豆には、ポリアミンやビタミンB、納豆キナーゼなどが含まれ、健康効果が高いポリアミンはアンチ エイジングに対する効果が期待される物質です。この物質は人間から微生物に至るまでほぼ全ての生物の体内に広く分布し、その役割は細胞の分裂や増殖を助けたり、新陳代謝を整えることです。さらには体内の炎症を抑制する働きもあり、体内のポリアミン量が少ない人は老化現象が加速してしまう可能性が指摘されています。
ポリアミンは大豆にたっぷりと含まれていますが、発酵する過程でさらに増えます。ポリアミンには腸内環境を整える働きもあり、免疫力を高める効果も期待でき、一部の研究ではビタミンががん細胞の増殖を抑える働きをすることも明らかにされています。
また、納豆には脂肪燃焼効果の高いビタミンB2も豊富に含まれており、ビタミンBは水溶性のビタミンで、糖質、脂質、そしてタンパク質の代謝に関係しています。ビタミンB1が主に糖質の代謝を助けるのに対し、ビタミンB2は脂質の代謝を特にサポートします。ビタミンB2は、発育のビタミンとも称され、皮膚や粘膜、髪の毛、爪などの細胞の再生を助ける大事な栄養素です。不足すると口角炎や肌荒れを起こしやすくなるだけでなく、疲労感を感じやすくもなります。
また、納豆に含まれる納豆キナーゼには、血液をサラサラにする効果があり、心筋梗塞や脳梗塞の予防はもちろん、最新の研究ではアルツハイマー型認知症の予防にも効果があることが分かっています。
キノコ
キノコは食物繊維が豊富なだけでなく、低カロリーで満腹感を感じやすい食べ物です。さらにキノコ類には血行を良くするナイアシン、ビタミンB6、葉酸などが豊富に含まれています。健康や美容を気にする人は最低でも3日に1回はキノコ類を食べましょう。
キノコは種類によって健康効果が変わります。便秘やむくみ解消にはエリンギ、美肌や免疫力アップには椎茸、舞茸が効果的です。ビタミンD、カルシウムの補給にはえのき、ビタミンB2や食物繊維が欲しい時はしめじです。キノコは味噌汁の具として食べると相乗効果で栄養が摂れます。味噌に含まれる麹菌とそれぞれのキノコが持っている菌を一緒に食べることで、効果が上がります。
たまご
たまごは完全タンパク質と言われ、体が自己生成できない9種類の必須アミノ酸を全て含んでいます。動物性タンパク質の中で最も優秀な食べ物で、最低でも1日1個食べることが推奨されています。
タンパク質は私たちの体を構成する基本的な素材で、健康的な筋肉、骨、髪を維持するためには不可欠です。
たまごを食べるタイミングとしては夕食後で、肌に潤いを与える成分は夜に合成されやすいからです。たまごの美容成分が就寝中にしっかり吸収、合成されることで肌の若返効果が高まります。
牛肉赤身のロース
牛肉は高タンパクなだけでなく体にとって重要なビタミンとミネラルを豊富に含んでいなす。ビタミンB12、ビタミンB6、鉄、亜鉛、セレニウムなど他の肉と比べても高栄養用です。牛肉を選ぶときのポイントは赤身のロースを選ぶことです。余分な脂肪を摂らずにしっかり鉄分を補うことができます。牛肉には亜鉛が含まれていますが、特に赤身の部分に多く含まれています。
亜鉛は免疫システムの健康を維持するのに重要な役割があり、亜鉛が不足すると免疫力が低下する可能性があります。また亜鉛は皮膚の修復を助ける役割もあるため、亜鉛不足になると傷やニキビの治りも遅くなってしまいます。
ミニトマト
シミは肌の色素メラニンが異常に集まることによって発生しますが、色素メラニンが異常に集まる原因になっているのが活性酸素です。活性酸素は、酸素が体内で代謝される過程で発生する化学物質ですが、同時に体を劣化させるものでもあります。過剰に蓄積すると細胞や組織にダメージを与え、シミを発生させてしまいます。
この活性酸素を減らすには、抗酸化力が最強のミニトマトを食べると良いでしょう。ミニトマトに含まれるリコピンは、非常に強力な抗酸化物質で酸素を中和する効果があります。一部の研究ではリコピンがコラーゲンの生成を助ける可能性があるとされています。リコピンは新たにシミを作らせないという効果もあるため定期的に食べましょう。
理想としては、毎日ミニトマトを5つ食べることです。ちなみにミニトマトは真っ赤に熟している方がリコピンの量が多くなります。注意点としてはトマト を加工したトマトジュースやケチャップなどはリコピン量が減っています。
ニンジン
肝臓は私たちの体の中で重要な役割を果たしています。主な役割は、体内の毒素を取り除き、血液を浄化することです。これは一種のデトックス作用とも言えます。この肝臓のデトックス作用を助ける食材の一つがニンジンです。人参の効果は主にβカロテンによるものです。
βカロテンは、ビタミンAとなり肝臓の機能を助け、体内の毒素を排出する役割を果たします。これはビタミンAが肝臓の細胞を強化し、その働きを活性化することで実現されます。つまり人参を食べることで肝臓がより効率的に働き、体内の毒素を取り除くことが可能になります。
また人参に含まれる食物繊維は消化器系全体の健康を維持するのに役に立ちます。食物繊維は消化器系を通過する食物の流れをスムーズにし、余分な物質を体外に排出してくれます。これにより肝臓にかかる負担が軽減され、デトックス作用が強化されます。
さらに人参は ビタミンも豊富に含んでおり、ビタミンCは強力な抗酸化物質であり、体内のフリーラジカルを中和します。フリーラジカルを中和することで 肝臓の細胞が保護され、その働きが維持されます。このようにニンジンは、ビタミンA、食物繊維、ビタミンC などの栄養素により、肝臓のデトックス作用を強化します。
インナービューティー
このような質の良い食事をしっかり摂ることで、食事制限はほどほどでも美しさを保つことはきます。このアプローチ方法は、インナービューティーと呼ばれ、若さを維持する上でも非常に大切な考え方です。ビタミンC、セレン、βカロテンなどの抗酸化物質を多く含む食品をたくさん食べること、そして高品質な脂質、オメガ3脂肪酸や抗生物質、タンパク質もしっかり摂ること、加工食品や高糖質の食品を無理に避けること、食事量を適切に制限することなど、これらができていれば体の内側から美しさを引き出すことができます。
また、食事だけでなく運動や睡眠、ストレス管理も大切です。運動はストレスを軽減し、体重を管理するためにも重要です。理想としては 週250分の中程度の強度の運動、もしくは週に75分の高強度の運動を続けることです。睡眠に関しては7から9時間の睡眠が必須であり、中々眠れないという人は睡眠環境を改善したり、趣味や楽しい活動をする時間を増やして いくと良いでしょう。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。