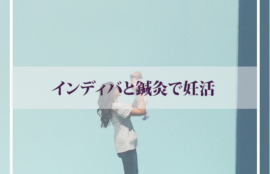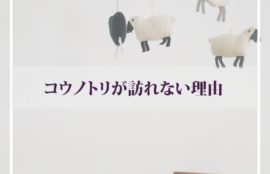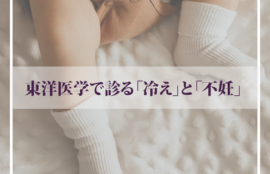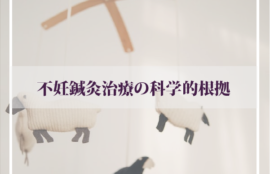月経前、月経中にイライラしたりや痛みが生じるなどの生理痛(月経痛)は、日本国内で推定800万人が悩む症状であるとされており、女性の月経回数の増加がひとつの原因とされています。その心身の不調による欠勤や労働量・質の低下(労働損失)は4,9110億円と経済損失があるとも言われています。
主な症状は、個人の体質によって様々であり、心身に様々な不快症状が現れますが、多くは月経が始まると解消します。主な症状は、腹痛、頭痛、めまい、不眠、肩こり、むくみ、乳房の張り、だるさ、便秘など多種多様な症状があります。また精神的なイライラや落ちんだりするなどの感情面での影響もあります。
ストレスや生活週間などの原因から体内リズムが崩れて、ホルモン働きに支障が出ることで、月経痛や、さらにひどい場合には生理痛(月経困難症)やPMS(月経前症候群)などといった症状に繋がります。
特に日常生活に支障をきたすほどの痛みを生じる「生理痛(月経困難症)、PMS(月経前症候群)」は、月経に伴って下腹部痛、腰痛など一般に生理痛とよばれる症状に加え、おなかの張り、吐き気、頭痛、疲労感、脱力感、食欲不振、いらいら、下痢および憂うつなどの疼痛の症状です。
生理痛(月経困難症)、PMS(月経前症候群)
月経困難症には、原因疾患がない「機能性月経困難症」と原因疾患があるために起こる「器質性月経困難症」に分けられます。
前者は、月経困難症を訴える人の4割以上を占めます。特に若年層では月経困難症で悩んでいる方のほとんどは、「機能性月経困難症」と言われています。月経痛の原因として、内分泌失調・自律神経失調や心因的要因が考えられており、それらが誘因となって子宮筋に過度なストレスがかかって、痛みを引き起こすとされています。
後者は、原因となる疾患として、①子宮内膜症、②子宮腺筋症、③子宮筋腫などがあり、この中でも①子宮内膜症の8割以上の方に月経困難症が認められるといわれています。
20代以降で月経周期が安定してからの月経困難症は、器質性月経困難症の可能性が高く、すぐに婦人科を受ける必要があります。主な症状は激しい生理痛です。不妊症との関わりも深く、原因不明の不妊症の半分に子宮内膜症があると言われています。機能性月経困難症については、鍼灸の適応症になります。ハリニーでは、生理痛(月経困難症)とPMS(月経前症候群)について、西洋・東洋医学の両面から鍼灸治療をしていきます。
生理痛(月経困難症)の原因
機能性月経困難症の原因には様々な説がありますが、大きく分けると①プロスタグランジンの過剰分泌、②子宮口が狭い、③心理的要因、④運動不足や冷えです。
この中でも注目されているのが、プロスタグランジンの過剰分泌です。プロスタグランジンとは、子宮内膜が分泌期から月経期に産生されるもので、子宮筋が過剰に収縮して、子宮の血流が悪くなり痛みが起こる、とされています。
PMS(月経前症候群)の診断について
月経・排卵のある女性の約8割が、月経が近くなると不調を感じ、残りの2割がPMS(月経前症候群)にあたり、その中でも心の不調が強く現れるPMDD(重症型の月経前不快気分障害)が2%前後だと言われています。PMS(月経前症候群)であるかどうかは、日常生活に支障がないかどうかがひとつの判断基準になります。PMSの主な症状は、体調不調(お腹の張りや痛み、頭痛、吐き気、冷え、肌荒れ、強い眠気など)、感情の乱れ(イライラ、憂鬱など)が月経前の5日から7日の間に強い症状が現れますが、月経が始まるとそれら症状は全く見られなくなります。
このPMSがなぜ引き起こされるかは解明されていませんが、幸せホルモンであるセレトニン分泌が関わってくると考えられています。月経周期においては、低温期にはエストロゲンが活発に働き、排卵をきっかけとして高温期のプロゲステロンに変化する過程で、セレトニンの働きに変動があるため、この急激なホルモンの変化に脳や体が適応できない状態になるからです。
ホルモンバランスとの付き合い方
PMSがすごく重い人は、ホルモンがたくさん出るか出ないかというよりも、その変化の幅が大きい人です。その変化が緩やかであれば慣れていくことができますが、人の体は変化に強くできていないため、1月の間に大きな波(生理と排卵)があれば、体が痛くなったり、頭痛が起きたり、気持ちにもそれが反映することがあります。
例えば、すごく寂しい気持ちになったり、自分には誰も味方がいないなど、そういう気持ちに2、3日、長ければ1週間ぐらいなる場合があります。しかしそれは本当に助けてくれる人がいないわけではなく、ただ生理的な変化として、その気持ちが生まれてきてしまうことを知ってほしいです。つまり自分で何とかしようとしてできる問題ではないということです。このホルモン変動の幅が激しい人は、それによって体も左右されるし、メンタルも左右されることが大きくなるため、投薬や鍼灸で調整しましょうかとか、この時期はあまり重要な意思決定をしないでおこうなど、まず自分自身を知ることがすごく大事です。
一方で、PMSだけでなくトランスジェンダーやノンバイナリーにおいて、ホルモンバランスの影響で「希死念慮」が生まれることが研究で分かっています。希死念慮は、特に性的マイノリティの方に多く生まれ、例えば自分には味方がいないという風に感じてしまい、生理的にも誰も助けてくれる人がいないと思ってしまいやすい状況が脳の中でできてしまうことが指摘されています。これが重なっていくと望ましくない決断をしてしまうってこともあり得るので、少なくとも自分が考えるベースに生理的な条件があると立ち止まって考えることが必要です。
誰も助けてくれないと思うような嫌な気持ちが出てきた時に、これは寒暖差によって体の中のホルモンのバランスが変わったなど、体の方に原因がある場合が多くあります。脳のホルモンの変化は自分ではコントロールできないことなので、その波を乗り切れるのを待とうと思うことが大事です。激しい雨は必ず止みますし、その間はゆっくり家の中で過ごすことも大事です。
東洋医学で診る「生理痛(月経困難症)・月経困難症(PMS)」
東洋医学では月経困難症を「痛経」または「経行腹痛」といい、「気」と「血」の滞りによるものとし、肝鬱気滞・気血両虚・肝腎陰虚の3つが主な原因として考えられます。特に「血」は酸素や栄養素を体の隅々まで運び、また老廃物を排出する重要な役割を担っていますが、この血の流れが滞る「瘀血(おけつ)」が生理痛やPMSの主な原因であると考えられています。また自律神経を司る「肝」、ホルモン分泌に関係する「腎」という臓腑の働きが乱れることで不調が起こると考えます。さらに個々の体質や環境などの影響、そして卵巣から分泌されるホルモンバランスの変化などが複雑に影響して、体内のバランスが崩れることで様々な不調が引き起こされます。
そのため鍼灸治療では、血の流れを改善し、月経痛の軽減、自律神経の調整、下腹部の凝り、ホルモンバランスの乱れを整えていきます。それと同時に体の冷えを改善するために、インディバの深部加温で内臓にしっかり熱をつくっていきます。その結果、痛みの緩和、ホルモンや自律神経のバランスだけでなく、気・血の巡りを促すことも行っていきます。鍼には即効性があるため、辛い症状を早く和らげることができ、深部加温によって気・血を巡らせることで、相乗効果を得ることができます。
妊活のためにも
東洋医学では、同じ病気でも個々の体質に合わせて治療方法を変える「同病異治」という言葉があります。つまり同じ症状であっても治療方法は異なります。表面に現れている症状と、体質に起因する根本的な原因は違い、それを同時に整えていく必要があります。それを「標本同治」と言い、身体全体のバランスを整えて健やかな状態を目指すことが大事です。
月経に関する悩みや症状の多くは、妊活にも繋がっているため、ホルモンや子宮・卵巣の力を高める「補腎」も合わせて行うことで、身体のバランス調整機能を整えることが大事です。
鍼灸と生理痛改善のツボ
生理痛・月経困難症の痛みを和らげる方法としてお腹・腰周り(子宮や骨盤内)の血流をよくすること、特に下腹部を冷やさず温めることが重要です。
当院では、「気」と「血」の流れの状態をよくして、子宮の周辺の状態をよくすることを目的に施術します。冷え症を持っている方は、併せて施術していきます。また自律神経を整えていくことも症状を治していく早道です。
生理痛の特効穴として『三陰交』というツボがあります。三陰交は五臓六腑の肝・脾・腎の3つの経絡が交わり、身体の中を流れる全ての物質の循環を促進させる働きを持つとされ、婦人病の改善に特に有名なツボです。
三陰交(さんいんこう):足の内くるぶしの一番高い所から指4本分進んだところの骨のきわ

毎日軽く押してみたり、簡易的なお灸で刺激してあげるのも効果的です。
【本コラムの監修】

・経歴
大学卒業後、美容の世界に入り、セラピストへ。豊富な美容知識や実務経験を活かし、その後、10年間は大手企業内講師として美容部員やエステシャンの育成、サロン店舗運営のサポートを行う。現在は、セラピスト、エステティシャン、美容カウンセラー、鍼灸師の経歴を活かし、お肌とこころと身体のトータルビューティースタイルを提案。表面だけでなく根本からのケアとして、老けない生活についてのコーチングを行う。